「また同じ言葉ばっかり言ってる…」「どうして会話が進まないの?」
3歳前後になると、子どもが同じ言葉やフレーズを繰り返すことが増える時期があります。ママとしては「ちょっとしんどいな」「イライラしてしまう…」と感じる瞬間も多いですよね。
でも、この“同じ言葉の繰り返し”には、成長のサインである場合と、発達障害の特徴として表れる場合の両方があります。大切なのは「なぜ繰り返すのか?」という背景を理解すること。理解できるとママの心が少しラクになります。
この記事では、3歳児が同じ言葉を繰り返す理由を発達の視点・心理的な視点・発達障害の特徴など、多角的に解説します。そして「イライラしてしまうときにどう対応すればいいのか?」も、専門家の知見を交えながら紹介していきます。
【発達段階?発達障害?】3歳で同じ言葉を繰り返す理由
3歳児に多い“言葉の繰り返し”は成長サイン?
3歳前後は、言葉の発達が一気に進む時期です。子どもにとっては、聞いた言葉を繰り返すことで覚えたり、口の動きを練習したりしています。例えば「ワンワン」「バイバイ」など、耳にしたフレーズを楽しそうに繰り返す姿は、言葉の発達にとって大切なプロセス。
つまり「同じ言葉を繰り返す=異常」ではなく、「ことばの練習」や「遊びの一部」であることも多いんです。
安心したい気持ちの表れ?子どもの心理背景
子どもは、不安なときや気持ちを落ち着けたいときに、同じ言葉を繰り返すことがあります。たとえば「ママは?」と何度も聞いてくるのは、「そばにいてね」という安心を求めるサインかもしれません。
また、幼稚園や保育園など新しい環境に慣れていないときに、言葉の繰り返しが強く出る子もいます。これは大人でいう「おまじない」のようなもので、子どもなりに心を落ち着けようとしている行動です。
発達障害の特徴?エコラリアとの関係を専門家が解説
一方で、発達障害の特性としての“同じ言葉の繰り返し”も存在します。特に自閉スペクトラム症(ASD)の子どもに多く見られる「エコラリア(反響言語)」です。
エコラリアには大きく分けて2つあります。
- 即時エコラリア:聞いた言葉をすぐにオウム返しする
- 遅延エコラリア:以前聞いたフレーズを後になって繰り返す
例えば、テレビで見たセリフを何度も口にする、質問に対してそのまま返すなどが当てはまります。
ただし、エコラリア=発達障害確定ではありません。言葉を理解するステップのひとつとして出ることもありますし、適切な支援や関わりで会話に発展することも多いです。
重要なのは、繰り返しに「意味があるのか?」「会話として広がっていくのか?」という点を観察することです。
ここまでで、「発達のサイン」「心理的要因」「発達障害の特性」と3つの視点から“同じ言葉の繰り返し”を解説しました。これらを知るだけでも「なるほど、うちの子は安心を求めてるのかも」と気づけたり、「発達相談に行ってみよう」と一歩踏み出すきっかけになるはずです。
【共感】同じ言葉の繰り返しにママがイライラしてしまうワケ
子どもが同じ言葉ばかり繰り返していると、「またそのフレーズか…」「なんで答えても終わらないの?」とイライラしてしまうこと、ありますよね。
決してママが悪いわけではなく、誰でも繰り返されると疲れるし、ストレスになるんです。ここでは、ママがイライラしてしまう背景を3つの視点から見ていきましょう。
「普通の会話がしたい」期待とのギャップ
3歳といえば、少しずつ会話が成り立つ年齢。周りの子を見ても「ママ、これなあに?」と質問したり、「今日は○○したよ」と報告したり、会話が広がっているように見えることも多いですよね。
その中でわが子が「ママ、ママ」「これなに?これなに?」と同じ言葉ばかり繰り返すと、ママとしては「もっと普通の会話がしたいのに…」という気持ちになってしまいます。
さらに、周囲と比べると「うちの子は大丈夫かな?」という不安も重なり、イライラに拍車がかかります。これはとても自然な感情で、「期待」と「現実」とのギャップがストレスを生んでしまうんです。
何度も繰り返されることで疲れるストレス
子どもは同じフレーズを何十回でも言えちゃうエネルギーを持っています。だけど、大人はそうはいきません。ご飯を作っているとき、下の子の世話をしているとき、家事で手いっぱいのときに何度も繰り返されると、「もうやめて…」と疲れてしまうのは当たり前なんです。
心理学的にも、同じ刺激が繰り返されると人はストレスを感じやすくなるといわれています。つまり「返事をしても同じ質問が返ってくる」状況は、大人にとっては強い心理的負担になりやすいんです。
「子どもが悪いわけじゃない」と頭でわかっていても、心と体がついていかなくなることってありますよね。
睡眠不足や孤独感…ママの心の余裕不足も影響
もうひとつ見逃せないのは、ママ自身のコンディションです。夜中の授乳や子どもの夜泣き、朝から晩までの家事育児…それだけで体力も気力もギリギリ。そこに「同じ言葉の繰り返し」が加わると、心の余裕は一気になくなります。
さらに、発達が気になる子を育てていると「うちの子だけ違うのかな」と感じたり、周りのママ友には相談しにくかったりして、孤独感を抱えやすいんです。その孤独感がストレスを増幅させ、ちょっとしたことでもイライラしやすくなってしまいます。
要するに、ママのイライラは「子どもが同じ言葉を繰り返すから」だけではなく、疲労・期待とのギャップ・孤独感が重なっている結果なんですね。
ここまで読んで、「あ、私だけじゃないんだ」と思えたママもいるはず。イライラしてしまうのは“自然なこと”で、むしろ多くのママが経験していることなんです。大事なのは、そのイライラをどうやって軽くしていくかということ。次の章では、専門家の視点から「イライラを減らすための対応法」を紹介していきますね。
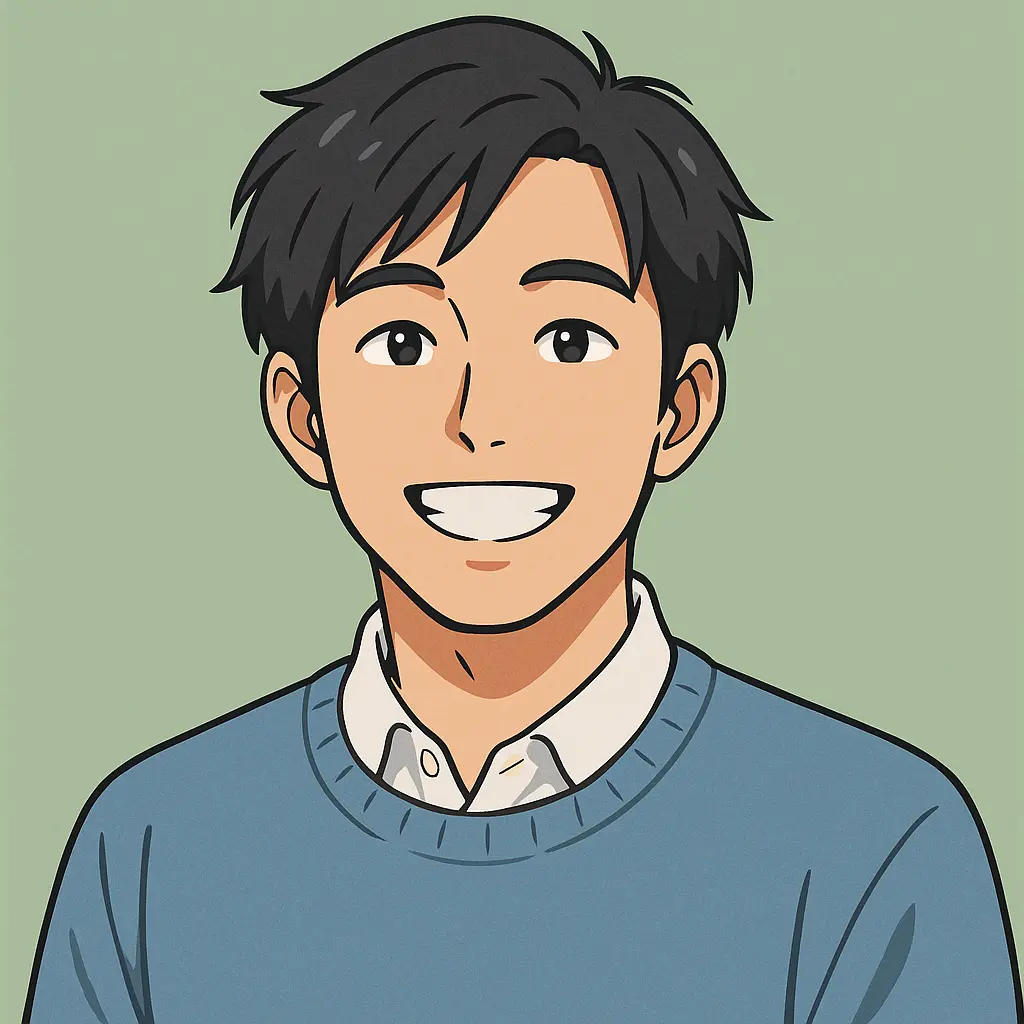
【専門家直伝】イライラを減らす対応法5選
「イライラするのは自然なこと」と分かっていても、毎日続くと心がすり減ってしまいますよね。ここでは、発達支援や心理の専門家も勧めている、ママのイライラを減らす実践的な方法を5つ紹介します。すぐにできる工夫から、長く続けやすい工夫までありますので、できそうなところから取り入れてみてください。
子どもの言葉を否定せず“ゆるく受け止める”
子どもが同じ言葉を繰り返すと、つい「もうその話はいいでしょ!」と反応したくなるもの。でも否定されると、子どもは不安になってさらに繰り返すことがあります。
そこでおすすめなのが、“ゆるく受け止める”対応です。
例えば…
- 「そうだね」と短く返す
- 「うん、聞いてるよ」と軽く目を合わせる
- 時にはニコッと笑って返すだけ
こうすることで、子どもは「ちゃんと聞いてもらえた」と安心し、ママも無理に長く会話を続けなくて済みます。否定せずに軽く返すのがポイントです。
聞き流す工夫でママの心を守る方法
毎回真剣に答えていると、正直しんどいですよね。そんなときは、“聞き流すスキル”を使ってママ自身を守ることも大切です。
例えば、料理中に子どもが同じ言葉を繰り返したら、手を止めずに「そうだね」とだけ返す。場合によっては、相づちのバリエーションを増やして「へぇ〜」「うんうん」と交わすのもありです。
専門家も「子どもの繰り返しに全部反応する必要はない」と言っています。聞き流すのは“手抜き”ではなく、ママの心を守るための工夫なんです。
繰り返しを“ポジティブなやり取り”に変えるコツ
子どもの繰り返しにただ疲れてしまうよりも、遊びややり取りに変えてしまう方がラクなこともあります。
例えば…
- 「ママ!」と何度も呼ばれたら「はーい!」と少し大げさに返してみる
- 「これなに?」と繰り返すときは「これは○○!○○は何色かな?」と質問をプラスする
こうすることで、単なる繰り返しがコミュニケーションのきっかけになります。無理に会話を広げなくても、ちょっと工夫するだけで「やり取りが楽しくなる」瞬間が増えていきます。
歌やまねっこ遊びで「会話ごっこ」に発展させる
繰り返しは、遊びにするとママの負担も減ります。特におすすめなのが、歌やまねっこ遊び。
例えば…
- 子どもが「ワンワン」と言ったら、「ワンワン♪にゃんにゃん♪」と歌にして返す
- 子どもが同じ言葉を言ったら、ママも同じ動きを加えて「まねっこ遊び」にする
このやり取りは、言葉の発達にもプラスになりますし、「繰り返しが楽しい遊び」に変わるのでママのイライラも軽減されます。
イライラが爆発する前にできるリフレッシュ術
どんなに工夫しても、イライラが限界に近づく瞬間はあります。そんなときは、爆発する前に“自分をクールダウンさせる時間”を作ることが大切です。
例えば…
- 子どもが安全に過ごせる状況なら、数分だけ別の部屋に行って深呼吸
- お気に入りの飲み物を一口飲む
- 窓を開けて空気を入れ替える
これだけでも気持ちが切り替わりやすくなります。心理学的にも「小さなリフレッシュは大きなストレスを防ぐ効果がある」と言われています。「ちょっと休んでいい」と自分に許可を出すことが、長い子育てを続けるコツなんです。
ポイントは、「子どもを変えよう」とするのではなく、「ママの対応の仕方を少し変える」こと。それだけで、繰り返される言葉へのイライラが少しずつ軽くなっていきます。
【家庭でできる】言葉の発達を支える遊び&環境づくり
「同じ言葉を繰り返す」こと自体は子どもにとって自然な行動ですが、そこから少しずつ*ことばの世界”を広げてあげる工夫ができると、ママも安心しやすくなります。
ここでは、家庭で気軽に取り入れられる遊びや環境づくりのヒントを紹介します。どれも特別な教材は必要なく、日常生活の中で少し工夫すればできるものばかりです。
絵本・言葉カードで語彙を増やすアイデア
言葉を覚える一番の近道は、「たくさんの言葉に出会うこと」です。
そのために効果的なのが 絵本 と 言葉カード。
- 絵本は、同じものを何度も読んであげることで、子どもがフレーズを自然に覚えて口に出すようになります。繰り返しのフレーズが出てくる絵本(「いないいないばあ」など)は特におすすめです。
- 言葉カードは、動物や食べ物のイラストと単語が書かれているもの。子どもが「ワンワン!」と繰り返したら、「そうだね、犬だよ」と新しい言葉をプラスして返すと、少しずつ語彙が増えていきます。
絵本やカードを使うときは、「一緒に楽しむ」ことが大事。ママが笑顔で声を出していると、子どもも自然にマネしたくなります。
ごっこ遊び・リトミックで楽しくコミュニケーション
言葉は机に座って勉強するものではなく、遊びの中でこそ育ちやすいもの。おすすめは「ごっこ遊び」と「リトミック(音楽と動きの遊び)」です。
- ごっこ遊びでは、「いらっしゃいませ!」「ジュースどうぞ!」と簡単なフレーズを繰り返すだけでもOK。やり取りが自然に生まれ、会話のリズムを体験できます。
- リトミックでは、音楽に合わせて「トントン」「ワンワン」などの言葉を動きと一緒に出します。言葉+体の動きがリンクすると、記憶に残りやすく、発語を促す効果も期待できます。
遊びに取り入れることで、「言葉を繰り返す」ことがただのイライラ要因ではなく、コミュニケーションを楽しむきっかけに変わっていきます。
スケジュール表や絵カードで「安心できる日常」をつくる
発達障害の特性をもつ子どもに多いのが、「先の見通しが立たないと不安になる」という傾向です。その不安から同じ言葉を繰り返すこともあります。
そこで役立つのが、スケジュール表や絵カードです。
- 朝起きてから寝るまでの流れをイラストで見せると、子どもが安心して行動できます。
- 「今日は幼稚園」「帰ったらおやつ」などを絵カードで提示することで、「次は何をするんだろう?」という不安を減らせるんです。
安心できる環境があると、子どもの言葉の繰り返しも落ち着く場合があります。つまり、繰り返し言葉=環境からのSOSかもしれないんですね。
家庭でできる工夫は「難しいトレーニング」ではなく、日常の中でちょっとした工夫を積み重ねること。これを意識するだけで、子どもが言葉を楽しむ場面が増え、ママのイライラも和らいでいきます。
【要チェック】受診や専門相談を検討すべきサイン
「同じ言葉の繰り返し」は成長のひとつのステップとしてよくあることですが、場合によっては専門家に相談した方がいいサインになることもあります。
ここでは、気をつけたいポイントを3つに分けて解説します。
会話が成立しにくい・ことば以外の表現が少ない場合
3歳を過ぎると、短い会話が少しずつ成り立ってくる時期です。たとえば「おやつ食べたい」「これなあに?」など、やり取りのキャッチボールが少しずつ増えていくのが一般的です。
でももし…
- 質問に答えられず、オウム返しばかりになる
- 自分の気持ちや欲求を言葉で伝えにくい
- ジェスチャーや表情など、ことば以外のコミュニケーションが乏しい
こうした様子が見られるときは、言葉の発達に遅れがある可能性も考えられます。必ずしも発達障害とは限りませんが、専門家に相談すると安心できるケースが多いです。
強いこだわりや感覚過敏が見られる場合
発達障害の特性としてよく見られるのが、「こだわり」や「感覚の過敏さ」です。
例えば…
- 毎日同じルートでしか歩きたがらない
- 並べたおもちゃを崩されると強く怒る
- 大きな音や特定の素材の服を嫌がってパニックになる
こうした行動は「性格かな?」と思うこともありますが、繰り返し言葉と合わせて強く出る場合は、発達特性の影響も考えられます。
ママが「ちょっと生活に支障があるかも」と感じるなら、早めに相談してみることが安心につながるんです。
発達相談・児童発達支援など専門機関の活用方法
「相談したいけど、どこに行けばいいの?」と迷うママも多いですよね。実は身近なところに、頼れる機関があります。
- かかりつけ小児科:まずは気軽に相談できる入口。必要に応じて専門機関を紹介してくれます。
- 自治体の保健センター:無料で発達相談ができるところが多く、心理士や保健師に話を聞いてもらえます。
- 児童発達支援事業所:遊びや療育を通して、言葉やコミュニケーションをサポートしてくれる場所。
「受診」と聞くとハードルが高く感じますが、「相談してみる」だけでもOKなんです。早めに相談しておくと、ママの不安も軽くなり、必要な支援につながりやすくなります。
ポイントは、「困っているのは子どもだけじゃなく、ママ自身も」という視点です。イライラや不安を抱え込まず、気になるサインがあれば専門家を頼るのは前向きな一歩。子育てを一緒に支えてくれる人がいると分かるだけで、心がグッとラクになりますよ。
【ママケア】子育てストレスを軽くするセルフケア習慣
子育てをしていると、「自分のことは後回し」になりがちですよね。特に発達障害の特性がある子の育児は、想像以上に体力も気力も使います。だからこそ大切なのは、ママ自身が心と体を整えること。
セルフケアというと「特別な時間を作らなきゃ」と思いがちですが、実は日常の中でちょっと工夫するだけでもストレスはぐっと軽くなります。ここでは、無理なく続けられるセルフケア習慣を紹介します。
「完璧じゃなくていい」と自分をゆるめる考え方
多くのママが抱えているのが、「ちゃんとやらなきゃ」「いいママでいなきゃ」というプレッシャー。けれど、家事も育児も100点満点でやろうとすると、心も体も疲れてしまいます。
大切なのは、「完璧じゃなくて大丈夫」と自分に言い聞かせること。
- ご飯は手作りじゃなくても冷凍食品やお惣菜でOK
- おもちゃを片づけられない日があってもOK
- 子どもにテレビを見せてママが休むのもOK
むしろ「力を抜けるポイントを見つけること」が、長く子育てを続ける秘訣なんです。
同じ悩みを持つママとのつながりで心が軽くなる
「うちの子だけ違うのかな…」と感じると、孤独感でストレスが大きくなります。でも実は、同じ悩みを抱えているママはたくさんいます。
- 地域の発達相談会や親子教室に参加してみる
- SNSやオンラインコミュニティで同じ境遇のママとつながる
- 保育園や幼稚園で、信頼できる先生に気持ちを打ち明ける
誰かに「わかるよ」と共感してもらえるだけで、心がふっと軽くなることってありますよね。心理学的にも、「人と気持ちを共有すること」はストレス軽減に大きな効果があるといわれています。
一人時間を確保する家事・育児の工夫
「自分の時間なんてない…」と思うママも多いですが、ほんの5分でも一人の時間を持つことが心のリセットにつながります。
例えば…
- 洗濯物を畳まずそのまま使うなど、家事を減らす工夫をする
- 子どもが遊んでいる間に、コーヒーを一口飲む“休憩リチュアル”を作る
- 家族に「お風呂だけは一人で入りたい」とお願いする
「小さな一人時間」があるだけで、気持ちに余裕が戻ります。ママが笑顔になれば、子どもも安心して過ごせるようになります。
ポイントは、「自分を追い込まないこと」と「少しでも自分を大事にする時間を持つこと」。それだけで、毎日のイライラやストレスが和らぎ、子育てに向き合うエネルギーも自然と戻ってきます。
【体験談】3歳で同じ言葉を繰り返す子と向き合ったママたち
同じ言葉の繰り返しにイライラする気持ちは、多くのママが経験しています。ここでは実際に「どう向き合ったか」を体験談として紹介します。きっと、読むだけで「私も大丈夫」と安心できるはずです。
「安心のサイン」と気づいて楽になったエピソード
Aさん(3歳男の子のママ)は、息子さんが毎日のように「ママ、ママ」と何十回も呼んでくることに疲れていました。最初は「なんで同じことばっかり?」とイライラしていましたが、発達支援の先生から「それは“安心したい”というサインですよ」と教えてもらったそうです。
その日から「ママはここにいるよ」と笑顔で返すようにしたら、息子さんの呼びかけが少しずつ減ってきたとのこと。Aさんは「あ、子どもなりに安心を求めていたんだ」と気づいたことで、気持ちがぐっと楽になったと話していました。
言葉遊びで笑顔が増えた実践ストーリー
Bさん(発達が気になる3歳女の子のママ)は、娘さんが「これなに?これなに?」と何度も繰り返すことに悩んでいました。毎回きちんと答えていたけれど、正直しんどくなることも…。
そこで試したのが、「言葉を遊びに変える」工夫です。
例えば、娘さんが「これなに?」と聞いたときに、「これはリンゴ!じゃあこれは?」と逆に質問してみたり、「リンゴ♪リンゴ♪」と歌にして返してみたり。
すると娘さんは大笑い!繰り返しのやり取りがストレスではなく“楽しい遊び”に変わった瞬間でした。Bさんは「イライラが笑顔に変わるなんて思わなかった」と振り返っています。
支援センター相談で救われたママの体験
Cさん(3歳男の子のママ)は、息子さんが同じフレーズを繰り返すことに不安を感じ、「発達障害なのかな?」と毎日モヤモヤしていました。周りに相談できる人もなく、孤独感でいっぱいだったそうです。
思い切って地域の子育て支援センターの発達相談に行ってみたところ、専門のスタッフから「言葉の繰り返しは発達の段階でもよくあること。でも気になるなら一緒にサポートしていきましょう」と言われたそうです。
その言葉を聞いて、Cさんは「私だけで抱えなくていいんだ」と涙が出るほど安心したと話していました。今は月に数回、児童発達支援に通いながら息子さんと楽しく言葉遊びをしているそうです。
こうした体験談からわかるのは、「ママの受け止め方ひとつで気持ちが楽になる」ということ。そして「専門家や支援機関に相談することで孤独感が軽くなる」ということです。
さいごに|「同じ言葉を繰り返す」は子どもの大切なメッセージ
3歳の子どもが同じ言葉を繰り返すのは、「発達の一環」や「安心したい気持ちの表れ」であることも少なくありません。大人から見ると「なんで同じことばっかり?」と不思議に思えたり、ついイライラしてしまったりしますよね。でも、子どもにとっては “安心を得るための方法” や “言葉を覚えるトレーニング” になっていることがあるんです。
一方で、ママがイライラしてしまうのも自然なことです。毎日繰り返されると疲れるのは当然ですし、「普通に会話したい」という気持ちだってとてもよくわかります。だからこそ大事なのは、ママ自身が自分を責めないこと。「私も頑張ってる」「完璧じゃなくていい」と、自分の心を守るセルフケアを意識することが必要です。
そして、もし「これはちょっと気になるな」「発達障害かもしれない」と感じることがあれば、早めに専門機関に相談することが安心につながります。児童発達支援センターや自治体の子育て相談窓口は、ママが一人で悩みを抱え込まないためのサポート場所。早く相談したからといって不利益になることはありませんし、むしろ「何もなかった」と安心できるきっかけになることも多いです。
まとめると、
- 「同じ言葉の繰り返し」は子どもなりの大切なメッセージ
- ママのイライラも自然なこと。だからこそセルフケアが大事
- 気になるときは専門家に相談するのが安心への近道
この3つを覚えておくだけで、少し心が軽くなるはずです。
子育ては正解が一つじゃないからこそ、焦らず、ゆっくり、子どものペースとママの気持ちの両方を大事にしていきましょう。
以上【3歳で同じ言葉を繰り返す子にイライラ…発達障害との違いと正しい対応法について】でした。

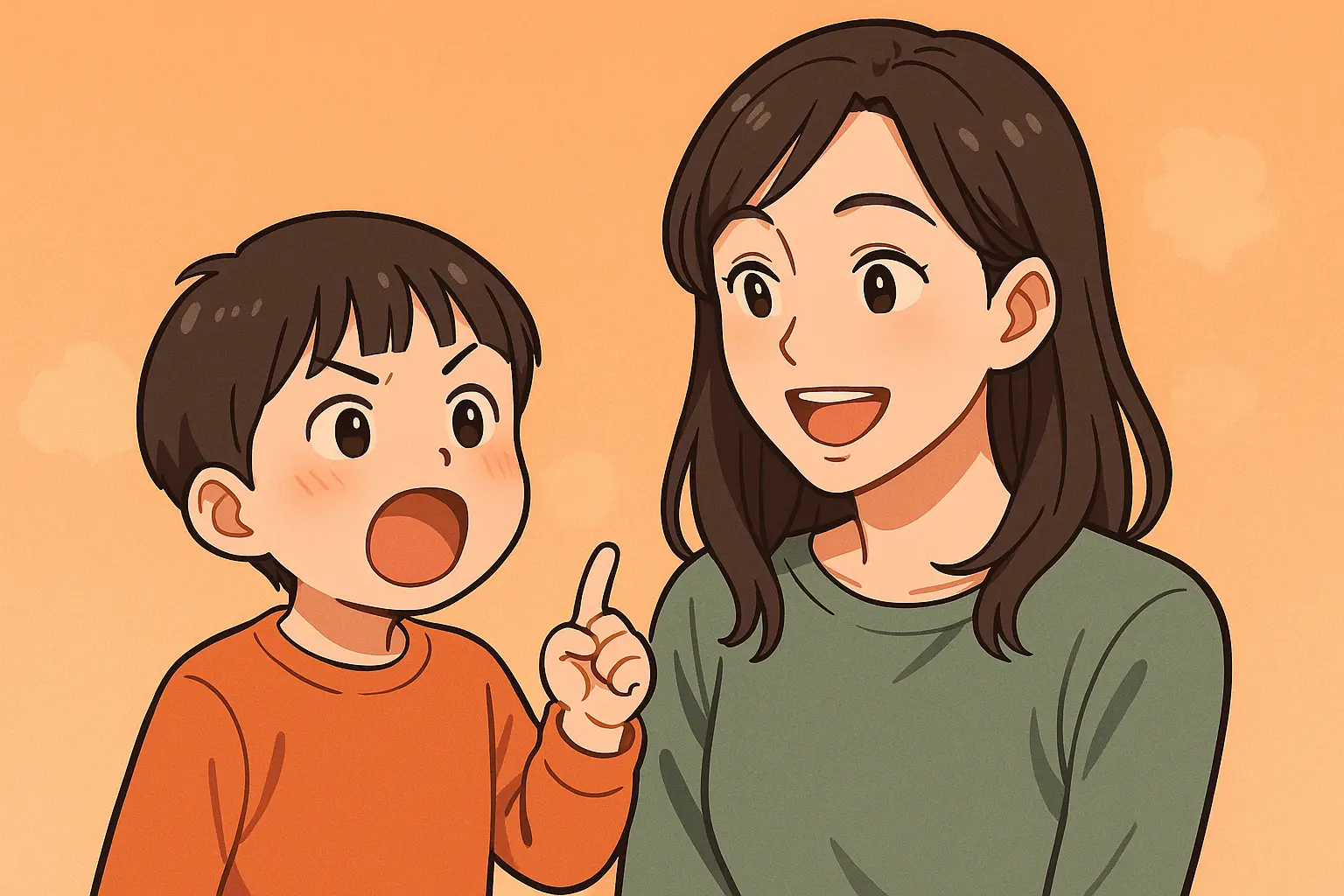









コメント