家庭学習がうまくいかない…そんなお悩みに!通信教育で「できた!」を育てよう
「机に向かわせるだけでひと苦労…」
「ドリルをやらせても集中が続かない…」
「周りの子と比べて遅れてる気がして不安…」
発達が気になるお子さんの家庭学習に取り組んでいると、こうした悩みを感じることってありませんか? 実はこのような困りごとは、子どものやる気や性格の問題ではなく、「学習スタイルが合っていない」ことが原因の場合も多いんです。
最近では、発達の特性を理解したうえで作られた通信教育サービスが増えてきていて、家庭学習の選択肢がぐっと広がりました。
特に注目されているのが、子ども一人ひとりのペースや興味に合わせて取り組める「自宅型学習」。中でも「通信教育」は、以下のような理由から、多くのご家庭で取り入れられています。
- 決まった時間に通う必要がなく、家庭のペースで進められる
- 視覚・聴覚など、感覚の得意・不得意に合わせた教材設計がされている
- ゲーム感覚で取り組めるなど、子どもが楽しく学べる仕掛けが満載
- 保護者がそばでサポートしやすく、成長を実感できる
また、発達障害やグレーゾーンのお子さんにとって、「できた!」という成功体験を積み重ねていくことは、自己肯定感や学習意欲につながるとても大切なステップです。
本記事では、そんな発達が気になる子にぴったりな通信教育を5つ厳選してご紹介します。
さらに、「うちの子に合う教材はどれ?」「どう選べば失敗しない?」という保護者の方の疑問にもお答えできるよう、選び方のポイントや比較表も盛り込んでいます。
発達特性のあるお子さんでも、楽しく学び、自信をつけられる方法は必ずあります。
この記事を通じて、家庭でも安心して学べる通信教育との出会いがあればうれしいです。
通信教育が発達が気になる子にピッタリな理由とは?
「集団だと難しい…」を解決!通信教育が合う子の特徴と5つの理由
「学校の授業についていけないみたい…」
「プリント学習がどうしても苦手で、つい親子でイライラしてしまう…」
発達が気になるお子さんと家庭学習に取り組んでいると、そんなモヤモヤにぶつかることってありますよね。
でも、それって本当に「できない」からじゃなくて、「その子に合った学び方になっていない」だけかもしれません。
最近では、発達の特性をもつお子さん向けの教材やサポートが進化していて、その中でも通信教育は「自分のペースで学びたい子」にとって、かなり相性がいい学習スタイルだと言われています。ここでは、その理由を5つの視点からご紹介します。
1. 自分のペースで進められるから、焦らなくていい
集団の授業では「今日はここまで」と進度が決まっていますが、発達に特性がある子どもの場合、そのスピードが合わないこともよくあります。
通信教育なら、「わかるまで何度でも」「好きな時間に短時間ずつ」など、ペースも量も自由に調整できるので、子どもが混乱せずに安心して学べます。マイペースに取り組めることは、自己肯定感のアップにもつながります。
2. 感覚特性に合わせた「見て・聞いて・動かせる」教材が豊富
発達が気になる子の中には、視覚優位(目で見て理解するのが得意)な子や、聴覚過敏(音に敏感)な子、触覚が苦手な子もいます。
通信教育は、そうした感覚の特性に配慮した設計の教材が多く、タブレット学習では「視覚で見て理解」「音声で指示を聞く」「画面をタップして操作する」など、複数の感覚を使って学べるのが大きな魅力。
たとえば、図形の動きや数字のブロックを動かす学習など、「体感しながら学べる工夫」が詰まっている教材も増えています。
3. 苦手な部分はスモールステップで。得意なところはどんどん伸ばせる
発達特性のある子どもには、「国語は苦手だけど算数は得意」「文字を書くのは苦手だけど話すのは得意」など、得意・不得意がはっきりしているケースが多いです。
通信教育では、こうした差に対応できるよう、苦手な部分はスモールステップで丁寧に、得意なところはどんどん先に進められる教材も多くなっています。
特に無学年方式を採用している教材は、年齢や学年にとらわれず、「今のその子」に合ったレベルからスタートできるのが嬉しいポイント。
4. 通わなくていい安心感と、親のサポートのしやすさ
毎日学校に通うだけでもエネルギーを使う発達の特性があるお子さんにとって、「習い事に通う」のはかなりの負担になることも。
その点、通信教育なら自宅で学べるので、移動や人間関係のストレスがありません。また、親がそばで見守れることで、子どもの学びや成長をリアルタイムで感じられるというメリットもあります。
「今日は調子がいいから多めにやろう」「今日は5分だけにしよう」など、親子で調整しながら進められる自由度の高さは、家庭学習を続けるうえでとても大きな魅力です。
5. 「できた!」が増えると、自己肯定感が育つ
発達が気になる子は、学校や集団の中で「できない」と言われたり、比べられたりすることが多く、自信を失いやすい傾向があります。
でも、通信教育で自分のペースで学んでいくと、「できた!」「わかった!」という達成感を積み重ねることができます。
これは、学力の向上だけでなく、「学ぶのって楽しい」「自分にもできることがある」という気持ちを育てるきっかけに。
こうしたポジティブな経験こそが、将来の自己肯定感や社会性を育てる土台になります。
まとめ:学び方を変えれば、「できない」は「できる」に変わる
発達が気になる子どもにとって、通信教育はまさに「学び方そのものを変える」選択肢。
学校と同じ方法でうまくいかなくても、その子に合ったスタイルなら驚くほど前向きに学べるケースはたくさんあります。
このあと紹介する5つのおすすめ教材は、いずれも発達特性への理解があるものばかり。
それぞれの特徴を比べながら、お子さんにぴったりの一冊(または一台)を見つけてみてくださいね。
失敗しない選び方!通信教育を選ぶ前にチェックしたい5つのポイント
「うちの子に合う?」を見極める!後悔しない通信教育選びのコツ
通信教育って、種類も多いしそれぞれ特徴もバラバラで、「正直、どれを選んだらいいかわからない…」という声、よく聞きます。
特に発達が気になるお子さんの場合は、教材との“相性”が学習のモチベーションに大きく影響することも。無理に合わない教材を使い続けると、やる気が下がったり、自己肯定感を損ねてしまったりするリスクもあるんですよね。
そこでこの章では、「これは外せない!」という通信教育選びの5つのポイントをわかりやすく解説します。迷ったときは、このチェックリストを見ながら比較すると、スムーズに選びやすくなりますよ。
1. 子どもの発達特性に合っているかどうか?
発達に特性がある子どもは、感覚の得意・不得意や、理解しやすい学習スタイルが一人ひとり違います。
たとえば、
- 目で見て覚えるのが得意(視覚優位)
- 耳で聞くほうが理解しやすい(聴覚優位)
- じっと座るのが苦手/手を動かしながら覚えるタイプ
など、タイプはさまざま。
通信教育を選ぶときは、その子の得意なインプット方法に合っているかどうかをしっかりチェックしましょう。
最近の教材は、「タップで動かせる」「音声でガイドが入る」「アニメーションで学べる」など、視覚・聴覚・触覚に訴える工夫がされているものも多いので、特性に合わせて選ぶと失敗しにくいです。
2. 学習の進度や難易度が調整できるか?
学校の進度に合わせた教材もありますが、発達が気になるお子さんにとっては「今の学年」よりも、「今の理解度」に合った教材のほうが学びやすいこともあります。
そこで注目したいのが、無学年方式や個別最適化といった仕組み。
これがあると、
- 「得意な分野はどんどん進める」
- 「つまずいている分野は、繰り返し戻ってやり直せる」
という学習スタイルが可能になります。
年齢や学年にとらわれず、子ども自身の力に合った学びができることは、ストレスの軽減にもつながります。できるだけ、「柔軟に調整できる仕組み」がある教材を選びたいですね。
3. 保護者がサポートしやすい仕組みがあるか?
通信教育って、子どもが一人でどんどん進めてくれたら理想だけど、実際は「つまづいたときに親がフォローする場面」もけっこうあります。
そのときに役立つのが、
- 学習記録の見える化
- わかりやすい進捗レポート
- 子どもへの声かけ例や保護者向けのアドバイス機能
など、親子で学びを共有できるツールやサポート体制が整っているかどうかです。
また、発達特性のある子は「何が苦手なのか」を客観的に見つけにくい場合もあるので、教材側から「苦手ポイント」を可視化してくれる機能があると、親もフォローしやすくなります。
4. 楽しんで続けられる“しくみ”があるか?
「よし、今日もやるぞ!」と毎日モチベーション高く取り組むのは、大人でもなかなか難しいですよね。
子どもならなおさら、楽しさや達成感がないと続けるのはハードルが高いものです。
通信教育では、
- ごほうび機能やポイント制度
- キャラクターとのやりとりやストーリー仕立ての進行
- ゲームのような演出や音・アニメーション
など、子どもが「自分からやりたくなる工夫」が用意されているものがあります。
「どの教材が一番楽しそうに取り組めそうか?」という視点も忘れずに。
継続できる仕組み=習慣化しやすい=成果につながりやすいという流れは、どの子にとっても共通です。
5. 発達支援の視点が取り入れられているか?
最後のポイントは、教材そのものに「発達障害やグレーゾーンの子への理解」があるかどうか。
具体的には、
- 特別支援教育の専門家が監修している
- 発達障害児向けの学習設計がなされている
- 特別支援学校や支援学級でも導入されている実績がある
などが挙げられます。
こうした教材は、「どこでつまずきやすいか」「どうすれば理解しやすいか」への配慮が細かく行き届いていることが多く、実際に使用しているご家庭の評価も高い傾向があります。
「なんとなく人気だから」ではなく、「この子にとって使いやすいか」で選ぶのが大切ですね。
まとめ:選ぶ前に「子どもと教材の相性チェック」がカギ!
通信教育を選ぶとき、つい「値段」や「口コミの数」に目がいってしまいがちですが、本当に大事なのは“その子に合っているかどうか”。
今回ご紹介した5つの視点──
①発達特性への合致
②進度調整の柔軟性
③保護者サポートのしやすさ
④続けやすさの仕組み
⑤発達支援の視点の有無──を意識して比較することで、後悔しない選択ができます。
このあとご紹介するおすすめ5教材は、いずれもこれらのポイントをしっかり押さえたサービスばかり。
「うちの子に合うのはどれ?」とイメージしながら、読み進めてみてくださいね。
人気5教材を徹底比較!発達が気になる子どもにおすすめの通信教育
現役ママも絶賛!発達の特性に寄り添う通信教育5選【2025年最新版】
ここでは、発達が気になるお子さんに特におすすめの通信教育5つをピックアップしてご紹介します。
どれも人気があり、「わが子に合った学び方が見つかった!」と好評の教材ばかり。
それぞれに特色があるので、「どんな子に向いているか」や「どんなサポートがあるのか」を客観的に比べてみてくださいね。
ワンダーボックス|遊びながら学べる!創造力を伸ばすSTEAM教材
「机に向かうのが苦手」「自由な発想が得意」なお子さんには、ワンダーボックスがイチオシ。
STEAM(科学・技術・工学・アート・数学)教育をベースにした体験型教材で、アプリと紙の教材を組み合わせた“遊びながら学べる”通信教育です。
特徴とおすすめポイント
- 決まった答えがない自由な課題が中心
- 創造性や論理的思考を育てる設計
- パズル、図形、プログラミングなどが「楽しい!」に変わる
発達支援的な視点
- 親子で一緒に取り組める仕組みが多く、「できた!」の共有がしやすい
- 自分のペースで進められるため、プレッシャーを感じにくい
対象年齢・料金
- 年中〜小学生(4歳〜10歳)
- 月額4,200円(税込)〜 ※年払いで割引あり
こんな子におすすめ!
- じっくり考えるのが好きな子
- アイデアを出すのが得意な子
- ルールに縛られすぎるのが苦手な子

RISUきっず/RISU算数|算数に特化!無学年制で「得意」がグングン伸びる!
「数字が好き」「パズル感覚で解くのが楽しい!」というタイプの子にぴったりなのが、RISUきっず/RISU算数です。
算数特化型の通信教育で、無学年制を採用しているのが最大の特長。
特徴とおすすめポイント
- 学年にとらわれず、自分のレベルで先取りもOK
- タブレットに表示された問題を解いていくシンプルな構成
- AIが理解度を分析して出題内容を調整してくれる
発達支援的な視点
- 視覚的にわかりやすく、シンプルなデザインで集中しやすい
- 「わかる→解ける→進める」のサイクルが、達成感につながりやすい
対象年齢・料金
- 年中〜小学生
- 月額2,948円〜
こんな子におすすめ!
- 数字や計算が得意な子
- 得意を伸ばしたい子
- 自信をつけたい子

すらら|特別支援対応あり!やる気を引き出す対話型オンライン教材
「うちの子、文章問題になると苦手意識が…」
そんな時に試してほしいのが、すらら。
国語・算数・英語の3教科に対応し、発達障害支援の専門家監修による“特別支援コース”があるのが大きな特徴です。
特徴とおすすめポイント
- アニメキャラとの対話形式で進む「つまずき診断つき」個別学習
- 苦手なポイントをAIが分析し、復習タイミングも自動で調整
発達支援的な視点
- LDやADHD、不登校の子にも対応できる仕組みが整っている
- 教材の設計がスモールステップで無理がない
対象年齢・料金
- 小学生〜高校生まで幅広く対応
- 月額4,400円〜
こんな子におすすめ!
- 読み書きに困難さがある子
- 一斉授業が苦手な子
- 自宅でじっくり取り組みたい子

スマイルゼミ|続けやすさNo.1!タブレット一台で全教科まるっとカバー
「とにかく家で学習習慣をつけたい!」というご家庭に人気なのがスマイルゼミ。
専用タブレット1台で、国語・算数・理科・社会・英語までオールインワンで学べる定番の通信教育です。
特徴とおすすめポイント
- 教科書準拠で学校の勉強をしっかりサポート
- AIが苦手を分析してくれる「きみ専用カリキュラム」搭載
発達支援的な視点
- 書き取り練習や反復学習が豊富で、定着しやすい
- シンプルなUIで、子どもが迷わず取り組める設計
対象年齢・料金
- 年少〜中学生
- 月額3,630円〜
こんな子におすすめ!
- 学習習慣をつけたい子
- タブレット操作が得意な子
- 反復が必要な子

天神|発達支援学校でも採用!基礎をしっかり固める王道学習ソフト
「学校の授業に合わせて、しっかり基礎を固めたい」という方に根強い人気なのが、天神。
教科書に準拠した内容で、特別支援学級などでも採用されている本格派です。
特徴とおすすめポイント
- パソコンを使って取り組む形式。教科ごとに細かく選べる
- 学校の進度と同じ内容だから、復習にも◎
発達支援的な視点
- ナレーション付きで視覚+聴覚のWサポート
- 反復が簡単で、確実に理解を積み上げられる
対象年齢・料金
- 幼児〜高校生(教材購入制、1教科ごとの価格設定)
- 初期費用が高め(数万円〜)だが買い切り型
こんな子におすすめ!
- 確実に基礎力をつけたい子
- 学校の授業についていきたい子
- 反復練習が得意な子
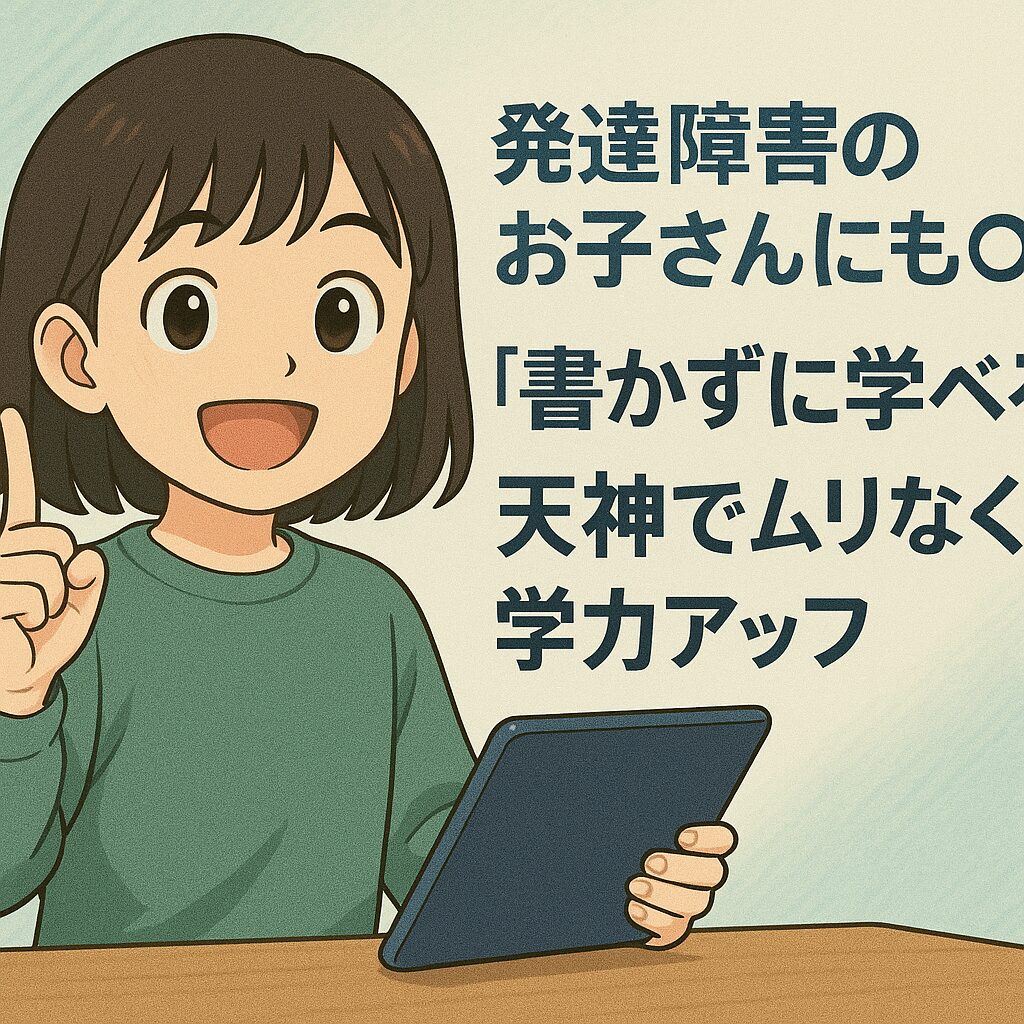
まとめ:どの教材も「正解」。大切なのは“その子に合っているか”
今回ご紹介した5つの通信教育は、それぞれ特長もサポート体制も異なりますが、共通しているのは「発達特性に寄り添っている」こと。
- 創造力を育てたいなら「ワンダーボックス」
- 算数が得意なら「RISU」
- 特別支援対応を求めるなら「すらら」
- 習慣化重視なら「スマイルゼミ」
- 教科書ベースで基礎固めしたいなら「天神」
迷ったときは、お子さんの「得意」「苦手」「学ぶ環境」を軸に選んでみると、ぐっと絞りやすくなりますよ。
あの教材はどんな子に合う?タイプ別おすすめ早見表
「うちの子はどれ向き?」が一目でわかる!通信教育タイプ別診断チャート付き
ここまで読んで、「それぞれ良さはわかったけど、結局どれを選べばいいの?」と思った方も多いのではないでしょうか。
実際、「発達が気になる子に合う通信教育」といっても、子どもの性格や特性によって向き・不向きは違います。
そこでこの章では、子どものタイプ別におすすめの教材をマッチングしてみました!
感覚の傾向・得意不得意・学び方のスタイルなど、日々の様子を思い浮かべながらチェックしてみてくださいね。
タイプ別おすすめ早見表|どの教材がうちの子向き?
| 子どものタイプ | 向いている教材 | 理由・特徴 |
|---|---|---|
| 好奇心旺盛!自由な発想が得意 | ワンダーボックス | 自由課題で創造力を伸ばせる。感覚遊びに強い子にも◎ |
| 数字・計算が得意!黙々と進めたいタイプ | RISUきっず/RISU算数 | 無学年制で先取りOK。視覚的にシンプルで集中しやすい |
| 読み書きが苦手。音声や対話での理解が得意 | すらら | 特別支援対応あり。つまずきを見つけてスモールステップで進められる |
| 継続が苦手。楽しみながら学びたい子 | スマイルゼミ | ゲーム感覚+ごほうび機能で学習習慣をつけやすい |
| 学校の授業についていきたい。教科書ベースが安心 | 天神 | 教科書準拠で基礎を反復練習。特別支援学校でも導入実績あり |
こんなチェックポイントも参考に!
「うちの子、ちょっとタイプが混ざってるかも…」
そんな場合もありますよね。そこで、さらに選びやすくなるように保護者視点のチェックポイントもまとめてみました。
感覚特性が強め(感覚過敏・視覚or聴覚優位など)
→ 「わかりやすいUI」「シンプルな構成」「自分で操作できる教材」がおすすめ。
→ RISUやスマイルゼミは余計な刺激が少なく、取り組みやすいです。
集団行動や一斉授業が苦手・不登校気味
→ 対話型の教材や、自由度が高いものが合いやすいです。
→ すららやワンダーボックスが、ストレス少なく進められます。
親の負担が少ないものを選びたい
→ 自動採点・AI診断・レポート機能がある教材が便利!
→ スマイルゼミは家庭でのフォローが最小限でOK。
苦手を克服したい(読み書き・計算など)
→ スモールステップ&反復設計がしっかりあるものを選びましょう。
→ 天神やすららは、苦手な単元を丁寧に強化できます。
通信教育選びに迷ったときのアドバイス
「どれもよさそうだけど、うちの子に本当に合うのはどれ?」と迷ったときは、“子どもの反応”を基準にするのが一番のヒントになります。
体験版があれば一緒にやってみたり、教材のサンプル動画を見せたりして、興味を持ったときの目のキラキラ感や集中の様子を観察してみてください。
また、教材によっては、
- 無料体験や資料請求ができる
- タブレットをレンタルできる
- 途中解約が可能でリスクが少ない
など、始めやすさも工夫されているところが多いです。気になった教材はまず“お試し”から入ってみるのもおすすめです。
まとめ:「うちの子にぴったり」を見つけるコツは“観察”と“比較”
今回のタイプ別表やチェックポイントを見て、少しでも「これかも!」と思える教材があれば、まずは情報収集してみてください。
大事なのは、「合っているかどうか」を見極めること。
それだけで、子どもが前向きに取り組めるようになったり、家庭の負担がぐっと軽くなったりします。
次章では、実際に通信教育を無理なく続けるためのコツや工夫について紹介していきます。
「始めたのに三日坊主で終わった…」なんてことにならないよう、ぜひ参考にしてみてくださいね!
続かない…を卒業!家庭学習を習慣化する3つのコツ
怒らず続ける!通信教育を“楽しい習慣”に変える親のアイデア集
せっかく通信教育を始めても、気づけばタブレットがホコリをかぶっていたり…「結局、続かなかった」という声、実は少なくありません。
特に発達が気になるお子さんの場合、習慣づけには“コツ”が必要なんですよね。
でも大丈夫!
やり方を少し工夫するだけで、子どもが“自分からやりたくなる”流れをつくることはじゅうぶん可能なんです。
この章では、親子でストレスなく家庭学習を続けていくために知っておきたい、3つの実践的なコツをご紹介します。
1. 「やらせる」より「一緒に楽しむ」が習慣化の第一歩
家庭学習が続かない理由のひとつが、「やらされ感」。
「早くやりなさい」「どうしてサボるの?」と声をかけるたび、子どもはどんどんやる気を失ってしまいます。
そこでおすすめなのが、学習を“親子のコミュニケーション”として楽しむ姿勢。
たとえば…
- 親も「今日はどんな問題?見せて〜」と興味を持つ
- 解けたら「おっ!やるね〜!」とちょっと大げさなくらい褒める
- 難しい問題では「ここは一緒に考えてみようか」と仲間感を演出する
こうすることで、子どもは「やらなきゃ」から「見てもらいたい」「一緒にやるのが楽しい」にシフトしていきます。
特に発達が気になる子は、「できた!」という肯定的なフィードバックをもらうことで自己肯定感がアップし、次の行動へのモチベーションにもつながります。
2. 無理に詰め込まない!“短く・軽く・楽しく”が続くコツ
「1日30分!」と意気込んでも、現実はうまくいかないもの。
特に集中力が続きにくいお子さんの場合は、“短くてOK”のマインドが大事です。
実は、5分でも10分でも、毎日続けることの方が学習効果は高いと言われています。
しかも「今日はこれだけでいいよ」と区切ることで、子どもも安心して取り組みやすくなります。
さらに…
- タイマーをセットして“学習タイムは短く集中”
- 終わったら「おつかれ〜!」のハイタッチやスタンプシールで達成感UP
- 毎日決まったタイミングにする(例:夕食前・おやつの後など)
こうしたちょっとした習慣の積み重ねが、“学習が日常に溶け込む”第一歩です。
3. 目に見える“ごほうび”でモチベーションをキープしよう
どんな子でも、「がんばった結果が目に見える」ことでやる気が持続しやすくなります。
これは大人も同じですよね。
通信教育によっては、スタンプやポイント機能、ごほうびアイテムなどを使って、「がんばったらうれしいことがある」仕組みを取り入れているものもあります。
でもそれがない場合でも、家庭で簡単に作れます。
たとえば…
- カレンダーに毎日シールを貼る「見える化習慣」
- 一週間できたら「好きなおやつ」や「公園に行く」など小さなごほうび
- 学習記録ボードを作って家族で掲示(パパにも見てもらえる!)
ただし、ここで大切なのは「ごほうびのためにやる」ではなく、「やったらいいことがついてくる」という自然な流れにすること。
あくまで目的は「学ぶ楽しさ」や「達成感」にあることを忘れずに。
番外編:親自身が「焦らない」「怒らない」ことも大切です
「続けてほしい」「学力を伸ばしたい」
そう思うからこそ、つい口調がきつくなったり、「どうしてやらないの!」と感情的になってしまうこと、ありますよね。
でも、子どもにとって家庭は安心できる場所であってほしい場所。
だからこそ、親が「まぁ今日はちょっとだけでもOK」「できたところを認めよう」という心持ちでいることが、結局はいちばんの“続く秘訣”かもしれません。
まとめ:「勉強=楽しい時間」にできれば、自然と続いていく!
家庭学習って、「続けること」が一番難しいけれど、やり方をちょっと工夫するだけで驚くほど変わることもあります。
- 親子で一緒に楽しむ
- 短時間でもOKと割り切る
- ごほうびや見える化で達成感を得る
この3つを意識することで、通信教育は“勉強”から“楽しい習慣”に変わっていくはずです。
次の章では、そんな家庭学習についてよくある疑問や不安をQ&A形式でまとめていきます。「うちの場合どうなの?」という声にもしっかりお答えしますので、ぜひ続けて読んでみてくださいね!
通信教育の気になるギモンを解決!よくある質問まとめ
「本当にうちの子に合うの?」「学校と両立できる?」Q&Aで不安を解消!
ここまで読んで、「通信教育、ちょっと気になってきたかも!」と思ってくれた方も多いかもしれません。
でも一方で、こんな疑問や不安もあるのではないでしょうか?
- 本当にうちの子でも続けられるのかな?
- 学校の勉強と内容がかぶったりしない?
- サポートってちゃんとしてる?
- タブレット学習って目に悪そう…
などなど、始める前に知っておきたい“リアルな疑問”はたくさんありますよね。
この章では、実際によくある質問をまとめて、現実的で安心できる回答をお届けします。
不安を一つずつクリアにして、納得して通信教育を取り入れていきましょう!
Q1. 発達が気になる子でも本当に続けられる?途中でイヤにならない?
これは最も多く寄せられる質問のひとつ。
結論から言うと、「子どもに合った教材を選べば続けやすい」です。
たとえば、集中力が続きにくいお子さんには、学習時間を自由に調整できる教材や、短時間で区切れる構成のものが向いています。
また、アニメーションやキャラクターとやりとりする教材は、飽きずに続けられる工夫がされているため、モチベーション維持にもつながります。
ポイントは、「最初から完璧を目指さないこと」。
「1日5分でもOK」「できた日はいっぱい褒める」くらいのゆるいスタートが、長続きの秘訣です。
Q2. 学校の勉強とのバランスは?かぶったり、ずれたりしない?
学校の授業とのバランス、気になりますよね。
実は通信教育には、大きく分けて2つのタイプがあります。
- 教科書準拠型(例:スマイルゼミ・天神) → 学校の進度に合わせて学べる
- 個別最適型・探究型(例:ワンダーボックス・RISU・すらら) → 興味やレベルに応じて学べる
つまり、「学校と同じ内容で復習したい子」には教科書準拠型が向いていて、
「得意な分野を伸ばしたい」「学校の内容にとらわれずに学びたい」子には探究型が合うということ。
もちろん、組み合わせて使うのもOK!
たとえば、「平日はスマイルゼミで学校の復習、週末はワンダーボックスで遊びながら学習」なんて活用法も◎です。
Q3. 親のサポートってどれくらい必要?忙しくても大丈夫?
これは家庭によって気になる度合いが大きく変わるポイントです。
基本的に、タブレット型の通信教育は“子どもがひとりでも取り組みやすい設計”になっているものが多いです。
特にスマイルゼミやRISUなどは、自動採点・音声ガイド・進捗管理ツールなどが充実していて、保護者の負担は最小限に抑えられます。
ただし、お子さんがまだ慣れていないうちは、最初の数週間だけは“そばで見守る期間”をつくるのがおすすめ。
親がそばにいるだけで安心感が増し、「学習=安心できる時間」になっていきますよ。
Q4. タブレット学習って、視力に悪くないの?画面見すぎが心配…
これはよくある不安ですが、結論から言えば、適切に使えば問題ありません。
多くの通信教育では、
- ブルーライトを抑えたディスプレイ設計
- 1回ごとの学習時間が短く区切られている
- 30分ごとに「休憩しよう」と表示が出る設計
など、目への負担に配慮された工夫が施されています。
また、保護者側でも、
- 明るい部屋で学習させる
- 1回10〜15分に区切る
- 終わったら遠くを見る・体を動かす習慣をつける
などの対策を心がけることで、過度な負担を防ぐことができます。
Q5. 教材が合わなかったときの“おためし”方法はある?
教材が合うかどうかは、やっぱり実際に使ってみないとわからない…というのが本音ですよね。
安心してください。
最近の通信教育は、無料体験・資料請求・返金保証など、お試し制度がとても充実しています。
例:
- ワンダーボックス:資料請求+体験キット送付あり
- RISU:体験後にキャンセルOK(条件あり)
- スマイルゼミ:2週間の全額返金保証付き
- すらら:申し込み前に体験動画やサンプル問題が見られる
- 天神:教室体験や説明会あり(地域による)
なので、まずは“体験してから決める”という流れがおすすめです。
まとめ:不安を解消して、わが子にピッタリの学びを
通信教育を始めるとき、不安や疑問があるのは当たり前。
でも、今の通信教材は「発達特性のある子どもにもやさしい設計」になっているものが本当に増えています。
- ペースに合わせて進められる自由さ
- 学校と両立しやすいカリキュラム設計
- 親の負担も軽く、無理なく続けられる工夫
そして何より、「わかった!」「できた!」という小さな成功体験が、子どもの自信になっていくんです。
次章では、そんな通信教育で得られる“変化”や“成長”をまとめながら、どのように選び進めていけばいいのか、最終的なまとめをお届けします。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
まとめ~子どもの「得意」と「自信」を引き出す通信教育、見つけてみませんか?
迷ったらここをチェック!5教材の特徴まとめ&選び方の再確認
ここまで読んでくださった方、本当にお疲れさまでした!
通信教育ってひとことで言っても、それぞれ内容もアプローチも違っていて、「どれを選べばいいのか迷ってしまう…」という気持ち、よくわかります。
でも逆に言えば、それだけ「子どもに合う教材が見つかりやすくなってきた」という時代でもあるということ。
今は、発達が気になるお子さんに配慮された教材や、個別の特性に合わせて学べるツールがどんどん登場しています。
“できない”を責めるより、“できた!”を見つけて伸ばす。
それを叶えるのが、今どきの通信教育です。
今回紹介した5つの教材をおさらい!
| 教材名 | 特徴 | 向いている子 |
|---|---|---|
| ワンダーボックス | STEAM教育×アナログ教材/自由な発想を育てる | 創造力が豊か・手を動かすのが好きな子 |
| RISUきっず/RISU算数 | 無学年制/算数特化の個別最適化 | 数字や計算が得意・先取りしたい子 |
| すらら | 対話型学習/特別支援対応あり | 読み書きに困難さがある・不登校傾向の子 |
| スマイルゼミ | 教科書準拠/全教科対応のタブレット型 | 継続が苦手・毎日の習慣をつけたい子 |
| 天神 | 教科書準拠/反復学習と基礎固めに強い | 学校の授業と連動させたい・理解を深めたい子 |
教材選びで大切なのは、“その子らしさ”に目を向けること
どれが良い・悪いではなく、どの教材が「その子に合っているか」が何より大事な視点です。
たとえば…
- 「集中が続かない」なら、短時間でも楽しめる工夫がある教材を
- 「得意を伸ばしたい」なら、無学年制や個別対応がある教材を
- 「親のサポートが負担」なら、進捗管理や自動採点がある教材を
こんなふうに、子どもの特性×家庭のスタイルで照らし合わせながら選ぶと、ピッタリの教材が見つかりやすくなります。
最後に:子どもの“今”を大切にした学びを
発達が気になる子どもにとって、「自分のペースで学べる」「比べられずに成長できる」環境って、本当に大きな安心感になります。
そしてその中で得られる小さな「できた!」は、やがて大きな自信と笑顔に変わっていきます。
通信教育は、そんな“わが子らしい学び方”を見つけるための、やさしい選択肢のひとつです。
もし今、「なんだかうまくいかないな…」と感じているなら、ちょっと視点を変えて、通信教育を試してみるのもアリかもしれません。
焦らず、比べず、その子のペースで。
そんな家庭学習のパートナーが、この記事をきっかけに見つかれば嬉しいです。











コメント