子どもの行動に振り回されて、「なんでこんなにわがままなの?」と感じたことはありませんか?
スーパーで急に泣き出す、予定が変わると大パニック、順番を待てずに走り出す……。
毎日の育児の中で、どう対応すればいいのか悩んでしまうことも多いですよね。
でも、ちょっと待ってください。その行動、実は「わがまま」ではなく、別の理由があるかもしれません。
この記事では、子どもの行動の「本当の理由」を知り、親としてどんなふうに関わればいいのかを具体的にお伝えします。
お子さんとの毎日がもっとラクになるヒントが詰まっているので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
それ、本当に「わがまま」?
自閉症の子どもの行動が「わがまま」と見られてしまうことがあります。スーパーで大声を出す、急に怒り出す、好きなことをやめられない──こういった行動を目にして、「駄々をこねている」と感じる人も少なくありません。
しかし、それは本当に「わがまま」なのでしょうか?
自閉症の特性を理解すると、その行動の裏には深い理由が隠れていることがわかります。本記事では、こうした誤解を解消し、自閉症の子どもとの接し方や対処法を具体的に解説します。
「わがまま?」いいえ、それは自閉症の特性です!
「うちの子、すぐ怒るし、ワガママがひどい…」そんなふうに感じること、ありませんか?
でも、ちょっと待ってください。それ、本当に「わがまま」でしょうか?
実は、自閉症の子どもが見せる行動の多くは、「わがまま」ではなく、自閉症の特性によるものです。つまり、本人の意思でコントロールできるものではなく、生まれつきの脳の働き方によるものなのです。
ここでは、なぜ自閉症の子どもの行動が「わがまま」に見えてしまうのか、その理由を解説していきます。
どうして「わがまま」に見えるの?自閉症の特性を解説!
自閉症スペクトラム障害(ASD)は発達障害の一つで、子どもによって特徴はさまざまですが、特に以下のような3つの特性が共通して見られます。
① こだわりの強さ:特定のやり方や順番に固執する
自閉症の子どもは、決まった手順やルーティンを大切にすることが多いです。たとえば、「家に帰ったら必ず玄関で3回ジャンプする」「赤いお皿じゃないとご飯を食べない」といった行動が見られます。
このこだわりが崩れると、強いストレスを感じ、パニックを起こすこともあります。
しかし、これは単なる「わがまま」ではなく、安心できるルールを守ろうとしているだけなのです。
② 感覚過敏:音や光、触覚などの刺激を過剰に感じる
自閉症の子どもは、五感が一般的な人より敏感だったり鈍感だったりすることがあります。特に「感覚過敏」を持っている場合、普通の人には気にならない刺激が、本人にとっては耐えられないほどつらいことも。
例えば、
- スーパーのBGMや蛍光灯の光がうるさくて痛いほどに感じる
- 服のタグがチクチクして耐えられない
- シャンプーの感触が気持ち悪くて泣いてしまう
こうした感覚過敏があると、突然泣き出したり、服を脱ぎ捨てたりすることがあります。
でも、これは「好き嫌い」ではなく、本当に体がつらくて耐えられない状態なのです。
③ 言語の発達遅れ:言葉で気持ちを伝えることが難しい
自閉症の子どもは、言葉で自分の気持ちを表現するのが苦手なことがあります。
「もっとこうしてほしい」「これがイヤ」と伝えられず、結果として「泣く」「怒る」「物を投げる」といった行動に出ることも。
たとえば、「喉が渇いた」と言えなくてコップを投げてしまうことがあります。これは「コップを投げたらお茶をくれるかもしれない」という考えではなく、単純に「どうしたらいいかわからなくてパニックになった」からなのです。
こんな行動、心当たりない?「わがまま」と誤解されやすい例
では、具体的にどんな行動が「わがまま」と誤解されやすいのでしょうか?
以下のようなケース、思い当たることはありませんか?
① 突然のパニック:予定変更や環境の変化に敏感
例えば、「今日は公園に行く予定だったのに、雨が降ったから中止」と伝えた瞬間、大泣きしたり怒ったりすることがあります。
親からすると「そんなことで?」「雨だから仕方ないでしょ?」と思うかもしれません。
でも、子どもにとっては、「予測していた未来と違うことが起こった!」という大事件なのです。
自閉症の子どもは「変化に対する耐性が低い」ため、突然の予定変更に対応するのが苦手です。
「お昼ご飯はカレーだよ」と言っていたのに、急に「やっぱりパスタにしよう!」と言われるだけで、パニックになることもあります。
② 好きなことをやめられない:好きな活動に集中していると時間を忘れる
自閉症の子どもは「没頭する力」が強いと言われています。
例えば、おもちゃで遊んでいる最中に「もうやめてご飯食べよう!」と言われると、大泣きしてしまうことがあります。
これは、「ご飯よりおもちゃが大事」ということではなく、頭の中を切り替えるのが難しいからです。
大人でも「映画を見ている途中で突然電源を切られたらモヤモヤする」のと同じ感覚ですね。
③ 感覚過敏による拒否反応:特定の食べ物や服を嫌がる
「うちの子、食べ物の好き嫌いが激しすぎる…」と感じることはありませんか?
しかし、それは「好き嫌い」ではなく、感覚過敏が原因かもしれません。
例えば、
- 「トマトの皮の食感が気持ち悪い」
- 「服のタグがチクチクして痛い」
- 「歯磨き粉のミントが刺激が強すぎて苦しい」
これらはすべて、本人にとっては耐えがたい感覚なのです。
④ 順番待ちが苦手:社会的ルールを理解するのが難しい
スーパーのレジや公園の遊具で、順番を待てずに割り込んでしまうことがあります。
「順番は守るもの」と大人は当たり前に思っていますが、自閉症の子どもにとっては、それを理解するのが難しいのです。
「なぜ待たなければいけないのか?」が納得できないと、不安やパニックにつながることもあります。
「わがまま」と本当の「困りごと」の違いとは?
一般的な「わがまま」は、「欲しいものを手に入れるための手段」として行動します。
でも、自閉症の子どもの場合、「こうしたい!」という意図ではなく、「そうするしかない」状況に陥っていることがほとんどです。
大切なのは、子どもの行動の「理由」を知ること。
「わがままだからやめさせよう」ではなく、「この行動の背景には何があるのかな?」と考えることで、子どもとの関わり方が変わってきます。
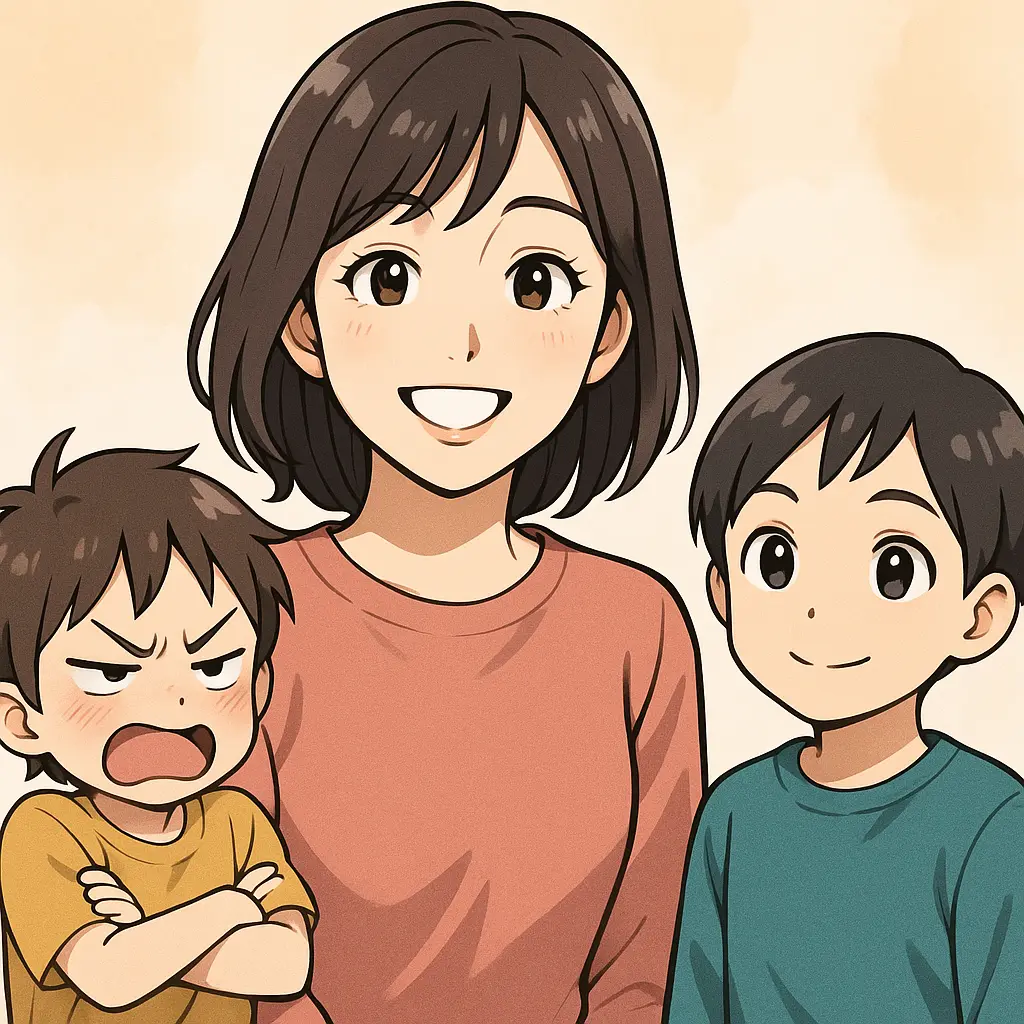
その行動、理由があります!子どもの気持ちを理解するコツ
「うちの子、すぐ怒るし、何でもイヤイヤするし、どうしたらいいの?」
そんなふうに悩んでいる親御さんは多いですよね。
でも、ちょっと視点を変えてみると、その「困った行動」にはちゃんと理由があるんです。
自閉症の子どもは、自分の気持ちや状況をうまく伝えられないことが多いため、行動で訴えかけることがあります。
「泣く」「怒る」「物を投げる」「大声を出す」——それは決して「わがまま」ではなく、本人なりの必死の表現方法なんです。
ここでは、そんな子どもたちの視点に立って、「どうしてそんな行動をするのか?」を考えてみましょう。
もしあなたが自閉症だったら?子どもの世界をのぞいてみよう
まず、想像してみてください。
もし、あなたが突然「自閉症の感覚」を持つことになったら、どんな世界に感じるでしょうか?
感覚過敏ってこんな感じ!
自閉症の子どもは、音・光・匂い・触覚などの刺激を普通の人より強く感じることがあります。
たとえば、
- スーパーに行くと、照明が眩しくて目が痛い!
- テレビの音量が普通の人にはちょうどよくても、自分には爆音に聞こえる!
- 服のタグがチクチクして、まるで針で刺されているみたい!
- シャンプーの匂いが強すぎて気持ち悪い!
こんな世界にいたら、どうでしょう?
「うるさい!」「痛い!」「気持ち悪い!」と感じても、周りの人にはわかってもらえない…。
そんな時、あなたならどうしますか?
言葉で「この音、もう少し小さくしてくれる?」と伝えられればいいですが、もしそれができなかったら?
おそらく、大声を出したり、耳をふさいだり、パニックになったりしてしまうでしょう。
つまり、自閉症の子どもたちは「わがまま」なのではなく、耐えられないほどのストレスを感じていることが多いのです。
言葉で伝えられないって、どんな気持ち?
「今日は何が食べたい?」と聞かれた時、
答えが頭の中にあるのに、うまく言葉にできないとしたらどうでしょう?
「お腹は空いてるけど、何が食べたいのかわからない…」
「いつも食べてるご飯がいいのに、言葉で説明できない…」
そんな状態で、もし親が「じゃあこれにしよう!」と勝手に決めてしまったら?
子どもは「違う!」「イヤだ!」という気持ちを伝えるために、泣いたり怒ったりするしかないんです。
でも、それを大人が「わがまま!」と決めつけてしまうと、子どもはますます混乱してしまいます。
「どうせわかってもらえない…」と感じると、コミュニケーションそのものをあきらめてしまうこともあります。
「感情調整」が苦手なのはなぜ?
自閉症の子どもは、気持ちをコントロールするのが苦手です。
「嬉しい」「悲しい」「怖い」「イライラする」などの感情が、一気に爆発してしまうことがよくあります。
「ちょっとしたことで怒るなぁ…」と思うかもしれませんが、本人にとっては「ちょっとしたこと」ではなく、突然心が大きく揺さぶられる出来事なんです。
例えばこんな場面
- お気に入りのおもちゃが見つからない! → パニック!
- いつもと違う道を通った → 大泣き!
- お友達におもちゃを取られた → 怒って叩いてしまう!
これらはすべて、「感情を整理する力がまだ育っていない」から起こること。
大人でも、突然パソコンが壊れたら「どうしよう!」とパニックになりますよね?
子どもにとっての「困ったこと」も、同じように大きなストレスなんです。
特に、自閉症の子どもは「気持ちを落ち着ける方法」を自分で見つけるのが苦手なので、親がその手助けをしてあげることが大切です。
「困った行動」の裏に隠された本当の理由とは?
では、実際に子どもが「困った行動」をしたとき、その裏にはどんな理由があるのでしょうか?
ここで、いくつかの例を見てみましょう。
① 「大声を出す!」
→ 音がうるさくて耐えられない!
たとえば、スーパーの中で突然大声を出したり、耳をふさいだりすることがあります。
これ、親からすると「静かにしなさい!」と言いたくなるところですが、子どもにとっては「うるさすぎて我慢できない!」というSOSのサインかもしれません。
→ 対策:イヤーマフやノイズキャンセリングイヤホンを活用すると、音の刺激を軽減できます。
② 「物を投げる!」
→ 言葉で伝えられず、イライラが爆発している!
何かを伝えたいのに言葉でうまく言えないとき、「どうしたらいいかわからない!」という気持ちが行動に出ることがあります。
物を投げるのは、本人にとっては「自分の気持ちを知ってほしい」というメッセージなんです。
→ 対策:「○○がしたかったんだね」「○○が嫌だったんだね」と気持ちを代弁してあげると、落ち着くことが多いです。
③ 「泣き叫ぶ!」
→ 予定変更に対応できず、パニックになっている!
自閉症の子どもは、予定変更に対応するのが苦手です。
「今日は公園に行く予定だったのに、雨が降ったから中止」なんて言われると、もう頭がパンクしてしまいます。
→ 対策:「天気が悪いから行けなくなったね。でも、かわりにおうちでボール遊びしよう!」など、代替案を提示すると気持ちが落ち着きやすくなります。
まとめ
自閉症の子どもの「困った行動」には、必ず理由があります。
それを理解し、子どもが感じている世界に寄り添うことで、対応の仕方が見えてきます。
「わがまま」ではなく、「どうしたらいいかわからないだけ」——
そう思って接するだけで、親子の関係がぐっと楽になりますよ!
次の章では、実際に親ができる「3つの正しい対処法」について詳しくお話しします!
親ができる3つの正しい対処法!これで悩みがグッと減る!
「うちの子、すぐにパニックになっちゃう…」「どうやって伝えたら動いてくれるの?」
こんな悩みを抱えている方は多いと思います。
でも大丈夫!
子どもの特性を理解し、ちょっとした工夫を加えるだけで、日常の困りごとがグッと減るんです。
ここでは、親ができる3つの対処法を紹介します。
どれもすぐに実践できるものばかりなので、ぜひ試してみてくださいね!
1. 事前の準備&環境調整でトラブルを防ぐ!
スケジュールを視覚化すると、子どもが安心する!
自閉症の子どもは、「次に何が起こるのか?」を知っておかないと不安を感じやすいです。
だからこそ、スケジュールを「見える形」にしておくことが大切!
例えば、
朝起きたら→朝ごはん→歯磨き→着替え→お出かけ
といった流れを絵カードやボードに貼っておくと、子どもは「次に何をするのか」がわかりやすくなります。
突然「じゃあ、そろそろ出かけるよ!」と言われると、パニックになってしまう子も、
「今はこのカードの順番だから、次はお出かけだな」と心の準備ができるんです。
ポイント
- 文字よりも「絵や写真」のほうが伝わりやすい!
- 1つ終わるごとにシールを貼るなど、「できた!」を実感できる工夫を加えると◎
感覚過敏に配慮する!「刺激を減らすだけ」でグッと落ち着く
自閉症の子どもは、音・光・匂い・触覚などの刺激を強く感じやすいです。
だから、ちょっとした環境の変化だけで、イライラしたりパニックになったりすることも…。
そんなときは、「刺激を減らす」工夫をするだけで、落ち着くことが多いんです。
例えば、
イヤーマフやノイズキャンセリングイヤホン → 騒がしい場所でも安心
サングラス → まぶしさを軽減
タグのない服・肌触りの良い服を選ぶ → チクチクする不快感を防ぐ
「なんで急に機嫌が悪くなったの?」と思ったら、
「周りの音がうるさくないか?」
「服がチクチクしていないか?」
など、子どもの感じている刺激をチェックしてみましょう!
落ち着ける「安心ゾーン」を作る!
家の中や出先で「ここなら落ち着ける」という場所を作っておくのも効果的!
例えば、
家の中の「安心スペース」 → ぬいぐるみやブランケットを置いた、小さなテントのような空間を作る
外出先でも安心できるグッズを持ち歩く → 好きなぬいぐるみ、好きな音楽の入ったイヤホン など
ちょっとイライラしてきたら、「ここでちょっと休もうか」と誘導すると、気持ちを切り替えやすくなります。
2. 「伝え方」を変えるだけで、子どもがスムーズに動く!
「これやって」じゃなくて、「こうしよう」と伝える!
自閉症の子どもは、曖昧な指示や突然の指示が苦手です。
「これやって!」と言われても、何をどうすればいいのかわからず、動けなくなることも…。
例えば、
「片付けなさい!」 → 何をどうすればいいのか、よくわからない
「ブロックをこの箱に入れよう!」 → 具体的な指示で理解しやすい
同じことを伝えるのでも、短く・具体的に伝えるだけで、子どもがスムーズに動けるようになります!
絵や写真を使うと、もっと伝わりやすい!
言葉だけでなく、視覚的なサポートを加えると、子どもにとっては「わかりやすさ」がグッとアップ!
例えば、
「手を洗おう」ではなく、手を洗っている写真を見せる
「着替えよう」ではなく、着替えの流れを絵カードで示す
「言葉で伝えても動かない…」と感じたら、見せて伝える工夫を試してみてください!
3. 感情コントロールのサポートでパニックを減らす!
まずは「共感」!「大変だったね」と言うだけで安心する
自閉症の子どもは、自分の感情をコントロールするのが苦手。
だからこそ、親が「気持ちをわかっているよ」と伝えるだけで、安心しやすくなります。
例えば、
「もう泣かないの!」 → 否定されると、ますます混乱してしまう
「嫌だったね、つらかったね」 → 共感すると、落ち着きやすくなる
「言葉がまだうまく話せない子」でも、親が気持ちを代弁してあげることで、「そうそう、そういうこと!」と感じて落ち着くことが多いんです。
落ち着ける方法を一緒に見つけよう!
「感情を落ち着ける方法」を親子で一緒に見つけておくと、パニックを防ぎやすくなります。
例えば、
深呼吸をする → ゆっくり「すーっ、はーっ」と息を吐く練習
音楽を聴く → お気に入りの曲を聴くと落ち着く子も多い
リズム遊びをする → 手をポンポンと叩く、体を揺らす など
子どもによって「落ち着く方法」は違うので、いろいろ試しながら「これなら落ち着く!」という方法を見つけることが大切です。
「できた!」を増やして、自己肯定感アップ!
子どもは、「できた!」という経験を積み重ねることで、少しずつ「自信」をつけていきます。
だから、どんな小さなことでも「できたら褒める!」を意識しましょう。
例えば、
「ちゃんとおもちゃ片付けられたね!すごい!」
「今日、静かに待てたね!がんばったね!」
こういう小さな成功体験を増やすことで、子ども自身も「頑張ったらできるんだ!」と感じられるようになります。
まとめ
「わがまま」ではなく、「どうしていいかわからないだけ」。
だからこそ、ちょっとした工夫を加えるだけで、子どもとの関わりがグッと楽になります!
事前の準備&環境調整で、トラブルを防ぐ!
伝え方を変えるだけで、子どもがスムーズに動く!
感情コントロールのサポートで、パニックを減らす!
次の章では、親が「無理をしすぎない」ための工夫についてお話しします!
「わがまま」じゃなくて「個性」!子どもと向き合うための心得
「どうしてうちの子は、こんなにわがままなの?」
「ほかの子はできるのに、なんでうちの子はできないの?」
こう思ってしまうこと、ありますよね。
でも、ちょっと視点を変えてみると、子どもの行動は「わがまま」ではなく「個性」として受け取ることができるかもしれません。
自閉症の子どもには、その子なりの「得意なこと」「苦手なこと」があります。
無理に「普通」に合わせようとするよりも、「この子が生きやすくなる方法」を見つけることが大切です。
ここでは、子どもと向き合うために大事な「3つの心得」についてお話しします。
「わがまま」と決めつけないことが大切
「なんでこんなことばっかりするの?」とイライラすること、ありますよね。
でも、ちょっと考えてみてください。
あなたが「普通」と思っていることは、本当に「みんなにとっての普通」でしょうか?
例えば、
- スーパーで大声を出してしまう → 「静かにしなさい!」と言いたくなるけど、本人は音がうるさくてつらいのかも?
- 順番を守れずに割り込んでしまう → 「ルールを守りなさい!」と叱るよりも、「次は〇〇ちゃんの番だね」と具体的に伝えたほうが伝わるかも?
「わがまま」ではなく、「その子なりの理由がある」と考えるだけで、対応の仕方が変わってきます。
親の「普通」を押し付けてしまうと…?
大人が「こうすべき」「こうあるべき」と決めつけてしまうと、子どもはどんどん「自分らしさ」を失ってしまいます。
例えば、「みんなと一緒に遊ばなきゃダメ!」と無理にお友達と遊ばせようとしても、本人が一人遊びを楽しんでいるなら、それでいいんです。
大事なのは、「どうしたら子どもが安心して過ごせるか?」を考えること。
「普通になってほしい」ではなく、「この子が生きやすくなる方法」を見つけることが大切!
他の子と比べるのはNG!
「〇〇ちゃんはできるのに、なんでうちの子はできないの?」
つい、そう思ってしまうこと、ありますよね。
でも、ちょっと待ってください。
子どもはそれぞれ成長のペースが違うんです。
比較することのデメリット
「〇〇ちゃんはもう字が書けるのに、どうしてうちの子はできないの?」
「みんなはお箸を使っているのに、うちの子だけスプーン…」
こんなふうに親が焦ってしまうと、子どももプレッシャーを感じてしまいます。
「できない自分はダメなんだ…」と思ってしまうと、ますます自信をなくしてしまうことも。
大事なのは「その子なりのペース」を大切にすること!
例えば、
- 字を書くのが苦手なら、まずはなぞり書きから始めてみる
- お箸が難しいなら、先にフォークの練習をしてみる
「できる・できない」ではなく、「少しずつ成長している!」と前向きにとらえることが大切なんです。
「他の子」ではなく、「昨日の自分」と比べてみる!
「昨日より少しでもできることが増えた!」という視点を持つと、子どもも親もストレスが減ります。
例えば、
「昨日はおもちゃを片付けられなかったけど、今日は一つだけでも片付けられた!」
「今までは順番を守れなかったけど、今日は少しだけ待てた!」
小さな「できた!」を積み重ねることで、子どもは自信を持つようになります。
無理に「普通」に合わせる必要はない!
「社会に適応させなきゃ!」
「周りと同じようにできるようにしなきゃ!」
そう思う気持ちもわかります。
でも、無理に「普通」に合わせることが、本当に子どもにとって幸せなのでしょうか?
「普通」って、そもそも何?
「普通」にこだわると、子どもはどんどん苦しくなってしまいます。
例えば、
- みんなと一緒に給食を食べられない → 無理に食べさせようとすると、ますますストレスに
- 大勢の中にいるのが苦手 → それなのに、無理にお友達と遊ばせようとするのは逆効果
自閉症の子どもには、「社会に適応する力を伸ばす」ことも大切ですが、「その子が楽に生きられる方法を見つける」ことのほうがもっと大事!
子どもの「強み」を伸ばすことが大切!
「普通にできるようになる」ことよりも、「この子の良いところを伸ばしてあげる」ことを意識してみてください。
例えば、
絵を描くのが好きなら、たくさんお絵描きの時間を作ってあげる!
音楽に興味があるなら、リトミックを取り入れてみる!
本が好きなら、一緒に図書館に行ってみる!
「得意なこと」を活かしてあげると、子どもはどんどん自信を持つようになります!
「普通」を目指さなくても大丈夫!
「わがまま」ではなく、「個性」だと考えてみる。
「他の子と比べる」のではなく、「昨日の自分と比べてみる」。
「普通に合わせる」のではなく、「その子が生きやすくなる方法を見つける」。
この3つの考え方を持つだけで、親の心もグッと楽になります。
子どもは、その子なりのペースで、ちゃんと成長しています。
だからこそ、焦らず、その子に合った方法を見つけてあげましょう!

さいごに~小さな成長を大切に。お子さんと一緒に歩む毎日を楽しんでいこう
子どもの行動に戸惑ったり、思い通りにいかなくて悩んだりすること、ありますよね。
「どうしてうちの子はこんなにわがままなの?」と感じることがあったかもしれません。
でも、今日の記事を通して、少し違った視点でお子さんの行動を見られるようになったのではないでしょうか?
今日の記事では、次の3つの大切なポイントをお伝えしました。
子どもの行動には必ず理由があり、決して「わがまま」ではないこと。
親が少し工夫するだけで、伝わりやすさが変わり、親子のストレスが減ること。
無理に「普通」に合わせる必要はなく、その子の個性を大切にすること。
お子さんは、確実に成長しています。
昨日できなかったことが、今日できるようになるかもしれない。
そんなふうに、小さな成長を一緒に楽しんでいきましょう。
焦らなくても大丈夫。愛情はちゃんと伝わっています。
これからも、お子さんのペースを大切にしながら、一緒に成長を楽しんでいきましょう。
以上【わがままと誤解しないで!自閉症の子どものわがままに見える行動と親ができる3つの正しい対処法】でした











コメント