療育って聞いたことある?初めてでも安心の入門ガイド!
「療育」って言葉、なんとなく聞いたことがあるような、ないような…。
でも実際のところ、「療育って何?」と聞かれると、スラスラ説明できる人は少ないかもしれませんね。
でも大丈夫!
この記事では、初めて療育を知るママ・パパに向けて、
分かりやすく、そして詳しく「療育」の基本を解説していきます。
療育とは?
そもそも「療育」ってどんな意味なんでしょうか?
簡単に言うと、発達に困難を抱える子どもたちの成長をサポートするための支援のことを指します。
「療育」という言葉には、「療」と「育」という漢字が含まれていますよね。
- 療(治療):心や身体の発達をサポートする
- 育(教育):生活スキルや社会性を身につける
この2つが組み合わさっているので、療育は医療的な支援と教育的な支援の両方を取り入れた支援方法なんです。
つまり、ただ治療するだけでもなく、ただ教育するだけでもなく、子どもの発達を多角的に支えていくアプローチなんですね。
どんな子どもが療育の対象になるの?
療育の対象となるのは、主に発達障がいを持つ子どもです。
具体的には、以下のような子どもたちが対象になります。
- 自閉スペクトラム症(ASD):
- コミュニケーションが苦手だったり、こだわりが強かったりする子ども
- 例えば、お友だちと遊ぶ時にうまく順番を待てなかったり、特定の物への執着が強かったりすることがあります。
- 注意欠陥・多動性障がい(ADHD):
- 集中力が続かない、じっとしていられない、衝動的に行動してしまう子ども
- 例えば、授業中に突然立ち上がってしまったり、順番を待たずに割り込んでしまったりすることがあります。
- 知的障がい:
- 年齢相応の理解力や判断力が未発達な子ども
- 例えば、年齢相応の言葉の理解が難しかったり、指示を正しく理解できなかったりすることがあります。
- 感覚過敏・鈍麻:
- 音や光、触覚などに過敏だったり、逆に鈍感だったりする子ども
- 例えば、掃除機の音が耐えられないほど嫌だったり、逆に痛みに鈍感だったりするケースがあります。
療育の目的とは?
療育の目的は、子どもの発達段階に合わせた支援を行い、自立した生活を目指すことです。
具体的には以下のような目標があります。
- 社会性を育てる:
- 友だちと遊ぶルールを学んだり、自分の気持ちを伝える練習をしたりします。
- 生活スキルを習得する:
- 着替えや食事、トイレトレーニングなど、日常生活で必要なスキルを学びます。
- 自己肯定感を高める:
- できたことを認めてもらうことで、「自分もできるんだ!」という成功体験を積み重ねていきます。
- 感情のコントロールを学ぶ:
- 癇癪(かんしゃく)を起こしやすい子どもには、感情をコントロールする方法を教えます。
- 例えば、「深呼吸をしてみよう」「好きな音楽を聴いてリラックスしよう」といった具体的な方法を取り入れます。
療育って何歳から始めるべき?
「療育って、いつから始めればいいの?」という疑問もよく聞きますが、
基本的には、気になることがあれば早めの相談がベストです。
療育は、早ければ早いほど効果的と言われています。
3歳未満の早期療育もあれば、学齢期の療育支援もあります。
例えば、2歳頃に言葉の遅れが見られた場合、言語療法を受けることでコミュニケーション能力を高めるサポートができます。
また、小学校に入る頃にはソーシャルスキルトレーニング(SST)を取り入れて、
集団生活でのルールを学ぶ機会を作るのも効果的です。
\ここまでのまとめ/
- 療育とは、発達障がいを持つ子どもたちの成長をサポートするための支援方法。
- 医療的支援+教育的支援の組み合わせがポイント!
- 対象となるのは、自閉スペクトラム症(ASD)、ADHD、知的障がい、感覚過敏・鈍麻などの子どもたち。
- 療育の目的は、社会性の向上、生活スキルの習得、自己肯定感の育成、感情コントロールのサポート。
- 療育の開始時期は早ければ早いほど効果的。気になることがあれば、まずは相談してみよう!

【第2章:療育を受けると何が変わる?効果とメリットを徹底解説】
療育で目指すのはどんな成長?3つのポイントを解説!
「療育を受けると、子どもにどんな変化が現れるの?」
これ、親御さんたちが一番気になるポイントですよね。
療育の目的は、単に子どもの行動を矯正することではありません。
むしろ、子ども自身がより生きやすくなるためのスキルを身につけることが大きな目標なんです。
具体的には、以下の3つの成長ポイントが期待できます。
1. コミュニケーション力の向上
「言葉のキャッチボールができるようになる!」
療育では、言葉の発達が遅れている子どもに対して、言語療法(ST)やソーシャルスキルトレーニング(SST)を取り入れます。
例えば、以下のような練習が行われます:
- あいさつの練習:「こんにちは」「ありがとう」「さようなら」など、日常で使う言葉を繰り返し練習する。
- 質問と答えのやりとり:「今日は何を食べたの?」→「カレーライス!」のように、質問に対して適切な答え方を学ぶ。
- 絵カードを使った練習:絵カードを見ながら、「これは何?」と問いかけ、言葉を引き出す練習。
これらの活動を通じて、自分の気持ちや考えを言葉で伝えられる力が育ちます。
結果として、「〇〇してほしい」「これは嫌だ」など、自分の要求を適切に伝えられるようになり、親子のコミュニケーションもスムーズになります。
2. 自立スキルの習得
「自分でできることが増えると、自己肯定感もUP!」
療育では、生活スキルの習得も重要なポイントです。
例えば、「ボタンをかける」「靴を履く」「トイレに行く」といった日常生活の基本動作を一つずつ練習していきます。
具体的な例として:
- 着替えの練習:服の前後を区別する、ボタンをかける練習を繰り返す。
- トイレトレーニング:「行きたくなったら教えてね」と促しつつ、自分で行けるようにサポート。
- 片付けの習慣化:「おもちゃをこの箱に入れようね」と、片付け方を教える。
こうした活動を繰り返すことで、できることが一つずつ増えていく感覚が子どもにも伝わります。
「できた!」という成功体験を積み重ねることで、自己肯定感が育ち、自信につながるんです。
3. 社会性の向上
「お友だちと遊べるようになると、世界が広がる!」
療育では、集団活動を通じて社会性の発達もサポートします。
例えば、以下のような活動が行われます:
- 順番待ちの練習:「次は〇〇くんの番だよ」と声かけし、待つことの大切さを学ぶ。
- 共同作業の経験:「一緒にブロックを積もう!」と誘い、他の子どもと協力して作業する。
- ルールのある遊び:「鬼ごっこ」「カードゲーム」など、ルールを守る遊びを通して、順番や待つことを覚える。
このような体験を通して、他の子どもとの関わり方や集団の中での振る舞い方を学んでいきます。
結果として、保育園や幼稚園、小学校などの集団生活にもスムーズに適応できるようになるのです。
療育で変わった!親子が実感した5つの成長ポイント
療育を受けた親子の実際の声を通して、どんな変化が起きたのかを見ていきましょう。
1. 自分の気持ちを伝えられるようになった!
「今まではただ泣いていただけだったのに、『〇〇したい』『△△がイヤだ』と言えるようになった!」
2. パニックが減ってきた!
「療育で感情のコントロール法を教わってから、癇癪の頻度が減った。」
3. 一緒に遊べるようになった!
「ルールのある遊びを繰り返し練習したら、お友だちとも楽しそうに遊べるようになった。」
4. 自分でお片付けができるようになった!
「お片付けの順番を教えてもらったら、少しずつ自分で片付けを始めた!」
5. 親の気持ちも楽になった!
「子どもの成長を感じられるようになり、『療育ってすごい!』と実感できた。」
おうちでできる!日常生活で取り入れたい療育のヒント
療育は専門機関だけでなく、家でも取り入れられるものなんです。
親子で楽しみながらできる療育アイデアをいくつかご紹介します!
- コミュニケーション力UP!絵カード遊び
- 絵カードを見せて「これは何?」と質問。
- 「これはリンゴ」「これはバナナ」と言葉を引き出す。
- 感覚統合遊び!ふわふわタオルリレー
- 柔らかいタオルにおもちゃを乗せて「落とさないように運んでね!」と挑戦。
- 手先の感覚とバランス感覚を鍛えられる。
- 順番待ちの練習!トランプゲーム
- トランプを使って「次は誰の番?」と順番を意識させる。
- 楽しみながら社会性も学べる。
\ここまでのまとめ/
- 療育の目的は、コミュニケーション力、自立スキル、社会性の向上!
- 療育で得られる具体的な成長例:
- 言葉で気持ちを伝えられるようになった
- 癇癪が減って感情コントロールができるようになった
- お友だちと遊べるようになった
- 自分でお片付けができるようになった
- 親の負担感も軽減された
- おうち療育でもできることはたくさん!
- 絵カード遊び、タオルリレー、順番待ちの練習など、楽しく取り入れてみよう!
【第3章:療育の種類はこんなにある!お子さんに合った方法を見つけよう】
医療的アプローチ編:作業療法・言語療法の魅力とは?
「療育ってどんなことをするの?」と疑問に思うママ・パパも多いはず。
療育にはさまざまな方法がありますが、その中でも代表的なのが医療的アプローチです。
医療的アプローチには、以下の2つが含まれます:
1. 作業療法(OT:Occupational Therapy)
作業療法とは、手先の器用さや身体のバランスを整えるための訓練です。
例えば、こんなサポートが行われます:
- ボタンの練習:
- ボタンをつまむ、押し込む動作を繰り返し練習する。
- 自分で着替えができるようになると、自信もUP!
- スプーンやフォークの使い方練習:
- スプーンの持ち方やご飯をすくう動作を反復練習。
- 食事の時間が楽しみになることも。
- バランスボールで遊びながら体幹強化:
- バランスボールに座って、前後左右に揺れてみる。
- 楽しみながらバランス感覚を養える。
作業療法は、ただ運動機能を高めるだけでなく、日常生活の中で必要なスキルを遊び感覚で学べるのが魅力です。
子どもにとっては「訓練」というよりも「遊び」の延長のような感覚なので、抵抗感も少なく取り組めます。
2. 言語療法(ST:Speech Therapy)
言語療法は、言葉の発達が遅れている子どもや、コミュニケーションが苦手な子どもに対して行う療育です。
- 発音の練習:
- 舌や唇を動かす練習を繰り返すことで、正しい発音ができるようになる。
- 会話のキャッチボール練習:
- 「今日は何をしたの?」→「公園で遊んだよ!」
- 質問に対して適切な返事ができるようにトレーニング。
- 絵カードを使った言葉遊び:
- 絵カードを見せて、「これは何?」と問いかけることで、言葉の引き出しを増やす。
言語療法の目的は、単に言葉を覚えることではなく、自分の気持ちや考えを伝えられる力を育てることです。
「おなかすいた」「やめてほしい」など、自分の気持ちを適切に伝えられるようになることで、癇癪(かんしゃく)が減ることも多いんです。
教育的アプローチ編:ソーシャルスキルトレーニングのすすめ
ソーシャルスキルトレーニング(SST)は、子どもの社会性を育むための療育です。
具体的には、「順番を守る」「挨拶をする」「相手の気持ちを考える」など、社会生活で必要なスキルを練習します。
例えば:
- 順番待ちの練習:
- おもちゃを使って「次は〇〇くんの番だよ」と声かけしながら順番を意識させる。
- ロールプレイで挨拶の練習:
- 「こんにちは!」「ありがとう!」と挨拶を練習。
- お母さん役・お友だち役など、役割を交代しながら練習する。
- 感情の表現練習:
- 「嬉しい時はどんな顔をする?」「悲しい時は?」と、表情カードを使って感情表現を学ぶ。
SSTは、単なる遊びではなく、社会性を養うための訓練として非常に効果的です。
「〇〇くんの番だよ」と伝えても、「今は私の番!」と泣いてしまう子どもには、
このような順番待ちの練習を繰り返すことで、少しずつ理解が深まっていきます。
感覚統合療法とは?遊び感覚で楽しく支援!
感覚統合療法は、感覚の過敏さや鈍感さを整える療育です。
例えば、音や光、触られる感覚が苦手な子どもには、この療法が効果的です。
具体的な遊び例:
- ふわふわタオルリレー:
- 柔らかいタオルでおもちゃを運ぶ。
- 手先の感覚とバランス感覚を育てる。
- ビーンズプール遊び:
- プラスチックのビーズや豆の中に手を入れて「〇〇を探して!」と感触遊び。
- 触覚の刺激に慣れる訓練。
- ブランコでリラックス:
- ゆらゆら揺れるブランコで前後に揺れながら体の動きを感じる。
感覚統合療法は、楽しく遊びながら感覚を整えることができるのが魅力です!
自宅療育と通所療育、どっちが合ってる?メリット・デメリットを比較!
| 療育の種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 通所療育 | 専門家のサポートを受けられる | 送り迎えが必要 |
| 自宅療育 | 日常生活の中で実践しやすい | 専門的な支援が不足しがち |
地域の療育支援センターって何?賢く活用する方法
療育支援センターでは、発達相談や療育の計画作成をサポートしてくれます。
「どの療育がうちの子に合っているの?」と迷ったら、まずは相談してみましょう!
\ここまでのまとめ/
- 療育には様々なアプローチがある!
- 医療的アプローチ:作業療法(OT)と言語療法(ST)で身体とコミュニケーションをサポート
- 教育的アプローチ:ソーシャルスキルトレーニング(SST)で社会性を育てる
- 感覚統合療法:遊びながら感覚を整える
- 自宅療育と通所療育の選び方
- 通所療育:専門家のサポートが得られるが、送迎が大変
- 自宅療育:生活の中で自然に取り入れられるが、専門支援は不足しがち
- 地域の療育支援センターを活用しよう!
- 相談窓口としての役割
- どの療育が適しているかのアドバイスがもらえる

【第4章:療育を始めるための手順とポイント】
まずはここから!療育相談の流れを徹底解説
「療育って何から始めればいいの?」
初めて療育を考えるとき、一番困るのがここですよね。
でも、大丈夫!療育のスタートは相談から始まります。
療育相談は、いくつかの窓口で受けられます。具体的には:
1. 発達相談センター
発達相談センターは、地域ごとに設置されている相談機関です。
ここでは、専門の相談員が子どもの発達状況をチェックしてくれるだけでなく、
「どんな療育が合っているのか」をアドバイスしてくれます。
利用の流れ:
- 予約を取る(電話またはWeb)
- 初回面談で子どもの発達状況をヒアリング
- 必要に応じて療育計画の作成
- 療育施設やサービスの紹介
2. 小児科・発達外来
小児科や発達外来も療育相談の重要な窓口です。
特に「うちの子、少し発達が遅れているかも?」と感じた時は、まずはかかりつけの小児科で相談するのが安心です。
相談のポイント:
- 子どもの行動や言葉の遅れを具体的に伝える(例:「言葉がまだ出ない」「友達と遊ばない」など)
- 医師から療育の必要性について説明を受ける
- 療育施設への紹介状を書いてもらう場合もあり
3. 児童相談所
「どうしてもどこに相談していいかわからない…」という場合は、児童相談所も活用できます。
ここでは、子どもの発達相談だけでなく、福祉サービスの利用方法も詳しく教えてもらえます。
療育手帳の取得方法を完全ガイド!
「療育手帳ってなに?」と疑問に思う人も多いですよね。
療育手帳は、発達障がいのある子どもが福祉サービスを受けやすくするための手帳です。
取得の流れ:
- 申請窓口に連絡する
- 市区町村の福祉課や児童相談所で手続き可能。
- 発達検査を受ける
- 知能検査や行動観察を行い、発達の程度を確認。
- WISCや田中ビネーなどの検査が一般的。
- 診断結果の確認
- 検査結果に基づき、手帳の取得可否が決定される。
- 療育手帳にはA判定(重度)とB判定(軽度)の2種類がある。
- 手帳の交付
- 療育手帳が交付されると、福祉サービスや療育施設の利用がスムーズに。
療育手帳のメリット
- 療育施設の利用がしやすくなる
- 発達相談の際に適切なサポートが受けられる
- 公共交通機関の割引や手当の申請も可能
ただし、手帳の取得には時間がかかることも多いので、早めの準備が大切です!
親が今からできること!療育スタート前に心がけたいこと
療育を始める前に、親が準備しておくべきこともあります。
療育は、親のサポートがあってこそ効果が高まるもの。
以下の3つのポイントを押さえておきましょう!
1. 子どもの特性を理解する
- 子どもの得意なこと・苦手なことをリストアップしておく。
- 例えば、「絵を描くのが好き」「音に敏感で泣きやすい」など。
2. 日常生活の様子を記録する
- 発達相談や療育計画の際、子どもの普段の様子を伝えることが大切。
- 「朝はなかなか起きられない」
- 「順番待ちが苦手で癇癪を起こすことが多い」
3. 親自身のメンタルケアも忘れずに!
- 療育が始まると、親のサポートが必要な場面も増えます。
- 自分のリフレッシュ方法を見つけて、ストレスケアも大切にしましょう。
\ここまでのまとめ/
- 療育相談の窓口は3つ!
- 発達相談センター:発達の状況をチェックし、療育計画を立てる
- 小児科・発達外来:医師の診断をもらい、療育の必要性を確認
- 児童相談所:福祉サービスの相談や療育手帳取得のアドバイス
- 療育手帳の取得手順:
- 申請 → 発達検査 → 診断結果 → 手帳交付
- 療育施設を選ぶポイント3つ:
- プログラム内容・専門性・通いやすさ
- 療育スタート前に親ができる準備:
- 子どもの特性を理解する
- 日常生活の記録をつける
- 自分のストレスケアも忘れずに
【第5章:療育を続けてわかったメリット・デメリット】
療育の効果を実感!親子が感じた成長エピソード3選
療育を始めたばかりの頃は、「本当に効果があるの?」と半信半疑な親御さんも多いですよね。
でも、療育を続けることで、子どもにも親にも小さな変化が訪れることがあるんです!
ここでは、実際の親子が感じた療育の成長エピソードを3つご紹介します。
エピソード1:癇癪(かんしゃく)が減った!
5歳のA君は、感覚過敏が強く、音や光に敏感で癇癪を起こしがちでした。
療育で取り入れたのは感覚統合療法。
- ビーズプール遊び:
- ビーズの中に手を入れ、触覚を刺激しながらリラックスする時間を作った。
- 聴覚過敏対策:
- ノイズキャンセリングヘッドホンをつけて好きな音楽を聴く時間を設ける。
これを続けた結果、以前は掃除機の音で泣き叫んでいたA君が、
「今日は大丈夫だった!」と笑顔で言えるようになったそうです。
エピソード2:友だちと一緒に遊べるようになった!
6歳のBちゃんは、コミュニケーションが苦手で、
「一緒に遊ぼう」と言われても無視してしまうことが多々ありました。
そこで療育で取り入れたのがソーシャルスキルトレーニング(SST)。
- 順番待ちの練習:
- 「次はBちゃんの番だよ」と声をかけ、順番を守る練習を繰り返し行った。
- おもちゃの貸し借り練習:
- 「貸して」「どうぞ」といった言葉のやり取りを、ロールプレイで練習。
すると、ある日、お友だちに「一緒にお砂場で遊ぼう!」と自分から声をかける場面が!
「今まで一人で遊ぶことが多かったのに…」とママもびっくり!
エピソード3:自分の気持ちを言葉で伝えられるようになった!
4歳のC君は、言葉の発達が遅く、癇癪を起こすたびに泣いてばかりでした。
そこで療育で取り入れたのが言語療法(ST)。
- 絵カードを使った練習:
- 「おなかがすいた」「眠い」「遊びたい」などの感情カードを使って、自分の気持ちを言葉で表現する練習を続けた。
- 簡単な質問と返答の練習:
- 「今日は何を食べたの?」→「カレー!」といったシンプルなやり取りからスタート。
その結果、「ママ、ジュース飲みたい」と言葉で要求を伝えられるようになり、
癇癪の頻度が減少!ママも「こんな日が来るなんて!」と感動したそうです。
療育の壁にぶつかったら…解決策を教えます!
療育を続けていると、必ず壁にぶつかる時期があります。
例えば、「子どもが療育を拒否する」「施設への通所が難しい」など。
ここでは、よくある壁とその対処法を見ていきましょう!
壁1:子どもが療育を嫌がる場合
療育施設に行くのを嫌がったり、療育中に癇癪を起こしてしまうことも。
そんな時は、以下の対策を試してみましょう!
- 無理に通わせない:
- 休む日があってもOK!無理強いは逆効果。
- ごほうび作戦を活用:
- 療育後に好きなおやつを食べる、好きな動画を見る時間を設けるなど。
- 療育の内容を事前に伝える:
- 「今日は〇〇ちゃんと一緒にボール遊びをするよ!」と、具体的に伝えて心の準備をさせる。
壁2:通所が難しい場合
共働きで送迎が難しい、近くに療育施設がない場合もありますよね。
そんな時は:
- オンライン療育の活用:
- 自宅でできる療育プログラムをオンラインで受講できる施設も増えてきています。
- 家庭療育を取り入れる:
- 療育の先生に自宅でできる課題を教えてもらう。
療育に期待しすぎない!親が抱えがちな悩みとその対処法
療育を始めると、「絶対に効果が出るはず!」と期待してしまうのも親心。
でも、療育は即効性があるものではなく、時間をかけて取り組むもの。
- 期待しすぎると疲れてしまう:
- 「今日もまたできなかった…」と落ち込むことも。
- でも、焦らず小さな成功に目を向けることが大切です!
小さな成長を見逃さない!療育を続けるモチベーション術
療育の効果は、一歩一歩の積み重ねで現れます。
そこで大事なのが「小さな成長を見逃さない」こと!
- 成長記録をつける:
- 今日できたことを1つだけ書き出してみる。
- 「お片付けができた」「挨拶ができた」など、些細なことでもOK!
- 親子でごほうびタイムを作る:
- 一緒に好きな絵本を読む、おやつを食べるなど、療育の後に楽しい時間を作る。
\ここまでのまとめ/
- 療育を続けると感じる成長例:
- 癇癪が減ってきた
- お友だちと遊べるようになった
- 言葉で気持ちを伝えられるようになった
- 療育の壁と解決策:
- 子どもが嫌がる→無理をせず、ごほうび作戦を活用
- 通所が難しい→オンライン療育や家庭療育を取り入れる
- 期待しすぎないことが大切!
- 小さな成長を見つけて、親子で喜ぶ時間を作る
- 療育のモチベーションを保つコツ:
- 成長記録をつける
- 親子でのごほうびタイムを設ける

【第6章:家庭でできる療育サポート術】
今日からできる!家庭で取り入れる療育アイデア5選
療育って、専門機関だけで行うものだと思っていませんか?
実は、日常生活の中にも療育のヒントはたくさん隠れているんです。
ここでは、今日からすぐに取り入れられる療育遊びのアイデア5選をご紹介します!
1. ビーズプール遊び:感覚統合療法の第一歩!
用意するもの:
- プラスチックビーズや乾燥豆
- 小さめの箱やタライ
遊び方:
- ビーズの中におもちゃやボールを隠して「〇〇を探してみよう!」と声かけをする。
- 指先を使って探し出すことで、触覚の刺激や手先の器用さを養うことができます。
ポイント:
- 最初は手を入れるのを嫌がる子どももいるので、無理せず少しずつ慣らしていきましょう!
- 「冷たいね」「ツルツルしてるね」と触った感覚を言葉で表現してもらうと、言葉の練習にもなります。
2. おもちゃの順番待ちゲーム:社会性を育てる遊び!
用意するもの:
- おもちゃ(電車やミニカーなど)
遊び方:
- おもちゃを一つずつ順番に渡していきます。
- 「次は〇〇くんの番だよ!」と順番を意識させるように声かけをします。
ポイント:
- 順番待ちが苦手な子には、タイマーを使って「〇〇分待ったら次の番だよ!」と時間を可視化するとスムーズです。
- 「ありがとう」「どういたしまして」のやり取りも取り入れて、コミュニケーション力も同時に育てましょう!
3. 絵カードでお話ししよう:言葉の練習遊び
用意するもの:
- 絵カード(動物、食べ物、感情など)
遊び方:
- 「これは何?」と質問して、カードの名前を答えてもらう。
- 「どうして〇〇してるの?」と質問を投げかけて会話のキャッチボールを練習する。
ポイント:
- 言葉が出にくい子には、選択肢を与えて答えやすくすると成功体験につながります。
- 例:「リンゴかな?バナナかな?」
4. ふわふわタオルリレー:バランス感覚&協調性アップ!
用意するもの:
- タオル1枚
- 軽いおもちゃ
遊び方:
- タオルの上におもちゃを乗せて、親子で協力して運びます。
- 「落とさないようにゆっくりね!」と声をかけて進めます。
ポイント:
- おもちゃの大きさや重さを変えて難易度を調整すると、飽きずに取り組めます。
- おもちゃが落ちた時も「またチャレンジしようね!」と前向きな声かけを心がけましょう。
5. お片付けチャレンジ:自己肯定感を高める習慣作り!
用意するもの:
- おもちゃ箱
遊び方:
- 「1つずつ数えながらお片付けしてみよう!」と声かけをして、おもちゃを箱に戻してもらいます。
- 全て片付けられたら「全部できたね!すごい!」と成功体験をしっかり褒める。
ポイント:
- お片付けの時間を毎日のルーティン化すると、習慣として身に付きやすくなります。
親も学ぼう!療育を支えるためのスキルアップ法
療育を効果的に進めるには、親も知識を身につけてサポートできるようになることが重要です。
ここでは、親が学べるスキルアップ方法をご紹介します!
1. オンライン講座の活用
- ユーキャンや自治体の無料講座などで発達障がい支援に関する講座が受けられます。
- 自宅で学べるので、忙しいママ・パパにもおすすめ!
2. 支援者向けの勉強会に参加
- 地域の発達相談センターや児童館で開催される勉強会は、最新の療育情報が得られる場です。
- 他の親との情報交換もできるので、孤立感も軽減されます。
療育仲間を見つけよう!ママ友・パパ友と繋がる方法
療育を続ける中で、「同じ悩みを抱える親と話したい…」と思うこともありますよね。
そんな時は、コミュニティを活用して仲間を見つけましょう!
オンラインコミュニティ
- FacebookグループやLINEグループで「療育支援」「発達障がいサポート」などのコミュニティを探してみる。
リアルな親の会
- 地域の児童館や療育施設で開催される親の会に参加。
- 子どもの療育中に親同士で交流できる場も多いです。
親の心のケアも忘れずに!ストレス軽減のコツ
療育に取り組む中で、親自身も疲れを感じることが増えてくることも。
そんな時は、自分のメンタルケアも忘れずに行いましょう!
1. 自分の時間を確保する
- 療育が終わったら、15分だけでも自分のリラックスタイムを作る。
- コーヒーを飲んだり、好きな本を読むなど、小さな楽しみを大切に。
2. 支援者に話を聞いてもらう
- 療育スタッフやカウンセラーに気持ちを吐き出す場を設ける。
- 話すことで、心が軽くなることもあります。
\ここまでのまとめ/
- 家庭で取り入れられる療育アイデア5選:
- ビーズプール遊び
- 順番待ちゲーム
- 絵カード遊び
- タオルリレー
- お片付けチャレンジ
- 親も学べるスキルアップ法:
- オンライン講座の活用
- 地域の勉強会に参加
- 療育仲間を見つける方法:
- オンラインコミュニティ
- 親の会への参加
- 親の心のケアも忘れずに!
- 自分の時間を確保する
- 支援者に相談する
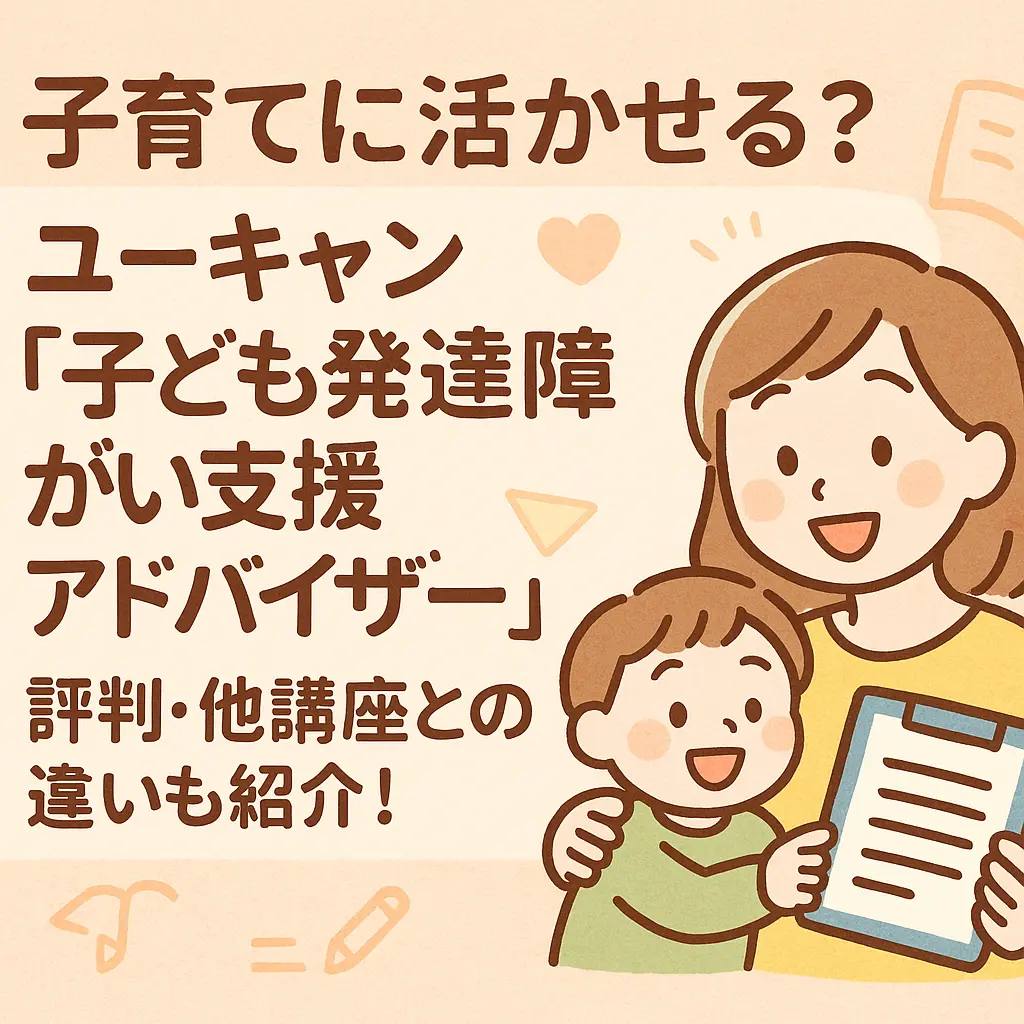
まとめ~療育って難しい?そんなことない!親子で楽しみながら成長しよう!
「療育」と聞くと、なんだか特別で難しそうなイメージがありますよね。でも、ここまで読んできたように、療育って決して特別なことではありません。むしろ、日常生活の中で楽しみながら取り入れられる工夫がたくさんあるんです!
1. 療育の基本は「無理せず、楽しく」
療育は、子どもの発達をサポートするための支援方法ですが、
それは決して「できないことを無理にやらせる」という意味ではありません。
むしろ、子どものペースに合わせて少しずつ進めることが大切なんです。
例えば:
- 順番待ちの練習も、無理にやらせるのではなく、お気に入りのおもちゃを使って楽しく取り組む。
- 感覚統合遊びも、「今日はビーズプールで遊ぼうね!」とワクワク感を演出して始める。
これなら、子ども自身も「やらされている」という感覚ではなく、「遊んでいるうちにできるようになった!」という成功体験につながります。
2. 小さな成長を見逃さないことが大事!
療育を続けていると、親としては「まだこれができていない」「あれもできるようにしたい」と焦りが出てしまうこともあります。
でも、ちょっと待ってください。
療育は、一気に成長を求めるものではありません。
むしろ、一歩一歩の成長を見逃さずに喜ぶことが大切です。
例えば:
- 今日は絵カード遊びで「リンゴ」と言えた!
- お片付けチャレンジで、1つでも自分で片付けられた!
- 順番待ちゲームで、「次は〇〇くんの番だよ」と声かけを受け入れられた!
こんな小さな成功体験こそが、子どもの自信と親の安心感につながるんです。
そして、そういう成功体験を積み重ねることが、大きな成長につながるステップになります。
3. 親の心のケアも忘れずに!
療育を頑張るのは子どもだけではありません。
親だって、日々のサポートや通所の送迎、計画の見直しで疲れてしまうこともありますよね。
そんな時は、「少し立ち止まること」も必要です。
- 子どもが療育を受けている間、自分の時間を確保する
- 親の会やコミュニティで同じ立場の人と話してみる
- 相談員や支援者に話を聞いてもらう
親自身が元気で余裕がある状態でないと、子どもに優しく接することも難しくなることがあります。
だからこそ、親の心のケアも療育の一環として考えていきましょう。
4. 療育は長期戦。でも、焦らず、楽しく進めていこう!
療育は、すぐに結果が見えるものではありません。
だけど、続けているうちに「あれ?できるようになった!」という瞬間が必ず訪れます。
例えば:
- ずっと順番待ちが苦手だった子が、ある日「次は〇〇くんの番だよ」と言われて待てるようになったり。
- 癇癪が減って、「自分の気持ちを言葉で伝えられるようになった」と親子で喜べる瞬間があったり。
その小さな一歩一歩が積み重なって、やがて大きな成長につながるんです。
だからこそ、療育を続ける中で、「今日はこれができた!」「昨日より少しだけ落ち着いて遊べた!」と、目の前の成長をしっかり見つけて、親子で喜んでいきましょう!
これで、「療育って難しい?そんなことない!」ということが伝わったでしょうか?
親子で楽しみながら、少しずつ成長を積み重ねていくことで、療育の効果も自然と現れてきます。
さあ、今日も一緒に「できた!」をたくさん見つけていきましょう!

以上「療育ってなに?初心者ママ・パパでもスッキリわかる完全ガイド!」でした。最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!

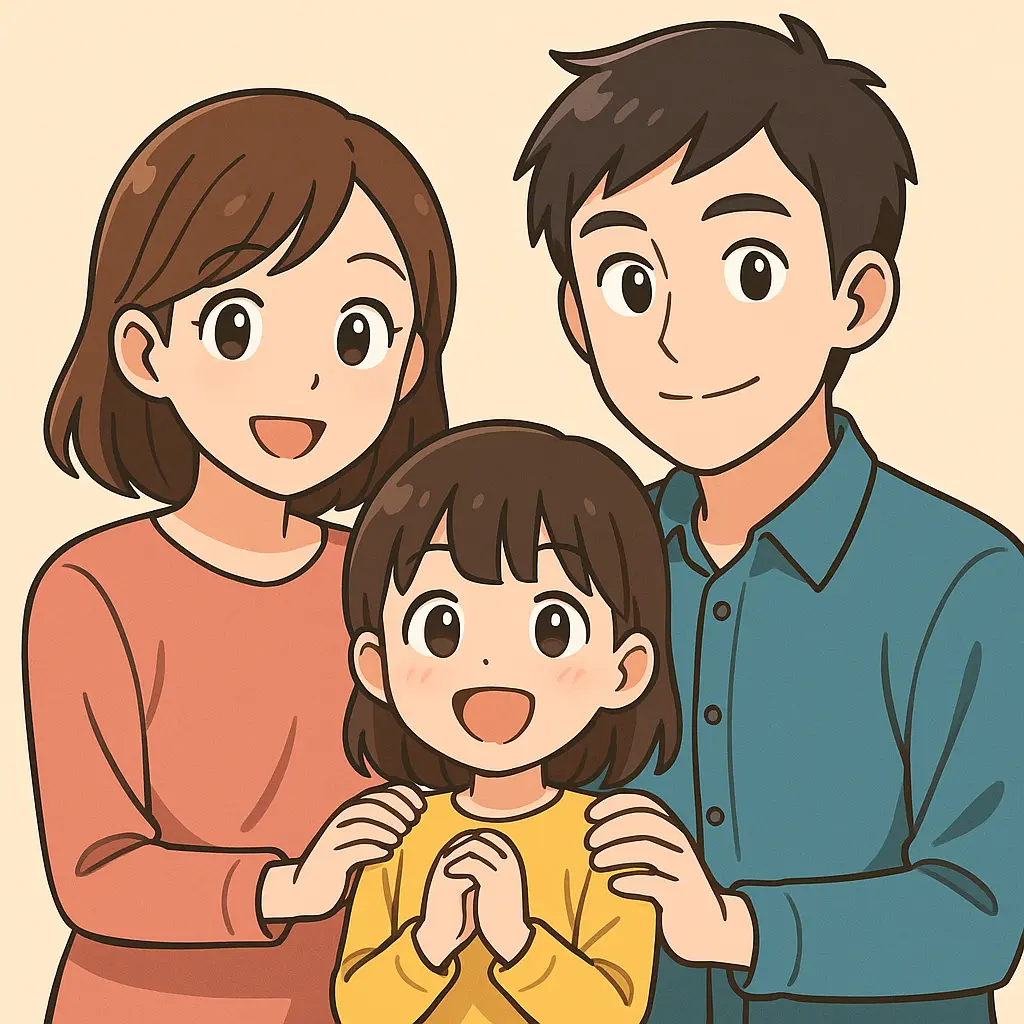









コメント