「感覚統合」ってなに?100均グッズで子どもの発達をサポートしよう!
「うちの子、落ち着きがなくて…」「同じ遊びばかりで困ってる」「どう関わってあげたらいいの?」
――そんな悩みを感じたことはありませんか?
実はその背景にあるかもしれないのが、「感覚統合」の課題です。
ちょっと専門的な言葉ですが、「感覚統合」とは、視覚・聴覚・触覚・前庭感覚(バランス感覚)・固有受容覚(身体の動きを感じる力)など、いろいろな感覚情報を脳の中でうまく整理して、体をスムーズに動かす力のこと。
この感覚統合がうまくいっていると、子どもは安心して動いたり、遊んだり、人と関わったりできるようになります。逆に、感覚統合の働きが未発達だと、次のようなことが起こりやすくなります。
- じっと座っていられない
- 手先が不器用で困る
- 音やにおい、服のチクチクに敏感すぎる
- 反対に鈍感で強い刺激を求めてしまう
- お友だちとの関わりを避けがちになる
このような状態は、いわゆる「発達が気になる」と言われる子どもたちに多く見られる傾向ですが、実は発達に特性がない子にも当てはまることがあります。
そこで注目されているのが、「感覚統合あそび」というアプローチ。
遊びを通して感覚を刺激し、子どもの発達を自然に後押しする、まさに“楽しくてためになる”支援方法なんです。
しかも最近では、市販のおもちゃに頼らず「100円ショップの材料だけで感覚統合グッズを手作りする」ママ・パパが急増中!
費用も抑えられて、子どもに合わせた工夫もしやすく、何より一緒に作る時間もいい刺激になる――まさに一石三鳥のアイデアです。
感覚統合あそびの効果とは?
「遊びで本当に発達が変わるの?」と思う方もいるかもしれません。
でも、感覚統合あそびには、こんなにたくさんの効果が期待できるんです。
- 集中力がついて、落ち着いて取り組めるようになる
- バランス感覚や姿勢保持がよくなる
- 手先が器用になって、工作や食事がラクになる
- 感覚の過敏さ・鈍感さが和らぐ
- 人とのやりとりがスムーズになる
これらは、療育や作業療法の現場でも実際に活用されている方法。
特別な知識がなくても、家庭で“あそび感覚”でできるのが最大の魅力です。
このブログでわかること【材料一覧/作り方/遊び方を網羅】
この記事では、感覚統合あそびをおうちでカンタンに取り入れる方法を、はじめての方にもわかりやすく紹介します。
具体的には、こんな内容をお届けします:
✅ 100均でそろう材料一覧表(目的別・グッズ別)
✅ 実際に作れる感覚統合グッズ7選の作り方+使い方
✅ 年齢や発達段階に合わせたアレンジ方法
✅ 安全に遊ぶための注意点や工夫ポイント
✅ 子どもが夢中になる声かけ例・関わり方のコツ
さらに、「どれを買えばいいの?」がすぐわかるチェックリストPDF付き!
買い物前にスマホでチェック、印刷して持ち歩きにも使える便利な特典もご用意しています。
「お金をかけずに、楽しく・安心してできる発達支援があったらいいな」
そんな想いをもつすべてのご家庭に向けて、この記事がお役に立てば嬉しいです。
それでは、さっそく次の章で、「感覚統合あそび」の基本から一緒に見ていきましょう!
感覚統合あそびってなに?初心者でもわかるやさしい解説
感覚統合=子どもが心地よく動ける力の土台づくり
「感覚統合」って、ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、実はとっても身近なもの。簡単に言うと、「自分の体とまわりの世界をうまくつなぐ力」のことなんです。
たとえば、滑り台を滑るとき。私たちは無意識に「体をまっすぐに保つ」「スピードを調整する」「終点で止まる」といった動きをしていますよね。これは、目で見た情報(視覚)、揺れを感じる力(前庭感覚)、筋肉の動きや力の入れ具合(固有受容覚)などを、脳がうまく整理しているからできること。
でも、この感覚の整理=感覚統合の力がうまく育っていないと、転びやすい・怖がる・力加減がわからない…といった困りごとが出やすくなります。
感覚統合は、“運動能力”の話だけじゃなく、心の落ち着きや人との関わりにも影響するものなんです。だからこそ、土台づくりとしてとても大切なんですね。
どんな子に必要?発達が気になる子・グレーゾーンの子にも◎
感覚統合あそびは、「特別な支援が必要な子向けのもの」と思われがちですが、実はそうではありません。どんな子にも役立つ遊びなんです。
でも、特におすすめしたいのは、こんなタイプの子どもたち:
- 落ち着きがない、よく動き回る
- 音や光に敏感で、すぐにびっくりする
- 逆に、刺激に鈍くて強い遊びを好む(激しく揺らす・叩くなど)
- 手先が不器用、工作やお箸が苦手
- 他の子とのやりとりがうまくいかず、ひとりで遊びがち
これらの傾向は、自閉スペクトラム症(ASD)やADHD、HSC(敏感気質)などの子によく見られますが、診断の有無に関係なく、「ちょっと気になるな」と思う子にもよくあります。
いわゆる「グレーゾーン」と言われる子や、個性の強い子にとっても、感覚統合あそびは“心地よく世界とつながる練習”になるんです。
感覚統合あそびのメリットとは?集中力・安心感・人との関わりもUP!
では、実際に感覚統合あそびを取り入れると、どんな良いことがあるのでしょう?
専門家の視点や家庭での実例をもとに、代表的な3つのメリットを紹介します。
① 集中力がアップする
身体の中の感覚が整ってくると、「ムズムズして集中できない」「気が散ってじっとできない」状態が減り、静かに取り組む力が育ちます。
これは、保育園や学校生活にも大きな効果を発揮します。
② 安心して過ごせるようになる
感覚の過敏さや鈍感さが落ち着いてくると、「嫌な刺激を避けたい」「怖くてチャレンジできない」といった不安が減り、子ども自身が安心して過ごせるようになります。
「泣く回数が減った」「癇癪が落ち着いた」と感じる保護者の声も多いですよ。
③ 人との関わりがスムーズになる
感覚が整理されてくると、自分の体がうまく使えるようになるため、お友だちとの遊びにも入りやすくなります。
“走る・止まる・投げる”などが上手にできるようになると、集団遊びでのトラブルも減り、自信にもつながります。
つまり感覚統合あそびは、「遊びながら、子どもが生きやすくなる土台を育てる」取り組みなんです。
しかも、それが100均素材で手軽に始められるなんて…これはやってみるしかありませんよね♪

【100均で完結】感覚統合あそびに“手作り”が選ばれる3つの理由
「感覚統合あそびって、なんだか難しそう…」「それに、専用のおもちゃは高そうだし…」
そんなふうに感じて、はじめの一歩をためらってしまう方も多いのではないでしょうか。
でも、実は最近、100均グッズだけで感覚統合あそびができる「手作りアイテム」が注目されているんです!
お金をかけず、しかもわが子にぴったり合わせた遊びができるとあって、子育て中のママ・パパから大人気。
ここでは、なぜ“手作り”が選ばれているのか?3つの理由からじっくり紹介していきます。
安い・カンタン・自由自在!100均DIYが人気なワケ
まず、いちばんの魅力はやっぱりこれ。
「安くてカンタン、しかもアイデアしだいでいくらでも応用できる」という点です。
100円ショップには、感覚統合あそびに使えるアイテムが想像以上にそろっています。たとえば:
- 色とりどりのビーズやフェルト(視覚・触覚の刺激)
- 握って気持ちいいスポンジやボール(固有受容覚の刺激)
- バランス遊びに使えるロープや柔らかマット(前庭感覚の刺激)
- スライム素材、洗濯のり、風船など(工作や手指あそびにも◎)
しかも、「材料を買う→その場で作る→すぐに遊べる」のも魅力。
特別な道具もいらず、ハサミとテープ、ボンドがあればOKという手軽さもあって、忙しい家庭にもぴったりです。
さらに、100均なら「ちょっと合わなかったな…」と思ったとしても、コストが低いから気軽にやり直せる安心感も大きいですよね。
市販グッズに負けない効果!子どもにぴったりフィットさせる工夫
市販の感覚統合グッズは確かに高機能なものも多くありますが、よくあるのがこんな悩み。
- 「サイズが大きすぎて場所をとる」
- 「刺激が強すぎて子どもが嫌がる」
- 「気に入ってくれなかった…高かったのに(涙)」
その点、手作りなら安心。お子さんの年齢や発達の段階、感覚の特性にあわせて「ちょうどいい刺激」を調整できるんです。
たとえば、触覚に敏感なお子さんには…
→ ザラザラ・チクチクしない素材を選ぶことで、無理なく触れる練習ができます。
反対に、刺激を求めやすい子には…
→ スライムや重みのあるクッションを作って、強めの感触を楽しませてあげることもできます。
さらに、「好きな色・キャラクターでデコる」「一緒に作って“自分のグッズ”にする」ことで、子ども自身の愛着ややる気もアップ!
親子のコミュニケーションツールにもなりますし、作る過程自体が立派な“感覚統合あそび”になるんです。
安全&衛生面の注意点|誤飲・アレルギー・素材選びのコツ
もちろん、手作りするうえで注意しておきたいこともあります。特に小さなお子さんの場合は、「安全」と「衛生面」の配慮がとても重要です。
まず、誤飲の危険。
ビーズ・ボタン・ビー玉などの小さなパーツは、口に入れてしまわないようにサイズ選びに注意しましょう。
目安は「トイレットペーパーの芯を通るサイズはNG」と覚えておくと安心です。
次に、アレルギーや肌トラブル。
スライムづくりに使う「洗濯のり」や「ホウ砂」は、人によっては肌に刺激がある場合も。
ゴム手袋を使う/洗い流しやすい素材を選ぶ/敏感肌の子は避けるなど、子どもに合わせた選択が大切です。
また、何度も使うものについては、洗える素材を選ぶ、アルコール除菌ができるものを使うといった衛生管理も意識しておきましょう。
手作りならではの「自由さ」は、子どもにとっても大きなメリット。
でも、その分、安全・衛生のバランスもしっかり意識しておくことで、安心して長く使える遊びになります。
【保存版】100均でそろう!感覚別おすすめ素材リスト
「感覚統合あそびをやってみたいけど、どんな材料をそろえたらいいの?」
そんな方のために、ここでは目的別・感覚別に分けて、100円ショップで手に入るおすすめ素材をズラリとご紹介します!
素材選びって、実はとっても大切。
なぜなら、子どもが“心地よい”“楽しい”“もう一回やりたい!”と感じるには、感覚に合った刺激が必要だからです。
「触った感覚に敏感な子」や「強い動きが好きな子」など、子どもによって求める刺激はさまざま。
だからこそ、感覚ごとに適した素材を知っておくと、ぐっと遊びの質が上がります!
感覚別おすすめ素材早見表|触覚・前庭感覚・固有受容覚 etc.
ここでは、感覚の種類ごとに、100均で手に入る素材と活用例をわかりやすくまとめました。
| 感覚の種類 | 刺激のねらい | 100均で手に入る素材例 | 活用例 |
|---|---|---|---|
| 触覚 | やさしく触れる、ざらざら・ふわふわなどの違いを感じる | フェルト/ビーズ/スポンジ/毛糸/スライム素材 | 触る・握る・なぞるなどの手指あそびに最適 |
| 前庭感覚(バランス) | 揺れる・回る・傾くなどの動きを通じて空間を感じる | ロープ/布/バランスボール(ミニ)/フラフープ | ブランコ風ロープ、くるくる回転あそびなど |
| 固有受容覚 | 押す・引く・重さを感じる動きで身体の力加減を覚える | ペットボトル/お米/砂/おもり用ビーズ/輪ゴム | 抱える・押す・引っ張る・お手玉づくりなどに活用 |
| 視覚 | 色・形・動きなどの視覚刺激を楽しむ | カラービニール/カラーボール/LEDライト | 色分け遊び、光の動きの観察など |
| 聴覚 | 音の強弱・リズム・高低を感じ取る | 鈴/マラカス/ペットボトル+ビーズで手作り楽器 | 自作楽器あそびや音の出る反応遊びに最適 |
どの感覚に働きかけるかを意識して素材を選ぶと、その子に合った“ちょうどいい刺激”が提供できるようになります。
特に発達が気になる子や、感覚に敏感な子の場合は、刺激が強すぎないものから少しずつ試していくのがコツです。
ダイソー・セリア・キャンドゥで買えるおすすめ素材&品ぞろえ比較
100円ショップといっても、お店によって品ぞろえやテイストがちょっと違うんですよね。
ここでは、代表的な3社「ダイソー」「セリア」「キャンドゥ」の特徴を、感覚あそび目線で比較してみました。
ダイソー:とにかく種類が豊富!定番素材はここでそろう
- 感覚遊びに使える材料が一番多い印象。
- 工作コーナー・キッズおもちゃコーナーに注目!
- スライム素材・センサリーボール・ビーズ系などが豊富
セリア:おしゃれ&ナチュラル素材が強み
- 手芸用品が充実していて、フェルト・毛糸・布類のバリエーションが豊富
- ナチュラルテイストの木製アイテムも◎
- 色合いやデザインが落ち着いていて、敏感な子にもおすすめ
キャンドゥ:小さな子向け素材や知育おもちゃに注目
- 感覚遊びに使える“手のひらサイズ”の素材が見つかりやすい
- シール・ステッカー・ビーズ系も充実
- スペースは小さいが、意外な掘り出し物がある印象!
3社とも定期的に商品の入れ替えがあるので、「気になる素材を見つけたらとりあえずゲットしておく!」のがコツ。
最近は季節ごとのイベント素材(ハロウィン・クリスマスなど)も感覚刺激にぴったりのものが多いので、シーズンコーナーもぜひチェックしてみてくださいね。
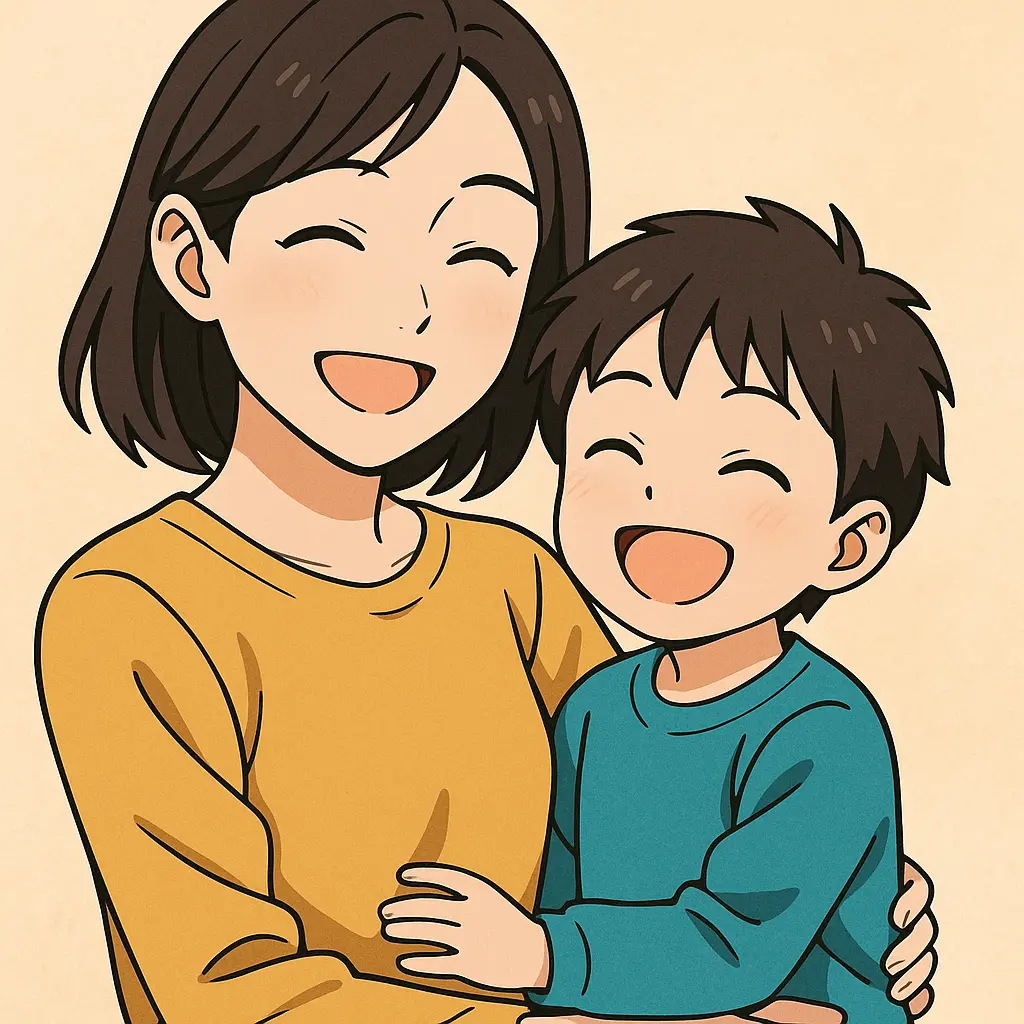
【全部100均でOK】感覚統合あそびグッズの作り方&遊び方7選
「感覚統合あそびに良さそうな素材はわかったけど、実際にどうやって遊ぶの?」
そんな声にお応えして、ここでは100均の材料だけでつくれる感覚統合あそびグッズを7つ厳選してご紹介します!
どれも実際に療育や発達支援の現場でも使われているアイデアをもとにしており、遊びながら自然に“発達の土台”が育つのがポイント。
しかも、家にあるものでサクッと作れるから、忙しいママやパパにもぴったりです♪
では、さっそく見ていきましょう!
① 集中力と手先の器用さUP!「ポットン落とし」
定番中の定番、「ポットン落とし」は視覚・聴覚・手指の動きを同時に刺激できる万能あそび。
100均の容器やペットボトルキャップなど、手に入りやすいもので手軽に作れます。
材料:
フタ付き容器/ペットボトルキャップ/フェルトやビーズ/シール/カッターやハサミ
作り方:
容器のフタにキャップが通るくらいの穴を開けるだけ!キャップに色をつけたり、フェルト素材に変えることでバリエーションも広がります。
発達への効果:
- 目と手の協調運動(コーディネーション)
- 指先の使い方(巧緻性)
- 落ちる音や感触が心地よい“感覚刺激”として作用
「〇の形だけ入れてみよう」など、遊びにルールを加えると認識力や判断力も育ちます。
② 抱っこで落ち着く!手作り「重みクッション」
感覚が敏感だったり、刺激に過敏なお子さんには“重さのある刺激”が有効なことも。
そんなときにおすすめなのが、手作りの「重みクッション」です。
材料:
布製ポーチ or 靴下/お米 or 小豆/輪ゴム or 布用テープ
作り方:
中にお米やビーズを詰めて、袋の口をしっかり閉じれば完成!サイズは子どもが抱きしめられる程度に。
使い方と効果:
- 膝の上にのせたり、抱きしめたりすることで「安心感」を与える
- 固有受容覚(筋肉や関節の感覚)を刺激して、自分の体を感じやすくなる
- 情緒の安定や姿勢保持のサポートにも◎
お出かけ先や不安定になりやすい場面での「お守りアイテム」にもなりますよ。
③ 感触がクセになる♪「手作りスライムあそび」
ヌルヌル、プルプルのスライムは、触覚へのアプローチに最適なあそび。
特に「触られるのが苦手」「感触に敏感」な子の感覚慣れにも使えます。
材料:
洗濯のり/ホウ砂 or コンタクト洗浄液/水/食紅 or 絵の具
作り方:
容器に洗濯のりと水を混ぜ、少しずつホウ砂を加えて好みの固さに。
色をつければ見た目の楽しさもアップ♪
あそび方&ねらい:
- 「冷たいね」「ぬるぬるするね」など感触に注目する声かけを意識
- 触る・伸ばす・ちぎる動作が触覚への刺激+手指の運動に
- 怖がる子にはビニール袋越しに触らせて、慣らしていくのがおすすめ
④ 投げても握ってもOK!「お手玉風おもりボール」
にぎにぎ・ポイッ!で全身に効くお手軽感覚アイテムです。
小さな力でも反応できるので、発達段階に関係なく使いやすいのが魅力!
材料:
風船/小豆 or 塩/ストッキング or ラップ/漏斗
作り方:
漏斗で中身を風船に詰め、二重にして丸めれば完成。ストッキングで包むと破損対策にもなります。
こんな力が育つ!
- 握る動作による手の筋力・力加減の感覚(固有受容覚)
- 投げてキャッチする遊びは、目と手の連動やバランス感覚も強化
- 軽いので室内でも安心して使えます♪
⑤ 夢中になれる!「段ボール迷路でビー玉転がし」
空間認知や集中力を高めたいときにおすすめの工作系あそび。
ストローで道を作る工程も、指先の練習になりますよ。
材料:
段ボール/ストロー/ビー玉/カッター/両面テープ
作り方:
段ボールにストローで道を作って貼り付けるだけ!コースは自由にアレンジ可能。
こんな効果が期待できる:
- 手首や腕のコントロール力UP(微細運動)
- 傾ける角度で動きをコントロール→因果関係の理解にも◎
- 「ゴールに入った!」という達成感が、自己肯定感にもつながります。
⑥ お部屋で揺らゆら♪「ブランコロープ」
「ブランコ」といっても、公園の大きなものじゃなくてOK!
お部屋で簡単に作れる“揺れのあそび”は、前庭感覚(バランス感覚)を育てる最高の刺激です。
材料:
ロープ/洗濯かご or タオル/クッション/S字フック
作り方&使い方:
洗濯かごやタオルに座ったり、包まれたりした状態で、ゆらゆら揺らすだけ。
床に接していても十分効果があります。
こんな子におすすめ:
- 揺れに敏感 or 揺れを求めがちな子
- 気持ちの切り替えが難しいときの“落ち着きスペース”としても活用可
- 安全面には注意し、大人がそばについて見守ってくださいね。
⑦ 引っ張ってストレッチ!「ゴムバンドあそび」
“全身を使って感覚を調整する力”を育てるなら、引っぱり遊びが効果的!
筋肉や関節にじっくり刺激を入れることができ、ストレス発散にも◎。
材料:
トレーニングチューブ or タイツ/取っ手(百均フック)/滑り止めマット
遊び方例:
- 手足に巻いて「のび〜る!」ストレッチ遊び
- 片方を固定して「引っ張り合いっこ」ゲーム
- トンネル状にして「くぐる・抜ける」あそびも楽しい!
得られる効果:
- 固有受容覚(体の深部感覚)を刺激して、姿勢や動きが安定
- 引っ張る・押すなどの力加減の調整練習に
- ルールをつけて遊ぶことで、遊びの幅がさらに広がります
以上、どれも100円ショップで気軽にそろう材料ばかり!
子どもの反応や感覚の特性に合わせて、無理なく・楽しく取り入れてみてくださいね♪
声かけひとつであそびが変わる!親子で楽しむ感覚あそびのコツ
感覚統合あそびって、ただ「やらせる」だけじゃもったいないんです。
ちょっとした声かけや関わり方次第で、遊びの質がぐんと深まり、子どもの反応が大きく変わることって、実はよくあります。
たとえば、同じ「ポットン落とし」でも、
「はい、やってみて」だけだと興味がわかない子でも、
「どっちの色が落ちるかな?音も聞いてみよう!」と声をかけると、目をキラキラさせて集中し出すことも。
この章では、遊びをもっと楽しく、もっと“発達につながる時間”に変える声かけのヒントをお伝えします。
感覚に注目させる声かけ例【年齢別】
「ただ楽しく遊べばいい」もちろんそれも大事ですが、
感覚統合あそびの効果を引き出すには、“今どんな感覚を使ってる?”を言葉で意識させるのがポイントです。
でも、年齢によって言葉の理解度も違うので、声かけもひと工夫。以下に年齢別の例をまとめてみました。
0~2歳頃:シンプルで感覚に寄り添う声かけ
- 「ふわふわだね~」「ツルツルしてるね」
- 「ころころ転がったね、音がしたね」
- 「ぎゅってしたら、気持ちよかったね~」
▶ ポイントは、“今、どんな感覚?”をママ・パパが代弁してあげること。
まだ言葉が出ない時期でも、感覚に名前をつけてあげることで、脳の中では“気づき”が育っています。
3~5歳頃:質問&共感で感覚に意識を向ける
- 「どっちのほうがザラザラしてた?」「音、どんなふうに聞こえた?」
- 「ぎゅーってしたら、落ち着く感じする?」
- 「転がすの、速くしたらどうなるかな?」
▶ この時期の子どもは、言葉で感じたことを表現する力が育ってくる時期。
大人がうまく問いかけることで、自分の感覚を言葉にする力=“内省力”も伸びていきます。
6歳以上:考えを引き出す+応用力を育てる声かけ
- 「こうすると揺れが強くなるって気づいたんだね、すごい!」
- 「スライム、手にくっつきすぎると気持ち悪い?どうしたら気持ちよくなるかな?」
- 「どうやったらもっと面白くなると思う?」
▶ この年齢になると、感覚を活かして“どうしたらもっと楽しくなるか”を自分で考えるチカラを育てていく時期。
「試して→感じて→工夫する」プロセスを言葉で支えるのがポイントです。
子どもの反応を見て調整するコツ|無理せずステップアップ
「感覚統合あそび」といっても、いつでも“いい感じ”に進むわけではありません。
子どもの日によっては、不機嫌だったり、急に嫌がったりすることも。
でも、それは悪いことではなく、「その子が自分の感覚を調整しようとしているサイン」でもあるんです。
こんなときはどうする?
▶「触りたくない」と避けるとき
→ 無理にすすめず、そばで大人が楽しそうにやって見せるだけでOK!
→ 刺激が強すぎるかもしれないので、似た素材で“やさしい感触”に変えてみるのもおすすめ。
▶「同じことばかり」になってきたら
→ 飽きたわけではなく、「安心してできること」に繰り返し取り組んでいる可能性も。
→ ちょっとだけ“いつもと違うルール”を加えてみるとステップアップにつながることも。
大人が意識したいこと
- 子どものペースを尊重すること
- 無理に誘導しないこと
- 「できた!」より「楽しかったね」で終わること
特に感覚が敏感な子や、自信がない子にとっては、「自分のペースでOK」という安心感が何よりの支えになります。
声かけや関わり方をほんの少し意識するだけで、感覚統合あそびはもっと楽しく、もっと深い学びの場になります。
次回のあそび時間に、ぜひ気軽に試してみてくださいね♪
まとめ|手作り感覚統合あそびは、親子の時間と発達を育てる宝物
感覚統合あそびって、ちょっと専門的なイメージがあるかもしれません。
でも、実際は「子どもが“なんか気持ちいい!”“楽しい!”と感じる時間を、ちょっと工夫してあげるだけ」で十分なんです。
しかも今回紹介したグッズは、全部100均の材料で手作りできるものばかり。
高価な知育玩具や専門的な道具がなくても、家庭にあるもの+ちょっとの工夫で“子どもにぴったりの遊び”が作れるって、なんだかすごくないですか?
遊びの中で、
- 手でつかむ
- 落とす
- 揺れる
- 引っ張る
- 抱きしめる
といった動きを繰り返すことで、自然に五感が刺激され、体の動かし方や感情のコントロール、集中力までもが育っていく。
さらに、“わが子のために作った”という気持ちは、親にとっても「関われた」「支えられた」という自信につながります。
つまり、感覚統合あそびは、子どもと親、両方の心と発達をあたためる“宝物”のような時間なんです。
もちろん、完璧を目指す必要はありません。
はじめは不器用でもいいし、素材がなければアレンジしてもOK。
大事なのは、「うちの子に合う遊びってなんだろう?」って考えてみること。
「お金をかけずに、子どもにぴったりのあそびを!」という想いがあれば、それだけでスタートは十分です。
まずは1つ、気になったあそびを作って、今日のあそび時間に取り入れてみましょう。
遊びながら「どんな刺激が好きかな?」「どんな反応をするかな?」と観察していくことで、
きっと、親子だけの特別な“感覚あそびのレシピ”ができあがっていくはずです。
子どもの発達に寄り添うことって、難しく考えすぎるとしんどくなってしまうけれど、
「遊び」という形に変えることで、親も子もぐっとラクに、そして楽しく向き合えるようになります。
この記事が、そんなきっかけになれたらとっても嬉しいです。
さあ、「まずは1つ」、遊びを通して、わが子の感覚と心に寄り添ってみましょう!
以上【100均だけでOK!感覚統合あそびグッズ7選&簡単DIY術~材料一覧付き】でした。











コメント