「性教育=早すぎる」は大誤解!?発達障害の子こそ今すぐ始めたい理由
「性教育って、小学生になってからでいいよね?」「うちの子にはまだ早いかな…」
そんなふうに思っている方、きっと多いと思います。実際、「性」という言葉が出てくると、ちょっと身構えてしまいますよね。ですが、性教育は“思春期の知識を教えること”だけではありません。もっと小さな頃から、日常の中で自然に伝えられる大事なことがたくさんあるんです。
特に、発達障害のある子どもたちは、暗黙のルールや場面の空気を読み取ることが苦手なことが多いです。「どこまでがOKで、どこからがNGか」といった“グレーゾーン”が理解しづらいからこそ、性にまつわるトラブルに巻き込まれやすい傾向があります。たとえば、友達との距離感が近すぎてしまったり、自分の体を触られることへの違和感をうまく表現できなかったり……。
だからこそ、性教育は“今すぐ始めるべき”なんです。
もちろん、「うまく説明できる自信がない」「子どもがどこまで理解できるのかわからない」と不安に感じる方も多いはず。実際に、よく聞く保護者の声にはこんなものがあります。
- 「うちの子、性の話をすると変に興味を持ちそうで怖い」
- 「そもそも“性教育”って、どこまで話すべきなの?」
- 「性に関して教えるのって、ちょっと恥ずかしい…」
こうした気持ち、ものすごくよくわかります。でも安心してください。性教育は、“一気に全部を教える”ものではなく、子どもの成長に合わせて“少しずつ積み重ねていくもの”です。むしろ、早いうちからスタートした方が、子どもにとっても自然に受け入れやすくなります。
また、発達障害のある子の場合、視覚的な支援や具体的なルールづけがあると理解しやすいことが多いため、工夫次第で、年齢や理解度に合わせた性教育がちゃんと可能なんです。
このあとの章では、「じゃあ実際に、何歳から・何を・どう伝えたらいいの?」という具体的な内容を、年齢別・発達特性別にわかりやすく紹介していきます。性教育が苦手なパパママでも無理なく実践できるような方法や、日常生活の中で取り入れやすいアイデアもたっぷりご紹介しますので、ぜひ読み進めてみてくださいね。
なぜ発達障害のある子に“性教育”が不可欠なの?
「性教育って、特別なことを教えるんでしょ?」と身構える方も多いかもしれませんが、実はそうではありません。性教育の本質は、“自分と他人の境界線を知ること”や“自分の気持ちや違和感を言葉にできる力を育てること”なんです。
そしてこの「境界線」や「場面に応じた行動の切り替え」って、実は発達障害のある子どもたちにとってとても難しいテーマだったりします。
だからこそ、性教育は発達障害のある子にとって“絶対に必要な学び”なんです。
ではなぜそんなに重要なのか?2つの視点から、くわしく見ていきましょう。
実はこんなに違う!定型発達の子との教え方の差
まず最初に知っておきたいのが、性教育の伝え方は、発達特性によってアプローチが大きく変わるということ。
たとえば、定型発達の子どもであれば「なんとなく」「空気を読んで」行動を学んでいく場面がたくさんあります。たとえばこんな感じ:
- 他の子の反応を見て「これはやってはいけない」と気づく
- お友達が嫌がっている表情を察して距離を取る
- 親がちょっと注意しただけで、「あ、これはダメなんだ」と理解する
でも、発達障害のある子どもはこうした“暗黙のルール”や“微妙な感情の変化”を読み取るのが苦手です。
だからこそ、言葉で明確に・具体的に伝える性教育がとても大切。
たとえば、
- 「パンツの中はプライベートゾーン。誰にも見せていい場所じゃないよ」
- 「『やめて』って言われたら、それ以上近づいちゃダメなんだよ」
- 「服を脱ぐのはトイレかお風呂だけね」
…といったように、“感覚ではなくルールとして”教える必要があるんです。
また、視覚的に理解しやすいように絵カードや写真、ロールプレイなどを使って教えると効果的です。これは「性教育だから特別」なのではなく、普段の生活支援と同じように、子どもの理解スタイルに合わせて工夫することがポイントなんですね。
被害者にも加害者にも…知らないと怖い性のトラブルリスク
もうひとつ大事な視点が、「トラブルの防止」という観点です。
性教育というと、“恋愛や性行為の話をすること”だと思われがちですが、実はもっと基本的な「自分の身を守る力」を育てるのが最優先。
たとえば、こんなケースがあります。
- 知らない大人に体を触られたのに、違和感をうまく言えず、そのままにしてしまった
- お友達にズボンを下ろされて笑われたけど、それが“いけないこと”だと理解できなかった
- テレビで見たマネをして、他の子の体を触ってしまった(本人に悪気はない)
こうした場面、実は支援現場でもたびたび報告されています。
発達特性があると、無意識のうちに“被害者”にも“加害者”にもなってしまうリスクがあるんです。
そして何より怖いのは、本人が「何が悪かったのか」「なぜ怖かったのか」を言葉にできず、そのまま記憶に残ってしまうこと。
これは将来的な自己肯定感の低下や、人間関係のトラブルにもつながりかねません。
つまり性教育は、子ども自身が“NO”を言える力、“これはおかしい”と気づける力を育てる重要なプロセス。
「難しい話は後でいい」ではなく、“今この瞬間から必要な支援”なんです。
このように、発達障害のある子どもたちにとっての性教育は、「知識」以上に「自分と他人の違いを理解し、適切に行動できる力」を育てるための大切なステップです。
次の章では、年齢ごとに“どんなことをどんなふうに伝えたらいいのか”を、具体例つきで紹介していきますね!
「うちの子にはまだ早いかも…」と感じていた方も、ぜひ続きをチェックしてみてください。
あなたの子どもに“必要なタイミング”は、実はもう始まっているかもしれません。
【年齢別】何歳で何を教える?性教育のステップと伝え方ガイド
性教育って、「小学校高学年くらいからでいいかな」と思っている方も多いかもしれません。でも実は、“もっとずっと前から”スタートできる内容がたくさんあるんです。
とくに発達障害のある子どもは、一度に理解するのが難しかったり、抽象的な説明では伝わりにくい特性があります。だからこそ、年齢や発達段階に合わせて、少しずつ丁寧に伝えていくことがとても大切。
ここでは、【3~5歳】【6~8歳】【9~12歳】【13歳以上】の4つのステージに分けて、「ねらい・教えるべき内容・伝え方の具体例」をわかりやすく紹介します!
3~5歳|“プライベートゾーン”を知る一歩め!
この時期の子どもたちは、まだ“性”という概念は持っていません。でも実は、性教育のスタートとして最も大切なのがこの時期。
ここでのねらいは、「自分の体は自分だけのものだよ」という感覚を育てること。
たとえば、次のようなことを日常の中で少しずつ伝えていきましょう。
- 体の正しい名前(例:おちんちん、ちつ)を教える
→「おまた」などのあいまいな言い方ではなく、医学的に正しい名前で伝えることが大切。 - 「パンツで隠れているところは見せない・触らせない」が基本ルール
→保育園やお風呂での着替えの時などに繰り返し伝えて。
さらに、「いや!」と自分の気持ちを表現する練習もこの時期から大事。
たとえば、くすぐり遊びの途中で「もうやめて」と言われたら「うん、わかった」と受け入れてあげる。このやり取りが、“NOを言っていい”という感覚を育てる基盤になります。
6~8歳|「触っていい?ダメ?」を判断できる力を育てる
この年齢になると、お友達との関わりがぐっと増えてきます。
同時に、「スキンシップがどこまでOKか」「どんな行動が迷惑になるのか」などの社会的なルールを理解する力も必要になってきます。
ここでの性教育のねらいは、「相手との距離感」や「自分と他人の違い」を具体的に知ること。
- 「お着替えは個室で」「トイレはドアを閉めて」などの場面別ルールの確認
- 「男の子と女の子で体のつくりが違う」ことを伝える
→恥ずかしがらずに、図鑑や絵本を使ってさらっと説明するのが◎
また、家の中でも「玄関では服を脱がない」「おしりを出したらダメ」といった行動ルールを繰り返し具体的に伝えることが大切です。
発達特性によっては、1回では覚えられないことも多いので、“何度でも・視覚的に・肯定的に”教えるのがポイント。
9~12歳|心と体の変化に戸惑う時期こそ“安心の声かけ”を
この頃からは、いよいよ第二次性徴が始まり、体にも心にもさまざまな変化が現れてきます。
でも、「どうしてイライラするの?」「なぜ急に体が変わるの?」と戸惑っている子どもも多く、変化をうまく言葉にできないケースもよく見られます。
この時期のねらいは、以下の2つです。
- 体の変化(月経・精通など)を具体的に理解する
- 気持ちの揺れに“気づき・受け止める”力を育てる
たとえば、
- 月経については、実物のナプキンを見せて「こんな時に使うよ」と説明する
- 精通については、「これは体が大人に近づいているサインだよ」と伝える
- 感情の波に対して、「イライラするのも普通だよ」と安心できる言葉がけを意識する
さらに、「ひとりになりたい」「なんとなくさわっていたくなる」といった気持ちにも肯定的に寄り添うことで、子どもは「これでいいんだ」と安心します。
“隠す・叱る”のではなく、“受け止めて教える”スタンスが鍵。
13歳~|恋愛・性・SNSトラブル…現実的なテーマを伝える時期
中学生以降になると、いよいよ“実際の性行動”に関する話題も避けては通れません。
発達障害のある子どもの場合、ネットリテラシーや同意の概念など、あいまいで複雑なテーマが特に理解しづらいことがあります。
この時期のねらいは、
- 「同意」と「自分で判断する力」を育てること
- 恋愛・性行為・ネットの危険性について現実的に伝えること
たとえば、
- 「同意とは、相手が“いいよ”と言っても、気が変わったらいつでも断ってOKなんだよ」と何度も確認
- 避妊や性感染症についても、図解や動画などで視覚的に説明
- SNSでのやり取り・写真の送信はどんなリスクがあるのかをロールプレイで体感させる
また、気持ちが高ぶった時の対処法や、「この場合は大人に相談しようね」と相談先を具体的に示しておくことも重要です。
このステージでは、子どもの意思や選択を尊重しながら、正しい情報と安心できる支えをセットで届けることがカギになります。
以上が、年齢別に見た性教育のステップと伝え方のポイントです。
どのステージも、「完璧に教える必要」はありません。
大切なのは、“今その子に必要なことを、少しずつ、わかりやすく”届けていくこと。
【発達特性別】伝え方のコツまとめ!性教育がもっと伝わる工夫
性教育って、子どもの年齢だけじゃなく、その子の発達特性に合わせて伝え方を工夫することがとっても大事なんです。
同じ内容でも、伝える順番や言い方、ツールをちょっと変えるだけで、理解の深まり方がぐんと変わることもあります。
ここでは、ASD(自閉スペクトラム症)タイプ、ADHD(注意欠如・多動症)タイプ、そして知的障害を伴うタイプの3つに分けて、性教育を“もっと伝わるもの”にするためのヒントをご紹介します!
ASDタイプ|“見える化”と繰り返しがカギ!
ASDタイプの子どもは、抽象的な言い回しや空気を読むことが苦手な傾向があります。
「みんなが嫌がるからダメだよ」「ちゃんと場面を考えて」など、あいまいな表現だと伝わらないことが多いんですよね。
だからこそ、「これはOK」「これはNG」といったルールをハッキリ言語化して伝えるのが効果的です。
たとえば、
- 「おちんちんはお風呂とトイレ以外では見せないよ」
- 「“さわっていい?”と聞いて、相手が『いいよ』って言わないとダメなんだよ」
- 「キスはママとだけ、友達にはしないよ」
など、具体的な行動を“そのままの言葉”で伝えるのがポイント。
さらに、ASDの子どもは視覚的な情報に強いことが多いので、絵カードや写真、イラスト入りの絵本などを活用するのもおすすめです。
また、一度教えて「わかった」と言っても、それで終わりじゃありません。繰り返し・くり返し・何度も伝えることが大切!
構造化(いつ・どこで・どうする)+視覚支援のタッグで、理解しやすさがグッとアップします。
ADHDタイプ|衝動的な行動にはルールの繰り返し練習
ADHDタイプの子どもは、注意がそれやすい・思いついたらすぐに動いてしまう(衝動性)といった特性があるため、性に関する行動でもトラブルになりやすいことがあります。
たとえば…
- 「面白そうだから」という理由でお友達のズボンを突然引っ張ってしまった
- 注意された直後なのに、また同じことを繰り返してしまう
- 好きな子に何度も体を触ってしまい、距離感のトラブルに
こういったケースでは、「していいこと・ダメなこと」を明確に伝えるだけでなく、“場面ごとの練習”がとても有効。
たとえば、
- 「保育園でのお着替え」「公園で友達と遊ぶ時」「お風呂上がりに体を拭く」など、具体的なシーンでロールプレイ
- 「やっていい時・やってはいけない時」を表(チャート)で視覚化
- 忘れてしまっても叱らず、「もう一回やってみようか」と前向きにくり返す姿勢が大切
ADHDの子には、失敗を責めない・成功を大げさに褒めるくらいのメリハリがあると、より伝わりやすくなりますよ。
知的障害を伴うタイプ|とにかく“わかりやすさ”重視!
知的障害を伴うタイプの子どもには、「性」に関する言葉自体が難しく感じられることも多いです。
「生理」「性別」「プライベートゾーン」などの概念を、言葉だけで説明しても理解が追いつかないことも。
だからこそ、“とにかくわかりやすく、視覚的に、シンプルに”が大原則!
具体的には…
- 絵カードや写真を見せながら説明する
- 性器や体の違いについて、ぬいぐるみを使って一緒にお風呂ごっこをしながら教える
- 「いい・わるい」を色で分けた表やマーク(◎/×)で伝える
- お話絵本や動画を繰り返し観ることで、少しずつ理解を深めていく
また、「パンツの中をさわってしまう」「人前で服を脱いでしまう」などの行動があった時も、ただ注意するだけでなく、「どこで・どうしたらいいか」を行動で教えることが大切です。
「トイレで1人のときにするよ」「お部屋に戻ってから着替えようね」など、場所と行動をセットで伝えることで、子どもも混乱しにくくなります。
このように、発達特性によって性教育の伝え方にはさまざまな工夫が必要です。
でも、どの子も「ちゃんと理解したい」「自分を大切にしたい」という気持ちは同じ。その子に合った方法で伝えれば、性教育だってちゃんと届きます。
「言っても伝わらない」ではなく、「伝え方を変えてみよう」と視点を切り替えることが、支援の第一歩です。
【保護者の悩みQ&A】恥ずかしい・難しい…その気持ちに寄り添います
「性教育って大切だとは思うけど、正直どうしていいかわからない…」
「わが子に話すとなると、なんか照れちゃって…」
こんな気持ち、実はたくさんの保護者が抱えています。とくに発達障害のある子に対しては、“伝え方が難しそう”“どこまで話すべき?”という悩みも加わって、踏み出せずにいる方も少なくありません。
でも、完璧な教え方なんてなくて大丈夫。まずは「気になったときがベストタイミング」という気持ちでOKです。
ここでは、よくある保護者の“リアルな声”と、それに対するヒントをQ&A形式でまとめました。
Q. 「性の話をすると逆に興味を持ちすぎるのでは?」
A. 興味を持つのは自然!“正しい知識”がカギです。
「性の話をすると、かえって興味を持ってしまうのでは?」と心配する方はとても多いです。
でも実は、それはまったく逆。“正しい知識がない”ほうが、子どもは不安や好奇心から誤った情報に引っ張られやすいんです。
たとえば、インターネットや動画の中には、過激な表現や誤った情報もたくさんありますよね。
そういった情報に最初に触れてしまうと、「性=恥ずかしい」「性=暴力的」といった間違ったイメージがついてしまうことも…。
だからこそ、親や信頼できる大人が“あたたかく・正しく・わかりやすく”教えてあげることが、子どもの安心につながります。
興味を持つのは成長の証。興味を“正しい知識に変えてあげる”ことが、性教育の大きな役割なんです。
Q. 「自慰を始めたらどうすればいい?」
A. 叱らずに“マナー”として伝えるのがベストです。
子どもが自慰をしている場面を見て、びっくりしてしまったという保護者の声はよくあります。
でも、自慰(マスターベーション)はとても自然な行動で、思春期前後に限らず、幼児期から見られることもあります。
大切なのは、「やってはいけないこと」ではなく、「どこで・いつ・どうするか」をマナーとして伝えること。
たとえばこんなふうに伝えると◎です。
- 「体に触れるのは悪いことじゃないけど、お部屋の中で1人のときにね」
- 「トイレやリビングではしないようにしよう」
- 「気持ちが落ち着かないときにしたくなることもあるよね」
叱ったり否定したりすると、子どもは“性”に対して罪悪感を抱いてしまうことがあります。
そうなると、体の変化を伝えることも、悩みを話すことも難しくなってしまうんですよね。
だからこそ、「安心して話せる相手」である親が、“受け止める姿勢”を見せることがとても大切なんです。
Q. 「性のこと、口に出すのがどうしても無理…」
A. 教材の力を借りればOK!親が完璧じゃなくていいんです。
「やっぱり性の話は恥ずかしい」「なんて言っていいか分からない…」という方も、もちろんたくさんいます。
その気持ち、本当に自然なことです。
でも、無理して苦手な話をするよりも、“頼れる道具に頼る”のも立派な選択肢!
いまは、性教育に役立つ絵本やカード、動画教材などがたくさんあります。
たとえば、
- 親子で一緒に読む「プライベートゾーン」の絵本
- 性のルールをイラストで学べるカードゲーム
- YouTubeなどの信頼できる性教育チャンネル
こういったツールを使えば、親が言葉を選んで苦労することなく、“自然な流れ”で性の話ができるようになります。
さらに、必要であれば、放課後等デイサービスや学校の支援スタッフに協力をお願いするのもアリ!
親が全部背負わなくていいんです。「話せないなら、話せる人にお願いする」も立派な支援です。
どの悩みも、最初は誰もが抱くもの。
でも、「無理をしなくていい」「自分のやり方で少しずつ伝えていけばいい」という気持ちで取り組めば、きっと子どもにもその“安心”が伝わっていきます。
性教育は、教える側の親にとっても、実は“子どもと一緒に育っていくプロセス”。
最初の一歩が難しいだけで、やってみると意外とスムーズにいくこともたくさんありますよ。
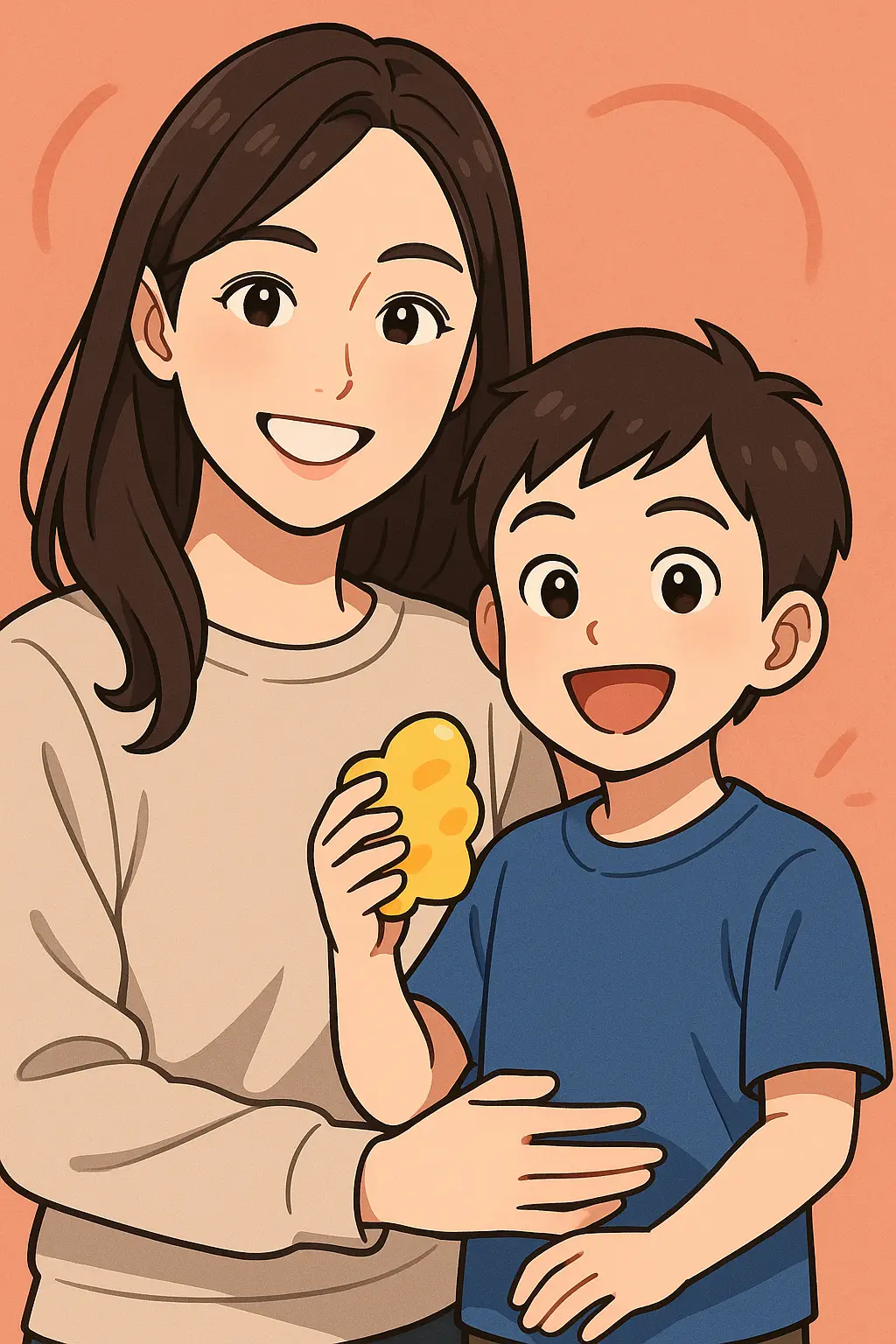
【厳選】性教育に役立つ!おすすめ教材・支援アイテム
性教育って、「どこから話せばいいのかわからない…」「なんだか気まずい…」と感じる方も多いですよね。
でも、そんなときに頼れるのが、“教材”や“支援アイテム”といったサポートツールたち。
最近では、発達障害のある子どもにもわかりやすく作られた絵本やカード、動画教材がたくさん登場しています。
また、家庭だけで頑張るのではなく、支援機関と連携することで、性教育を無理なく自然に進めることも可能なんです。
ここでは、「これは使いやすい!」と評判の良い教材やサポート体制についてご紹介していきます。
年齢別おすすめ教材|絵本・動画・ぬいぐるみなど
“これなら話しやすい!”親子で使える定番ツール集
「どう伝えればいいの?」と悩んだとき、教材があると話のきっかけづくりにもなります。
特に発達障害のある子どもは、視覚情報からの理解が得意な場合も多いため、絵や写真を使った教材はとても効果的。
以下に、年齢別で使いやすい教材をまとめてみました。
3~5歳向け
- 【絵本】『あなは だれのもの?』
→体の名前と「プライベートゾーン」についてやさしく伝えられる一冊 - 【ぬいぐるみ】着せ替え人形(下着のついたタイプ)
→着替えごっこをしながら、体の扱い方を遊びで学べる
6~8歳向け
- 【動画教材】NHK for School『からだのひみつ』シリーズ
→短時間で、体の違いやマナーをアニメで楽しく学べる - 【カード教材】「これはいい?だめ?」シチュエーションカード
→公共の場での行動をゲーム感覚で判断する練習ができる
9~12歳向け
- 【図鑑】『からだの本』(学研・福音館など)
→第二次性徴や月経・精通について、絵と写真でわかりやすく解説 - 【ワークブック】『わたしのからだノート』
→体や気持ちの変化について、自分のことを考えながら書き込める
13歳以上向け
- 【動画教材】YouTube「せいぎょちゃんねる」「せいのがっこう」など
→同意・避妊・SNSリスクなど、思春期以降のリアルなテーマをやさしく解説 - 【ロールプレイ教材】YES/NOカード
→「してもいい?」「ダメって言う勇気」を練習する場として活用できる
教材を使うことで、親が言葉でうまく伝えられなくても、“視覚的なヒント”が会話を助けてくれるのがポイント。
また、絵本やカードなら兄弟姉妹とも一緒に取り組めるので、家族の理解を広げるツールにもなります。
家庭×支援機関のWサポートで、無理なく性教育を進めよう
放課後等デイ・支援センターを頼ってOK!
「家庭だけで教えるのはちょっと不安…」「うちの子、親の言うことは聞いてくれなくて…」
そんなときは、学校や福祉の支援機関と“チーム”を組んで取り組むのがベスト。
たとえば…
放課後等デイサービスでの支援
- ロールプレイや集団プログラムの中で、“距離感”や“NOの伝え方”を練習してくれる施設も
- 担当スタッフと連携して、「家庭ではこういう教え方をしている」と共有できる
発達障害者支援センターや保健センター
- 専門スタッフによる相談や性教育プログラムの紹介を受けられる
- 医療・教育・福祉のネットワークを活用して、より安心な支援体制に
学校での対応
- 通級指導教室や特別支援学級の先生と連携し、家庭と同じ方針で伝えてもらうことで子どもに一貫性を持たせられる
性教育は、どうしてもセンシティブな話題になりがち。
でも、家庭と支援機関がタッグを組むことで、「教える人が違っても、伝えることは同じ」という安心感を子どもに届けることができます。
「親だけで頑張らなきゃ」と思わなくて大丈夫。頼れる支援はどんどん使っていきましょう!
このように、性教育をスムーズに進めるためには、“道具”と“仲間”の力を借りることがカギになります。
【リアル体験談】「うちの子も変わった!」成功事例に学ぶ
ここまで読んで「性教育が大事なのはわかったけど、実際にやってみてどうだったの?」と思った方もいるのではないでしょうか。
確かに、性教育は“正解がひとつじゃない”分野。だからこそ、他の家庭や支援現場でのリアルな体験談が、すごく参考になるんです。
この章では、実際に早期から性教育に取り組んだご家庭と、通所支援施設で成功した支援者の声をご紹介します。
「これならうちでもできそう!」と思えるヒントがきっと見つかりますよ。
早めの性教育で安心感UP!母の実体験
トラブルゼロで成長中!家庭でできることはこれだった
小学1年生の息子さんがASD(自閉スペクトラム症)と診断されたというAさん。
きっかけは、「友達との距離が近すぎる」「ズボンを突然下ろしてしまう」といった行動が気になったことだったそうです。
最初は戸惑ったものの、「今ならまだトラブルになる前に教えられるかも」と思い、5歳の頃から性教育をスタート。
Aさんが取り入れたのは次のような取り組みでした。
- 絵カードで「していいこと/ダメなこと」を視覚的に整理
- 入浴中に「パンツで隠れているところは自分だけの大事な場所だよ」と繰り返し伝える
- 「友達の体に触るときは“いい?”って聞いて、相手が“いいよ”って言ったらOKだよ」とロールプレイ練習
その結果、息子さんは徐々に公共の場での行動をコントロールできるようになり、トラブルもゼロに!
Aさんいわく、「難しい言葉より、生活の中で“これはしていい・ダメ”を具体的に何度も伝えることがポイント」とのこと。
また、「性教育=性行為の話ではないと知ってから、気持ちがラクになった」とも話してくれました。
性教育は“守る力”を育てるもの。 その実感を持てたことで、Aさんも息子さんも、日々の安心感がぐんと増したそうです。
通所支援の“ロールプレイ”で行動が変わった!
現場スタッフの工夫と子どもの反応の変化
次は、放課後等デイサービスで実践された性教育支援の事例をご紹介します。
対象は、ADHDと軽度知的障害のある小学4年生の男の子。日頃からスキンシップが激しく、「好きな子には何回も抱きついてしまう」「場面の切り替えが難しい」といった行動が見られていました。
そこで施設スタッフは、週1回の時間を使って、“場面ごとの行動練習(ロールプレイ)”をスタート。
- 「友達に挨拶するときの距離はこのくらい」
- 「“イヤ”って言われたら、こうやって手を引っ込めよう」
- 「好きな子に気持ちを伝えたいときは、こんなふうに話してみよう」
といった内容を、ぬいぐるみやイラストカードを使いながら、遊び感覚で反復。
最初は戸惑っていた子どもも、回数を重ねるごとに“場面と行動をセットで覚える”力がついてきたそうです。
スタッフいわく、「ポイントは、叱るのではなく、“こうしたらうまくいくよ”というポジティブな練習をすること。」
また、「“なんでダメか”を感情ではなくルールとして教えると、子ども自身も納得しやすい」とも話していました。
その子は現在、「こういう時はこうする」と自分から言葉にできる場面が増えてきており、支援者と家族の連携で行動も安定してきているとのことです。
性教育は、「一度教えたら終わり」ではありません。
でも、日常の中で少しずつ繰り返すことで、子どもたちはちゃんと“自分を守る力”を育てていくことができるんです。
そして何より、親や支援者が「教えてあげたい」「一緒に学びたい」という姿勢を持っていることが、子どもにとっての最大の安心感になります。
まとめ~性教育は「教えられることから、できることから」でOK!
性教育というと、どうしても「ちゃんと教えなきゃ」「全部説明しなきゃ」と身構えてしまいがちですが、実際はそんなにかしこまる必要はありません。
性教育は、“一気に教えるもの”ではなく、“その子に合わせて、少しずつ積み重ねていくもの”。
大切なのは、親ができるタイミングで、無理なく始めること。
たとえば、「お風呂のときに体の名前を教えてみる」「トイレの後に『プライベートゾーン』の話をしてみる」など、身近な生活の中に“伝えるチャンス”はたくさんあります。
そして、最初から完璧な知識を伝える必要もありません。
まずは“1つのルール”から始めればOK。
- 「パンツの中は見せない・さわらせない」
- 「イヤなときは“イヤ”って言っていい」
- 「お着替えは1人でできる場所で」
こうしたシンプルなルールでも、子どもにとっては大切な「安心の土台」になります。
また、性に関する話題は、親自身も学びながら伝えていくもの。
「どう説明すれば伝わるかな?」「こう言ってみたら分かりやすいかな?」と試行錯誤しながら、親子で一緒に成長していけることこそが、性教育の醍醐味ともいえるでしょう。
さらに、正しい知識を伝えることで、子どもは「自分の体は大切なんだ」と実感し、“自分を守る力”や“他人を思いやる心”も育っていきます。
それは、将来の人間関係や社会性にもつながる、かけがえのない力です。
性教育=難しいもの、恥ずかしいもの、ではありません。
“子どもと一緒に考える、日常の会話のひとつ”として、もっと気軽に取り組んでいいんです。
今日できることを、ひとつ。
明日もう少しできそうなら、またひとつ。
その積み重ねが、子どもにとっての「安心と自信」になっていきます。
性教育は、親だけが頑張るものでも、子どもに一方的に教え込むものでもありません。
「子どもと一緒に、少しずつ育てていくもの」。
そんな気持ちで、ゆっくり、楽しく、始めてみてくださいね。
以上【発達障害の子に“性”をどう教える?年齢別にわかる伝え方&リアルな実例つき】でした。











コメント