はじめに|他害がひどい子どもの行動に悩むママへ
子育てをしていると、「どうしてうちの子はこんなに手が出てしまうんだろう…」と悩むことはありませんか?
特に発達に特性のある子どもは、「叩く」「噛む」「物を投げる」などの“他害行動”が目立ちやすいと言われています。
もちろん、子ども自身は「悪いことをしてやろう」と思ってやっているわけではありません。
でも実際にその場面に直面すると、相手の子どもをケガさせてしまわないか心配になったり、周りのママからどう見られているか不安になったりしますよね。
「うちの子だけが他害がひどいのかな?」と感じて孤独になるママは少なくありません。
でも実際には、多くのママたちが同じように悩んでいるんです。
発達障害や発達がゆっくりな子を育てるママの声を集めてみても、
- 「突然噛みついてしまって、どう止めたらいいか分からない」
- 「物を投げてしまい、兄弟がケガしないか心配」
- 「外出先で叩いてしまい、周りの視線がつらい」
など、共通の困りごとがたくさん出てきます。
ここで大切なのは、子育ての悩みをひとりで抱え込まないことです。
ママ自身がつらくなってしまうと、子どもに向き合うエネルギーまで失われてしまいます。
他害行動には「なぜその行動が出ているのか」という背景が必ずあります。
その背景を理解しながら、「どう対応すれば安全か」「どうすれば落ち着けるか」を少しずつ工夫していけば、ママの気持ちもぐっと楽になります。
この記事では、
- 家庭でできる実践的なアイデア
- ママ自身がイライラしないための工夫
この2つの視点から、無理なく続けられる対応法をお伝えしていきます。
「他害がひどい子どもとどう向き合えばいいのか…」と悩むママが、少しでも安心して笑顔を取り戻せるヒントになれば嬉しいです。
他害がひどい子どもの行動|原因と背景を理解しよう
子どもが「叩く」「噛む」「投げる」などの行動をすると、ママはとてもショックを受けますよね。
「どうしてこんなことをするの?」「しつけが足りないのかな?」と自分を責めてしまう方も少なくありません。
でも実は、他害行動には必ず理由や背景があるんです。
ここでは、まず「他害行動とは何か?」という基礎から整理し、そのうえで発達障害の子に多い原因、そして大事な視点についてお伝えしていきます。
【基礎知識】「他害行動」とは?叩く・噛む・投げるなどの具体例
「他害行動」とは、周囲の人や物に危害を加える行動のことを指します。
よく見られる具体例には、次のようなものがあります。
- 友達や兄弟を叩く・つねる
- 怒ったときに噛みつく
- 物を投げたり壊したりする
- 髪を引っ張る
- 大声で叫んで相手を威嚇する
もちろん、これらは「悪意を持っているから」ではありません。
まだことばや気持ちの表現方法が未熟で、自分の欲求や不安をどう伝えればいいのか分からないときに、こうした行動が出やすくなるのです。
【なぜ?】発達障害の子どもに他害が多い背景と原因
発達障害や発達特性のある子どもには、他害行動が出やすい傾向があります。
その背景にはいくつかの理由が考えられます。
- 言葉で気持ちを伝える力が未発達
「貸してって言えない」「嫌だって言えない」 → 代わりに手が出てしまう。 - 感覚の過敏・鈍感がある
大きな音や人混みが苦手で、強いストレス反応として叩く・叫ぶことがある。 - 切り替えの難しさ
遊びをやめられない → 急に片づけと言われる → 怒って投げる。 - 自己主張や欲求表現の方法が限られている
「気づいてほしい」「思い通りにしたい」気持ちが、行動でしか出せないことも多い。
つまり、他害行動は“困っているサイン”の表れなんです。
子ども自身も実は「どうしていいか分からない」状態で、行動がエスカレートしてしまうんですね。
「他害がひどい=悪い子」ではない!困り感を理解する重要性
ここで一番大切にしてほしいのが、「他害がひどい=悪い子」ではないという視点です。
他害行動が目立つと、どうしても周囲から「乱暴な子」「しつけがなっていない」と思われがちです。
でも実際には、子どもが持つ発達の特性や困り感が行動に出ているだけなんです。
例えば、
- ことばで伝える力がまだ弱い
- 感覚に敏感で落ち着けない
- 気持ちの切り替えが苦手
こうした背景を知ると、ママ自身も「この子は困っているんだ」と受け止めやすくなります。
もちろん、だからといって他害行動を放っておいていいわけではありません。
でも、“困っている子どもを助ける”という気持ちで向き合うことが、解決への第一歩になります。
【家庭でできる】他害がひどい子どもへの対応・実践アイデア
他害行動が出ると、ママは「どうすれば止められるの?」「もう疲れた…」と感じやすいですよね。
でも、対応の仕方は必ずしも難しいものばかりではなく、家庭の中で工夫できるアイデアがたくさんあります。
ここでは「安全対策」「気持ちの伝え方」「遊びの工夫」など、毎日の生活に取り入れやすい実践的な方法を紹介します。
安全第一!家庭内でケガを防ぐ環境づくりの工夫
他害行動が起きたときに一番心配なのは、やっぱり子ども自身や兄弟姉妹がケガをしてしまうこと。
まずは「叩いた」「投げた」などの行動が起きても大きな事故にならないように、環境を整えることが最優先です。
- 角のある家具にはクッションカバーをつける
- 投げやすい物は事前に片づけておく
- 安全に落ち着ける「クールダウンスペース」を家の中に作る
といった工夫だけでも安心感がぐっと増します。
「行動をゼロにする」よりも、まずは「危なくないように備える」ことがスタートラインになります。
「言葉が出ない」を補う!気持ちを伝える代替手段アイデア
他害行動の大きな理由のひとつが、「ことばでうまく気持ちを伝えられない」こと。
そんなときは、ことばの代わりになるツールを使うのが効果的です。
- 絵カードや写真で「やりたいこと」を伝えられるようにする
- 「嫌だ!」「やめて!」を表すサインやジェスチャーを一緒に練習する
- クッションや人形を「叩いていいもの」として代わりに使う
これなら、子どもも「伝わった!」と安心できて、他害行動が減りやすくなります。
「ことばのかわりにどう伝えるか」を考えることが、ママにできる大事なサポートです。
順番を守る練習に◎ターンテイキング遊びで育つ社会性
「自分の思い通りにならないと叩いてしまう」ことってありますよね。
そんなときに役立つのが、ターンテイキング(順番を交代する遊び)です。
例えば、
- ボールを「はい、どうぞ」と交互に投げ合う
- 積み木を1つずつ積んでいく
- カードを順番にめくる簡単なゲーム
こうした遊びを通して「待つ」「譲る」「交代する」経験を重ねることで、少しずつ他害行動が減っていきます。
最初は短い時間から始めて、「できたね!」と一緒に喜ぶことが大事です。
ストレス発散に効果的!感覚遊び・体を使った活動の取り入れ方
子どもが他害行動をするとき、実は「体に余ったエネルギーをどう発散していいか分からない」ことも多いです。
そこでおすすめなのが、感覚遊びや体を使った活動。
- 粘土やスライムをこねて、手で感覚を味わう
- 水遊びや泡遊びで気持ちをリフレッシュ
- トランポリンや布団の上でジャンプして体を動かす
これらの遊びは、子どもの気持ちを落ち着ける“ガス抜き”の役割を果たします。
「叩く」代わりに「遊びで発散する」場を用意してあげると、自然と安心につながります。
リズムと音楽で落ち着きを取り戻す!簡単リトミック法
「音楽」や「リズム」には、気持ちを切り替える力があります。
発達支援でもよく使われる方法で、家庭でも取り入れやすいですよ。
- 手をつないで「いち、に、さん」と声を合わせて歩く
- 短い歌やリズムを一緒に歌ってみる
- 太鼓や手拍子でテンポを合わせる
こうした活動を繰り返すうちに、「リズムに合わせて気持ちを整える」習慣がついていきます。
難しいルールはいらないので、「楽しむ」気持ちでやるのが一番です。
「できた!」を実感できる!成功体験を積ませる仕組みづくり
他害行動が続くと、ママも「また叩いた…」とマイナスな面ばかり目に入りがちですよね。
でも子どもにとっては、「できた!」と感じる成功体験が行動改善のカギになります。
- 「今日は叩かずに待てたね!」とすぐに褒める
- ごほうびシールやカレンダーで達成感を“見える化”する
- 小さな課題(5分だけ順番を守るなど)を設定して成功を重ねる
こうすることで、子どもは「叩かなくても認めてもらえるんだ」と学んでいきます。
行動のマイナスを見るより、“できたことを増やす”視点がとても大切なんです。
👉 この実践アイデアは、次の「園や学校との連携」にもつながる内容です。
ママが家庭で工夫したことを、支援者や先生と共有すると効果がさらに大きくなりますよ。
【Q&A】他害がひどい子に関するよくある疑問と答え
子どもの他害行動については、多くのママが同じような悩みを抱えています。
ここでは、よく寄せられる質問をまとめて、できるだけわかりやすくお答えします。
「私だけじゃないんだ」と思えるきっかけになれば嬉しいです。
Q1. 他害がひどいと将来どうなる?発達と成長の見通し
「このままずっと叩いたり噛んだりするの?」と不安に思うママは多いですよね。
結論から言うと、多くの子どもは成長とともに落ち着いていくケースが多いです。
- ことばで気持ちを伝えられるようになる
- 感情のコントロール力が少しずつ育つ
- 周囲の環境調整や支援によって安心感が増える
こうした変化が重なって、他害行動は少しずつ減っていきます。
もちろんすぐに変わるわけではありませんが、「今はまだ成長の途中」と考えることが安心につながります。
Q2. 兄弟や友達にケガをさせたらどう対応すればいい?
「ケガをさせてしまったらどうしよう…」これはママにとって一番心配なことですよね。
対応の流れとしては、次のように考えると分かりやすいです。
- まずは安全確保
子どもたちを距離をとらせて、落ち着くスペースを作る。 - 相手への謝罪と説明
「今、気持ちをうまく伝えられなくて手が出てしまいました」とシンプルに伝える。 - 子どもへのフォロー
「叩くんじゃなくて『やめて』って言おうね」と、次にどうしたらいいかを教える。
完璧に防ぐことは難しいですが、事故を小さくおさえる工夫と誠実な対応が信頼につながります。
Q3. 他害=発達障害の特徴?診断の有無と相談の目安
「他害がひどい=発達障害なんでしょうか?」と心配になるママもいます。
ただ、他害行動があるからといって必ず発達障害というわけではありません。
- 成長段階で一時的に見られるケースもある
- 環境の変化やストレスがきっかけになる場合もある
- でも発達特性が関係していることも多い
診断が必要かどうかは専門家でなければ判断できません。
もし「毎日困っている」「家庭生活に大きく影響している」と感じたら、早めに相談してみるのがおすすめです。
相談することで「今の子に合った対応法」を知るきっかけになります。
Q4. 他害がひどい時に叱るのは効果的?正しい注意の仕方
つい「なんで叩くの!」と大きな声で叱りたくなりますよね。
でも実は、強く叱ることは逆効果になることが多いんです。
- 子どもがパニック状態で、話が入ってこない
- 怒られることで余計に不安が強くなる
- 「注目してもらえた」と感じて繰り返してしまうことも
正しい対応は、
- まずは落ち着かせる(安全確保+距離をとる)
- 落ち着いたあとで、「叩くんじゃなくて、やめてって言おうね」と伝える
つまり、行動を止めるだけでなく「次にどうすればいいか」を教えることが大事なんです。
Q5. 相談できる専門機関・支援先まとめ【保存版】
「一人で抱え込むのは限界…」と感じたら、専門機関に相談してみましょう。
地域によって違いはありますが、代表的な相談先は次の通りです。
- 児童発達支援センター:未就学児向けに療育や相談ができる
- 発達相談センター・子育て支援センター:自治体が運営、相談員や心理士が対応
- 小児科や発達外来:診断や医療的なサポートが必要なときに有効
- 保育園・幼稚園・学校の先生:日常での様子を共有して支援をお願いできる
- 親の会やママ向けコミュニティ:同じ経験をしている人の声が心の支えになる
「どこに行けばいいか分からない」というときは、まず自治体の子育て相談窓口に連絡するのが一番分かりやすいです。
子どもの成長とママの笑顔のために大切なこと
他害行動はママにとって本当に大きな悩みですが、将来にわたって続くとは限りません。
正しい理解と対応を積み重ねれば、少しずつ落ち着いていくことが多いです。
そして、困ったときには一人で抱え込まず、専門家や支援先に頼ることが大切。
「叱る」よりも「どうしたらよかったか」を伝えていくことで、子どもの成長につながります。
まとめ|他害がひどい子どもと向き合うために大切なこと
子どもの「叩く」「噛む」「投げる」といった他害行動は、見ているママにとって本当に大きな悩みのひとつです。
でも大切なのは、その行動の裏には必ず理由や背景があるということ。
「言葉で伝えられない」「気持ちの切り替えが難しい」「感覚が過敏でつらい」など、子どもなりの“困り感”が行動に出ていることを忘れないでください。
行動の背景を理解することが第一歩
他害行動を見ると「どうして?」「またやってしまった…」とつい表面的な行動だけに目が行きがちです。
でも、行動の奥にある子どもの気持ちや特性を理解することが、対応の第一歩になります。
理解することで「悪い子だからやっているんじゃない」と気づき、ママのイライラや罪悪感も少し軽くなります。
実践的な対応アイデア+ママ自身の心のケアが両輪
子どもの行動を落ち着けるためには、実践的なアイデア(安全な環境づくり、代替手段、感覚遊びなど)が欠かせません。
でも同時に、忘れてはいけないのがママ自身の心のケアです。
- 「できなかったこと」よりも「今日はここまでできた!」を見つける
- 一人で抱え込まずに支援者や仲間とつながる
- 時にはママ自身の休憩やリフレッシュを優先する
この2つのバランスが取れてはじめて、家庭全体が少しずつ落ち着いていきます。
「完璧じゃなくていい」ママが笑顔でいることが子どもの安心につながる
他害行動が続くと、「もっとちゃんとしなきゃ」「完璧な対応をしないと」と自分を追い込んでしまうことがあります。
でも実は、子どもにとって一番の安心は“ママが笑顔でいること”なんです。
完璧でなくても大丈夫。
「今日は叩かなかったね」「少し待てたね」と、できた瞬間を一緒に喜んであげるだけで十分なんです。
そしてママ自身が笑顔を取り戻せれば、それが子どもにとって何よりも大きな支えになります。
👉 他害行動に悩む日々は決して楽ではありませんが、一歩ずつでも工夫を重ねていけば、必ず「落ち着く瞬間」が増えていきます。この記事が、その一歩を踏み出す小さなヒントになればうれしいです。
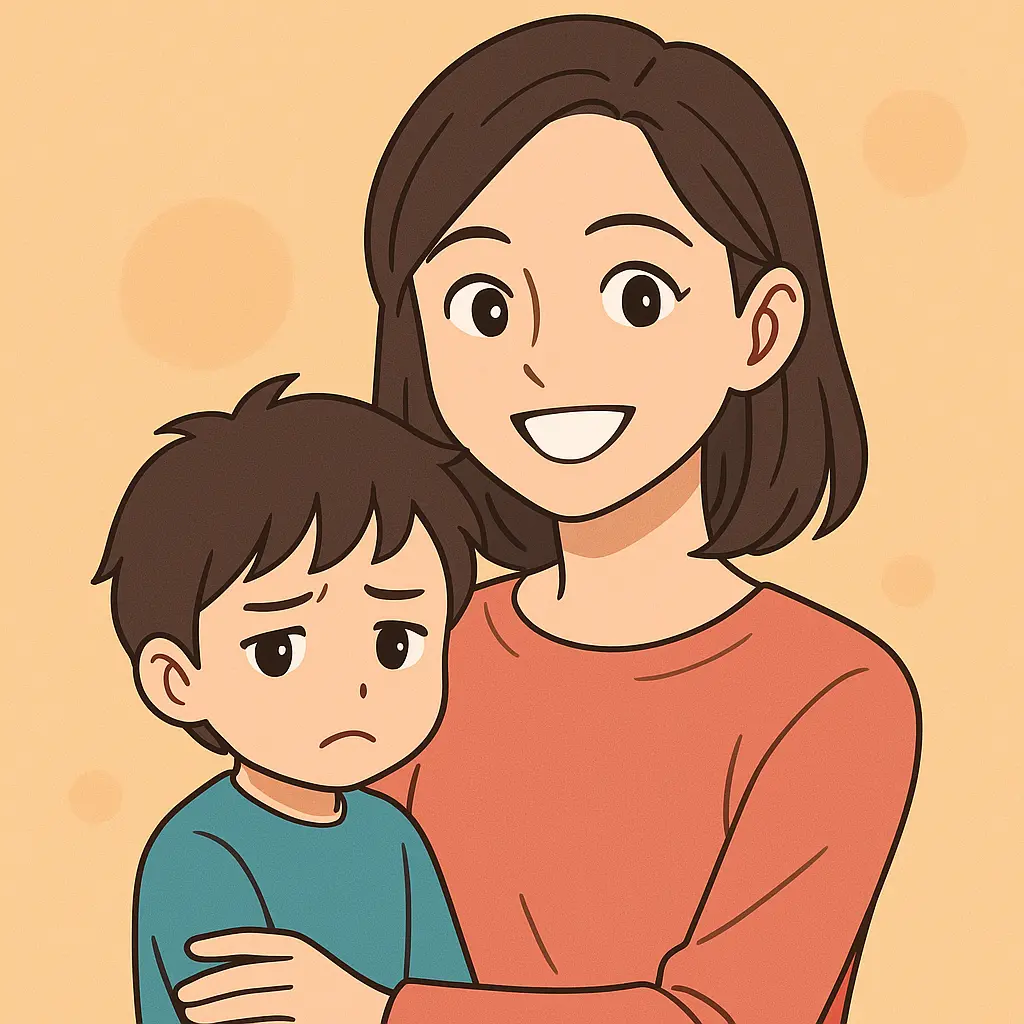
以上【他害がひどい子と向き合う!実践対応アイデアとママが笑顔になれる工夫について】でした。

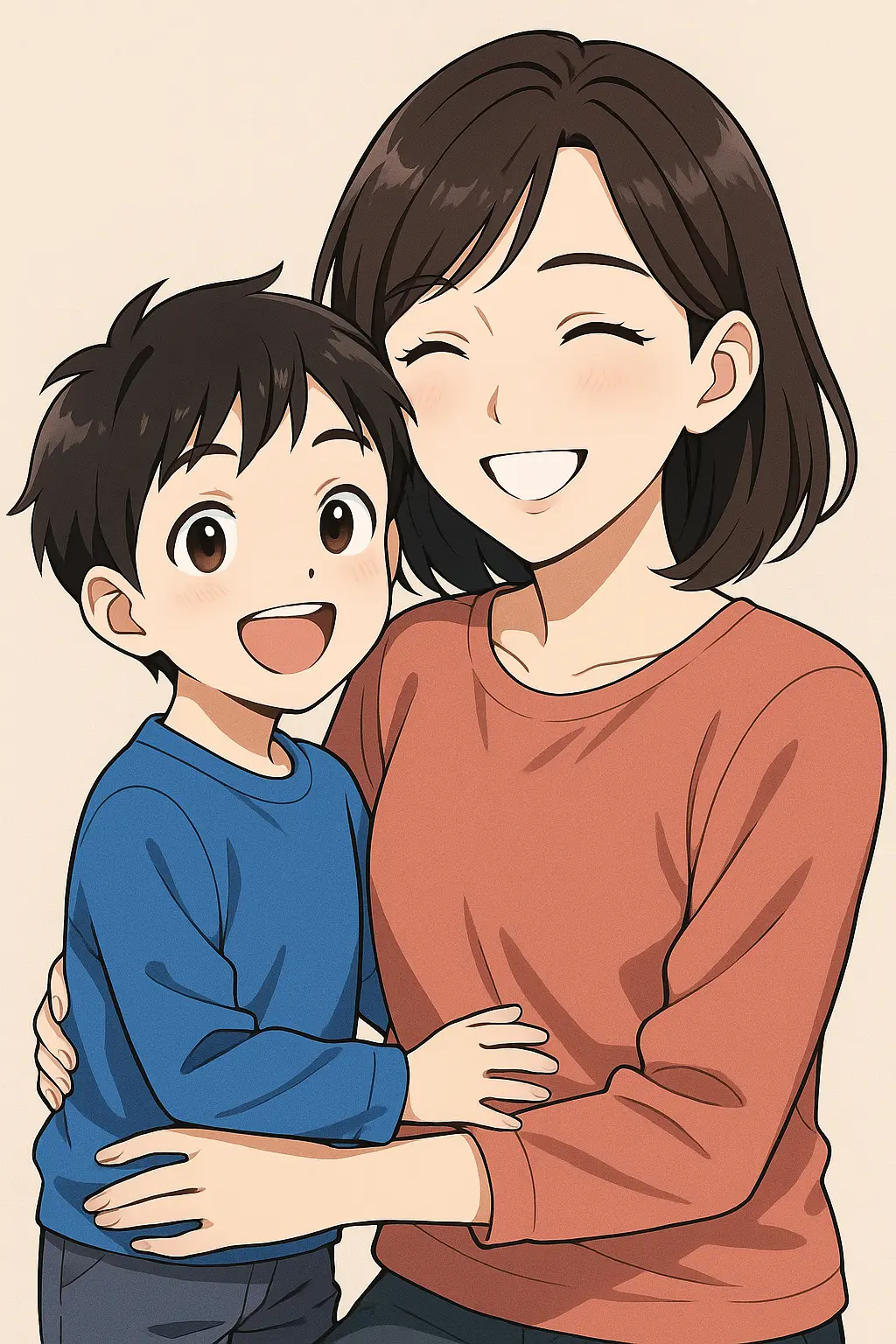









コメント