「同じ言葉を何度も繰り返す大人」を見て、家族として「どう接したらいいの?」と戸惑ったことはありませんか?
たとえば、同じフレーズをブツブツつぶやいたり、会話の中で相手の言葉をそのまま返したり…。知らない人が見れば「からかってるの?」と誤解されやすいのも事実です。
でも実はこれ、発達障害の特性のひとつとしてよく見られる行動なんです。専門用語では「エコラリア(反響言語)」と呼ばれ、本人にとっては「安心するための行動」や「言葉を理解するための工夫」だったりします。
この記事では、
- 発達障害と「同じ言葉を繰り返す行動」の関係
- 大人に見られる特徴や心理的な背景
- 家族が直面しやすい困りごと
- 家庭でできる支援方法と安心できる工夫
について、できるだけわかりやすく解説していきます。
「特性」と知ることで、ママ自身の不安も軽くなり、子育てにも役立つヒントがきっと見つかります。
発達障害と「同じ言葉を繰り返す行動」の関係性
まず知っておきたいのは、「同じ言葉を繰り返す」=発達障害だけに見られる行動ではないということ。緊張したときに独り言をつぶやく人がいるように、誰にでも似たような行動はあります。
ただし、発達障害のある人の場合、この行動が生活の中で頻繁に出やすいのが特徴です。
発達障害とは?大人にも続く特性と基本の理解
発達障害にはASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、LD(学習障害)などがあります。これらは「子どもの障害」というイメージが強いかもしれませんが、大人になっても特性は消えずに続くことがあります。
そのため、「どうして同じ言葉を繰り返すんだろう?」という疑問も、大人の発達障害を理解する大事な入り口になります。
どんなときに同じ言葉を繰り返す?よくある場面例
- 一人のときにCMのフレーズを何度も言う
- 相手の言葉をそのまま返す(オウム返し)
- 昔聞いた好きなセリフを繰り返す
こうした行動は、本人にとっては「安心」や「言葉の確認」につながっています。
【専門用語】エコラリア(反響言語)とは?
エコラリアには2種類あります。
- 即時エコラリア:相手の言葉をすぐに繰り返す
- 遅延エコラリア:過去に聞いた言葉を後になって繰り返す
発達障害のある人にとって、これは言葉を理解したり気持ちを落ち着けたりする大事な手段なんです。
発達障害で同じ言葉を繰り返す大人の特徴
「なぜ大人になっても繰り返すの?」と感じる方も多いでしょう。ここではその特徴を整理します。
特徴① 不安や緊張を和らげる「自己刺激行動」
人は緊張すると手をいじったり貧乏ゆすりをしたりしますよね。それと同じで、言葉の繰り返しが「安心のスイッチ」になっている場合があります。
特徴② 言葉の理解や記憶を助けるため
聞いた情報を頭に残すために繰り返すケースです。学生時代に「声に出して暗記」した経験はありませんか?それに近いイメージで、繰り返すことで理解を補っているんです。
特徴③ オウム返しで会話に参加
「そうなんだね」と言いたいけど、どう表現していいかわからない…。そんなとき、相手の言葉をそのまま返すことで会話に参加しようとする意思表示をしています。
特徴④ 興味やこだわりの表れ
アニメや本のセリフを繰り返すのは、自分の好きなことを共有したい気持ちから。こだわりの強さが言葉に出ているのです。
大人になっても「言葉の繰り返し」が続く理由
「子どもの頃だけかと思っていたら、大人になっても続いている」──これは珍しいことではありません。
発達障害の特性は大人になっても残る
発達障害は「治る・治らない」というより生まれ持った特性。年齢を重ねても行動のクセとして残りやすいのです。
ストレスや環境要因で増えることも
仕事のプレッシャーや家庭内の不安が強まると、繰り返し言葉が増えるケースもあります。安心できる環境づくりが大切です。
習慣として定着する
子どもの頃からの「安心のパターン」として残っている場合も多いです。
発達障害で同じ言葉を繰り返すことで起こる困りごと
周囲から誤解されやすい
「バカにしてるの?」と誤解されるのは本人にとってつらいこと。本当は会話をしたいのに、誤解されて孤立するリスクがあります。
職場や社会生活でのトラブル
会議や面接など、大事な場面で繰り返してしまうと不利になることがあります。
家族の悩みやストレス
「子どもが真似しちゃう」「やめてほしいけど言えない」といった悩みを持つママも少なくありません。
家庭でできる!発達障害の大人への支援方法
否定せずに受け止める
「やめて!」と言うと余計に不安が強まります。まずは受け止めて安心感を与えることが大切です。
環境調整で安心感をつくる
- 静かな空間
- 生活のルーティン
こうした工夫で繰り返しが減ることがあります。
言葉を広げる工夫
繰り返した言葉を少し広げて返すと、自然に会話につながることも。
例:「ご飯、ご飯」と繰り返す →「そうだね、ご飯の時間だね。今日はカレーだよ」
ストレス軽減
運動や音楽など、感覚を調整できる活動を取り入れると安心につながります。
専門家に相談する
言語聴覚士や臨床心理士など、専門の支援機関を頼るのも選択肢です。
子育てに役立つ学び
- 子どもが言葉を繰り返すとき、「大人と同じだ」と理解できる
- 家族が理解を深めることで、子育て全体の安心感が増す
発達障害と「同じ言葉を繰り返す行動」の関係性
「どうして同じ言葉を何度も言うの?」と不思議に思うこと、ありませんか?
たとえば、大人になってからも子どもの頃と同じように同じフレーズを口にしていたり、会話の中でオウム返しが多かったり…。
実はこれは、発達障害の特性と深く関係している行動なんです。
もちろん「誰にでもある行動」ではありますが、発達障害のある人の場合は、それが日常生活の一部としてよく現れることがあります。
この章では、まず発達障害の基本的な理解を押さえつつ、「同じ言葉を繰り返す行動」がどんな場面で出やすいのか、そして専門用語の「エコラリア」についてやさしく解説していきます。
発達障害とは?大人にも続く特性と基本の理解
「発達障害」という言葉、子どもに関するイメージが強いですよね。
でも実際には、発達障害は“子どもの頃だけのもの”ではありません。
発達障害には大きく分けて、
- ASD(自閉スペクトラム症):こだわりが強い、コミュニケーションが苦手など
- ADHD(注意欠如多動症):集中が続かない、忘れ物が多い、衝動的に動いてしまうなど
- LD(学習障害):読み書きや計算に特定の苦手さがある
といった種類があります。
子どものころに気づかれずに大人になり、社会に出てから初めて「生きづらさ」として表れるケースも少なくありません。
そしてその特性のひとつとして現れやすいのが、「同じ言葉を繰り返す行動」なんです。
どんなときに同じ言葉を繰り返す?よくある場面例
「同じ言葉の繰り返し」といっても、場面はいろいろです。
たとえばこんなこと、心当たりはありませんか?
- 一人でいるときに、CMやドラマのセリフをつぶやく
- 誰かと会話していて、相手の言葉をそのまま返す(オウム返し)
- 昔から好きなフレーズを繰り返し口にする
- 緊張したときに同じ言葉をブツブツ繰り返す
一見すると「なんでそんなことをするの?」と不思議に思うかもしれません。
でも、本人にとっては 「安心する」「頭を整理する」「相手と関わろうとする」 などの大事な意味があります。
つまりこれは単なるクセではなく、その人なりのコミュニケーションや気持ちを落ち着ける方法なんですね。
【専門用語】エコラリア(反響言語)とは?種類と特徴
繰り返し言葉を使う行動には、専門的に「エコラリア(反響言語)」という名前があります。
エコラリアには大きく2つの種類があります。
- 即時エコラリア:相手が言った言葉をすぐに繰り返す
→ 例:「今日は暑いね」→「暑いね」
この場合は、会話に参加する合図や理解を確認する行動になっています。 - 遅延エコラリア:昔聞いた言葉やフレーズを後になって繰り返す
→ 例:小さい頃に好きだったアニメのセリフを、大人になっても口にする
この場合は、安心したいときのセルフケアや好きなことを表現する手段になっていることが多いです。
発達障害のある人にとって、この「エコラリア」は生活を支える大切な機能なんです。
「変なクセ」ではなく、その人にとって必要なコミュニケーション方法と考えると、受け止めやすくなるのではないでしょうか。
発達障害で同じ言葉を繰り返す大人の特徴
「どうしてこんなに同じ言葉を繰り返すんだろう?」と感じたことがあるかもしれません。
実は、発達障害のある大人が同じ言葉を口にする背景には、いくつかの理由や特徴があります。
ここでは代表的な4つを紹介します。
特徴① 不安や緊張を和らげる「自己刺激行動」
発達障害のある人にとって、言葉を繰り返すことは「心を落ち着けるための行動」になることがあります。
これを「自己刺激行動(セルフスティミュレーション)」とも言います。
たとえば、
- 緊張する場面で手をモジモジする
- イライラすると貧乏ゆすりをする
これらは誰にでもある行動ですが、発達障害のある人はその代わりに「言葉の繰り返し」を安心のスイッチとして使うことがあるのです。
つまり、繰り返すこと自体が「リラックス法」の一つ。
「落ち着きたいから言葉を繰り返しているんだ」と理解するだけで、見え方が変わってきます。
特徴② 言葉の理解や記憶を助けるために繰り返すケース
「大事なことは声に出して覚える」って、誰でもやったことがありますよね。
同じように、発達障害のある大人も情報を整理するために言葉を繰り返すことがあります。
例えば…
- 「10時に集合」と言われたら、頭の中で「10時、10時」とつぶやく
- 新しい言葉を聞いたときに何度も口にする
これは単なるクセではなく、理解や記憶を助ける大切な方法なんです。
繰り返すことで「なるほど、こういう意味なんだな」と頭に定着させているのです。
つまり、繰り返しは「頭の中のノート取り」のようなもの。
本人にとって学びやすくする工夫と考えるとわかりやすいでしょう。
特徴③ オウム返しで会話に参加するコミュニケーション方法
「オウム返し=からかっている」と思われることがありますが、実はその逆。
「会話に参加したい」というサインの場合が多いんです。
たとえば、
- Aさん:「今日は寒いね」
- Bさん:「寒いね」
この場合、Bさんは「そうだね」と返す代わりにオウム返しをしているだけかもしれません。
本人なりに「会話に参加していますよ」という気持ちを表しているのです。
特に、発達障害のある人は「自分の言葉で返す」ことが難しい場合があります。
だからこそ、オウム返しがコミュニケーションの入り口になっているのです。
家族としては「会話したい気持ちはあるんだな」と受け止めてあげると良いですね。
特徴④ 興味・こだわりが強く表れる言葉の繰り返し
発達障害のある人は、自分の好きなことやこだわりを強く持っていることが多いです。
そのため、好きな言葉やフレーズを何度も繰り返すことがあります。
たとえば、
- 好きなアニメのセリフを繰り返す
- 昔から気に入っているフレーズを何度も口にする
これも「変なクセ」ではなく、大好きなものを共有したい気持ちや安心感から来ています。
「好きだから繰り返す」──とてもシンプルで、人間らしい行動なんです。
子どもが好きな歌を何度も口ずさむのと同じように、大人でも“こだわりの言葉”を繰り返すことがあると考えると理解しやすいでしょう。
必要な理由があるということ。
この視点を持つと、家族としての接し方もきっと変わっていくはずです。
大人になっても「言葉の繰り返し」が続く理由
「子どもの頃だけかと思っていたのに、大人になっても同じ言葉を繰り返している…」
そんな姿を見ると、家族として少し不安になることもありますよね。
でも実はこれは珍しいことではなく、発達障害の特性として自然に続いている場合が多いんです。
ここでは、大人になっても「言葉の繰り返し」が見られる主な理由を3つ紹介します。
発達障害の特性は大人になっても残る
発達障害は「子どものときにだけあるもの」ではなく、生まれ持った脳や神経の特徴です。
ですから、年齢を重ねても特性がゼロになるわけではありません。
もちろん、大人になると経験を積んで工夫ができるようになったり、繰り返す頻度が減ったりする人もいます。
でも完全に消えるというよりは、「その人の性格や行動の一部として残り続ける」のです。
たとえば、
- 子どもの頃からオウム返しが多かった人は、大人になっても同じ傾向が出やすい
- 小さい頃に好きだったセリフを、大人になっても繰り返して安心する
このように、特性が大人になっても形を変えて表れることがあります。
ストレスや環境要因で増える言葉の繰り返し
大人になると、子どもの頃よりも人間関係や仕事などでストレスを感じる場面が増えますよね。
そのストレスが強まると、安心したい気持ちが高まり、言葉の繰り返しが出やすくなることがあります。
たとえば、
- 職場でプレッシャーを感じると、同じ言葉を口にして落ち着こうとする
- 家庭でトラブルがあると、昔から好きなフレーズを何度も言って安心しようとする
つまり、言葉の繰り返しは「心を守るセーフティネット」のような役割を果たしているんです。
また、安心できる環境が整うと不思議と繰り返しが減ることもあります。
「行動そのもの」よりも「環境との関係性」に注目すると理解しやすいですね。
習慣化したコミュニケーションスタイルとして定着
繰り返し言葉を使うことが、長い年月をかけて「その人なりの会話スタイル」になっているケースもあります。
たとえば、
- 会話で返答に困ったとき、とりあえず相手の言葉を繰り返す
- 家族とのやり取りの中で、同じフレーズが合言葉のように使われる
このように、繰り返し言葉は「変えられないクセ」というよりも、習慣化した表現方法になっているんです。
もちろん、周囲から見ると「会話になっていない」と感じることもあります。
でも本人にとっては、「会話に参加するための自然な方法」であり、「安心感のあるやり取り」でもあるのです。
発達障害で同じ言葉を繰り返すことで起こる困りごと
「同じ言葉を繰り返す」という行動は、本人にとっては安心や理解を助ける大切なもの。
でも、残念ながら周囲から誤解されやすい行動でもあります。
その結果、学校や職場、家庭など、いろんな場面で困りごとにつながることがあります。
ここでは「よくある困りごと」を3つに分けて整理してみましょう。
周囲からの誤解や「会話が成り立たない」と思われる悩み
まず一番多いのは、周囲からの誤解です。
たとえば相手の言葉をオウム返しすると、
「からかっているの?」
「ちゃんと話を聞いていないの?」
と受け取られてしまうことがあります。
でも実際には、「会話に参加したい」「理解しようとしている」サインであることが多いんです。
ただ、周囲がその意味を知らないと、会話が続かず「意思疎通ができない人」と思われてしまうことも…。
本人は悪気がないのに、誤解が重なって孤立感を強めてしまうケースがあります。
ここで大事なのは、繰り返し言葉にも“意味”があることを家族や周りが知っておくこと。
それだけで、誤解を減らして「会話のきっかけ」に変えられることもあるのです。
職場や社会生活での人間関係トラブル
大人になると、言葉の繰り返しは社会生活に直結する困難を生みやすくなります。
例えば、
- 会議で同じフレーズを繰り返してしまい、仕事が進まないと誤解される
- 面接や商談で繰り返しが出て、「不自然な人」と思われてしまう
- 職場で「話が通じない」と見られ、人間関係に溝ができる
このように、本人の意図とは違う形で不利になってしまうことがあるんです。
ただしここでも大切なのは、繰り返すこと自体が悪いわけではないということ。
本当は「安心して働ける環境」や「理解のある人間関係」があれば、困りごとはぐっと減らせるのです。
家族が抱えるストレスや子育てへの影響
家庭内でも、言葉の繰り返しは家族にとって悩みの種になることがあります。
よくあるのはこんな声です。
- 「何度も同じことを聞かれるから疲れてしまう」
- 「子どもが真似をして困っている」
- 「どう反応すればいいのかわからない」
繰り返し自体は悪いことではありませんが、毎日となるとママにとって負担になるのも自然なことです。
また、子どもが成長するにつれて「お父さん(お母さん)の行動を真似してしまうのでは?」という心配も出てきますよね。
ここで大事なのは、「困っているのは本人だけではなく、家族も同じ」という視点を持つこと。
家族が抱えるストレスを「小さな工夫」や「外部の支援」で軽くしていくことが、長い目で見るととても大切になります。
家族が“行動の背景”を知ることこそ、支援の第一歩になるのです。
家庭でできる!発達障害の大人への支援方法
「同じ言葉を繰り返す」こと自体は悪いことではありません。
むしろ本人にとっては、安心したり頭を整理するための大事な行動なんです。
でも、家族として「どう接したらいいの?」と悩む場面もありますよね。
ここでは、家庭の中で今日からできる支援方法を具体的に紹介します。
否定せずに受け止める|安心感を与える接し方
まず大切なのは、「否定しないで受け止める」ことです。
「また同じこと言ってるの!」「やめなさい!」と強く言うと、本人はますます不安になります。
繰り返しは安心するための行動なので、それを奪ってしまうと逆効果になってしまうんです。
代わりに、
- 軽くうなずく
- 「そうだね」と共感する
- 必要なら別の話題につなげる
といった対応をすると、本人も落ち着きやすくなります。
安心感を与えることが一番の支援になると覚えておきましょう。
環境調整で安心できる暮らしをつくる工夫
繰り返しの言葉は、不安や緊張から出やすくなります。
だからこそ、家庭の環境をちょっと整えるだけで、安心して過ごせる時間が増えるんです。
例えば…
- 予定をカレンダーに書いて見える化する
- 家の中に「静かに落ち着ける場所」を用意する
- 生活のリズムを一定にする
こうした「環境の工夫」は、本人の安心だけでなく、家族全体の落ち着きにもつながります。
言葉を広げる会話練習|繰り返しから自然な対話へ
同じ言葉を繰り返したとき、ただスルーするだけでは会話が広がりません。
でもちょっと工夫するだけで、自然な会話のきっかけにできます。
例:
本人:「ご飯、ご飯」
家族:「そうだね、ご飯の時間だね。今日はカレーだよ」
こんなふうに、繰り返した言葉に「情報」をプラスして返すことで、会話がキャッチボールになっていきます。
子どもとのやり取りにも応用できるので、ぜひ試してみてください。
ストレス軽減の工夫|趣味・運動・音楽の活用法
言葉の繰り返しは、ストレスがたまったときに増えることがあります。
だからこそ、ストレスを減らす工夫も支援のひとつです。
たとえば、
- 好きな趣味の時間を大切にする
- 軽い運動を取り入れる(散歩やストレッチでもOK)
- 音楽を聴いてリラックスする
特に音楽は、感覚を整えたり気持ちを落ち着けたりする効果があるのでおすすめです。
家族で一緒に楽しめば、コミュニケーションの時間にもなりますよ。
専門家のサポートを取り入れる|相談先と活用方法
「家庭だけで抱え込まないこと」も大切です。
繰り返しの行動が強くて困るときや、家族が疲れてしまったときは、専門家に相談してみるのも良い方法です。
相談できる先は…
- 言語聴覚士(ことばの専門家)
- 臨床心理士やカウンセラー
- 発達障害者支援センター
- 自治体の相談窓口
専門家に相談することで、家庭での工夫や本人に合った支援方法を一緒に考えてもらえます。
「相談するのは大げさかな?」と思うかもしれませんが、実際には早めに相談するほうが家族の安心につながることが多いです。
できることから少しずつ取り入れるだけで、本人も家族もラクになるんです。

子育てに役立つ「大人の繰り返し言葉」から学べること
「同じ言葉を繰り返す」行動って、どうしてもネガティブに見られがちですよね。
でも実は、大人の繰り返し言葉を理解することが、子育てにもプラスになるヒントになるんです。
繰り返す理由や背景を知ることで、子どもの行動に対する見方も変わってきますし、家族全体の関係性も良くなります。
ここでは、子育てに役立つ視点を紹介します。
子どもの言葉の繰り返し理解にもつながるヒント
子どももよく「同じ言葉」を繰り返しますよね。
例えば、「ママ、ママ」「バナナ、バナナ」など。
大人と同じように、子どもにとっても繰り返しには安心感や自己表現の意味があります。
もし大人の繰り返し言葉を理解していれば、
「子どももきっと同じように気持ちを整えているんだな」
と捉えられるようになります。
つまり、大人の繰り返し言葉を知ることは、子どもの行動を理解する“手がかり”になるんです。
また、「ただ繰り返しているだけ」ではなく、
- 不安を落ち着けたい
- 言葉を覚えたい
- 会話に入りたい
といった意図が隠れていることにも気づきやすくなります。
そうすると、子どもへの声かけやサポートがより的確になりますよ。
家族全体の安心感と肯定的な子育てへの効果
繰り返し言葉を「困ったこと」ではなく、「一つの特性」や「工夫のしかた」として理解できると、家族の雰囲気も変わります。
「また同じこと言ってる」とイライラする代わりに、
「そうか、安心したいんだね」「言葉を使って頑張ってるんだな」
と受け止められるようになるんです。
このように家族の中で否定せずに肯定的に受け止める習慣が育つと、子育てにも大きなプラス効果があります。
- 子どもが安心して自分を表現できる
- 家族の中で「受け止めてもらえる」という信頼感が生まれる
- 育児のストレスが少し和らぐ
結果的に、子どもも親も「安心して過ごせる家庭環境」が整うんです。
よくある質問(Q&A)
Q1: 繰り返しが多いのは病気のサイン?
まず安心していただきたいのは、「同じ言葉を繰り返す=すぐに病気」ではないということです。
発達障害の特性の一つとして見られることはありますが、必ずしも深刻な病気を意味するわけではありません。
例えば、大人でも「考えごとをするときに同じフレーズを口にする」ことってありますよね。
それと似ていて、心を落ち着けたり、頭の中を整理したりするために繰り返しているケースも多いんです。
ただし、繰り返しが 本人や周囲の生活に強く影響している場合(仕事が進まない、人間関係が悪化するなど)は、発達障害や心の状態が関係している可能性もあります。
そのときは専門家に相談してみると安心です。
Q2: 子どもが真似して困るときの対処法は?
子どもは身近な大人の言葉をよく真似しますよね。
特に繰り返し言葉は耳に残りやすく、自然と口に出てしまうこともあります。
もし「同じことばかり言って困るな」と感じたら、まずは否定せずに受け止めることが大切です。
「ダメ!」と強く止めると、子どもが余計に不安になってしまうことがあります。
代わりに、違う言葉を楽しく提案するのがおすすめです。
例えば、子どもが「ママ、ママ」と繰り返しているときに、
「そうだね、ママはここにいるよ。じゃあ一緒に『パパ』って言ってみようか」
と声をかけてみるなど。
繰り返し自体を否定するのではなく、言葉を広げてあげるサポートを意識すると安心です。
Q3: 仕事に支障がある場合の改善策は?
大人が繰り返し言葉を口にしてしまうと、職場で「会話が成り立たない」と誤解されることもあります。
そんなときは、環境やストレス要因を見直すことが改善につながります。
- メモや付箋を使って言葉に出す回数を減らす
- 深呼吸やストレッチで気持ちを切り替える
- 信頼できる同僚や上司に特性を理解してもらう
こうした工夫で、少しずつ繰り返しが減ったり、職場での誤解が減ったりすることがあります。
また、発達障害の特性に理解のある職場を選ぶことも大切です。
最近では就労支援やカウンセリングを取り入れている会社も増えてきていますよ。
Q4: 医療機関や発達相談を受ける目安は?
「これって普通なのかな?」と不安になったら、早めに相談するのが安心です。
特にこんな場合は、一度医療機関や相談窓口を利用してみましょう。
- 繰り返しが止まらず、日常生活に支障が出ている
- 強い不安やストレスとセットで現れている
- 家族や職場での人間関係に影響している
相談することで「病気かどうか」だけでなく、その人に合った工夫や支援方法を教えてもらえるのが大きなメリットです。
Q5: 支援機関や相談窓口の探し方は?
「どこに相談したらいいの?」と迷ったときは、まず身近なところから始めるのがおすすめです。
- 市区町村の発達支援センターや保健センター
- 病院の精神科・心療内科・発達外来
- 就労支援サービスや発達障害者支援センター
インターネットで「発達障害 支援 センター +(地域名)」で検索すると、地域ごとの窓口が見つかります。
また、子どもの発達相談に対応している機関でも、大人の相談を受け付けてくれる場合があります。
一人で抱え込む必要はありません。
支援機関をうまく活用することは、家族にとっても安心できる大きな一歩になりますよ。
✅ まとめると:
繰り返し言葉はすぐに「病気」と結びつける必要はありません。
ただ、生活や仕事に影響している場合は、早めに相談&環境調整が安心につながります。
否定ではなく理解が大切!家族にできる寄り添い方
「同じ言葉を繰り返す」行動は、決して悪いことや恥ずかしいことではありません。
それは発達障害の特性のひとつであり、同時に「安心したい」「気持ちを落ち着けたい」という心のサインでもあるのです。
だからこそ、家族が「なんでこんなことばかり言うの?」と否定するのではなく、
「そうか、安心したいんだね」と受け止めて理解してあげる姿勢がとても大切になります。
もちろん、繰り返し言葉があると生活の中で困ることも出てきます。
でも、そんなときには 家庭でできる小さな工夫(安心できる環境づくり、会話を広げる練習、ストレスを減らす方法など)を取り入れることで、ぐっと楽になることがあります。
さらに、必要なときには専門家のサポートを受けることも大切な選択肢です。
相談することで「こうしたらもっと楽に過ごせますよ」という具体的なアドバイスが得られるので、本人にとっても家族にとっても安心につながります。
そして忘れてはいけないのは、この経験が子育てにも活かせるということ。
大人の「繰り返し言葉」を理解することは、子どもの行動を受け止めるヒントにもなり、家族全体の安心感を育ててくれます。
つまり、「同じ言葉を繰り返す」行動は困りごとであると同時に、支援や理解を深めるきっかけでもあるんです。
家族が否定せず寄り添っていくことで、本人も安心して過ごせるようになり、結果的に子育てや家族関係にもプラスの循環を生み出してくれますよ。
以上【発達障害で同じ言葉を繰り返す大人|特徴・原因・家庭でできる支援方法まとめ】でした。

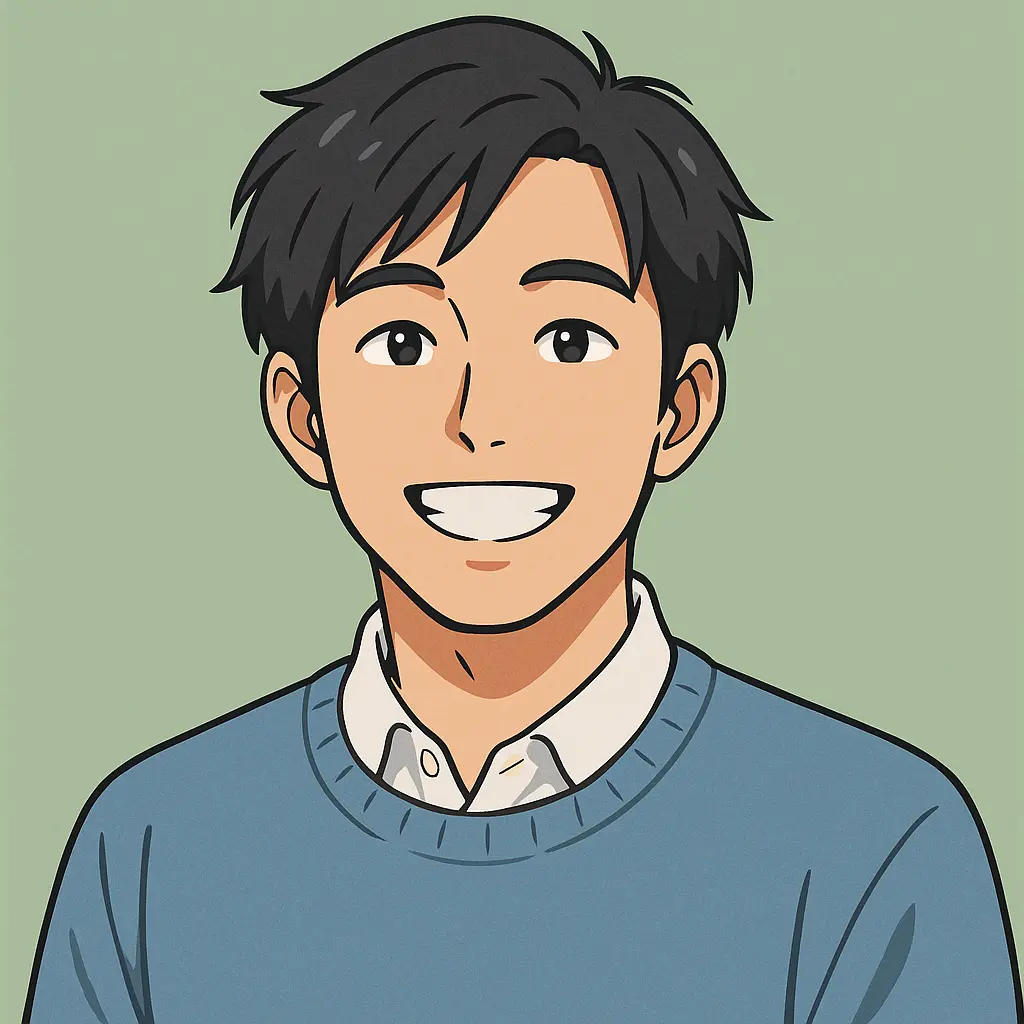









コメント