自閉症は大人になってから診断されることもある
「自閉症」と聞くと、多くの方は子どものうちにわかるものと思いがちですよね。
でも実際には、大人になってから初めて診断を受ける人も少なくありません。
これは決して珍しいことではなく、最近ではよく耳にするようになってきました。背景には、昔と今とで「発達障害の理解度」や「診断基準」が変わってきたことがあります。
つまり、子どもの頃には「ちょっと変わってる子」と思われて終わってしまっていた人が、大人になってから「これは自閉症の特徴だったんだ」と気づくケースが多いんです。
子どもの頃に自閉症と診断されなかった理由とは?
では、なぜ子どもの頃に診断されなかった人がいるのでしょうか?
大きく分けて、いくつかの理由があります。
- 昔は発達障害の理解が今ほど進んでいなかった
- 今でこそ「発達障害」という言葉が広く知られていますが、20年〜30年前は一般的な認知度が低く、「自閉症スペクトラム」という概念もあまり浸透していませんでした。
- そのため、特性があっても「性格の問題」や「しつけの問題」と捉えられることが多かったのです。
- 症状が軽くて目立たなかった
- 自閉症にはとても幅広いグラデーションがあります。
- コミュニケーションが苦手でも、学力が高かったり、周囲に合わせる力があったりすると、違和感が見過ごされやすいのです。
- 環境によって隠れてしまった
- 家族がとても理解的で、生活が特性に合っていた場合、「困りごと」が表面化しにくいことがあります。
- 逆に、進学や就職などで環境が変わると一気に生きづらさが強まることも。
要するに、子どもの頃に診断されなかったのは「親が悪い」とか「先生が気づかなかったから」ではなく、時代背景や環境による影響が大きかったんです。
今、大人になってから発達障害に気づく人が増えている背景
最近になって「大人になってから診断を受けた」という声をよく耳にするようになりました。これにはいくつかの理由があります。
- 社会全体で発達障害への理解が広がった
- 学校やメディアで発達障害に関する情報が増え、一般の人も「そういう特性があるんだ」と知るようになりました。
- その結果、「もしかして自分も?」と気づく大人が増えています。
- 診断や検査が受けやすくなった
- 発達障害外来や専門クリニックが増えてきて、以前よりも相談のハードルが下がりました。
- インターネットで情報を調べて受診につながる人も多いです。
- 子育てをきっかけに自分を振り返る人が多い
- 子どもが発達検査を受けたことで、「実は自分も似たところがある」と気づくママ・パパが少なくありません。
- 「子どもの特性を理解しようとしたら、自分自身の特性にも気づいた」という流れですね。
つまり、大人になってから気づく人が増えたのは、隠れていた特性が見えるようになったからとも言えるのです。
【体験談】自閉症 大人になってから気づいた人の声
「子どもの頃からちょっと周りと違うな」と感じていたけれど、はっきりとした理由はわからないまま成長した…。
そんな経験を持つ人が、大人になってから「これは自閉症の特性だったんだ」と気づくケースは少なくありません。
ここでは、実際に聞かれる体験談をもとに、幼少期・学生時代・社会人になってからのエピソードを紹介します。
読むことで「うちの子も似てるかも」と気づいたり、「大人になっても大丈夫なんだ」と安心できたりすると思いますよ。
幼少期にあった“違和感”のリアルエピソード
多くの人が「子どもの頃からちょっと違った」と振り返ります。
- 一人遊びが好きで、友達と遊ぶのが苦手だった
周りが鬼ごっこをしているのに、ブロックや電車遊びばかりしていた、という声が多いです。
本人にとっては楽しい時間なのに、「どうして一緒に遊ばないの?」と大人から指摘されることもありました。 - 感覚に敏感すぎた
洋服のタグや靴下のゴムがどうしても嫌で泣いてしまう、運動会のピストルの音で耳をふさいでしまう…。
周囲には理解されにくく、「わがまま」や「神経質」だと思われがちでした。 - 強いこだわりがあった
毎日同じお皿でごはんを食べたい、ぬいぐるみを決まった順番に並べないと落ち着かない…。
子どもにとっては安心できる習慣ですが、大人からすると「不思議なこだわり」に映ったようです。
こうした幼少期の特徴は、後から振り返ると「自閉症のサイン」と気づく人が多いのです。
学生時代に見られた特徴と生きづらさ
小学校・中学校・高校と進むにつれて、周囲との違いがさらに大きくなっていきます。
- 友達関係が続かない
会話が一方的になってしまったり、冗談が通じなかったりして、気づいたらグループから外れていた。
本人は悪気がないのに、「変わった子」と言われて孤立することもありました。 - 集団行動が苦手
体育祭や合唱コンクールなど「みんなで同じことをする」場面がとても苦痛だったという声は多いです。
指示があいまいだと混乱し、「どうしてできないの?」と怒られる体験を繰り返してしまうことも。 - 勉強の得意不得意が極端
数学は得意だけど国語は苦手、暗記は得意だけど作文が書けない…といった“学習の凸凹”が表れやすいのも特徴です。
「努力不足」と誤解されることで、自己肯定感が下がることもありました。
こうした経験は、ママたちが「子どもが学校に馴染めない」と悩む場面と重なるかもしれませんね。
社会人になってから気づいた発達障害のサイン
大人になって社会に出ると、子どもの頃には隠れていた困難が一気に表面化することがあります。
- 職場での人間関係がうまくいかない
報告や相談のタイミングがわからない、雑談が苦手、上司のあいまいな指示に対応できない…。
こうした困難が重なって「働きづらい」と感じる人が多いです。 - 臨機応変さが求められる場面でパニックに
予定外の仕事や突然の変更が入ると混乱し、頭が真っ白になる。
子どもの頃からの「予定変更が苦手」という特性が、大人になっても続いているのです。 - 強いストレスから心身の不調に
人間関係や仕事のプレッシャーから、うつや不安障害を発症し、その過程で検査を受けたら「自閉症スペクトラム」と診断されたというケースも少なくありません。
こうした流れから、「大人になってから初めて自分の特性を知った」という人が増えているのです。
自閉症 大人になってから気づく人の「子どもの頃の違和感」とは?
大人になってから「自分は自閉症かもしれない」と気づいた人に話を聞くと、ほとんどの人が「子どもの頃から違和感はあった」と振り返ります。
ただし、その違和感は周りにとっては「性格の一つ」や「ちょっと変わった子」と見られてしまい、特性として理解されにくいものでした。
ここでは、よく聞かれる「子どもの頃の違和感」をいくつかの視点から紹介します。ママにとっても「うちの子も当てはまるかも」と気づきやすい部分だと思います。
友達関係・コミュニケーションの苦手さ
自閉症の特性を持つ子どもは、人との関わり方に独特のスタイルを持っていることがあります。
- 一人で遊ぶのが好き
周りの子が鬼ごっこやごっこ遊びをしていても、自分はブロックや本の世界に夢中…。
本人にとってはとても楽しい時間なのに、大人からは「どうして友達と一緒に遊ばないの?」と見られてしまうことも。 - 会話のキャッチボールが続かない
質問されても一言で終わってしまう、あるいは逆に自分の興味のあることを延々と話してしまう。
悪気があるわけではなく、相手の気持ちを読むのが難しいだけなんです。 - 空気が読みにくい
周囲の雰囲気や暗黙のルールがわからず、「変な子」「マイペースすぎる」と思われることもありました。
このように、人との距離感や関わり方の違いは、周囲から誤解されやすいポイントでもあります。
感覚過敏・偏食など日常生活での特徴
多くの人が口にするのが、「感覚の強さ」や「食のこだわり」です。
- 音や光への敏感さ
運動会のピストルの音が苦手で耳をふさいで泣いてしまう、蛍光灯の光がまぶしくて頭が痛くなる…。
周囲にはわかりにくいけれど、本人にとってはとてもつらい感覚なんです。 - 服のタグや靴下のゴムがイヤ
「かゆい」「チクチクする」と着替えを嫌がることもよくあります。
親からすると「わがまま?」と思いやすいですが、これは立派な感覚過敏のサイン。 - 偏食の強さ
白いご飯しか食べない、同じ形のパンしか食べないなど、食べ物へのこだわりも特徴のひとつです。
実はこれも味覚や触感に敏感すぎることが影響しています。
日常の中で「どうしてこんなことにこだわるの?」と思う部分が、後から見れば自閉症の特徴だったということも多いのです。
強いこだわりやマイルールの存在
自閉症の子どもにとって、「自分なりのルール」や「安心できる手順」はとても大切です。
- 毎日同じルーティンを繰り返したい
朝ごはんは同じお皿、寝る前は必ず同じ絵本を読む…。
これが崩れると不安になってしまい、泣いたり怒ったりすることもあります。 - 物を並べたり、順番にこだわる
車のミニカーを色ごとに並べる、ブロックを大きさ順に並べないと気が済まない。
大人からすると「なんでそんなことに?」と不思議に思うかもしれませんが、本人にとっては安心する行動なんです。 - 予定が変わると混乱する
遠足が雨で中止、授業が急に変更…そんな時にパニックになりやすいのも特徴です。
この「こだわり」は、子どもにとっての安心材料であり、周囲が理解して支えてあげることがとても大切です。
言葉の使い方や理解に見られる偏り
言葉の面でも「ちょっと違うな」と感じるエピソードがよくあります。
- 冗談やあいまいな表現がわからない
「ちょっと待っててね」と言われると、時間を文字通りに受け止めて延々と待ち続けてしまうことも。
周りからは「融通がきかない」と誤解されがちです。 - 独特な話し方
本で読んだ表現をそのまま使ったり、大人びた言葉を使ったり…。
大人からすると「賢いね」と思うけど、同年代の友達からは浮いてしまうこともあります。 - 相手の気持ちを想像するのが難しい
相手が退屈そうにしていても気づかずに話し続けるなど、「気持ちのキャッチボール」が難しいこともあります。
こうした言葉の特徴も、子どもの頃には「ちょっと変わってるね」で済まされることが多いですが、大人になって振り返ると「これも自閉症のサインだった」と理解されるのです。
親世代が知っておきたい「発達障害に気づく視点」
子どもの発達を見守っていると、「もしかしてうちの子、ちょっと違う?」と感じる瞬間がありますよね。
実はそれ、親自身の過去とつながっていることもあるんです。最近では「子どもの発達をきっかけに、自分の特性に気づいた」という親御さんも増えています。
ここでは、親世代が知っておくと安心できる「気づきの視点」や「支援の工夫」を紹介します。
子育てを通して「自分もそうだった」と気づくケース
発達障害は遺伝的な要素も関わるといわれています。そのため、「子どもの特性が、自分の子ども時代と似ている」と感じるママ・パパは少なくありません。
- 「自分も小さい頃は友達が作りにくかった」
- 「人前で話すのが苦手だった」
- 「音や光に敏感で、よく困っていた」
こうした経験を思い出すと、「あの時の困りごとは、発達特性が原因だったのかもしれない」と気づく人もいます。
一方で、「自分もそうだったけど、大人になれたから大丈夫」と前向きに考えられる場合もあれば、「自分は苦労したから、子どもには同じ思いをさせたくない」と不安になる場合もあります。
どちらにしても大切なのは、「親の経験が子どもの理解に生かせる」という視点を持つことです。自分の体験は、子どもをサポートするヒントになります。
子どもを支えるために大切な“環境調整”とは?
発達障害のある子どもを育てるうえで欠かせないのが、“環境調整” です。
これは「子どもの特性を変える」ことではなく、子どもが安心して過ごせる環境を整えることを意味します。
例えば――
- 見通しをもたせる工夫
スケジュール表やイラストを使って「次に何をするのか」を視覚的に示すことで、不安が減ります。 - 感覚に配慮する工夫
音が苦手な子にはノイズキャンセリングイヤーマフを使う、服のタグを切る、照明を落ち着いたものにするなど。 - 安心できるルーティンを守る
いつも同じ順番で行動できるようにすると、落ち着いて過ごせます。
環境調整の良いところは、「子どもの特性を否定せずに、そのまま受け入れる支援ができる」こと。
これは子どもの自己肯定感を守るうえでも、とても大切です。
学校や家庭でできる発達障害の支援アイデア
発達障害の支援というと専門的に聞こえますが、実は家庭や学校でできる工夫もたくさんあります。
- 家庭でできる工夫
- 朝の準備をイラストでチェックリスト化する
- 食べられるものを尊重しながら、少しずつ食の幅を広げていく
- 子どもの「好き」にとことん付き合ってあげる
- 学校でできる工夫(先生と共有したいポイント)
- 授業中の指示はできるだけ具体的にしてもらう
- 大きな音が苦手なら、体育館の席を端にしてもらう
- 休み時間の過ごし方をあらかじめ決めておく
こうした支援のアイデアは、「子どもを困らせないため」ではなく「子どもが安心して力を発揮できるようにするため」の工夫です。
ほんの少しの工夫で、子どもの学校生活や家庭での暮らしがぐっとラクになることも多いんです。
大人になってから自閉症と診断された人の体験談
「自閉症って子どもの頃にわかるものじゃないの?」と思う方も多いですよね。
でも実際には、大人になってから診断を受けて初めて自分の特性に気づいたという人も少なくありません。
そのきっかけは人によってさまざまです。
職場での生きづらさ、子育てを通しての気づき、体調を崩したことがきっかけで受診したケース…。
ただ共通しているのは、「診断を受けてから生き方が変わった」という声が多いことです。
ここでは、実際によく聞かれる体験談をいくつかの角度からご紹介します。
診断を受けて安心できた人たちの声
まず多いのは、「診断を受けてホッとした」という声です。
- 「今まで“自分はダメだ”と思っていたけど、特性があるから仕方なかったんだとわかって気持ちが軽くなった」
- 「ずっと原因不明の生きづらさを感じてきたけど、理由がはっきりしただけで安心できた」
このように、診断は“ラベルを貼ること”ではなく、「自分を理解するための手がかり」になります。
自己理解が深まることで、無理に周りに合わせるのではなく、自分に合った暮らし方を見つけやすくなるんです。
家族や職場の理解が進んでラクになった体験
診断を受けたことで、家族や職場が「特性」として理解してくれるようになったというケースも多いです。
- 「家族に“怠けている”と誤解されていたけど、“特性だから仕方ない”と受け止めてもらえた」
- 「職場で上司に相談したら、仕事内容を調整してくれて働きやすくなった」
特に職場では、診断があることで配慮を受けやすくなるケースがあります。
たとえば、静かな場所で仕事をさせてもらえる、口頭指示ではなくメールで指示してもらえるなど。
このように、診断は“周囲に理解を求めるためのパスポート”のような役割を果たすこともあります。
支援を受けて前向きに生きられるようになった事例
大人になって診断を受けると、支援につながるチャンスも広がります。
- 就労支援を活用したケース
「一般企業でつらかったけど、就労支援のある職場に変わったら安心して働けるようになった」 - カウンセリングや発達障害向けプログラムの活用
「専門のカウンセラーに話を聞いてもらうことで、気持ちの整理ができた」
「自分の得意・不得意を一緒に整理してくれる支援員さんがいて心強い」 - 当事者コミュニティに参加
「同じ特性を持つ仲間とつながれたことで、“自分だけじゃない”と前向きになれた」
このように、診断をきっかけに支援やコミュニティと出会い、安心して生活できる人が増えているのです。
子育て中のママに伝えたい「安心のメッセージ」
子育てをしていると、「なんで他の子と同じようにできないんだろう…」と心配になる瞬間、きっと誰にでもありますよね。
でも、大人になってから自閉症に気づいた人たちの体験談を聞くと、「違和感=問題」ではないことがよくわかります。
ここでは、子どもを育てているママにぜひ届けたい安心のメッセージをまとめました。
子どもの違和感=問題ではないという考え方
まず伝えたいのは、「子どもの違和感=すぐに問題というわけではない」ということです。
- 「集団行動が苦手」
- 「音や服の感覚に敏感すぎる」
- 「好きな遊びばかりしている」
こうした特徴は、周囲から「困りごと」に見えるかもしれませんが、実際には子どもの特性や個性の一部でもあります。
大人になってから自閉症に気づいた人の中には、子どもの頃に同じような特徴を持っていたけれど、環境や出会いによって力を発揮できる場を見つけた人がたくさんいます。
だからこそ、ママが覚えておいてほしいのは、
「違和感を見つけたときは問題視するのではなく、“どう支えられるかな”と考えることが大切」という視点です。
自閉症 大人になってから気づいた人の成功体験に学ぶ
「自閉症 大人になってから気づいた人」の中には、自分の得意分野を活かして成功している人も多くいます。
- 研究やクリエイティブな分野で活躍
こだわりの強さや集中力を武器に、研究職やデザインの世界で才能を発揮している人もいます。 - 趣味を仕事に変えたケース
子どもの頃から夢中になっていた鉄道やプログラミングが、そのまま大人になってからの仕事につながった例もあります。 - 「人とは違う視点」を強みにできた人
周囲と違う感覚や発想を持っていたことが、逆に社会で必要とされる能力になった人もいます。
このように、発達の特性は弱点ではなく、育て方や環境によっては「強み」に変わるのです。
子どもの未来を考えるとき、「大人になってから成功している人がたくさんいる」という事実は、ママにとって安心材料になりますよね。
発達支援センターや相談窓口の活用法
とはいえ、子育ての中で不安をひとりで抱え込むのはとても大変です。
そんなときに頼れるのが、発達支援センターや相談窓口です。
- 発達支援センター
子どもの発達に関する相談や、専門家によるアドバイスが受けられます。
早期に支援をつなげることで、子どももママも安心して過ごせます。 - 地域の子育て支援窓口
市町村の保健センターや教育相談室などでも、発達に関する相談を受けています。 - 専門医やカウンセラー
必要に応じて発達検査や診断を受けることもできますし、親の気持ちを整理するカウンセリングも役立ちます。
ここで大切なのは、「困ってから相談する」ではなく「ちょっと気になるなと思ったら気軽に相談していい」ということです。
相談するだけでも心がラクになることは多いですし、支援につながることで子育てがぐっとスムーズになることもあります。
まとめ|大人になってから自閉症に気づく人の体験談が教えてくれること
ここまで見てきたように、大人になってから自閉症に気づく人の体験談は、今子育てをしているママにとって大きなヒントになります。
なぜなら、その人たちが振り返る「子どもの頃の違和感」こそが、親にとっての“気づきの種”になるからです。
「友達と遊ぶより一人遊びを好んだ」
「音や光が苦手だった」
「予定変更に強いストレスを感じていた」
こうしたエピソードは、ママが日々感じる“ちょっと気になるな”と重なることも多いですよね。
でも、それをすぐに「将来が不安」と決めつける必要はありません。
子どもの違和感は「将来の不安」ではなく「成長のサイン」
ママに覚えておいてほしいのは、子どもの違和感は必ずしも“問題”ではないということです。
むしろ、「成長のサイン」や「特性の現れ」であることが多いんです。
- 感覚に敏感 → 音楽や芸術で才能を発揮することも
- こだわりが強い → 研究やものづくりに集中力を生かせる
- 一人で遊ぶのが好き → 自分の世界を大事にできる力になる
つまり、違和感は「欠点」ではなく、子どもが持っている“伸びる芽”かもしれません。
それを理解できると、ママの心も少しラクになりますよね。
親も子どもも安心して暮らせる社会資源や支援があることを知ってほしい
そしてもうひとつ大切なのは、ママも子どもも安心して暮らせるサポートがちゃんとあるということです。
- 発達支援センターや療育施設
- 地域の子育て支援窓口
- 専門医やカウンセラー
- 当事者や保護者同士がつながれるコミュニティ
これらの社会資源を活用すれば、子どもに合った支援を受けられるだけでなく、ママ自身も安心できます。
「一人で抱え込まなくていい」ということを、ぜひ知っておいてください。
大人になってから自閉症に気づいた人たちの声は、ママにとって「未来はきっと大丈夫」という安心を与えてくれます
- 子どもの違和感を不安の種にするのではなく、成長のヒントに変えていけること。
- そして、親子を支えてくれる社会資源があること。
この2つを知っているだけで、子育ての見え方は大きく変わりますので、「子どもはきっと大丈夫」という気持ちを忘れずに、毎日の子育てを続けていってくださいね。

以上【自閉症 大人になってから気づく人たちの体験談|子どもの頃に見逃されやすい違和感と特徴】でした。

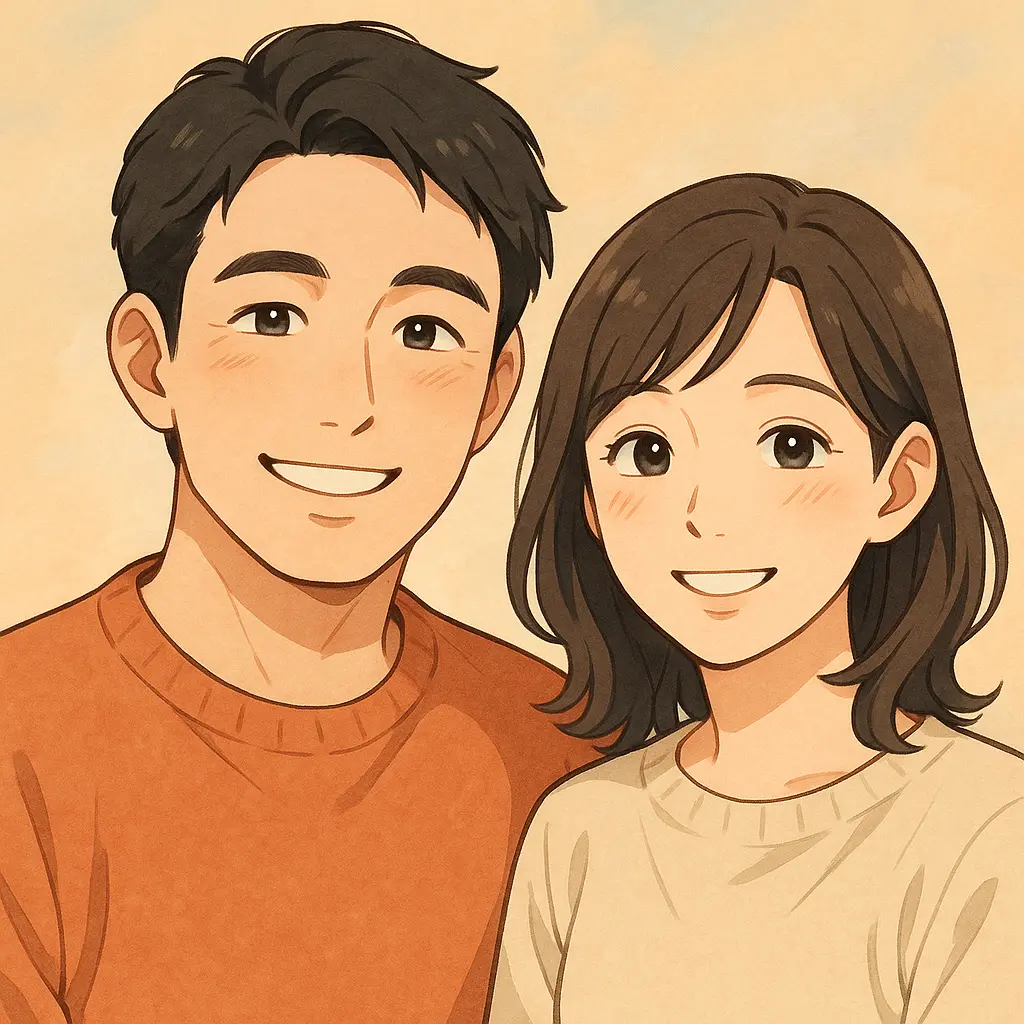









コメント