自閉症の癇癪とは?発達障害の子どもに多い特徴を理解しよう
自閉症の子どもが起こす癇癪(かんしゃく)は、一般的な子どものぐずりやイヤイヤと少し違います。
「なんでこんなに強く怒るの?」「どうしてこんなに長く続くの?」と戸惑うママも多いと思います。
でも、まず大切なのは 「癇癪=わがまま」ではなく「子どもが困っているサイン」 だと理解すること。
ここを押さえておくと、ママの気持ちも少しラクになり、対処の仕方も見えてきます。
自閉症の子どもと一般的な癇癪の違い
どんな子どもでも、欲しいものが手に入らなかったり、思い通りにならなかったときに癇癪を起こすことはあります。
ただし、自閉症の子どもの癇癪はそれとは少し性質が違うんです。
- 一般的な癇癪:要求が通ると比較的すぐに収まることが多い
- 自閉症の癇癪:理由が複雑で、要求が通ってもなかなか落ち着かないこともある
たとえば「音が大きくてつらい」「予定が急に変わった」「気持ちを言葉で伝えられない」など、本人の中にある “感覚や理解の困難さ” が原因になっていることが多いんです。
癇癪が起こる原因|感覚過敏や予測困難との関係
自閉症の子どもに癇癪が多い理由のひとつが 感覚の過敏さ。
音・光・におい・肌に触れる服の素材など、大人には気にならないことが子どもにとっては大きなストレスになってしまいます。
また、予測できないことへの不安 も大きな原因です。
「次に何が起こるかわからない」「急に予定が変わった」といった状況が強い不安を引き起こし、癇癪につながります。
さらに、言葉で思いをうまく表現できないことも要因のひとつ。
「言いたいけど言えない」「わかってほしいのに伝わらない」——このギャップが強い frustration(フラストレーション)になり、爆発してしまうのです。
癇癪が出やすいシーン(日常生活・園や学校・外出先)
癇癪はどんな場面でも出る可能性がありますが、特に出やすいのは次のようなシーンです。
- 日常生活:朝の支度、食事のとき、お風呂や寝る前などの切り替え時
- 園や学校:集団行動で周囲に合わせる必要があるとき、騒がしい環境
- 外出先:人混みや大きな音、慣れない場所に行ったとき
つまり、「環境の変化」や「見通しのなさ」が癇癪の引き金になりやすいということ。
ママが少し先回りして準備することで、癇癪の回数をぐっと減らせる ケースも多いんです。
癇癪は「困っているサイン」だと理解する大切さ
ここで一番大事なのは、もう一度お伝えしたいこと。
癇癪は「困っているよ」という子どもからのサイン だということです。
「うちの子はすぐ癇癪を起こして困る」ではなく、
「うちの子は“困っているから”癇癪を起こす」と考えてみる。
そうすると、ママの心の負担が軽くなるだけでなく、
「じゃあどうしたら困らない環境をつくれるかな?」と 前向きな対応 に変えやすくなります。
癇癪をゼロにするのは難しいですが、理解することで子どもに寄り添いやすくなり、結果的に落ち着く場面が増える。
その積み重ねが、ママにも子どもにも安心につながります。
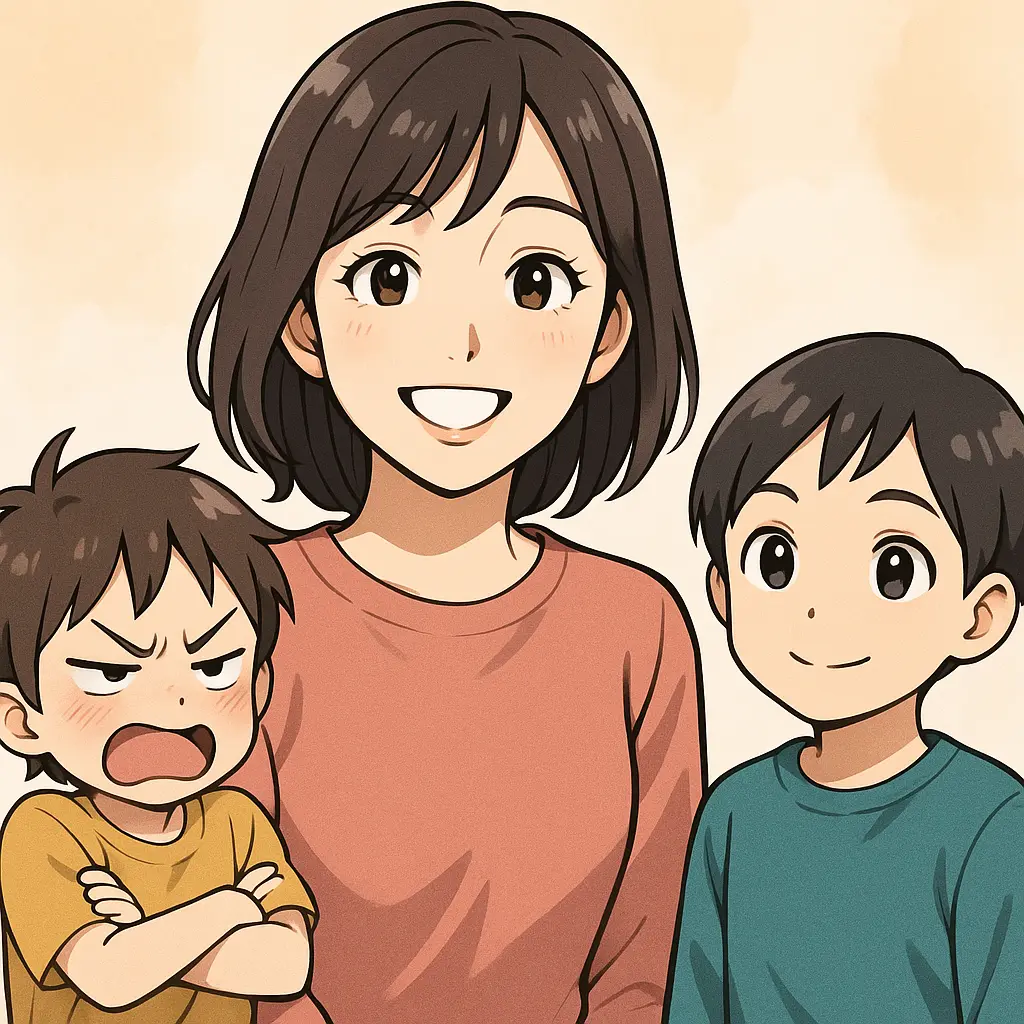
自閉症の癇癪が起こる原因|よくある5つの要因
自閉症の子どもが癇癪を起こすとき、その背景にはいくつか共通する要因があります。
「うちの子だけ特別なんだろうか?」と感じるママも多いですが、実は多くのご家庭で同じような状況が見られています。
ここでは、癇癪のよくある5つの原因 をわかりやすく整理してみましょう。
環境要因(音・光・においなどの感覚過敏)
自閉症の子どもは、感覚がとても敏感 なことがあります。
たとえば、掃除機やトイレの乾燥機の音にパニックを起こしたり、蛍光灯のチラつきや強い光に耐えられなかったりすることも。
また、スーパーのにおいや、人混みでのざわざわした声がストレスになることもあります。
大人にとっては「ちょっと気になる」程度でも、子どもにとっては我慢できないくらい強烈な刺激になるんです。
だからこそ、環境要因を減らしてあげる工夫(イヤーマフを使う、照明を調整する、静かな場所を選ぶ)が癇癪の予防につながります。
言葉の遅れやコミュニケーションの難しさ
「お腹がすいた」「もうやめたい」「これが欲しい」——本当は伝えたいことがあるのに、うまく言葉にできない。
この “伝えたいのに伝わらない” frustration(フラストレーション) が、癇癪の大きな原因になることがあります。
ママが気づかないうちに、子どもは「どうしてわかってくれないの!」という気持ちでいっぱいになり、それが爆発してしまうんです。 この場合は、絵カードやジェスチャーなど言葉以外の方法で伝えられる手段を用意してあげると、癇癪の回数がぐっと減ることもあります。
予定変更やこだわりによる不安や混乱
自閉症の子どもは、予定や順序が変わることがとても苦手です。
「今日は公園に行くって言ったのに急にやめた」「お風呂の順番を変えられた」——これだけで強い不安や混乱が生まれ、癇癪につながります。
また、「この道じゃなきゃイヤ!」「この順番で遊ばないとダメ!」といったこだわりもよく見られます。
大人から見ると「そんなことくらいで…」と思うことでも、子どもにとってはとても大事なこと。 予定変更があるときは、できるだけ早めに伝える・視覚的に説明するなどの工夫で安心感を持たせてあげることが大切です。
空腹・疲れなど身体的なコンディション
意外と見落としがちなのが、身体的なコンディションです。
お腹がすいているとき、眠いとき、体調が悪いときに癇癪が出やすくなるのは、大人でも同じですよね。
自閉症の子どもは「お腹がすいたからご飯が食べたい」とうまく伝えられず、結果として大きな癇癪になってしまうことがあります。
ママが気づいたときには「もう爆発してから…」というケースも多いので、こまめな休憩やおやつ、水分補給を意識することが予防につながります。
癇癪の前ぶれを知る!ママのためのチェックリスト
癇癪は突然起こるように見えて、実は前ぶれのサインが出ていることが多いです。
ママがそれに気づけると、爆発する前に手を打つことができます。
チェックしておきたい前ぶれの例はこんな感じです
- 落ち着きなくソワソワし始める
- 表情がこわばってくる
- うつむいて無言になる
- 手を強く振ったり、耳をふさいだりする
- 好きなおもちゃや行動に執着が強くなる
こうしたサインをキャッチできれば、「ちょっと静かな場所に移動しよう」「予定をカードで見せよう」など早めの対応ができて、癇癪を防げる可能性が高まります。
【今すぐできる】自閉症の癇癪を落ち着かせる対処法
癇癪が起こったとき、ママは「どうしたらいいの?」と焦ってしまいますよね。
でも実は、ちょっとした工夫で 子どももママも安心できる対応 があるんです。
ここでは「今すぐ試せる」具体的な方法をまとめてご紹介します。
まずは安全を守る!ケガを防ぐ環境づくり
癇癪が始まったときに最優先すべきは、子どもと周りの安全です。
頭を床に打ちつけたり、物を投げたりすることもあるので、危険な物はできるだけ手の届かない場所に。
- 角のある家具にはクッションカバー
- 投げられそうな物はあらかじめ片づけておく
- 床にマットを敷いておく
こうした工夫で、癇癪の最中でも大きなケガを防ぎやすくなります。
気持ちを受け止める声かけフレーズ集
癇癪のときに叱ってしまうと、子どもの気持ちはさらに混乱してしまいます。
大切なのは、「気持ちはわかるよ」と受け止めてあげること。
たとえばこんなフレーズがおすすめで
- 「びっくりしたね」
- 「いやだったんだね」
- 「いまはつらいんだね」
「でもダメ!」と否定するのではなく、まずは気持ちに寄り添う。
それだけで子どもが少しずつ落ち着きを取り戻すことがあります。
視覚支援グッズで安心感を与える(絵カード・スケジュール)
言葉だけで説明しても伝わりにくいことが多いのが自閉症の子どもの特徴です。
そこで役立つのが 視覚支援グッズ。
- 「次は何をするか」がわかる 絵カードやスケジュール表
- タイマーや砂時計を使って「あと何分」を見える化
こうしたアイテムがあると、子どもは先の見通しが持てるので安心できます。
「もう少しで終わるんだ」と理解できれば、癇癪も落ち着きやすくなります。
クールダウンできる「落ち着くスペース」の作り方
子どもが気持ちをリセットできる「安心できる場所」をつくるのも効果的です。
たとえば…
- テントやカーテンで仕切った小さなスペース
- お気に入りのぬいぐるみや毛布を置いたコーナー
- 静かに過ごせるソファやクッション
この「クールダウンスペース」があると、子どもは自分から「落ち着こう」と動けるようになります。
「逃げ場がある」と思えること自体が安心につながるんです。
感覚統合に効くグッズ(イヤーマフ・重みブランケット)
癇癪のきっかけに多いのが「感覚過敏」。
それを和らげるアイテムもたくさんあります。
- イヤーマフ:大きな音をやわらげて安心できる
- 重みブランケット:体に適度な圧をかけて落ち着きを促す
- スピナーやストレスボール:手を動かすことで気持ちが切り替わる
子どもによって効果のあるものは違いますが、お気に入りの“お助けアイテム”を一つ見つけておくと癇癪のときに役立ちます。
癇癪中に絶対避けたいNG対応
つい焦ってやってしまいがちなのが、逆効果になる対応です。
たとえば…
- 大声で叱る → 子どもの不安や怒りがさらに増える
- 無理やりやめさせる → 身体的な抵抗につながる
- 長々と説得する → 言葉が多すぎて理解できずパニック
癇癪中は「理屈を理解できる状態ではない」ことを忘れずに。
安全の確保と気持ちの受け止めを最優先にしましょう。
ママ自身が冷静さを取り戻すための呼吸法と工夫
癇癪のときに一番消耗するのは、実はママの心と体です。
イライラや焦りで対応すると、子どもにもその気持ちが伝わってしまいます。
おすすめなのは 「深呼吸で自分を落ち着かせる」こと。
- ゆっくり鼻から吸って、口から長く吐く
- その間は「いまは嵐の時間、必ずおさまる」と自分に言い聞かせる
また、子どもが落ち着いたあとに 「自分の気持ちを整えるルーティン」(コーヒーを飲む・音楽を聴くなど)を用意しておくのも大切です。
ママが落ち着けることが、子どもにとっても安心材料になります。
癇癪を減らすための環境づくり|家庭でできる予防法
癇癪は「起きてから対応する」よりも、「起きにくい環境をつくる」ことがとても大切です。
ちょっとした工夫で子どもが安心できれば、癇癪の頻度をぐっと減らすことができます。
ここでは、家庭でできる予防法をいくつか紹介します。
見通しを持てる生活(タイマー・予定表の活用)
自閉症の子どもは、「次に何が起こるか」が見えにくいと不安になります。
そこで役立つのがタイマーや予定表です。
- キッチンタイマーや砂時計で「あと◯分」を見える化
- 絵カードや写真で一日の流れを提示
- ホワイトボードに予定を書き出す
これらを使うことで「突然の切り替え」が減り、子どもは安心して過ごせます。
「先のことがわかる=心が落ち着く」、これは癇癪予防の大きなポイントです。
睡眠・食事・休憩で生活リズムを整える
大人も寝不足や空腹だとイライラしますよね。子どもも同じで、生活リズムが乱れると癇癪が出やすくなります。
- 毎日同じ時間に寝る・起きる
- 食事やおやつの時間を決めておく
- 疲れる前にこまめに休憩を入れる
特に自閉症の子どもは体内リズムが乱れやすいため、規則正しい生活を意識することが癇癪予防につながるんです。
小さな選択肢を与えて「自己決定感」を育てる
「やりたいことが選べない」「全部決められてしまう」ことも、子どもにとってはストレスです。
そこで効果的なのが 「小さな選択肢」を与えること。
- 「赤い服と青い服、どっちにする?」
- 「先にお風呂?ごはん?」
- 「ジュースはリンゴ?オレンジ?」
こうして少しずつ自分で選べるようにすると、「自分で決められた!」という満足感が生まれます。
この感覚があると癇癪が減りやすくなりますよ。
感覚過敏への対策グッズ(耳栓・サングラス・肌着)
感覚過敏の子には、ちょっとした刺激が大きなストレスになります。
そんなときは、グッズで環境を調整してあげるのも効果的です。
- 耳栓・イヤーマフ:大きな音をやわらげる
- サングラスや帽子:強い光から守る
- タグのない肌着ややわらかい素材の服:チクチクを防ぐ
こうしたアイテムがあると、「安心できる条件」が増えるので、癇癪のきっかけを減らせます。
外出先で役立つ!癇癪予防アイテム5選
外出は癇癪が起きやすいシーンのひとつ。だからこそ、“持ち歩けるお助けアイテム”があると安心です。
おすすめはこの5つ
- イヤーマフや耳栓(騒音対策)
- お気に入りのおもちゃやスピナー(気持ちの切り替え用)
- 小さなお菓子や水筒(空腹・喉の渇きを防ぐ)
- タブレットや音楽プレーヤー(安心できる刺激を与える)
- 小さなブランケットやハンカチ(落ち着く感覚刺激)
外で癇癪が始まりそうになっても、“いつもの安心アイテム”があると子どもは気持ちを切り替えやすくなります。
遊びながら癇癪を減らす療育アイデア(リトミック・感覚統合遊び)
癇癪を防ぐためには、日常の中で「気持ちを切り替える力」や「感覚を調整する力」を育てていくのも大切です。
おすすめは 遊びながらできる療育アプローチ。
- リトミック:音楽に合わせて体を動かすことでリズム感と自己表現が育つ
- 感覚統合遊び:トランポリン、ブランコ、ボールプールなどで体を動かすと、感覚の偏りがやわらぐ
- やりとり遊び:ボールの投げ合いや順番ゲームで「待つ・交代する」経験を積む
これらを繰り返すことで、癇癪を起こしにくい土台作りができるんです。
年齢別の癇癪対処法|幼児期から思春期までの工夫
癇癪はどの年齢でも見られますが、子どもの発達段階によって原因や出方、対応の仕方は変わってきます。
「小さいときは毎日のように大変だったけど、小学生になったらまた違う困りごとが…」というママの声も多いです。
ここでは、年齢ごとに癇癪への対応ポイントを整理してみましょう。
未就学児(2〜6歳)の癇癪対応ポイント
この時期は「イヤイヤ期」とも重なるので、癇癪が一番多い年代ともいえます。
特に自閉症の子どもは「言葉で伝えられない」「見通しが立てにくい」ことから癇癪が頻発します。
対処のポイントは…
- 視覚支援:絵カードやスケジュールで「これから何をするか」を見せる
- 安心できるルーティン:毎日の流れをできるだけ同じにする
- 短い言葉で伝える:「ダメ!」より「おしまい」「あとでね」のようにシンプルに
幼児期は「安心できる環境」と「言葉以外の伝え方」を工夫することで、癇癪が少しずつ落ち着いていきます。
小学生(6〜12歳)に合った対処法と支援の工夫
小学生になると、集団生活が中心になります。
ここで増えるのが 「学校や友達との関わりでの癇癪」です。
たとえば…
- 授業中に集中できない
- 先生の指示が曖昧で混乱する
- 友達とトラブルになりやすい
この時期の対処法は、家庭だけでなく 学校と連携することが大切です。
- 担任の先生に子どもの特性を伝える
- 「できること・苦手なこと」を共有してもらう
- 家ではリラックスできる時間を意識的につくる
小学生期は「学校で頑張って疲れて帰ってくる」ことが多いので、家では安心して気持ちを解放できる場を用意することがママの支えになります。
思春期(12歳以降)に増える癇癪と対応方法
思春期になると、「小さい頃より落ち着いてきた」という子もいますが、逆に 反抗期と重なって癇癪が強くなるケースもあります。
この時期の癇癪の特徴は…
- 「自分の気持ちをわかってほしい」という強い欲求
- 身体が大きくなることで癇癪が激しく見える
- 感情のコントロールが難しく、親子で衝突しやすい
対応のポイントは、幼児期や小学生期のように「直接的に止める」よりも、対等なコミュニケーションを意識することです。
- 気持ちを否定せず、話を聴く
- ルールを一緒に決める
- 落ち着いたときに次の方法を考える
思春期は「親がコントロールする」よりも、子ども自身が自分をコントロールできるように支えることが大切になります。
きょうだいへの影響とフォローの仕方
癇癪が激しいと、どうしても きょうだいが巻き込まれることがあります。
「お兄ちゃんばかり大変で、私のことは見てもらえない」と下の子が感じてしまうケースも珍しくありません。
フォローの工夫としては…
- 上の子が癇癪を起こしているときは、下の子を安心できる場所に避難させる
- 下の子だけと過ごす特別な時間を意識的につくる
- 「あなたも大切に思っているよ」と気持ちを言葉で伝える
また、きょうだいに「お兄ちゃん(お姉ちゃん)はこういう特徴があるんだよ」とわかりやすく説明することも効果的です。
きょうだい関係を良好にすることは、家族全体の安心感につながります。
癇癪は年齢とともに変化していきます。
「幼児期は環境を整える」「小学生期は学校との連携」「思春期は対等な関係」「きょうだいフォローも忘れない」——この視点を持っていると、ママの対応がずっとラクになりますよ。
癇癪対応で疲れたママのセルフケア方法
癇癪が続くと、子どもだけでなくママの心もすり減ってしまいます。
「私がもっと頑張らなきゃ」と思うほど、心も体も疲れてしまい、悪循環になってしまうことも…。
でも忘れないでほしいのは、ママ自身の元気が子どもの安心につながるということ。
ここでは、癇癪対応で疲れたママが自分をリセットできるセルフケアの方法を紹介します。
癇癪対応のストレスを減らすリセット習慣
毎日のように癇癪に向き合っていると、ストレスが積もって爆発しそうになりますよね。
そんなときに役立つのが「リセット習慣」です。
- 深呼吸を3回して気持ちを整える
- 子どもが寝た後に好きな音楽を聴く時間をつくる
- 家事は手を抜いて「今日はお弁当やお惣菜でOK」と割り切る
小さな習慣でも、続けることでストレスを軽くする効果があります。
家族や周囲に頼る!支援を得るための工夫
「自分が全部やらなきゃ」と思う必要はありません。
むしろ 誰かに頼ることも立派な育児スキルです。
- パパに具体的にお願いする(「ちょっと見てて」ではなく「10分抱っこしててね」と伝える)
- 実家や親せきにヘルプを頼む
- 一時保育やファミリーサポートなどのサービスを利用する
ママが休むことで、子どもも安心して育つ環境が整うんです。
同じ悩みを持つママとのつながり(ピアサポート・SNS活用)
「自分だけが大変なのかな」と感じると、孤独感が強くなりますよね。
そんなときは、同じ悩みを持つママとのつながりが大きな支えになります。
- 発達障害児の親の会やオンラインコミュニティ
- SNSで共感し合える仲間を見つける
- 地域の子育て支援センターで交流する
「わかるよ、その気持ち」という共感は、ママの心を軽くしてくれる魔法の言葉です。
「罪悪感」を手放すための考え方
癇癪対応の中で、「つい怒鳴ってしまった」「もっと優しくできたら…」と落ち込むことはありませんか?
でも、それはママが頑張っている証拠です。
大切なのは「完璧なママ」ではなく、「子どもにとって安心できる存在」であること。
- できなかったことより、できたことに目を向ける
- 「また明日やり直せばいい」と思う
- 自分を責める代わりに「今日はここまでやった」と認める
罪悪感を手放すことが、ママの笑顔につながり、子どもの安心にもなるんです。
相談できる専門機関・支援サービスまとめ
「一人で抱え込むのは限界…」と思ったら、専門機関に相談するのも大切です。
- 児童発達支援センター:未就学児を対象にした療育支援
- 発達相談窓口(市区町村):発達の心配を気軽に相談できる
- スクールカウンセラー・特別支援コーディネーター:学校生活でのサポート
- 医療機関(小児精神科・発達外来):診断や医療的なケア
専門家と一緒に考えることで、新しい対応法や安心できる支援を得られることがあります。
癇癪と長く付き合うために|発達支援と家庭での工夫
癇癪は「今日からゼロにできます!」というものではなく、子どもの成長と一緒に少しずつ変わっていくものです。
だからこそ「どうやって長く付き合っていくか」が大切になってきます。ここでは、成長に合わせた工夫や支援の取り入れ方について紹介します。
子どもの成長で変化する癇癪の特徴
癇癪の出方は、年齢や発達段階によって少しずつ変わります。
- 幼児期は「泣き叫ぶ・寝転がる」といった全身を使った表現
- 小学生になると「言葉での反発」や「物に当たる」といった行動
- 思春期になると「イライラが長く続く」「自分の殻に閉じこもる」ことも
このように、成長とともに癇癪の形が変わるので、ママも対応をアップデートしていくことが必要です。
感情表現やコミュニケーション力を育てる方法
癇癪の背景には「言葉にできない気持ち」があることが多いです。
そこで役立つのが、気持ちを表現するトレーニング。
- 「怒った」「悲しい」「楽しい」など感情カードで遊ぶ
- 日記や絵で気持ちを表す練習をする
- 家族が普段から「今ちょっと疲れたな」「嬉しいな」と自分の気持ちを口にする習慣を持つ
感情を言葉にできるようになると、癇癪の爆発が減る可能性が高まります。
ソーシャルストーリーや絵本での支援アイデア
「どう行動すればいいか」を伝えるのに役立つのがソーシャルストーリー(短い物語形式で社会的なルールや場面を説明する方法)です。
- 例:「スーパーで欲しいお菓子が買えないとき」の物語を作る
- 「我慢したあとに待っているごほうび」をイラストで見せる
- 絵本を読み聞かせて、登場人物の気持ちを一緒に考える
物語の形にすると、子どもが自然に理解しやすくなるんです。
学校や園と連携する際に伝えるべきこと
家庭だけで頑張る必要はありません。学校や園と協力することが、子どもの安心につながります。
- 癇癪が起こりやすい場面(例:運動会、給食の時間)
- 落ち着く方法(例:静かな場所に行く、絵カードを見る)
- 家庭で実践している工夫(例:タイマーを使った声かけ)
先生に具体的に伝えることで、子どもに合ったサポートをしてもらいやすくなるんです。
専門的な療育・支援サービスを利用するメリット
療育や専門サービスを利用すると、ママ一人では思いつかないような工夫を取り入れることができます。
- 療育センター:遊びや活動を通して社会性を育てる
- 言語聴覚士や作業療法士:コミュニケーションや感覚過敏のサポート
- 放課後デイサービス:学校帰りの安心できる居場所
専門家と一緒に考えることで、家庭での対応がぐっとラクになり、子ども自身も安心して成長できるんです。
実体験から学ぶ!自閉症の癇癪対応の成功例と失敗例
ママが悩む「癇癪対応」は、正解がひとつではありません。子どもによって効く方法も違えば、思わぬ失敗をしてしまうこともあります。ここでは、実際にあった成功例と失敗例を紹介しながら、「なるほど、こうすればいいんだ」「これは気をつけたほうがいいな」と参考にしていただける内容をまとめました。
【成功例】視覚支援で癇癪が減ったケース
あるママは「予定変更」にとても敏感なわが子に困っていました。毎日の「今日はなにをするの?」という不安から癇癪が続いていたのです。
そこで取り入れたのが、絵カードやスケジュールボード。
1日の流れをイラストで貼り出しただけで、子どもは「これから何があるのか」を目で確認できるようになりました。
結果、見通しが持てる安心感から癇癪が激減。
「ママも子どももラクになった」と実感できたそうです。
【成功例】感覚過敏への配慮で外出が楽になったケース
別のケースでは、スーパーに行くたびに大泣きしてしまう子がいました。原因は「蛍光灯の光」と「店内の音」。
そこでママは、サングラスとイヤーマフを持参。
最初は「人目が気になる…」と勇気が必要だったそうですが、つけた途端に子どもは落ち着き、買い物もスムーズに。
ここから学べるのは、感覚過敏への小さな工夫が生活の大きな安心につながるということです。
【失敗例】叱ってしまい逆効果になったケース
「いいかげんにしなさい!」とつい声を荒げてしまった、という経験は誰にでもありますよね。あるママも同じように、癇癪のたびに叱ってしまったことがありました。
でも結果は…子どもの癇癪がより激しくなってしまったんです。
なぜなら、子どもにとっては「伝わらない frustration(フラストレーション)」がさらに大きくなり、爆発してしまうから。
この体験から学べるのは、「叱る=しつけ」ではないということ。子どもに必要なのは「安心感」と「理解されている感覚」なんですね。
【失敗例】癇癪を避けすぎて行動が制限されたケース
「癇癪が起きるのが怖いから」と、外出を極力控えたママもいました。確かに一時的には平和かもしれません。
でもその結果、子どもは新しい経験をする機会を失ってしまい、外の世界に慣れるチャンスがなくなったのです。
ママ自身も「子どもと出かけたいのに…」とストレスがたまりました。
このケースからの学びは、「癇癪を避ける」だけではなく、「癇癪が起きても対応できる準備をする」ことが大事だということです。
ママのリアル体験談から得られる学び
成功にも失敗にも共通しているのは、「子どもの行動には必ず理由がある」ということ。
- 視覚支援で「見通し」が持てれば安心できる
- 感覚への配慮で「外出」が楽になる
- 叱るより「理解して受け止める」ことが効果的
- 癇癪を避けるより「起きても大丈夫と思える準備」が必要
ママたちの体験談は、同じ悩みを持つ人にとって大きなヒントになります。完璧を目指さなくても、一歩ずつ「うちの子に合うやり方」を見つけていければOKです。

よくある質問(Q&A)
Q1. 自閉症の癇癪は成長すると落ち着きますか?
答えは「はい、ただし子どもによって違う」です。成長とともに言葉や気持ちの表現が増えていくと、少しずつ癇癪が減るケースは多いです。ただし、感覚過敏やこだわりなど特性は残ることもあります。
つまり「癇癪が完全になくなる」というよりも、「癇癪の頻度や強さが弱まっていく」「癇癪以外の方法で気持ちを伝えられるようになる」と考えたほうが現実的です。
Q2. 癇癪と発達障害の関係は?
自閉症やADHDなどの発達障害のある子どもは、「感覚が人より敏感」「予定変更が苦手」「気持ちを言葉にしにくい」といった特性を持つことがあります。
そのため癇癪は「わがまま」ではなく、「環境にうまく対応できないときのSOS」であることが多いのです。
発達障害=必ず癇癪がある、というわけではありませんが、特性と強く関係していることは覚えておくと安心です。
Q3. 癇癪とパニックの違いは?
よく混同されがちですが、実はニュアンスが少し違います。
- 癇癪:自分の思い通りにならなかったときの感情の爆発。泣いたり叫んだり、床に寝転がるなど。
- パニック:感覚の刺激や予想外の出来事に体が耐えられなくなったときの反応。混乱して暴れたり、逃げようとしたり。
どちらも「困っているサイン」ですが、癇癪は気持ちの表現、パニックは身体的な反応に近いイメージです。対応の仕方も少しずつ変わってきます。
Q4. 癇癪が激しいとき病院に行くべき?
基本的に癇癪そのものは「病気」ではありません。ですが、あまりに激しく長引く場合や、ケガにつながる危険がある場合は、専門の医師や発達相談機関に相談することをおすすめします。
また、発達障害かどうかの診断がついていない子の場合、癇癪がきっかけで「一度専門家に見てもらおう」と思う家庭も多いです。
「困っているのはママと子どもだけじゃない。相談していいんだ」と考えてOKです。
Q5. 保育園・学校での癇癪へのお願いの仕方は?
園や学校で癇癪が起きると「先生に迷惑をかけているのでは…」と不安になりますよね。でも実際は、事前に子どもの特性を伝えておくことがとても大切です。
お願いするときのコツは:
- 「困っている行動」よりも「対応すると落ち着きやすい方法」を具体的に伝える
- 例:「予定が急に変わると混乱します。前もって声をかけてもらえると助かります」
先生もママからの情報があると対応しやすくなりますし、家庭と学校で連携がとれることで子どもも安心します。
✅ まとめ
- 癇癪は成長とともに変化していく
- 発達障害の特性と深く関わっている
- 癇癪とパニックは似ているけれど違う反応
- 激しすぎるときは専門機関に相談してOK
- 学校や園には「具体的にできる支援」を伝えることが大事
癇癪対応は一人で抱え込むとつらくなりがち。「理解してくれる人に話す」「ちょっとずつ工夫する」ことが、ママと子どもの安心につながります。
まとめ|自閉症の癇癪は「困りごとのサイン」
ここまで、たくさんの視点から「自閉症の癇癪」についてお話してきました。最後に大事なポイントを整理しましょう。
まず、何よりも伝えたいのは、癇癪はママの育て方のせいではありません。
「うちの子はどうしてこうなんだろう…」「私の接し方が悪かったのかな?」と悩むママも多いですが、それは違います。癇癪は、子どもがまだ自分の気持ちや感覚をうまく伝えられないときに出てくる「困りごとのサイン」なのです。
「理解 → 対処 → 予防 → 心のケア」の流れをおさらい
- 理解:癇癪は子どもが「助けて!」とサインを出していることを知る。
- 対処:癇癪が起きたとき、安全を守りつつ落ち着かせる工夫をする。
- 予防:予定を見える化したり、感覚過敏への配慮をして癇癪が起きにくい環境をつくる。
- 心のケア:ママ自身も休んでリフレッシュし、「また頑張ろう」と思える気持ちを大切にする。
この流れを意識するだけで、「どうしたらいいかわからない…」という不安が少しずつ整理されていきます。
今日からできる一歩
大きなことをしなくても大丈夫。「小さな一歩」を積み重ねることが癇癪対応の近道です。
たとえば…
- 絵カードや写真で予定を見えるようにする(視覚支援)
- リビングの一角に毛布やクッションを置いて「落ち着くスペース」を作る
- ママ自身が「今日はここまでできた」と自分をほめる
こうした工夫はすぐに始められて、子どももママも安心感を得やすくなります。
癇癪は大変ですが、「子どもが困っているから助けてほしい」というサインでもあります。
ママがそのサインを受け止め、一緒に工夫していけば、子どもも少しずつ自分の気持ちを表現する力を身につけていけます。
そして、ママ自身も「私は悪くない」「うちの子に合ったやり方を見つければいい」と思えるようになることが大切です。
完璧を目指す必要はありません。
今日からできる一歩を大事に、少しずつ癇癪との付き合い方を見つけていきましょう。
以上【自閉症の癇癪対処法|子どもが落ち着く!ママが今すぐできる安心の工夫集】でした











コメント