発達障害の子がおもちゃを取るのはなぜ?原因と心理を理解しよう
「うちの子、どうしてお友達のおもちゃをすぐ取っちゃうんだろう?」
そう悩んでいるママは多いと思います。実は、この行動にはいくつかの発達特性や心理的な背景が関わっています。ここを知っておくと、ただ「やめなさい!」と叱るよりも、ずっと落ち着いて対応できるんです。
欲しい気持ちをことばで表せない子どもの特性
発達障害のある子どもは、「欲しい」「貸して」といった気持ちをことばで伝えるのが難しいことがあります。
本当は「僕も遊びたい」「一緒にやりたい」と思っていても、それを上手に口にできない。だから、行動で先に手が出てしまうんです。
これは「わがまま」や「意地悪」ではなく、ことばの発達と気持ちの表現のギャップから起こることが多いんですね。
衝動性や感覚過敏など脳の特性による行動
発達障害には、注意が散りやすかったり、衝動的に行動してしまう特性があります。
例えば、欲しいおもちゃを見た瞬間に「今すぐ欲しい!」という気持ちが抑えられない。
また、感覚過敏や感覚鈍麻がある子は、
- 「お気に入りの感触が欲しいから取る」
- 「気持ちを落ち着けるために手に持ちたい」
など、感覚的な理由でおもちゃを取ってしまうこともあります。
遊び方や順番のルールがわかりにくい背景
「順番を待つ」「交代する」などの社会的ルールは、発達障害の子にとって理解しづらいことがあります。
大人からすれば「当たり前」のことでも、子どもにとっては目に見えないルールはわかりにくいんです。
だから「今はお友達が使ってるから待とうね」と言われても、頭では理解しづらく、行動に結びつかないことがあります。
不安やストレスで「取る行動」に出る場合も
実は「おもちゃを取りたい気持ち」だけじゃなく、不安やストレスからくる行動のこともあるんです。
- 知らない場所で落ち着かない
- お友達とのやりとりに自信がない
- 気持ちをどう表していいかわからない
こうしたときに、安心を得るためにおもちゃを取るケースもあります。大人でも、緊張すると無意識に手遊びをしたりしますよね。それと似た感覚だと考えるとわかりやすいかもしれません。
発達段階でよくある行動との違いを見極める
実は、発達障害の有無にかかわらず、小さい子なら「おもちゃを取っちゃう」のはよくあることです。2〜3歳頃は「自分のもの!」という感覚が強い時期なので、自然な発達の一部とも言えます。
でも、年齢が上がっても同じ行動が繰り返される、またはトラブルが大きくなっていくときは、特性からの影響を考えてあげるといいですね。
おもちゃを取る行動への基本対応!ママが知っておきたい考え方
子どもがおもちゃを取ってしまったとき、つい「やめなさい!」と叱りたくなりますよね。周りの目も気になるし、ママ自身も恥ずかしかったり焦ったり…。でも、この場面で大切なのは、「どうして取ってしまうのか」背景を理解することと、家庭でできる小さな工夫です。ここでは、その基本的な考え方をお伝えします。
「わざと」ではなく特性から出る行動と理解する
まず大切なのは、おもちゃを取るのは「性格の問題」でも「わざと困らせようとしている」わけでもない、ということ。
発達障害の子どもは、衝動のコントロールやことばでのやりとりが苦手な場合があります。そのため、本人も「いけないこと」とわかっていても、気持ちが先に行動になってしまうんです。
大人の目には「乱暴」に見えても、子どもにとっては自然に出てしまった行動。この視点を持つだけで、ママの受け止め方がぐっと変わります。
ママが抱える恥ずかしさや焦りをどう受け止めるか
正直、外でおもちゃを取ってしまうと、ママは「周りにどう思われているかな」と不安になりますよね。
でも、ここで大事なのは、ママが自分を責めすぎないことです。
多くの専門家も「発達障害の特性から起こる行動は、家庭で工夫すれば必ず改善の余地がある」と言っています。
つまり、今はまだ発達の途中で学んでいる段階。焦る必要はありません。
「恥ずかしい…」という気持ちは自然なことなので、その気持ち自体を否定せず、「子どもと一緒に練習していけばいい」と切り替えられると楽になります。
すぐやめさせるより「少しずつ減らす」が大切
「どうにかしてすぐやめさせなきゃ」と思うと、ママも子どもも苦しくなってしまいます。
大事なのは、行動をゼロにするのではなく「少しずつ減らす」意識です。
例えば、
- 毎回おもちゃを取っていたのが → 半分くらいの回数になった
- 取ってしまった後に「ごめんね」と言えた
これだけでも大きな進歩です。
子どもの成長は小さなステップの積み重ね。完璧を目指さず、できたことを一緒に喜んであげると、子どもも自信を持てます。
環境を整えることが家庭でできる最初の支援
「子どもの行動を変える」のは時間がかかりますが、環境を整えることは今すぐできる支援です。
例えば、
- 友達と遊ぶときは同じ種類のおもちゃを2つ用意しておく
- 取り合いになりやすいおもちゃはあらかじめ隠しておく
- 遊ぶ場所やルールを事前に決めておく
こうした環境調整は、子どもが安心して遊べる土台づくりになります。
「行動を叱る」よりも「環境を変える」方が、実はずっと効果的なことも多いんです。
家庭でできる!おもちゃを取る行動への具体的な対応法
おもちゃを取ってしまう行動は、ママが少し工夫するだけで減らすことができます。ポイントは、事前に備える・実際に起きたときの対応・家での練習・成功体験を積ませること。順番にみていきましょう。
トラブルを防ぐために事前にルールや予告を伝える
子どもは「先にわかっていれば落ち着ける」ことが多いです。
遊ぶ前に、「今日は順番で遊ぼうね」とか「お友達が終わったら貸してもらおうね」と伝えておくと、頭の中で準備ができます。
例えば公園に行く前に、
- 「ブランコは順番だよ」
- 「今日は貸してほしい時に『貸して』って言おうね」
と、事前に予告するだけでもトラブルが減ります。
子どもにとって「突然言われる」のは一番難しいので、予告はとても大事です。
実際に取ってしまった時の効果的な声かけ例
取ってしまった瞬間に「ダメ!」と叱ると、子どもは混乱してしまいます。
そんな時は、「気持ちを代弁+どうすればいいか」をセットで伝えるのが効果的。
例)
- 「欲しかったんだね。でも今は〇〇ちゃんが遊んでるよ」
- 「一緒に待ってみよう。終わったら貸してもらおうね」
こうすると、子どもは「気持ちはわかってもらえた」安心感を持ちながら、次の行動を学べます。
叱るのではなく「どうすればよかったか」を考えさせる
叱るだけだと「取っちゃダメ」しか残りません。でも、子どもに必要なのは「じゃあどうすればいいのか」を学ぶこと。
取った後に落ち着いてから、
- 「どう言えばよかったかな?」
- 「今度はどうしたらいいと思う?」
と一緒に考えるのがおすすめです。
答えられないときは、ママが正しい言い方を短く教えるとGOOD。例えば「貸してって言うんだよ」と実際に見せてあげると、次に使いやすくなります。
家でできるロールプレイや兄弟との練習方法
家庭で練習すると、本番で行動に移しやすくなります。
おすすめはロールプレイ(ごっこ遊び)。ぬいぐるみやお人形を使って、
- 「これ貸して」→「いいよ」
- 「順番ね」→「うん!」
とやりとりを見せるだけでも効果的です。
兄弟がいる家庭なら、順番遊びの練習が自然にできます。
兄弟がいない場合でも、ママと交代しながら遊ぶことで、「待つ」「交代する」感覚を身につけられます。
成功体験を積ませて「できた!」を増やす工夫
発達障害の子にとって、「できた」という成功体験が次の行動のやる気につながるんです。
おもちゃを貸してもらえた時や、順番を守れた時には、
- 「待ててすごいね!」
- 「ちゃんと貸してって言えたね!」
と、具体的にほめてあげましょう。
ポイントは「できたことをその場で言葉にする」こと。子どもは「ママが認めてくれた!」と感じ、次も頑張ろうと思えるようになります。

ママ必見!おもちゃを取る子への声かけ実例集
「おもちゃを取っちゃダメ!」とつい言いたくなりますよね。でも、ただ禁止するだけでは子どもには伝わりにくいんです。
発達障害の子どもは、ことばを理解する力や気持ちの調整がゆっくりなことが多いので、声かけを工夫することでぐっと伝わりやすくなります。ここでは、すぐに使える声かけの実例を紹介します。
欲しい気持ちを代弁して安心させる言葉
まず大切なのは、「欲しい気持ちをわかってもらえた」と感じさせることです。
いきなり「ダメ!」と言われると、子どもは「自分の気持ちを否定された」と思ってしまいます。
例)
- 「〇〇が欲しかったんだね」
- 「遊びたかったんだね」
こうやって気持ちを代弁してあげると、子どもは安心して落ち着きやすくなるんです。
相手の気持ちを伝えて共感力を育てるフレーズ
お友達のおもちゃを取ったときは、「相手の気持ち」を短く伝えることも大事です。
発達障害の子は相手の気持ちを想像するのが難しいことが多いので、大人が言葉で補ってあげる必要があります。
例)
- 「〇〇ちゃんも遊びたかったんだよ」
- 「取られてびっくりしちゃったね」
こうした声かけを繰り返すことで、少しずつ共感力が育っていきます。
子どもに伝わりやすい短くシンプルな声かけ
子どもに長い説明はNGです。特に発達障害の子は、一度にたくさんの言葉を理解するのが難しいことがあります。
だから、「短く・シンプルに」伝えることがポイントです。
例)
- 「順番ね」
- 「待とうね」
- 「今は〇〇くんの番」
短い言葉なら、子どももすぐに理解しやすいです。
遊びを切り替える「提案型」の声かけテクニック
「ダメ!」と制止するだけだと、子どもはどうしていいかわからず混乱します。そこで有効なのが、「提案型の声かけ」です。
例)
- 「こっちのおもちゃで遊ぼうか」
- 「一緒にブロックしよう」
ただ禁止するのではなく、代わりの行動を提案することで気持ちを切り替えやすくなるんです。
「やめて」より「こうしよう」で行動を促す
子どもは「やめて」と言われても、じゃあどうすればいいのかがわかりません。
そこで、「こうしよう」という具体的な行動に置き換えて伝えることが効果的です。
例)
- 「やめて!」ではなく → 「貸してって言おうね」
- 「取らない!」ではなく → 「順番にしようね」
このように伝えると、子どもが次にどう行動すればいいかが明確になるので、実際にできるようになりやすいです。
遊びの中で学べる!おもちゃを取らない練習方法
「貸して」「順番ね」って、頭ではわかっていても実際にできるのはなかなか難しいもの。特に発達障害のある子どもは、社会的なルールをことばで理解するのが苦手な場合があります。
そんなときこそ、遊びを通して自然に練習することが効果的です。遊びの中なら「教え込む」よりずっと楽しく学べます。
ターンテイキング(順番を待つ遊び)で学ぶ
「ターンテイキング」とは、順番を交代して遊ぶことです。
例えば、ブロックを一つずつ積んでタワーを作る遊びや、ボールを交互に転がす遊び。こうした単純なやりとりで、「自分の番」と「相手の番」を体感できるんです。
最初は大人が「今はママの番、次は〇〇くんの番」と声をかけながらやると、子どもも流れを理解しやすくなります。
協力して楽しむ共同遊びを取り入れる
一人で完結する遊びだけでなく、一緒に協力しないと完成しない遊びを取り入れるのもおすすめです。
例えば、
- 大きなブロックで一緒に家を作る
- ジャンボパズルを協力して完成させる
- 電車の線路を一緒につなげる
こうした遊びでは、「相手と一緒にやると楽しい!」という経験ができます。自然に「取る」より「協力する」ことが増えていきます。
「貸して・どうぞ」のやりとり練習でスキルアップ
「貸して」「どうぞ」のやりとりは、実際に声に出して練習することが大事です。
例えば、家でぬいぐるみを使って「〇〇貸して」「はいどうぞ」と遊びながらやってみる。
この練習を繰り返すことで、子どもは「どう言えばいいか」が身についてきます。
ポイントは、貸してもらえたときにママがしっかりほめること。それが子どもの次のやる気につながります。
ボードゲームやカードゲームで自然に学ぶ方法
ルールのある遊びは、順番を守ることを自然に学べる絶好の機会です。
- 「UNO」や「ババ抜き」などのカードゲーム
- サイコロを振るすごろく
こうした遊びは「自分の番を待つ」練習になり、しかも楽しみながら取り組めます。
ただし、最初から難しいルールのゲームはハードルが高いので、シンプルなゲームからスタートするといいですよ。
大人が仲介して「今は〇〇くんの番」と補助する
最初のうちは、子ども同士だけで順番を守るのは難しいこともあります。そんなときは、大人が仲介役になることが大切です。
例えば、
- 「今は〇〇ちゃんの番だよ」
- 「次は〇〇くんの番だから待っててね」
と、短く補助してあげるだけで子どもは理解しやすくなります。
大人の声かけがあると、子ども同士のトラブルを未然に防げるし、子どもも安心して遊びに集中できるんです。
おもちゃトラブルを減らす家庭の環境づくり
「おもちゃを取らないように教え込まなきゃ」と思いがちですが、実は行動そのものを変えるより、環境を整えるほうが効果的なことが多いんです。
発達障害のある子は、状況によって衝動が出やすくなることもあります。だから、トラブルが起きにくい環境を準備してあげることが、ママにできる大きなサポートになります。
シェアしやすいおもちゃ選びでトラブル回避
おもちゃの種類によって、取り合いが起きやすいものと、みんなで楽しめるものがあります。
例えば、ブロック・積み木・電車の線路などは、一緒に遊べるのでトラブルになりにくいです。
逆に、キャラクター人形や乗り物など「ひとつしか使えないおもちゃ」は、取り合いの原因になりやすいですね。
遊びやすいおもちゃを選んであげることで、自然に「一緒に遊ぶ」経験を増やすことができます。
数を増やす・同じものを用意する工夫
取り合いになりやすいおもちゃは、数を増やすのが一番シンプルな解決法です。
たとえば車のおもちゃなら、同じ種類を2台用意しておくと安心です。
「同じものを2つも買うのはどうかな…」と思うかもしれませんが、トラブルでママが疲れてしまうより、結果的にずっと楽なんです。
必要に応じて100均などを活用して、「共有しやすい数」をそろえておく工夫をしてみてください。
遊ぶ場所や片付けルールを明確にする
「ここで遊ぶ」「遊んだら片付けてから次のおもちゃ」というように、遊ぶ環境のルールを明確にすることも大切です。
ルールが曖昧だと、子どもは「どこまでOKなのか」がわからず、トラブルにつながってしまいます。
おすすめは、遊ぶスペースを視覚的に区切ること。
例えばマットを敷いて「ここはおもちゃゾーン」とわかりやすくするだけでも効果があります。
片付けについても、箱やかごを使って「ブロックはここ」「車はここ」と決めておくと、子ども自身も切り替えやすく、落ち着いて遊べるようになります。
友達やママ同士で事前にルールを共有しておく
お友達が遊びに来るときは、ママ同士でルールを確認しておくことも大切です。
「このおもちゃは取り合いになりやすいから今日は出さないね」
「順番を待つときはママが声かけするね」
こんなふうに事前に共有しておくだけで、その場で慌てなくて済むんです。
また、お友達のママに子どもの特性を少し伝えておくだけで、理解してもらいやすくなります。
静かに安心して遊べる環境をつくる
発達障害の子どもは、音や刺激が多い場所では落ち着けず、衝動的に行動してしまうことがあるんです。
だから、できるだけ静かで安心できる環境を用意してあげることが効果的です。
例えば、
- テレビを消して遊ぶ
- 人が多すぎない空間にする
- クッションやお気に入りの毛布をそばに置く
こうした工夫で、子どもが安心して遊べる「安全基地」をつくることができます。
ママの心を守る!発達障害育児の気持ちの整え方
子どもがおもちゃを取ってしまったり、周りとトラブルになったりすると、ママの心はとても疲れてしまいますよね。
「どうしてうちの子だけ…」と落ち込んでしまうこともあると思います。
でも、そんなときに大切なのは、ママ自身の心を守ることです。ここでは、気持ちを少し楽にするための考え方や工夫を紹介します。
「うちの子だけじゃない」と知ることの安心感
まず伝えたいのは、「おもちゃを取ってしまう行動は、どの子にもあること」だということです。
発達障害の子は特性の影響で頻度が多くなったり長引いたりするだけで、決して「うちの子だけ」ではありません。
実際、幼児期の子どもはみんな「自分のもの」という気持ちが強く、取り合いは日常茶飯事です。
「これは発達の一部なんだ」と理解するだけで、ママの心は少し軽くなるはずです。
他の子のママへの伝え方で誤解を減らす
おもちゃを取ってしまうと、周りのママの目も気になりますよね。
そんなときは、誤解を減らすために短く伝えておくと安心です。
例)
- 「衝動的に取っちゃうことがあるけど、少しずつ練習中なんです」
- 「ことばで伝えるのが苦手なので、行動が先に出ちゃうことがあるんです」
こう伝えると、相手のママも「なるほど」と理解しやすくなります。
誤解を減らすだけで、人間関係のストレスもぐっと減りますよ。
罪悪感を抱かないための考え方とリフレーミング
「また取っちゃった…私の育て方が悪いのかな?」と罪悪感を抱くこともあると思います。
でも大事なのは、「これは子どもの特性であって、ママのせいではない」と考え直すこと。
心理学で「リフレーミング」という方法があります。
- 「取っちゃう」 → 「好奇心や欲求が強い証拠」
- 「待てない」 → 「エネルギーがいっぱいある」
このように視点を変えると、マイナスに見える行動も、成長のためのステップに見えてきます。
家族と共有して一人で抱え込まない方法
ママ一人で「なんとかしなきゃ」と抱え込むと、とても苦しくなります。
だからこそ、家族と情報を共有することが大切です。
- パパに子どもの特性や対応法を伝えて一緒に考える
- 祖父母にも「こういう理由でおもちゃを取っちゃうことがある」と説明しておく
こうすることで、ママだけが責任を背負わずに済みます。
「家族みんなで支える」環境があると、ママの心はぐっと楽になります。
支援機関や専門家に相談するメリット
それでも「どうしてもうまくいかない…」と感じたときは、支援機関や専門家に相談するのも一つの方法です。
- 発達支援センター
- 児童発達支援(療育)
- 保健センターや臨床心理士
こうした場所では、専門家が具体的な声かけや支援の工夫を一緒に考えてくれるので、ママが一人で悩む必要はありません。
同じ悩みを持つママたちとつながれる場もあり、「自分だけじゃない」と安心できるのも大きなメリットです。
実際に効果があった!おもちゃトラブル改善の体験談
「本当に効果あるの?」と不安になるママも多いと思います。
ここでは、実際に取り組んでおもちゃトラブルが少しずつ改善したママたちの体験談を紹介します。どれも特別な方法ではなく、家庭でできる工夫ばかりです。
声かけを変えて落ち着いた成功例
あるママは、子どもがおもちゃを取ったとき、つい「ダメ!」と強く言ってしまっていました。すると子どもは泣いたり怒ったりして、逆にトラブルが長引いてしまうことに…。
そこで、声かけを「欲しかったんだね」「終わったら貸してもらおうね」に変えてみたそうです。
すると、子どもが少しずつ落ち着き、泣き叫ぶことが減ったとのこと。
「声を変えるだけで、こんなに違うんだ!」と驚いたそうです。
おもちゃを増やしてトラブルが減った実例
別のご家庭では、車のおもちゃを取り合ってばかりで毎回ケンカに。
思い切って同じおもちゃを2台用意したら、取り合いが激減したそうです。
ママは「もっと早くやっておけばよかった!」と笑っていました。
やっぱり、数を増やすだけでも効果があるんですね。
順番遊びでスムーズになった家庭の工夫
「順番を待つ」が苦手なお子さんの場合、ママが順番遊びを毎日少しずつ練習したそうです。
例えばブロックを1つずつ交代で積むとか、ボールを転がし合う簡単な遊びからスタート。
最初は待てずに取ってしまうこともあったけど、続けるうちに「自分の番」と「相手の番」がわかるように。
幼稚園でも「待てることが増えたね」と先生に言われたそうです。
ママ自身の気持ちが楽になったケース
あるママは、「うちの子だけがトラブルを起こしている」と思い込んで毎日しんどかったそうです。
でも、ブログや支援センターで「同じ悩みを持つママがたくさんいる」と知ったことで、気持ちが軽くなったとのこと。
「子どもの成長はゆっくりだけど、私も一緒に学んでいけばいい」と思えるようになり、子どもに対してイライラよりも応援の気持ちを持てるようになったそうです。
幼稚園や療育と連携して改善した実体験
あるご家庭では、幼稚園でもおもちゃの取り合いが続いていました。
そこで、先生と相談して家庭と園で同じルール・声かけを徹底してもらったそうです。
「貸してって言おうね」「順番だよ」と園と家庭で同じ声かけをすることで、子どもが混乱せず、少しずつ行動が安定してきたとのこと。
ママは「家庭だけで抱え込まず、園や療育とつながることで安心できた」と話していました。

よくある質問Q&A:ママが知りたいリアルな悩み
「おもちゃを取ってしまう行動」に悩んでいるのはあなただけではありません。
ここでは、実際にママたちからよく寄せられる質問と、その考え方や対応のヒントを紹介します。
何度言ってもやめない時の対応は?
「やめようね」と言っても繰り返す…。そんなとき、ママは疲れてしまいますよね。
でも、「すぐやめる」ことをゴールにしないのがポイントです。
子どもは一度で理解できるわけではなく、何度も繰り返して学んでいくものです。
同じ声かけを繰り返すこと自体が学習になっています。
焦らず、「昨日より少し落ち着けたかな?」と小さな変化を見つけることが大切です。
兄弟のおもちゃをすぐ取ってしまう場合は?
兄弟げんかはよくあることですが、発達障害の子の場合は衝動的に動いてしまうことも多いです。
対策としては、
- 同じ種類のおもちゃを2つ用意する
- 遊ぶおもちゃをあらかじめ「これはお兄ちゃんの、これは弟の」と分けておく
また、兄弟それぞれに「遊ぶ時間」「貸すタイミング」をママがサポートすると、大きなトラブルを防ぎやすくなります。
公園や外出先でのトラブルが怖い時は?
「取ったらどうしよう」とドキドキして、公園に行くのがつらくなるママもいます。
そんなときは、事前に予告することが有効です。
「今日はブランコは順番で遊ぶよ」「誰か使っていたら待とうね」と伝えておくと、子どもの頭に準備ができます。
それでもトラブルが起きたときは、すぐに止めるより気持ちを代弁してあげると落ち着きやすいです。
「遊びたかったんだね、でも今は〇〇ちゃんが使ってるよ」と声をかけてあげましょう。
療育に通うべきか迷ったときの判断基準
「このままで大丈夫かな?療育に行ったほうがいいのかな?」と悩むママは多いです。
基本的には、「子育てが毎日しんどい」「家庭だけでは対応が難しい」と感じたら相談してみるのがおすすめです。
療育に行くことは「問題がある」というより、子どもに合ったサポートをもらえるチャンスです。
相談だけでもOKなので、迷っているときは一度話を聞いてみると気持ちが楽になります。
おもちゃを取られた側の子へのフォロー方法
忘れがちなのが、取られてしまった側の子へのフォローです。
相手の子はびっくりしたり悲しくなったりしています。
「びっくりしたね」「貸してくれてありがとう」など、気持ちを代弁して安心させてあげることが大切です。
また、順番が回ってきたときに「待ててすごかったね!」と伝えると、相手の子の自己肯定感も守れます。
まとめ・今日からできる小さな一歩
おもちゃを取る行動は、発達障害の子どもにとって「わざと」ではなく特性から生まれる行動であることが多いです。
だからこそ、ママが叱ることに力を使うよりも、環境を整えたり声かけを工夫したりすることがとても大事なんですね。
ここまでご紹介した対応法を振り返ると、ポイントは大きく5つにまとめられます。
- 気持ちを代弁して安心させる声かけ
- 「順番」「貸して」など具体的に教える練習
- 遊びを通して自然に学べる工夫
- 環境を整えてトラブルを未然に防ぐこと
- ママ自身の心を守ることも忘れないこと
どれも一気にやろうとすると大変です。
大切なのは、今日からできる小さな一歩を選んで試すこと。
例えば…
- 今日の遊びの中で「今はママの番、次は〇〇くんの番」と声をかけてみる
- おもちゃ箱を整理して「ブロックはここ」とわかりやすくしてみる
- 子どもが「貸して」と言えたら、その瞬間に「できたね!」と笑顔でほめてみる
こうした小さな工夫を積み重ねていくだけで、子どもは少しずつ「取らなくても大丈夫」という経験を増やしていきます。
そして何より大事なのは、ママが一人で頑張りすぎないこと。
家族や園の先生、支援機関や同じ立場のママ友とつながることで、気持ちもぐっと楽になります。
おもちゃトラブルは、子どもの成長の一部。
「困った行動」ではなく「学びのチャンス」ととらえられるようになったとき、ママと子どもの関係ももっと優しく、もっと安心できるものになっていきます。
まずは「声かけをちょっと変えてみる」「環境を少し整えてみる」など、できそうなことをひとつ選んで始めてみませんか?
以上【発達障害の子が友達のおもちゃを取る!家庭でできる対応法と声かけ実例】でした。

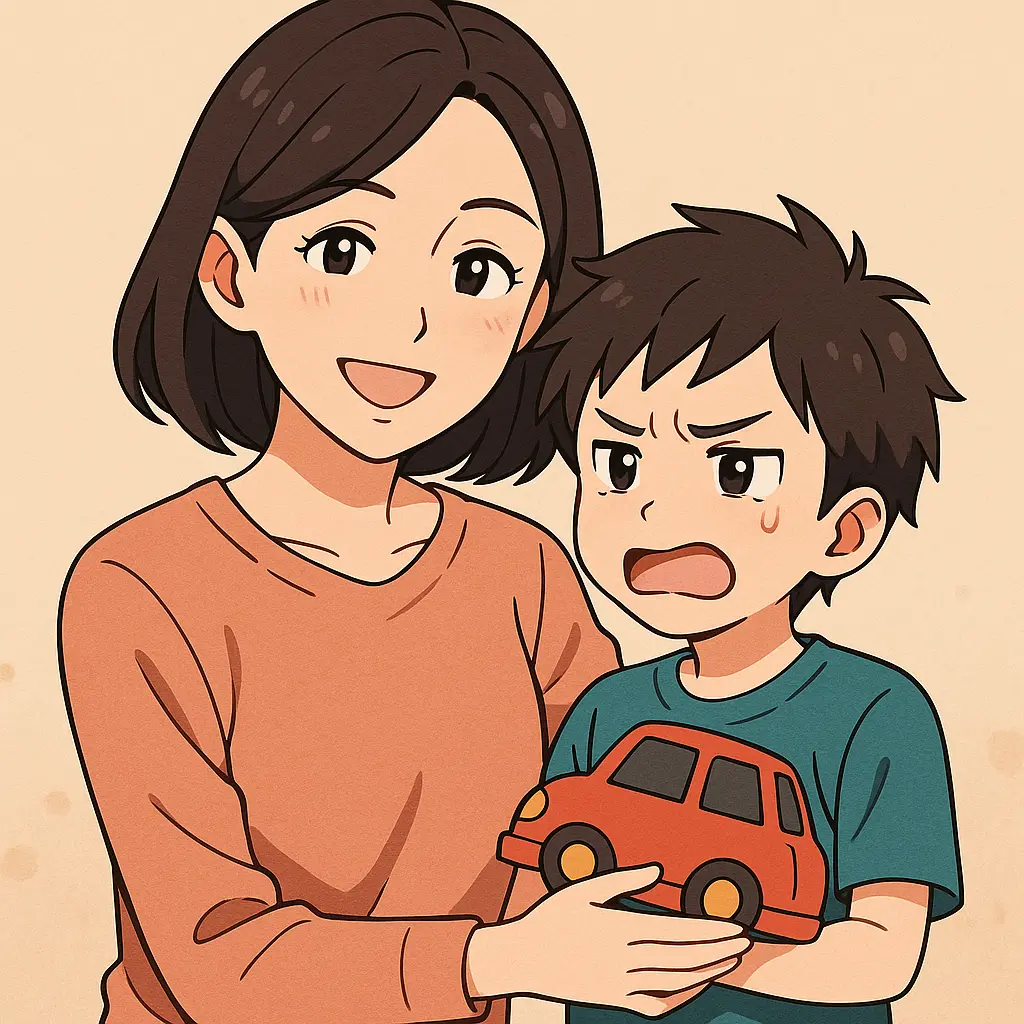









コメント