小学生が「おもちゃを貸せない」理由とは?
子どもが「おもちゃを貸せない」場面って、ママにとってはちょっと気になる瞬間ですよね。
「うちの子、わがままなのかな?」「友達関係に支障が出るんじゃ…」と心配になる気持ち、とても自然なことです。
でも実は、おもちゃを貸せないのにはちゃんと理由があるんです。ここでは、子どもの発達段階や特性、そして環境の影響という3つの視点から解説していきます。
発達段階に見られる自然な独占欲
小学生といっても、まだまだ「自分の物を守りたい」という気持ちが強い年齢です。特に低学年のうちは、「貸したくない=自分の物を大事にしているサイン」ともいえます。
心理学的にも、子どもは成長の過程で「自己主張」が出てきます。これは「自分のもの」と「相手のもの」を区別できるようになった証拠。むしろ健康的な発達の一部なんです。
ただし、この「独占欲」が強いときは、友達と遊ぶときにトラブルが起きやすいのも事実。ママとしては「今はこういう時期なんだ」と捉えることで、少し気持ちが楽になるかもしれません。
発達障害が関わるケース
一方で、発達障害がある子どもの場合、貸せない背景に特性ならではの理由が隠れていることがあります。
たとえば、
- 見通しが立たないと不安になる
→「今貸したら返ってくるの?」「いつ戻ってくるの?」が分からないと怖い。 - 強いこだわり
→「このおもちゃはこう使う!」と決めているから、人に触られるのが嫌。 - 感覚過敏
→他の子に触られることで「汚れた」と感じたり、違和感を覚える。
こうした理由から「貸せない」という行動につながることも多いです。
周囲からは「頑固だな」と見られがちですが、実は子どもなりの必死な自己防衛なんですね。
過去の経験や環境の影響
最後に見逃せないのが、過去の経験や育つ環境です。
例えば、以前に貸したおもちゃが壊されたり返ってこなかった経験があると、「もう貸したくない」と思ってしまうのは自然なことです。
また、家庭や学校でのルールの違いも影響します。
家庭では「兄弟でシェアするのが当たり前」でも、学校や友達の家では「自分の物は自分だけが使う」という文化があるかもしれません。そんな時に子どもは戸惑い、貸すことを拒むことがあります。
つまり、「貸せない」にはその子なりのストーリーがあるんです。ママがその背景を理解してあげることで、少しずつ子どもの気持ちがほどけていきます。

ママが抱えやすい悩みと不安
子どもがおもちゃを貸せないとき、いちばん悩むのはやっぱりママですよね。
その場で子ども同士がトラブルになるのもつらいけれど、実はママ自身が「どう思われているんだろう?」と不安を抱えやすいのも大きなポイントです。ここでは、ママが感じやすい代表的な悩みを整理してみます。
友達関係がうまく築けないのでは?
「おもちゃを貸せない=友達ができないのでは?」と心配するママは多いです。
子ども同士の遊びは“貸し借り”がつきもの。そこで断ってしまうと、相手の子に嫌われてしまうんじゃないか…と不安になりますよね。
でも実際には、子ども同士の関係は思っている以上に柔軟です。最初はぎこちなくても、遊び方を工夫したりサポートが入れば友達関係は十分築けることが多いんです。
大切なのは「貸せない=友達ができない」と短絡的に考えず、子どもに合った関わり方を探す視点を持つことです。
「わがまま」と思われることへの心配
ママが強く感じやすいのは、「他の人からどう見えるか」という視線です。
貸せない場面があると、「わがままな子だね」と言われそうでドキッとしますよね。
でもここで大事なのは、貸せない=性格が悪いわけではないということ。発達段階や特性による行動だと理解してもらえるように、必要なら先生や仲良しのママに説明しておくのも一つの方法です。
また、最近は発達特性への理解も少しずつ広がっています。
「わがまま」と決めつけられるよりも、「そういう子もいるんだね」と受け止めてもらえるケースが増えているのも事実です。
兄弟げんか・家庭内トラブルのストレス
家庭の中でも「おもちゃを貸せない問題」は起こります。
特に兄弟・姉妹がいると、貸さないことでけんかが絶えない…という声はよく聞かれます。
ママとしては「どうしてちょっと貸してあげられないの?」とイライラしてしまう瞬間もありますよね。
でも兄弟げんかの裏側には、「自分の存在を認めてほしい」「大切なものを守りたい」という気持ちが隠れていることも多いんです。
もちろん、毎日トラブル続きではママも疲れてしまいます。そんなときは、共有するおもちゃと“専用”のおもちゃを分ける工夫をすると、ストレスがグッと減ることがあります。
周囲のママからの視線や孤立感
公園や学校、放課後の集まりなどで「おもちゃを貸せない」場面があると、つい周囲のママの視線が気になってしまいますよね。
「気まずい…」「他の子と比べられてるかも」と感じると、外出や交流そのものがストレスになることも。
ここで忘れてはいけないのは、同じように悩んでいるママはたくさんいるということ。
見えないだけで、実は多くの親子が同じような経験をしているんです。
また、理解のあるママ友や支援者とつながれると、「自分だけじゃない」と安心できて気持ちがラクになります。孤立感は少しずつほぐれていくものなので、一人で抱え込まない工夫も大切です。
おもちゃを貸せない子への基本的な関わり方
子どもがおもちゃを貸せないとき、ママとしては「どう声をかければいいの?」「無理に貸させたほうがいいの?」と悩んでしまいますよね。
でも実は、関わり方をちょっと工夫するだけで、子どもの気持ちがラクになり、少しずつ「貸す」ことへのハードルが下がっていくんです。
ここでは、日常で取り入れやすい 3つの基本的な関わり方 を紹介します。
否定せず気持ちを受け止める
まず大切なのは、子どもの気持ちを頭ごなしに否定しないことです。
「どうして貸せないの?」「意地悪しないで!」と言ってしまうと、子どもは自分を責められたと感じてしまいます。すると余計に「貸すのは怖いことだ」と思い込んでしまうんですね。
そこでおすすめなのが、共感の声かけです。
例えば、子どもが貸せないときに「このおもちゃ、大事にしてるんだね」「お気に入りだから渡したくないんだね」と伝えてみましょう。
こうした言葉で「自分の気持ちを分かってもらえた」と感じると、子どもは安心します。
安心できると、少しずつ「じゃあちょっとだけ貸してみようかな」という前向きな気持ちが芽生えることもあるんです。
安心できる環境を整える
次に大事なのは、無理に貸さなくてもいい環境を整えることです。
「絶対に貸したくない!」と思うほど大切なおもちゃは、遊びに来る前にあらかじめ避難させておきましょう。
これをしておくと、子どもは「大事なものは守られている」という安心感を持てます。
その結果、他のおもちゃなら「まあ貸してもいいかな」と思える余裕が生まれやすいんです。
これは兄弟げんかにも効果的。専用の“宝物ボックス”を作って、そこに入れた物は触らないというルールを決めておくと、トラブルが減ってママもラクになりますよ。
事前にルールを設定する
そしてもうひとつの工夫が、遊ぶ前にルールを決めておくことです。
「遊んでいる最中に突然『貸して』と言われる」のは、子どもにとって大きなストレス。見通しがないと不安になりやすいんです。
そこで役立つのが タイマーや砂時計。
「5分経ったら交代しようね」とルールを共有しておけば、子どもは心の準備ができます。
順番が“見える化”されていると、相手の子も納得しやすく、ケンカも減ります。
こうした「ルールの見える化」は、発達障害のある子にとって特に効果的。
見通しが立つことで不安が減り、少しずつ貸し借りに挑戦できるようになります。
実践できる工夫と遊びアイデア
「おもちゃを貸せない子」に無理やり「貸しなさい!」と伝えても、子どもの心はなかなか動きません。
でも、ちょっとした工夫や遊びの取り入れ方次第で“貸すって意外と悪くない”という経験につながることがあります。
ここでは、すぐに家庭で試せるアイデアを4つ紹介します。
「特別ボックス」で大切なおもちゃを守る
まずおすすめしたいのが、「特別ボックス」を作る方法です。
これは「絶対に貸したくないおもちゃ」をあらかじめ入れておく専用の箱。兄弟や友達が遊びに来る前に「ここにしまった物は誰も触らない」とルールを決めておきます。
こうすることで、子どもは「大事なものは守られている」と安心できます。結果として、その他のおもちゃは「じゃあこれは貸してもいいよ」と気持ちを切り替えやすくなるんです。
これは心理的なガードを下げるための工夫でもあります。「貸せない気持ち」を尊重しながら、「貸せる体験」に近づける第一歩になります。
交換遊びでシェアの楽しさを経験する
次のステップは、「交換遊び」です。
「貸す」=「取られる」と感じてしまう子にとって、ただ渡すだけの貸し借りはハードルが高いんです。
そこで「一方的に貸す」のではなく、「お互いに交換する」スタイルにすると抵抗が減ります。
例えば、「この車とその人形を交換しよう」「3分後に交代しよう」といった形。
交換遊びを繰り返すと、子どもは「貸しても必ず返ってくる」という安心感を持ちやすくなります。さらに、「相手とやり取りするって楽しい!」という体験にもつながるんです。
協力型の遊びを取り入れる(ボードゲーム等)
おもちゃを「一人で独占する」状況を減らすためには、協力型の遊びが効果的です。
たとえば、
- ボードゲーム
- カードゲーム
- ジェンガなどの順番遊び
これらは「順番を待つ」「役割を分け合う」ことが自然に含まれています。
一人だけが持っているおもちゃをどうするか…と悩む場面が少ないので、“みんなで一緒に楽しむ”経験が増えるんです。
発達障害のある子にとっても、こうした遊びは「社会性の練習」になりやすいポイント。遊びながら学べるのは嬉しいですね。
親がモデルとなる行動を見せる
そして意外に効果的なのが、親自身が「貸し借りのモデル」になることです。
例えば、
- 「ママのペン貸してあげるね」
- 「ありがとう、返してくれて助かったよ」
といった日常のやり取りをあえて子どもに見せます。
子どもは大人の行動をよく観察しているので、「貸すと相手が喜ぶ」「返してもらえると気持ちがいい」という体験を間接的に学ぶことができます。
さらに、家族の中で「ありがとう」「どうぞ」のやり取りを繰り返すと、子どもは自然と「貸す=安心できる行動」と理解しやすくなります。
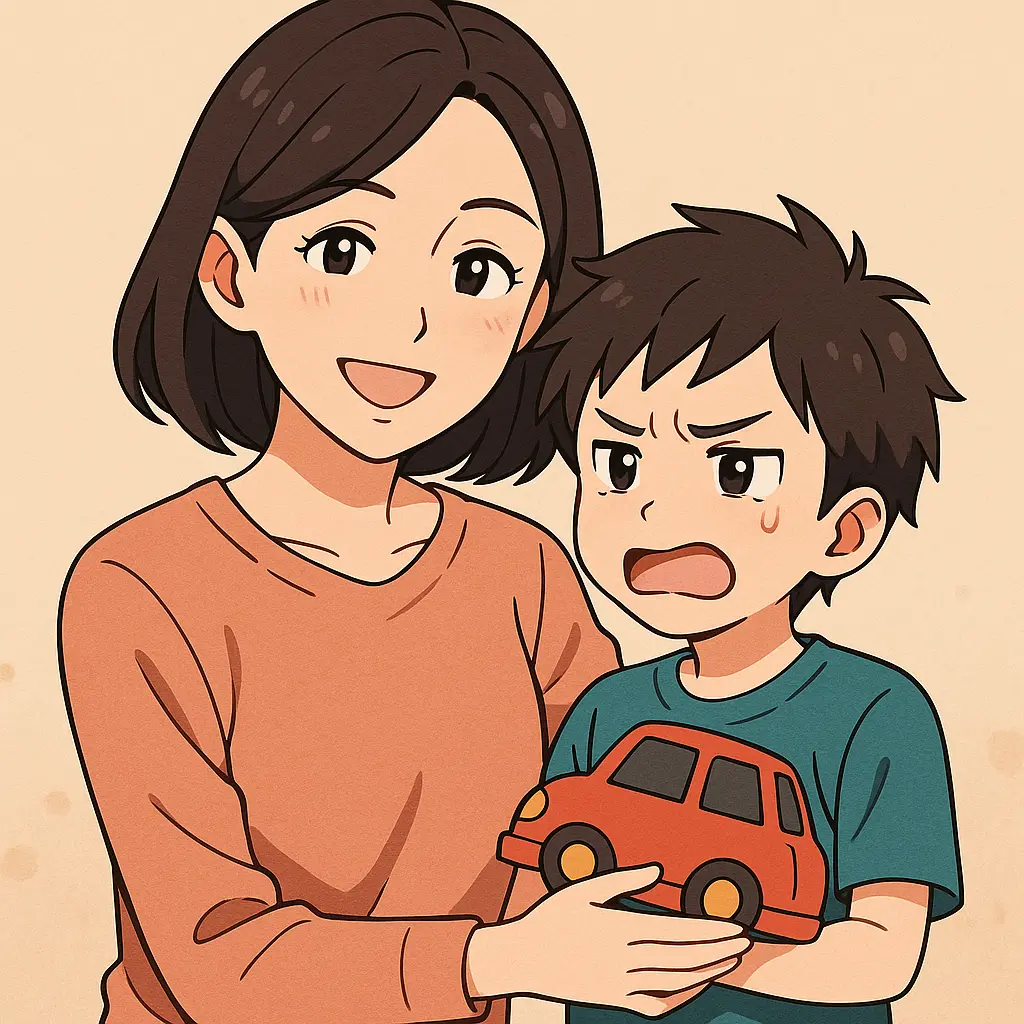
ケース別の具体的対応
「おもちゃを貸せない」というのは家庭だけでなく、学校や友達との関わりの中でもよく出てくる課題です。
そしてその状況によって、ママの悩み方や対応のポイントも変わってきます。
ここでは、よくある3つのケースに分けて具体的な工夫を紹介します。
学校でトラブルになる場合
学校生活の中では「消しゴム貸して」「鉛筆ちょっと貸して」など、小さな貸し借りが日常的にありますよね。
そこで「貸せない!」となると、友達とのトラブルに発展してしまうこともあります。
そんなときは、先生との連携がとても大事です。
「うちの子は物を貸すのが難しいことがある」ということを事前に伝えておくと、先生も配慮しやすくなります。
たとえば、
- 貸し借りが起きやすい場面では先生がフォローしてくれる
- 「予備の鉛筆」や「予備の消しゴム」を子どもに持たせておく
- ルールをみんなで共有して、子どもが安心できる環境を作る
こうした工夫で、教室内での衝突を減らし、子どもが安心して過ごせるように支援することができます。
兄弟姉妹とのけんかに発展する場合
家庭内でもっとも多いのが、兄弟姉妹とのけんかです。
「貸してよ!」「いやだ!」と、毎日のようにバトルが勃発…というご家庭も多いはず。
この場合に役立つのは、物理的な環境を整えることです。
たとえば、
- 個別スペースを確保する → 「この棚のものは○○ちゃん専用」というルール
- 順番制を導入する → タイマーやカードを使って「今はお兄ちゃんの番、次は妹の番」と分かるようにする
これによって、子ども同士の「不公平感」を減らすことができます。
ママがその都度ジャッジして仲裁するよりも、ルールや仕組みが守ってくれる状態を作ったほうが、ママ自身もぐっとラクになりますよ。
発達障害の診断がある場合
発達障害のある子どもが「おもちゃを貸せない」ときは、その子の特性に合わせた支援が必要になります。
療育の場では、実際にこんな取り組みがされています。
- 先生や支援員と一緒に「順番遊び」を練習する
- 役割を交代しながら遊べるゲームを繰り返す
- 絵カードを使って「次はあなた、その次は友達」と視覚的に伝える
こうした方法を通して、子どもは「少しずつ貸せる経験」を積み重ねていきます。
また、ママとして気をつけたいのは、専門機関に相談すべきサインを見逃さないことです。
例えば、
- 友達との関わりが極端に難しい
- 貸す・貸さないの場面で強いパニックが続く
- 学校や家庭でトラブルが繰り返し起きる
こうした場合には、発達支援センターや児童発達支援事業所などに相談するのがおすすめです。
専門家の視点が入ることで、ママの負担も軽くなりますし、子どもにとっても安心できる環境が広がります。
ママの声かけアイデア集
子どもがおもちゃを貸せるかどうかは、その子の気分や状況によって大きく変わります。
そんなときにママがかける一言は、子どもの気持ちをラクにしたり、自信を育てたりする大切なきっかけになります。
ここでは、日常で使いやすい声かけの工夫を3つの場面に分けて紹介します。
肯定的に伝えるフレーズ例
まず大事なのは、子どもの気持ちを否定せず、肯定的に伝えることです。
「どうして貸せないの?」「意地悪しないで!」と責めるよりも、気持ちを認めてあげる言葉が効果的です。
例えばこんな声かけがおすすめです。
- 「そのおもちゃ、大事にしてるんだね」
- 「気に入ってるから貸したくない気持ち、わかるよ」
- 「今はまだ難しいよね。でも、やろうとしたことはえらいよ」
こうした言葉をかけることで、子どもは「自分の気持ちをわかってもらえた」と安心します。
安心感があると、少しずつ「じゃあ貸してみようかな」という気持ちに変わることもあるんです。
貸せたときに褒める工夫
子どもが頑張って貸せたときには、その瞬間をしっかり褒めてあげることが大切です。
「貸せた=いいこと」という経験が積み重なると、子どもにとって自信につながります。
ただし、ここでの褒め方にはコツがあります。
- 「えらいね!」と短く終わらせず、行動を具体的に言葉にする
→「友達に貸してあげられて、とっても優しかったね」 - 気持ちにフォーカスする
→「自分の大事なおもちゃを貸せて、ちょっとドキドキしたかな?でも頑張ったね」
子どもは「ちゃんと見てもらえている」と感じると、“貸してよかった”という肯定的な記憶が残りやすくなります。
貸せなかったときのフォロー方法
もちろん、いつも貸せるとは限りません。むしろ「貸せなかった…」場面の方が多いかもしれません。
そんなときに「なんで貸せないの!」と叱ってしまうと、子どもはますます貸すことが苦手になってしまいます。
大切なのは、貸せなかったときのフォローです。
例えばこんな言葉が役立ちます。
- 「今日は大事だから貸せなかったんだね。それでいいよ」
- 「次のときはちょっとだけ挑戦してみようか」
- 「貸せなかったけど、自分の気持ちをちゃんと伝えられたのはすごいよ」
このようにフォローしてあげることで、子どもは「貸せなくても受け入れてもらえた」と安心できます。
そして、少しずつ“次はやってみようかな”という気持ちに変わっていくんです。
家庭でできる練習方法
「おもちゃを貸す」って、子どもにとっては思っている以上にハードルが高いこと。
だからこそ、日常の中でちょっとずつ練習できる工夫を取り入れると、自然に“貸すのもアリかも”という気持ちが育っていきます。
ここでは、家庭で今日からできる練習方法を3つ紹介します。
交代遊び(ターンテイキング)の導入
まずおすすめなのは、交代遊び(ターンテイキング)を日常の中に取り入れることです。
例えば、
- ジェンガやUNOなどのカードゲーム
- ボールの投げ合い
- ブロックを交代で積み上げる遊び
こうした遊びは「今は自分の番、次は相手の番」と順番を意識する練習になります。
これを繰り返すことで、“貸す=相手の番を待つこと”というイメージが自然に身についていきます。
ポイントは、短い時間で成功体験を積むこと。最初から長時間交代は難しいので、数分で切り替えるくらいがちょうどいいです。
ロールプレイ(貸す・借りるのごっこ遊び)
次に効果的なのが、ロールプレイ(ごっこ遊び)です。
例えば、ぬいぐるみやミニカーを使って、
- 「このおもちゃ貸してくれる?」
- 「いいよ、どうぞ!」
- 「ありがとう、返すね!」
というやり取りを演じてみましょう。
実際の友達とのやり取りでは緊張してしまう子でも、ごっこ遊びなら安心して練習できるのがポイントです。
ママと一緒に「ありがとう」「どうぞ」を繰り返すうちに、貸し借りの流れが体に染み込んでいきます。
また、子どもに「今日はママが貸す役ね」「次はあなたが貸す役ね」と交代で役割を変えると、“貸す側・借りる側”どちらの気持ちも体験できるので理解が深まります。
絵本・動画で「シェアの大切さ」を学ぶ
最後におすすめなのが、絵本や動画を活用する方法です。
「貸す」「シェアする」ことの良さを描いたストーリーは、子どもにとってわかりやすい学びのきっかけになります。
例えば、
- お友達と協力して遊ぶキャラクターのお話
- 「貸したら楽しかった!」というエピソードが入った絵本
- 短いアニメ動画で“ありがとう”や“どうぞ”を伝えるシーン
こうしたものを一緒に見て、「この子は貸してあげたんだね」「友達が嬉しそうだね」と会話を重ねていくと、子どもが自然にイメージを持ちやすくなるんです。
発達障害のある子にとって、視覚的にわかる教材はとても効果的。頭で理解するだけでなく、映像や絵から直感的に「シェアっていいことなんだ」と感じられるのは大きなポイントです。
理解を深めるために大切な視点
「おもちゃを貸せない」という行動に直面すると、つい「なんでできないの?」「他の子はできてるのに…」と焦ってしまうこと、ありますよね。
でもここで大切なのは、子どもの成長を“比べる”のではなく“理解する”視点を持つことです。
成長のペースは一人ひとり違う
子どもの成長スピードは、本当にバラバラです。
ある子は5歳でスムーズにシェアができても、別の子は小学校に入ってから少しずつできるようになることも。
特に発達障害がある子は、「できるようになるタイミング」が周りよりゆっくりな場合が多いんです。
でも、それは「できない子」ではなく、「時間が必要な子」というだけのこと。
ママが「うちの子のペースで大丈夫」と思えると、子どもも安心して少しずつ挑戦していけます。
「できない」ではなく「まだ難しい」
子どもがおもちゃを貸せないとき、つい「できない」と決めつけてしまいがち。
でも本当は、「まだ難しいだけ」なんです。
例えば、自転車に初めて乗るとき。最初はできなくても、練習を重ねれば少しずつできるようになりますよね。
貸し借りも同じで、経験や環境の工夫で“できるようになる日”が来るんです。
「できない」ではなく「まだ難しい」と思い直すだけで、ママの気持ちもぐっと軽くなります。
周囲の大人が焦らない姿勢
子どもにとって一番の安心材料は、周りの大人が焦らず見守ってくれることです。
「早くできるようにならなきゃ」とプレッシャーをかけられると、子どもは余計に不安を抱えてしまいます。
逆に、大人が「まあゆっくりでいいよ」「今日は貸せなくても大丈夫」と伝えてあげると、子どもは安心して挑戦できます。
焦らず見守る姿勢が、結果的に成長を後押しする力になるんです。
もちろん、時にはママも「本当にこのままで大丈夫?」と不安になるもの。そんなときは、一人で抱え込まずに先生や支援機関に相談するのも立派な選択です。
まとめ|おもちゃを貸せない小学生との上手な関わり方
子どもがおもちゃを貸せないとき、つい「どうしてできないの?」と不安になったり、焦ってしまうことがありますよね。
でも実は、「貸せない」という行動は自然な発達の一部なんです。
「貸せない」は自然な発達の一部
子どもが「これは自分のもの!」と主張するのは、自己を確立していく大切な過程です。
特に小学生になっても、まだ「独り占めしたい」という気持ちが出るのは普通のこと。
また、発達障害のある子どもの場合は、特性から「見通しのなさ」「こだわり」「不安感」が重なって、貸すのがさらに難しくなることもあります。
でもそれは“性格が悪い”のではなく、その子なりの理由がある行動だと理解してあげることが大切です。
無理に矯正せず、安心と経験の積み重ねが重要
大切なのは、「貸せるようにしなきゃ」と無理に矯正しないことです。
叱ったり強制したりすると、子どもにとって「貸す=嫌なこと」として記憶されてしまう危険もあります。
それよりも、
- 「今日はちょっとだけ貸してみる」
- 「順番を決めて交代する」
- 「親子でロールプレイをする」
といった工夫で、少しずつ安心できる経験を積み重ねることの方がずっと効果的なんです。
経験を重ねるうちに、子どもは「貸すのも悪くないかも」と感じられるようになります。
ママ自身も焦らず伴走する姿勢が子どもの自信につながる
そして何より大切なのは、ママ自身が焦らず、子どものペースに伴走する姿勢です。
「まだ難しいけど、少しずつでいいよ」と見守る姿勢が、子どもに安心を与えます。
安心感があると、子どもは挑戦する力を持てるようになります。
その積み重ねが、「自分もできるんだ」という自信につながっていくんです。
ママが焦らずに子どもと向き合うこと自体が、何よりの支援になります。
以上【おもちゃ貸せない小学生との上手な関わり方とは?】でした。











コメント