【基礎知識】発達障害とは?ADHD・ASD・LDなど3つのタイプを簡単に解説
「発達障害」という言葉、よく聞くけれど…実際どんなものか、ちょっと分かりにくいですよね。
ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)といった言葉もよく耳にしますが、
「それぞれどう違うの?」と感じているママも多いと思います。
ここでは、難しい専門用語をできるだけ使わずに、発達障害の基本的な考え方をわかりやすく紹介します。
「発達障害」とは脳の発達の特性による“生きづらさ”
まず最初に知っておきたいのは、発達障害は「病気」ではないということ。
風邪やケガのように「治す」ものではなく、生まれつきの脳の働き方の違いによって起こる“特性”なんです。
たとえば、
- 人より集中しにくい
- 音や光に敏感すぎる
- 相手の気持ちを読み取るのが苦手
- 一度決めたことを変えにくい
こういった「その子らしい特性」が、生活の中で少し困りごととして現れることがあります。
でもそれは「悪いこと」ではなく、脳の発達のバランスが少し違うだけなんです。
専門的には、発達障害は「脳機能の特性によって、社会生活や学習に支障が出る状態」と定義されています。
つまり、脳の一部の働きが「得意・不得意」として偏っているということ。
ただし、社会や学校の仕組みが“みんな同じようにできる”ことを前提にしているため、
その特性が「生きづらさ」につながってしまうこともあります。
だからこそ、周囲の理解とサポートが何より大切。
子ども自身が安心して過ごせる環境を整えることが、支援の第一歩になります。
発達障害の種類とそれぞれの特徴
発達障害といっても、実はいくつかのタイプがあります。
ここでは代表的な3つを紹介します。どのタイプも「個性の幅」がとても広いので、
「うちの子も少し当てはまるかも」と感じても、心配しすぎなくて大丈夫です。
自閉スペクトラム症(ASD)
ASDの子は、「人との関わり方」や「こだわりの強さ」に特徴が見られることがあります。
たとえば、
- お友だちと一緒に遊ぶより一人遊びが好き
- スケジュールが変わると混乱する
- 興味のあることには驚くほど集中する
ASDの特徴は「こだわり」「感覚の強さ」「人との距離感の感じ方」が人とは少し違うという点です。
でもそれは「冷たい」「わがまま」ではなく、脳が情報を処理する仕組みが独特なだけ。
ASDの子は、自分の世界観を大切にする天才肌タイプでもあります。
注意欠如・多動症(ADHD)
ADHDは、「集中力」「衝動性」「多動性」の特性が目立つタイプです。
よく見られるのは、
- 忘れ物が多い
- 授業中に立ち歩く
- 思いついたことをすぐ口にする
これは「やる気がない」「落ち着きがない」ではなく、
脳の働きが常に“フル回転”している状態なんです。
ADHDの子はアイデアが豊富で、行動力も抜群。
ただ、切り替えや集中のコントロールが苦手なため、環境づくりがとても大切になります。
学習障害(LD)
LDは、「読む」「書く」「計算する」など特定の学習領域にだけ困難があるタイプです。
たとえば、
- 音読は上手だけど漢字が覚えにくい
- 数字の桁がすぐにわからなくなる
- 書くスピードが極端に遅い
こういった困難がある一方で、話す力や創造力はとても高い子も多いです。
つまり、「できない」ことと「できる」ことの差が大きいのがLDの特徴です。
LDもADHDやASDと重なることがあり、ひとりの子が複数の特性をもっていることもあります。
日本での診断・支援の流れ
「うちの子、ちょっと気になるけど…どこに相談すればいいの?」
多くのママが最初にぶつかるのがこの疑問ですよね。
発達障害の診断や支援は、乳幼児期から小学生ごろにかけて見つかることが多いです。
気づきのきっかけ
- 園で「落ち着きがない」「集団行動が苦手」と言われた
- 家で同じ遊びばかりしている
- 先生から発達の相談をすすめられた
このような場面が、相談の第一歩になることが多いです。
相談先の流れ
- 市区町村の発達相談窓口(保健センターなど)で相談
- 必要に応じて小児科や発達外来を紹介される
- 専門機関(児童発達支援センターなど)で発達検査・観察・診断を実施
診断名がつくことよりも、
「どんな特性があるのか」「どうすれば生活がスムーズになるか」を知ることが何より大切です。
支援につながるサポート例
- 児童発達支援(就学前)
- 放課後等デイサービス(就学後)
- 保育園・学校との連携支援
行政や医療、教育のそれぞれがつながることで、
子どもが“安心して自分らしく生きられる”環境づくりが進んでいきます。
【完全ガイド】ADHD(注意欠如・多動症)の特徴と診断基準
「うちの子、なんだか落ち着きがないかも」「話を最後まで聞けないことが多い」──。
そんなときに耳にすることが多いのがADHD(注意欠如・多動症)という言葉です。
でも、実際にどんな特徴があるのか、どんな子がADHDなのか、イメージしづらいですよね。
ここでは、ADHDのタイプや症状、診断の流れをわかりやすく・やさしく解説します。
ADHDとは?3タイプに分かれる特徴を解説
ADHDは、「集中が続きにくい」「落ち着きがない」「思いつきで行動してしまう」といった特性が見られる発達障害のひとつです。
医学的には「Attention Deficit Hyperactivity Disorder(注意欠如・多動症)」と呼ばれます。
実はADHDといっても一つのタイプではなく、3つのタイプに分かれています。
① 不注意優勢型
集中力のコントロールが難しいタイプです。
- 話を聞いていても途中で別のことを考えてしまう
- 忘れ物や落とし物が多い
- 片づけが苦手で机の上がいつもごちゃごちゃ
こうした行動は「だらしない」わけではなく、脳の“注意を切り替える力”が少し弱いことが原因です。
一度にいろんな刺激を受け取ると、どれに集中していいのか分からなくなってしまうのです。
② 多動・衝動型
落ち着いて座っていることが難しかったり、思ったことをすぐに口に出してしまうタイプです。
- 授業中に立ち歩いてしまう
- 話を最後まで聞かずに答えてしまう
- 遊びや会話で順番を待てない
このタイプの子は、エネルギーがとても高く行動的。
ただ、頭の中に浮かんだことをすぐ実行してしまうため、“ブレーキをかける力”が弱いとも言えます。
でも見方を変えれば、行動力があり、好奇心旺盛でチャレンジ精神が強いタイプとも言えます。
③ 混合型
上の2つが両方見られるタイプです。
- 集中が続かないうえに、衝動的な行動も出やすい
- その日の調子や環境によって行動にムラがある
実際にはこの「混合型」が最も多いとされています。
また、年齢や環境によっても特徴の出方は変化します。
年齢・環境で変化するADHDの特徴
ADHDの行動は、年齢が上がるにつれて変化していくのも特徴です。
- 幼児期 → 動きが止まらず「多動」が目立つ
- 小学生 → 忘れ物・集中力のなさが目立ち始める
- 中学生〜高校生 → 衝動性よりも「ミスが多い」「段取りが苦手」といった面が中心に
つまり、成長とともに特性の表れ方が変わるということ。
「昔は落ち着きがなかったけど、今は集中のムラが気になる」など、
その子の発達段階によって支援のポイントも変わっていきます。
ADHDの主な症状と行動例
ADHDの特徴は大きく分けて3つです:
不注意・多動・衝動性。
これらが組み合わさって、日常生活の中でさまざまな困りごとが出てきます。
不注意(集中が続かないタイプ)
- 忘れ物・落とし物が多い
- 話を聞いている途中で別のことを始める
- 授業中や遊びの途中で集中が途切れる
「人の話を聞かない」「だらしない」と思われがちですが、
注意のスイッチを入れ続けることが難しいだけなんです。
多動(体がじっとしていられないタイプ)
- 座っていても体をゆらしたり手を動かしたりする
- 一人で静かに遊ぶのが苦手
- 何かしていないと落ち着かない
これは「わざと動いている」わけではなく、
体を動かすことで集中を保とうとしている脳の自然な働きでもあります。
衝動性(思いつきで行動してしまうタイプ)
- 順番を待てない
- 思ったことをすぐ口にしてしまう
- 感情が抑えられずトラブルになる
この衝動的な行動も、「わがまま」や「自分勝手」ではなく、
脳の“抑制機能”が未熟なために起こる自然な反応なんです。
“叱っても直らない”理由は脳の発達特性にある
「何度注意しても同じことをする」「言ってもわからない」──。
これはママたちが最も悩むポイントですよね。
でも実は、ADHDの子どもにとって「叱られること」はあまり効果がありません。
なぜなら、「どうすればいいか」を頭で整理して行動に移す力が弱いからです。
叱られることで「また怒られた」「失敗した」というネガティブな記憶が増えてしまい、
逆に自信をなくしてしまうこともあります。
だからこそ、
「ダメ!」ではなく「こうすると上手くいくよ」と具体的に伝えることが大切。
行動を正すよりも、成功体験を積ませて“できた!”を増やす方が長い目で見て成長につながります。
ADHDの診断基準と検査方法
「うちの子、ADHDかも?」と思っても、すぐに診断できるわけではありません。
専門的な診断には、時間をかけた観察と複数の情報が必要です。
DSM-5に基づく診断のポイント
ADHDは、アメリカ精神医学会の「DSM-5(精神疾患の診断と統計マニュアル)」の基準をもとに診断されます。
主な診断基準は次のようなものです:
- 不注意または多動・衝動の症状が12歳以前から見られる
- その行動が家庭や学校など複数の場面で現れている
- 学業・社会生活に支障をきたしている
つまり、ただ「落ち着きがない」「集中できない」だけではADHDとは言えません。
年齢に合わない行動が、日常生活で続いているかが大きなポイントになります。
医療機関・発達支援センターでの相談ステップ
- 保健センターや園・学校での相談
→ 気になる行動を伝えることから始めましょう。 - 小児神経科・発達外来などの専門医を受診
→ 医師が問診・発達検査・行動観察を行います。 - 必要に応じて心理士・作業療法士の検査へ
→ 注意力・記憶力・感情のコントロールなどをチェック。
診断がついた後は、「どう支援していくか」が大切です。
児童発達支援や放課後等デイサービスなど、専門の支援機関を利用することで子どもの生活がぐっと安定することも多いです。
【図でわかる】ADHDと発達障害の違いをやさしく整理!
「ADHDって発達障害なの?」「ASDとは別なの?」──
こんなふうに、“ADHDと発達障害の関係”に混乱するママはとても多いです。
実はADHDは、「発達障害」という大きな枠の中に含まれるひとつのタイプなんです。
ここでは、ADHD・ASD・LDの違いをわかりやすく整理していきます。
図や表で理解すると、「どう違うのか」がすっと頭に入ってきますよ。
ADHDは発達障害の中のひとつ
まず前提として、「発達障害」という言葉は“総称”です。
その中に、主に3つのタイプが含まれます。
発達障害
├── 自閉スペクトラム症(ASD)
├── 注意欠如・多動症(ADHD)
└── 学習障害(LD)
つまり、ADHDは発達障害の“中のひとつ”として分類されます。
- ASDは「人との関わり方やこだわり」に特徴があるタイプ
- ADHDは「集中力や行動のコントロール」に特徴があるタイプ
- LDは「読む・書く・計算など特定の学習分野」に困難があるタイプ
それぞれの特性は重なり合う部分も多く、“混合タイプ”として見られる子も珍しくありません。
だからこそ、「この子はどれ?」と一つに決めるよりも、
“どんな特性が強く出ているのか”を理解することが大切なんです。
ADHDとASD(自閉スペクトラム症)の違い
ADHDとASDは、同じ発達障害の仲間ですが、特徴の出方や困りごとの種類はかなり違います。
ただ、行動が似て見えることも多いため、よく混同されるんです。
以下の表で、2つの違いをわかりやすく整理してみましょう。
| 比較項目 | ADHD | ASD(自閉スペクトラム症) |
|---|---|---|
| 主な特性 | 不注意・多動・衝動 | 対人関係・こだわり |
| 行動の傾向 | 思いつき行動・忘れ物が多い | ルール重視・変化が苦手 |
| コミュニケーション | 話を遮る・順番を待てない | 一方的に話す・空気を読みづらい |
ADHDの特徴
ADHDの子は、行動のコントロールが難しいタイプです。
「気づいたら動いてる」「ついしゃべっちゃう」といった“衝動的な行動”が目立ちます。
例えば、
- 授業中に立ち上がってしまう
- 思ったことをすぐ口にする
- 集中しようとしても別のことに気を取られる
これは“わざと”ではなく、脳の「ブレーキをかける機能」が未発達なため。
本人も「いけない」とわかっていても、体が先に動いてしまうんです。
ASDの特徴
一方ASDの子は、人との関わりや変化への対応が苦手なタイプです。
「相手の気持ちを読み取るのが難しい」「自分の世界を大切にする」といった傾向があります。
例えば、
- 会話が一方的になりやすい
- スケジュールが変わると不安になる
- 特定の遊びや言葉に強くこだわる
ASDの子にとって、「変化」や「曖昧さ」はとてもストレス。
ルールやパターンが決まっていると安心するので、マイルールが強く出ることもあります。
似ているようで全然違う!
たとえば「友だちとのトラブル」という場面でも、原因は違います。
- ADHDの子 → 話の途中で割り込んでしまい、相手を怒らせる
- ASDの子 → 相手の気持ちがわからず、結果的に距離を取られる
行動は似て見えても、根っこにある理由はまったく別なんです。
そのため、支援の方法も変わってきます。
ADHDには「環境を整えて集中を助ける支援」、
ASDには「相手の気持ちやルールを“見える化”する支援」が効果的です。
ADHDとLD(学習障害)の違い
次に、ADHDとLD(学習障害)の違いについて見ていきましょう。
どちらも「勉強でつまずく」ことがあるため、混同されやすいタイプです。
ADHDの場合
ADHDの子が勉強でつまずく理由は、“集中が続かないこと”や“行動のコントロールが難しいこと”。
問題自体を理解する力はあるのに、
- 宿題を始める前に気がそれてしまう
- 手順を飛ばしてミスをしてしまう
- 注意が他に向いてしまい、ケアレスミスが多い
といった形で、「本来の力を出しきれない」ことが多いです。
LDの場合
一方のLDは、“特定の学習領域”だけが極端に苦手という特徴があります。
- 文字が反転して見えるように感じる(読字障害)
- 書くスピードが極端に遅い(書字障害)
- 数の概念を理解しにくい(算数障害)
つまりLDの子は、「集中できない」のではなく、
“特定のスキルそのものを脳がうまく処理できない”状態なんです。
両方を併発するケースも
実際には、ADHDとLDの両方をもつ子どもも少なくありません。
集中が続かない+学習スキルの難しさ、両方が重なることで、
「やる気がないように見える」「努力が足りない」と誤解されがちです。
でも本当は、脳の特性が重なって見えづらくなっているだけ。
支援の方向性を間違えないためにも、専門的な評価がとても大切です。
ADHDと性格・しつけの問題との違い
最後に、よくある誤解についてお話しします。
「落ち着きがないのは性格のせい?」「ちゃんとしつければ治るの?」──
これは多くのママが一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
結論から言うと、ADHDは性格やしつけの問題ではありません。
脳の発達の特性によって、注意や感情をコントロールする力が生まれつき少し弱いだけなんです。
「だらしない」「やる気がない」ではない
ADHDの子どもが忘れ物をしたり、何度言っても同じ失敗をするのは、
「怠けている」からではなく、「仕組み上そうなってしまう」だけ。
脳の前頭前野(行動をコントロールする部分)の働きが未熟なため、
“次に何をするか”を頭の中で整理するのが難しいのです。
叱るより「できた瞬間を褒める」
ADHDの子は、「できた!」という成功体験が次のやる気につながります。
だからこそ、叱るよりも「今のやり方、よかったね!」と肯定的に伝える方がずっと効果的。
たとえば、
- 忘れ物をせずに登園できた → 「今日はバッチリだったね!」
- 宿題を途中まで頑張った → 「途中までできたね、すごいよ!」
こうした“できた瞬間”を認めることで、脳が「このやり方がいい」と覚えていくんです。
つまり、叱るよりも“褒めて伸ばす”方が、子どもの脳の仕組みに合っているんですね。
【誤解注意】ADHDと発達障害が混同されやすい理由とは?
「ADHDとASDって、どっちも“発達障害”なんでしょ?」
「うちの子、ADHDなのかASDなのか、どっちかわからない…」
──こんなふうに感じたこと、ありませんか?
実は、ADHDとASD(自閉スペクトラム症)は行動がとても似て見えることが多く、
専門家でも診断に慎重になるほどなんです。
ここでは、「なぜ混同されやすいのか」「どんな違いがあるのか」を、
ママ目線でわかりやすく解説していきます。
ADHDとASDが似て見える行動の例
「集中できない」「マイペース」「空気を読まない」──
こういった行動、実はADHDにもASDにもよく見られる特徴なんです。
でも、その“見た目”が似ているだけで、困りごとの原因はまったく違うケースが多いんです。
たとえば「集中できない」場合
- ADHDの子は:外からの刺激に反応しやすく、注意がそれてしまう。
→ 音・動き・話し声などに敏感で、集中が中断されやすい。 - ASDの子は:興味がないことに注意を向けづらい。
→ 興味の対象が明確で、関心のないことには意識が向かない。
つまり、どちらも「集中できない」ように見えても、
ADHDは「集中のスイッチが安定しない」、
ASDは「興味のスイッチが限られている」──という違いがあります。
「マイペースで空気を読まない」と言われる場合
- ADHDの子は:思いついたらすぐ行動してしまう。
→ 相手の話を遮ってしまったり、順番を待てなかったり。 - ASDの子は:相手の気持ちや場の雰囲気をつかむのが難しい。
→ 無意識のうちに話題がずれてしまったり、反応が薄く見えたり。
どちらも「協調性がない」と誤解されがちですが、
ADHDは“衝動的”、ASDは“認知のずれ”による違いです。
「忘れ物・ミスが多い」場合も原因は異なる
- ADHDの子:注意が散漫で「やるべきことを覚えていられない」
- ASDの子:段取りが苦手で「順序立てて行動できない」
どちらも同じような結果に見えるけれど、
実は脳の使い方の違いが大きく関わっています。
こうして見てみると、行動の「表面」だけを見ると似ているけれど、
「なぜそうなるのか」という“背景”が全く違うことが分かりますよね。
ADHDの子には「環境の刺激を減らす工夫」、
ASDの子には「手順やルールを見える化する工夫」が効果的──といったように、
原因を理解してこそ、支援の方向が変わるのです。
幼児期は診断が難しい?「特性の重なり」と診断の変化
「発達相談に行っても、“まだ様子を見ましょう”と言われた」
「以前はADHDと言われたけど、成長してASDの特徴が強くなった気がする」
──実はこうした話は、決して珍しくありません。
発達障害の診断は、年齢や発達段階によって変化することがあるんです。
幼児期は「特性の重なり」が多い時期
幼児期(3〜6歳ごろ)は、まだ脳の発達が進行中。
そのため、ADHD・ASD・LDなどの特徴が重なって見えることがあります。
たとえば、
- 幼児期は「落ち着きがない(ADHD的)」ように見えても、
→ 成長すると「こだわりが強い(ASD的)」特徴がはっきりしてくる。 - 逆に、小学生で「ASDっぽいこだわり」が目立っていた子が、
→ 思春期には「注意の切り替えの難しさ(ADHD的)」が目立つようになる。
こうした変化は、脳の発達や環境との相互作用による自然な現象なんです。
成長とともに診断名が変わることもある
専門的な見方をすると、発達障害は「診断名そのもの」よりも、
どんな特性が生活に影響しているかを重視します。
そのため、
- 以前は「ASD」と診断されたけれど、今は「ADHDの傾向が強い」と言われる
- 最初は「グレーゾーン」と言われたけれど、学齢期に診断がついた
──といったケースもよくあります。
これは誤診ではなく、成長や環境によって“特性の表れ方”が変わるからなんです。
「今困っていること」をベースに支援を考えることが大切
診断名にとらわれすぎると、「ASDだから」「ADHDだから」と考えがちですが、
実は一番大事なのは、“今この子が何に困っているか”を見つけること。
たとえば、
- 集中できない → 環境を静かに整える
- こだわりが強い → 変化を予告して安心感をもたせる
- 衝動的に動く → スケジュールや手順を見えるようにする
このように、診断名ではなく「行動の理由」に合わせた支援を考えることで、
子どもがラクに過ごせる時間が増えていきます。
【チェックリスト付き】ADHD・発達障害の特徴を見分けるポイント
「うちの子、ちょっと落ち着きがないかも?」
「どうして話を聞いてくれないんだろう?」
そんな“ちょっと気になる行動”が、実は発達障害やADHDのサインであることもあります。
もちろん、ひとつの行動だけで判断することはできませんが、
早めに気づくことで、子どもに合った関わり方や支援を始めるきっかけになります。
ここでは、年齢ごとに気づきやすいサインと、
「相談したほうがいいかも?」と思ったときの相談先をわかりやすくまとめました。
未就学児(3〜6歳)で気づくサイン
未就学児期(3〜6歳)は、発達の差が大きく出やすい時期。
「みんなできているのに、うちの子だけちょっと違うかも…」と感じるママも多いでしょう。
でも、この時期の“違い”は決して悪いことではありません。
脳の発達スピードがゆっくりな子もいれば、得意・不得意がはっきりしている子もいます。
じっとしていられない
- 座っていられるのはせいぜい数分
- ごはん中やお話し中に立ち上がる
- 外では走り回りっぱなし
これは、ADHDの「多動性」や「衝動性」が関係している場合があります。
脳が常に刺激を求めているため、体を動かすことでバランスを取っていることも多いです。
ただし、3〜4歳ごろは誰でもじっとしていられない時期なので、
「落ち着きのなさが極端に続くかどうか」を見極めるのがポイントです。
話を最後まで聞けない
- 「〜してね」と言っても途中でいなくなる
- 質問に最後まで答えられない
- 絵本の読み聞かせも途中で別の話に
これは注意の切り替えや集中を保つ力が未熟なため。
ADHDの「不注意」の特徴に似ていますが、興味があることにはしっかり集中できることも多いです。
つまり、「集中できない」ではなく「集中のスイッチが偏っている」と考えるとわかりやすいです。
🔹ルール遊びが苦手
- 順番を守るのが難しい
- 負けると泣いてしまう
- 集団での遊びがうまくいかない
ルールを理解していても、「待つ」や「切り替える」が難しいのがADHDの特徴です。
また、ASD(自閉スペクトラム症)の子は、「自分のペースが乱れること」自体に強いストレスを感じることもあります。
どちらの場合も、「ルールを守らない=わがまま」ではなく、
“ルールを守るための力がまだ育っていない”という見方が大切です。
【3〜6歳で気づくチェックリスト】
- じっと座っていられない
- 落ち着きがない・多動が目立つ
- 話を最後まで聞けない
- 忘れ物・なくし物が多い
- お友だちとのトラブルが多い
- こだわりが強く、予定の変更に混乱する
3つ以上当てはまる場合は、「相談してみようかな」と思ってOKです。
小学生以降で気づくサイン
小学校に入ると、集団生活や学習の中で“発達の特性”がはっきりしてくることがあります。
家庭では気づかなかったことが、「学校のルールの中で難しさとして表れる」のがこの時期です。
忘れ物が多い
- 毎日の持ち物をチェックしても、何かしら忘れてくる
- プリントを出し忘れる
- 筆箱やノートをよくなくす
これはADHDの「不注意」タイプに多い特徴。
脳の「ワーキングメモリ(作業記憶)」がうまく働かず、一度に複数のことを覚えておけない状態なんです。
「昨日言ったのに…」とつい叱りたくなりますが、
“わざと”ではなく“忘れてしまう仕組み”があると理解してあげることが大切です。
宿題に集中できない
- 勉強中にすぐ立ち上がる
- 机に向かっても他のことを始めてしまう
- 取りかかるまでに時間がかかる
これは注意の持続や切り替えが難しいため。
ADHDの子にとって、「始めること」自体がとてもハードルが高いのです。
コツとしては、
✅ 宿題を「5分ずつ」などの短い区切りで進める
✅ 「終わったら好きなことをしてOK」と明確に伝える
このように、「小さな成功体験を積み上げる工夫」が効果的です。
整理整頓ができない
- 机の中がぐちゃぐちゃ
- プリントをどこに入れたかわからない
- 部屋の片づけが続かない
これは「片づける力がない」のではなく、
“順序立てて考える力(実行機能)”が苦手なことが多いです。
1つずつ指示を出したり、写真で「片づけた状態」を見える化したりすることで、
少しずつ「整理する感覚」をつかめるようになります。
【小学生以降で気づくチェックリスト】
- 忘れ物や提出忘れが多い
- 勉強中に集中が続かない
- 宿題を始めるのに時間がかかる
- 集団行動が苦手
- 感情のコントロールが難しい
- 片づけが苦手・部屋が散らかりやすい
当てはまる項目が多いほど、「発達特性が生活に影響している」可能性があります。
こんなときは相談を!早期発見のための相談先
「相談って、診断してもらうほどじゃないとダメ?」
「まだ小さいのに、発達相談なんて早すぎる?」
──そんなことはありません。
発達障害やADHDの支援は、“気になる段階”で相談してOK!
むしろ、早めに動くことで子どもへの理解が深まり、ママの不安も軽くなります。
相談先の例
- 児童発達支援センター
→ 専門スタッフ(心理士・作業療法士など)が発達の状態を見てくれます。 - 小児発達外来・小児神経科
→ 医師による発達検査・診断が受けられます。
(必要に応じて支援機関を紹介してもらえることも) - 市区町村の子育て支援センター・保健センター
→ 無料で相談でき、家庭支援サービスの情報ももらえます。
相談のタイミングの目安
- 保育園や幼稚園で「集団行動が難しい」と言われたとき
- 家でも園でも“似た行動の困りごと”が見られるとき
- 「このままで大丈夫かな?」と感じたとき
こうした小さなサインが、相談のきっかけとして最も大切なタイミングです。
相談は“早ければ早いほど安心”
発達障害やADHDは、早期に気づいて環境を整えることで、
子どもが自分らしく成長できる可能性がぐんと広がります。
相談したからといって、すぐに「診断」がつくわけではありません。
「今どんなサポートができるか」を一緒に考えるためのスタート地点です。
【家庭でできる】ADHD・発達障害の支援と対応のコツ
「どう接すればいいのか分からない」
「つい叱ってしまって、自己嫌悪…」
──そんな思いを抱えているママは、本当にたくさんいます。
でも大丈夫。
ADHDや発達障害の子どもを支援するコツは、“特別な方法”ではなく、“理解と環境の工夫”です。
子どもたちは、叱られるよりも「わかりやすい仕組み」や「成功体験」でぐんと伸びます。
ここでは、家庭・園・学校・医療機関それぞれでできる具体的な支援方法を紹介します。
家庭で今日からできる工夫
家庭での工夫は、「子どもが見通しをもてること」と「できた!という成功体験を積むこと」がカギです。
視覚的にわかるスケジュールボードを使う
ADHDや発達障害の子どもは、頭の中で時間の流れをイメージするのが苦手です。
そのため「次に何をすればいいか」が分からなくなり、行動が止まったり混乱したりします。
そんなときに役立つのが、スケジュールボードです。
- 朝の支度
- ごはん
- 歯みがき
- 登園
といった1日の流れを、イラストや写真で“見える化”するだけで、ぐんとスムーズになります。
たとえば100均のホワイトボードに、マグネットや手作りカードを貼るだけでもOK。
「終わったらカードを外す」など、視覚的に達成感を感じられる仕組みにすると効果的です。
小さな成功体験を積ませる「肯定的な声かけ」
ADHDの子どもは、「うまくいかないこと」が多くて、自信をなくしやすい傾向があります。
だからこそ、ママやパパの声かけがとても大切です。
つい「どうしてできないの?」と言いたくなりますが、
その代わりに「できたところ」「がんばったところ」を具体的に褒めることを意識してみてください。
例:
- ✖「ちゃんとしなさい!」
- ◎「今、着替えを始められたね。えらい!」
このように、“行動の一歩”を褒めることで、子どもは「次もがんばろう」という気持ちになります。
褒めるポイントは、“結果”よりも“過程”を認めること”。
「がんばったね」「自分でできたね」の積み重ねが、子どもの自己肯定感を育てます。
集中しやすい環境づくりのポイント
ADHDの子どもは、音や光、視覚的な刺激に影響を受けやすいです。
たとえば、宿題をしていても、テレビやおもちゃが目に入ると注意がそれてしまいます。
集中しやすい環境をつくるには、以下のような工夫が有効です。
- 勉強スペースを壁向きにする
- テーブルの上には必要な物だけを置く
- 静かな時間帯に取り組む
- タイマーを使って「あと○分」と区切る
特に“時間の見える化”は効果的。
「あと5分でおしまいね」と予告しておくことで、切り替えの準備ができます。
保育園・学校での支援の実際
家庭での工夫と同じくらい大切なのが、園や学校との連携です。
「家庭ではこういう特徴があります」と共有することで、支援の方向性が統一され、子どもも安心して過ごせます。
先生との情報共有と一貫した対応がカギ
発達特性のある子どもは、環境が変わると混乱しやすいです。
だからこそ、家庭と学校が“同じ言葉・同じ対応”で関わることが大切。
たとえば、
- 家で使っているスケジュール表を園にも共有する
- 家庭で使う声かけ(例:「あと1回ね」「おしまいカード」)を先生にも伝える
- 苦手な場面(音・集団・切り替え)を事前に知らせておく
このように情報を共有すると、子どもが安心しやすくなります。
「集団の中で安心できる居場所」を確保する工夫
ADHDや発達障害の子どもは、集団の中で「自分の居場所」を見失いやすいことがあります。
「みんなと同じように動けない」「注意されることが多い」と感じると、
学校が“つらい場所”になってしまうことも。
そんなときは、先生と一緒に安心できるスペースや時間をつくることが大切です。
たとえば、
- 図書室や保健室など、落ち着ける場所を確保する
- 授業中に「少し立ってもOK」と決める
- 休み時間に“ひとりで過ごせる時間”を許す
このような柔軟な対応が、子どもの安心感と自己コントロールを育てます。
医療・発達支援サービスの活用方法
発達障害やADHDの支援は、家庭だけで抱え込まなくても大丈夫。
専門家の力を借りることで、ママも子どももずっとラクになります。
発達外来・心理検査・作業療法などの併用支援
まずは小児科や発達外来で相談するのが第一歩です。
必要に応じて、以下のような支援が受けられます。
- 心理検査(WISCなど):認知の強み・弱みを明らかにする
- 作業療法(OT):集中・感覚・動作のバランスを整える練習
- 言語療法(ST):ことばやコミュニケーションの支援
これらを組み合わせることで、“その子に合った支援プラン”を立てることができます。
専門家に相談するときの準備ポイント
初めて相談するときは、どこから話せばいいか迷いますよね。
以下のようなメモを準備しておくと、スムーズに伝えられます。
- 気になる行動(例:落ち着かない・忘れ物・パニックなど)
- 家や園・学校での様子の違い
- できること・得意なこと
- 相談したいこと(例:「叱り方」「学校での支援」など)
これだけでも、専門家が全体像を把握しやすくなります。
また、相談後は「聞いたことをメモする」ことも大切。
支援は一度きりではなく、“成長とともに見直していく”ものだからです。
【境界ケース】ADHDと発達障害のグレーゾーンとは?
「病院で“様子を見ましょう”と言われたけど、やっぱり気になる…」
「診断はつかなかったけど、うちの子ちょっと生きづらそう…」
──そんなお子さんは、いわゆる“グレーゾーン”にあたるかもしれません。
最近では、「発達障害の傾向があるけれど、診断基準を満たさない」という子どもが増えています。
しかし、その中には日常生活でしっかりと支援が必要なケースもあります。
ここでは、「グレーゾーン」とはどんな状態か、そして家庭でどう支えていけばいいのかを、わかりやすく整理していきます。
診断がつかない“グレーゾーン”の子どもとは
「グレーゾーン」とは、簡単に言うと
“発達の特性はあるけれど、診断基準を満たすほどではない”状態のことです。
つまり、発達障害(ADHD・ASD・LDなど)の診断はつかないけれど、
生活の中で「困りごと」がある子どもたちを指します。
明確な診断が出ないが、生活に困難があるケース
グレーゾーンの子どもによく見られる特徴には、次のようなものがあります。
- 集中が続かず、注意がそれやすい
- 集団行動で遅れがち・マイペース
- 感情の切り替えが難しい
- 忘れ物が多く、整理整頓が苦手
- 空気を読むのが苦手でトラブルになりやすい
これらはADHDやASDの特徴に似ているため、周囲からは「発達障害では?」と思われることもあります。
しかし、発達の段階や環境によって行動が変化することも多く、
医師が診断を出すのを慎重に判断するケースも少なくありません。
支援を受けづらい現状とその課題
実はこの「グレーゾーン」という状態、
一番支援が必要なのに、一番支援が届きにくい立場でもあるのです。
たとえば、
- 医療機関では「診断がないから対象外」
- 学校では「普通学級だから特別支援の枠に入らない」
- 行政でも「発達障害者支援法の対象外」とされる
このように、制度の狭間で支援が受けづらい現実があります。
ただし、最近では保育園・学校・地域でも、
診断の有無に関係なく“発達特性に応じた支援”を行う流れが広がっています。
つまり、「診断がない=何もできない」ではなく、
“今ある困りごと”に焦点をあてたサポートができる時代になってきています。
グレーゾーンの子への関わり方と支援のヒント
グレーゾーンの子どもたちに大切なのは、
“診断名よりも、困っている理由を理解すること”。
子どもの「困っている姿」は、本人が悪いのではなく、
環境や関わり方がその子の特性に合っていないだけのことも多いのです。
診断にこだわらず「困りごと」に焦点をあてる
たとえば、
- 集中できない → 刺激が多い環境を見直す
- 集団行動が苦手 → 小集団での活動に変えてみる
- 感情が爆発しやすい → スケジュールを見える化して安心感をもたせる
このように、「どうしてこの行動が出るのか?」を考えて対応することが、
グレーゾーンの子どもへの最大の支援になります。
また、ママが「うちの子は発達障害ではないのに…」と悩む必要はありません。
発達障害というのは、あくまで“特性の名前”であって“ラベル”ではないのです。
環境調整・感覚の理解・安心できる生活リズムを整える
グレーゾーンの子どもは、感覚の過敏さや疲れやすさを抱えていることも多いです。
たとえば、
- 音や光に敏感で、騒がしい場所でパニックになる
- 衣服のタグや素材が気になって集中できない
- 頑張りすぎて家に帰るとぐったりする
こうした子どもには、「無理をさせない環境調整」がとても大切です。
具体的には、
- 静かなスペースで過ごす時間をつくる
- 衣服や生活用品を“快適さ優先”にする
- 「今日はこれだけできたね」と小さな成功を認める
また、生活リズムを整えることも効果的です。
睡眠・食事・活動のリズムを安定させるだけで、情緒も安定しやすくなります。
家庭でできる「安心感を育てる」関わり方
グレーゾーンの子どもたちは、日常の中で「叱られる経験」が多くなりがちです。
だからこそ、家では安心できる場所であることが何よりの支えになります。
ポイントは3つ:
- できたことを見つけて言葉にする
→ 「自分で片づけできたね」「今日は泣かずに頑張れたね」 - スケジュールを見せて見通しをもたせる
→ 予定を見える形にすると安心しやすい - 休む時間を“悪いこと”としない
→ 疲れやすい子は、休むことで回復します
グレーゾーンの子は、「ちゃんとできるけど、疲れやすい」「頑張りすぎる」タイプも多いです。
そのため、“できない”ではなく“がんばりすぎている”と捉える視点がとても大切です。
【理解が支援の第一歩】ADHDと発達障害の違いを知る意味
「発達障害」と聞くと、どこか難しく感じたり、
「うちの子は普通なのに…」と戸惑ってしまうママも少なくありません。
でも、まず知っておいてほしいのは、
“発達障害=できない”ではなく、“得意と苦手に差がある”ということ。
ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)などは、
それぞれ違った「脳の特性」があるだけで、
一人ひとりに“強み”がちゃんとあるんです。
その違いを知ることは、子どもを“ラベルで見る”ためではなく、
“その子らしさを理解して支える”ための第一歩なのです。
違いを知ると「子どもの得意」が見えてくる
ADHDや発達障害の違いを知ることは、
“診断名を覚える”ことではありません。
大切なのは、「子どもがどんなときに困るのか」「どんなときに輝くのか」を見つけることです。
「できない」より「どうすればできるか」を探す姿勢
つい「集中できない」「片づけができない」「落ち着きがない」など、
“できないところ”ばかりが目につきがちですよね。
でも、その裏側には、
「集中しすぎる」「思いついたらすぐ行動できる」「好奇心が強い」といった
ADHDならではの長所が隠れていることもあります。
たとえば:
- 「忘れ物が多い」→ 興味があることに夢中になれるタイプ
- 「衝動的」→ 行動力やひらめきがある
- 「落ち着きがない」→ エネルギーが高く、活動的
つまり、「できない」を責めるよりも、
「どうすればその力を生かせるか」を考える視点がとても大切なんです。
子どもの強みに目を向けることで親子関係がラクになる
ADHDや発達障害の子どもは、
叱られる経験が多くなる分、自信をなくしやすい傾向があります。
でも、ママが「この子はこういう良さがある」と理解して関わるだけで、
親子の関係が驚くほどラクになります。
たとえば、
- 「落ち着きがない」→ 体を動かすことが得意
- 「じっとできない」→ クリエイティブな発想をもっている
- 「マイペース」→ 自分の世界を大切にできる
ママが“苦手”より“得意”に目を向けることで、
子どもは「受け入れられている」と感じ、自分らしく伸びていきます。
そして不思議なことに、
ママの見方が変わると、子どもの行動も少しずつ落ち着いてくることが多いのです。
ママ自身の心を軽くする“考え方のコツ”
発達特性のある子を育てる中で、
「どうしてうまくいかないんだろう」「私の育て方が悪いのかな」と、
自分を責めてしまうママは本当に多いです。
でも、そんなときこそ思い出してほしいのは、
「ママが悪いわけではない」ということ。
そして、完璧な支援を目指さなくていいということです。
「完璧な支援」より「理解して寄り添う姿勢」で十分
子どもの発達支援は、専門的な知識がなくてもできます。
大切なのは、「この子は何に困っているのかな?」と考える姿勢です。
たとえば:
- 集中できないなら → 音や刺激を減らしてみる
- 感情が爆発するなら → 事前に予定を伝えて安心させる
- 苦手な作業があるなら → 小さく分けて達成感を与える
こうした小さな工夫の積み重ねが、“家庭でできる最良の支援”です。
そして、すべてを完璧にこなす必要はありません。
「今日はできた」「明日は休もう」くらいでちょうどいい。
ママが安心していることが、子どもにとって一番の支えになるんです。
支援機関・SNS・地域とのつながりを活用して孤立を防ぐ
発達障害の子育ては、一人で抱え込むと本当に大変です。
でも、世の中には同じように悩みながら、前を向いているママがたくさんいます。
たとえば:
- 発達支援センターや児童発達支援では、専門家と一緒に困りごとを整理できます。
- 保健センターや地域子育て支援では、無料相談や交流会が開かれています。
- SNSやオンラインコミュニティでは、全国のママたちとつながることができます。
こうしたつながりをもつことで、
「私だけじゃない」「わかってもらえる」という安心感が得られます。
また、他の家庭の工夫を知ることで、
「こうすればいいんだ!」と新しい視点が生まれるきっかけにもなります。
【まとめ】ADHDと発達障害の違いを知ることが、子どもの未来を変える
ここまで読んでくださったママさん、本当におつかれさまでした。
ADHDや発達障害のことを理解しようとするその姿勢こそが、
すでにお子さんへの最高の支援の第一歩です。
ADHDは発達障害の一種であり、混同されやすいが理解すれば支援がしやすい
ADHD(注意欠如・多動症)は、発達障害の一つです。
ただし、自閉スペクトラム症(ASD)や学習障害(LD)と特性が重なって見える部分が多いため、
「どっちなんだろう?」と混乱してしまうこともありますよね。
でも実は、混同されやすいからこそ“理解”が大切なんです。
たとえば、
- ADHDの「忘れっぽい」「集中できない」は、“注意の切り替えが苦手”という脳の特性。
- ASDの「空気を読めない」「こだわりが強い」は、“安心できる予測性”を求める特性。
どちらも“わざと”ではなく、“脳の特性からくる行動”なんです。
そう理解できると、「叱る」ではなく「助ける」方向に意識が変わるんです。
理解が深まれば、ママの関わり方も自然と変わります。
“問題行動”が“特性”に見えてくると、支援がグッとしやすくなるんですよ。
診断名よりも「特性理解」と「環境調整」が最優先
多くのママが気になるのが、「診断名がつくかどうか」。
でも実は、そこにとらわれすぎないことがとても大事です。
診断名はスタート地点であって、ゴールではありません。
大切なのは、
- 「この子はどんな場面で困っているのか」
- 「どういう環境なら安心して過ごせるのか」
- 「どんなサポートで力を発揮できるのか」
──こうした“特性の理解”と“環境の調整”です。
たとえば、
- 集中できない → 静かなスペースをつくる
- 集団が苦手 → 小集団や一人時間を確保する
- 感覚が敏感 → 衣服や音の刺激を減らす
たったそれだけでも、子どもがグッと過ごしやすくなることがあります。
つまり、「診断よりも“日常の困りごと”に注目する」ことが、
本当の意味での支援につながるんです。
子どもの“困りごと”を見極め、家庭・園・学校で連携して支えていこう
ADHDや発達障害の子どもを支えるとき、
ママだけが頑張る必要はありません。
むしろ、家庭・園・学校が連携して支えることがとても大切です。
たとえば、家庭では「朝の支度のサポート」、
園では「見通しが持てるスケジュール提示」、
学校では「集中しやすい座席配置」など、
それぞれの場面で子どもが安心して過ごせる工夫を取り入れることができます。
また、情報を共有すると、支援が一貫しやすくなります。
「家ではこうしています」「学校ではこう工夫しています」と伝え合うことで、
子どもが混乱せずに安心できる環境をつくれます。
ママが一人で抱え込まず、先生や専門家と一緒に考えることで、
子どもも「守られている」と感じ、少しずつ自信を取り戻していきます。
最後に:理解は“子どもの未来を変えるチカラ”になる
ADHDや発達障害の理解を深めることは、
決して「難しい医療知識を学ぶこと」ではありません。
「この子はどう感じているのかな?」と想像してみること。
それが、いちばんの“理解”です。
そして、理解が生まれると、
子どもの行動が“問題”から“個性”へと見え方が変わります。
- 「落ち着きがない」→ エネルギーがあふれている
- 「忘れ物が多い」→ 夢中になれることを見つける力がある
- 「マイペース」→ 自分のペースを大切にできる
このように、見方を変えるだけで“できない子”が“可能性のある子”に変わるのです。
ママの理解は、まさに子どもの未来を変えるチカラ。
そのチカラがあれば、どんな特性も、きっと子どもの“強み”になります。
焦らず、比べず、
「うちの子のペースで大丈夫」と信じてあげてくださいね。
以上【ADHDと発達障害の違いとは?特徴・診断・見分け方を専門家がわかりやすく解説!】でした

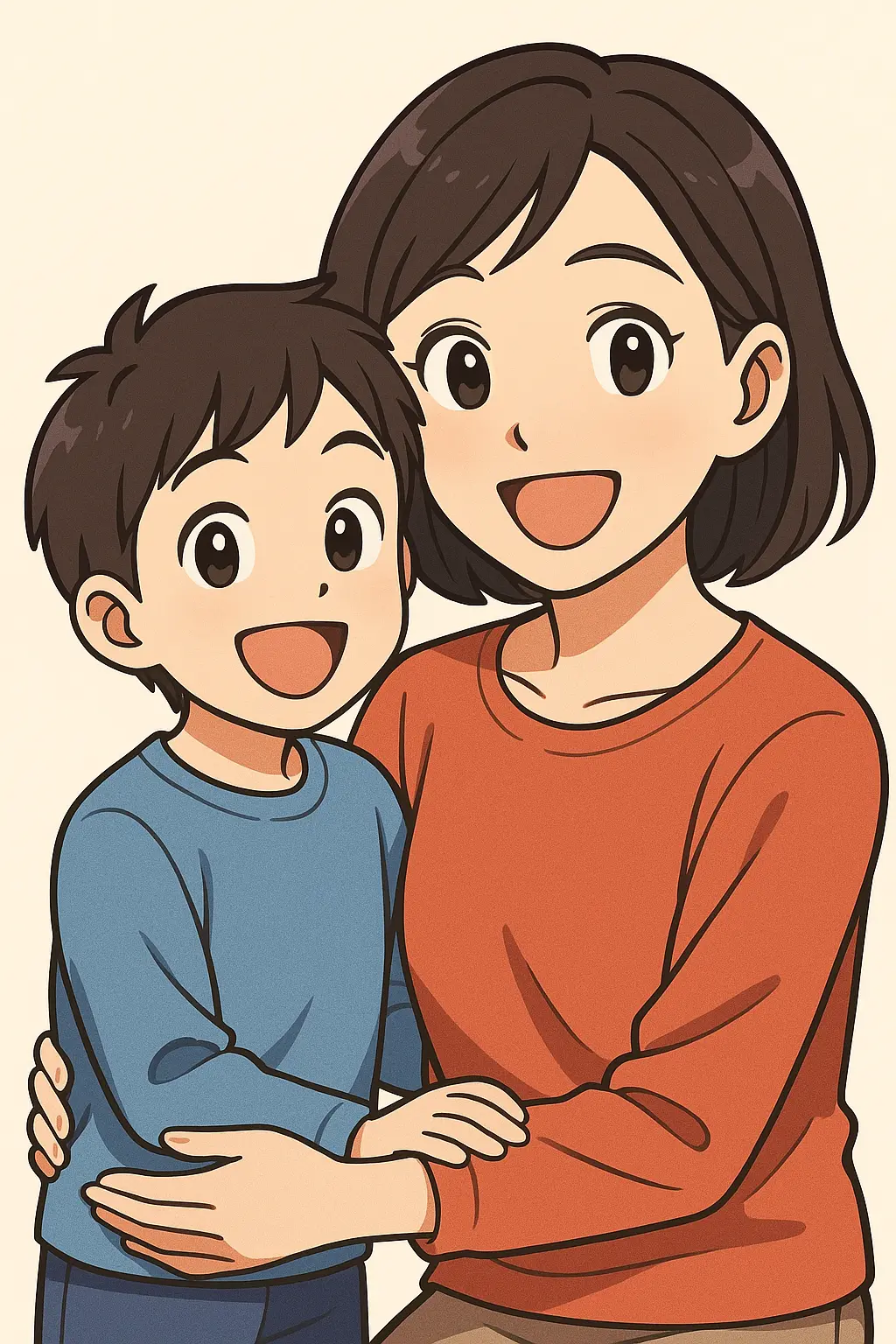









コメント