ADHDの子どもが「頭の中がうるさい」と感じる本当の理由
ADHDの子どもが「頭の中がうるさい」と言うとき、親としては「え? 今、家の中は静かだよ?」と驚くことがありますよね。
でも実はこの“うるささ”、外の音ではなく、子どもの脳の中で起こっていることなんです。
頭の中で、いろんな考えや感覚、記憶、音の情報が一気に流れ込んでしまう。
それが整理できずに「頭がごちゃごちゃ」「静かにできない」という感覚につながります。
「頭の中がうるさい」ってどういう状態? ADHDの子に起こる“脳の混乱”とは
ADHDの子は、脳の中の情報を整理する力が少し苦手な傾向があります。
たとえば、ママが話しかけている声・冷蔵庫の音・テレビの音・自分の考え…これらを同時にキャッチしてしまう。
本来なら必要な情報だけを選んで処理するのが理想ですが、ADHDの脳では“全部の音が同じボリューム”で流れているように感じるんです。
その結果、
「頭の中でいろんな声がして集中できない」
「静かなのに、心がざわざわして落ち着かない」
といった状態が起こります。
これは決して“わがまま”や“集中力がない”わけではなく、脳の情報処理の仕組みそのものに関係しているのです。
ADHDの脳の仕組みと関係する3つの要因
【ワーキングメモリ・抑制機能・ドーパミン】
では、どうして脳の中がそんなに忙しくなってしまうのでしょうか?
ポイントは3つの脳の働きです。
- ワーキングメモリの過負荷(作業記憶)
ADHDの子は「今やっていること」と「次にやること」を同時に覚えておくのが難しい傾向があります。
そのため、脳が「これも忘れちゃダメ」「あれも覚えておかなきゃ」とフル稼働状態に。
結果的に、頭の中が常に“満員電車”のように混雑してしまいます。 - 抑制機能の弱さ(いらない刺激をシャットアウトできない)
通常の脳は「今必要な情報」と「いらない情報」を仕分けしてくれます。
でもADHDの子は、その“仕分け機能”が少し苦手。
だから、ちょっとした音や動きにもすぐ気が取られてしまい、脳の中で常に何かが騒がしい状態に。 - ドーパミンの不足(注意や意欲を調整する物質)
ADHDでは、このドーパミンという神経伝達物質の働きが弱いことがあります。
ドーパミンが少ないと、脳が刺激を求めて“いろんなことを考えよう”と頑張ってしまうんです。
その結果、思考のエンジンがずっと回りっぱなしのような状態になります。
つまり、ADHDの子の「頭の中がうるさい」は、脳の中で信号があちこちに飛び交っている状態。
この“混線”を理解してあげるだけでも、ママの見方がガラッと変わります。
感覚過敏や感覚統合の乱れが「うるさい原因」になる仕組み
もう一つ、見逃せないのが感覚の過敏さです。
ADHDの子の中には、聴覚・視覚・触覚など、五感のどれかがとても敏感なタイプが多くいます。
たとえば、
- 冷蔵庫の「ブーン」という音が耳につく
- 照明のチカチカが気になって集中できない
- 衣服のタグがチクチクしてイライラする
こうした感覚の刺激が脳に入りすぎて、脳がずっと緊張モードになってしまうんです。
その結果、「外の音+心の中の思考+不快な刺激」が混ざり合い、さらに“うるさく”感じてしまうのです。
感覚統合の視点から見ると、これは脳が感覚をうまく整理できていない状態ともいえます。
感覚が整理されないと、どの情報を優先していいか分からず、常に頭の中が混乱。
だからこそ、「音」だけでなく「光・触感・匂い」など、環境全体を整えてあげることが大切なんですね。
こうして見てみると、ADHDの子どもが「頭の中がうるさい」と感じるのは、性格や努力ではなく、脳の特性と感覚の働きによるもの。
ママが「この子の脳は今、頑張って情報を整理しようとしてるんだ」と理解してあげるだけで、関わり方がぐっと優しく変わります。
ADHDの子が「頭の中がうるさい」と感じやすい日常シーン5選
ADHDの子どもたちは、ある特定の場面になると「頭の中がごちゃごちゃして落ち着かない」と感じやすくなります。
それは、脳の特性や感覚の敏感さが関係していて、本人の努力ではコントロールが難しいことが多いんです。
ここでは、特に「頭の中がうるさい」となりやすい5つのシーンを紹介します。
ママがどんな時に起こりやすいかを知っておくと、事前に環境を整えたり、声かけのタイミングを工夫したりすることができますよ。
静かなのに落ち着かない?“内的ノイズ”に苦しむ瞬間
部屋が静かで、外からの音がないのに「なんか落ち着かない…」と感じることはありませんか?
ADHDの子にとって、“静けさ”は必ずしも安心ではないんです。
脳が常に刺激を求めるタイプの子どもは、外が静かになると、
→ 今度は自分の中の思考や心の声がどんどん大きくなってしまうんです。
たとえば、
「明日のことどうしよう」
「あの時怒られたの思い出しちゃった」
「なんか怖い感じがする」
といった“頭の中のつぶやき”が止まらなくなります。
つまり、外の音は静かでも、心の中ではざわざわとした“内的ノイズ”が鳴り続けている状態。
静かに過ごす時間をつくるよりも、心が安心できる音やリズム(ゆったりしたBGMなど)を流してあげるほうが落ち着くこともあります。
教室やスーパーで「音の洪水」にパニックになる理由
ADHDの子が最も混乱しやすい場所のひとつが、人が多くて音が入り乱れる環境です。
教室、スーパー、ショッピングモールなどは、まさに“音の洪水”状態。
脳が刺激をフィルタリングできないため、
- 友だちの笑い声
- 教師の声
- 椅子を引く音
- エアコンの風の音
など、すべての音が同じ大きさで飛び込んできます。
この状態では、子どもの脳は「どの音を聞けばいいのかわからない!」とパニックになってしまうんですね。
だから、本人は「頭がガンガンする」「もう無理!」と感じてしまう。
そんな時は、「静かにしなさい」と言うよりも、その場から少し離れて落ち着ける場所に移動することが大切です。
“環境を変えることが一番の支援”になることを覚えておきましょう。
宿題・就寝前など“集中が必要な時間”に頭がざわつくワケ
ADHDの子は、“今に集中する”という行為がとても苦手です。
だからこそ、「集中しなきゃ」と思う場面ほど、頭の中がざわざわしてしまいます。
宿題をしている時、「鉛筆の音」「時計の音」「お母さんの足音」など、
関係ない刺激まで全部意識してしまう。
そして、気づけば考えがあちこちに飛び、思考の渋滞が起こります。
また、夜寝る前になると、昼間の出来事を思い出して脳が動き出すことも。
「明日怒られたらどうしよう」「早く寝なきゃ」などの思考が止まらず、余計に眠れない。
このように、ADHDの子にとって“静かに集中”は実はとても難易度が高いんです。
そんな時は、短時間で区切る(10分だけ宿題→5分休憩)や、
寝る前に「1日の出来事を口に出して整理する」など、
“頭の中を外に出す”工夫をすると落ち着きやすくなります。
楽しい予定の前後に興奮して思考が止まらないケース
ADHDの子どもたちは、感情の起伏がとても豊かです。
その分、うれしいこと・楽しみな予定があると、脳が一気にフル稼働。
「明日の遠足、楽しみ!」
「遊びに行く準備しなきゃ!」
とワクワクする気持ちが爆発して、頭の中がまるでお祭り状態に。
でも、終わったあとに“静かになる切り替え”が難しいため、
楽しかった気持ちが残りすぎて、なかなか落ち着けない子もいます。
これは「感情のスイッチの切り替え」に時間がかかるため。
楽しみの前後は“静かにする”より“気持ちをやさしく落とす時間”をつくることがポイントです。
(例:遊びのあとに、ぬりえや読書など「静かな楽しみ」に切り替える)
疲れや睡眠不足が引き金になる「頭の中の騒がしさ」
最後に見落とされがちなのが、疲れや睡眠不足による“脳のノイズ”です。
ADHDの子は、1日の中で常に刺激をたくさん受けています。
そのため、普通の子よりも脳が疲れやすいんですね。
疲れてくると、情報を整理する力がさらに落ちてしまうので、
「いつもよりソワソワしてる」「小さい音にもびっくりする」といった状態になります。
また、寝不足の日は脳の抑制機能が弱まり、
普段なら気にならない音や光まで気になってしまうことも。
つまり、「頭の中がうるさい」は、脳の疲労サインでもあるんです。
ママとしてできることは、
- 睡眠リズムを整える
- 予定を詰め込みすぎない
- “何もしない時間”を意識的につくる
といった“脳の休憩タイム”を日常に取り入れることです。
このように、「頭の中がうるさい」と感じるのは、特定の場面に共通点があるんです。
静けさ・音の多さ・集中・感情・疲労…どれも脳への刺激が関係しています。
ママが子どもの“ざわつきサイン”に気づけるようになると、早めのフォローや安心のサポートができるようになりますよ。
ADHDタイプ別「頭の中がうるさい」原因と静め方のコツ
同じ“ADHD”といっても、子どもによって「頭の中がうるさい」と感じる理由はさまざまです。
その子の感じ方・考え方・脳の反応パターンが違うからなんですね。
大きく分けると、「思考過多タイプ」「感覚過敏タイプ」「過集中タイプ」の3つに分かれます。
それぞれの特徴を知っておくと、「どう対応すればいいか」がぐっと見えやすくなります。
【思考過多タイプ】考えすぎて止まらない!頭の中を整理する書き出し法
このタイプの子は、考えがどんどん浮かんで止まらないタイプです。
「もしこうなったらどうしよう」「さっきのこと、怒られたかも」と、過去や未来のことを延々と考えてしまう。
外から見るとじっとしているのに、頭の中ではものすごいスピードで思考が回っています。
まるで、テレビのチャンネルが一秒ごとに切り替わっていくような感覚です。
このタイプの子は、“頭の中で考え続ける”こと自体がストレスになっています。
そのため、効果的なのが「書き出すこと」。
ノートやホワイトボードに、思っていること・やること・気になることを全部外に出して見える形にするんです。
たとえば、
- 「やらなきゃいけないこと」→□宿題 □明日の支度 □ハンカチ入れる
- 「気になること」→“先生怒ってたかも?”“明日うまくできるかな”
こうして書くことで、脳の中で散らかっていた情報が整理され、“考えなくてもいい状態”をつくれるんです。
「書く=安心する」習慣が身につくと、夜の“頭のぐるぐる”も少しずつ静まっていきます。
【感覚過敏タイプ】小さな音がストレスに…五感を落ち着かせる環境づくり
ADHDの中でも、感覚が敏感なタイプの子は、ほんの小さな刺激にも大きく反応してしまいます。
たとえば、
- 冷蔵庫のモーター音が気になる
- 蛍光灯の光がチカチカして落ち着かない
- 洋服のタグが肌に当たってイライラする
など、日常の“ちょっとしたこと”が頭の中のノイズになってしまうんです。
こうした状態では、脳が常に「危険がないか」「不快なものがないか」と見張りをしているようなもの。
つまり、頭の中がずっと緊張状態にあるということです。
このタイプの子には、五感を落ち着かせる環境づくりがとても効果的です。
💡具体的な工夫としては…
- 音環境を整える:イヤーマフやホワイトノイズ(一定の心地よい音)を活用
- 光の刺激を減らす:間接照明にする・蛍光灯をLEDに変える
- 触覚を守る:タグを取る・柔らかい素材の服を選ぶ
- においの刺激を和らげる:無香料の洗剤や柔軟剤を使う
また、“おこもりスペース”をつくるのもおすすめです。
部屋の隅にお気に入りの毛布やぬいぐるみを置いて、安心できる空間をつくることで、子どもは“頭の中のうるささ”を自然に鎮めやすくなります。
感覚過敏タイプの子は、「うるさい=心が不安定になっているサイン」であることも多いので、
「静かな場所に行こうか」とやさしく促すだけでも、十分な支援になります。
【過集中タイプ】集中しすぎて疲れ切る子に必要な“切り替え習慣”
ADHDの中には、逆に集中力が高すぎるタイプの子もいます。
ゲームや好きな遊びに夢中になると、時間も忘れて没頭してしまう。
でも、終わったあとはどっと疲れて、頭の中がパンク状態になってしまうことがあります。
この“過集中タイプ”の子は、実はとても頑張り屋。
でも、脳のブレーキがうまく働かないため、集中が切れた瞬間にイライラ・泣き・癇癪が出ることも珍しくありません。
そんな子には、「切り替えの習慣」を先に仕込んでおくことが大切です。
たとえば、
- 10分集中→2分休憩というリズムを決めておく
- タイマーを使って「ピッ!となったら一度ストップ」
- 終わったあとに深呼吸やストレッチをする
これらはどれも、脳をリセットする“スイッチ”の役割を果たします。
最初は難しくても、習慣化することで「自分で落ち着ける力」が育っていきます。
また、ママが「楽しかったね」「ここで一休みしよう」と声をかけることで、
子どもは“終わり=イヤなこと”ではなく、“休憩=安心できること”と学んでいきます。
過集中タイプの子は、集中が続く=能力が高いと見られがちですが、
実はその裏で脳がすごく疲れていることも多いんです。
だからこそ、「頑張りすぎない仕組み」を整えてあげることが何よりの支援になります。
タイプを知れば、子どもの「静けさ」が見えてくる
ADHDの子の「頭の中がうるさい」は、“ひとくくり”では語れません。
思考が止まらない子もいれば、音に敏感な子、集中しすぎて疲れる子もいます。
大切なのは、「この子はどのタイプの“うるささ”を感じているのかな?」と観察すること。
タイプが分かると、叱るよりも支えやすくなり、家庭の雰囲気もぐっと穏やかになります。
頭の中がうるさいADHDの子に効く!今すぐ試せる静め方・対策法
ADHDの子どもが「頭の中がうるさい」と感じるとき、脳は“フル稼働”の状態です。
つまり、考えすぎ・感じすぎ・刺激の処理に追いつけないということ。
この章では、そんな状態をやさしく落ち着かせるための“おうちでできる実践法”を紹介します。
どれもすぐに取り入れられるものばかりなので、まずは気軽に試してみてくださいね。
環境調整で「安心できる静けさ」をつくる【音・光・温度・におい】
ADHDの子が落ち着けるかどうかは、環境づくりが8割といっても過言ではありません。
脳が刺激を拾いやすい子にとって、ほんの少しの音や光でも“ストレスのもと”になってしまうことがあります。
まず意識したいのは、次の4つ。
- 音:テレビや家電の音を最小限に。ホワイトノイズや静かなBGMを流すのも◎。
- 光:蛍光灯のチカチカはNG。間接照明や暖色系ライトでやさしい空間に。
- 温度:体温が上がると落ち着きにくくなるので、涼しめに保つのがおすすめ。
- におい:強い香りは集中の妨げに。無香料やアロマの微香で“安心感”をプラス。
特に効果的なのが、「子ども専用の安心スペース」をつくること。
お気に入りの毛布・ぬいぐるみ・間接照明をそろえて、“自分の静けさゾーン”にするだけでも、頭の中の騒がしさがスッと落ち着きやすくなります。
感覚統合あそびでリラックス!家庭でできる“おうち療育”アイデア
ADHDの子が「頭の中がうるさい」と感じる背景には、感覚のアンバランス(感覚統合の乱れ)が関係していることがあります。
そこでおすすめなのが、家庭でも簡単にできる感覚統合あそび。
難しく考えず、「体を使って安心感を取り戻すあそび」と思ってOKです。
たとえば、
- ゆらゆらブランコあそび:バスタオルで体を包み、左右にゆっくり揺らす。前庭感覚(バランス感覚)を整える効果。
- お布団くるまれごっこ:毛布や布団で軽くくるんで、体に“圧”をかける。安心感を得やすい。
- 風船ぽんぽんバレー:視覚・運動感覚を同時に使う。集中が必要な動きで、余計な思考をリセット。
感覚統合あそびは、「落ち着きなさい」よりもずっと効果的な静め方です。
子どもの脳が「安心できるリズム」を取り戻せるように、1日5分からでも取り入れてみましょう。
頭の中のモヤモヤを外に出す「書き出し&スケジュール化」
ADHDの子どもは、頭の中に“考え”や“やること”がたくさん詰まってしまいがち。
結果、脳が混乱して「もううるさい!」「わかんない!」となってしまうんです。
そんな時に役立つのが、書き出すことと見える化です。
ポイントは2つ:
- モヤモヤを紙に書いて外に出す
→「気になること」「心配なこと」「やること」を付箋やノートに書く。
→書き終えたら「これはあとでOK」「これはすぐやろう」と分類。 - スケジュール化して“頭の中の順番”を決める
→1日の流れを絵やマグネットで見えるようにする。
→「次に何するか」がわかると、脳の混乱が減って落ち着きやすくなる。
つまり、頭の中を“外に出して整理する”ことで静けさをつくるということ。
紙・ホワイトボード・タブレットなど、子どもが使いやすいツールを選んでみてくださいね。
音楽やリズムで落ち着く!リトミックを使った静め方
音やリズムを使って心を落ち着ける「リトミック」は、ADHDの子にとって非常に効果的な方法です。
特に、「頭がうるさい」「集中できない」というときに、ゆっくりとしたテンポの音を感じることで、脳が安心モードに切り替わります。
家庭でできる簡単なリトミック例はこんな感じ:
- 音に合わせてスカーフをゆらゆら動かす(深呼吸と同じリズムで)
- 「ドーン・パン・トントン」などのリズムを一緒に手で叩く
- メトロノームアプリで60〜80拍/分のリズムに合わせて呼吸
これらは、音の刺激を“整えるリズム”として活用しているイメージです。
ADHDの子は「音に敏感」でも、「一定のリズム」には安心を感じやすい傾向があります。
つまり、“静けさ”は音を消すことではなく、“心地よいリズムを与えること”でもつくれるということです。
呼吸で脳をリセット!親子でできる腹式呼吸&深呼吸あそび
最後に紹介するのは、どんなタイプの子にもおすすめできる“脳リセット法”。
それが、呼吸を整えることです。
深呼吸には、自律神経を整え、頭の中の興奮をしずめる効果があります。
でも「息を吸って〜吐いて〜」と言っても、子どもにはちょっと難しいですよね。
そこでおすすめなのが、あそび感覚の呼吸法。
- 「風船をふくらませるつもりで、ゆっくり息を吐こう!」
- 「お花のにおいをクンクン〜、ふ〜って雲を飛ばそう!」
- 「3秒吸って、5秒でふーっと吹くゲーム」
このように、遊びながら呼吸を意識させることで、自然と心拍が落ち着き、“頭の中のうるささ”もスッと静まっていきます。
ママ自身も一緒に呼吸を合わせると、親子でリラックス効果が高まりますよ。
どの方法も、“静けさ”を無理に作るのではなく、子どもの心と脳を落ち着かせるリズムを取り戻すための工夫です。
ぜひ、子どものタイプやその日の様子に合わせて、できそうなものから取り入れてみてくださいね。
家庭でできる!ADHDの子の「頭の中を静める」日常ルーティン
ADHDの子は、1日の中で頭の中が“うるさくなりやすい時間帯”があります。
朝の支度、学校や園での活動、夜の寝る前…どれも脳に負担がかかるタイミングなんです。
でも、日常の中で「静けさを取り戻すルーティン」を作ってあげると、子どもの脳が“安心モード”に切り替わりやすくなるんです。
ここでは、家庭で簡単にできる「頭を静める習慣づくり」を紹介します。
朝・登園前に頭を落ち着かせる“リズム準備ルーティン”
朝は、ADHDの子にとって“1日の中でもっとも頭が混乱しやすい時間”。
まだ脳が完全に目覚めていない状態で、着替え・朝食・支度など、やることが多いからです。
そんな時は、「リズムで動くルーティン」がおすすめです。
リズムとは、テンポのある動きや音のこと。
たとえば、
- 朝の支度の順番を歌やリズムで覚える(「着替えて♪ごはん〜♪ハンカチOK〜♪」)
- タイマーを鳴らして“音で切り替え”をする
- 一緒に朝の深呼吸ルーティン(3回吸って吐く)をする
こうした“動きのリズム”は、頭を整理するスイッチになります。
つまり、朝のバタバタを「テンポに変える」ことで脳が落ち着くんです。
「支度が遅い」ではなく「リズムが合ってないだけ」と考えると、ママの気持ちも少し軽くなりますよ。
学校・園で「音がうるさい」と感じやすい子へのサポート法
学校や園では、どうしても音や刺激が多い環境になります。
ADHDの子は、特にその影響を受けやすく、頭の中がすぐ“オーバーヒート状態”になってしまうんです。
そんな時に役立つのが、「音環境の工夫」+「安心グッズ」です。
たとえば、
- イヤーマフや小さな耳栓型イヤープラグを使う(完全防音でなく、音をやわらげる程度が◎)
- 教室の後ろや端など、静かめな場所に席を置いてもらう
- カバンに“落ち着くアイテム”を入れておく(好きなキャラのキーホルダーや香りのハンカチなど)
さらに、先生と共有しておくのも大切です。
「うるさく感じて頭がいっぱいになることがあるので、その時は少し席を外してもいいですか?」と、子どもが休める選択肢を確保しておくと、安心感がぐっと増します。
つまり、“静けさを持ち運ぶ工夫”ができると、子どもの1日がぐんと穏やかになります。
夜の“うるさい思考”を静める寝る前の安心ルーティン
夜は、1日の疲れと情報がいっぺんに押し寄せる時間。
特にADHDの子は、昼間の出来事を思い出して考えすぎてしまう傾向があります。
「怒られたの思い出した」
「明日うまくいくかな」
「眠れない…」
そんな時に効果的なのが、“安心を積み重ねる寝る前ルーティン”です。
おすすめの流れはこんな感じ↓
- 照明を落とす(視覚刺激を減らす)
- ぬいぐるみや毛布で“安心の重み”を感じる
- 1日の中でうれしかったことを1つ話す(“今日のうれしいニュース”)
- 呼吸を合わせて「ふーっ」と3回ゆっくり吐く
この4ステップを続けるだけで、脳が「寝る=安心できる時間」と認識するようになります。
つまり、寝る前に“考えすぎスイッチ”を切る練習です。
「寝る前のルーティン=静けさの儀式」と思って、毎日同じ流れを大切にしましょう。
家族で共有したい「うるさい度チェックリスト」の活用法
子どもが「頭の中がうるさい」と言っても、ママやパパが“どれくらいなのか”を想像するのは難しいですよね。
そこでおすすめなのが、「うるさい度チェックリスト」。
このリストは、子ども自身の“今の状態”を見える化するツールです。
たとえば、こんな感じ↓
| うるさい度 | 状態の目安 | ママの声かけ例 |
|---|---|---|
| ★☆☆☆☆ | ちょっと集中しにくい | 「静かな場所で少し休もうか?」 |
| ★★☆☆☆ | 頭がソワソワしてる | 「好きな音楽かけようか?」 |
| ★★★☆☆ | もううるさい感じ | 「一緒に深呼吸してみよう」 |
| ★★★★☆ | パニック寸前 | 「静かな部屋に行こう」 |
| ★★★★★ | 限界!泣く・怒る | 「ギュッて抱っこするね」 |
こうして数で表すことで、ママも「今は話しかけない方がいいな」「静かな時間を作ろう」と判断しやすくなります。
さらに、子ども自身が「自分の状態を言葉にする練習」にもなるんです。
「今★3くらい」と伝えられるようになると、トラブルの前に自分で落ち着く力が育ちます。
ルーティンは“頭を静めるリズム”になる
ADHDの子にとって、毎日の「ルーティン」は単なる習慣ではなく、頭の中を静める“リズムの支え”です。
朝はテンポ、昼は環境、夜は安心。
それぞれの時間帯で“静けさを取り戻すポイント”を意識していくと、子どもの1日が格段に穏やかになります。
ママが少し工夫するだけで、子どもが「落ち着ける時間」を取り戻せる。
それが、家庭でできる“心と脳のケア”の第一歩です。
ADHDの子が落ち着くために大切な“親の関わり方”とは?
ADHDの子が「頭の中がうるさい」「落ち着けない」と感じている時、親の関わり方が“静けさのスイッチ”になります。
子どもの心が不安定な時ほど、言葉や態度のちょっとした違いが大きく影響するんです。
ここでは、ママやパパが“無理せずできる”関わり方のコツを紹介します。
どれも「特別なこと」ではなく、日常の中のちょっとした声かけや距離の取り方で変わる内容です。
「落ち着いて!」より「一緒に静かになろう」が効果的な理由
つい子どもがパニックになったり、興奮している時に言ってしまいがちな言葉、
それが「落ち着いて!」。
でも、ADHDの子にとってこれは“命令”のように聞こえてしまうことが多いんです。
脳が興奮している状態では、“落ち着く”という言葉そのものを理解するのが難しいからです。
そこでおすすめなのが、「一緒に静かになろう」という声かけ。
この言葉には、「あなたを助けたい」「一緒に頑張ろう」という安心のメッセージが含まれています。
たとえば、
「静かな音にしてみようか」
「ママも深呼吸するね。一緒にやろう」
といった言葉に変えるだけで、子どもの緊張がスッとやわらぎます。
つまり、“命令ではなく共感で伝える”ことが、落ち着きを取り戻す第一歩なんです。
否定せず“共感”するだけで子どもの脳が落ち着く仕組み
「そんなことで泣かないの」「我慢しなさい」――。
つい言ってしまいがちなこの言葉。
でも、ADHDの子にとってはこれが一番つらい否定になってしまうことがあります。
なぜなら、ADHDの子どもの脳は“共感されると落ち着く”仕組みを持っているからです。
共感とは、「そう感じたんだね」「イヤだったんだね」と、まず気持ちを受け止めること。
心理学では、この共感が「オキシトシン」という安心ホルモンを増やすことがわかっています。
このホルモンが出ると、脳の「闘う・逃げる」を司る部分(扁桃体)が静まり、
思考の整理がしやすくなる=頭の中が静かになるんです。
たとえば、
「イヤだったね」
「びっくりしたよね」
「音が大きくてつらかったね」
と短く共感するだけでも効果があります。
叱るよりも、「わかってもらえた」と感じた瞬間に、子どもの心は落ち着き始めるんです。
感情が高ぶる前に“そっと離れる”距離感の魔法
子どもが興奮しているとき、親が必死に「話そう」「止めよう」とするほど、逆効果になることがあります。
ADHDの子の脳は、刺激が重なるほど興奮が増すという特徴を持っているからです。
そんな時に効果的なのが、“そっと離れる”という対応。
たとえば、
「ママ、ここにいるから落ち着いたら教えてね」
「今は静かにするね。後で話そう」
このように、“安全な距離を保ったまま見守る”ことが大切です。
これは、放っておくのとは違います。
あくまで「安心できるスペースをあげる」ということ。
子どもは“見放されていない”と感じることで、自然に落ち着きやすくなります。
実際、療育現場でも「過剰な言葉かけを減らす」ことで、パニック時間が短くなったという報告は多いんです。
つまり、“距離”もまた、支援のひとつの形なんです。
ママ自身のストレスが子に伝わる!自分の心を整えるケア法
ここまで子どもへの関わり方を紹介してきましたが、
実は一番大切なのは――ママ自身の心を整えること。
ADHDの子どもは、親の感情をとても敏感に察知する傾向があります。
ママがイライラしていたり、疲れていると、その“空気”を感じ取って落ち着きにくくなるんです。
でも、「いつも穏やかに」なんて、そんなの無理ですよね。
だからこそ、ママのための“セルフケア時間”を意識的にとることが大切です。
たとえば、
- コーヒーを飲む5分を“自分だけのリセット時間”にする
- 深呼吸を「子どもと一緒にやる」ことで、自分も整える
- SNSや情報から少し離れて“静かな夜”をつくる
大事なのは、「完璧な親であろうとしない」こと。
ママが穏やかでいられる時間を増やすだけで、子どもはその安心を肌で感じ、自然と静まっていきます。
親の心が穏やかだと、子どもの“頭の中の静けさ”もついてくる――。
それが、一番やさしい家庭療育なんです。
落ち着かせるのではなく、“一緒に落ち着く”
ADHDの子を“落ち着かせよう”とするのではなく、
「一緒に落ち着こう」というスタンスが、親子の心を守ります。
叱るでも、教えるでもなく、
「見守る」「共感する」「一緒に静かになる」。
この3つの関わり方を続けるだけで、子どもは少しずつ自分で感情を整える力(自己調整力)を身につけていきます。
ママが変わると、子どもの世界も変わる。
その第一歩が、“静けさを一緒に感じる時間”なんです。
ADHDの「頭の中がうるさい」に効く!専門支援・相談先まとめ
「頭の中がうるさい」「落ち着けない」「気が散る」――。
ADHDの子どもが日常で感じているこの“うるささ”には、脳の働き方や感覚処理の特性が深く関係しています。
家庭での工夫ももちろん大切ですが、専門家の支援を取り入れることで、子ども自身が“どうすれば静かになれるか”を少しずつ学べるようになるんです。
ここでは、ママが知っておくと心強い「相談できる専門機関」と「支援の受け方」をやさしくまとめました。
小児神経科・発達外来での診断と薬の選択肢
まず、「頭の中がうるさい」「集中できない」などの症状が続く場合、医療機関での診断が第一歩になります。
受診先としては、小児神経科・発達外来・児童精神科などが対象です。
ADHDの場合、脳内のドーパミンやノルアドレナリンという神経伝達物質のバランスが関係しているため、必要に応じて薬のサポートが検討されることもあります。
代表的なのは以下のような薬です:
- コンサータ/インチュニブ/ストラテラ など
これらは、脳の中の情報の流れをスムーズにして、思考の混乱を和らげる役割を果たします。
ただし、「薬を使う=ずっと飲み続ける」わけではありません。
多くのケースでは、生活支援や環境調整と並行して使うことで、より良い効果を得られます。
診察の際は、
- どんな時に「頭がうるさい」と感じるか
- 生活で困っている具体的な場面(学校・家庭など)
をメモして伝えると、医師がより正確に判断しやすくなります。
感覚統合療法(OT)やカウンセリングでのアプローチ方法
もし「音や光に敏感」「体の動きで落ち着く」といった感覚の特徴が見られる場合、
作業療法士(OT)による感覚統合療法がとても効果的です。
感覚統合療法とは、感覚の過敏さや鈍さを調整し、脳が情報を整理しやすくする訓練のこと。
たとえば、
- ブランコやトランポリンなどで体の感覚を整える
- 触覚や聴覚に慣れる遊びを通して刺激の受け取り方を調整する
といった方法で、子どもが「自分で落ち着く感覚」を身につけていけるのです。
また、心の混乱や不安が強い子には、心理士によるカウンセリングやプレイセラピーも有効です。
「自分の気持ちを言葉や絵で表現できるようになる」と、頭の中の“モヤモヤ”が少しずつ整理されていきます。
どちらの支援も、医療機関・発達支援センター・児童発達支援事業所などで受けられることが多いです。
発達支援センター・学校との連携で“安心できる環境”を整える
家庭や医療だけでなく、学校や地域の支援機関とつながることもとても大切です。
各自治体には、発達に関する相談を受けてくれる
「発達支援センター」「こども発達支援課」などがあります。
ここでは、専門の心理士・保育士・OTなどがチームで対応してくれ、
家庭・園・学校と連携しながら支援計画を立ててくれます。
たとえば学校の場合、
- 教室の席の位置を変える(窓際や通路から離す)
- イヤーマフやノイズキャンセリングイヤホンを許可する
- 授業中の刺激を減らす配慮をお願いする
といった「環境調整」ができるようになります。
また、担任や支援コーディネーターと定期的に話し合うことで、
「どんな時にうるさく感じているか」「どうすれば安心できるか」を共有できます。
つまり、“子どもが落ち着ける環境”はチームでつくるものなんです。
専門家に相談するときに伝えるべき「観察ポイント」
実際に医師や支援機関に相談する際、
「頭の中がうるさい」と言われても、なかなかその様子を正確に伝えるのは難しいですよね。
そんな時は、次のような観察ポイントをメモしておくと、専門家が理解しやすくなります
📝観察のチェックポイント
- どんな時に「うるさい」と言うか(例:宿題中・寝る前・外出時など)
- どんな反応が出るか(例:耳をふさぐ・泣く・走り回る・固まる)
- 周囲の音や光に敏感か(例:掃除機・テレビの音・教室のざわめき)
- 頭がうるさい時、どんな言葉を使うか(例:「止まらない」「頭がごちゃごちゃする」)
- 落ち着くために自分でしている行動(例:ゆらゆら揺れる・特定の曲を聴く)
これらを伝えると、
医師・作業療法士・心理士が「脳の働き」「感覚の特徴」「ストレス要因」をより的確に分析できます。
また、学校や園に共有することで、支援方法の一貫性も生まれ、子どもが安心して過ごせるようになります。
専門家とつながることで「静けさの道」が見えてくる
「頭の中がうるさい」という感覚は、
本人にしか分からない、とてもつらいもの。
けれど、専門家と連携していくことで、少しずつ“静けさ”を取り戻す道が見えてきます。
医療・感覚支援・学校の協力をうまくつなげていくことが、ママと子ども、どちらの安心にもつながります。
家庭で抱え込まず、
「うちの子に合う支援を一緒に考えてほしい」と、まずは気軽に相談してみてください。
それが、子どもが“頭の中のざわめき”から少しずつ解放されていく第一歩です。
ADHDの子が“静けさ”を取り戻すために親ができること
ADHDの子どもにとって、「静けさ」はただ“音がない状態”を指すわけではありません。
それは、心が落ち着き、安心していられる時間のこと。
「うるさい」と感じやすい子ほど、外の音や自分の思考に押し流されやすく、静けさを保つのが難しい傾向があります。
でも、ママのちょっとした関わり方や環境づくりで、少しずつ“静けさを感じる力”を取り戻していくことができるんです。
ここでは、家庭で実践できる3つのステップを紹介します。
「静けさ=無音」ではなく「安心できる空間」をつくる視点
まず大切なのは、「静けさ=音がないこと」ではないという考え方。
ADHDの子どもにとって、“無音の空間”はかえって不安になることもあるんです。
たとえば、
- 音がなくなると、自分の頭の中の考えがどんどん浮かんできて落ち着かない
- 無音の部屋だと、ちょっとした物音でもびくっとしてしまう
といったことが起きるケースがあります。
そのため、子どもが安心できる「静けさの形」はそれぞれ違います。
たとえば、
- 小さなBGM(環境音やオルゴール)を流す
- お気に入りのぬいぐるみやブランケットをそばに置く
- 照明を少し暗くして“包まれる安心感”をつくる
こうした“安心を感じる五感の工夫”こそが、子どもにとっての本当の静けさ。
つまり、「音を消す」よりも「安心を足す」ことがポイントなんです。
ママが「うちの子にとっての安心音・安心空間」を一緒に探してあげることで、
子どもは「ここにいると落ち着く」という感覚を少しずつ覚えていきます。
毎日の小さな変化を記録する「うるさい度日記」のすすめ
ADHDの子は、日によって“頭のうるささ”の感じ方が大きく変わります。
ある日は平気なのに、翌日は些細な音にも反応してしまう――そんな波があるんです。
だからこそおすすめなのが、「うるさい度日記」。
これは、「その日の頭のうるささ」や「気分の状態」を軽くメモしておく習慣です。
絵やマークでもOK。
たとえば↓
| 日付 | うるさい度(1〜5) | 状況 | 対応・結果 |
|---|---|---|---|
| 10/17 | ★★★★☆ | 学校の帰りにうるさかった | 公園でブランコ→落ち着いた |
| 10/18 | ★★☆☆☆ | 朝の支度中 | 音楽をかけたら笑顔になった |
こうやって記録をつけていくと、「どんな時に頭がうるさくなるのか」が見えてきます。
すると、ママ自身も「対処法の引き出し」が増えていくんです。
しかも、これは支援センターや医師に相談するときにも役立ちます。
「うるさいと言うタイミング」「落ち着いた行動」を具体的に見せられるので、より的確な支援プランを立ててもらえます。
なにより、ママが「ちゃんと記録してる」という安心感を持てることも大切。
焦らず、1日1行から始めてみましょう。
子ども自身が“静けさを感じる力”を育てる関わり方
最終的に目指したいのは、子どもが自分で静けさを取り戻せるようになること。
そのためには、ママが「一緒に感じる時間」を意識してつくることが大切です。
たとえば、
- 一緒に深呼吸をする
- 「この音、心地いいね」と安心できる音を共有する
- 「今、静かだね」「風の音が気持ちいいね」と“静けさ”に気づく言葉を添える
こうした関わりを通して、子どもは“静けさを意識する力”を育てていきます。
ADHDの子どもは、刺激が多い世界で生きているため、
静けさを“感じる”よりも“探す”ことにエネルギーを使ってしまいがち。
だからこそ、「静けさってこんなに気持ちいいんだよ」と親が一緒に体験する時間がとても大事なんです。
また、感情が高ぶったときに、ママが先に落ち着く姿を見せるのも有効です。
「ママ、深呼吸するね」
「少し静かにして、音を聴いてみよう」
といった“モデリング(お手本行動)”を重ねることで、
子どもは自然と「自分も落ち着ける方法」をまねして覚えていきます。
つまり、静けさは教えるものではなく、“一緒に感じる”ものなんです。
静けさを「探す」から「育てる」へ
ADHDの子どもにとって、頭の中の“うるささ”は避けようのない特性のひとつ。
でも、ママと一緒に“静けさを育てていく”ことで、少しずつ自分で落ち着く力が育っていきます。
ポイントは、
- 「音を消す」より「安心を足す」
- 「記録して見える化」する
- 「一緒に静けさを感じる時間」をつくる
この3つを意識すること。
子どもにとっての静けさは、ママの安心とつながっています。
だからこそ、完璧じゃなくて大丈夫。
“うるさい日”も“静かな日”も、親子で一緒に過ごす時間そのものが支援になります。
まとめ|頭の中がうるさいADHDの子も「安心できる静けさ」はつくれる
ADHDの子どもがよく口にする「頭の中がうるさい」という言葉。
それは決して“わがまま”でも“気のせい”でもありません。
この“うるささ”は、脳の情報処理の特性や感覚の過敏さによって生まれるもので、本人がどれだけ頑張ってもコントロールできないことが多いんです。
「頭の中がうるさい」は脳の特性であり、努力不足ではない
ADHDの子どもは、脳の中で「情報を整理する部分」と「感情を抑える部分」のバランスが少し違います。
そのため、頭の中に“思考や感覚のノイズ”があふれやすい状態にあるんです。
たとえば、
- 宿題をしているのに、他の音や考えが次々に入ってきて止まらない
- 静かな部屋でも、頭の中で“考えごと”や“映像”がぐるぐるする
- 感覚が鋭く、音・光・人の気配に反応してしまう
こうした状態は「集中力がない」「落ち着きがない」と誤解されやすいですが、
実際は脳の働き方の違いによる“混乱”なんです。
だからこそ、親ができるのは「叱る」ことではなく、“どうすれば落ち着けるか”を一緒に探していくこと。
その姿勢こそが、子どもにとっての大きな安心になります。
家庭での小さな環境調整やルーティンで落ち着きを取り戻せる
ADHDの子にとって、“安心できる環境”は最大の味方。
特別な設備がなくても、家庭でできる工夫はたくさんあります。
たとえば、
- 照明を少し落として、刺激を減らす
- 好きな音(環境音・オルゴールなど)を流して安心感をつくる
- 朝・夜のルーティンを一定にして、予測できる1日をつくる
これだけでも、脳が「今は安全だ」と感じて、頭の中のざわつきがスッと静まることがあります。
ポイントは、「静けさ=無音」ではないということ。
ADHDの子が落ち着くのは、“五感が安心する空間”です。
ママが少しずつ環境を整えていくことで、
子どもは「ここにいると落ち着く」「この音を聞くと安心する」といった“自己調整の感覚”を育てていくことができます。
この「安心の積み重ね」が、将来的に学校生活や社会生活でも子どもを支えてくれます。
専門家・支援機関と連携しながら、親子で“静けさ”を育てていこう
もし「家庭だけでは難しい」と感じたら、それは自然なことです。
ADHDの特性には、医療・心理・教育の視点が複雑に関わっているため、専門家の支援を取り入れることで見えてくることがたくさんあります。
たとえば:
- 小児神経科・発達外来では、脳の状態を詳しく調べてもらえる
- 作業療法(感覚統合療法)で、“落ち着く感覚”を体で覚える
- 発達支援センターや学校と連携して、環境調整や配慮を相談できる
これらを組み合わせることで、家庭・学校・専門機関が一緒に「子どもの静けさ」を支える体制をつくることができます。
そして何より大切なのは、ママ自身が「ひとりで抱え込まないこと」。
「わからない」「助けてほしい」と声をあげることは、弱さではなく“支援のスタートライン”です。
支援の輪に入ることで、ママも子どもも「一緒に進んでいける安心感」を得られます。
おわりに:静けさは“与えるもの”ではなく“一緒に育てるもの”
「頭の中がうるさい」と言う子どもに、
ママができる一番のことは、“静けさを与える”ことではなく、“一緒に探す”こと。
その日によってうるさい度は違っても、
「今日はどんな音が安心する?」「今はどんな気分?」と寄り添うことで、
子どもは少しずつ“自分の心を静める力”を身につけていきます。
ADHDの子が安心できる静けさは、決して特別な場所じゃありません。
それは、ママの優しい声、やわらかい光、好きな音楽、安心できるリズムの中にちゃんとあります。
完璧じゃなくても大丈夫。
今日の「少し落ち着けた時間」こそが、明日の成長につながる大切な一歩です。
以上【ADHDの子どもの頭の中がうるさい原因と静め方|家庭でできる対策を徹底解説!】でした

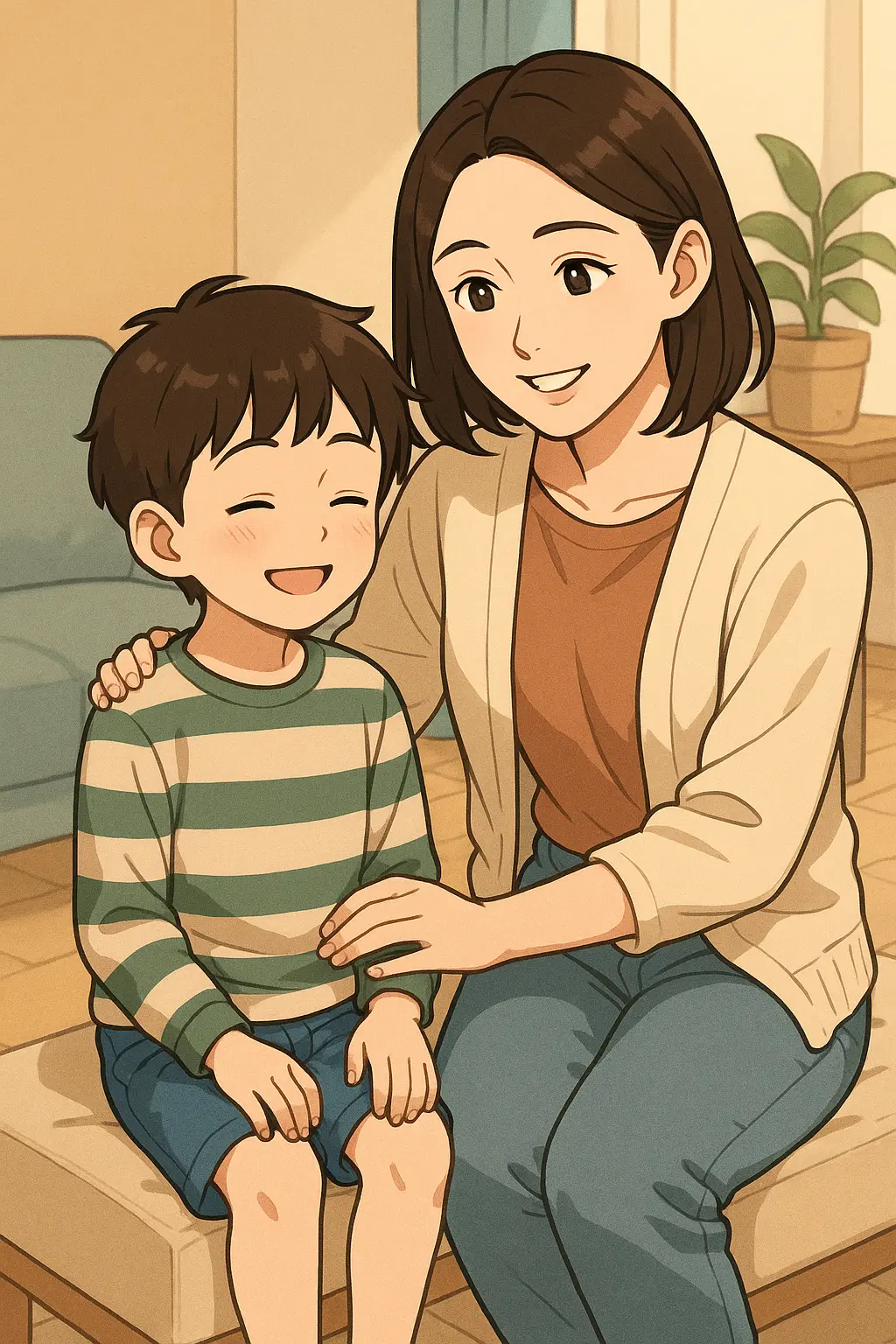









コメント