「発達障害/ADHD傾向」って何?ママが知っておきたい基礎知識
「うちの子、ちょっと落ち着きがなくて…」「話を最後まで聞けないのは性格?」
そんな不安を感じたこと、ありませんか?
最近では「ADHD(注意欠如・多動症)傾向」という言葉を耳にするママも増えています。
でも、“傾向”という表現には、「まだ診断されてはいないけれど、特徴が少し見られる」という意味があります。
つまり、ADHD傾向がある=病気や障害というわけではなく、“その子の特性”のひとつなんです。
子どもによって得意・不得意があるように、集中力や行動のコントロールにも“その子なりのクセ”があるんですね。
発達障害の一種としての「注意欠如・多動症(ADHD)傾向」とは
ADHDは、発達障害のひとつで、主に3つの特徴があると言われています。
それが「不注意(集中しにくい)」「多動(じっとしていられない)」「衝動性(思いつくまま動く)」の3つです。
たとえば…
- 宿題の途中で他のことに気を取られる
- 話している途中で別の話題に飛ぶ
- 順番を待てずに割り込んでしまう
こういった行動が続く場合、「ADHD傾向があるかも?」と感じるきっかけになります。
でも、ここで大切なのは、「悪いことをしているわけではない」ということ。
本人に悪気はなく、脳の中で「注意」や「行動」をコントロールする力の発達が少しゆっくりなだけなんです。
脳の発達や神経の伝わり方には個性があり、子どもによって得意な情報処理の方法が違うんです。
たとえば、視覚からの情報が得意な子、音から理解するのが得意な子など、その子の“学びのスタイル”にもつながっています。
子どもに出やすい「ADHD傾向の特徴」:不注意・多動・衝動のサイン
ADHD傾向のある子どもに見られやすい行動を、わかりやすく3つに分けてみましょう。
①不注意タイプ
- うっかりミスが多い
- 宿題や作業に集中できない
- 話を聞いていないように見える
→ 集中力のスイッチが入りにくいタイプです。
このタイプの子は、興味のあることには驚くほど集中しますが、興味がないと一瞬で気がそれます。
「集中できない」というより、「集中をコントロールする力が未発達」なんです。
②多動タイプ
- じっとしていられず、体を動かしていたい
- しゃべり続ける、静かに遊ぶのが苦手
→ 体を動かすことで安心するタイプです。
ママから見ると「落ち着きがない」と感じるかもしれませんが、本人にとっては“動いているほうが落ち着く”こともあります。
③衝動性タイプ
- 思いついたことをすぐ口にする・行動に移す
- 我慢が苦手でトラブルになりやすい
→ 考える前に行動してしまうタイプです。
大人から見ると「わがまま」「自分勝手」と見える行動も、実は感情を抑える脳の働きが未熟なだけなんです。
ママが見つけやすい「我が子の気になるサイン」:家庭チェックポイント
では、どんなときに「ADHD傾向かも?」と気づくのでしょうか。
家庭でママが気づきやすいサインをいくつか挙げてみます。
- 朝の支度に時間がかかる(服を着替える途中で他のことを始める)
- おもちゃを出しっぱなしで、片づけをしてもすぐ散らかる
- 何度言っても忘れ物をする
- 感情の波が激しく、注意すると泣いたり怒ったりする
- 「ダメ」と言われると余計にやりたくなる
こうした行動があっても、“怠けている”のではなく、“できない”ことが多いんです。
脳の発達の仕組みを理解すると、叱るよりも「どうすればやりやすくなるか」を考える方が、ずっと前向きですよね。
たとえば、
- 朝の支度はタイマーを使ってリズムを作る
- 片づけは「箱に入れるだけ」にしてシンプルにする
- 忘れ物は「見えるリスト」で防ぐ
など、ちょっとした工夫でママも子どももラクになることがたくさんあります。
ADHD傾向のある子に多い“困りごと”TOP5
ADHD傾向のある子どもたちは、頭の中がいつも“フル回転”しています。
ひとつのことに集中している途中で、別の刺激が目や耳に入ると、すぐに意識がそちらへ向かってしまうことも。
そのため、家庭の中では「落ち着きがない」「忘れ物が多い」「切り替えが苦手」など、日常生活でちょっとした困りごとが起きやすいんです。
でも、それは本人の努力不足ではなく、“脳の特性”によるもの。
ママが少し視点を変えて環境や声かけを工夫することで、グッと過ごしやすくなります。
ここでは、ADHD傾向のある子に多い困りごとを5つ紹介しながら、「家庭でできる現実的な工夫」を一緒に見ていきましょう。
困りごと①:集中できない・気が散りやすい
〜「宿題・支度・学習」が苦手な子への対応〜
ADHD傾向の子どもは、集中力が“ゼロ”ではありません。
むしろ、好きなことには驚くほど集中できるのが特徴です。
問題は、「興味がない」「刺激が多い」状況で集中が続かないこと。
宿題や朝の支度など、“やらなければいけないこと”ほど集中しにくくなるんです。
環境を整えて集中力アップ:乱雑な刺激を減らす工夫
子どもにとって、集中できる環境はとても大事。
ADHD傾向の子は、視覚的な刺激(見えるものの多さ)や聴覚的な刺激(音の多さ)に影響されやすいです。
たとえば、
- 勉強机の上に物が多い
- テレビや家族の話し声が聞こえる
こうした環境では集中スイッチが入りません。
おすすめは、机の上は最小限、静かな場所で作業すること。
背景音が必要な場合は、「ホワイトノイズ」や静かな音楽を流すのも効果的です。
タイマー&短時間集中法で“できた”を増やす
「30分座って勉強」なんて大人でも大変ですよね。
ADHD傾向の子は、短い時間で区切ることがコツ。
例えば、
- 「5分集中→1分休憩」
- 「宿題1ページ→好きなこと1分」
このように、“短時間で達成できる設定”にすると成功体験が増えます。
タイマーを使って「ピッと鳴ったらおしまい」と見通しをつけてあげましょう。
音やリズムを味方につける:気が散る子のための集中ツール
集中が難しい子には、リズムや音の刺激が助けになることもあります。
たとえば、「1・2・3・始めよう!」とテンポをつけて声かけしたり、作業のリズムを歌にしてみたり。
音があることで、「今はこの時間」と頭の切り替えがスムーズになります。
まるで音楽療法のように、リズムで集中を支える方法はとても効果的です。
困りごと②:忘れ物・なくし物が多い
〜持ち物管理も一苦労〜
「昨日言ったのに、また忘れてる…」と、ママがため息をつく場面、よくありますよね。
でも、ADHD傾向の子にとって“覚えておく”という行動はとても難しいんです。
これは、ワーキングメモリ(短期的な記憶力)の働きが弱いため。
頭に入ってもすぐ他の情報で上書きされてしまうような状態です。
“見える化”で習慣化:持ち物チェック表・ゾーン設定
口で「持ち物そろえてね」と言っても、すぐ忘れてしまいます。
そこで効果的なのが、“見える形で”リマインドする工夫。
- 玄関に「持ち物チェック表」を貼る
- ランドセル置き場に“忘れ物ゾーン”を作る
- 写真付きのチェックリストを使う
これだけで、子どもが自分で確認できるようになります。
着替え~支度~連絡帳まで順序を固定して安心
ADHD傾向の子は、「次に何をすればいいか」がわからなくなると混乱します。
そこで、やることの順番を“固定化”しておくのがポイント。
たとえば、
着替え → 朝ごはん → 歯みがき → 連絡帳チェック → 出発
と、毎朝同じ順序にすることで、習慣として定着しやすくなります。
「できたね!」の一言で習慣を育てる
忘れ物を減らす一番の近道は、「できた」を褒めること。
完璧じゃなくても、「昨日より早く準備できたね!」など、小さな成功を一緒に喜びましょう。
成功体験の積み重ねが“やる気”を育てます。
困りごと③:切り替えが苦手・癇癪を起こしやすい
〜遊びから学習・家事への移行がスムーズにいかない〜
ADHD傾向の子は、好きなことに夢中になると“切り替え”がとても難しいです。
遊びをやめて宿題を始めるときなどに、泣いたり怒ったりしてしまうことも。
でも、「切り替えが苦手」=「こだわりが強い」ということではなく、“見通しのなさ”からくる不安なんです。
終わりを予告して安心感を:あと●分/あと●回を上手に使う
「いきなり終わり!」と言われると、誰でも嫌ですよね。
ADHD傾向の子は、“終わりの予告”で心の準備をすることが大切。
たとえば、
「あと3分でおしまいね」
「あと2回やったら終わりだよ」
と予告するだけで、切り替えがスムーズになります。
“次”を提示する遷移支援:終わり→次の構えで混乱を防ぐ
「終わり」と言われると、頭の中が“空白”になります。
そこで、「次」を示してあげると安心感が生まれます。
「おしまいにしたら、次はおやつにしよう」
「終わったら一緒にお散歩行こう」
といった“次への橋渡し”が、混乱や癇癪を防ぎます。
感情整理を手助け:絵カード・感情ボードで“今の気持ち”を言葉に
子どもが感情を言葉で表すのは難しいもの。
「怒ってる」「悲しい」「嫌だった」などの感情語を覚える練習を、遊び感覚で取り入れてみましょう。
絵カードや感情ボードを使って「今の気持ちはどれ?」と選ばせるのもおすすめです。
気持ちを言葉にできると、泣き続ける時間が減っていきます。
困りごと④:片づけ・整理整頓ができない
〜「散らかる」「どこから手をつける?」が日常に〜
「片づけてね」と言っても、手が止まる。
これは“やる気がない”のではなく、「どうやって片づければいいか分からない」からなんです。
収納場所を見える化:ラベル・写真・色分けで一目で分かる
「おもちゃ」「絵本」「ブロック」など、収納場所をラベルや写真で示すことで、子どもが迷わなくなります。
同じ形の箱を色で分けるのもおすすめ。
例:青=ブロック、赤=車のおもちゃ、黄=絵本
“見た目でわかる収納”は、片づけやすさの第一歩です。
ママと一緒に“片づけタイム”を!完璧は求めず習慣化
最初は一人でやらせるより、一緒に“体験”することが大切。
「どこから片づけようか?」と声をかけながら、片づけの流れを一緒にやってみましょう。
「全部きれいに」よりも、「おもちゃ箱に入れるだけ」でOK!
完璧より“続けられること”を目指すのがコツです。
ゲーム感覚で片づけ:タイマー競争&ご褒美シール作戦
子どもは“遊び”の中で力を発揮します。
「1分でどれだけ片づけられるかな?」など、ゲーム感覚で取り入れると意欲が上がります。
ご褒美シールやカレンダーで達成を見える化すると、続ける力が育ちます。
困りごと⑤:感情のコントロールが難しい
〜「怒り・泣き・イライラ」が突然来る〜
「泣かないで!」ではなく、「悲しかったね」「びっくりしたね」と共感して言葉にすることが大切。
ママが代弁してあげることで、子どもは「気持ちを言葉で伝えていいんだ」と学びます。
落ち着くルーティンを作る:深呼吸・お気に入りのぬいぐるみ・クールダウンスペース
癇癪が起きたときに“落ち着ける行動”を決めておくと安心です。
- 深呼吸を3回する
- お気に入りのぬいぐるみを抱っこする
- クールダウン用の静かなスペースに行く
これらを日常のルーティンにしておくと、感情が爆発しても回復が早くなります。
ママが“感情のモデル”になる:自身の気持ちを言葉にして子どもと共有
子どもはママの表情や言葉をよく見ています。
「ママも少しイライラしたけど、深呼吸したら落ち着いたよ」と伝えるだけで、感情の扱い方を学ぶチャンスになります。
発達障害(ADHD傾向)の子を家庭で「伸ばす」支援ポイント
「どうして同じことを何度も言わなきゃいけないの?」
「ほかの子はできるのに、うちの子はどうして…?」
そんな風に思うこと、ありませんか?
でも、ADHD傾向のある子どもにとって、家庭での“関わり方”がそのまま成長のスピードを変えることがあります。
ここで大切なのは、「叱る」より「整える」、そして「比べる」より「信じる」という視点。
ママが少し工夫するだけで、子どもが“できた!”と笑顔になる瞬間が増えていきます。
叱るのではなく“仕組み”で支える:環境調整+声かけのコツ
ADHD傾向の子どもに「何度言っても伝わらない」と感じたことはありませんか?
それは、聞いていないのではなく、脳の“注意の切り替え”がうまく働きにくいからなんです。
たとえば、
- ママの声がテレビや音の中にまぎれて聞き取りにくい
- 「~して、~して、それから~ね」と複数の指示が一度に入ってこない
このようなときに叱っても、子どもは「どうしたらいいか分からない」ままになってしまいます。
環境を整えることが最大の支援
- 声をかける前にテレビを消す
- 注意がそれやすい場所では、必要な物だけを置く
- やることリストを壁に貼る
このように、「やりやすい環境を作る」ことで叱る回数がぐっと減ります。
環境を整えることは、“ママの心を守る支援”にもなるんです。
声かけは短く・具体的に・肯定的に
抽象的な言葉(例:「ちゃんとしなさい」「早くして」)は伝わりにくいです。
代わりに、
「靴をはこうね」
「お皿をテーブルに置いてね」
のように具体的な行動を短く伝えるのがポイント。
そして、できたときには「ありがとう」「助かったよ」とすぐに声をかけましょう。
子どもは“叱られるより、認められることで伸びる”んです。
小さな“できた”を積み重ねて自信に変える:成功体験の設計法
ADHD傾向の子どもは、失敗体験が多くなりがち。
忘れ物をしたり、叱られたり、集団の中で浮いてしまったり…。
そんな中で、「どうせできない」と自己肯定感が下がってしまうことがあります。
でも、本当は“ちょっとした工夫”で成功体験を増やすことができるんです。
成功体験を“意図的に作る”という考え方
たとえば、
- 最初から「1分間だけお片づけ」など、ハードルを下げて設定する
- できたら「やったね!」と笑顔で伝える
- “完璧に”よりも“少し進んだこと”を評価する
この積み重ねが、「できるかも」「やってみよう」につながります。
「できない」を「できる形」に変える工夫
- 宿題が続かない → 5分タイマーを使って短く区切る
- 忘れ物が多い → 写真付きチェックリストを使う
- 集中が続かない → リズムや音で切り替えを促す
つまり、子どもに合わせてやり方を変えることが“支援”なんです。
「努力させる」ではなく、「できるように工夫する」。それがママにできる一番のサポートです。
「できたね」の瞬間を逃さない
子どもが自信を持つ瞬間は、意外と短いものです。
その瞬間を見逃さずに、「頑張ったね」「助かったよ」と声をかけてください。
ママの一言が、子どもの心のエネルギーになります。
周囲と比べない・“子ども軸”で見守る:その子らしさを大切にする視点
SNSやママ友との会話で、つい「ほかの子と比べてしまう」こと、ありますよね。
でも、ADHD傾向の子の成長スピードは“その子のペース”で進むものです。
「うちの子はまだできない」ではなく、
「昨日よりちょっとできた」
「今日は泣かずに挑戦できた」
そうやって、“その子の成長軸”で見てあげることが大切です。
発達には“でこぼこ”があるのが普通
発達は、まっすぐな坂道のように伸びていくわけではありません。
得意なことがぐんと伸びて、苦手なことがゆっくり追いかける――。
これが、子どもたちの自然な成長の姿なんです。
「比べない育児」はママをラクにする
他の子と比べるほど、ママの心が苦しくなります。
それよりも、「うちの子のいいところを見つける」時間を増やしてみましょう。
毎日ひとつ、「今日できたこと」「楽しかったこと」を一緒に話すだけでも、
親子の関係があたたかくなりますよ。
家庭で使える支援ツール&学校連携のヒント
ADHD傾向のある子を支えるために、ママができる工夫はたくさんあります。
特別な教材や高価なアイテムを買わなくても、100円ショップや家にあるもので十分効果的な支援ができるんです。
また、家庭での工夫だけでなく、保育園や学校との“連携”もとても大切。
ママだけががんばりすぎず、周囲と協力することで子どもも安心し、成長しやすい環境が整っていきます。
おうちで使えるおすすめグッズ&視覚支援アイデア
〜タイマー・チェック表・絵カードなど〜
「口で言っても伝わらない」「何度言っても動かない」——
そんなときに役立つのが、“見てわかる”支援=視覚支援です。
ADHD傾向のある子は、耳からの情報よりも目で見て理解するほうが得意な場合が多いです。
つまり、「言葉で伝える」よりも「見える形で示す」ほうがスムーズなんですね。
タイマー:時間の見通しを“見える化”する魔法のツール
ADHD傾向の子は、時間の感覚をつかむのが少し苦手です。
「あと5分でおしまいね」と言われても、“5分”がどのくらいなのか分かりにくいことがあります。
そんなときは、タイマーを使って時間を視覚的に示すのがおすすめ。
たとえば、
- キッチンタイマー
- 時間が減っていくタイプの「ビジュアルタイマー」
- スマホアプリのカウントダウン機能
を使って、「赤い部分が消えたら終わりだよ」と見せると、子どもも安心して切り替えやすくなります。
タイマーは「急かす」ためではなく、“見通しを持たせる”ための道具として使うのがポイントです。
チェック表・ToDoリスト:やることを整理して混乱を防ぐ
ADHD傾向の子どもは、やることが頭の中でごちゃごちゃしやすいです。
「何を先にすればいいか」が分からず、途中で別のことを始めてしまうこともあります。
そんなときは、チェック表やToDoリストを使うととても便利。
- 朝の支度(着替え→朝ごはん→歯みがき→連絡帳)
- 学校の準備(筆箱→連絡帳→水筒→タオル)
のように、やることを順番に並べておき、終わったら✔️をつけるだけ。
これだけで、「次に何をすればいいか」が明確になり、ママの声かけが減って親子のストレスも軽くなります。
壁に貼るタイプでも、ホワイトボードに書いてもOK。
「できたね!」と一緒に✔️を入れる時間を、親子のコミュニケーションタイムにするのもおすすめです。
絵カード・スケジュールボード:視覚で理解をサポート
まだ文字が読めない子どもや、言葉での説明が苦手な子には、絵カードが効果的です。
たとえば、
- 「ごはん」「はみがき」「トイレ」「ねる」などをイラストで並べた1日の流れ
- 「怒っている」「うれしい」「悲しい」を表した感情カード
を使うと、言葉にしにくいことを“見える形”で伝えられるようになります。
「今はこの時間」「次はこれをする」が見えると、子どもは安心して動けます。
絵カードは手作りでもOK。100均のシールや写真を使っても十分実用的です。
その他の“おうち支援アイデア”
- 色分け収納:ランドセル・文具・おもちゃを色ごとに分けると、整理しやすくなる
- リマインダー音声:「そろそろ出発の時間だよ」とアラームで知らせる
- ママの一言メモ:「できたらシール!」など、小さなご褒美でやる気アップ
支援のコツは、“管理”ではなく「安心して動ける環境」を作ること。
道具を使うことで、ママの声かけが減り、子どもも「自分でできた!」という達成感を味わいやすくなります。
保育園・学校と連携して困りごとを減らす
〜担任との共有ポイントと家庭→園・学校間の連絡のコツ〜
ADHD傾向のある子どもは、家庭ではできても学校では難しい、その逆もよくあります。
だからこそ、家庭と園・学校が同じ方向を向くことがとても大事。
ママがすべてを背負うのではなく、「チームで支える」意識が子どもの安心につながります。
担任との共有ポイント:具体的に伝えるのがコツ
先生に相談するときは、「ADHD傾向があるかもしれません」といった言い方よりも、
“具体的な行動面”に焦点をあてて伝えると、理解してもらいやすくなります。
たとえば、
- 「集団の中で指示が通りにくいようです」
- 「一度に複数の指示が入ると混乱してしまいます」
- 「興味のあることには集中しますが、切り替えが苦手です」
というように、状況を客観的に説明するのがポイント。
そのうえで、
「家庭ではチェックリストを使うとスムーズにできています」
など、うまくいった工夫を共有すると、先生も取り入れやすくなります。
家庭と園・学校間の連絡のコツ
家庭と学校の情報共有は、「連絡帳」や「ノート」で継続的に行うのがおすすめです。
- 「家庭では落ち着いていました」
- 「最近は忘れ物が減りました」
- 「昨日は眠れず少し不安定でした」
など、小さなことでも書き残しておくことで、先生がその日の対応を調整しやすくなります。
また、「うまくいったこと」も必ず書くのが大切。
「今日は授業中に最後まで座っていられたそうです!」など、学校側のポジティブな報告も、ママの励みになります。
“チームで支える”という意識を持とう
子どもの成長は、ママ・先生・支援員など、周囲の人たちとの協力で少しずつ進んでいくものです。
連携を通して、ママが一人で抱え込む負担を減らすことができます。
「先生と協力して、子どもに合ったペースを見つける」
「できたことを一緒に喜ぶ」
その積み重ねが、子どもの安心と自信を育てる土台になります。
【まとめ】困りごとは“特性”の表れ。今日からできる家庭支援で親子笑顔に
ADHD傾向のある子を育てていると、「なんでうまくいかないんだろう」「どうしてこの子だけ違うんだろう」と感じる日もありますよね。
でも、その“困りごと”は、実は子どもの個性=特性の表れでもあるんです。
たとえば、
- 集中できない → 興味のあることに強く惹かれる力がある
- 落ち着かない → 行動力があり、思い立ったらすぐ動ける
- 忘れっぽい → その瞬間を全力で生きている
一見“困った行動”に見えることも、見方を変えれば「その子らしさ」そのもの。
大切なのは、“できないこと”に焦点を当てるのではなく、“どうすればできるようになるか”を一緒に考えることです。
ADHD傾向=「その子らしい成長ゆえの特性」
ADHD傾向とは、発達が“でこぼこ”な成長パターンのひとつ。
つまり、苦手なことがある一方で、得意なことや強みもはっきりしているのが特徴です。
「話を聞くのが苦手」でも、「発想力がすごい」子もいます。
「集中が続かない」けれど、「ひとつのことに夢中になると誰にも負けない」子もいます。
ママがこの“強み”を見つけてあげるだけで、子どもの表情はどんどん変わります。
子どもの中に“光る部分”を見つけて育てる。
それが、家庭でできるいちばんの支援です。
今日からできる小さな工夫の積み重ねで大きな変化に
支援は、難しいことをしなくても大丈夫。
「今日からできること」を少しずつ重ねるだけで十分です。
たとえば、
- 朝の支度をタイマーでリズム化する
- 片づけの時間を「一緒に楽しく」に変える
- 「ダメ!」より「こうしてみようね」と伝える
そんな小さな工夫の積み重ねが、親子の笑顔につながるんです。
家庭での工夫は、すぐに効果が出るわけではありません。
でも、焦らずに続けていくうちに、
「あれ?このごろ癇癪が減ったかも」
「少しずつ落ち着いてきた気がする」
そんな変化に気づける日が、必ずやってきます。
ママが笑顔でいられる日々=子どもの安心と自信に直結
子どもにとって、ママの笑顔は何よりの安心材料です。
どんなに注意されることがあっても、ママが「大丈夫だよ」と笑ってくれると、子どもは「自分は愛されている」と感じます。
ママが「うまくいかなくてもいい」「今日はこれでOK」と思えるようになると、
その安心感が子どもにも伝わって、親子の関係がふんわり優しく変わっていきます。
だからこそ、ママの心のケアも忘れずに。
「少し疲れたな」と感じたら、コーヒーを一杯飲んで深呼吸するだけでもOK。
ママが笑顔でいられることが、子どもにとって最大の支援です。
以上【ADHD(注意欠如多動症)傾向のある子にありがちな困りごとTOP5&今すぐできる対処法】でした

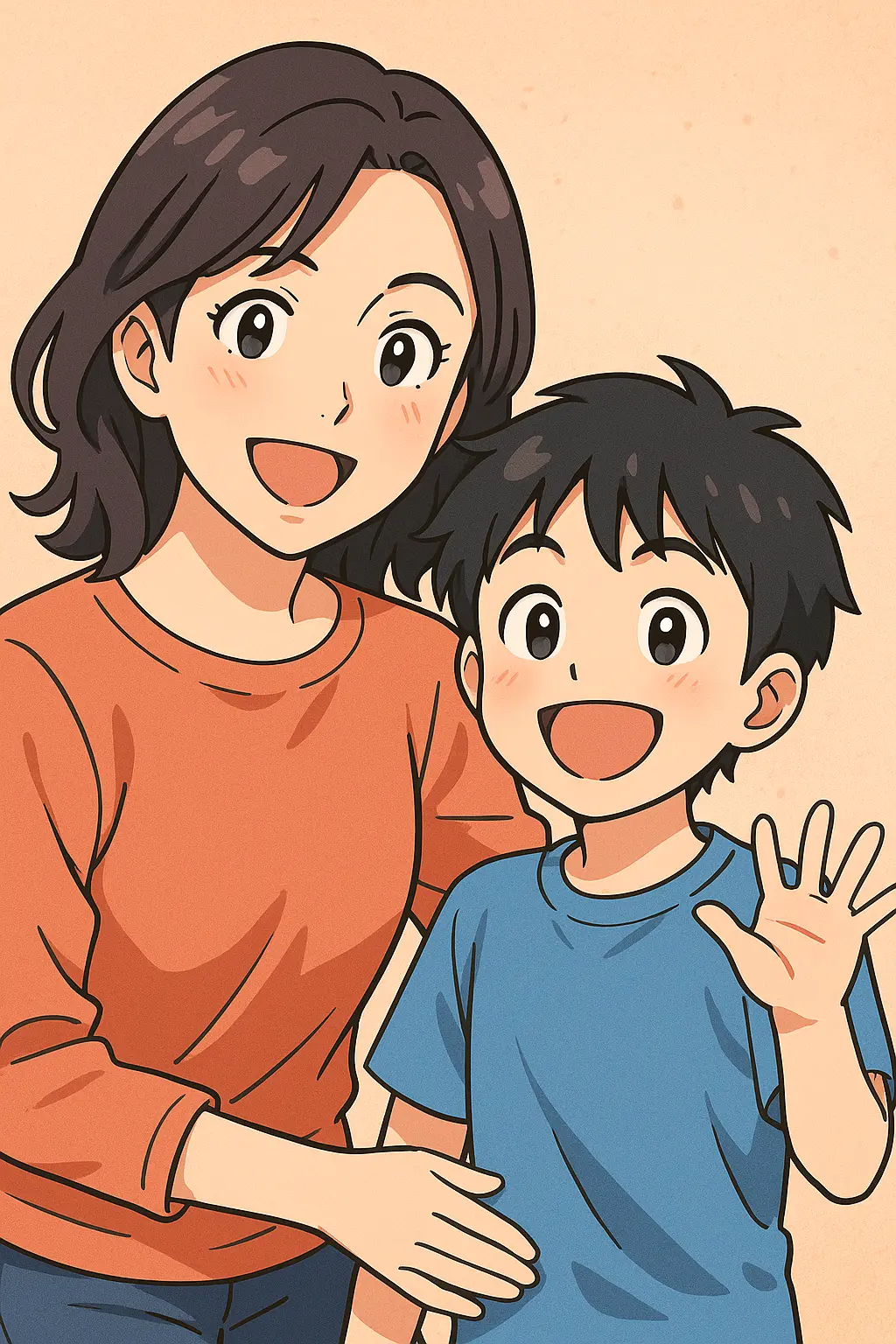









コメント