ADHDの子どもはなぜ眠い?「過眠」と睡眠リズムの関係を徹底解説
ADHDとは?特性と「睡眠リズムの乱れ」に関係がある理由
ADHD(注意欠如・多動症)は、集中が続きにくい・落ち着きがない・衝動的に行動してしまうといった特性をもつ発達特性のひとつです。
でも実は、これらの特性だけでなく、「睡眠リズムが乱れやすい」という共通の特徴もあることがわかっています。
たとえば、夜になると急に元気が出てしまったり、朝なかなか起きられなかったり…。
「夜更かししてるからでしょ?」と思われがちですが、そうではありません。
ADHDの子どもたちは、脳の“覚醒スイッチ”がうまく切り替わらないことが多いんです。
つまり、昼間に頭がボーッとしたり、夜に眠れなくなったりするのは、「生活態度の問題」ではなく脳の働き方の違いが関係しているんですね。
この「覚醒と睡眠のバランス」が崩れることで、結果的に“過眠”や“寝つきの悪さ”につながることがあります。
「ADHDの過眠」とは?ただの寝不足とは違う特徴
ADHDの子どもが「眠い」「寝ても寝ても眠い」と言うと、「寝不足なんでしょ?」と思われることが多いですよね。
でも、ここでいう“過眠”は、単なる寝不足や生活リズムの乱れとは少し違います。
過眠とは、十分な睡眠時間をとっても日中に強い眠気が続く状態のこと。
つまり「寝てるのに眠い」「朝から頭が重い」「動き出すまで時間がかかる」などが特徴です。
ADHDの子どもは、脳が情報を整理したり、感情を抑えたりするためにとてもエネルギーを使っています。
そのため、日常生活の中で“脳が疲れやすい”傾向があり、その疲れが「過眠」という形で出てくることもあります。
また、「学校では頑張って起きているけど、家ではぐったり」というように、場所によって眠気の出方が変わる子もいます。
これは、脳が常にオンの状態で働き続けているため、家で一気にエネルギーが切れてしまうからなんですね。
ADHDの子が過眠になりやすい3つの原因
ADHDの子どもが過眠になりやすい理由はいくつかありますが、ここでは代表的な3つを紹介します。
① 脳の覚醒システムの乱れ
ADHDの子どもは、脳の「オン」と「オフ」を切り替える機能が少し不安定です。
普通の人なら、朝になると自然に「覚醒ホルモン(ドーパミン・ノルアドレナリンなど)」が働いて体がシャキッとしますが、ADHDの子ではこの働きが弱いことがあります。
そのため、朝になっても脳が“起動”しない状態が続くんです。
逆に、夜になると覚醒が高まり、眠れなくなることも…。
この「昼夜逆転のリズム」が、慢性的な過眠につながることもあります。
② 睡眠の質の低下
ADHDの子どもの多くは、眠りが浅く、途中で何度も目が覚めるといわれています。
これは、体は寝ていても脳が完全には休めていない状態。
「朝まで寝たのに疲れが取れない…」と感じるのはこのためです。
また、寝る直前までスマホやテレビなどで強い光を浴びると、睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌が抑えられてしまい、さらに眠りの質が悪くなります。
結果として、「長く寝ても眠気がとれない」という悪循環に…。
③ 夜型生活・刺激過多などの生活習慣
ADHDの子どもは、刺激に敏感で好奇心旺盛。
夜になっても頭の中がフル回転して、「もう少し遊びたい!」「考えが止まらない!」という状態になりやすいです。
こうした夜型の生活習慣が続くと、体内時計がずれてしまい、朝の覚醒リズムが乱れます。
さらに、ADHDの特性として「一度始めたことをやめられない」「興味のあることに集中しすぎる(ハイパーフォーカス)」という傾向もあります。
その結果、寝る時間がどんどん遅くなり、昼間の眠気が強くなるという流れが生まれてしまうのです。
「頑張っても起きられない」は怠けじゃない!親が知るべき理解のポイント
ADHDの子どもが朝なかなか起きられないと、つい「また寝てるの?」「いい加減に起きて!」とイライラしてしまいますよね。
でも、ここで大事なのは、“頑張っても起きられない”のはサボりではなく、脳の特性によるものという理解です。
ADHDの子どもにとって、朝起きるという行為は「脳のエンジンをかける」ようなもの。
そのエンジンがうまく回らないときに「早く動け!」と言われても、体がついてこないんです。
もしここで叱ってしまうと、子どもは「どうせ自分はダメなんだ」と感じ、自己肯定感がどんどん下がってしまいます。
すると、「朝=怒られる時間」と思って、ますます起きられなくなる悪循環に…。
まずは、「朝が苦手なのはこの子のせいじゃない」「どうすれば気持ちよく目覚められるかを一緒に探そう」というスタンスで寄り添うことが大切です。
理解から始まる支援が、子どもの心と生活リズムを整える第一歩になります。
ADHDの子どもの眠気対策!家庭で見直すべき5つの生活習慣
ADHDの子どもは、朝に弱かったり、日中ぼーっとしてしまったりと、眠気の波が激しいことがよくあります。
それは単なる「夜更かし癖」ではなく、脳の覚醒リズムが整いにくいことが関係しています。
ここでは、家庭でできる“ちょっとした見直し”で、眠気を軽くしてあげる方法を紹介します。
どれも特別な道具や難しい知識はいりません。毎日の中で少しずつ取り入れていくことが大切です。
朝スッキリ起きる!ADHDの子に効く「起きる時間固定法」
「寝る時間を早くしなきゃ」と思っても、なかなか寝つけない…。
ADHDの子にとって、“寝る時間”をコントロールするのは難しいことがあります。
そこでおすすめなのが、「起きる時間を固定する」という考え方。
寝る時間よりも「毎朝同じ時間に起きること」を優先するんです。
たとえ前の晩に寝るのが遅くなっても、朝はできるだけ同じ時間に起こす。
最初は眠そうにしていても、体内時計は“朝の光”で少しずつリセットされていきます。
朝になったら、カーテンを開けて太陽の光を部屋いっぱいに入れてみましょう。
光が目に入ることで、脳のスイッチが入り、「メラトニン(眠気ホルモン)」が減って「セロトニン(やる気ホルモン)」が分泌されるようになります。
さらに、
- 朝に好きな音楽を流す
- 香り(アロマやコーヒーの匂いなど)で覚醒を促す
- 起きたら「〇〇できたね!」と褒める
など、“朝が楽しい時間”に変える工夫も効果的です。
「起きなさい!」よりも、「一緒に朝ごはん食べよう」「今日は天気いいね」など、軽い会話から始めるとスムーズですよ。
夜になると元気?ADHD特有の“夜型リズム”を整える工夫
ADHDの子どもは、夜になると急にエネルギーが湧いてきて、テンションが上がることがあります。
これは、脳の覚醒スイッチが夜に入ってしまう「夜型リズム」によるものです。
「もう寝る時間だよ」と言っても、頭の中が活発に動いている状態ではなかなか眠れません。
このタイプの子には、“寝る準備スイッチ”を作るのがおすすめです。
たとえば…
- 寝る1時間前にはテレビやスマホを消す
- 照明を少し暗くして“夜モード”に切り替える
- 静かな音楽やオルゴールを流す
- お風呂のあとに絵本を読む・ストレッチをする
こうして「もうすぐ寝る時間」というサインを体に伝えることが大切です。
特に注意したいのが、スマホやタブレットの画面。
強い光(ブルーライト)は脳を覚醒させてしまい、眠気ホルモンの分泌を止めてしまうんです。
「寝る前は10分だけ…」のつもりが、つい1時間経っていた、なんてこともありますよね。
もしどうしても使いたい場合は、夜9時以降はブルーライトカットモードに設定したり、音声だけのコンテンツに切り替えるなど、段階的に減らす工夫もおすすめです。
夜を“リラックスする時間”に変えていくことで、自然と眠りのスイッチが入りやすくなります。
食事と睡眠の深い関係|朝食・栄養バランスで眠気をリセット
睡眠と食事は、実はとても深くつながっています。
ADHDの子どもにとって、「何を・いつ食べるか」は、眠気のコントロールにも影響します。
特に大事なのが朝ごはん。
朝ごはんを食べることで、体内時計が「朝だよ!」とリセットされます。
逆に朝食を抜くと、脳がまだ“夜モード”のままで、午前中ずっとぼーっとしてしまうことも。
おすすめは、たんぱく質をしっかりとる朝ごはんです。
卵、納豆、ヨーグルト、ツナ、チーズなどは、脳内の「セロトニン」を増やしてくれます。
セロトニンは、夜になると「メラトニン(眠気ホルモン)」に変化するので、“よく寝て、スッキリ起きる”ための材料にもなるんです。
また、日中の食事もポイント。
- 甘いお菓子やジュースを摂りすぎない
- 夜遅い時間の食事を避ける
- 鉄分やビタミンB群も意識して摂る
といったバランスが大切です。
食事を整えることは、眠気対策だけでなく集中力アップや情緒の安定にもつながるので、無理のない範囲で少しずつ取り入れていきましょう。
感覚過敏にも配慮!ADHDの子どもが眠れる寝室づくりのコツ
ADHDの子どもの中には、「音」「光」「触感」などの刺激に敏感なタイプの子も多くいます。
そうした感覚過敏があると、眠りづらさにもつながります。
まず見直したいのは寝室の環境です。
「静かにすれば寝られる」という単純な話ではなく、“その子が安心できる空間”を作るのがポイント。
たとえば:
- 真っ暗が怖い子 → 小さな常夜灯をつける
- 静かすぎて落ち着かない子 → やさしい環境音(雨音や波の音)を流す
- 布団の感触が苦手な子 → 柔らかめや重めのブランケットに変える
また、寝る位置を変えただけで落ち着く子もいます。
壁側に頭を向けることで「安心感」が増して眠りやすくなるケースもあります。
温度や湿度も意外と重要です。
特に冬は部屋が乾燥すると喉が痛くなったり、寝苦しさにつながることがあります。
加湿器や空気清浄機をうまく活用して、“心地よく眠れる空気”を整えることも大切です。
寝室の環境を変えることで、「夜が楽しみ」「お布団が気持ちいい」と思えるようになれば、寝つきが驚くほど良くなる子も多いです。
まとめ:生活リズムを整える第一歩は“環境と習慣”から!
ADHDの子どもの眠気対策で大事なのは、「努力」ではなく「仕組み」です。
無理に頑張らせるよりも、自然とリズムが整っていく環境を作ることが近道です。
朝の光、夜の静けさ、食事のリズム、安心できる寝室…。
どれかひとつ変えるだけでも、子どもの体は少しずつ変化していきます。
家庭でできる!眠気が止まらないADHDの子に試したい5つの支援方法
第2章では、生活習慣の整え方をお伝えしましたが、
ここではさらに一歩進んで、実際に家庭でできる“具体的な支援方法”を紹介します。
「朝、起きない」「昼間に眠くて集中できない」「夜になっても寝ない」…
ADHDの子の眠気トラブルは、ママの根気だけではどうにもならないことが多いですよね。
でも大丈夫です。
「頑張らせる」よりも「仕組みで助ける」ことがポイントなんです。
ここで紹介する5つの方法は、どれもすぐ始められるものばかり。
子どもの“できない”を“できた!”に変えるコツを一緒に見ていきましょう。
【支援①】「朝起きられない」を変える!楽しく起きる朝ルーティン術
ADHDの子どもは、朝の切り替えがとても苦手です。
目が覚めても、脳がまだ“スリープモード”のままということがよくあります。
そんな子どもに「早く起きなさい!」と怒っても、逆に動けなくなってしまうんですよね。
そこで大切なのが、「楽しく・心地よく起きられる工夫」です。
音楽・光・香りで“心地よく目覚める”工夫
朝、いきなり目覚まし時計の大音量で起こすのではなく、
やさしく刺激を与えるのがポイントです。
- 好きな曲をタイマーで流す(アニメのテーマ曲などもおすすめ)
- カーテンを開けて自然光を入れる
- アロマディフューザーや柑橘系の香りで脳を“覚醒モード”に
光・音・香りの3つの刺激を使うことで、脳が「朝だ!」と自然に反応していきます。
中でも朝日を浴びることはとても効果的。
朝の光が体内時計をリセットし、メラトニンの分泌をストップしてくれるんです。
ADHDの子におすすめの目覚ましアイテム&成功体験の作り方
ADHDの子には、「体を動かす目覚まし」が合うこともあります。
たとえば、部屋の反対側で鳴るタイプや、光で起こすタイプの目覚ましなど。
自分で止めに行くことで、自然に体が目覚めていきます。
また、「起きる」という行動を“成功体験”として感じさせてあげるのも大切。
起きたらすぐ「よく起きられたね!」「今日はスムーズだったね」と小さく褒めることで、
子どもは“次も頑張ろう”という気持ちになります。
朝のスタートを「失敗体験」ではなく「成功体験」に変えること。
これが、朝のバトルを減らす第一歩です。
【支援②】昼間の眠気対策!ADHDの子に合った活動量コントロール
ADHDの子は、体の動きと脳の働きのバランスが取りづらい傾向があります。
つまり、「動きすぎても疲れる」「動かなすぎても眠くなる」という状態です。
「動きすぎ」「動かなすぎ」を防ぐ1日のバランス調整
たとえば、
午前中にずっとゲームや動画を見ていると、体は休んでいるのに脳が疲れてしまいます。
逆に、朝から外で走り回りすぎると、昼過ぎにエネルギー切れを起こすことも。
ポイントは、活動と休息のリズムを交互に入れること。
- 朝:軽い運動(ストレッチ・散歩・トランポリンなど)
- 午前:集中する時間(学習・作業)
- 昼:しっかりご飯+静かな遊び
- 午後:短時間の外遊びや体を使う活動
こうして、1日の中で「動く時間」と「落ち着く時間」を意識的に交互に入れることで、
脳の覚醒レベルが安定し、眠気の波が減っていきます。
昼寝・休憩のタイミングで集中力アップ
昼間の眠気を防ぐために、「昼寝」を上手に取り入れるのもおすすめ。
ただし、寝すぎには注意!
- 目安は20〜30分以内
- 15時以降はできるだけ控える
少しの昼寝で脳の疲れをリセットでき、午後の集中力がグンと上がることがあります。
もし寝かせたくない場合でも、10分ほど静かに横になる“リラックスタイム”を設けるだけで効果があります。
【支援③】“眠りの質”を上げる夜のリラックス習慣
夜の時間は、1日の緊張をほどいて副交感神経を整える時間です。
特にADHDの子どもは、頭の中がいつも動いていて、気持ちの切り替えが苦手な子が多いですよね。
そこでおすすめなのが、「寝る前の安心ルーティン」。
就寝前の安心ルーティンで副交感神経を整える
寝る前に毎日同じ流れを作ることで、脳が「もうすぐ寝る時間だ」と認識します。
たとえば、
- お風呂に入る
- パジャマに着替える
- 部屋を暗くして絵本を読む
- 「おやすみなさい」のハグをする
このように、安心できる順番を毎日繰り返すだけでも、眠りの質が変わってきます。
脳が“安心”を感じることで、自然に眠気がやってくるんです。
ストレス・緊張を和らげる音楽・アロマ・スキンシップ活用法
寝る前に心を落ち着かせるには、感覚を使ったリラックスが効果的。
- やさしい音楽やオルゴールを流す
- ラベンダーなどのアロマを香らせる
- 背中をさすって「今日もよく頑張ったね」と声をかける
こうしたスキンシップは、安心感と睡眠ホルモンの分泌を促します。
「寝る=心地いい時間」と思えるようになると、夜の入眠がスムーズになりますよ。
【支援④】“時間の見通し支援”で生活リズムを安定化
ADHDの子どもは、「あと5分」「もうすぐ寝るよ」と言われてもピンと来ないことが多いです。
時間の感覚(タイムマネジメント能力)が育ちにくいからなんですね。
ADHDの子が苦手な「時間感覚」を補うビジュアルタイマーの活用
目で見て分かるタイマーを使うことで、「時間の流れ」がつかみやすくなります。
たとえば、残り時間が赤い円で見える「ビジュアルタイマー」や、
砂時計・カウントダウンアプリなどを使うのもおすすめです。
これがあると、
「もうすぐ寝る時間だね」→「赤い部分がなくなったら寝るんだね」
というように、“見える化”で理解できるようになります。
朝・夜の流れを見える化する支援ツール例
スケジュールボードやチェックリストも有効です。
たとえば:
朝の流れ
- 顔を洗う
- ごはんを食べる
- 歯を磨く
- 服を着る
夜の流れ
- お風呂に入る
- パジャマを着る
- 歯を磨く
- 絵本を読む
こうしたボードを子どもと一緒に作るのもおすすめ。
「今日はどこまでできたかな?」と確認することで、自分で動く力(自己管理力)が育ちます。
【支援⑤】「自分でもできる!」を育てる自己理解と声かけ
最後に大切なのは、“自分を責めない気持ち”を育てる支援です。
ADHDの子どもは、「できない自分」に気づきやすく、自己否定感を持ちやすい傾向があります。
だからこそ、ママの言葉がけがとても大事なんです。
「眠くて動けない」気持ちを否定しない関わり方
「なんで起きないの!」「やる気がないの?」ではなく、
「眠いよね、体が動かない感じなんだね」と気持ちを言葉で受け止めることから始めてみましょう。
気持ちを認められることで、子どもは安心し、少しずつ動き出せるようになります。
「できたね」「少し動けたね」で自尊感情を守る
朝に起きられた、服を着替えられた、歯を磨けた――
その小さな一歩を見逃さず、「できた!」を積み重ねることが自信になります。
たとえ完璧じゃなくても、
「昨日よりちょっと早く起きられたね!」
「自分で顔洗えたね!」
そんな一言で、子どもは確実に前に進んでいきます。
まとめ:支援のカギは“理解・環境・声かけ”の3つ
眠気の強いADHDの子どもに必要なのは、叱ることではなく、理解と仕組みと優しい言葉です。
少しずつできることを増やしていくことで、「朝が苦手な自分」から「できる自分」に変わっていきます。
焦らず、ゆっくり、親子で歩いていきましょう。
いつ相談すべき?ADHDの過眠が続くときに受診したい専門機関
「毎日眠そう」「学校で居眠りしてしまう」「朝がどうしても起きられない」…。
ここまで紹介してきた生活習慣の見直しや家庭での支援をしても、なかなか改善しないときは、専門家に相談するタイミングかもしれません。
ADHDの子どもの「眠気」には、発達特性だけでなく、別の睡眠障がいが隠れている場合もあるからです。
この章では、受診を考えるべきサインや、相談先の選び方・伝え方のポイントをわかりやすく解説します。
医師に相談が必要な“睡眠異常サイン”とは?
ADHDの子どもの眠気が続くとき、すべてが「発達特性だから」とは限りません。
睡眠そのものに問題がある場合もあります。
次のようなサインがある場合は、早めに専門医へ相談してみましょう。
睡眠時無呼吸症候群・ナルコレプシー・周期性過眠症の可能性
眠っている間に呼吸が止まったり、浅い呼吸が続いたりする睡眠時無呼吸症候群。
寝ても寝ても眠気が取れないナルコレプシーや、数日〜数週間、極端な眠気が続く周期性過眠症など、
ADHDの症状と似たような“眠気のトラブル”を起こす病気もあります。
見分けがつきにくいですが、次のようなサインがある場合は注意です。
- 朝どんなに寝ても強い眠気が続く
- 睡眠時間が長いのに疲れが取れない
- 夜にいびきをかく、呼吸が止まる
- 急に意識が落ちるように眠ってしまう
- 情報処理や記憶が以前より遅くなった
これらの症状が見られる場合は、脳や睡眠の働きに関わる疾患の可能性があります。
発達外来や小児神経内科、小児睡眠外来などで相談してみるとよいでしょう。
学校や日常生活に支障が出ているときの相談目安
眠気が強いことで、次のような状態が続いている場合も、受診の目安になります。
- 学校で授業中に居眠りしてしまう
- 朝起きられず、登校が遅れる日が多い
- 宿題や勉強に集中できない
- 感情が不安定で、イライラ・不機嫌が続く
ADHDの特性だけでなく、睡眠不足や過眠が学習・行動・感情に影響している可能性があるからです。
特に、「以前はできていたことができなくなった」「性格が変わったように感じる」場合は、脳の疲れや睡眠の質の低下が背景にあることも。
ママが「ちょっと変だな」と感じたときが、相談のベストタイミングです。
「様子を見よう」と思っているうちに、子どもの自己肯定感が下がってしまうこともあるので、早めの相談が安心です。
発達外来・睡眠外来・療育機関との上手な連携方法
「どこに相談したらいいの?」と迷うママも多いですよね。
実は、ADHDの眠気問題は“ひとつの機関だけ”では解決しにくいことが多いんです。
だからこそ、医療・療育・学校の三者連携がとても大切になります。
ADHDの眠気を理解してもらうための伝え方例
受診時に「朝が苦手なんです」「寝ても眠いみたいで…」とだけ伝えると、医師も具体的な状態をつかみにくいことがあります。
そこで、少し詳しく状況を整理して伝えると、診察がスムーズになります。
たとえば、こんな伝え方がおすすめです。
- 「寝るのが遅く、起きるのが難しい。朝は1時間くらい動けません」
- 「睡眠時間は8〜9時間ですが、日中も強い眠気があります」
- 「週に何回か、授業中に眠ってしまうようです」
- 「生活リズムを整えても改善が見られません」
こうした具体的な情報があると、医師が睡眠障がいの可能性を検討しやすくなります。
できれば、1〜2週間の睡眠記録(就寝・起床時間、昼寝の有無など)をメモして持参するとさらによいでしょう。
「朝が苦手」子どもに学校で配慮をお願いする際の具体的フレーズ
学校での配慮をお願いするときも、“甘え”や“怠け”と誤解されないような伝え方が大切です。
先生にお願いするときの例文をいくつか紹介します。
例文①:授業への配慮をお願いしたい場合
「朝の切り替えが難しく、1時間目は集中が続きにくいことがあります。最初のうちは声かけをゆっくりめにお願いできますか?」
例文②:遅刻や欠席が増えている場合
「体調というよりも、睡眠リズムの乱れが関係しているようです。できる範囲で出席できるよう支援していきたいと思っています。」
例文③:学校全体に理解を促したい場合
「ADHDの特性として、朝の覚醒に時間がかかる子もいます。本人なりに頑張っていますので、焦らせない対応をお願いしたいです。」
こうした言葉を使うことで、先生も「支援が必要な状態」として理解しやすくなります。
また、療育機関や発達外来の先生に「学校にこう伝えたいのですが、どう説明すればいいですか?」と相談するのもおすすめです。
学校・医療・家庭が連携できると、子どもが安心して過ごせる環境が整い、生活リズムも安定しやすくなります。
まとめ:眠気が続くときは“早めの相談”が安心
ADHDの子どもの「過眠」には、
- 発達特性による覚醒リズムの乱れ
- 睡眠障がいの可能性
- 生活環境・心理的ストレス
など、いくつもの要因が重なっていることがあります。
ママが「この子、なんだかおかしいな」と感じたときは、それが最初のサインです。
我慢や努力ではなく、医師や専門家と一緒に仕組みを整えることが何よりの支援になります。
そして、どんな結果になっても、子どもに伝えたいのはこの一言。
「眠くても大丈夫。あなたのせいじゃないよ。一緒に楽しく整えていこうね。」
理解と共感こそが、子どもの心を支えるいちばんの力になります。
毎朝バトルにならないために|ママの心のケアとサポート法
ここまで、「ADHDの子どもが過眠になりやすい理由」や「家庭でできる支援方法」を紹介してきました。
けれど、どんなに知識が増えても、実際に毎朝“起こす側”のママのしんどさは変わりませんよね。
「なんで起きられないの?」「また遅刻…」
頭では分かっていても、ついイライラしてしまう。
そしてあとで「怒らなければよかった」と落ち込む――そんな日もあると思います。
でも、それはあなただけではありません。
発達特性のある子どもを育てている家庭では、“朝の戦い”が一番のストレス源になることが多いのです。
ここでは、ママ自身の心を守りながら、親子で穏やかな朝を迎えるためのヒントをお話しします。
「頑張っても起きない」子に疲れたママへ|罪悪感を軽くする考え方
ADHDの子どもにとって「起きる」という行動は、私たちが思っているよりずっと大変なこと。
脳の覚醒スイッチが入りにくいので、本人も“起きたいのに起きられない”と苦しんでいる場合があります。
それを知らないままだと、どうしても「怠けてるのかな?」「親のしつけが悪いのかな?」と感じてしまいがち。
でも、ここで忘れてほしくないのは――
子どももママも、どちらも悪くない。
ということです。
「できない」には“理由”があると知るだけでラクになる
子どもが起きられないとき、つい「意志が弱い」と思ってしまいがちですが、実際は脳の機能の問題が関係しています。
覚醒を促す神経の働きや、体内時計のリズム調整が上手くいかないことで、
「頑張っても体がついていかない」状態になっているんです。
つまり、「起きられない=怠けている」ではなく、
“起きるための仕組みがまだ整っていない”だけ。
この視点を持つだけで、ママの罪悪感はぐっと軽くなります。
「うまくいかない朝」も学びのチャンスに変える
朝バトルになった日こそ、親子にとっての成長チャンスです。
「今日は起きられなかったね。でもどうすれば少し楽になるかな?」
と、一緒に考える時間にしてみましょう。
子ども自身が「ママと一緒に考えてくれる」と感じるだけで、安心してチャレンジできます。
完璧を目指すより、“気づきの積み重ね”が次の一歩につながります。
ママ自身の睡眠・休息も“家庭のリズム支援”の一部
子どもの睡眠を整えることばかりに意識が向くと、つい忘れがちなのが、
ママ自身の休息と睡眠の大切さです。
実は、親の疲労や睡眠不足は、家庭全体のリズムにも大きく影響します。
ママの心と体が整っていると、子どもにもその“落ち着きのリズム”が伝わるんです。
無理せず完璧を求めない「今日はここまででOK」の発想
ADHDの子の朝支援は、うまくいく日もあれば、どうにもならない日もあります。
そんなときは、「今日はここまでできたからOK!」と、“合格ラインを下げる勇気”を持ってください。
たとえば、
- 起きられなかったけど朝ごはんは食べられた
- 着替えは手伝ったけど、登園(登校)は笑顔でできた
- 準備に時間がかかったけど、最後までやり遂げた
これだけでも、十分に前進しています。
「全部できなかった」ではなく、「これだけできた」に目を向けることで、ママの心も軽くなります。
夫・家族・専門家と連携して“親の睡眠負債”を防ぐ
毎日の朝支援をママ一人で抱えると、心も体も疲れきってしまいます。
その疲れが続くと、いわゆる「睡眠負債(慢性的な寝不足)」になり、
イライラや無気力、集中力の低下につながることもあります。
だからこそ、「一人で頑張らない」ことが最大の支援。
- 夫や家族に「朝の声かけ」や「朝食の準備」を一部お願いする
- 週末はママが少しゆっくり寝られる日を作る
- 療育や発達外来で「朝が大変」と相談し、支援方法を一緒に考えてもらう
家庭と専門家で支え合うことで、ママの睡眠も“家庭のリズム支援”の一部として守ることができます。
継続が力に変わる!少しずつ整っていく親子の生活リズム
ADHDの子どもの生活リズムは、すぐには整いません。
けれど、続けていくうちに少しずつ変化が見えてくるものです。
「昨日より今日が少しマシ」でもOK
「今日は昨日より3分早く起きられた」
「泣かずに着替えられた」
――そんな小さな変化を見つけて、“進歩”として喜ぶことが大切です。
大人の感覚だと「たった3分」と思うかもしれませんが、
子どもにとっては「自分でできた!」という大きな一歩。
成功体験を積み重ねることで、子どもは「自分にもできる」という自信を育てていきます。
この“小さなできた”が積もって、やがて“自分で起きられる力”へとつながります。
成功体験の積み重ねが“朝の自信”につながる
ママの声かけも、「できたところ」に焦点を当てるのがポイントです。
たとえば:
- 「今日は早く目が覚めたね!」
- 「昨日よりスムーズに着替えられたね!」
- 「自分からお布団から出られたの、すごいね!」
こうした肯定的な言葉が、子どもにとっての“エネルギー”になります。
叱られるよりも「できたね!」の一言のほうが、次の日の行動を変える力になるんです。
まとめ:ママが笑顔だと、子どもの朝も明るくなる
朝のバトルを減らすために大切なのは、
「頑張らせる」よりも「寄り添う」こと。
そして、ママが自分を責めずに、自分のペースで支援を続けること。
ママが少しでも穏やかに過ごせるようになると、子どもも安心して成長していきます。
最後にお伝えしたいのは、こんな言葉です。
「朝はうまくいかない日があってもいい。親子で笑顔になれる瞬間を、少しずつ増やしていこう。」
焦らず、比べず、親子のペースで。
それが、“眠気と上手に付き合う”いちばんの近道です。
まとめ~眠気に悩むADHDの子どもに必要なのは「理解」と「仕組み」
ADHDの子どもの「眠気」や「朝の弱さ」に悩むママは、本当に多いですよね。
毎朝の声かけ、学校への送り出し、そして「また起きられなかった…」という自己嫌悪。
きっと何度も繰り返してきたと思います。
でも、ここで大事なのは、子どもが“わざと”そうしているわけではないということ。
そして、ママのせいでもないということです。
ADHDの過眠は脳の特性によるもので“怠け”ではない
ADHDの子どもが過眠(寝すぎてしまう・朝起きられない)傾向を示すのは、脳の働き方に理由があるからです。
脳の「覚醒システム(起きるスイッチ)」が少しゆっくり反応するため、
朝になってもまだ眠気ホルモンが残っていたり、体が思うように動かなかったりします。
つまり、「やる気がない」「怠けている」ではなく、脳のリズムが整いにくいだけなんです。
このことを理解してあげるだけで、ママの関わり方もぐっと変わります。
たとえば、
- 「起きられないのは仕方ない。じゃあどうしたら少し楽に起きられるかな?」
- 「起きられなかったけど、昨日よりイライラしなかったね」
といった“できない”ではなく“できる方法を一緒に考える”視点が、子どもの安心と自信につながります。
家庭でできる工夫で、眠気の波を少しずつ整えていける
ADHDの眠気対策は、特別な薬や療法だけではなく、家庭のちょっとした工夫でも大きく変わります。
たとえば、
- 朝の光を取り入れて「体内時計」を整える
- 寝る前のスマホ・テレビを控えて、脳をクールダウンさせる
- 食事でセロトニン(覚醒ホルモン)を増やす工夫をする
- 「寝室の明るさ」「音」「布団の感触」など、感覚過敏に合った環境を作る
こうした小さな積み重ねが、“眠気の波を穏やかにしていく第一歩”になります。
最初から完璧に整えようとしなくても大丈夫。
「昨日より少しスムーズに起きられた」
「今日は笑顔で朝ごはんを食べられた」
そんな一歩一歩が、確実にリズムを作っていきます。
「朝が苦手な子ども」も、自分らしいリズムで成長できる
ADHDの子どもにとって、“朝が苦手”というのは個性のひとつ。
無理に「みんなと同じようにしなきゃ」と思う必要はありません。
大切なのは、“自分に合ったペース”で整えていくこと。
その子なりのリズムが見えてくると、だんだんと眠気との付き合い方もうまくなっていきます。
そして何より、ママが「この子はこの子のペースで頑張ってる」と認めてあげることで、
子どもは安心して挑戦できるようになります。
朝の時間がうまくいかなくても、焦らなくていい。
「今日は起きられなかったね。でもまた明日、やってみよう。」
その一言で、子どもは“次も頑張ってみよう”と思えるんです。
最後に──ママへのメッセージ
子どもの眠気に向き合うことは、簡単なことではありません。
毎日が試行錯誤の連続で、時には「もう限界…」と思う日もあるでしょう。
でも、ママがここまで頑張っていること自体が、すでに立派な支援です。
「理解しよう」と思ってこの記事を読んでいる時点で、もう一歩前に進めています。
眠気を責めるのではなく、理解して支える。
その姿勢こそが、子どもにとって一番の安心です。
親子のリズムは一朝一夕で整うものではありません。
けれど、理解と仕組みを重ねていけば、きっと少しずつ笑顔の朝が増えていきます。
どうか焦らず、比べず、
ママも「自分を責めない朝」を過ごしてくださいね。
以上【ADHD×過眠】眠気が止まらないADHDの子に試したい家庭でできる5つの支援方法とは でした

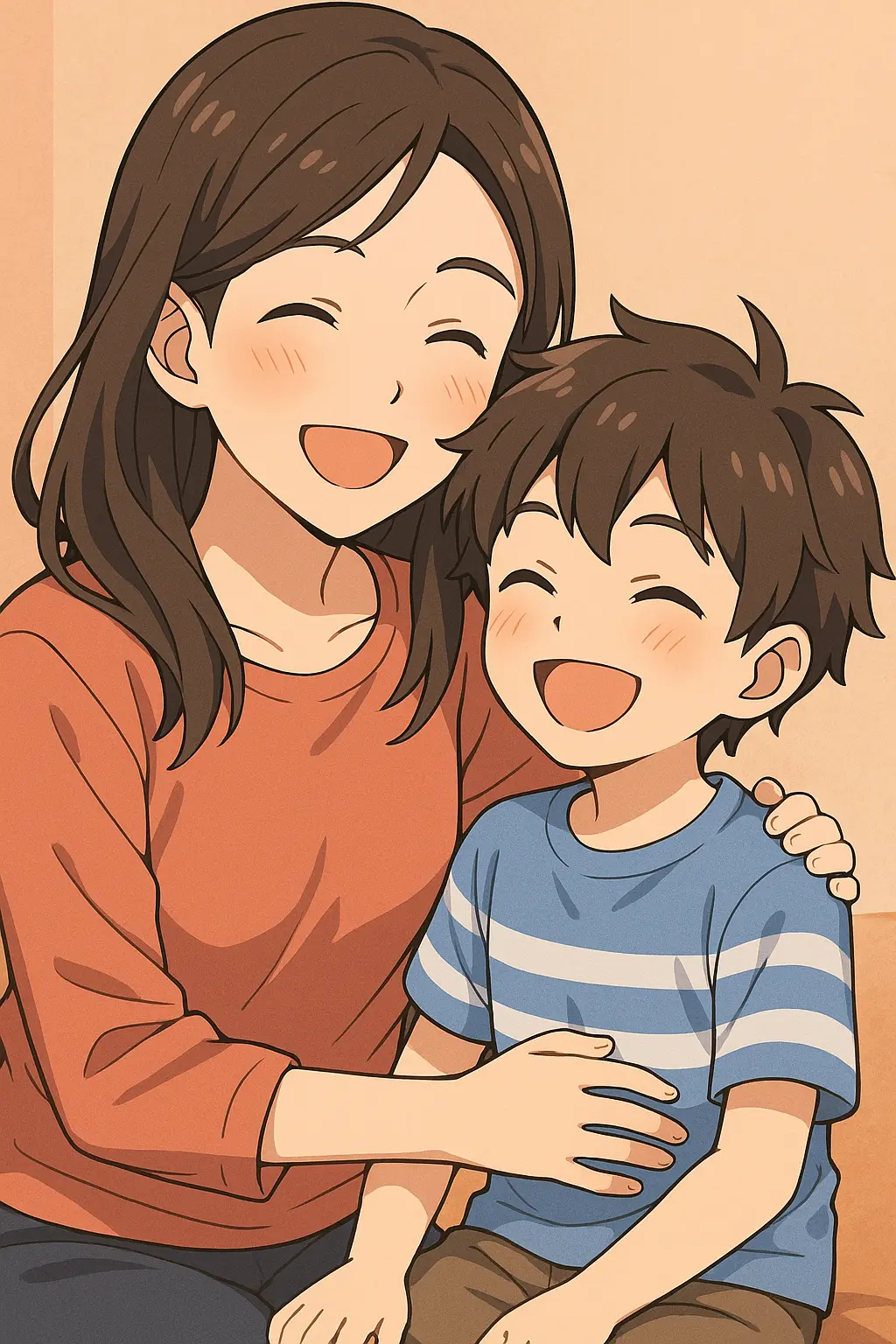









コメント