ADHDとは?1歳半では診断できるの?違いをわかりやすく解説
「ADHD」という言葉を聞くと、「うちの子もそうなのかな…?」と不安になるママも多いと思います。
でもまず知っておきたいのは、ADHDは“性格”ではなく“脳の特性”ということ。
少し専門的に言うと、脳の「注意をコントロールする働き」や「行動を抑える力」がちょっと違うタイプの発達の個性なんです。
ここでは、まずADHDの基本的な特徴をやさしく紹介したあと、
「1歳半で診断できるの?」というよくある疑問、そしてイヤイヤ期や自閉スペクトラム(ASD)との違いについても見ていきましょう。
【基礎知識】ADHD(注意欠如・多動症)とは?特徴をやさしく解説
ADHDは、日本語では「注意欠如・多動症」と呼ばれる発達特性です。
おもに次の3つの特徴(タイプ)が見られることが多いです。
① 不注意タイプ(集中が続きにくいタイプ)
・一つの遊びに集中できず、すぐに次のことに気が移る
・人の話を聞いているようで、すぐ別のものに目がいく
・片づけや整理が苦手
これは「やる気がない」のではなく、脳の中で“注意を切り替えるスイッチ”が少し違う動きをしているためです。
② 多動タイプ(体を動かさずにいられないタイプ)
・じっとしているのが苦手で、いつも動き回っている
・座って食べる、座って遊ぶなどの「静かな時間」が続かない
・つい走り出したり、机の上に登ったりする
こうした行動は、脳が「動きたい!」と感じやすい仕組みを持っているために起こります。
③ 衝動性タイプ(思ったらすぐ行動してしまうタイプ)
・順番を待つのが苦手
・思ったことをすぐ口に出してしまう
・「ダメ」と言われてもつい手が出る
衝動的な行動は、感情をコントロールする前頭葉の発達の進み方に個性があるためです。
多くのADHDの子は、この3つの特徴が混ざって見られます。
たとえば、「集中できない+動きが多い」など。
そして重要なのは、これらの特徴は“育て方のせいではない”ということ。
ADHDは「脳の働き方のちがい」によるもので、叱っても改善するものではありません。
むしろ、特性に合った関わり方をすることで、得意を伸ばしたり行動が安定したりすることが多いんです。
【重要】1歳半でADHDの診断はできる?早期発見の考え方
「うちの子、1歳半検診で“落ち着きがない”って言われた…」「これってADHDなの?」
そんな声をよく聞きます。
実は、1歳半の時点ではADHDの“診断”はほとんどの場合できません。
なぜなら、1〜3歳ごろの子どもは誰でも動きが多く、集中時間も短い時期だからです。
いわゆる“イヤイヤ期の始まり”と重なり、行動の幅もとても大きいんですね。
一般的にADHDの診断がつくのは、小学校入学前〜学童期(5〜6歳以降)です。
ただし、1歳半でも「気づき」はとても大切です。
たとえば、
- 落ち着きが極端になくて座っていられない
- 名前を呼んでも反応しにくい
- こだわりや感覚の強さが気になる
こうした場合、診断ではなくても、発達支援センターや保健センターでの早期相談が役立つことがあります。
早く気づくことで、
- 家庭での環境づくり(安全対策・遊び方)
- 保育園などとの連携
- 必要なときの療育や支援へのつながり
といった「支援の準備」ができるようになります。
つまり、1歳半の段階では「診断」ではなく、“発達の個性を理解して見守る段階”と考えると良いでしょう。
ADHDと“似ているけど違う”行動の見分け方
1歳半ごろの行動の中には、ADHDとよく似ているけれど違う特徴もあります。
焦って「ADHDかも…」と決めつける前に、他の発達の特性や成長の段階も知っておきましょう。
自閉スペクトラム症(ASD)との違い
ADHDは「注意や行動のコントロール」が苦手なタイプ。
一方、ASDは「コミュニケーションや感覚の違い」が中心のタイプです。
たとえば…
- 【ADHD】…呼びかけには反応するけれど、すぐ他のことに気がいく
- 【ASD】…呼びかけそのものに反応しづらい、視線が合いにくい
また、ASDでは特定の遊びを何度も繰り返す・こだわりが強い傾向がありますが、
ADHDでは「興味が移りやすい・すぐ次に行く」傾向が見られます。
イヤイヤ期との違い
1歳半〜2歳はちょうど自己主張が育つ時期。
「イヤ!」「自分で!」という行動は自然な発達段階です。
しかし、ADHD傾向がある子は、
- 注意を向けることが難しく、気持ちの切り替えが極端に苦手
- 怒りや興奮が爆発的で、落ち着くまで時間がかかる
という違いが見られることがあります。
“発達の個性”という視点で見ることが大切
1歳半の時期は、誰にでも発達の“ばらつき”があるのが自然です。
「できる・できない」ではなく、
“どんな場面で落ち着いているか”“何が苦手なのか”を丁寧に観察することが大事。
その違いを理解できると、
「うちの子、ちょっと違うかも」ではなく、
「この子はこういう伸び方をしているんだ」と前向きに関われるようになります。
ADHDが気になる1歳半の子に見られる「5つのサイン」
1歳半ごろになると、子どもの行動がますます活発になってきますよね。
ただ、「うちの子、ちょっと落ち着きがないかも」「呼んでも聞こえてない気がする…」と気になる瞬間も増えてくる時期。
もちろん、1歳半はまだ“発達の個人差”がとても大きい時期です。
だからこそ、「ADHDなのかも…」とすぐに決めつける必要はありません。
でも、もし少し気になる行動が続いているなら、“早めに気づく”ことが安心につながります。
ここでは、ADHDが気になる1歳半の子に見られやすい5つのサインを、家庭での観察ポイントとあわせて紹介します。
サイン①:常に動き回る・じっとしていられない【多動傾向】
「とにかく止まらない!」「一日中動いてる気がする」
そんなお子さん、いますよね。
1歳半の子はもともとエネルギーいっぱいですが、ADHD傾向のある子はその“動き方”が少し違うことがあります。
たとえば、
- 絵本を1ページも見ずにすぐ立ち上がる
- 何かを渡す前にもう次のおもちゃに行ってしまう
- 食事中でも席にいられず動き回る
こうした行動が「毎日・長期間続く」ときは、多動傾向が強いサインかもしれません。
ただし、「落ち着きがない=悪いこと」ではありません。
多動は、脳が新しい刺激を求めやすい特性によるもの。
見方を変えれば、「探究心が旺盛」「感覚的に世界を感じ取っている」とも言えます。
観察ポイント
家庭では、「どんな時に落ち着けているか」を見るのが大切です。
好きなおもちゃや安心できる人といる時は集中できるのか?
特定の場所や時間帯に落ち着く傾向があるのか?
その“違い”をメモしておくと、今後の支援や相談にも役立ちます。
サイン②:呼んでも反応が薄い・集中が続かない【不注意傾向】
「名前を呼んでも全然こっちを見てくれない…」
そんな場面が多いと、心配になりますよね。
でも、まず知っておきたいのは、“呼んでも反応しない=聞こえていない”とは限らないということ。
ADHD傾向のある子は、耳で聞くよりも“目の前の刺激”に意識が向きやすいため、呼びかけよりおもちゃや音に集中してしまうことがあります。
また、集中が続かないのも特徴のひとつ。
1歳半での集中時間は一般的に2〜3分程度ですが、ADHD傾向がある子は1分も続かないことも。
これは意欲がないわけではなく、脳の「注意を保つ回路」がまだ育っていないだけなんです。
観察ポイント
・「静かな環境だと反応するか?」
・「呼びかけを何回すると反応するか?」
・「視覚的な合図(手を振る・顔を近づける)では反応があるか?」
これらを比べると、注意の入り方に個性があるかどうかが見えてきます。
聴覚過敏や感覚統合の違いが関係しているケースもあるため、「ただ無視している」とは考えないようにしましょう。
サイン③:かんしゃく・物を投げるなど衝動的な行動が多い
「怒るとすぐ泣く」「気に入らないと物を投げる」——そんな行動も、この時期によく見られます。
ただし、ADHD傾向のある子は“感情のブレーキ”がかかりにくいため、他の子よりも爆発的に反応しやすいことがあります。
たとえば…
- 少し注意しただけで大泣きして止まらない
- 遊びを中断されるとパニックのように泣く
- おもちゃを取られるとすぐ叩いてしまう
これは、脳の前頭葉(感情をコントロールする部分)の発達がまだ途中だから。
つまり「悪い子」ではなく、「まだ気持ちを整理する力が育っていない」だけなんです。
観察ポイント
かんしゃくの後に、「気持ちの切り替えがどのくらいでできるか」を見てみましょう。
10分以上続く場合や、何をしても落ち着けない場合は、感情のコントロールが特に苦手なタイプかもしれません。
また、疲れている時や音・光などの刺激が強い時に爆発しやすい傾向もあります。
サイン④:寝つきが悪い・生活リズムが乱れやすい
「全然寝ない!」「寝てもすぐ起きる…」という悩みもよく聞かれます。
実はこれも、ADHD傾向のある子に多い特徴のひとつです。
理由は、脳が常に“オン状態”になりやすいから。
ADHDの子どもは、日中の刺激が脳に残りやすく、寝る直前まで活発に動いてしまいます。
また、メラトニン(眠りを促すホルモン)の分泌リズムがずれやすいとも言われています。
夜だけでなく、昼寝も苦手な子が多く、「眠いのに遊びたい!」というアンバランスさが見られることも。
家庭でできる工夫
- 就寝前のテレビ・スマホを控える
- 部屋を少し暗くして静かに過ごす“寝る準備タイム”を作る
- 同じ時間に寝る・起きるリズムをキープする
睡眠リズムは、情緒の安定や集中力にも深く関係しています。
「眠れない」は放っておかず、生活全体を整えるサインとして見てあげましょう。
サイン⑤:音や光に敏感・こだわり行動が強い
「掃除機の音で泣く」「服のタグを嫌がる」「特定のおもちゃしか触らない」——
そんな“感覚の強さ”も、ADHD傾向のある子に見られることがあります。
実はADHDの子どもは、「感覚統合」と呼ばれる脳の働き方に独特の特徴があることが多いです。
つまり、音・光・触感などの刺激を“普通より強く”感じてしまうんです。
その結果、
- 急な音や明るい光を怖がる
- 洋服の素材やタグを嫌がる
- “同じ遊び”や“決まった手順”を繰り返したがる
といった行動が見られます。
観察ポイント
感覚の過敏さは、「イヤイヤ」や「わがまま」と誤解されやすい部分です。
でも、本人にとっては“我慢できないほど不快”なことも。
たとえば、「音が大きくて痛い」「服がチクチクして気が散る」など、大人が想像するよりも強い感覚体験をしています。
そんなときは、「無理に慣れさせる」のではなく、
- 静かな環境で遊ぶ
- 素材を選んだ服を着せる
- 安心できるお気に入りアイテムを用意する
といった“安心できる選択肢”を増やすことが大切です。
「ADHDかも?」と思ったら!1歳半での見極め方と観察のコツ
「うちの子、落ち着きがない気がする」「名前を呼んでも反応しない」——
そんな小さな違いに気づくママの直感は、とても大切です。
でも一方で、「これってただの成長のムラ?」「ADHDなの?」と悩んでしまうことも多いですよね。
実は1歳半の時期は、“発達の個性”と“発達の特性(傾向)”が混ざり合う時期なんです。
だからこそ、「見極めよう」と思い詰めるよりも、“観察して気づく力”を育てることが大切。
ここでは、1歳半で「ADHDかも?」と感じたときに押さえておきたい、
3つの見極めポイントと観察のコツをわかりやすく紹介します。
一時的な発達の“個性”と“継続する傾向”を見分ける
まず最初に大切なのは、「一時的な発達の個性」と「継続して見られる傾向」を分けて考えることです。
たとえば、1歳半ごろは
- 好きな遊びばかりする
- 集中が続かない
- すぐ動き回る
といった行動は、どの子にもよく見られること。
これは「その子の発達ペース」や「興味の方向性」によるもので、一時的な個性の範囲です。
一方で、
- 数ヶ月たっても同じ行動が強く続いている
- 環境を変えても行動のパターンが変わらない
- 生活に支障が出るほど落ち着かない or 感情の起伏が激しい
こうした場合は、発達特性(ADHD傾向)の可能性がある“継続する傾向”として見ていくことが大切です。
ポイントは、「その時だけの様子」ではなく「時間の流れで見ていく」こと。
昨日できなかったことが今日できた、逆に以前はできたのに最近できなくなった——
そういった変化の積み重ねを見ていくことで、“成長のムラ”と“特性のサイン”を区別できるようになります。
つまり、1歳半で大事なのは「診断」よりも、“成長のリズムを見守る目”を持つことなんです。
行動記録をつけると見えてくる“本当の傾向”
ママが日々感じる「なんか違う…」という違和感。
それを言葉や記録に残すことで、見えない“パターン”が見えてくることがあります。
たとえば、以下のような簡単なメモからでもOKです。
📘【観察ノートの例】
- 朝:呼びかけに反応せず、走り回る
- 午後:好きな音楽をかけると落ち着いて座る
- 夜:寝つきに時間がかかる、寝る前にかんしゃく
こうして時間帯・状況・気分などを一緒に記録しておくと、
「眠いときにかんしゃくが出やすい」「好きな音楽の時は落ち着ける」など、
“行動の原因”や“安心のヒント”が自然と見えてきます。
特にADHD傾向のある子は、環境の影響を強く受けるため、
“いつ・どこで・何がきっかけで起きているか”を見つけることが支援の第一歩になります。
そして、この記録は「相談するとき」にもとても役立ちます。
発達相談や小児神経科などで、「具体的な日々の様子」を伝えることで、
より正確なアドバイスやサポートが受けやすくなるんです。
“記録する=見守る”というやさしいサポートの形として、
ママ自身が安心できるツールにもなりますよ。
他の子と比べないでOK!“発達の幅”を知ることが安心につながる
ついSNSや公園などで「同じ月齢なのに…」と他の子と比べてしまう。
それ、ママなら誰でも一度は経験ありますよね。
でも、ここで大事なのは、発達には“幅”があるということ。
たとえば、1歳半で話す単語が10個の子もいれば、まだ1語も出ていない子もいます。
どちらも実は正常な発達の範囲なんです。
ADHD傾向のある子は、特にこの“発達の幅”が大きく見えることがあります。
- 運動は早いけど、言葉がゆっくり
- 好奇心は強いけど、集中が続かない
- できる日とできない日の差が激しい
これは“発達のアンバランス”であり、「遅れている」ではなく「順番が違う」だけのこと。
比べるより大事なのは、「昨日よりできたこと」や「落ち着けた瞬間」に目を向けること。
他の子と比べると焦りが増えますが、自分の子の成長を“縦に”見ていくと安心が増えます。
「前よりスプーンを持てた」「今日は1回だけ走り出した」
そんな小さな変化を見つけて褒めることで、ママの心も落ち着き、子どもの自己肯定感も育ちます。
【実践版】家庭でできるADHD傾向の子への関わり方5選
1歳半でADHD傾向がある子との毎日は、まるで“止まらない嵐”のように感じることもありますよね。
でも、ママのちょっとした工夫で、「叱らなくても落ち着く時間」や「笑顔が増える瞬間」をつくることができます。
ここでは、今日からおうちでできる5つの実践的な関わり方を紹介します。
どれも特別な準備はいりません。日常の中で「できること」から、少しずつ始めていきましょう。
対応①:1日の流れを“見える化”して安心感を育てる
ADHD傾向のある子は、「次に何が起こるか」わからない状況がとても苦手です。
予想できないことが続くと、不安や混乱から行動が荒れやすくなります。
そこで効果的なのが、1日の流れを“見える化”すること。
たとえば、
- 朝の支度(顔を洗う・ごはん・お着替え)を絵カードで並べる
- 「今」「次」「あとで」を絵や写真で表示する
- 時計やタイマーを使って、時間の流れを感覚で見せる
こうすることで、子どもは「次に何をすればいいか」が分かり、安心して行動できるようになります。
ポイント
「やること」を一度に全部見せるのではなく、“今やること”と“次にやること”だけを提示するのがコツ。
情報が多すぎると、かえって混乱してしまいます。
「見通しを立てられる=安心できる」ことは、ADHD傾向の子にとって最高の支援なんです。
対応②:動いてもOK!安全に遊べる“動きの発散環境”を整える
ADHD傾向のある子は、とにかく「体を動かしたい欲求」が強いです。
じっとしていられないというより、「動かすことで安心している」ことも多いんです。
だから、「動かないようにさせる」よりも、“動ける環境”を整えることがポイント。
たとえば…
- クッションやマットを敷いてジャンプスペースを作る
- 廊下でバランスを取る“平均台ごっこ”をする
- トンネルや布の中をくぐる“感覚統合あそび”を取り入れる
これらは、叱らずに済む動きの発散としてとても有効です。
動くことで脳内の刺激が整い、結果的に落ち着く時間が増えることも多いです。
豆知識
ADHDの子は、体を動かすことで“前庭感覚”や“固有感覚”が安定するといわれています。
つまり、動くことは「興奮を発散する」だけでなく、「心を整える」役割もあるんです。
「止めるより、動かせる工夫をする」——それが、家庭でできるやさしい支援です。
対応③:集中しやすい“短時間あそび”を取り入れる
ADHD傾向のある子は、集中できないのではなく、集中の“スイッチ”が短いんです。
だから、長時間じっと遊ぶのはハードルが高め。
おすすめは、“5分で終わる遊び”を何個か用意しておくこと。
たとえば、
- 積み木を10個積む → 終わったら次の遊びへ
- ボールを3回転がす → 「できたね!」と切り替え
- 音の鳴るおもちゃでリズムあそび → 1曲終わったらおしまい
こうして「短くて達成できるあそび」を重ねることで、
子どもは「できた!」という満足感をたくさん得られます。
環境づくりのコツ
遊びの時間を区切るときは、「タイマー」や「音の合図」が効果的。
視覚や聴覚で時間の区切りがわかると、切り替えがスムーズになります。
短く区切ることで、「集中できた!」という成功体験を積み重ね、
“集中する力”そのものを育てていくことができるんです。
対応④:“叱るより褒める”で行動を導く声かけのコツ
ADHD傾向のある子は、行動が予想外に多く、どうしても叱る場面が増えがちです。
でも、実は叱るほどに行動がエスカレートしやすい傾向があります。
なぜなら、ADHDの子は“注意されること”も刺激として感じやすいから。
「ダメ!」と言われると、一瞬で感情が高ぶってしまうんです。
そこで大切なのが、“叱る前に褒める”意識。
たとえば、
- 「走っちゃダメ!」より「歩けたね、すごい!」
- 「やめて!」より「上手に片づけられたね!」
といった肯定的な言葉の積み重ねが、行動を穏やかに導いてくれます。
ポイント
褒めるときは、「具体的に・すぐに」が鉄則。
「おもちゃを片づけてくれてありがとう」など、行動の内容を具体的に伝えることで、
「これをすれば褒められるんだ」と子どもが理解しやすくなります。
“叱るより、うまくいった瞬間をキャッチする”——それだけで、親子の空気がぐっと優しくなります。
対応⑤:音とリズムで整える!リトミック&感覚あそび
ADHD傾向のある子は、音やリズムの刺激にとても敏感で反応が良いことがあります。
この“音への反応の良さ”を生かせるのが、リトミックや感覚あそびです。
リトミックとは、音楽に合わせて体を動かしたり、リズムを感じながら表現するあそびのこと。
たとえば、
- 音楽に合わせて手を叩く・足でトントンする
- 太鼓やマラカスでリズムをまねっこする
- 歌いながらバスタオルで「いないいないばあ」あそび
こうした活動は、感情のコントロール・体のバランス・集中力を自然に育ててくれます。
ポイント
リトミックは、上手にやる必要はありません。
「ママと一緒に楽しい」という体験が何より大事。
音と動きがつながることで、脳の神経ネットワークが活性化し、発達の土台が整うと言われています。
また、音楽に合わせて「動く→止まる」を繰り返すあそび(例:「ストップゲーム」)もおすすめ。
ADHD傾向の子が苦手な“切り替え”の練習になるからです。
ADHD傾向のある子に大切な「生活リズムと環境づくり」
ADHD傾向のある子どもにとって、“安心して過ごせる毎日のリズム”は何よりの支えになります。
どんなに発達に凸凹があっても、生活の土台が整っているだけで、感情の安定や集中力の持続にもつながります。
逆に、寝不足や食事の乱れ、刺激の多い環境が重なると、衝動性や多動が強く出やすくなることもあります。
ここでは、家庭で意識したい「生活リズムと環境づくり」のコツを3つの視点から見ていきましょう。
睡眠・食事・運動で整える“脳のバランス”
ADHD傾向のある子は、脳の神経伝達物質(ドーパミン・ノルアドレナリンなど)の働きが少し不安定だといわれています。
この脳のバランスを支えるのが「生活リズム」です。
睡眠:1日の“リセットスイッチ”
1歳半前後の子どもは、まだ眠りのリズムが不安定です。
特にADHD傾向がある子は、寝つきに時間がかかる・夜中に起きる・朝の目覚めが悪いなどの特徴が見られます。
そんなときは、
- 寝る前の30分は部屋を暗くして静かに過ごす
- 寝室の照明は暖かい色(オレンジ系)にする
- 同じ時間に「おやすみルーティン」を決める(例:歯みがき→絵本→おやすみ)
といった、“眠りへの導線”を整えることがポイントです。
特にブルーライト(テレビやスマホ)を寝る直前に見せないことは、メラトニン(眠気を促すホルモン)を守るためにも大切です。
食事:栄養で“心の安定”をサポート
ADHD傾向の子は、感覚過敏などの影響で偏食が見られることがあります。
しかし、朝ごはんを抜くと集中力が大きく低下するため、少しでもエネルギー源をとることが大切です。
朝におすすめなのは、
- ごはん+たまご+味噌汁など、シンプルな和食
- バナナやヨーグルトなど、手軽に食べられる組み合わせ
また、魚に含まれるDHA・EPAや、ナッツ・大豆に多い鉄や亜鉛は、脳の働きを助ける栄養素です。
毎日でなくても、「週に数回取り入れる」だけでも効果があります。
運動:体を動かして“神経を整える”
体を動かすことは、脳の発達を促す最強の習慣です。
ADHD傾向の子どもにとって、運動は「ストレス発散」だけでなく、「神経の調整」そのものになります。
おすすめは、
- 公園での追いかけっこやすべり台など“全身を使う遊び”
- 家の中なら風船バレーやトランポリン遊び
- 音楽に合わせて体を動かす“リトミックごっこ”
運動を通して、前庭感覚(バランス感覚)や固有感覚(体の位置感覚)が鍛えられ、落ち着きや集中力も高まります。
ポイント
“運動=スポーツ”ではなく、楽しく体を動かすことすべてが運動です。
無理に「運動させる」より、「一緒に遊んで楽しむ」ことを大切にしましょう。
刺激を減らす“安心できる空間設計”
ADHD傾向のある子は、周囲の刺激をそのまま全部受け取りやすい特性があります。
たとえば、
- テレビの音
- カーテンの柄
- 周囲の人の動き
…といった些細な刺激でも、集中が途切れたり、不安になったりすることがあります。
そこで意識したいのが、「刺激を減らす空間づくり」です。
家の中でできる環境調整のポイント
- テレビは必要なときだけつける(BGM代わりにしない)
- 壁やカーテンの色を落ち着いた色に(白・ベージュ・淡いグリーンなど)
- おもちゃは“見せる収納”より“しまう収納”にして視覚刺激を減らす
- 照明は暖色系に変えることでリラックス効果を高める
これだけでも、子どもが自然に落ち着く時間が増えることがあります。
小さな工夫でもOK
「完璧な環境を作らなきゃ」と気負う必要はありません。
大切なのは、“子どもが落ち着ける空間”を一緒に見つけていくこと。
たとえば、
「このクッションの上にいると落ち着く」
「この角で絵本を読むと静かにできる」
そんな“安心スポット”をおうちの中につくるだけでも、立派な支援になります。
家族全員で取り組む“叱らない育児”の共有ルール
ADHD傾向のある子どもにとって、家族の対応が一貫していることはとても大切です。
なぜなら、「ママは優しいけど、パパはすぐ怒る」「祖父母の対応が違う」といった環境では、子どもが混乱してしまうからです。
家族の“共有ルール”を決めよう
たとえば、家庭内で次のような共通ルールを作っておくと、対応がブレにくくなります。
- 「できたことを褒める」を最優先にする
- 「ダメ!」より「こうしようね」と伝える
- 叱る前に深呼吸をして、感情的に反応しない
- ルールは少なく・わかりやすく・守れる範囲で設定する
このように“叱らない方針を家族で共有”することで、子どもは安心して行動できます。
家族の中での支援連携
ママが毎日頑張っていても、パパや祖父母が「甘やかしすぎじゃない?」と言うこともあるかもしれません。
でも、叱らない育児は「甘やかす」ではなく「導く」ための方法。
行動の裏にある“子どもの困りごと”を理解するのが第一歩なんです。
みんなで子育てを支えるチームに
家庭での育児は、1人で抱えこむと息が詰まってしまいます。
だからこそ、家族みんなが同じ方向を向いて、協力し合うことが何よりの支援。
「ママだけ頑張る育児」から「みんなで見守る育児」へ。
その意識が、子どもの“安心”と“成長”を大きく支えていきます。
よくある質問Q&A|1歳半のADHDに関する疑問まとめ
ADHDに関してインターネットやSNSを見ていると、
「これってうちの子も当てはまるかも?」
「1歳半でもわかるの?」「将来どうなるんだろう…」
と、不安になるママも多いですよね。
ここでは、よく寄せられる疑問5つを、わかりやすくまとめました。
どれも医療・発達支援の現場で実際によく聞かれる内容です。
Q1:1歳半でADHDと診断されることはある?
結論から言うと、1歳半でADHDと正式に診断されることはほとんどありません。
ADHD(注意欠如・多動症)は、「不注意」「多動」「衝動性」という3つの特徴が、
複数の場面(家庭・保育園など)で継続して見られることが診断の条件です。
しかし1歳半の段階では、まだ脳の発達が大きく進んでいる途中。
行動のムラや集中の短さは、発達の個性の範囲であることも多いんです。
ただし、「気になる行動が長く続く」「生活に支障が出ている」と感じたら、
発達相談センターや小児発達外来で相談するのは早すぎではありません。
“診断”ではなくても、今できる支援のヒントをもらえることがあります。
ポイント
「診断」はまだでも、「支援」は早くてOK。
“気づき”を放っておかず、早めに相談することが、後の安心につながります。
Q2:ADHDは成長とともに落ち着く?
よく「ADHDは治るの?」と聞かれますが、“治る”というより“育つ”と考えるのが正確です。
ADHDは一生の特性ではありますが、年齢とともに脳の成熟が進み、行動をコントロールする力が育っていくため、
多動や衝動の強さは自然と落ち着いてくるケースが多いです。
つまり、早期に「自分に合った過ごし方」や「環境調整」を身につけることで、ぐんと生きやすくなるのです。
たとえば…
- 動きたいエネルギーを外遊びで発散する
- できたことを褒めて「自信」を積み重ねる
- 失敗しても責めず、「こうすればいいね」と切り替える
こうした関わりが、脳の発達とともに「自分で気持ちを整える力」を育てます。
成長とともに「困りごとが減る」子は多く、
家庭での関わりが、その“伸びしろ”を引き出す大切なカギになります。
Q3:保育園や家族にはどう伝えればいい?
「気になる行動があるけど、保育園の先生にどう話したらいいの?」
「祖父母に“うちの子はちょっと違うかも”って伝えるのが難しい…」
そんな悩みを抱えるママも多いですよね。
まず大切なのは、“診断名”よりも“行動の特徴”を共有すること。
たとえば、
「集団の中だと注意がそれやすいようです」
「音が大きい場所で不安になることがあります」
「興味を持ったことには集中できます」
といった形で、“特性”を具体的に伝えるのがコツです。
ポイント
- 「ADHDかもしれない」と断定せずに話す
- 「家庭でこんな工夫をしている」とポジティブな共有をする
- 先生や家族の“協力者”になってもらう気持ちで伝える
保育園や家族が理解を深めることで、子どもが安心して過ごせる時間が増えるはずです。
何より、“チームで子どもを支える”という意識が大切です。
Q4:家庭でNGな対応は?
ADHD傾向のある子にとって一番つらいのは、「叱られ続けること」です。
ママに悪気がなくても、「また落ち着かないね」「どうしてできないの?」と繰り返されると、
「自分はダメなんだ」と自己否定の気持ちが強くなってしまいます。
そこで避けたいのは次の3つです。
1️⃣ 感情的に叱ること
→ 子どもは「怒られた理由」より「怖かった気持ち」だけが残ります。
代わりに「こうすると助かるよ」と行動の方向づけをしましょう。
2️⃣ できないことを責めること
→ ADHDの子は“やりたくない”のではなく、“できない”。
「どうしたらできるかな?」と一緒に考える姿勢が大切です。
3️⃣ 比べること
→ 「〇〇ちゃんはできてるのに」は禁句。
それよりも、「昨日より今日は1個できたね!」と成長を見つけて褒めるほうが、ぐっと前向きに育ちます。
大事なのは、“できなかったこと”ではなく“できた瞬間”に注目すること。
その積み重ねが、子どもの自己肯定感を育てていきます。
Q5:どんな時に専門家へ相談すべき?
「もう少し様子を見た方がいいのかな?」
「でも、気になる気持ちがずっと消えない…」
そんなときこそ、専門機関への相談のタイミングです。
目安としては、次のようなサインがある場合です。
- 注意を向けるのが難しく、事故やケガが多い
- 感情の切り替えが極端に難しい(泣き出すと止まらないなど)
- 睡眠や食事の乱れが強く、生活に影響が出ている
- 集団行動が極端に苦手で、他の子との関係が続かない
これらが3か月以上続く場合は、
自治体の発達支援センターや小児神経科・発達外来に相談してみましょう。
相談のポイント
「診断を受けに行く」というより、「今の発達の段階を知りに行く」という気持ちでOK。
また、普段の様子をメモして持っていくと、より的確なアドバイスを受けられます。
専門家とつながることは、“親の安心”にもつながります。
「相談してよかった」「もっと早く行けばよかった」と感じるママもたくさんいますよ。
まとめ|1歳半の“気づき”が子どもの未来を変える
1歳半という時期は、まだ“発達の途中”であり、個性の幅がとても大きい時期です。
だからこそ、「うちの子、他の子と違うかも?」という違和感や心配は、
ママにとって不安の種になるかもしれません。
でも実は、その“気づき”こそが、子どもの未来を変える大切な第一歩なんです。
「診断」よりも大事なのは、“気づいて寄り添うこと”
1歳半では、まだADHDと断定できる時期ではありません。
けれども、「なんとなく育てにくい」「少し違う気がする」というママの直感には、
ちゃんと意味があります。
その感覚を無視せず、「今できること」を探していくことが、
将来の支援にも、ママの安心にもつながります。
つまり、今大切なのは“診断”ではなく、“気づきと準備”。
「困ってから対応する」ではなく、「気づいた時から支える」ことができるのは、
一番近くにいるママだからこそ、できることなんです。
“育てにくさ”は“成長のチャンス”でもある
ADHD傾向のある子は、たしかに手がかかることも多いです。
でも、それは「難しさ」だけでなく「伸びしろのサイン」でもあります。
たとえば、
- じっとしていられない → 好奇心と行動力が人一倍強い
- 集中が続かない → 興味を持てば驚くほど夢中になれる
- 感情の起伏が大きい → 感受性が豊かで表現が上手
このように、特性の裏には必ず強みがあるんです。
ママが少し視点を変えるだけで、「困りごと」が「個性の芽」に見えてきます。
たとえば…
「落ち着きがない」→「体を動かすのが好き」
「話を聞かない」→「自分の世界を持っている」
「同じことばかり繰り返す」→「興味を深める力が強い」
子どもの行動を“問題”ではなく“特性”として見られるようになると、
日々の関わり方が自然と変わっていきます。
家庭での関わりが、子どもの未来を育てる
ADHD傾向のある子にとって、「家庭の安心感」こそが最大の支援です。
特別な教材や療育を始める前に、
- 決まった生活リズムを整える
- 安心できる空間をつくる
- 「できたね!」をたくさん伝える
そんな日々の積み重ねが、子どもの脳と心を育てていきます。
研究でも、家庭での肯定的な関わりが、脳の発達や行動の安定に良い影響を与えることが分かっています。
つまり、「おうちでの関わり方」が、子どもの成長を左右する“栄養”なんです。
さいごに~比べず、焦らず。ゆっくり育つ時間を一緒に歩こう
「うちの子、ADHDかもしれない」と感じたとき、
ママの頭の中にはたくさんの「?」と「どうしよう」が浮かぶと思います。
でも、その不安を抱えながらも“気づけた”こと自体がすでに支援の始まりです。
子どもにとって、ママの存在は“安心の基地”。
焦らず、比べず、ゆっくり歩いていけば大丈夫。
発達のスピードは子どもによって本当にさまざまです。
早く進む子もいれば、時間をかけてゆっくり育つ子もいます。
どちらも立派な「成長」です。
ママの小さな気づきが、
「この子らしさを大切にできる未来」への第一歩になります。
どうか、今日の“気づき”を大事にしてあげてください。
そして、自分自身にも「よく頑張ってるね」と言ってあげてくださいね。
以上【ADHD 1歳半で気づく子の特徴|5つのサインと家庭でできる対応法】でした

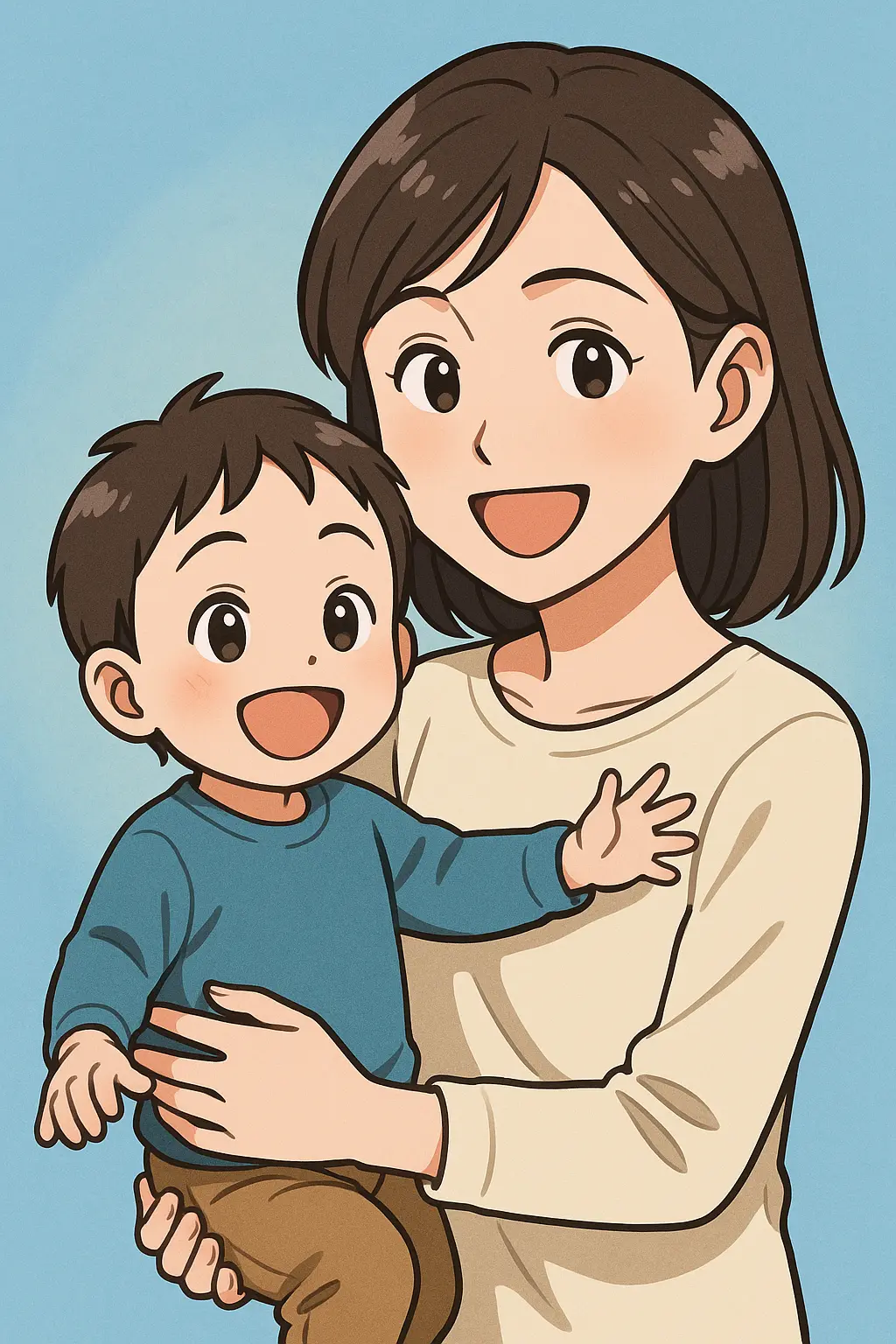









コメント