ADHDと鬱病の関係をわかりやすく解説|子どもの心に何が起きている?
ADHDの子どもは、外から見ていると「落ち着きがない」「集中できない」と言われがちです。
でも、心の中ではもっと複雑で繊細なことが起きています。
一見、元気そうに見えても、実はストレスやプレッシャーを強く感じているケースも少なくありません。
そんな中で、周囲の理解が得られずに傷ついたり、頑張っても空回りしたりすると、次第に心が疲れてしまいます。
それが続くと、鬱病(うつびょう)やうつ状態といった心の不調へとつながることもあるのです。
ここでは、ADHDの特性と、それがどのように「心の疲れ」につながるのかを、できるだけやさしく説明していきますね。
ADHDの特徴と「生きづらさ」
ADHDには、主に**「不注意」「衝動性」「多動」**という3つの特徴があります。
これらは単なる性格ではなく、脳の働き方の違いによるものなんです。
たとえば、不注意の強い子は、頭の中が常にいろいろな刺激でいっぱい。
目の前のことに集中したくても、別のことが気になって気が散ってしまいます。
衝動性のある子は、思ったことがすぐ口や行動に出てしまうタイプ。
「今やっちゃダメ」とわかっていても、体が先に動いてしまうんですね。
多動の子は、じっとしていると逆にストレスを感じやすく、動くことで落ち着こうとします。
つまり、ADHDの子どもたちは、「やりたい」「頑張りたい」と思っているのに、うまくコントロールできないという葛藤の中にいます。
それでも周囲からは「やる気がない」「ちゃんとしなさい」と言われてしまうことが多く、本人は「努力しても伝わらない」と感じやすいのです。
このような誤解が続くと、「自分はダメな子なんだ」と思い込むようになり、自己肯定感が下がっていくことがあります。
さらに、叱られる回数が多くなることで、**「どうせ怒られるからもうやりたくない」**と気力を失ってしまうことも。
これが、心の中で少しずつ“生きづらさ”として積もっていくのです。
鬱病とは?子どもにも起こる“見えない疲れ”
「鬱病」と聞くと、大人の病気のように感じるかもしれません。
でも実は、子どもにも鬱病や“うつ状態”は起こります。
たとえば、以前はよく笑っていたのに無表情になったり、好きだった遊びに興味を示さなくなったり。
親から見ると「反抗期なのかな?」と思うような変化でも、実は心のエネルギーが尽きかけているサインのこともあります。
最近では、学校生活や人間関係のストレスから、小学生でもうつ症状を訴える子が増えているという報告もあります。
とくにADHDの子は、次のような理由でうつ状態になりやすい傾向があります。
① 努力しても報われない体験が多い
ADHDの子は、頑張っているのに結果がうまく出ないことが多いです。
「ちゃんとやってるのにミスをする」「集中しようとしても気が散る」――。
本人なりに精一杯やっても、周りからは「なぜできないの?」と言われてしまいます。
このような経験が続くと、**「どうせ頑張っても意味がない」**という思い込みが生まれ、心が疲れてしまうのです。
② 失敗を繰り返すストレスがたまる
ADHDの子は忘れ物やうっかりミスが多く、それが日常的なストレスになります。
しかも、何度も注意されることで、「また怒られる」という不安が常につきまとうようになります。
このような慢性的な緊張感が、心のエネルギーをじわじわ削っていくのです。
③ 感情コントロールの難しさ
ADHDの子は、喜怒哀楽の波が激しい傾向があります。
たとえば、ちょっとしたことで泣いたり、怒ったり、逆にテンションが急に上がったり。
感情を調整するのが難しいため、自分でもどうしていいかわからなくなることがあります。
大人でも感情の浮き沈みが続くとしんどいですよね。
それが毎日続く子どもにとっては、心がいつも“疲れモード”のような状態なのです。
ADHDの子は、「弱いから落ち込む」のではなく、
頑張りすぎて疲れてしまう、そんな優しい子が多いです。
周りからの理解が少ないと、「なんでわかってくれないの?」という孤独も感じやすくなります。
それが積み重なることで、鬱病という形で心が悲鳴を上げることがあるのです。
ADHDの特性を「問題」として見るのではなく、**「どう支えるか」**に視点を変えることが大切です。
そして、少しでも「いつもと違う」と感じたら、心のサインを見逃さずに寄り添うことが、何よりの予防になります。
ママが「この子のペースでいいんだよ」と認めてあげること。
それが、子どもの心を守る一番の支えになるのです。
【早期発見】ADHDの子が鬱病になる前に見せる5つのサイン
ADHDの子どもは、気持ちのアップダウンが大きく、感情の波が激しいこともよくあります。
でも、その中に**「一時的な気分の波」ではなく「心の限界サイン」**が隠れていることもあるんです。
「いつもと違うな」「元気がないな」と感じたら、それは早めに気づくチャンスです。
ここでは、鬱病になる前に見られる**5つの変化(サイン)**を、わかりやすく紹介します。
サイン①:大好きだったことに興味を示さなくなる
「前はブロック遊びが大好きだったのに」「最近、絵も全然描かなくなった」――。
そんな変化が見られたら、それは心のSOSかもしれません。
ADHDの子どもは、本来興味や関心が強く、夢中になるタイプです。
だからこそ、「急に好きだったことに反応しなくなる」「何をしても楽しくなさそう」といった変化は要注意。
この状態は、専門的には**“興味・喜びの喪失(アネドニア)”**と呼ばれ、鬱病の初期サインとしてよく見られます。
親としては、「気分のムラかな」「飽きたのかも」と思いたくなりますが、
もし2週間以上その状態が続くようなら、心のエネルギーが減っているサインかもしれません。
このとき大事なのは、無理に「やろうよ!」と促すよりも、**「最近ちょっと疲れちゃったのかな?」「何か嫌なことあった?」**と声をかけてあげることです。
「無理しなくていいんだ」と思えるだけで、子どもの心は少しずつ回復していきます。
サイン②:眠れない・朝起きられない日が続く
「寝るのが遅い」「朝、何度起こしても起きない」――そんな状態が続くときも、心の不調を疑ってみてください。
ADHDの子どもはもともと睡眠リズムが乱れやすい傾向があります。
特に、「過集中」といって好きなことに夢中になりすぎると、夜になっても頭が興奮したまま眠れなくなることがあるんです。
この「過集中 → 疲弊 → 不眠」という流れを繰り返すと、次第に体も心もエネルギー切れになっていきます。
そうすると、朝起きられない・登園や登校を嫌がる・頭痛や腹痛を訴えるといった形で、心の疲れが体に出ることもあります。
もしこのような状態が1週間以上続く場合は、生活リズムを整えることが第一歩。
照明を落としたり、寝る1時間前はスマホやテレビを控えたりして、「寝る準備の時間」をつくるだけでも改善することがあります。
それでも改善しない場合は、無理に起こしたり叱ったりせずに、「体も心も休ませる」ことを優先してください。
サイン③:些細なことで泣く・怒る|感情の起伏が激しくなる
ADHDの子はもともと感情が豊かで、嬉しい・悲しい・悔しいを素直に表現する子が多いです。
でも、もし最近「涙もろくなった」「すぐ怒る」「小さなことで大泣きする」ようになったなら、それは心の疲れが限界に近いサインかもしれません。
たとえば、
- ほんの少し注意しただけで号泣する
- 急に怒り出して手がつけられない
- 自分でも理由がわからず涙が止まらない
こうした反応は、「気持ちの整理が追いつかない」状態です。
ここで見分けたいのが、ADHD特性による感情の波なのか、それとも鬱状態による情緒不安なのか。
ポイントは、「反応の強さと持続時間」です。
ADHD特性の感情の波は、一時的で、しばらくすると気持ちが切り替わります。
一方、鬱状態の場合は、怒りや悲しみが何日も続く・笑顔が減るといった変化が見られます。
そんなときは、「また泣いてるの?」ではなく、**「泣きたいときは泣いていいよ」**と受け止めることが大切。
感情を抑え込まず、安心して出せる環境をつくることで、心が少しずつ回復していきます。
サイン④:食欲の変化が極端になる
「最近ごはんを食べたがらない」「逆に食べすぎる」――。
こうした食欲の変化も、心の調子を表す重要なサインです。
鬱状態になると、脳の働きが変化し、食欲をコントロールするホルモン(セロトニンやドーパミン)が乱れます。
そのため、食べすぎたり、まったく食べられなくなったりすることがあります。
また、ADHDの子は感覚の偏り(食感・味・匂いの敏感さ)を持つことも多く、食事のストレスが重なりやすい傾向があります。
食べることが「苦痛」に感じるようになると、エネルギー不足→疲労→気分の落ち込みという悪循環に。
「しっかり食べなさい!」と叱るよりも、「今日はどれなら食べられそう?」と選ばせてあげるのがポイントです。
無理せず食べられる量から始めて、「食べられたね」「頑張ったね」と安心感を積み重ねることが、回復の一歩になります。
サイン⑤:「自分なんて…」と自己否定の言葉が増える
これは、最も注意すべきサインです。
「どうせ僕なんて」「私なんかいないほうがいい」といった言葉が出てきたら、すぐに耳を傾けてください。
それは「かまってほしい」ではなく、本気で苦しいサインであることが多いのです。
ADHDの子どもは、失敗経験が多く、叱られる回数も多いため、自己肯定感が低くなりがちです。
その結果、「どうせ自分はできない」「迷惑をかけてばかり」と感じ、心がどんどん閉じていくことがあります。
このときに大切なのは、否定せずに共感して受け止めること。
たとえば、
「そんなふうに思ってたんだね。つらかったね。」
「そう感じるくらい、頑張ってたんだね。」
こうした言葉をかけるだけで、子どもは「わかってもらえた」と感じ、心の負担が少し軽くなります。
また、自己否定の言葉が何度も出るようなら、迷わず医療機関や学校のカウンセラーに相談を。
早めの支援が、心を守る大きな助けになります。
子どもの「心のサイン」は、目には見えません。
でも、ママが毎日一番近くで見ているからこそ、小さな変化に気づけるんです。
「なんとなく気になる…」と思ったその瞬間が、早期発見のチャンス。
焦らず、責めず、寄り添いながら、少しずつ心のエネルギーを取り戻していきましょう。
【家庭でできる】ADHDと鬱病を見抜くチェックリスト
「なんだか最近、元気がない」「ちょっと前まで楽しそうだったのに…」
そんな小さな違和感を覚えたとき、ママがいち早く気づけると、子どもの心を守ることができます。
ADHDの子どもは、気分の波や行動の変化が大きいため、心の不調が見えづらいことがあります。
でも、普段の生活の中にもしっかりとサインは現れています。
ここでは、家庭で簡単にチェックできる行動・表情・会話の10項目を紹介します。
どれも“ちょっとした変化”なので、「当てはまるかも」と思ったら、ぜひ早めに気づくきっかけにしてくださいね。
早期発見に役立つ!行動・表情・会話のチェック10項目
まずは、以下のリストを見ながら、最近のお子さんの様子を思い出してみてください。
ひとつでも「当てはまるかも」と感じたら、それは“心が疲れているサイン”の可能性があります。
✅ 行動面のチェック
- 大好きだった遊びや趣味に興味を示さなくなった
- 朝、起きるのを嫌がる・支度に時間がかかるようになった
- 学校(園)に行きたくないと言うことが増えた
- 食欲が急に落ちた、または食べすぎるようになった
- 寝つきが悪い・夜中に目を覚ますことが増えた
✅ 表情・会話のチェック
- 笑顔が減り、ぼんやりしていることが多い
- 「疲れた」「めんどくさい」と口にすることが増えた
- 小さなことで泣いたり怒ったりするようになった
- 「自分なんてダメ」「どうせできない」と言うようになった
- 以前より友達や家族との会話を避けるようになった
この10項目は、どれも心のエネルギーが減っているサインです。
ADHDの子は、頑張りすぎて疲れてしまうことが多いので、
「やる気がない」「反抗してる」と決めつけず、**“心の充電が必要な状態”**と考えてください。
特に、複数の項目が2週間以上続いている場合は注意が必要です。
早めに家庭で休息を取ったり、必要であれば専門家に相談したりすることで、鬱病の悪化を防ぐことができます。
チェックで当てはまったときの最初の対応
チェックして「うちの子、ちょっと当てはまるかも…」と感じたとき、
まずやるべきことは、“叱る”でも“解決しようと急ぐ”でもなく、“休ませる”こと。
子どもの心は、体と同じで、疲れがたまると元気が出なくなります。
でも、周囲が「早く元気になって!」と焦ってしまうと、逆にプレッシャーになってしまうことも。
まずは、安心して休める環境を整えることが何より大切です。
ここでは、ママがすぐにできる「心が落ち着く環境づくり3ステップ」を紹介します。
🌿 ステップ①:安心できる空間をつくる
子どもが落ち着ける“安全基地”のような場所を用意してあげましょう。
お気に入りのぬいぐるみや毛布を置く、明るすぎない照明にするなど、
「ここにいるとホッとする」環境を整えることがポイントです。
とくにADHDの子は、刺激に敏感な子も多いので、
音・光・匂いなどを減らして“静かな空間”にするだけでも、気持ちが落ち着くことがあります。
🌿 ステップ②:無理に話させず、そばにいる
子どもが落ち込んでいるとき、つい「どうしたの?」「何があったの?」と聞きたくなりますよね。
でも、心が疲れているときは、言葉で説明することすらエネルギーが必要なんです。
そんなときは、**「話したくなったらいつでも聞くよ」**という一言で十分。
無理に聞き出すより、そっと寄り添って存在を感じさせることのほうが、ずっと安心します。
🌿 ステップ③:小さな“できた”を一緒に喜ぶ
心が疲れているとき、子どもは「何をしても自信が持てない」状態になっています。
そんなときは、「よく頑張ったね」「できたね」といった小さな成功体験を一緒に喜ぶことが大切です。
たとえば、
- 朝少し早く起きられた
- ごはんをひと口でも食べられた
- 自分から話しかけてくれた
こうしたことを大げさなくらいほめて、安心感を与えることで、
「自分は大丈夫」「また頑張れるかも」と思えるようになります。
チェックリストは、**「診断」ではなく「気づきのきっかけ」**です。
ママが気づいてあげることで、子どもは安心し、回復が早まります。
「気づく力」こそ、ママにしかできない最高の支援。
焦らず、比べず、少しずつ。
お子さんのペースで心の回復を見守ってあげましょう。
ADHDの子の鬱病を防ぐ!親ができる5つの支援方法
ADHDの子どもが心のエネルギーをすり減らしてしまう原因の多くは、
「頑張っても認められない」「叱られることが多い」「理解されない」という日常の積み重ねです。
でも逆に言えば、家庭での関わり方ひとつで、子どもの心は驚くほど元気を取り戻せるんです。
ここでは、ママが今日から実践できる5つの支援方法を紹介します。
難しいことはありません。ちょっとした言葉や態度の変化が、子どもの「生きる力」を育てていきます。
支援①:「できたね」を増やす|小さな成功体験で自己肯定感を育てる
ADHDの子どもは「失敗の経験」が多くなりがちです。
忘れ物をしたり、集中が続かなかったりして、**「また怒られた」「やっぱりできない」**と感じることが積み重なります。
だからこそ、ママが意識して増やしたいのが**「できたね」**という小さな成功体験。
たとえば――
- 「ちゃんと手を洗えたね!」
- 「自分から準備できたね!」
- 「泣かずに伝えられたね!」
ほんの少しのことでもOK。
「結果」ではなく「過程」や「気持ち」に注目してほめるのがポイントです。
「頑張ろうとした気持ち、ちゃんと見てたよ」
「前よりも少し長く集中できたね」
こうした言葉は、「自分はダメじゃないんだ」と感じる小さな光になります。
この“ほめの積み重ね”が、鬱病を遠ざける大きな防波堤になるのです。
支援②:「できない日」があっても責めない|完璧を求めない関わり方
ADHDの子どもは、調子の良い日と悪い日の差が大きいのが特徴です。
昨日できたことが今日はできない、そんなことは日常茶飯事。
でも、ママから見ると「どうして昨日できたのに?」と思ってしまうこともありますよね。
でもその波こそがADHD特性の一部。
脳のエネルギー配分が日によって違うため、「波がある=成長していない」ではありません。
「できない日」は責める日ではなく、**“休む日”“エネルギーをためる日”**と考えましょう。
むしろ、波を受け入れて柔軟に対応することで、
「今日はちょっとしんどい日でもいいんだ」と子どもが安心できるようになります。
ママが完璧を求めずに、「その子のリズム」を尊重することこそが、心を守る一番の支援なんです。
支援③:感情を受け止める|泣いても怒っても大丈夫な家庭づくり
ADHDの子どもは、感情の波が大きく、時に爆発することもあります。
でもそれは、**「わがまま」ではなく「どうしたらいいかわからない」**というサイン。
「泣かないで」「怒らないで」と止めるよりも、
**「泣いてもいいよ」「今は怒りたくなるよね」**と気持ちを受け止めることが大切です。
感情を吐き出すことは、心のストレスを外に出す自然な行動。
我慢させると、怒りや悲しみが内側にたまって、鬱状態に近づいてしまいます。
家庭では、「どんな気持ちも出して大丈夫」という安心感がとても重要です。
たとえば――
「悲しかったんだね」
「うまくいかなくて悔しかったね」
「今はそんな気分なんだね」
このように共感の言葉を添えるだけで、子どもは「自分を理解してもらえた」と感じます。
それが心を癒やす第一歩になるんです。
支援④:生活リズムを整える|予測できる1日が心の安定を生む
ADHDの子は、「次に何をするのか」「どれくらい時間があるのか」が分からないと、不安を感じやすいです。
そのため、生活リズムを整えて“見通しをもたせる”ことが、心の安定につながります。
たとえば、
- 朝起きる→顔を洗う→ごはん→登園(登校)
- 帰宅→おやつ→宿題→自由時間→お風呂→就寝
といった流れを、毎日ほぼ同じ順番で繰り返すだけでも効果的です。
さらに、予定を**目で見て分かるようにする「視覚支援」**もおすすめ。
イラストのスケジュール表や、タイマーを使って「あと5分だよ」と知らせる工夫を取り入れると、
**「次に何があるか分かる安心感」**が生まれます。
この“予測できる安心”が、ADHDの子にとっての安定剤。
心が落ち着くと、衝動的な行動も減り、鬱病のリスクをぐっと下げることができます。
支援⑤:ママ自身も限界を感じたら相談を|親のメンタルケアも大切
忘れないでほしいのは、ママも人間だということ。
毎日頑張って子どもを支えていると、知らないうちに心が疲れてしまうことがあります。
「イライラしてしまう自分が嫌」「もうどうしたらいいのか分からない」
そんなときこそ、**“頑張りすぎのサイン”**です。
子どもの支援には、ママの安定が欠かせません。
つまり、「母親が無理をしないこと」こそが最大の支援なのです。
無理を感じたときは、ひとりで抱え込まずに、
- 発達支援センター
- 学校・園のスクールカウンセラー
- 医療機関(児童精神科・心療内科)
- 発達障害支援NPOや親の会
などに相談してみてください。
話を聞いてもらうだけでも、心がふっと軽くなることがあります。
「助けを求める=弱いこと」ではなく、**「より良く支えるための行動」**なんです。
ADHDの子どもの心を守るために大切なのは、
**“特別な支援”ではなく“日常の中の小さな優しさ”**です。
「できたね」「今日は休もう」「つらかったね」――
その一言が、子どもの心を支える力になります。
ママの笑顔がある限り、子どもは必ず立ち直れます。
焦らず、少しずつ、**“一緒に歩く支援”**を続けていきましょう。
ADHD+鬱病の子にしてはいけないNG対応3選
ADHDと鬱病を併発している子どもは、**「がんばりたいのにできない」という葛藤の中で、日々たくさんのエネルギーを使っています。
そんなときに、親の何気ない言葉や態度が、知らず知らずのうちに“追い詰める一言”**になってしまうことがあるんです。
もちろん、ママに悪気なんてありません。
むしろ、「励ましてあげたい」「早く元気になってほしい」という思いから出る言葉なんですよね。
でも、心が弱っている子どもにとっては、その励ましがプレッシャーや孤独感に変わってしまうことがあります。
ここでは、ADHD+鬱病の子に対して避けたいNG対応3つを紹介します。
その理由と、代わりにかけたい言葉のヒントも一緒にお伝えしますね。
「頑張りなさい」は禁句|励ましがプレッシャーになる理由
「頑張りなさい」――これは親がよく口にする言葉の代表格ですよね。
でも、ADHD+鬱病の子にとっては、心に重く響く言葉になることがあります。
なぜなら、ADHDの子はすでに「頑張っても報われない」経験をたくさんしているから。
忘れ物をしないように頑張っても、また忘れてしまう。
集中しようとしても、頭の中がうまく整理できない。
つまり、本人なりには十分頑張っているのです。
そんな中で「頑張りなさい」と言われると、
「まだ足りないのか」「もっと頑張らないとダメなのか」と感じてしまい、
結果的に自己否定感を強めてしまうことがあります。
代わりにおすすめなのは、**「頑張ってるの知ってるよ」**という言葉。
この言葉には、「もう頑張らなくてもいい」「今のあなたで大丈夫」というメッセージが含まれています。
💬 例:「毎日ちゃんとやろうとしてるの、ママ見てるよ」
💬 例:「しんどいときは休んでいいんだよ」
“頑張らせる”より、“頑張りを認める”。
この言葉の違いが、子どもの心をラクにしてくれます。
「他の子と比べる」は逆効果|自己否定感を強める危険な言葉
「〇〇ちゃんはちゃんとできてるのに」
「お兄ちゃんはもう自分でやってたよ」
――こんな言葉、つい出てしまうことありませんか?
でも、ADHDの子どもにとって、比較は心を深く傷つける言葉になります。
なぜなら、ADHDの子はすでに「自分はみんなと違う」と感じていることが多いからです。
それを言葉で再確認させてしまうと、**「やっぱり自分はダメなんだ」**という気持ちが強くなってしまいます。
特に鬱状態がある子は、自分を責める思考が強くなっているため、
「比べられる=存在を否定された」と受け取ってしまうこともあります。
比べるよりも意識したいのは、**「その子の中での成長を見つけて伝える」**こと。
💬 例:「昨日よりちょっと早く準備できたね!」
💬 例:「少しずつできることが増えてきたね」
他人と比べるのではなく、**“昨日の自分と比べて前進できた”**と感じられる声かけが、
自己肯定感をじんわりと育てていきます。
ADHDの子は「できない」ではなく、**“やり方が合っていないだけ”**というケースも多いんです。
その子に合った方法を一緒に探していくことが、最大の支援になります。
感情的に叱る・黙って距離を取る|孤独感を悪化させる行動
ママも人間です。
イライラしたり、どう対応していいかわからなくなることもありますよね。
でも、ADHD+鬱病の子にとって、**「感情的に叱られる」ことや「黙って距離を取られる」**ことは、
予想以上に大きなショックになります。
感情的に叱られると、子どもは内容よりも**「ママが怖い」「嫌われた」という感情が残ります。
そして、黙って距離を取られると、「ママに見放された」「自分が悪い子だからだ」**と感じてしまうのです。
ADHDの子は、相手の表情や空気を敏感に感じ取る傾向があります。
そのため、親のちょっとした表情の変化やため息だけでも、
「自分のせいだ」と思い込んで心が沈んでしまうことがあるんです。
もちろん、ママにも休息は必要です。
感情的になりそうなときは、少し距離を取るのは悪いことではありません。
ただし、**「今ちょっと落ち着きたいから、あとで話そうね」**と一言添えてあげましょう。
💬 例:「ママも少し休憩するね。でも嫌いになったわけじゃないよ。」
💬 例:「今は怒ってるけど、落ち着いたらちゃんと話そうね。」
この一言があるだけで、**子どもは「見放された」ではなく「安心して待てる」ようになります。
叱るより、伝える。
突き放すより、“時間を置いてもつながっている”**ことを感じさせてあげることが大切です。
まとめ:子どもの心は「安心感」で回復する
ADHD+鬱病の子どもにとって、一番の薬は**「安心できる人の存在」です。
完璧な対応をする必要はありません。
ただ、「あなたの味方だよ」**というメッセージを日常の中で伝えることが、何よりの支援になります。
ママの優しいまなざしと、一言の温かい声かけ。
それだけで、子どもの心は少しずつ光を取り戻していきます。
【体験談】「うちの子もそうだった」ADHDの子が鬱病になる前に気づけた瞬間
ADHDの子どもが鬱病になるとき――そのサインは、
「急に落ち込む」よりも、もっと小さな変化から始まることが多いんです。
「最近、笑わなくなった」
「好きだった遊びをやらなくなった」
「叱ると反応がなくなってきた」
こうした“いつもと違う様子”は、心のSOSであることがあります。
ここでは、実際に子どもの変化に早く気づいて、家庭での関わりを見直したことで、
回復につながったママたちのリアルなエピソードを紹介します。
どの家庭も特別なことをしたわけではありません。
「ちょっと立ち止まって、子どもの心に耳を傾けた」――その一歩が大きな支えになったんです。
実際のママの気づきと対応事例
①「叱っても反応しなくなった」ことに気づいたママのケース
小学2年生の男の子。忘れ物や集中の途切れが多く、毎日つい叱ってしまう日々。
ある日、叱っても泣かなくなり、ただ無表情で俯く姿にママはハッとしたそうです。
「いつもなら反論したり泣いたりするのに、何も言わなくなった。
それを見て、“あ、もう限界なんだ”と思いました」
それからは、「怒る前に、どうしてできなかったのかを一緒に考える」関わりに変えたとのこと。
💬「『次どうしたらいいかな?』って聞くようにしたら、
少しずつ笑顔が戻ってきたんです」
このママは後から、「うつの入り口だったかもしれない」と振り返ります。
叱っても反応しなくなる=心のシャッターが下りているサイン。
早めに気づけたことが、その子の心を守る大きな転機になりました。
②「大好きな遊びをやらなくなった」ことに気づいたママのケース
いつもブロック遊びが大好きだった4歳の男の子。
ある日から突然、「もういい」「疲れた」と言って遊ばなくなりました。
最初は「飽きたのかな?」と思っていたママ。
でも、日が経つにつれて無表情が増え、声をかけても反応が薄くなったことで、違和感を感じたそうです。
その後、園の先生にも相談し、「最近ちょっと元気がない」と言われ、
児童精神科を受診。軽度のうつ状態が見つかりました。
💬「遊ばなくなったのは、心のエネルギーが減っていたからなんだと知りました。
“もっと遊びなさい”じゃなくて、“ゆっくりしていいよ”と言えばよかったんだと反省しました。」
このママは、**「できない=怠けている」ではなく、「疲れている」**という視点に変えたことで、
息子さんが少しずつ回復していったそうです。
ADHDの子にとって、遊びや活動はエネルギーを使うもの。
だからこそ、「楽しめなくなったとき」は、**“心の休憩が必要な合図”**なんです。
③「いつも謝るようになった」ことに気づいたママのケース
小学3年生の女の子。
もともと明るく元気なタイプだったのに、いつのまにか
「ごめんなさい」「私が悪いんでしょ?」と言うことが増えていったそうです。
最初は「素直になってきたのかな」と思っていたママも、
次第にその“ごめんなさい”の多さに違和感を覚えました。
💬「叱ってもいないのに“ごめんなさい”と言う姿が切なくて。
これは自信がなくなってるサインかもと思いました。」
その後、学校でのトラブルが続いていたことがわかり、
担任の先生と連携して、叱るよりも共感で寄り添うように家庭での対応を見直したそうです。
数か月後、「ママ聞いて!今日ね、上手にできたの!」と笑顔を見せるようになり、
少しずつ元気を取り戻していきました。
「ごめんなさい」が口ぐせになったときは、自己否定のサイン。
そんなときは、「あなたは悪くないよ」「どう感じたの?」と気持ちを聞いてあげることが大切です。
早期対応で回復につながった家庭のリアルストーリー
3人のママに共通していたのは、
子どもの変化に気づいたあと、**「叱る」よりも「寄り添う」**方向に舵を切ったこと。
そして、**「完璧を求めるより、安心できる時間を増やす」**ことに意識を向けた点です。
「できた・できない」よりも、「今日は一緒に過ごせてうれしかったね」
「あなたがいてくれるだけで大丈夫だよ」
そんな声かけが、子どもの心を少しずつ回復させていく力になります。
ADHDの子どもは、日常の中でたくさんの小さな挫折を経験しています。
でも、ママのまなざしひとつで、「自分は大切にされている」と感じることができるんです。
まとめ:気づく力が、いちばんの支援になる
ADHDと鬱病の関係は、医学的にも複雑ですが、
家庭の中でママが**「あれ? いつもと違うな」と感じる感覚**こそ、何より大事なサインです。
- よく笑っていたのに、最近無表情が増えた
- 好きなことをやらなくなった
- 「ごめんなさい」が増えた
こうした変化は、「心が疲れているよ」という子どもからのメッセージです。
ママがそれに気づき、「どうしたの?」と優しく声をかけるだけで救われる心があります。
どんなに小さな違和感でも、立ち止まって耳を傾ける――
それが、子どもを鬱から守る一番の支援なんです。
まとめ|“気づく力”が子どもの心を守る第一歩
ADHDの子どもが鬱病のような心の不調を抱えるとき、
その背景には「性格」や「気持ちの弱さ」ではなく、脳の働きや環境のストレスが深く関係しています。
つまり、鬱病は**「がんばりが足りないから」ではなく、「がんばりすぎた結果」**なんです。
まじめで一生懸命な子ほど、自分の思うようにいかない日々に苦しみ、
気づかないうちに心が疲れてしまうことがあります。
そんなときに何より大切なのが、ママの“気づく力”。
それは特別な知識ではなく、
「なんか元気がないな」「前より笑顔が少ないな」という日常の中の小さな違和感に気づける感性です。
鬱病は「性格の弱さ」ではない
「うちの子、心が弱いのかな?」
そう感じるママもいるかもしれません。
でも、鬱病は決して**“心の弱さ”ではありません。**
むしろ、「頑張り屋」「我慢強い」「人に迷惑をかけたくない」――
そんな優しい性格の子ほど、心が疲れやすいのです。
ADHDの子は、脳の特性によって注意が散りやすく、失敗や叱責を受けやすい環境にあります。
そのため、自分でも気づかないうちに**「どうせ自分はダメだ」**という思い込みを抱えやすくなります。
親がそのサインに早く気づき、「あなたは悪くないよ」「疲れたら休んでいいよ」と
伝えてあげることが、何よりの支えになります。
親が小さな変化に気づくことが最大の予防
鬱病を防ぐ“薬”のようなものはありません。
でも、「早く気づくこと」こそが最大の予防策になります。
- いつもより笑顔が少ない
- 好きな遊びをやらなくなった
- 「ごめんなさい」が増えた
- 朝なかなか起きられない
- 食欲に波がある
こうした小さな変化は、心のエネルギーが減っているサインかもしれません。
そして、ママがその変化に気づいて、
「どうしたの?」「疲れてる?」「一緒にゆっくりしようか」と声をかけるだけでも、
子どもは**“自分は見てもらえている”という安心感**を得られます。
子どもの心を守る第一歩は、特別な知識よりも、日々の小さな観察と優しいまなざしなんです。
今日からできる、心を守る一歩を一緒に
ADHDの子を育てる日々は、正直、想像以上に大変です。
注意しても直らない行動や、理解されにくい特性に、ママ自身が疲れてしまうこともありますよね。
でも、そんな中でも、
**「気づく」「受け止める」「休ませる」**という3つの行動だけで、
子どもの心は確実に守られていきます。
💬 今日は叱るより、抱きしめて終わりにしよう。
💬 できなかったことより、できたことを見てあげよう。
💬 「大丈夫だよ」と言葉にして伝えてあげよう。
その一つひとつが、**“うつを防ぐ力”**になります。
ママが完璧である必要はありません。
疲れたときは、誰かに話してもいいし、相談してもいい。
ママが自分をいたわることも、子どもの心を守る大切な支援のひとつです。
子どもが笑顔を取り戻すためには、
まず**「ママが安心できること」**が一番のスタートライン。
焦らず、比べず、
「今日も気づけた自分、えらいな」と、自分にも優しい声をかけてあげてくださいね。
あなたの“気づく力”が、今日もお子さんの心を守っています。🌱
以上【知らないと危険/ADHDの子が鬱病になる前に気づく5つのサイン】でした

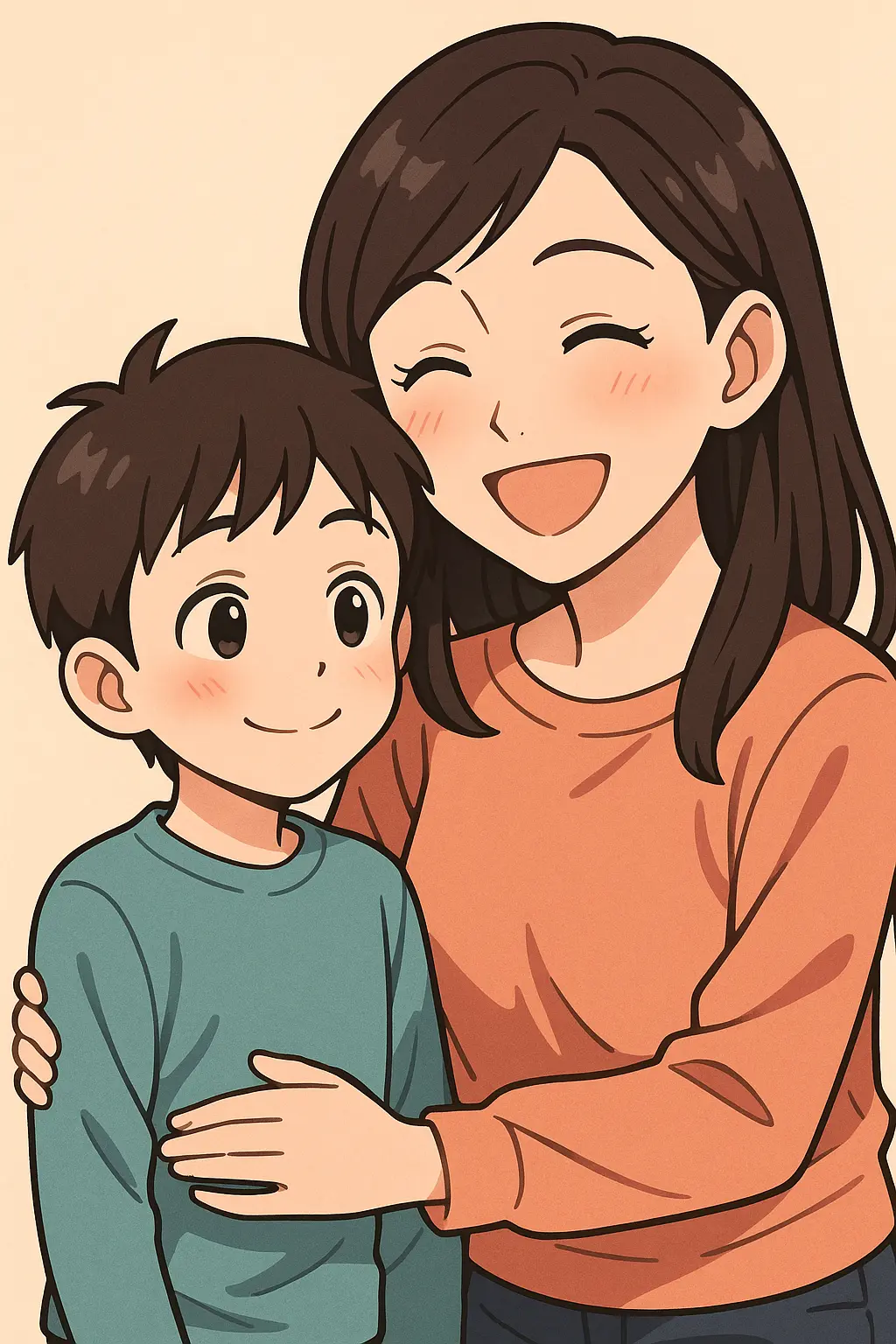









コメント