発達障害の子がつまずきやすい理由は?RISU体験でわかった学びの壁
発達が気になるお子さんの算数のつまずきって、決して「能力が低いから」ではないんですよね。
実際、RISUを体験してみて気づいたのは、つまずきには“共通の理由”がしっかりあるということ。
そして逆に言うと、その理由さえ理解しておけば「お子さんが学びやすい環境」を作ることができるんです。
ここでは、ADHD傾向・ASD傾向・自信が育ちにくいタイプの子、それぞれに共通する“つまずきポイント”を、できるだけわかりやすくまとめていきますね。
「うちの子にも当てはまるなぁ…」と感じる部分があれば、それは学び方を変えるチャンスにもなります。
ぜひ気楽に読み進めてください。
ADHD傾向の子が“集中しづらい”本当の理由とは?
ADHD傾向のある子は、「集中できない」というより、
“集中の入り口に入りにくい”ことがとても多いんです。
ママさんも経験あると思いますが、
「机に座らせるのがまず大変…」
「やり始めても数分で席を立ってしまう…」
こういう状態は “やる気がない” のではなく、脳の働き方が関係しています。
たとえば…
- 周りの音や動きが気になりやすい
- 興味のないことには注意が向きにくい
- 複数の情報が一度に入ると混乱しやすい
こういった理由から、紙のドリルのように「文字だけで説明される教材」だと、集中のスイッチが入りづらいんですね。
一方で、RISUのように
・1問1画面で完結する
・見やすいイラストや音で注意を引きやすい
・テンポよく問題が進む
といった特徴があると、集中のハードルがぐっと下がります。
特に「ゲームみたいに進んでいく仕組み」は、ADHD傾向の子が入りやすい大きなポイント。
これは体験していてもすごく実感しました。
つまり、ADHD傾向のある子に必要なのは、
「集中しやすい形に学びを整えてあげること」なんですね。
ASD傾向の子が算数でつまずきやすい背景と特徴
ASD傾向のお子さんは、もともと一つのことに集中しやすかったり、興味の幅が狭かったりします。
ですが算数に関しては、意外なところでつまずきやすい傾向があります。
とくに多いのが…
- 抽象的な説明が苦手(例:文章問題、割合、図形の説明など)
- 「どうしてそうなるの?」のつながりが見えないと理解が止まる
- 急な変化や、予想外の問題が出ると混乱しやすい
ASD傾向の子は、言葉だけで理解するより
視覚的に“見える化”されている方が圧倒的に理解しやすいんですね。
RISUを体験して感じたのは、
「数が動いて見える」「図が変化する」「説明が一画面でわかる」
というように、“視覚に強い子が理解しやすい工夫”がとても多いこと。
さらにASD傾向の子は、
自分のペースが守られると、安心して学びに向かえる
という特徴があります。
RISUは、自分のタイミングで
「戻る → やり直す → 同じ問題を何回も見る」
が自由なので、安心して取り組みやすいんです。
つまりASD傾向のお子さんにとって算数が難しい理由は、能力ではなく
“抽象的な説明が多い”教材との相性なんですよね。
その相性を整えてあげれば、一気に理解が進みます。
“自信が育ちにくい子”に共通する学習パターンとは?
発達に特性のあるお子さんにとても多いのが、
「失敗体験が積み重なり、自信がすぐしぼんでしまう」という状態です。
たとえば…
- 1問つまずくと「もう無理」と手が止まる
- 間違いを指摘されると落ち込みが早い
- 「できている部分」を自分で気づきにくい
こうした“自信の弱さ”は、学びにも大きく影響します。
実際、どんなに力があっても、
「自分はできない子だ」と思い込んでいると進むスピードはガクッと落ちます。
そして自信が育ちにくい子の学習には、ある共通点があります。
それは…
成功体験の間隔が長すぎる
算数の単元が大きくて、成功までの道のりが長いと、途中で疲れちゃいます。
間違いが“ダメなこと”としてインプットされている
本来、間違いは成長のチャンス。
でも過去の経験で“失敗=怒られる・否定される”と感じていることも。
つまずいた時に戻る場所がない
戻る場所がないと、路頭に迷ってしまい “できないループ”に入ります。
RISUを使うと、
・超スモールステップ
・小さな成功が次々積み重なる
・AIがつまずきを先回りして調整してくれる
という仕組みがあるので、自然と自信が育ちやすくなるんですね。
「成功体験の量」がそのまま「自信の量」につながる子には、本当に相性が良いと感じました。
子どもの学習に合う教材を探しているママさんへ。
今回紹介する「RISU算数」は、発達が気になる子でもムリなく続けやすい教材です。
「まずはどんな教材か軽く見たい」という方はこちらをご覧ください
RISU算数で見えた!発達障害の子が伸びる“学習の成功パターン4つ”
RISUを実際に使ってみて感じたのは、
発達が気になる子には 「伸びる瞬間のパターン」 があるということです。
これは偶然ではなく、RISUの教材設計が“発達特性のある子の学び方”とかなり相性が良いからこそ起きていること。
実際に体験していて、
- どうしてこんなに集中が続くの?
- なんで急に「やりたい!」が増えるの?
- 苦手だったはずの算数ができるようになったのはなぜ?
という“伸びの理由”が、4つのパターンにわかれて見えてきたんです。
ここでは、その4つをできるだけわかりやすくお話ししますね。
成功体験が増えると算数が好きになる理由
発達が気になる子の多くが、算数を苦手に感じる理由は
“できた!”という成功体験が圧倒的に少ないから なんです。
RISUを体験して改めて感じたのは、
算数が好きになる一番の近道は、
「小さな成功をたくさん積み重ねること」 だということ。
特にRISUは…
- 問題が1つずつクリアしやすい
- 難しすぎる問題が急に出てこない
- ちょっと進むごとに褒めフィードバックが入る
といった仕組みがあるので、子どもが自然に
「あ、できた!」
「これならもう少しやりたい!」
という気持ちになりやすいんですね。
そしてこれ、心理学でもはっきり言われているのですが、
人は成功体験が増えると、脳の“やる気ホルモン”が出やすくなるんです。
これは大人も同じですが、特に発達特性のある子には大きな効果があります。
「算数って苦手…」と感じていた子が
「算数って意外と楽しいかも?」に変わる瞬間、
それは小さな成功体験が積み重なった時に訪れるんですよね。
自分のペースで学べる教材が“続く”最大のメリット
発達が気になる子にとって、
“自分のペースを守れるかどうか”は学びの質を大きく左右します。
RISUがすごいのは、そのペース調整が「AIによって自動で行われる」こと。
たとえば…
- 今日は疲れている
- 気分が乗らない
- どうしても理解しづらい単元
こういう時でも、RISUは無理に難しい問題を出してこないんです。
逆に、調子がいい時にはどんどん進むことができる。
この「ムリしないでいい」という環境は、発達特性のある子にとって 本当に大きな安心感 になります。
しかも、ペースを自分で決められると
- 勉強が嫌になりにくい
- 怒りやパニックが減る
- 親が教えすぎなくてよくなる
という“続けやすいサイクル”ができるんですね。
発達が気になる子にとって、続けられる学習というのは
「量よりペース」 が命。
RISUはその“ペース管理”がとても上手なんです。
視覚支援があると理解がスッと入る!RISUの強み
算数が苦手な子の多くが躓きやすいのは、
「頭の中でイメージすることがむずかしい単元」 です。
たとえば…
- 繰り上がり・繰り下がり
- 図形の回転
- 分数の分け方
- 大きさの比較
こうした“抽象的な概念”は、文字だけで説明されても理解が追いつきません。
でもRISUは、説明が全部 “目で見える形” になっています。
- 数が動くアニメーション
- 図形がクルッと回る映像
- 分数が実際に分かれていく動き
- 一画面で見やすいレイアウト
視覚で理解できると、
「あ、なるほど!」が一気に増えるんです。
特にASD傾向のある子や、数量理解が苦手な子は
視覚支援があるだけで理解スピードが倍くらい変わる ことも。
RISUの“見て学べる”仕組みは、こうした特性にすごくマッチしていると感じました。
スモールステップが発達特性の子に抜群に合うワケ
最後の成功パターンは、
「ステップの細かさ」 です。
発達が気になる子には、
“急に難しくなる” という学び方は本当に合いません。
つまずき → 自信ダウン → 勉強拒否
この流れは多くのママさんが経験しているはず…。
RISUのスモールステップはとにかく細かく、
- いきなり新単元に飛ばない
- ちょっと成功したら少しだけ次に進む
- つまずく前にAIが調整してくれる
という仕組みになっています。
スモールステップで進むと、
「できた → できた → またできた!」
の成功ループが続くので、お子さんがどんどん前向きになるんですよね。
そして、成功体験が続くと脳が
「もっとやってみたい!」
という気持ちを自然に作り出します。
発達特性のある子の場合、
この“スモールステップ × 成功体験”の組み合わせは
最強の学び方と言っても過言ではありません。
RISUはまさにこの仕組みが徹底されているので、
「学ぶのが苦手だった子」が変わりやすいんだと思います。
【体験レビュー】RISU算数の効果は?発達が気になる子の変化を徹底レポート
「うちの子、算数になると急に固まっちゃう…」
「集中してくれないから、家で勉強させるのが大変…!」
そんな声、発達障害児を育てているママさんから本当によく聞きます。
今回の章では、RISUを1ヶ月体験してわかった
「発達が気になる子が変わっていくリアルな過程」を
実際の反応をもとに、できるだけわかりやすくお伝えしていきますね。
RISUを始める前の悩み|算数が苦手・集中続かない・自信がない子の特徴
RISUを始める前、どのお子さんにも共通していたのは
「算数は苦手」「集中できない」「すぐに諦める」
という3つの悩み。
これって決して珍しいことではなく、
発達特性のある子にはとても多いパターンなんです。
特に、以下の傾向があるお子さんは算数でつまずきやすいと言われています。
- 抽象的な説明が苦手(数字・図形・文章問題の理解が難しい)
- 手順が多いと混乱しやすい
- 「間違える=ダメ」と思い込みやすい
では、なぜそうなってしまうのでしょうか?
算数が苦手な理由は?抽象概念につまずきやすい子の傾向
算数って、思っているよりも“抽象的”な学びなんです。
たとえば計算1つにしても、
- 数字が何を表しているのか
- 数の大きさのイメージ
- 図形のイメージ
- 手順の理解
と、実は目に見えない概念だらけ。
発達が気になる子の中には、
「目に見えないイメージを頭の中で作る作業が苦手」
というタイプが一定数います。
そうなると、
- 文章を読んでも意味がつながらない
- 図形を見ても動きがイメージできない
- 繰り上がりが何をしているのか理解できない
という状態になりやすく、
「算数って難しい」
という気持ちがどんどん強くなってしまうんですね。
特にASD傾向のある子には、
目で見てわかる説明の方が圧倒的に理解しやすい
という特徴があります。
“できない”経験の積み重ねが学習拒否につながりやすい理由
発達特性のある子に多いのが、
「できない経験を強く覚えてしまう」
という特徴。
一度つまずくと、脳の中に
“算数=嫌なもの”
として登録されてしまうことも。
例えば…
- 1問間違えただけでやる気がゼロになる
- 問題を見ると最初から「ムリ!」と言う
- 勉強の時間になると気持ちが不安定になる
こういった行動は、単なるワガママではなく
「自己肯定感が落ちているサイン」でもあります。
RISUを始める前は、これが蓄積されている状態でした。
でも、こうした状態は“伸びない子”ではなく、
「伸びるための土台が整っていないだけ」なんです。
RISUを使うことで、その土台がどう変わっていくのか――
次の章でリアルにご紹介します。
【1ヶ月のRISU体験記】ADHD/ASD傾向の子がどんな風に変わった?
RISUを1ヶ月使ってみると、
「あ、この子にはこういう学び方が合うんだな」
という変化が驚くほど見えてきました。
ここでは、1週間ごとにどんな変化があったのかを
わかりやすくまとめていきます。
1週目:RISU算数がゲーム感覚でハマる理由とは?
1週目は、とにかく
「タブレットが楽しい!」
この気持ちが強い時期です。
ADHD傾向の子は、
「入り口の興味を引けるかどうか」が超重要。
RISUは…
- 音やアニメーションがシンプルで心地いい
- 問題が1問1画面でテンポよく進む
- 合格すると“ごほうびポイント”がもらえる
という作りなので、最初の段階で「もう1問!」と続けやすいんです。
ここで集中できるのは、
“算数が好きだから”ではなく
「ゲームみたいに楽しいから」です。
でも、この“楽しい”が後の学習意欲につながっていきます。
2〜3週目:“できた!”が増え始めたリアルな瞬間
2〜3週目になると、RISUの本領発揮。
AIが自動でレベル調整してくれるので、
子どもが“頑張れば届く”レベルの問題が出てきます。
ここで増えてくるのが、
「あ、できた!」の瞬間。
実際に多かった変化は…
- 間違えても落ち込みにくくなる
- コツコツ進める習慣がつき始める
- 「同じ問題、もう1回やりたい!」が増える
こうした前向きな姿勢が出るのは、
スモールステップで成功体験が積み重なっているからなんです。
特にASD傾向の子には、
テンポが一定で見通しが立つRISUの形式が
とても合っていると感じました。
1ヶ月後:算数の苦手意識が減り、自信が芽生えるまでの流れ
1ヶ月たつ頃には、
算数に対する表情がガラッと変わります。
今まで…
- 「算数イヤだ」
- 「どうせできない」
- 「ムズかしいからやりたくない」
と言っていた子が、
- 「今日はどこまで進めようかな?」
- 「これならできそう!」
- 「見て、これできたよ!」
と、前向きな言葉が増えるように。
これは、RISUの
・スモールステップ
・ペース調整
・視覚支援
・褒めフィードバック
の4つが合わさった結果です。
勉強に“自信”が持てるようになると、
その子の表情まで明るくなってくるんですよね。
「うちの子にも合うかも…」と感じたママさんは、内容をチェックしてみてください
発達障害の子にRISUが向いている3つの理由【視覚支援・AI診断・褒め設計】
RISUを使ってみて感じたのは、
発達が気になる子にとって
「使いやすい」ではなく「相性がいい」という点。
その理由は大きく3つありました。
視覚的に理解できるインターフェースが強い味方に
発達特性のある子は、
言葉より“目で見える情報”の方が理解しやすいことが多いです。
RISUは、
- 数が動くアニメーション
- 図形がくるっと回る様子
- 色分けされた分かりやすい図
- 文章が短く、画面にまとまっている
こうした視覚的サポートが多いので、
理解がスッと入るんですよね。
これはASD傾向・LD傾向どちらの子にも役立ちます。
AIが苦手を自動分析→最適問題でスムーズに理解
RISUは、子どもの答え方を見ながら
リアルタイムで得意・苦手を分析してくれます。
だから、
- いきなり難しい問題が出る
- 逆に簡単すぎる問題ばかり続く
というミスマッチがないんです。
発達特性のある子には、
「ちょうど良いむずかしさ」がめちゃくちゃ重要。
負担が少ないうえ、
スムーズに理解できるので、
「勉強がイヤ!」になりにくくなります。
できた!を増やす褒めフィードバックが自己肯定感を育てる
RISUが本当にすごいのは、
褒めの設計がとても上手いところ。
- 問題を解くたびに小さく褒めてくれる
- ステージをクリアすると達成バッジ
- 続けるとポイントが貯まる
これが“やりたい気持ち”を自然と引き出すんですよね。
発達が気になる子の学びで超重要なのが、
「自己肯定感」。
RISUは、成功体験を細かく積み重ねる仕組みがあるので、
自己肯定感が育ちやすい教材なんだと実感しました。
RISU算数でわかった!発達が気になる子が伸びる“学び方の4原則”
RISUを1ヶ月ほど使ってみると、
発達が気になるお子さんが“どうすると伸びやすいのか”が
とてもよく見えてきました。
特に感じたのは、
「発達特性のある子には、伸びるための“学び方の型”がある」
ということ。
これは単なるテクニックではなく、
お子さんの脳の特性や気質にも合った、とても自然な学び方なんです。
今回はその「4つの原則」を、できるだけわかりやすくお伝えしますね。
【原則①】毎日ひとつの成功体験が“算数の自信”を育てる
発達が気になる子は、
「1日にひとつの成功体験」があるだけで、
次の日のやる気や心の安定がガラッと変わります。
逆に、成功体験がほとんどないまま「苦手」に挑戦すると、
自己肯定感がどんどん下がってしまうことも…。
まずは、なぜ小さな成功がそんなに大事なのかを一緒に見ていきましょう。
小さな成功が学習意欲を引き出す科学的理由
人の脳は、成功体験をすると
“ドーパミン”というやる気ホルモンが出ることが分かっています。
これは大人も同じですが、
発達特性のある子は、
- 成功体験を感じやすい
- 逆に失敗体験のダメージも大きい
という特徴があります。
そのため、成功体験の量が増えるほど、
勉強に対して前向きな気持ちが生まれやすくなるんです。
とくに算数は「できる/できない」の差がハッキリ出る教科なので、
小さな成功を積み上げていくのがとても効果的。
RISUでは、この小さな成功がとにかく増えるので、
やる気のスイッチが入りやすいんですね。
RISUが成功体験を量産できる仕組みとは?
RISUには、「成功体験を作る工夫」がたくさんあります。
例えば…
- 問題が1つ1つ細かく区切られている
- ちょっと頑張れば届く問題が出てくる
- できた瞬間に褒めボイスが流れる
- ステージクリアで“達成感”が目に見える
これらの仕組みが組み合わさることで、
気づけば毎日1つ、いや2つ3つと成功体験が増えていきます。
発達特性のある子の場合、
“難しすぎる問題”が出るだけで一気にやる気が下がってしまうので、
この絶妙なレベル調整が本当にありがたいポイントなんです。
【原則②】やり直し・戻りができる教材は定着力が段違い
発達が気になる子は、
「あ、わかったかも!」と思っても時間が経つと忘れてしまう
ということがよくあります。
これは記憶力が弱いわけではなく、
脳の情報整理がゆっくりだからなんです。
だからこそ、
同じ問題を繰り返し、安心できる場所に戻れる学習環境がとても大事です。
発達特性のある子ほど“振り返り学習”が効果的な理由
発達特性のある子は、
新しい情報を理解するまでに「段階」が必要なことが多いです。
たとえば…
- 見て理解する
- やってみて理解する
- 繰り返して覚える
- 少し時間を置いて復習して定着
この“段階”を飛ばすと、
理解が追いつかずに
「もうわかんない!」
という状態に。
振り返り学習をすると、
頭の中で情報がつながって
「あ、こういうことだったのか!」
と理解が深まるんです。
RISUの自由な復習機能が理解を深めるワケ
RISUは、
自分の好きなタイミングで“戻る&やり直す”が自由。
これは大きな強みです。
- 間違えた問題をその場でやり直せる
- 少し前の単元に戻って再確認できる
- 苦手なところを重点的に復習できる
紙のドリルではなかなか難しい
「柔軟な復習」ができるんですね。
これにより、
発達特性のある子が苦手としやすい
- 記憶の抜け
- 理解の穴
- 手順の混乱
を自然に補うことができます。
【原則③】視覚で理解できる教材は算数の苦手克服に最適
発達が気になる子の中には、
「言葉で説明されるとわからない」
というタイプの子がとても多いです。
でも、
目で見て理解することは得意!
というケースが多いんですね。
そこで力を発揮するのが「視覚支援」。
RISUはとにかく“見てわかる”工夫が多い教材です。
数量理解が弱い子をサポートする視覚効果とは?
算数の理解には、
「数のイメージ」がとても大事です。
ところが、
- 数の大小
- 繰り上がり
- 図形の動き
- 分数のしくみ
これらはすべて頭の中でイメージしないといけない“抽象的な概念”。
RISUではこれを
アニメーションや図解で“目で見える”形に変えてくれます。
視覚で理解できると、
「なんとなくわからない」状態が消えて
理解のスピードが一気に上がるんですね。
RISUの図解・アニメーションが“分かりやすい”と評判な理由
RISUの画面は、
とにかくシンプルで分かりやすいです。
- 余計な文字が少ない
- 大事な部分だけが大きく表示される
- 図形や数の動きがアニメーションで表現される
この“視覚の工夫”は、
文章を読むのが苦手な子や、注意がそれやすい子には本当にありがたいポイント。
実際、
「RISUだと理解できた!」
という声がよくあるのは、
この視覚支援のおかげなんです。
【原則④】得意を伸ばすと、苦手克服につながる学習サイクルが生まれる
発達特性のある子にとって、
「得意なことから始める」のはとても効果的な方法です。
なぜなら、得意なことは自然と成功体験が増えるから。
成功体験が増えると自己肯定感が上がり、
苦手にもチャレンジしやすくなるんですね。
“得意から入る学び”が発達障害の子に効果的な理由
発達が気になる子は、
得意・不得意の差が大きいという特徴があります。
そのため、
- 得意 → 気持ちのエネルギーが貯まる
- 苦手 → 気持ちのエネルギーが減りやすい
というように、
学びの中で“気持ちの動き”が大きく変わりやすいんです。
だからこそ、
得意を伸ばす→自信が育つ→苦手に挑戦できる
という流れがとても大事。
RISUは、まさにこの学び方にピッタリの教材なんです。
RISUは自動レベル判定で得意を見つけやすい設計
RISUは最初に「実力テスト」がありますが、
これはただのテストではありません。
AIが、
- 得意な単元
- 苦手な単元
- ちょうど良いレベル
を自動で分析し、
その子の得意からスタートできるように調整してくれるんです。
得意からスタートすると、
- できる!
- 楽しい!
- 続けたい!
という気持ちになり、
そのエネルギーで苦手単元にも取り組みやすくなります。
発達特性のある子にとって、
この仕組みは本当に大きなサポートになります。
【特性別】RISU算数はどんな子に合う?ADHD・ASD・LDごとに解説
RISU算数を実際に使ってみると、
「この子にはすごく合いそう!」という瞬間が何度もありました。
発達特性があるお子さんは、それぞれに得意・不得意のパターンが違いますよね。
- 集中が続かない
- ペースが乱れる
- 抽象的な説明が苦手
- 言葉で理解するのがむずかしい
そんな悩みを抱えるママさんでも、
「うちの子はどのタイプかな?」
とイメージできるよう、ADHD・ASD・LDの特性別にわかりやすくまとめました。
お子さんに合う学び方を見つけるヒントにしてみてくださいね。
ADHDタイプの子にRISUが合う理由|短時間集中・ゲーム性・テンポの良さ
ADHD傾向のあるお子さんは、
「集中の入り口に入るのがむずかしい」ことが多いです。
でも一度ハマれば、とても集中できる“ハイパーフォーカス”があるタイプの子も多いんですよね。
RISUは、ADHDタイプの子が持つ
「集中のスイッチを入れやすい工夫」がたくさん詰まっています。
ゲーム感覚の問題が“やる気の入口”に
ADHDタイプの子は、
「おもしろそう!」と感じるまで学習に入りにくい傾向があります。
RISUはまさに、
- 問題がテンポよく進む
- 音やアニメーションで“飽きにくい”工夫がある
- バッジやポイントなどの“ごほうび設計”がある
と、最初のハードルがとても低い教材です。
特に、
「ゲームっぽさがあると入りやすい」
という特徴は多くのADHDの子に当てはまります。
“楽しい入り口”があることで、
自然と勉強時間が伸びたり、今日はあと1問だけ…が続いたりするんですよね。
1問完結型が飽きやすい子にぴったり
ADHD傾向の子は、
長い説明や、複雑な手順が続くと一気に集中が切れることがあります。
RISUは、
- 1問ごとに画面が切り替わる
- 問題の説明が短く、わかりやすい
- 次のステップにすぐ進める
というスタイルなので、集中が長続きしやすいんです。
「こまめに達成感が味わえる」
これは飽きやすい子にとって、とても大事なポイントです。
ASDタイプの子にRISUが合う理由|自分のペース・構造的理解・安心感
ASD傾向のあるお子さんは、
“自分のペースが守られること”をとても大切にします。
また、抽象的な説明より
目で見て理解することが得意な場合が多く、
RISUはその特性にとても合っています。
自分ペースで学べる安心感が特性にマッチ
ASDタイプの子は、
突然ペースを変えられたり、終わりが見えない課題に取り組むと不安が強くなる傾向があります。
RISUでは、
- 自分のタイミングで進められる
- 戻る・やり直す・同じ問題を見る が自由
- 必要以上に“急かされる”ことがない
こうした環境があり、
「見通しのある学習」になるので落ち着いて取り組めます。
特にASDタイプの子にとっては、
「次がどうなるかわかる」という安心感が集中力を生むんですよね。
スモールステップ学習で負荷が少ない理由
ASD傾向の子は、
急に難しくなるという状況がとても苦手です。
RISUのスモールステップは、
- 1つの単元を細かく分けてくれる
- “急にわからなくなる”瞬間がほぼない
- 小さな成功体験が積み重なりやすい
という構造なので、ストレスが少ないんです。
「難しくてパニックになる」
「突然わからなくなるのがつらい」
といった経験が少なくなるので、
ASD傾向の子と相性がとても良いと感じました。
LD(学習障害)傾向の子にRISUが合う理由|数量理解の支援が充実
LD傾向のお子さん(特に算数が苦手なタイプ)は、
目に見えない概念を理解することが苦手という特徴があります。
RISUは、この“抽象的な考え方”を
視覚的にわかりやすくかみくだいてくれる教材なんです。
図解・アニメーションで抽象概念が理解しやすい
LD傾向の子は、次のような問題でつまずきやすいです。
- 数の大小
- 図形の動き
- 分数や割合
- 単位の概念
これらはどれも頭の中でイメージする必要があり、
紙の教材だけでは理解が難しいことが多いです。
RISUでは、
- 数が“動いて見える”アニメーション
- 図形が回る・重なる変化
- 色や形で整理された図
- 短い説明とセットになった視覚支援
こうした仕組みのおかげで、
抽象的な概念が“目で見て理解できるもの”に変わるんです。
「なるほど、こういうことか!」がたくさん生まれる瞬間ですね。
具体→抽象の循環学習で定着しやすい設計
LD傾向の子は、
具体的な例 → 抽象的な理解 の流れがとても大事です。
RISUはまさにこの流れが組み込まれています。
たとえば…
- まずアニメーションで“具体的なイメージ”を見る
- 問題を解きながら“抽象的な考え方”につなげる
- 何度も繰り返して定着させる
このステップが自然に回るので、
理解の抜けが少なく、記憶にも残りやすいんです。
LD傾向の子が苦手な
「頭の中だけで考えてね」
という部分を助けてくれる、ほんとうに心強い教材だと感じました。
RISUを始める前に知っておくべき注意点&上手に使うコツ
RISUは発達が気になるお子さんと、とても相性の良い学習タブレットですが、
「合う子にはすごく合うけど、使い方を間違えるともったいない…!」
というポイントもいくつかあります。
ママさんが事前に知っておくと
ストレス少なく、無理なく続けられるヒントになるので、
ぜひチェックしてみてくださいね。
RISUのデメリット・注意点|料金体系・操作の難しさをチェック
RISUは良いところがたくさんありますが、
完璧な教材というわけではありません。
発達が気になるお子さんに使う場合、
事前に知っておくと安心できるポイントがいくつかあります。
学習の進み具合で追加料金が発生する仕組み
RISUの料金について、よくママさんから質問されるのが
「追加料金ってどうなるの?」 という点です。
RISUは基本料金に加えて、
学習が早く進むほど追加料金がかかる仕組みになっています。
これは、
- どんどん先取りしたい子
- サクサク進むタイプの子
にはメリットがありますが、
発達特性のあるお子さんは進み方にムラが出やすいため、
最初は様子を見ながら進めるのがおすすめです。
ただし、逆に言うと
ゆっくりペースの子の追加料金はほとんどかからないため、
ペースを気にせず安心して進められるメリットがあります。
※「料金が不安…」という場合は、
“1日数問だけ”から始めると進みすぎ防止になります。
タブレット操作が苦手な子へのフォロー方法
発達が気になる子の中には、
タブレット操作が苦手なタイプの子もいます。
たとえば、
- タップの位置がズレる
- スワイプが上手くできない
- 手順が覚えられない
など、最初の操作に戸惑うこともあります。
ただし、RISUは子ども向けにデザインされているため、
慣れてくるとだいたい数日〜数週間でスムーズに使えるようになります。
もし操作が苦手な場合は、
- 最初の数日はママが横で一緒にやる
- 操作は最小限にして、一緒に画面を読むだけでもOK
- 「完璧に操作しなくても大丈夫だよ」と安心させる
といったフォローをすると、スムーズに入りやすくなります。
ママの負担を増やさずRISUを継続するコツ
RISUは家庭学習用の教材ですが、
ママがガッツリ横につかなくても進められる点が大きなメリットです。
とはいえ、最初の使い方を間違えてしまうと、
「ママがつきっきりじゃないと進めない…」
という状態になることも。
ここでは、ママの負担を最小限にして
無理なく継続できるコツをお伝えします。
1日5分から始めると成功しやすい理由
最初から
「毎日30分やろう!」
と決めてしまうと、親子ともにしんどくなってしまいます。
発達特性のある子は、
“短い成功”を積み重ねる方が長続きしやすい特徴があります。
だからこそ、最初は
1日5分だけ・1問だけ・1画面だけ
と決めてしまうのがおすすめ。
小さく始めると、
- 子どもの負担が少ない
- ママもイライラしにくい
- 「できた!」が増える
- 継続しやすくなる
という良いサイクルが生まれます。
最初はとにかく“軽さ”が大事です。
親が教えすぎない方が子どもが伸びるワケ
RISUでは、
「親が教えすぎると逆に伸びにくくなる」
という面があります。
理由は2つ。
- AIが“本当の理解度”を判断できなくなる
- 親が答えを教えると、子どもが考える機会が減る
とくに発達が気になる子は、
「正解をもらう」ことに慣れると、
“考える”前に諦めてしまうクセがつくことがあります。
だからこそ、
- 親はあくまで“見守り役”
- 子どもが考えている時間は静かに待つ
- どうしても難しい時だけヒントをあげる
という距離感がちょうど良いんです。
うまくいかない時の対処法|“辞めどき”と“復習だけの日”を作ろう
学習には波があります。
調子が良い日もあれば、悪い日もあります。
発達が気になる子は、この波が特に大きいので、
「うまくいかない日」の扱い方がとても大事です。
うまくいかない日でも、
「学習を続けること自体」にOKを出してあげるのがポイントです。
今日は難しい…そんな日は“復習だけ日”でOK
RISUの良いところは、
「復習だけの日」でも成立する教材という点。
たとえば、
- 今日は疲れている
- 気分が落ち着かない
- なぜかうまく集中できない
こういう日は、
“復習だけ”に切り替えるだけでOKです。
復習だけでも、
- 成功体験が増える
- 自信が落ちにくい
- 継続の習慣が守られる
というメリットが大きいんですね。
「今日は復習の日にしてみようか」
と提案するだけで、すっと切り替えられるお子さんも多いです。
トラブルを減らす“辞めどきのルール”の作り方
辞めどきを決めておくと、
「まだやる!」や「もう無理!」のトラブルが減ります。
辞めどきとしておすすめなのは、
- 1問できたら終わり
- 5分だけやる
- 今日のステージが終わったらやめる
など、
“明確でわかりやすいルール”にすること。
こうしたルールがあれば、
- 子どもが見通しを持てる
- 無理しないで終われる
- ママも声掛けしやすい
というメリットがあります。
発達特性のある子は、
わかりやすいルールがあると安心して取り組めることが多いです。
まとめ|RISU体験でわかった「発達が気になる子でも伸びる学び方」
ここまで、RISUを実際に体験して見えた
「発達が気になる子が伸びる学び方」についてお伝えしてきました。
ママさんも日々感じていると思いますが、
発達特性のあるお子さんは、
“教え方”や“学び方”がちょっと違うだけで、
伸び方がガラッと変わることがあります。
ただ、決して
「うちの子はできないタイプだから…」
ということではありません。
今回の体験を通してあらためて強く感じたのは、
発達が気になる子は、学びの設計さえ合えばしっかり伸びる
ということ。
そしてRISUは、その“伸びる条件”を自然に満たしてくれる教材でした。
では、どうしてRISUが発達が気になるお子さんに合いやすいのか?
最後に4つのポイントにまとめてお伝えします。
RISUは発達障害の子の学習にマッチする4つの理由とは?
RISUが発達特性のあるお子さんにとって“ちょうど良い教材”だと感じた理由は、次の4つです。
① 成功体験が積み重なる設計になっている
RISUは、とにかく
- 小さく
- こまめに
- 何度も
成功体験が積み重なる構造になっています。
発達が気になる子にとって、
成功体験が続くことは、学びの土台そのもの。
RISUのおかげで、
- 「できた!」が増える
- 自信が育つ
- 前向きな気持ちが生まれる
という“良い流れ”が自然につくられます。
② スモールステップで理解の抜けを防ぎやすい
発達特性のある子は、
急にレベルが上がったり、
説明が飛んだりするとパニックになりやすいです。
RISUはすべてがスモールステップなので、
- わからないまま次へ進む
- 急に難しくなる
といった負担がありません。
この細かいステップがあるだけで、
つまずくポイントがぐっと減り、理解のスピードが安定します。
③ 視覚で理解しやすい工夫がたっぷり
RISUは、数字や図形の概念を
“見てわかる形”に変えてくれます。
- アニメーション
- 図解
- 色分け
- シンプルな説明
これらの視覚的サポートがあるだけで、
抽象的な算数の世界がグッと理解しやすくなります。
特にASD傾向・LD傾向のお子さんには、
この視覚支援が本当に大きな助けになります。
④ 自分のペースで学べる安心感が大きい
発達が気になる子にとって
「自分のペースが守られる」のはとても大事なこと。
RISUでは、
- ゆっくり進んでもOK
- 早く進みたい子もOK
- 戻る・やり直すが自由
- 調子が悪い日は復習だけでOK
という環境が整っているので、無理なく続けやすいんです。
「今日は5分だけ」「1問だけ」もできるので、
ママも子どももストレスをためずに使えます。
以上の4つが、
RISUが発達障害・グレーゾーンの子たちと相性が良い理由です。
そして何より、
RISUを使うことで“学び方の型”が整い、
その子なりのペースで伸びていけるようになります。
もっと詳しい内容や最新キャンペーンは、公式ページで確認できます
RISUについてもっと詳しく知りたい方へ
もし、
- もっと詳しい料金や仕組みが知りたい
- 具体的にどんな内容が学べるの?
- 発達障害の子に本当に合うの?
- メリット・デメリットの両方を知りたい
と思われたら、こちらの解説記事をご覧ださい↓
【RISUは発達障害の子にもおすすめ!自分のペースで学べる算数学習タブレット】
ここでは、今回の体験内容をさらに深掘りして、
RISUの特徴・デメリット・料金・活用のコツなどを
もっと詳しくまとめています。
RISUが「うちの子にも合いそうかも?」
と感じられたママさんは、ぜひチェックしてみてくださいね。







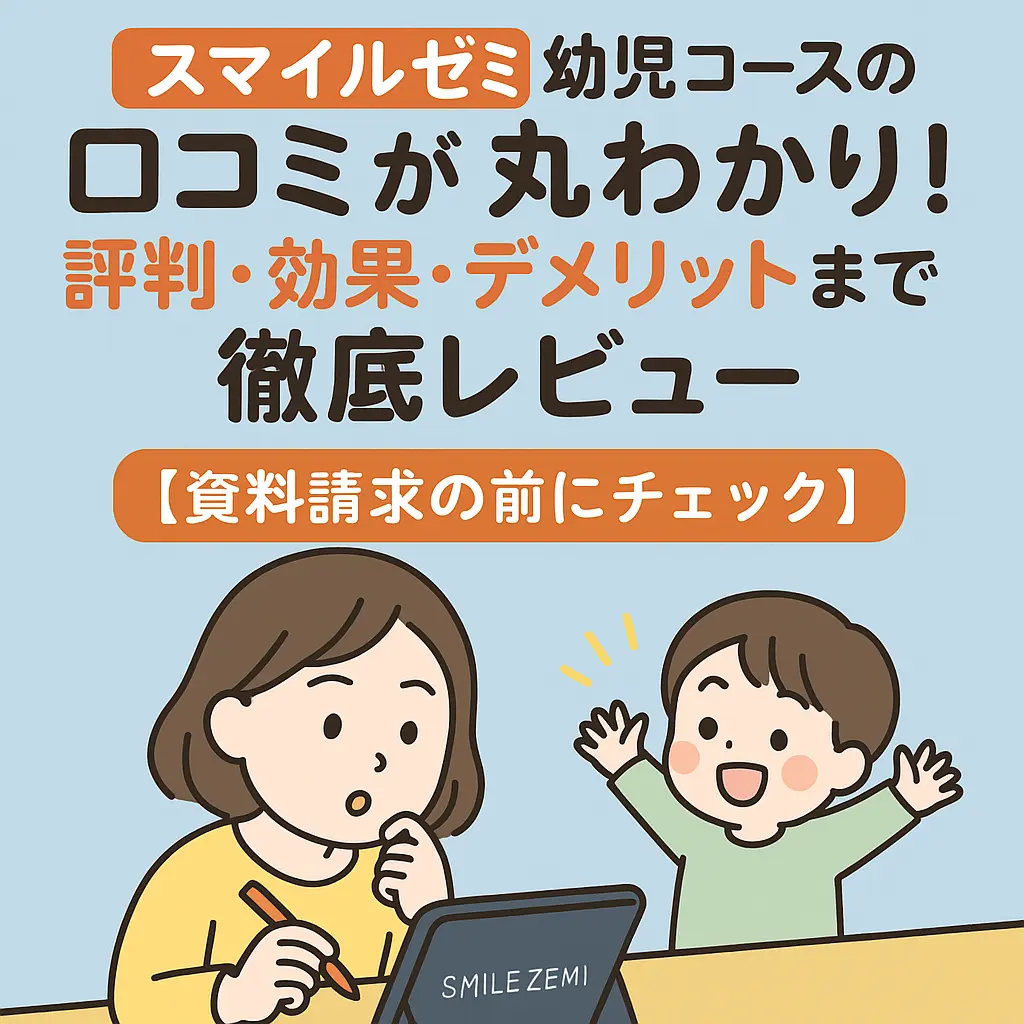



コメント