なぜADHDの子どもは片付けられないの?原因と理解ポイント
子どもが部屋を散らかしたまま遊び続けたり、声をかけてもなかなか片付けを始めなかったりすると、ママとしては「どうして片付けられないの?」とついイライラしてしまいますよね。
でも実は、ADHDの子が片付けられないのには“きちんとした理由”があるんです。性格の問題ではなく、脳の働きや発達特性が関係しています。ここを理解しておくと、ママの気持ちもぐっとラクになります。
ADHDの特性と「片付け苦手」の関係
ADHD(注意欠如・多動症)の子どもは、「注意のコントロール」が難しいという特徴があります。
例えば――
- 興味のあることには集中できるけど、片付けのような単純作業はすぐ飽きてしまう
- 周りの刺激に気を取られやすく、始めても途中で中断してしまう
- どこから手をつければいいのか分からなくなり、結局そのままになる
こうした特性から、片付けは「苦手なこと」の代表例になりやすいのです。
また、片付けは「物を分類する」「順序立てて動く」といったスキルが必要になります。これもADHDの子には少しハードルが高い部分。だからこそ、「苦手だからこそ工夫が必要」なんですね。
「片付けなさい」が響かない子どもの脳の仕組み
ママが「片付けなさい!」と声をかけても、全然動かない…そんな経験、ありますよね。
これは「やりたくないから」ではなく、ADHDの子どもの脳の仕組みが関係しています。
ADHDの子は、報酬や楽しさを感じにくい単純作業に取り組むのがとても苦手です。脳内の「やる気スイッチ」を入れるドーパミンという物質が出にくいため、片付けのような地味な作業ではなかなか行動につながらないのです。
さらに、ママから「早くして」「まだできてないでしょ!」と繰り返し注意されると、
- 「どうせできない…」と自己肯定感が下がる
- 「怒られるからやらなきゃ」になり、片付けがイヤなものとして刷り込まれる
といった悪循環に陥りやすくなります。だからこそ、叱るより“楽しく取り組める工夫”が大事になってきます。
ママが知って安心!できないのは性格ではなく特性
ここで大切なのは、「片付けられないのは子どもの性格ややる気の問題ではない」ということです。
脳の特性上、片付けがスムーズにできないだけ。つまり「できない」ではなく「工夫すればできる」なんです。
例えば、
- ゲーム感覚で取り組む
- 小さな目標に分けて達成感を積み重ねる
- 見える化(チェック表やポイント)でやる気を引き出す
こういった工夫をすることで、ADHDの子でも“片付けはできる!”という成功体験を積み重ねられるようになります。
ママがこの視点を持っていると、叱らずにサポートできるので親子の関係もグッと良くなりますよ。
ADHDの子にゲーム感覚が効く!片付け習慣が身につく理由
ADHDの子どもにとって「片付ける」という行動は、ただの作業ではなく「大きなハードル」になりやすいんです。
でも、そこに“遊び”や“ゲーム”の要素を加えると一気に変わることがあります。
なぜなら、ゲームには「楽しい!」「できた!」という体験が自然に組み込まれていて、子どもの脳が動きやすくなるから。ここでは、ゲーム感覚で片付けを取り入れることで得られる3つの大きな効果を見ていきましょう。
楽しいから続く!ゲームで得られる小さな達成感
「片付けなさい!」と言われるとイヤイヤになっても、「30秒でどこまで片付けられるかな?」とゲームに変わると子どもはスイッチが入ります。
ADHDの子は、達成感を感じることが難しいと言われています。普通の片付けでは「どこが終わりか分からない」ため、やる気が続きません。
でもゲームにすると、
- 目標が分かりやすい(「タイマーが鳴るまで」など)
- 成果が目に見える(「おもちゃ箱が空っぽになった!」など)
- 終わりがはっきりしているので達成感を得やすい
といったメリットがあります。
つまり、「やらされる片付け」から「やりたくなる片付け」に変わるんです。これは子どもにとって大きな成功体験の積み重ねになります。
「叱る片付け」から「褒める片付け」へシフトする効果
ママにとって、毎日の片付けバトルは本当にストレスですよね。つい「早くしなさい!」「なんでまだ散らかってるの!」と叱ってしまうこともあるはず。
でも、叱る片付けは子どものやる気を下げてしまうだけでなく、親子関係にも影響してしまいます。
逆に、ゲームを取り入れることで、自然と「褒める場面」が増えるんです。
例えば、
- 「30秒でブロック全部しまえたね!すごい!」
- 「赤いおもちゃ全部探せたね!やったね!」
と声をかけるチャンスがぐんと増えます。
褒められると子どもの表情も変わり、片付けに対して前向きな気持ちを持てるようになります。
ここで大事なのは、完璧じゃなくても褒めること。ほんの一部だけ片付けられただけでも「できたね」と認めることが、次につながります。
自己肯定感を育てるお片付けゲームの力
ADHDの子は、日常生活の中で「失敗体験」が積み重なりやすいです。
- 片付けができない
- 忘れ物をする
- 注意されることが多い
こうした経験が続くと、どうしても「自分はダメなんだ」と思いやすく、自己肯定感が下がりやすいんです。
そこで役立つのが、お片付けゲーム。
ゲームを通じて「できた!」を積み重ねることで、
- 成功体験が増える
- 「自分にもできるんだ」という気持ちが育つ
- 褒められることで自信がつく
といったポジティブな循環が生まれます。
つまり、片付けはただ部屋をきれいにするだけでなく、子どもの心の土台を育てる大切なチャンスになるんです。
【保存版】ママと一緒にできる!片付けが楽しくなるお片付けゲーム10選
「片付けなさい!」と口で言っても進まないのがADHDの子どもたち。でも、ゲームにしてしまえば自然と体が動くことが多いんです。ここでは、ママと一緒に楽しめる片付けゲームを10個ご紹介します。どれも特別な道具は不要。今日からおうちで実践できますよ。
1. タイマー対決ゲーム|集中力とスピードを養う
「よーい、スタート!」とタイマーを押して、制限時間内にどれだけ片付けられるかを競うシンプルな方法。
短い時間なら集中しやすく、終わりも見えやすいので達成感を味わえます。
- メリット:時間感覚を学べる、集中力アップ
- ポイント:長すぎると疲れてしまうので30秒〜1分程度がおすすめ
「やったー!30秒でブロック全部しまえた!」という達成体験は、子どもの自信につながります。
2. 色分け片付けゲーム|おもちゃ収納がぐんと楽に
「赤いものを集めよう!」「青いものを箱に入れよう!」と、色で分けながら片付ける方法。
ただの整理が“色探しゲーム”に変わるので、子どもも楽しく参加できます。
- メリット:色彩感覚や分類スキルが自然に育つ
- ポイント:収納ボックスを色ごとに分けるとさらに効果的
おもちゃ収納の習慣がつきやすく、ママの後片付けもラクになります。
3. サイコロお片付け|ランダム要素で飽きない習慣化
サイコロを振って、出た目の数だけおもちゃを片付ける遊び。
「3が出たからぬいぐるみを3個箱に入れよう!」と、ランダム性が楽しくて飽きにくいのが魅力です。
- メリット:数の概念を学べる、ゲーム感が強い
- ポイント:大きなサイコロを使うと子どもが喜ぶ
「次はどの数字かな?」とワクワクしながら片付けられるのがポイントです。
4. 音楽ストップ片付け|リズム感と楽しい雰囲気をプラス
音楽を流している間に片付けを進め、音楽が止まったら手を止めるルール。
まるでダンスゲームのように楽しく取り組めます。
- メリット:リズム感が育つ、楽しさが倍増
- ポイント:子どもが好きな曲を使うとやる気UP
「曲が終わる前に急げー!」と盛り上がれるので、遊びの延長で片付けができます。
5. 宝探し片付けゲーム|指示理解と整理力を同時に育てる
「青い車を探して箱に入れて!」など、特定のおもちゃを探して片付ける遊び。
片付け×宝探しになるのでワクワク感が強くなります。
- メリット:指示理解の練習になる、物を探す力が育つ
- ポイント:簡単な指示から始めて、少しずつ難易度を上げる
片付けが「冒険ごっこ」に変わるので、子どもの集中力が高まりやすいです。
6. ポイントカード方式|ご褒美でモチベーションを見える化
片付けができたらスタンプやシールをカードに貼っていく方法。
目に見える形で「できた!」がたまるのがポイントです。
- メリット:継続のモチベーションになる、達成感を実感できる
- ポイント:ご褒美は小さなもの(シールやおやつ)で十分
「あと3回でカードがいっぱいになる!」と子ども自身がワクワクしながら続けられます。
7. 親子リレー片付け|ママと一緒に楽しく役割分担
ママと子どもが交代で片付けをするリレー方式。
「ママの番!次はぼくの番!」とリズムをつけると楽しく取り組めます。
- メリット:役割分担を学べる、親子の一体感が高まる
- ポイント:小さな範囲から始めると成功しやすい
一緒にやることで「片付け=ママに怒られること」から「ママと楽しむこと」に変わります。
8. 写真ミッションゲーム|ビフォーアフターで達成感を実感
片付け前に写真を撮っておき、片付け後と見比べる遊び。
「こんなにきれいになった!」が一目で分かるので、達成感を強く感じられます。
- メリット:視覚的に変化を感じられる、モチベーションUP
- ポイント:子どもと一緒に「ビフォーアフター」を見て褒める
アルバムに残して「片付けがんばった記録」を作るのもおすすめです。
9. ラッキーアイテム片付け|特別感でやる気アップ
「今日のラッキーアイテムは赤いおもちゃ!」と設定し、それを片付けたらボーナスポイントをもらえる方式。
特別感を演出することで、やる気を引き出せます。
- メリット:遊び感が強い、飽きにくい
- ポイント:毎回違うアイテムにすると新鮮さが続く
「今日はどれがラッキーかな?」と子どもが楽しみにする習慣になります。
10. ゴールテープ片付け|達成体験で自信を育てる
片付けが終わったら、ママが紐やタオルでゴールテープを作って「ゴール!」と走り抜けるように演出。
運動会のように盛り上がって終わりを実感できるゲームです。
- メリット:達成感が大きい、成功体験が強く残る
- ポイント:最後は必ず褒めて「やったね!」と声をかける
片付けの終わりに楽しいご褒美があることで、「またやりたい!」という気持ちを育てます。
片付けは“遊び”にすれば自然に習慣化!
ここで紹介した10個のゲームは、どれも特別な準備がいらず、ママと子どもが一緒に楽しめる仕組みばかり。
「片付けは苦手」「いつも叱ってしまう」という親子のストレスを、遊びの力で笑顔に変えることができます。
ゲームを成功させるためのママの工夫ポイント
せっかく楽しい片付けゲームを取り入れても、「子どもがやる気をなくしてしまった…」「続かない…」ということもありますよね。
実は片付けゲームを成功させるには、ママのちょっとした工夫が大きなカギになるんです。ここでは、子どもが楽しく取り組み、長く続けられるようになるためのポイントを3つご紹介します。
叱らず褒める「声かけ」の工夫
ADHDの子どもは、できないことを注意されたり叱られたりする機会が多く、「また怒られた…」という経験が積み重なりやすいんです。だからこそ、片付けでは「叱る」よりも「褒める」を意識することが大切。
例えば――
- おもちゃを1個しまえただけでも「すごいね!」と褒める
- 「片付けできて助かった!」と、ママが気持ちを伝える
このように「できたこと」に目を向けて褒めてあげると、子どもは「片付けは怒られることじゃなく、褒められることなんだ」とポジティブに感じられるようになります。
心理学的にも、肯定的な声かけは子どもの行動を強化する効果があるといわれています。だから、ほんの小さな成功でも大げさなくらいに褒めてあげて大丈夫。ママの一言で、子どものやる気はグンと変わります。
達成基準は低く設定する
ママが「部屋を全部きれいにして!」と期待すると、子どもはハードルの高さに圧倒されてしまいます。特にADHDの子は、やることが多すぎると「どこから手をつけていいか分からない」状態になりやすいんです。
だからこそ、最初は小さなゴールでOK。
- 「この箱の中のおもちゃだけ片付けよう」
- 「今日は机の上だけきれいにしよう」
こんなふうに部分的に目標を決めると、子どもも取り組みやすくなります。
さらに「全部じゃなくてもいい」と分かることで、ママ自身の気持ちもラクになります。続けることが一番大切なので、最初は“片付け成功体験を増やすこと”を優先しましょう。
見える化でやる気を引き出す
ADHDの子どもは、頭の中だけで「できた感覚」を持つのが苦手なことがあります。そこでおすすめなのが「見える化」です。
例えば――
- 片付けができたらスタンプカードにシールを貼る
- チェックシートに「できた!」のマークをつける
- カレンダーにシールを貼って「連続記録」を作る
こうした仕組みを使うと、「やったことが目に見える形で残る」ので、子どもが達成感を実感しやすくなります。
さらに、「あと3回でカードいっぱいになる!」と次のゴールが分かるので、やる気も自然に続きやすくなります。これは大人のダイエットアプリや習慣管理アプリと同じで、視覚化は行動を習慣化する強い味方なんです。
片付けゲームを毎日の習慣にするコツ
「ゲームにしたら片付けてくれたけど、次の日はまた散らかしっぱなし…」
こんな経験はありませんか? ADHDの子どもにとって、片付けは一度できたからといってすぐに習慣になるものではありません。
でも安心してください。ちょっとした工夫で“毎日の習慣”に変えることができるんです。ここでは、そのための具体的な3つのコツをご紹介します。
「寝る前の5分」で習慣化|ルーティン化のポイント
子どもにとって「いつ片付けるのか」が曖昧だと、なかなか行動に移せません。そこで効果的なのが、「寝る前の5分」を片付けタイムに決めること。
「歯を磨いたら寝る」のように、行動と行動をセットにするのが習慣化のコツです。心理学でも「ルーティン化」は行動を定着させる有効な方法とされています。
- 「おやすみ前は片付けの時間」
- 「寝る前におもちゃが箱に入っている」
これを毎日繰り返すことで、子どもは自然と「片付け=寝る前の流れ」と覚えていきます。ママも「いつ片付けさせよう?」と悩まずに済むので気持ちがラクになりますよ。
ADHD特性に合わせた短時間お片付け法
ADHDの子どもは集中が続きにくいため、片付け時間は短く区切ることが鉄則です。長時間やろうとすると、すぐに疲れてしまったり、途中で気が散ってしまったりします。
おすすめは「3分〜5分」という短時間。タイマーをセットして、終わりが見える状態にすると子どもも取り組みやすくなります。
- 「5分だけ一緒にやろう!」
- 「タイマーが鳴ったら終わりね」
このルールを決めると、“やれば終わる”という安心感が子どもに生まれます。結果的に「片付けは短くて楽しいもの」というイメージを持ちやすくなります。
シールやご褒美ノートで続けたくなる仕組み作り
習慣を続けるには、子どもが「またやりたい!」と思える工夫が必要です。そこで効果的なのが「見えるご褒美」です。
- 片付けができたらシールを1枚貼る
- ご褒美ノートにスタンプを押す
- カレンダーに「できたマーク」をつける
こうすることで、子どもは「自分の頑張りが目に見える」ようになり、モチベーションが長続きします。
さらに、「シールが10個たまったら好きなおやつ」など、小さなご褒美と組み合わせると習慣化しやすいです。大人だってポイントが貯まると嬉しいですよね。それと同じで、子どもにとっては“目に見える成果”が次のやる気につながるんです。
片付け以外でも使える!ゲーム感覚で身につく生活習慣
「ゲームにすると子どもが動いてくれる!」と実感したら、ぜひ片付け以外の場面にも応用してみましょう。
ADHDの子どもは、楽しい刺激やワクワク感があると行動につながりやすいという特徴があります。これは片付けだけでなく、日常生活のいろいろな習慣に役立てることができます。
ここでは「朝の支度」「宿題・学習」「お出かけ準備」の3つの場面で使えるゲーム化のアイデアをご紹介します。
着替えをゲーム化して「朝の支度」をスムーズに
朝のバタバタで「早く着替えて!」と何度も声をかけるのは、ママにとって大きなストレス。ADHDの子は特に、気が散りやすく朝の支度に時間がかかりやすいんです。
そこでおすすめなのが「着替えタイムアタックゲーム」。
- タイマーをセットして「3分以内に着替えられるかな?」
- 「靴下とシャツ、どっちが早く着られるか勝負!」
といった形にすると、ただの作業が一気にワクワクに変わります。
さらに、「着替えられたらシール1枚ゲット!」のように小さなご褒美を組み合わせると継続しやすいです。これにより「朝の支度=楽しいチャレンジ」として習慣化でき、ママのイライラもぐっと減ります。
宿題・学習を楽しくするゲーム的工夫
「宿題しなさい!」という言葉ほど、子どものやる気をなくすものはありませんよね。特にADHDの子は「後でやろう」と先延ばしにしてしまう傾向があります。
そんな時は、宿題もゲームにしてしまいましょう。
- 「5分集中してできたらポイント1つ!」
- 「問題を3問解いたら好きなキャラクターシールを貼ろう!」
- 「タイマーが鳴る前に書き終えられるかな?」
など、小さな区切りを作って達成感を得やすくする工夫が効果的です。
また、学習に「ストップウォッチ」や「くじ引き」を取り入れると、ドキドキ感や遊び心が加わり、子どもが嫌がらずに取り組めることも多いです。教育的にも、「楽しい体験を伴う学びは記憶に残りやすい」といわれています。
お出かけ準備をゲームに!忘れ物防止にも効果的
お出かけのたびに「ハンカチ持った?」「水筒忘れてない?」と確認するのは、ママにとって大変。ADHDの子は忘れ物が多い特性があるので、毎回チェックが必要になります。
ここで使えるのが「お出かけ準備ビンゴ」。
- 持ち物リストを絵や写真で用意する
- できたらチェックシールを貼る
- 全部そろったら「ビンゴ!」と達成感を味わえる
これなら、楽しく忘れ物防止ができるんです。
また、「今日は誰が一番早く準備できるか競争!」と家族で取り組むのもおすすめ。準備自体をゲーム化すると、「やらされている」から「自分でできた!」へと意識が変わるので、子どもの自立にもつながります。
ゲーム感覚は片付けだけでなく、
- 朝の着替え → タイマーでスピード感UP
- 宿題・学習 → 小さな達成を積み重ねて集中力UP
- お出かけ準備 → 忘れ物防止&自立心UP
と、日常生活のいろいろな場面で活用できます。
大切なのは「叱らないで楽しむ仕組み」を作ること。ママと子どもが笑顔で取り組めれば、自然と生活習慣が身についていきますよ。
忙しいママも疲れない!片付けをラクにする考え方
「片付けなきゃ…でも時間も気力もない…」そんな日ってありますよね。特にADHDのお子さんを育てていると、日々のサポートでママはとても忙しい。
だからこそ大切なのは、“ママが疲れない片付けの考え方”を持つことなんです。無理に頑張りすぎず、家族みんながラクになれる工夫を取り入れましょう。
ADHD育児は「完璧を目指さない」が正解
SNSや雑誌で見るような「整然としたリビング」や「おしゃれ収納」を目指す必要はありません。
ADHDの子どもは特性上、「片付けを完璧にこなす」のが難しいことも多いからです。
だからこそ、ママのゴールは「完璧」ではなく、「生活できる程度に整っていればOK」にするのが正解。
- おもちゃは箱にポイッと入れるだけ
- 書類はとりあえず一箇所にまとめておく
こうした「ゆるい片付け」でも、十分に生活は回ります。
“散らかってても死なない”くらいの気持ちでいた方が、親子ともにストレスが減りますよ。
ママの心を整えるセルフケアの工夫
片付けだけでなく、育児や家事でいっぱいいっぱいになってしまうのがママの現実。そんな時は、まずママ自身の心を整えることが大切です。
- 1日5分でも自分の好きなことをする(コーヒータイム、音楽を聴くなど)
- 「今日は片付けできなくてもいい」と自分を許す
- 同じ悩みを持つママ友や支援グループで気持ちを共有する
心理学的にも、親の心の余裕は子どもの安定に直結するといわれています。
だから、ママが自分を追い込みすぎずにリラックスできる工夫を持つことが、実は片付けや育児を続ける大きなエネルギー源になるんです。
家族全員を巻き込む!片付けをチームプレイにする方法
「片付けはママの仕事」と思い込んでいませんか? 実は、家族全員でチームプレイにした方がずっとラクなんです。
- 子どもには「おもちゃ係」「ぬいぐるみ係」を任せる
- パパには「棚の整理」「ゴミ出し」などをお願いする
- 「みんなで1曲分だけ片付けよう!」と家族で一斉に動く
このように役割分担をすれば、「ママだけが頑張る状況」を避けられるし、子どもも「自分も家族の一員として役に立てる」と実感できます。
さらに、研究でも「家庭内の家事シェアは親のストレス軽減につながる」と報告されています。片付けを“親子一緒にやる遊び”にしてしまえば、親子のコミュニケーションの時間にもなりますね。
ADHDの子どもの片付け習慣を助けるおすすめ収納グッズ
片付けゲームを続けるうえで、“使いやすい収納グッズ”はとても大切です。ADHDの子どもは「どこに片付けたらいいか分からない」「しまう場所を忘れてしまう」という特性があるため、工夫次第で片付けやすさがぐんと変わります。
ここでは、ママと子どもが一緒に楽しく使える収納グッズを3つご紹介します。どれも特別なものではなく、100均やネット通販で手軽にそろえられるものばかりですよ。
色分けボックス&透明ケースでわかりやすい収納
ADHDの子どもは、「言葉で説明されてもイメージがつかみにくい」ことがあります。そこで役立つのが、色や形で直感的に分かる収納です。
- おもちゃは「赤いボックスにブロック」「青いボックスに車」など色ごとに分ける
- 透明ケースにして「中身が見える」状態にする
こうすることで、「どこに片付ければいいかがひと目で分かる」ようになります。
ママも「それは赤い箱にしまってね」と伝えやすくなるので、声かけがシンプルになり、親子でストレスが減ります。
タイマー&アラームで遊び感覚のお片付け時間管理
ADHDの子は、「時間の感覚をつかむのが苦手」といわれています。そのため、「あとでやるね」と言ったまま片付けが進まないこともよくあります。
そこで活躍するのが、タイマーやアラーム。
- 「5分だけ片付けよう」と時間を区切る
- 音が鳴ったら「ゴール!」と達成感を味わえる
ゲーム感覚で取り入れられるので、子どもが「よし、やってみよう」と気持ちを切り替えやすくなります。
さらに、タイマーを“視覚で見えるタイプ”にすると効果倍増。砂時計や色の変わるタイマーなら、子どもも残り時間を意識しやすくなります。
シール&スタンプカードで継続できる仕組みづくり
「1回はできたけど、続かない…」という悩みに効くのが、シールやスタンプカードです。
子どもは、自分の成果が目に見えるとやる気が続きやすいんです。
- 片付けができたらシールを1枚ペタッ
- 10個たまったら「好きなおやつ」や「パパと公園」など小さなご褒美
- カードがいっぱいになったら「片付け名人バッジ」を授与するのもおすすめ
こうした仕組みを作ると、「片付けは続けると楽しいこと」と子どもが実感できます。心理学でも、行動を習慣化するには「達成を見える化すること」が有効だとされています。
ADHD子育てママのよくあるQ&A
片付けゲームをやってみると、「うまくいった!」という日もあれば、「全然やってくれなかった…」という日もありますよね。
ここでは、ママたちからよく聞かれる質問をまとめて、無理なく続けるためのヒントをご紹介します。
Q1. 片付けゲームに飽きたらどうする?
子どもは新しい遊びにワクワクしますが、同じ方法を続けると飽きやすいのも自然なことです。
そんな時は、
- 「タイマーゲーム」→「音楽ストップゲーム」にチェンジ
- 「シールご褒美」→「写真でビフォーアフター」へ切り替え
- 片付け場所や順番を変えてみる
など、小さなアレンジを加えるだけで新鮮さが戻ります。
さらに、飽きてきたら「今日はどのゲームでやる?」と子ども自身に選ばせるのも効果的。主体的に関わることで、やる気も戻りやすくなります。
Q2. ご褒美がないと片付けなくならない?
「シールやおやつがないとやらないんじゃ…」と心配になるママも多いですが、最初はそれでOKなんです。
心理学でも、新しい習慣を定着させる時期は「外からのご褒美」で動機づけするのが有効だと言われています。
ただし、ずっと大きなご褒美を続ける必要はありません。
- 最初はお菓子やシールなど分かりやすいもの
- 慣れてきたら「ママのハイタッチ」や「できたね!」の声かけにシフト
最終的には、「片付けたら気持ちがいい」「ママに褒めてもらえる」という内側のご褒美へ自然と移行していきます。安心してくださいね。
Q3. きょうだいと一緒に片付けるときの工夫は?
きょうだいがいると、「片付けゲームで競争になってケンカする」という声もよく聞きます。
そんな時は、「対決」ではなく「協力」スタイルがおすすめ。
- 「お兄ちゃんはブロック係、妹はぬいぐるみ係」と役割分担
- 「二人で力を合わせて3分以内にできるかな?」とチーム戦にする
- 片付け後に「二人とも頑張ったね!」と一緒に褒める
こうすると、きょうだいの間に「助け合う楽しさ」が生まれやすくなります。
兄弟間のケンカが減り、親子全体で楽しく片付けを進められますよ。
Q4. 片付けグッズを選ぶときの注意点は?
収納グッズは種類が多すぎて「どれを選べばいいの?」と迷いますよね。ADHDの子どもの場合は、“使いやすさ”が一番大切です。
- 透明ケースや色分けボックス → 中身が見えるので分かりやすい
- ふた付きよりオープン収納 → 「開ける」というひと手間を省ける
- 軽い素材 → 子どもでも扱いやすい
逆に、複雑な収納や細かすぎる仕切りはNG。片付けが難しくなり、かえって散らかりやすくなります。
ポイントは「ママが管理しやすい」よりも「子どもが自分でできる」を優先して選ぶことです。
まとめ|ADHDの子には「叱らず楽しむ片付け」で習慣化!
ADHDの子どもが片付けられないのは、性格の問題でも、怠けているからでもありません。これは脳の特性によるもので、集中力や見通しを持つことが苦手なために起こることです。だからこそ、ママが「なんでできないの?」と責めるのではなく、特性に合った工夫を取り入れることがとても大切なんです。
その一つが、ママと一緒に楽しめる「お片付けゲーム」。
- タイマーを使ったスピード勝負
- シールやスタンプでやる気を引き出す
- 音楽に合わせてダンスしながら片付ける
こうした遊び感覚を取り入れることで、子どもは「やらされている」から「やってみたい!」に気持ちが変わっていきます。ママと一緒に楽しめる工夫こそ、習慣化の近道なんです。
さらに、どんなに小さなことでも「できたね!」と褒めることで、子どもは自信を積み重ねていけるようになります。この小さな成功体験の積み重ねは、片付けだけでなく学校生活や人間関係など、他の場面でも子どもの力になります。
そして忘れてはいけないのは、ママ自身もラクになるということ。片付けを「しなきゃ」ではなく「一緒に楽しむもの」に変えることで、叱る回数も減り、親子で笑顔の時間が増えていきます。
ADHDの子にとって片付けはハードルが高いこと。でも、「叱らず楽しむ片付け」を取り入れることで、少しずつ無理なく習慣化していけます。
大事なのは完璧を目指すことではなく、親子で笑顔になれる片付けの形を見つけること。
今日からぜひ、1日5分の「お片付けゲーム」からスタートしてみませんか?
以上【ADHDで片付けられない子も変わる!ママと楽しく身につくお片付けゲーム10選】でした









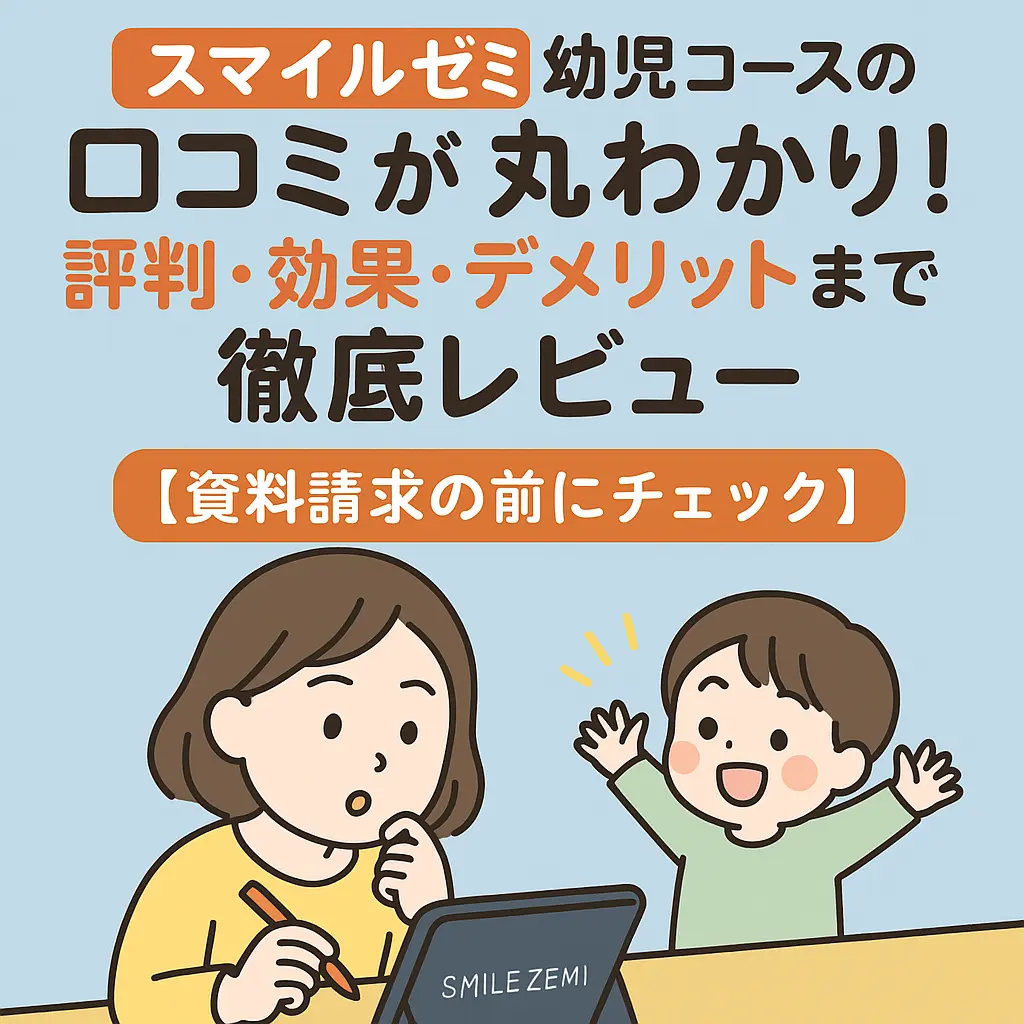

コメント