ADHDの子どもに多い「気分の浮き沈み」とは?情緒不安定の正体を理解しよう
「さっきまで笑ってたのに、急に泣き出した」「怒ったかと思えば、数分後にはケロッとしてる」——こんな“気分のジェットコースター”のような様子に、戸惑った経験はありませんか?
ADHDの子どもには、感情の波が激しくなる傾向があります。これは性格の問題ではなく、脳の仕組みや発達の特性によるものなんです。
つまり、「感情をうまく調整する力」がまだ育ち途中ということ。だからこそ、親が「落ち着いて」と言っても、すぐに切り替えるのが難しいのです。
この章では、そんな“気分の浮き沈み”がなぜ起こるのか、そして放っておくとどうなるのかを、わかりやすく解説していきます。
なぜADHDの子は感情の波が激しいの?脳の特性とストレス要因
ADHDの子どもは、感情をコントロールする脳の働き(前頭前野)がまだ十分に発達していないことがあります。
この部分は、気持ちを落ち着けたり、次の行動を考えたりする“ブレーキ”のような役割を持っています。
つまり、怒りや悲しみなどの強い感情が湧いたとき、
その感情を「ちょっと待って」と止める力が弱い状態なんです。
加えて、ドーパミンという“やる気ホルモン”の分泌バランスも関係しています。
ADHDの子はこのドーパミンの動きが不安定になりやすく、気分のアップダウンにつながることがあるんです。
さらに、ストレスや環境の刺激にも敏感です。
- 音や光などの強い刺激(感覚過敏)
- 頑張っても注意されるなどの“失敗体験”
- スケジュール変更など、予想外の出来事
こうした日常のちょっとした出来事が積み重なることで、心の中がいっぱいになり、イライラしたり落ち込んだりしやすくなります。
「ハイテンション⇄落ち込み」を繰り返す理由と典型パターン
ADHDの子の気分の波には、いくつか典型的なパターンがあります。
たとえば――
- 「朝はハイテンションなのに、夕方にはぐったり」
→ 学校や園での刺激が多く、エネルギーを使い切ってしまう。 - 「楽しい予定の後にどっと落ち込む」
→ 終わってしまった喪失感を強く感じる。 - 「失敗を引きずって気分が回復しにくい」
→ 自己否定感が強く、「また怒られるかも」と考えてしまう。
このような“気分のアップダウン”は、本人もどうしていいかわからないことが多いです。
親から見ると「なんで急に?」と思うかもしれませんが、本人の中では、
ちょっとした刺激や出来事が“引き金”になっていることがほとんどです。
そして、この波は成長とともに少しずつ穏やかになるケースも多いです。
焦らず、「今はそういう時期なんだ」と受け止めてあげることが、安心につながります。
気分の浮き沈みを放置するとどうなる?情緒の不安定さが及ぼす影響
気分の波が激しい状態が続くと、子どもは次第にこう感じ始めます。
「自分でもどうしてこうなるのかわからない」
「怒られてばかりでつらい」
つまり、自己肯定感が下がりやすくなるんです。
「どうせまた失敗する」「自分はダメなんだ」と思い込むようになると、
不安が強くなり、登園・登校しぶりや、対人関係のトラブルにつながることもあります。
また、感情の波が大きい子は、家族の雰囲気にも影響を与えやすいもの。
親も気を使いすぎて疲れてしまうことがありますよね。
でも大丈夫。
気分の浮き沈みは「悪いこと」ではなく、発達の途中にある自然なサインです。
「感情の波をなだらかにする環境づくり」や「落ち着く習慣」を取り入れることで、少しずつ穏やかな毎日を取り戻すことができます。
【専門家が解説】ADHDの気分の浮き沈みの原因は3つの“見えない要素”にある
ADHDの子どもが見せる“気分の波”には、実は目に見えない3つの要素が深く関係しています。
表面上は「わがまま」「気分屋さん」に見えても、
その裏では、脳の特性・感覚の違い・環境から受けるストレスが複雑に絡み合っているんです。
ここでは、「なぜそんなに感情が揺れるのか?」を理解するために、
3つの要素をわかりやすくひもといていきます。
理解が深まると、子どもの反応が「困った行動」ではなく、“助けを求めるサイン”として見えてくるはずです。
① 脳の発達特性による感情コントロールの難しさ
ADHDの子どもは、脳の前頭前野(ぜんとうぜんや)という部分の働き方が少し独特です。
この部分は、「感情を落ち着かせる」「行動をコントロールする」などの“ブレーキ役”を担っています。
でもこのブレーキがうまく効かないと、
「イライラが止まらない」「悲しい気持ちが急にあふれる」といった状態になりやすいのです。
たとえば、
- ちょっとした注意で大泣きしてしまう
- 楽しみにしていた予定が中止になると気持ちが切り替えられない
- 思い通りにいかないと、爆発したように怒る
こうした行動の裏には、「気持ちを整理する力」がまだ発達の途中にあることが関係しています。
大人のように「まあ、いいか」と切り替えるのが難しいんですね。
また、ADHDの子どもは、脳内のドーパミン(やる気を生み出す物質)が少ない傾向があります。
このドーパミンの量や働きのバランスが崩れると、集中力や気分が不安定になりやすくなるんです。
「感情のコントロールが苦手」というのは、決して甘えではありません。
脳の仕組みの“個性”として受け止めることで、子どもへの見方がぐっと優しくなりますよ。
② 感覚過敏・感覚鈍麻がもたらすストレス反応
次に注目したいのが、感覚の感じ方の違いです。
ADHDの子どもの中には、「音・光・におい・肌ざわり」などにとても敏感なタイプ(感覚過敏)や、逆に感じにくいタイプ(感覚鈍麻)の子がいます。
たとえば、
- 掃除機の音や教室のざわめきが“痛いほどうるさい”と感じる
- 服のタグや靴下のゴムが気になって集中できない
- 逆に、寒さやケガに鈍くて周りが気づくまで我慢してしまう
こうした感覚のズレがストレスになり、気分の浮き沈みにつながることがあります。
また、感覚過敏の子どもは、外からの刺激に疲れやすく、
「外では頑張って、家でどっと崩れる」というパターンもよくあります。
園や学校では我慢して過ごしていても、帰宅後に爆発するのは、その反動なんですね。
このように、気分の波の背景には見えない“感覚の負担”が隠れていることが多いです。
だからこそ、「今日は機嫌が悪いな」ではなく、
「もしかして疲れたのかな?」「音がうるさかったのかも」と、環境の要因にも目を向けることが大切です。
③ 周囲の環境ストレスや成功体験の少なさによる影響
そしてもうひとつ見逃せないのが、環境から受けるストレスと“できた体験”の少なさです。
ADHDの子は、集中力が切れやすかったり、忘れ物が多かったりするため、
どうしても「怒られる・注意される」場面が増えがちです。
周りの子がスムーズにできていることを、自分はうまくできない。
そんな経験が続くと、子どもは次第にこう感じてしまいます。
「自分はダメなんだ」
「また怒られるかもしれない」
このような“自己否定感”は、気分の波をさらに不安定にします。
そして、落ち込みや不安が強くなると、挑戦する意欲そのものが減ってしまうのです。
また、家庭や学校などの環境が合わない場合もストレスの原因になります。
- 先生や友達との関係のトラブル
- 集団活動が苦手なのに、休む時間がない
- 生活リズムが乱れて、睡眠不足が続く
こうした環境的なストレスも、気分の浮き沈みを引き起こす大きな要素です。
だからこそ、子どもが「安心して過ごせる環境」や「できた!を感じられる場面」を意識的につくることが大切。
「できた」「認められた」という小さな成功体験が積み重なると、自己肯定感が少しずつ育ち、気分の安定にもつながります。
まとめ:見えない要素を理解すると、子どもの見方が変わる
ADHDの子どもの“気分の波”は、決して性格のせいではありません。
脳の発達特性・感覚の感じ方・環境の影響という3つの要素が、
それぞれ重なり合って、子どもの心を揺らしているのです。
「どうして落ち着けないの?」ではなく、
「どんな要素が重なってつらいのかな?」と考えてみるだけで、
親のまなざしはぐっと優しく、そして支援的になります。
ADHDの子の気分の浮き沈みを落ち着かせる「家庭でできる対処法」
ADHDの子どもは、環境のちょっとした変化や刺激に敏感で、
その日の気分や感情が大きく揺れやすいものです。
けれども、家庭でのちょっとした工夫で、気分の波をゆるやかにすることができます。
ここでは、「無理なく続けられる」をテーマに、
毎日の生活の中でできる3つの実践的な方法を紹介します。
どれもすぐに取り入れられて、親子のストレスがぐっと減るものばかりですよ。
生活リズムを整える“見える化”の工夫|スケジュール表・タイマー活用術
ADHDの子どもは、時間の感覚をつかむのが苦手な傾向があります。
「あと5分で出発だよ」と言われても、頭の中では“あと5分”がどれくらいかピンとこないんです。
そのため、突然「もう行くよ!」と言われると、心の準備ができずにイライラやパニックにつながることも。
そこでおすすめなのが、「生活の見える化」。
つまり、「次に何をするのか」「あとどれくらいで切り替えるのか」を目で見てわかる形にしてあげることです。
たとえば——
- 朝の支度を「起きる→顔を洗う→ごはん→着替え→出発」とイラスト付きで貼る
- タイマーや砂時計を使って「あと○分」を視覚的に伝える
- 「できた!」とシールを貼ることで達成感を感じさせる
このように、見通しが立つと安心でき、次の行動にも移りやすくなります。
特に朝や寝る前など、切り替えが難しい時間帯にこそ効果的です。
また、時間に追われるよりも「流れに乗る」感覚をつかめるようになると、
感情の波も少しずつ穏やかになっていきます。
気持ちを表現できる子に育てる!感情カード&絵日記の使い方
ADHDの子どもは、自分の気持ちをうまく言葉で表現するのが苦手なことがあります。
「怒ってる」「悲しい」「イライラする」と感じていても、
どう言えばいいのか分からず、結果的に泣いたり怒ったりして表現してしまうんですね。
そんなときに役立つのが、「感情カード」や「絵日記」です。
感情カードとは、「うれしい」「かなしい」「くやしい」「こわい」など、
表情のイラストと感情の言葉がセットになったカードのこと。
「今の気持ちはどれ?」と選ぶだけで、子どもは自分の気持ちを“見える形”で整理できるようになります。
また、絵日記のように「今日うれしかったこと」「イヤだったこと」を絵で描くのも効果的。
言葉がまだ苦手な子でも、絵を通して気持ちを伝えられるようになります。
さらに、親子でその絵を見ながら、
「そうだったんだ」「これがイヤだったんだね」と共感を示してあげることが大切です。
「ちゃんと気持ちをわかってもらえた」という安心感が、情緒の安定につながります。
この練習を続けるうちに、子どもは少しずつ「気持ちを言葉にする力」を育てていきます。
その結果、“爆発する前に伝える”スキルが育ち、気分の浮き沈みをやわらげることができるんです。
子どもが安心できる“落ち着くスペース”をつくろう
子どもは、自分の感情が大きく揺れたとき、安心して気持ちをリセットできる場所があると落ち着きやすくなります。
それが、“落ち着くスペース”です。
これは特別な部屋を用意しなくても大丈夫。
リビングの一角やベッドの端など、「ここにいるとホッとする」という場所でOKです。
たとえば——
- 柔らかいクッションや毛布を置く
- 好きなキャラクターのぬいぐるみを置く
- 静かな音楽を流したり、間接照明を使って穏やかな空間にする
このような工夫をするだけで、子どもにとってその場所が「安心のサイン」になります。
気分が高ぶったときに「落ち着く場所に行こう」と促すことで、
自分で気持ちを切り替える練習にもなるんです。
ポイントは、「反省部屋」ではなく「安心スペース」にすること。
「怒られたから行く場所」ではなく、「落ち着くために行く場所」という認識にすることが大切です。
親も「ちょっと休もうか」「ここで一息つこう」と穏やかに声をかけてあげましょう。
“安心できる空間”は、子どもにとって心の安全基地になります。
まとめ:安心・見える化・共感が家庭でできる最強の3ステップ
ADHDの子どもの気分の浮き沈みを落ち着かせるには、
- 生活リズムを見える化して安心感をつくる
- 気持ちを言葉や絵で表現できるようにする
- 安心して気持ちをリセットできる場所を用意する
この3つのステップがとても効果的です。
「うちの子、なかなか落ち着かない…」と焦る気持ちは当然あります。
でも、子どもが安心できる環境と、気持ちを整理する仕組みが整うと、
少しずつ“自分で落ち着く力”が育っていきます。
無理に全部を完璧にやろうとせず、
まずは「見える化」や「安心スペース」など、できそうなところから始めてみましょう。
親子の時間が、今よりちょっと穏やかになりますよ。
ADHDの子に効果的!気分の浮き沈みをやわらげる落ち着く習慣10選
ADHDの子どもは、気分や感情の波がとても大きいことがあります。
でも、毎日の生活の中で少しずつ「落ち着く習慣」を取り入れていくことで、
情緒の安定や自己コントロール力を育てることができます。
ここで紹介する10の習慣は、どれも家庭で簡単に実践できるものばかりです。
子どもに合うものをひとつずつ試しながら、“自分で落ち着ける力”を育てていきましょう。
① 朝の「光・音リズム」で脳を整える|感情コントロールを助ける起床習慣
ADHDの子は、朝の切り替えがとくに苦手です。
寝起きの脳はまだ“オフモード”なので、急な声かけや刺激がストレスになってしまうことも。
そこでおすすめなのが、「光と音のリズム」で自然に目を覚ます方法。
- カーテンを開けて朝の光を取り入れる
- 鳥の声ややさしい音楽を流す
- 目覚ましの音を“ビックリ系”から“リズム系”に変える
光と音の刺激で体内時計がリセットされ、脳の覚醒スイッチがスムーズに入るんです。
この“ゆるやかなスタート”が、1日の感情コントロールを助けてくれます。
② 深呼吸トレーニングで“イライラ”を鎮める|簡単呼吸法と遊びアレンジ
ADHDの子どもは、感情が高ぶると呼吸が浅くなる傾向があります。
呼吸が早くなると、心拍も上がってさらにイライラしやすくなるんですね。
そこで試したいのが、深呼吸のトレーニング。
といっても難しいものではなく、「遊びながら呼吸を整える」ことがポイントです。
たとえば——
- 「風船呼吸」:お腹をふくらませてゆっくり息を吐く
- 「ロウソク消しゲーム」:長く息を吐いてロウソクを消すイメージ
- 「ふう〜と紙飛行機」:息をゆっくり吹いて飛ばす
“5秒吸って、5秒吐く”を意識するだけでも、脳が落ち着きモード(副交感神経)に切り替わります。
親子で一緒にやると、自然に“気持ちのリセット時間”ができますよ。
③ 音楽・リトミックで情緒安定|リズムが心を整える科学的理由
音やリズムは、心の安定にとても効果的。
音楽療法の研究でも、一定のテンポの音は脳の活動を落ち着かせることが分かっています。
リトミック(音楽に合わせて体を動かす活動)は、ADHDの子にもぴったり。
- ゆっくりした音でリラックス
- 速いテンポで体を動かして発散
- 止まる・動くを繰り返して“待つ力(ターンテイキング)”を育てる
音楽と動きがリンクすることで、脳の中の感情・運動・思考のネットワークが整いやすくなります。
親子で楽しく体を動かしながら、自然と感情の波が整っていきます。
④ 感覚あそびでストレス発散|粘土・ビーズ・スライムで落ち着きを取り戻す
ADHDの子は、頭の中が“フル回転”していることが多く、疲れがたまりやすいです。
そんなときには、手を使う感覚あそびがとてもおすすめ。
たとえば、
- 粘土をこねる
- ビーズをつまむ
- スライムをのばす
これらの活動は、「触覚」や「深部感覚(力の入れ具合)」を刺激して気持ちを落ち着かせる効果があります。
「考える」より「感じる」時間をつくることで、ストレスをリセットできます。
感覚あそびは、感情の爆発を防ぐ“リセットボタン”のようなもの。
日課として取り入れると、気分の浮き沈みを予防する習慣になります。
⑤ 「好きなこと時間」を1日10分|気分を安定させる“自己肯定”の習慣
ADHDの子どもは、「注意される」「失敗する」経験が多く、自信をなくしやすい傾向があります。
だからこそ、“好きなことに没頭できる時間”を毎日少しだけ確保することが大切です。
お絵かきでもブロックでも、好きなアニメでもOK。
「自分はこれが得意」「これをしてると落ち着く」と感じられる時間は、心のエネルギーをチャージしてくれます。
この時間を親が「大事にしてくれている」と感じることも、情緒の安定に大きく影響します。
たった10分でも、子どもにとっては“安心の時間”なんです。
⑥ 「できた!」を積み重ねる小さな成功体験づくり|達成感で気持ちを前向きに
ADHDの子は、「頑張っても注意される」「最後までできない」という経験が多く、
「どうせ無理…」と挑戦する前にあきらめてしまうことがあります。
そこで効果的なのが、“小さな成功体験”を積み重ねること。
- 1回で全部できなくても「途中までできたね!」と声をかける
- 小さな課題を分けて「今日はこれだけやろう!」とハードルを下げる
- 終わったらしっかり褒めて、達成感を「見える形」で伝える(シールなど)
ドーパミンが分泌され、「やればできる!」という感覚が増えることで、
気分の浮き沈みが減り、前向きな気持ちが続きやすくなります。
⑦ お風呂時間でリラックス|ぬるめの湯と感覚刺激で副交感神経を活性化
お風呂の時間は、実は“感情のリセットタイム”。
ぬるめのお湯につかることで、副交感神経が働き、気持ちが穏やかになります。
さらに、泡あそびやバスボムなどを使うと、感覚刺激が心地よく感じられ、
感覚統合(感覚を整理する力)のトレーニングにもなります。
「お風呂でリラックスする」という習慣は、
寝る前の情緒安定にもつながる、まさに“1日のリセット儀式”です。
⑧ 香りと照明で心を整える|ADHDの子に合うアロマと照明テクニック
視覚や嗅覚を使ったリラックス法も効果的です。
ADHDの子どもは刺激に敏感なので、“落ち着く香り”と“やさしい光”が大切。
たとえば、
- アロマならオレンジ・ラベンダー・ゼラニウムなど穏やかな香り
- 照明は白ではなく、暖色系(オレンジ系)の間接照明を使う
- 夜は部屋の明るさを徐々に落とし、睡眠リズムを整える
こうした環境調整だけでも、脳が「安心モード」に切り替わり、感情の波がやわらぐことがあります。
⑨ 「気持ちノート」で1日を振り返る|親子で感情整理する夜の習慣
1日の終わりに、子どもと一緒に「気持ちノート」をつけてみましょう。
「今日うれしかったこと」「いやだったこと」を1行でも書いたり、絵で描いたりするだけでOK。
これは、感情を“外に出して整理する”トレーニングになります。
親が一緒に「へぇ〜そんなことが楽しかったんだね」と共感することで、
子どもは「ちゃんと見てもらえた」という安心感を得られます。
気分の波を客観的に振り返る習慣を持つことで、自己理解と感情コントロール力が育ちます。
⑩ 就寝前のスキンシップで安心感UP|“おやすみハグ”で情緒を安定させる
1日の終わりに、親子のスキンシップを取り入れるのもおすすめです。
「おやすみハグ」「手のマッサージ」「背中トントン」など、身体への安心刺激が脳に“落ち着きサイン”を送ります。
スキンシップによって分泌されるオキシトシン(愛情ホルモン)は、
不安や緊張を和らげ、心の安定を助けてくれます。
「今日も一日がんばったね」「大好きだよ」と一言添えるだけで、
子どもの気持ちはぐっと安らぎ、安心して眠れる夜につながります。
まとめ:小さな習慣が“大きな安定”につながる
ADHDの子どもの気分の波は、親が“工夫”で支えられる部分がたくさんあります。
どれかひとつでも続けていくうちに、子どもの「落ち着く力」や「自己調整力」が少しずつ育っていきます。
焦らず、子どものペースで。
今日できる小さな習慣が、明日の笑顔を増やしてくれるはずです。
ADHDの子の感情コントロールを難しくする「NG対応」5つ
ADHDの子どもは、感情の波が大きく、ちょっとした刺激でも気分が変わりやすい特徴があります。
親として「落ち着いてほしい」と思うのは当然ですが、よかれと思ってした対応が、実は気持ちをさらに乱してしまうこともあるんです。
ここでは、ついやってしまいがちなNG対応と、その代わりにどんな声かけをすればよいかをわかりやすく紹介します。
完璧を目指す必要はありません。大切なのは、「気づいたときに修正していく」ことです。
① 「また怒ってるの?」と否定しない——感情を受け止める姿勢が大切
子どもが泣いたり怒ったりしたとき、思わず「また怒ってるの?」「そんなことで泣かないの」と言ってしまうこと、ありませんか?
でもこの言葉、子どもにとっては「自分の気持ちを否定された」ように感じてしまいます。
ADHDの子どもは、感情のブレーキがかかりにくく、気持ちが一気にあふれてしまうことが多いです。
そのときに「怒ってはいけない」「泣いてはいけない」と言われると、
「自分の気持ちはダメなんだ」と感じてしまい、自己肯定感を下げる原因になります。
そんなときは、まず「気持ちを受け止める」ことが第一歩。
たとえば——
「びっくりしたね」
「それはイヤだったね」
「そう感じたんだね」
このように気持ちに名前をつけて共感してあげると、子どもは少しずつ落ち着きを取り戻します。
感情の整理がうまくできるようになるのは、その“受け止めてもらえた経験”の積み重ねからなんです。
② 感情が高ぶっている最中に注意・説得しない
子どもが怒って泣き叫んでいるとき、つい「落ち着きなさい」「そんなことしてもダメでしょ」と言いたくなりますよね。
でも実は、感情がピークのときに言葉で注意しても、脳はまったく聞けない状態になっています。
ADHDの子どもは、感情のスイッチが入ると脳の中で“論理的思考”よりも“感情中枢(扁桃体)”が優先的に働きます。
つまり、「話を聞いて理解する」よりも、「戦うか逃げるか」でいっぱいになるのです。
この状態では、どんなに丁寧に説明しても逆効果。
親の言葉が“責められている”と感じ、さらに反発してしまうことがあります。
そんなときは、まず物理的に距離を取ることが最優先。
静かな場所に移動して、
「落ち着いてから話そうね」
と短く伝えるだけで十分です。
そして、落ち着いたあとに「どうしてイヤだったのか」「次はどうしたらいいか」を一緒に考えていきましょう。
“冷静なときに話す”が、感情コントロールの練習になります。
③ 他の子と比較しない——自己肯定感を守る声かけ法
「○○ちゃんはもうできてるのに」「お兄ちゃんはちゃんと我慢できるよ」
こんな言葉、つい出てしまいがちですよね。
でもこの“比較”が、ADHDの子どもにとっては一番つらいものです。
ADHDの子どもは、自分でも「思ったようにできない」ことをよくわかっています。
だからこそ、他の子と比べられると「自分はダメなんだ」と感じてしまい、気持ちが沈んでしまうのです。
代わりに意識したいのは、“昨日の自分”との比較。
「昨日よりちょっと早く着替えられたね!」
「前より怒らずに待てたね!」
こうした“成長の気づき”を言葉にすることで、
子ども自身が「自分も変われる」と感じられるようになります。
比較ではなく、その子自身のペースを認める声かけが、情緒の安定を支える鍵です。
④ 親自身のイライラを放置しない——親の気持ちも整える
実は、子どもの感情コントロールに最も影響を与えるのは、親の感情の安定です。
ママやパパがイライラしていると、子どもはそれを敏感に察知して、落ち着かなくなります。
「子どものために」と我慢しすぎてしまうと、結局どこかで爆発してしまうこともありますよね。
それは誰にでもあることです。
大切なのは、「自分の気持ちに気づいて、ケアする時間を持つ」こと。
たとえば、
- 一人でコーヒーを飲む時間を作る
- SNSで誰かに共感してもらう
- 信頼できる人に話す
- 深呼吸やストレッチで体をほぐす
たった数分でも、自分をいたわる時間を持つことで、子どもの感情にもより穏やかに向き合えるようになります。
親の心の安定は、子どもの安定とつながっているんです。
⑤ 子どもの“何もしない時間”を焦って奪わない——回復のための静けさ
ADHDの子どもは、外で頑張っている時間がとても多いです。
学校や園で周りに合わせる努力をしている分、家では何もしたくない時間が必要なんです。
でも親としては、「ゲームばかりして」「ぼーっとしてばかりで大丈夫?」と不安になりますよね。
実はその“何もしない時間”こそ、脳と心を回復させるために欠かせない時間なんです。
脳科学的にも、休息中の脳では感情の整理や記憶の統合が行われていることがわかっています。
つまり、ぼーっとしているように見えても、頭の中ではしっかり“整理整頓”が起きているんです。
親ができるのは、「早くやりなさい」と急かすのではなく、
「ゆっくりしていいよ」「疲れたよね」
と安心して休める雰囲気を作ること。
この“静けさ”があるからこそ、次に動く力が生まれます。
まとめ:子どもの心を守るのは「正しさ」より「安心感」
ADHDの子どもにとって、感情の安定は「環境」や「関わり方」に大きく左右されます。
NG対応を避けるというよりも、「安心して気持ちを出せる関係をつくる」ことを意識するのがポイントです。
親も人間です。うまくいかない日があって当然。
でも、「今日は受け止められたな」「ちょっと冷静に待てたな」と思えたら、それで十分。
その小さな積み重ねが、子どもの心を守り、感情コントロール力を育てていくんです。
ママ自身も落ち着く時間を|子どもの情緒安定は親の安心から生まれる
ADHDの子どもを育てていると、毎日が“感情のジェットコースター”のようですよね。
朝の支度でバタバタしたり、癇癪が起きたり、思い通りに進まないことも多くて……気づけばママの方がクタクタ。
でも、そんな日々の中で忘れがちなのが、「ママ自身の心を整える時間」なんです。
実は、ADHDの子どもの情緒の安定には、親の安心感や気持ちの余裕が深く関係していることが、心理学の研究でも分かっています。
「子どものために」と頑張るのは素晴らしいこと。
でも、ずっと頑張り続けると、ママの“こころのガソリン”が切れてしまいます。
その状態では、どんなに正しい声かけをしても、子どもに気持ちは伝わりにくいんです。
ADHDの子は親の感情に影響を受けやすい
ADHDの子どもは、人の感情の変化にとても敏感です。
表情や声のトーン、雰囲気の違いをキャッチして、
「ママが怒ってる」「なんか悲しそう」とすぐに感じ取ります。
特に、感情のコントロールがまだ未熟な子どもほど、
親の感情の揺れを“自分のせい”と感じてしまうことも少なくありません。
たとえば、ママが疲れてため息をついたとき、
子どもは「僕が悪かったのかな?」と思ってしまうことも。
逆に、ママが穏やかに笑っていると、それだけで安心して落ち着くんです。
つまり、ママの表情や雰囲気は、子どもにとって“安心のバロメーター”なんですね。
ママが心を整えることは、子どもの安心を守る“見えない支援”でもあるんです。
「親の安定=子の安定」の連鎖を意識する
子どもの情緒が乱れると、ママの気持ちも揺れやすくなりますよね。
でも、ここで意識したいのが、「親の安定が子の安定をつくる」という連鎖です。
親が穏やかでいると、子どもの脳もその安心感を受け取って落ち着きやすくなる。
このメカニズムは、神経科学的にも“共感神経”や“ミラーニューロン”の働きで説明できます。
つまり、親と子はお互いの感情を“映し合っている”んです。
たとえば、ママが落ち着いた声で話すと、子どもも自然と声のトーンが下がります。
ママが焦らずに待てると、子どもも「大丈夫なんだ」と感じて安心します。
「親が落ち着く → 子どもが落ち着く → また親も安心できる」という良い循環を意識することで、
毎日の感情トラブルも少しずつ減っていきます。
ママのストレスケア例(深呼吸・アロマ・ひとり時間)
とはいえ、「落ち着こう」と頭で分かっていても、
現実的にはイライラや疲れがたまってしまうもの。
だからこそ、ママ自身のストレスケア習慣を持つことが大切です。
ここでは、すぐにできる“3つのセルフケア”を紹介します。
① 深呼吸でリセットする
子どもが癇癪を起こしたとき、まずママが3回ゆっくり深呼吸してみましょう。
「落ち着かなきゃ」と思うより、「息を整える」と考えるとラクです。
深呼吸をすると、自律神経のうち副交感神経が働き、イライラが鎮まりやすくなります。
② アロマでリラックス
香りは脳に直接働きかけて、気分を整えてくれます。
おすすめは、ラベンダー・オレンジ・ゼラニウムなどの穏やかな香り。
ティッシュに1滴たらすだけでもOKです。
「いい香り〜」と感じることで、ママの表情がやわらぎ、子どもも安心します。
③ ひとり時間を“意識して”つくる
1日5分でも10分でも、「ママのための時間」をスケジュールに入れてOKです。
コーヒーをゆっくり飲む、スマホを見ずに空を眺める、短い散歩をする——
それだけで脳の疲れが和らぎ、リセットできます。
ママが安心できる時間を持つことは、「わがまま」ではなく、家族のための“心の充電”です。
安心して笑えるママがいることが、子どもにとって何よりの安心材料になります。
まとめ:ママの安心が、子どもの笑顔をつくる
ADHDの子どもは、ママの感情の変化を敏感に感じ取ります。
だからこそ、ママが“心地よくいられる時間”を持つことが、子どもの情緒安定につながります。
焦らず、頑張りすぎず、「今日はちょっと休もうかな」と思えるくらいがちょうどいい。
ママが深呼吸できると、子どもも自然に落ち着いていきます。
「ママが安心している」——それが子どもにとって、いちばんの安心です。
【まとめ】気分の浮き沈みは成長のサイン|“焦らず、親子で整えていこう”
ADHDの子どもの“気分の波”は、親にとって本当に悩ましいテーマですよね。
機嫌が良かったと思ったら、次の瞬間に怒ったり泣いたり…。
「どうしてこうなるの?」「私の育て方が悪いのかな?」と自分を責めてしまうママも少なくありません。
でも、まず一番に伝えたいのは——
「気分の浮き沈みは、甘えでもわがままでもない」ということ。
ADHDの子どもは、脳の発達や感覚の感じ方に独特の特徴があります。
それによって感情のコントロールが難しくなったり、気持ちの切り替えが追いつかなくなったりするんです。
つまり、これは性格やしつけの問題ではなく、“発達の特性”として理解することが大切なんです。
「今日できなくても、明日はきっと大丈夫」
ADHDの子どもの成長は、“波がありながら進んでいく”のが特徴です。
昨日は泣いてしまったけど、今日はちょっと我慢できた。
今日は怒ったけど、明日は気持ちを言葉で伝えられた。
そうやって少しずつ、感情をコントロールする力が育っていくんです。
大切なのは、「できた」「できなかった」ではなく、
「少しずつ整ってきている」ことに目を向けること。
親が焦ると、子どもも焦ります。
でもママが「まぁ今日はここまででいいか」と肩の力を抜けたとき、
子どもも不思議と安心して穏やかになります。
成長は“ゆっくりでも確実に進んでいる”——そのことを、どうか忘れないでくださいね。
親子で“落ち着く習慣”をひとつずつ積み重ねていこう
気分の波をゼロにすることは難しいけれど、
親子で“整える習慣”を積み重ねていくことはできるんです。
たとえば——
- 朝、太陽の光を浴びる
- 深呼吸でリセットする
- 「できたね」を言葉で伝える
- 一緒にハグして終わる一日
どれも小さなことですが、続けることで子どもの情緒は少しずつ安定していきます。
そして何より、その過程で親子の絆が深まっていくんです。
完璧を目指す必要はありません。
うまくいかない日があっても、それも成長の途中。
大切なのは、「親子で一緒に整えていく」という姿勢です。
おわりに:ママの安心が、子どもの心を育てる
ADHDの子の育児は、たしかに大変です。
でも、ママが子どもを理解しようとするその姿勢こそ、子どもにとって最大の支えです。
今日、少しイライラしても、
明日また「大丈夫」と声をかけられたら、それで十分。
子どもの情緒は、ママの安心感の中で少しずつ整っていきます。
焦らず、比べず、ひとつずつ“落ち着く習慣”を積み重ねていきましょう。
その先には、きっと今より笑顔の多い日々が待っています。
以上【ADHDの子の気分の浮き沈みがひどいときに試したい!家庭でできる落ち着く習慣10選】でした

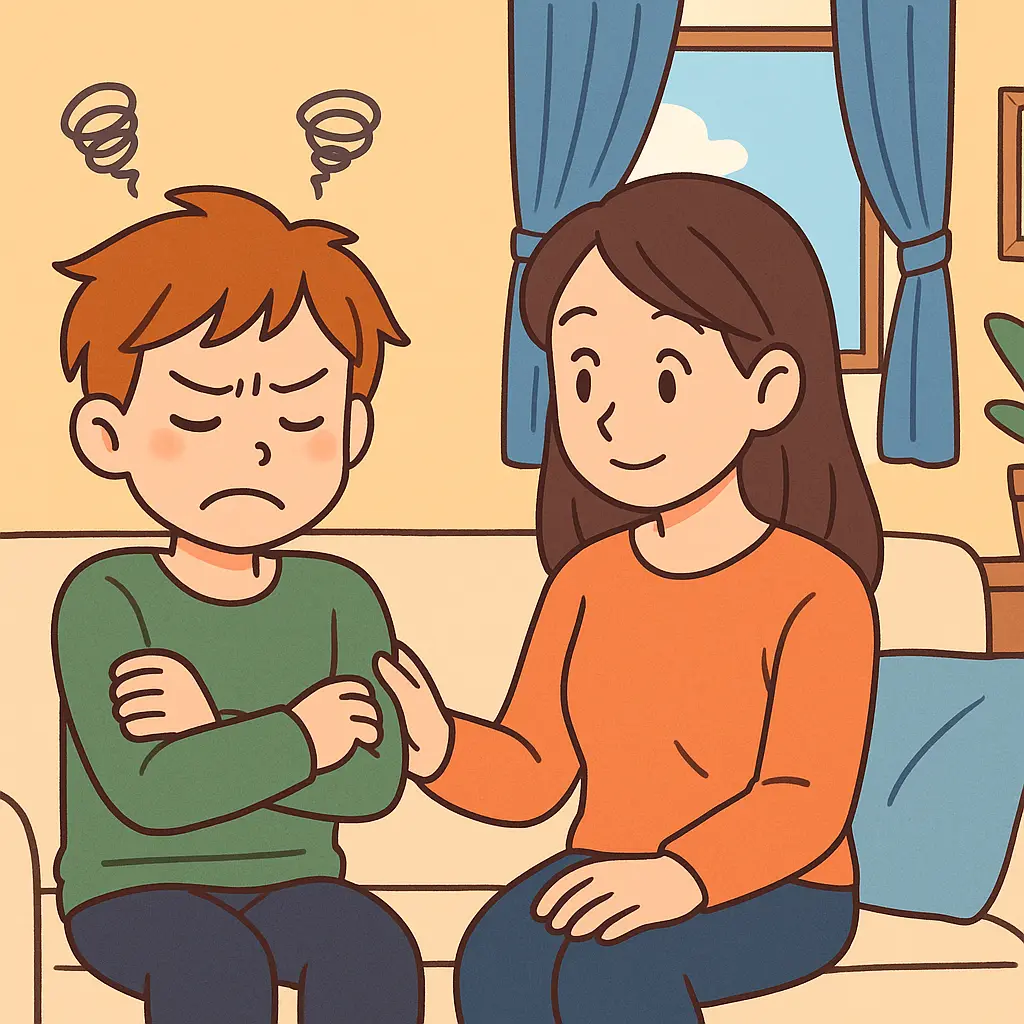









コメント