はじめに~「遊びが広がらない」と悩むママへ──家庭でできる支援アイデア
「うちの子、遊びが広がらないな…」と感じたことはありませんか?
自閉症や発達障害のある子どもには、同じ遊びを繰り返したり、新しい遊びに進みにくかったりする姿がよく見られます。これは特別なことではなく、発達特性から自然に出てくる行動なんです。でも、毎日の子育ての中でそれが続くと、「このままで大丈夫かな?」と心配になるママも多いはずです。
このブログ記事では、そんな悩みを抱えるママに向けて、家庭でできる遊びの工夫や支援アイデアをたっぷり紹介します。ポイントは「難しいことを特別にやる」のではなく、普段の生活の中にちょっとした工夫を取り入れるだけでOKということ。たとえば、ごっこ遊びが苦手な子でも「お買い物ごっこ」や「お店屋さんごっこ」など、身近な場面をヒントにすると遊びの幅が広がりやすくなります。
読むメリットは大きく3つあります。
- 遊びの幅が広がるきっかけがわかる
- 子どもの「できた!」を増やす関わり方がわかる
- 親子の時間がもっと楽しくなる
さらにこの記事では、「なぜ遊びが広がらないのか?」という原因を専門的な視点から解説しつつ、具体的に家庭で試せる方法をわかりやすくまとめています。遊びのアイデアだけでなく、声かけのコツや、ママが無理せず楽しむ工夫まで紹介するので、「明日からちょっとやってみようかな」と思えるはずです。
子育ては一人で抱え込むとつらくなることもありますが、遊びの工夫はママの心をラクにしてくれる力にもなります。この記事を通して、「うちの子らしさ」を大切にしながら、楽しく遊びを広げていくヒントを見つけてもらえたら嬉しいです。
自閉症の子どもに「遊びが広がらない」と感じる理由
「遊びが広がらないな…」と感じるとき、そこには子どもの個性や発達特性が関わっています。ここでは、よく見られる理由を4つの視点から整理してみましょう。理解することで、ママの心が少しラクになり、次の一歩を見つけやすくなります。
発達障害特性からくる遊びの偏り
自閉症や発達障害のある子は、同じ遊びを繰り返すことがとても多いです。たとえば、車を一列に並べる、ブロックを同じ形で積む、同じ絵本を何度も読む…といった行動です。大人から見ると「なぜ同じことばかり?」と不思議に思えるかもしれませんが、これは子どもにとって 安心できる行動パターン なんです。
繰り返し遊びは「予想ができる」「結果がわかっている」という安心感につながります。逆に新しい遊びに挑戦するのは、不安や混乱を招くこともあります。だからこそ、遊びの偏りは“悪いこと”ではなく、その子が安心して過ごすための工夫だと考えることが大切です。
感覚過敏・鈍麻が遊びに与える影響
自閉症の子どもには、感覚がとても敏感だったり、逆に鈍感だったりする特性が見られることがあります。これを「感覚過敏」「感覚鈍麻」と呼びます。
たとえば、光に敏感な子は「キラキラ光るおもちゃ」を嫌がったり、音に敏感な子は「おもちゃの音」や「友達の声」で遊びをやめてしまったりすることがあります。一方で、体の感覚に鈍感な子は、大きな動きを求めてジャンプや走り回る遊びに夢中になることもあります。
つまり、感覚の特性が遊びの幅を制限しているように見えるケースが多いのです。ママとしては「なぜ楽しそうに遊べないの?」と悩むこともありますが、そこには その子なりの感じ方や心地よさ が関わっていることを理解しておきましょう。
コミュニケーションの苦手さと遊びの停滞
遊びは本来、子ども同士のやりとりや想像力によって広がっていきます。でも、自閉症の子どもはことばのやりとりや、相手の気持ちを想像することが苦手な場合が多いんです。
たとえば、「お店屋さんごっこ」をするときに、「いらっしゃいませ」と声をかけるのが難しかったり、「お客さん役」と「店員さん役」を交代する流れが理解しにくかったりします。その結果、遊びが途中で止まってしまったり、1人で完結する遊びばかり選んでしまうことがあります。
これは「想像力」や「社会的なルール」を理解するのに時間がかかるから。決して「できない」わけではなく、ゆっくり練習していけば少しずつ広がっていく部分なんです。
ママが抱えやすい不安と悩み
「遊びが広がらない」姿を見ていると、どうしても 『発達の遅れ?』『将来は大丈夫?』 という不安が頭をよぎりますよね。特に他の子と比べたときに違いが目立つと、心配が大きくなりがちです。
でも、ここで大切なのは「他の子と比べる」ことではなく、「昨日より今日、ちょっとできたこと」を見つけることです。専門家もよく言うのですが、発達障害の子どもは「できるようになるスピード」がゆっくりなだけで、積み重ねていけばちゃんと成長していきます。
不安を抱えるのは自然なこと。でも、ママが子どもの成長を信じて見守ることが、遊びの広がりにつながる一番の支えになります。
遊びを広げるための家庭療育の基本
遊びを広げるといっても、特別な教材や専門的な道具が必要なわけではありません。大切なのは、子どもの「できていること」や「好きなこと」から少しずつ広げていくことです。そして、ママやパパが「やらせなきゃ!」と焦らず、子どものペースを尊重しながら一緒に楽しむこと。さらに、遊びを「生活の一部」として取り入れると、無理なく自然に発達を支援できます。ここではその基本を3つの視点で紹介します。
「できていること」から少しずつ広げる支援
自閉症や発達障害の子どもにとって、新しいことにチャレンジするのは大きなハードルです。だからこそ、すでにできている遊びをベースに広げるのが一番の近道。
たとえば、ブロックを縦に積むのが好きな子なら、「横に並べて道を作ってみよう」と誘ってみる。絵本を繰り返し読むのが好きな子には、「読んだ絵本のキャラクターをブロックで作ってみよう」と少し発展させてみる。こうすることで、子どもは安心感を持ちながら、新しい遊びに自然とチャレンジできます。
専門家もよく「得意なことから広げるのが一番効果的」と言います。子どもの「できている」を大切にしながら、ほんのちょっとの変化を加えることで、遊びはぐんと広がっていきます。
親が先回りせず、子どものペースを尊重する
つい「こうした方が楽しいよ!」「次はこれをやろう!」と先回りして提案したくなること、ありませんか? でも、自閉症の子どもにとっては、急な変化や予想外の展開がストレスになってしまうことがあります。
大事なのは、子どものペースを尊重すること。たとえ同じ遊びを何度も繰り返していても、「この子にとって今は安心できる大事な時間なんだ」と受け止めましょう。
「遊びを続けられること」そのものが力になります。遊びが途切れず続くことで、集中力や「やり切った」という達成感が育っていきます。だからこそ、親が焦らず見守ることが、遊びを無理なく広げる支えになるのです。
生活の中に遊びを取り入れる発達支援
遊びは特別な時間を作らなくても、日常の中にたくさん隠れています。「生活そのものを遊びに変える」発想を持つと、無理なく発達支援ができます。
- 食事:お皿を並べるのを「レストランごっこ」にしてみる。
- 着替え:タイマーを使って「何秒で着替えられるかな?」とゲーム感覚に。
- 外出:道の石をジャンプしながら歩いたり、信号を色あそびに取り入れる。
こうした工夫は特別な準備をしなくてもすぐにできます。しかも、生活の流れに遊びを取り入れることで、「楽しい」=「できた!」の積み重ねが増えていくのです。

【実践例】家庭でできる!遊びが広がるアイデア集
ここからは、実際におうちでできる遊びのアイデアを紹介します。特別な道具や教材はなくても大丈夫。「家にあるもの」や「日常の時間」を工夫するだけで、遊びはぐっと広がります。 しかも、ただ楽しいだけでなく、感覚・ことば・社会性など子どもの発達をサポートする効果もありますよ。
感覚遊び(感覚統合)で発達を促す
自閉症の子どもには、手や体を使った感覚遊びがとても効果的です。粘土をこねたり、水や泡で遊んだりすると、指先や全身の感覚が刺激されて発達を促します。
- 粘土遊び:丸める・ちぎる・型抜きをすることで手先の力を育てる。
- 水遊び:カップに入れ替えたり、色水を混ぜたりして実験気分に。
- 泡遊び:石けんの泡をスプーンですくったり、手で感触を楽しむ。
感覚遊びは「リラックス効果」も大きく、癇癪(かんしゃく)の予防や気持ちの切り替えにも役立ちます。
音楽・リズム遊びで楽しくことば支援
音楽は子どもの心を動かし、ことばの発達をサポートする力があります。リズムや歌を取り入れると、自然に言葉が出やすくなるんです。
- リズム運動:太鼓や手拍子で「トントン」とリズムを真似する。
- 模倣ダンス:親の動きをマネして一緒に体を動かす。
- 歌遊び:「手をたたきましょう」「グーチョキパーでなにつくろう」など簡単な歌を活用。
リズムに合わせると発語が出やすい子も多いので、「楽しい」と思える体験を繰り返すことがことば支援の第一歩になります。
絵本・カード遊びで言葉とコミュニケーションを広げる
絵本やカードは、言葉の理解ややりとりを広げる最強のツールです。
- 絵カード神経衰弱:同じ絵を探す遊びで集中力と語彙をアップ。
- ソーシャルストーリー導入:イラストで「順番を待つ」「挨拶する」など生活場面をわかりやすく伝える。
また、読み聞かせをただするだけでなく、「次はどうなると思う?」と問いかけることで想像力や会話の広がりにもつながります。
ごっこ遊びで社会性を伸ばす
自閉症の子にとって難しいことの一つが「相手とのやりとり」。その練習にぴったりなのがごっこ遊びです。
- お店屋さんごっこ:「いらっしゃいませ」「ありがとう」と言う練習になる。
- 人形遊び:人形を使って「どうしたの?」「元気になったね」と感情表現を学べる。
- 家事ごっこ:お皿を運ぶ、洗濯物をたたむなど生活スキルにも直結。
ごっこ遊びは「社会のルール」を遊びながら学べる貴重な時間。失敗しても遊びだから大丈夫、という安心感があるのも魅力です。
体を使ったダイナミックな遊びで発達支援
じっとしているより、体を思いっきり動かす方が安心できる子もいます。そんな子にはダイナミックな遊びが効果的です。
- トンネル遊び:クッションや段ボールでトンネルを作ってくぐる。
- 公園遊びの工夫:すべり台やブランコを「順番」「交代」などのルール学習につなげる。
大きな動きをすることで、体のバランス感覚や空間認識力が育つだけでなく、ストレス発散にもなります。
遊びを長続きさせるための工夫
「すぐに飽きてしまう」「途中でやめちゃう」という悩みは多いですよね。そこで役立つのが、タイマーや「見通しの提示」です。
- タイマー:「あと3分で終わりね」と知らせて区切りをつける。
- 見通し提示:絵カードやホワイトボードで「次にやること」を視覚的に示す。
この工夫で、子どもは「あとどれくらい?」がわかりやすくなり、集中が続いて遊びをやり切れる成功体験につながります。
自閉症の子どもの遊びを広げる声かけのコツ
子どもの遊びを広げるときに大切なのは、どんな声をかけるかです。声かけ次第で、子どもが「もっとやりたい!」と感じることもあれば、逆に「もうやめたい」となってしまうこともあります。ここでは、日常で使いやすい3つの声かけの工夫を紹介します。
興味に合わせた声かけで遊びを引き出す
子どもが大好きなものや夢中になっている遊びに合わせて声をかけると、遊びがぐっと広がりやすくなります。
たとえば、車が好きな子に「赤い車と青い車、どっちが速いかな?」と聞いてみる。ブロックを積むのが好きな子には「このブロックのおうちに誰を入れてあげようか?」と提案する。
子どもの関心を出発点にすることで、遊びは自然と膨らんでいきます。専門家も「子どもの興味をベースにすることが一番の発達支援」とよく言います。無理に違うことをやらせるのではなく、好きなことを広げてあげるのがポイントです。
肯定的な言葉で遊びを広げる関わり方
「すごいね!」「できたね!」という肯定的な言葉は、子どものやる気を引き出す魔法のスイッチです。
例えば、積み木を3個積めたときに「もっと高く積んで!」と言うのではなく、「3個積めたね!すごいね!」とまずはできたことをしっかり認める。すると子どもは「もっとやってみようかな」と自分からチャレンジしやすくなります。
大事なのは、「やらせるための声かけ」ではなく「楽しさを一緒に感じる声かけ」です。ママ自身も「いいね!」と笑顔で伝えることで、遊びはより前向きに広がっていきます。
「ちょい足し」で新しい遊びを自然に導入する
自閉症の子は、新しい遊びにいきなり誘うと「いや!」となってしまうこともあります。そこでおすすめなのが、今の遊びに少しだけ新しい要素を加える「ちょい足し」です。
たとえば、ブロック遊びをしているときに「ブロックの道にトンネルを作ってみようか」と少しだけプラスする。お絵描きをしているときに「この絵にシールを貼って飾ってみよう」とアレンジを加える。
このように、子どもが安心できる遊びに小さな変化を加えると、抵抗感なく新しい体験を楽しめるんです。ちょい足しは遊びを広げるだけでなく、「柔軟性」を育てる練習にもなります。
遊びが広がらない時によくある悩みと対策
「どうしてすぐやめちゃうの?」「また同じ遊び?」と悩むこと、ありますよね。自閉症や発達障害の子どもは、遊びに特徴が出やすいので、ママが戸惑うのも当然です。ここでは、よくある4つの悩みと、実際にできる対策をまとめてみました。
すぐに遊びをやめてしまう → 短時間遊びで成功体験を積む
「せっかく遊びを始めたのに、すぐにやめてしまう…」これは多くのママが経験する悩みです。
でも実は、短時間でも「遊べた」という成功体験を積むことがとても大事なんです。
最初は1分でもOK。「ブロックを3つ積んで終わり」「絵を1枚描いておしまい」でも十分。短い時間で「できた!」を繰り返すと、遊びを続ける力が少しずつついてきます。専門家も「小さな成功を積み重ねることが、継続の一番の近道」とよく言います。
同じ遊びばかり → 繰り返しの中に変化を入れる工夫
毎日同じ遊びばかりだと「またか…」と感じることもありますよね。でも、同じ遊びを繰り返すのは子どもにとって安心できることなんです。
そこでおすすめなのが、繰り返しにちょっとした変化を加える工夫。たとえば、ブロックを並べる遊びなら「今日は色ごとに分けてみよう」、絵本なら「ママが途中を止めて、子どもに続きを言ってもらう」といった具合です。
同じ遊びでも変化を入れると、子どもは安心しながら新しい挑戦に一歩踏み出せるようになります。
友達と遊びが続かない → 並行遊びから協同遊びへ
「お友達と一緒に遊べない」「すぐケンカになる」…これもよくある悩みです。
自閉症の子どもは、相手に合わせることや役割を交代することが難しいため、遊びが長続きしにくいんです。
ここで効果的なのが、並行遊び(同じ場所で同じ遊びをするけれど別々に行う遊び)から始めること。たとえば、同じテーブルで別々にブロックを作るだけでも「一緒にいる」経験になります。そこから「一つ交換してみよう」「一緒に道をつなげてみよう」と発展させていくと、自然に協同遊びに広がっていきます。
大事なのは、無理に「仲良く一緒に!」を求めないこと。段階を踏むことで、遊びの世界はちゃんと広がっていきます。
ママの疲れやストレス → 一緒に楽しめる遊びを選ぶ
忘れがちですが、ママ自身の疲れやストレスも大きな問題です。子どもの遊びに付き合ってばかりだと、どうしても「またか…」と疲れてしまいますよね。
そんな時は、ママも一緒に楽しめる遊びを選ぶことが大切です。音楽が好きなら一緒に歌う、体を動かしたいなら公園で走る、手作業が好きなら工作をする。ママが楽しいと、自然と子どもも笑顔になりやすいんです。
専門家も「遊びは親子が一緒に楽しむことが第一」とよく言います。ママの気持ちをラクにすることが、結果的に子どもの成長にもつながります。
遊びを発達につなげる家庭での工夫
遊びはただ楽しいだけでなく、子どもの成長をぐんと引き出す力があります。特に自閉症や発達障害のある子の場合、「遊び方=発達支援」になることが多いんです。ここでは、家庭で取り入れやすい3つの工夫を紹介します。
遊びの記録をつけて発達の成長を見える化
「この子、本当に成長してるのかな?」と不安になること、ありませんか? そんな時に役立つのが、遊びの記録を残すことです。
メモ帳やスマホで「今日は積み木を5個積めた」「今日は10分間絵本に集中できた」といった小さな記録をつけてみましょう。写真や動画でもOKです。あとで振り返ると、昨日より今日、先月より今月と少しずつ成長している姿が見えてきます。
専門家も「見える化することが保護者の安心につながり、次の支援のヒントになる」とよく言います。遊びの記録は、ママの心の支えにもなる大事なツールです。
療育や専門家と連携して遊びをサポート
家庭でできる工夫も大切ですが、専門家の視点を取り入れるとさらに安心です。療育施設や発達支援センターでは、子ども一人ひとりの特性に合わせた遊びや関わり方を提案してくれます。
「同じ遊びばかりで困っている」「集中が続かない」など、家庭での悩みを伝えるだけでも、専門家から新しいアイデアをもらえることがあります。また、家庭と療育で遊びの方法を共有すると、子どもが一貫した環境で安心して取り組めるというメリットも。
ママ一人で抱え込むのではなく、「プロに相談しながら一緒に育てていく」という視点を持つと、気持ちがラクになります。
ママのリフレッシュが子どもの成長を支える理由
忘れてはいけないのが、ママ自身の心と体の元気です。
子どもの遊びにずっと付き合っていると疲れたり、ストレスがたまったりしますよね。でも実は、ママのリフレッシュが子どもの成長に直結しているんです。
ママがリフレッシュして笑顔でいられると、子どもも安心して遊びに集中できます。逆にママが疲れてイライラしていると、子どもにもその空気が伝わってしまうんです。
リフレッシュの方法は人それぞれ。好きな音楽を聴く、友達とおしゃべりする、少しだけ一人の時間を持つ…どんな形でもいいので、ママが「楽しい」と思える時間を大切にすることが結果的に子どもの成長を支える力になります。
まとめ~一番大切なのは「親子で楽しく遊ぶこと」
自閉症や発達障害のある子どもは、どうしても「遊びが広がらない」ことが多いです。同じ遊びを繰り返したり、新しい遊びに入りにくかったりするのは、その子の特性による自然な姿でもあります。だから「どうしてうちの子だけ…」と悩みすぎる必要はありません。
ただし、ママやパパができるちょっとした工夫があると、遊びは自然に広がりやすくなり、発達のサポートにもつながります。例えば、子どもの好きな遊びに「ちょい足し」をしてみる、生活の中で遊び要素を取り入れる、肯定的な言葉をかけて自信を育てる…どれも特別な準備はいりません。
そして忘れてはいけないのは、一番大切なのは「親子で楽しく遊ぶこと」ということ。遊びの広がりや発達のスピードには個人差がありますが、親子で笑顔になれる時間こそが、子どもの心を育てる大切な栄養になります。
専門家も「発達支援は家庭の温かい関わりとセットで行うことが大切」と言っています。つまり、難しいことを完璧にこなす必要はなく、日常の中で楽しい瞬間を一緒に過ごすこと自体が支援になるのです。
ママが「今日はちょっと遊びが広がったな」「一緒に笑えたな」と思えたら、それが十分な成長の一歩。無理をせず、できることから少しずつ取り入れていきましょう。
以上【自閉症の子どもの遊びが広がらない時に役立つ!発達を伸ばす家庭療育アイデア集】でした

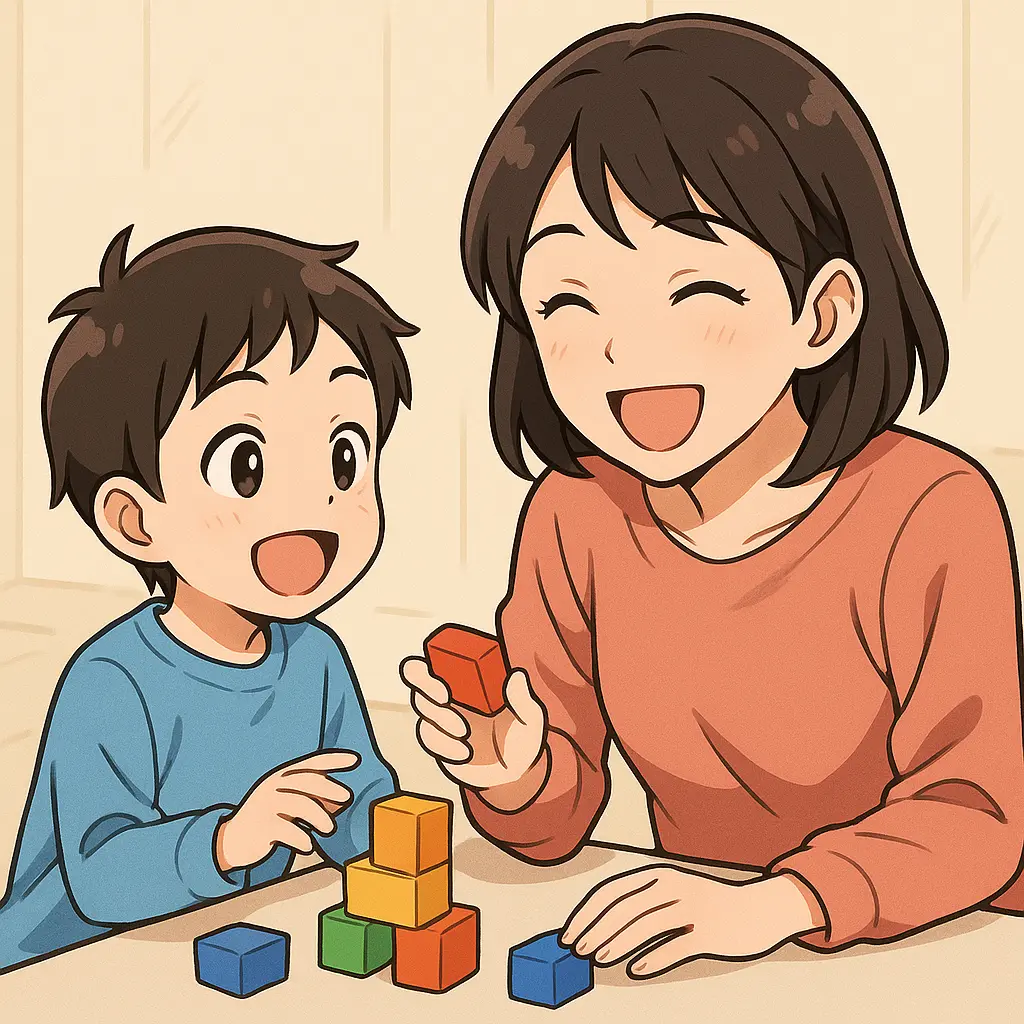









コメント