アスペルガー症候群のこだわり行動とは?
アスペルガー症候群のあるお子さんを育てていると、「どうしてここまで同じことにこだわるんだろう?」と感じる場面、ありますよね。
たとえば「同じ服しか着たがらない」「食べ物の形や色が気になる」「順番が変わると泣いてしまう」など。
これは単なる“わがまま”ではなく、アスペルガー症候群の特性として自然に表れる行動なんです。
こだわり行動はママにとって「困ったな」と思うことも多いですが、見方を変えると子どもの安心感を守る大事な仕組みにもなっています。ここから、少しずつ具体的に見ていきましょう。
アスペルガー症候群の基本特徴と子育てで見られる傾向
アスペルガー症候群のお子さんは、コミュニケーションや人との関わり方に特徴があったり、興味や行動が偏りやすい傾向があります。
子育ての中ではこんなシーンがよく見られます:
- 毎日同じ遊びを繰り返して楽しむ
- 特定のキャラクターや数字、電車などに強い興味を示す
- 規則や手順が変わると混乱してパニックになる
これらは脳の情報処理の仕方が一般的な子どもとちょっと違うから。子ども自身は「安心できるパターン」に従って動いているんですね。
こだわり行動が生まれる原因|安心・不安・感覚過敏との関係
こだわり行動にはいくつか背景があります。
- 安心感を得るため
知っていること・決まったやり方は、子どもにとって安心できる「お守り」のようなもの。大人でもお気に入りのカフェやルーティンがあると落ち着きますよね。 - 不安を減らすため
初めての状況や予想外の変化は、とても大きなストレスに感じられることがあります。その不安を打ち消すために「自分の決まりごと」を守ろうとします。 - 感覚過敏との関係
光や音、肌ざわりなどが強く気になる子も多いです。例えば「タグがチクチクする服は着られない」「白ごはんに混じる黒い粒が気になる」など。これは感覚がとても敏感だからこだわりにつながることもあります。
このように、こだわりは単なる「頑固さ」ではなく、子どもなりの工夫や自己防衛なんです。
こだわり=悪いことじゃない!強みに変わる可能性も
「こだわり」と聞くと、ネガティブに感じてしまうかもしれませんが、実は強みになることもたくさんあります。
- 好きなものへの集中力がすごい → 将来の得意分野につながる
- 規則や順番にこだわる → コツコツ努力できる力になる
- 細かい部分に気づける → 大人になってから専門職で役立つ
つまり、こだわりは子どもの個性のひとつなんです。ママにとっては大変なこともあるけれど、「この子の安心のため」「この子の強みに変わるかも」と考えると、気持ちが少し軽くなることもありますよ。

【実例集】アスペルガー症候群のこだわり行動例
「うちの子だけ?」と思ってしまうような行動も、実はアスペルガー症候群の特性としてよくあるパターンです。ここでは年齢ごとの特徴や、家庭でよく見られるシーンを具体的に紹介します。読んでみると「あ、これってうちの子にもある!」と安心できるかもしれません。
幼児期によく見られるこだわり行動とエピソード
幼児期(3〜6歳ごろ)は、こだわり行動が特に目立ちやすい時期です。
- 同じ洋服しか着たがらない
たとえば「この赤いTシャツじゃないとイヤ!」と泣き出す。洗濯中だと大騒ぎになることも。 - 決まった道順でしか歩けない
公園に行くときに、1本違う道を通っただけで「違う!戻る!」とパニックに。 - おもちゃの並べ方に強いこだわり
車のおもちゃを色順に並べて満足。それを兄弟が崩してしまうと大泣き…。
こうした行動は、子どもなりに世界を安心して理解するためのルールなんです。ママからすると「面倒だな」と思う瞬間も多いですが、背景には安心を得たい気持ちが隠れています。
小学生の生活・学校場面でのこだわり行動例
小学校に入ると、生活の場が家庭から学校へと広がります。その分、こだわりも勉強や人間関係に影響しやすくなるんです。
- 授業中の筆箱の中身や並べ方に強いこだわり
消しゴムや鉛筆の位置がズレると集中できなくなる。 - 予定変更への強い抵抗
体育が雨で中止になると「今日は体育の気分だったのに!」と混乱して落ち着かない。 - 友達との遊びでルールに厳格
鬼ごっこでルールを少し変えただけで「それは違う!」と怒ってしまう。
学校生活では「柔軟性」が求められる場面が多いため、こだわりが原因でトラブルになりやすいんですね。
中高生以降のこだわり行動と成長に伴う変化
思春期以降になると、こだわりの内容がより専門的・具体的になっていくことがあります。
- 趣味や研究への極端な集中
電車やゲーム、歴史など特定のテーマを深く調べ続け、周囲が驚くほど知識を蓄える。 - 時間管理やマイルールへの強いこだわり
「必ず夜10時に寝る」「毎朝同じルーティンで準備する」など。 - 人間関係での誤解
相手のちょっとした発言にこだわりすぎて「嫌われた」と思い込むケースも。
中高生になると、こだわりが“強み”に変わりやすい一方で、対人関係での課題も出やすいのが特徴です。ここで大事なのは「否定するのではなく、適度にコントロールできるように支える」こと。
食事・睡眠・遊びなど家庭で頻発するこだわり例
家庭の中でも、こだわりは日常のあちこちに顔を出します。
- 食事のこだわり
「カレーはこのお皿じゃないと食べない」「白ごはんに黒い粒(雑穀)が混ざるのはNG」など。偏食にもつながりやすいですね。 - 睡眠のこだわり
「同じぬいぐるみを抱っこしないと眠れない」「カーテンは完全に閉めてほしい」など。寝る前の“儀式”が必要なことも。 - 遊びのこだわり
ブロックやカードを毎回同じ並べ方にする、同じ動画を何十回も繰り返し見るなど。
これらは家庭で毎日のように起こるため、ママのストレスにつながりやすい部分でもあります。ただし同時に、子どもの安心や集中力の源になっているので、「全部やめさせなきゃ」と思う必要はありません。
アスペルガー児育児でママが直面する困りごと
アスペルガー症候群のお子さんを育てていると、毎日の生活の中で「なんでこんなにこだわるの?」「どうして柔軟にできないの?」と悩むことも多いですよね。
もちろん、こだわりには良い面もありますが、強すぎるこだわりがトラブルやストレスにつながることもあるのが現実です。ここではママが直面しやすい困りごとを整理しながら、どう対応すればいいか考えていきましょう。
強すぎるこだわりで起きるトラブルと日常生活への影響
こだわりが強すぎると、日常生活にいろいろな影響が出てきます。
- 朝の支度が進まない
「この靴下じゃなきゃダメ!」と選ぶのに時間がかかって、保育園や学校に遅刻しそうになる。 - 外出がスムーズにいかない
公園へ行く道を必ず同じ順番で歩かないと泣いてしまう。ママとしては「急いでるのに!」と焦ってしまいますよね。 - 友達との関係にトラブル
遊びのルールを守らない子がいると怒ってしまい、「わがまま」と誤解されることも。
こうした日常の場面で、ママが疲れてしまうことも少なくありません。こだわりが強い=悪いことではないのですが、生活に支障が出ると「困りごと」として対応が必要になってきます。
放置NG!専門相談が必要なサインとは?
こだわり行動はどの子にもありますが、「日常生活がまわらないレベル」になっているときは注意が必要です。
例えばこんなサインは要チェックです:
- パニックや癇癪(かんしゃく)が毎日のように起きている
- 学校や園に通うのが難しくなっている
- 食事や睡眠など健康に関わる部分に大きな影響が出ている
- ママや家族が「もう限界…」と感じている
こうした状況を放っておくと、ママも子どももストレスがたまり、親子関係がギクシャクしてしまうこともあります。
「これってうちだけかな?」と悩むよりも、早めに専門機関へ相談することが解決の第一歩になります。
どこに相談すればいい?発達支援センター・専門機関の活用法
「相談が必要かも」と思ったとき、どこに行けばいいか迷うママも多いですよね。実は、身近に使えるサポートは意外とたくさんあります。
- 自治体の発達支援センター
子どもの発達に関する相談を受けてくれる窓口。発達検査や支援プランの提案をしてくれる場合もあります。 - 児童発達支援や放課後等デイサービス
専門スタッフと一緒に「こだわりへの対応」や「コミュニケーション練習」ができる場。 - 小児科・児童精神科
医学的な診断や必要に応じた治療、支援先の紹介をしてもらえる場所です。 - 学校・園の先生やスクールカウンセラー
学校生活で困りごとがあるときは、担任や支援員に相談することで連携した支援につながります。
ポイントは、「一人で抱え込まないこと」。
ママがちょっとでも「大変だな」と思ったときに相談できる先を知っておくだけで、気持ちがずっとラクになります。
毎日の育児がラクになる!アスペルガー対応方法
アスペルガー症候群のお子さんとの暮らしは、こだわりや感覚の特性があるぶん、大変なことも多いですよね。
でも、ちょっとした工夫を取り入れるだけで、ママの負担を減らしながら子どもも安心できる環境をつくることができます。ここでは、毎日をラクにする具体的な対応アイデアをご紹介します。
見通しを持たせるスケジュール管理と工夫
アスペルガーのお子さんは、「先が読めないこと」に強い不安を感じやすいです。予定の変更や突然の出来事にパニックになってしまうこともあります。
そこで役立つのが、スケジュールを“見える化”すること。
- 朝の支度を絵カードや写真で並べる
- ホワイトボードに1日の予定を書き出す
- タイマーを使って「あと5分でおしまい」と伝える
これだけで子どもは「何をするのか」がわかって安心できますし、ママも声かけがスムーズになります。「見通しがあると安心する」ことは、育児をラクにする大事なポイントです。
選択肢を与えて自発性を育む声かけ術
「こっちにしなさい!」と決めつけられると、こだわりの強い子は反発してしまいがち。そんなときは、選択肢を与える声かけが効果的です。
例:
- 「赤い服と青い服、どっちにする?」
- 「先に宿題やる?それともごはんのあと?」
こうやって自分で選べる余地を残すと、子どもは安心して動きやすくなるんです。自発性を育むことにもつながりますし、ママにとっても「指示しても聞いてくれない!」というストレスが減ります。
感覚過敏への対応アイデア|イヤーマフ・感覚統合あそび
アスペルガー症候群の子には、音や光、肌ざわりに敏感な子が多いです。これは「わがまま」ではなく、感覚が普通よりも強く入ってくるためです。
対応の工夫としては:
- イヤーマフやノイズキャンセリングヘッドホンで音をやわらげる
- 肌ざわりが気になる服は、タグを切ったり素材を工夫する
- ブランコやトランポリンなどの感覚統合あそびで体を動かし、バランス感覚を整える
こうした工夫で、子どもが過ごしやすくなり、外出や集団生活がラクになるケースも多いです。
興味や得意分野を強みに変える育て方
アスペルガーのお子さんは、特定のものにものすごい集中力を発揮することがあります。電車・昆虫・数字・ゲーム…とにかく深く掘り下げるんです。
ママとしては「こだわりすぎて心配」と思うこともありますが、この集中力は大きな強み。
- 電車好き → 図鑑や社会科の勉強につなげる
- 数字好き → 算数やパズルに応用する
- 絵が得意 → 表現力や創作活動につなげる
「こだわり=弱み」ではなく、「こだわり=才能のタネ」と考えて伸ばしてあげると、子どもも自己肯定感が高まります。
兄弟・家族で取り組む「こだわり対応ルール」づくり
こだわり行動は、兄弟や家族との関係にも影響しますよね。兄弟がブロックの並べ方を崩して大げんか…なんて場面、よくあります。
そんなときは、家族みんなで「こだわり対応ルール」を決めるのがおすすめです。
- 「このおもちゃは本人専用」
- 「一度崩したら“もう一回だけ直す”で終わり」
- 「食事中は〇〇くんの席を変えない」
こうしたルールを共有すると、兄弟も「守ってあげよう」という気持ちになり、家族全体がラクになります。ママ一人で抱え込まない仕組みをつくることが大切です。
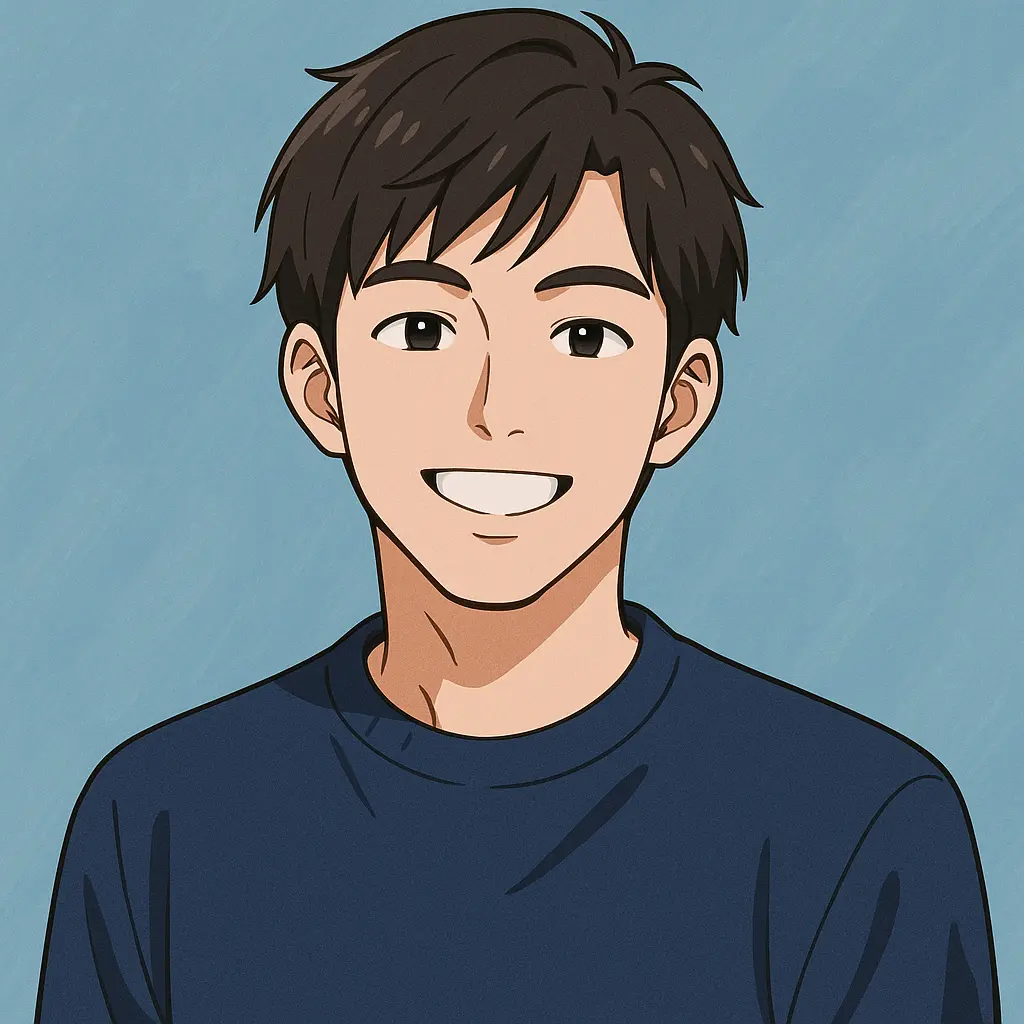
【体験談あり】アスペルガー症候群のこだわり対応に成功したママの声
「うちの子だけ?」と思っていたこだわりも、工夫や周囲のサポートで少しずつラクになったママたちがいます。ここでは、実際の体験談をもとにしたエピソードを紹介します。同じように悩んでいるママの背中を押すヒントになれば嬉しいです。
幼児期の「同じ食器しか使えない」こだわりの克服体験
あるママは、幼児期の息子さんが「このお皿じゃないと絶対にごはんを食べない!」という強いこだわりに悩んでいました。毎回その食器を洗って使うのは大変で、外出先では食事が大混乱…。
でも、少しずつ工夫を重ねたそうです。
- まずは「同じ色のお皿」からチャレンジ
- 慣れてきたら「模様は違うけど形は同じ」ものを使う
- 最後に「外食先ではお気に入りのスプーンだけ持参」
この段階的な工夫で、少しずつ柔軟になり、今では外食もスムーズに楽しめるようになったとのこと。
客観的に見ると、これは「刺激に対して安心感を得たい」という感覚特性が背景にあります。無理にやめさせるのではなく、段階的に広げるのが成功のポイントですね。
学校生活のこだわりを先生と一緒に乗り越えた体験談
小学生の娘さんを育てるママは、「授業で予定が変わると泣いてしまう」ことに困っていました。たとえば、体育が雨で中止になっただけで混乱してしまい、授業に参加できないことも。
そこで、学校の先生と連携して次の工夫を取り入れました。
- 連絡帳に「明日の予定」と「変更の可能性」をあらかじめ書いてもらう
- 教室に「今日のスケジュール表」を掲示して、変更があれば先生が一緒に書き換える
- 不安が強いときは、「変更の理由」を丁寧に説明してもらう
結果として、娘さんは少しずつ「予定変更も受け入れられる経験」を積むことができました。
ママは「先生と一緒に対応したことで、家庭だけではできない支援ができた」と話しています。
ここからわかるのは、家庭と学校が連携することの大切さ。ママが一人で抱え込むよりも、周囲の大人と協力したほうが子どもも安心しやすいんです。
ママ自身の気持ちがラクになった考え方の変化
もう一つ大事なのが、ママの気持ちの持ち方です。あるママは、以前は「なんで普通にできないの?」とイライラしてしまい、毎日つらかったそうです。
でも、発達支援センターで専門家に相談したときに「こだわりは“困ったこと”でもあるけれど、“安心する工夫”でもあるんですよ」と言われ、ハッとしたそうです。
それ以来、「うちの子はこだわりで安心しているんだ」と考えられるようになり、気持ちがとてもラクになったとのこと。
結果として、子どもにも穏やかに接することができるようになり、親子関係が良い方向に変わったそうです。
客観的に見ても、育児で大事なのは「子どもを変えること」だけでなく、「ママ自身の視点を少し変えること」なんですね。
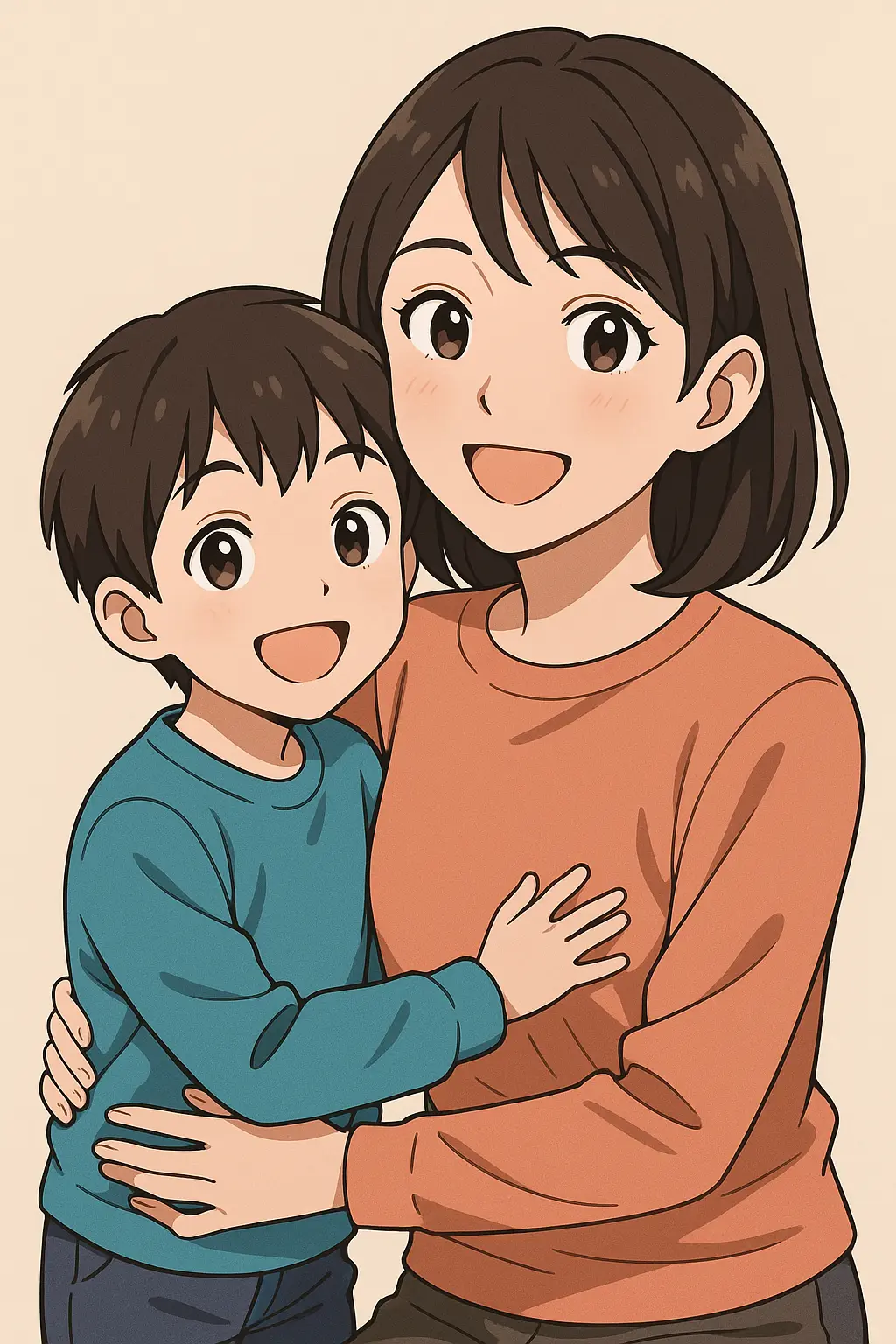
専門家がすすめるアスペルガー児の支援・療育アプローチ
「こだわりが強くて毎日大変…」という気持ちを抱えるママは少なくありません。でも、専門家がすすめる支援や療育の方法を知ることで、「こういう工夫があるんだ」と視野が広がり、育児がラクになることも多いんです。ここでは、実際に療育や学校で取り入れられている方法や、専門家の考え方を紹介します。
療育で実際に使われる支援方法(ソーシャルストーリー等)
療育の場では、子どものこだわりや不安に寄り添いながら、生活をスムーズに進めるための工夫がたくさん使われています。その代表例が「ソーシャルストーリー」です。
ソーシャルストーリーとは、イラストや短い文章で「どんな場面で、どう行動したらいいか」をわかりやすく伝える支援ツール。たとえば、
- 「順番を待つときはどうする?」
- 「給食で苦手な食べ物が出たら?」
などを絵本のようにまとめて見せることで、子どもが安心して行動できるようになります。
さらに、視覚支援(スケジュール表や絵カード)もよく活用されます。口頭で「あと5分で出かけるよ」と言っても伝わりにくいとき、タイマーやカードを使うと理解しやすいんです。
専門家の視点から見ると、「見える化」することが安心につながり、こだわりによる混乱も減らせるのがポイントです。
学校・園で活用できる支援制度と個別指導計画
家庭だけで頑張るのはとても大変。だからこそ、学校や園で活用できる支援制度を知っておくことが大切です。
例えば、
- 「合理的配慮」:子どもの特性に合わせて、座る場所やテストの配慮をしてもらえる制度。
- 「個別指導計画(IEP)」:子どもの得意・苦手に合わせて、目標や支援方法を先生たちが一緒に考えてくれる仕組み。
実際に「板書をノートに写すのが難しい子」に対しては、プリントをあらかじめ用意してもらうなどの対応が取られることがあります。
ママとしては「学校にこんなお願いをしていいのかな?」と不安になることもありますよね。でも、制度として認められている支援を受けるのは権利なんです。先生や支援コーディネーターと話し合うことで、子どもに合った環境を整えられます。
専門家が語る「こだわり行動との付き合い方」
多くの専門家が共通して伝えているのは、「こだわりを無理にやめさせなくてもいい」という考え方です。
こだわり行動は、
- 不安を減らすための安心材料
- 集中力や得意分野につながる可能性
といったプラスの側面もあります。だから、全部を「やめさせる対象」にするのではなく、「生活に支障がある部分は少しずつ緩める」「強みにつながる部分は伸ばす」という姿勢が大切なんです。
例えば、電車に強いこだわりを持つ子なら、
- 通学路で電車を見て気持ちを落ち着ける
- 学習では路線図を使って地理を覚える
といったふうに、「こだわりを強みに変える」工夫も可能です。
ママが「困ったこと」だと思うこだわりも、専門家の視点では子どもの成長につながる芽になることがあるんですね。
育児ストレスを減らす!ママのセルフケアと支援活用
発達特性のある子どもを育てていると、どうしても「普通に子育てしているだけ」では済まない場面に出会いますよね。こだわりへの対応や急な癇癪、学校や園とのやり取りなど、毎日がフル稼働で休む暇がないと感じる方も多いはず。
でも、ママの心と体が疲れてしまっては、子どもを支える力も出ません。ここでは、ストレスをため込みすぎないためのセルフケアと、支援の上手な活用法についてお伝えします。
完璧主義を手放す子育てマインドセット
多くのママが「もっとちゃんとやらなきゃ」「私が頑張れば子どもも落ち着くはず」と、自分を追い込んでしまいがちです。でも実は、子育てに「完璧」なんて存在しません。
専門家の視点からも、「親が100%完璧に対応する必要はない」と言われています。むしろ、7割くらいの力でちょうどいいと考えるほうが、親子の関係は長続きするんです。
たとえば、
- 夕食は冷凍食品に頼る日があってもOK
- 子どものこだわりに全部対応できなくても大丈夫
- イライラしてしまったら「次から気をつけよう」で十分
こうした気持ちの切り替えが、ストレスを減らす大きな一歩になります。
家族・地域・支援サービスに頼る賢い工夫
「ママが一人で全部抱える」ことが、ストレスを大きくする原因のひとつです。だからこそ、周りに頼る工夫がとても大切です。
- 家族にお願いする:パパに寝かしつけを任せる、おばあちゃんに短時間子どもを見てもらう。
- 地域のサービスを利用する:ファミリーサポート、子育て支援センター、一時預かりなど。
- 専門的な支援を取り入れる:発達支援センター、児童発達支援事業所、相談窓口など。
「人に頼るのは申し訳ない」と思うかもしれませんが、実は逆で、支援を活用することは子どもにとってもプラスです。ママが少し余裕を持つことで、子どもにも安心感が伝わり、親子関係が安定しやすくなるんですね。
ママが元気になる!自分時間の作り方アイデア
毎日バタバタの生活の中でも、ママが「自分の時間」を持つことはとても大切です。ほんの10分でも、自分のために過ごすだけで気持ちがリセットできます。
おすすめの自分時間アイデアは、
- 子どもが寝たあとに好きなドラマを1話だけ観る
- 朝のコーヒーをゆっくり味わう
- 好きな音楽をイヤホンで聴く
- ちょっと高めのスイーツをこっそり楽しむ
- 週末に1時間だけパパに任せてカフェに行く
大事なのは「時間の長さ」ではなく、自分がホッとできることをやること。ママが元気でいることが、結局は子どもにとって一番の安心材料になります。
まとめ|アスペルガー症候群のこだわり行動は「困りごと」であり「強み」
アスペルガー症候群の子どもに見られる「こだわり行動」。毎日の育児の中で直面すると、「どうしてうちの子だけ…」と不安になったり、ストレスを感じたりすることもあるかもしれません。たしかに、日常生活や学校生活での困りごとにつながる場面はあります。
でも同時に、こだわりは子どもの個性であり強みにもなるんです。たとえば、好きなことをトコトン突き詰める集中力や、物事のルールや順序をきちんと守ろうとする姿勢は、将来の学びや社会生活で大きな武器になります。
事例と対応を理解すれば育児はラクになる
大切なのは、こだわりを「ただの困りごと」として見るのではなく、「どう理解し、どう対応するか」という視点を持つことです。
具体的な事例と対応方法を知っておくだけで、ママの気持ちはグッとラクになります。
- 急な予定変更に不安を示す → 事前に予定を絵やカレンダーで見える化
- 食べ物に強いこだわり → 少しずつ選択肢を広げて「食べられる」を増やす
- 同じ遊びを繰り返す → 安心感のサインとして受け止めつつ、新しい遊びに少し混ぜていく
こうした工夫を重ねることで、子どもの安心も守れますし、ママの負担も和らぎます。
こだわりを否定せず、強みに変えていく視点が大切
こだわり行動を「ダメなこと」と決めつけてしまうと、子ども自身が傷つき、親子関係にも影響が出やすくなります。
むしろ、こだわりを強みに変える視点を持つことが重要です。
- 電車好きなら → 地図や数字の学びに活かせる
- 並べることが好きなら → 整理整頓や観察力のトレーニングになる
- 同じ絵本を繰り返し読むなら → 言葉の理解や記憶力が伸びる
「こだわり=成長のチャンス」と捉えるだけで、育児の見え方が変わりますよ。
ママ自身も「ひとりで抱え込まない」ことが支援の第一歩
最後に忘れてはいけないのは、ママ自身の気持ちと体を守ることです。
どんなに工夫しても、子どものこだわりに毎日向き合うのは大変。だからこそ、「全部自分で頑張らなきゃ」と抱え込む必要はありません。
- パパや家族に頼る
- 保育園や学校の先生と共有する
- 発達支援センターや相談窓口を利用する
こうした「支援につながる一歩」を踏み出すことは、ママにとっても子どもにとっても安心につながります。
アスペルガー症候群のこだわり行動は、困りごとでもあり、強みでもあるという両面性があります。事例を知り、対応を工夫し、強みとして活かす視点を持つことで、毎日の育児はぐっとラクに、そして前向きに変わっていきます。
そして何より、ママがひとりで抱え込まずに支援を受けることが、子育てを続ける大きな力になるんですよね^^
以上【アスペルガー症候群のこだわり例と育児ストレスを減らす対応方法まとめ】でした

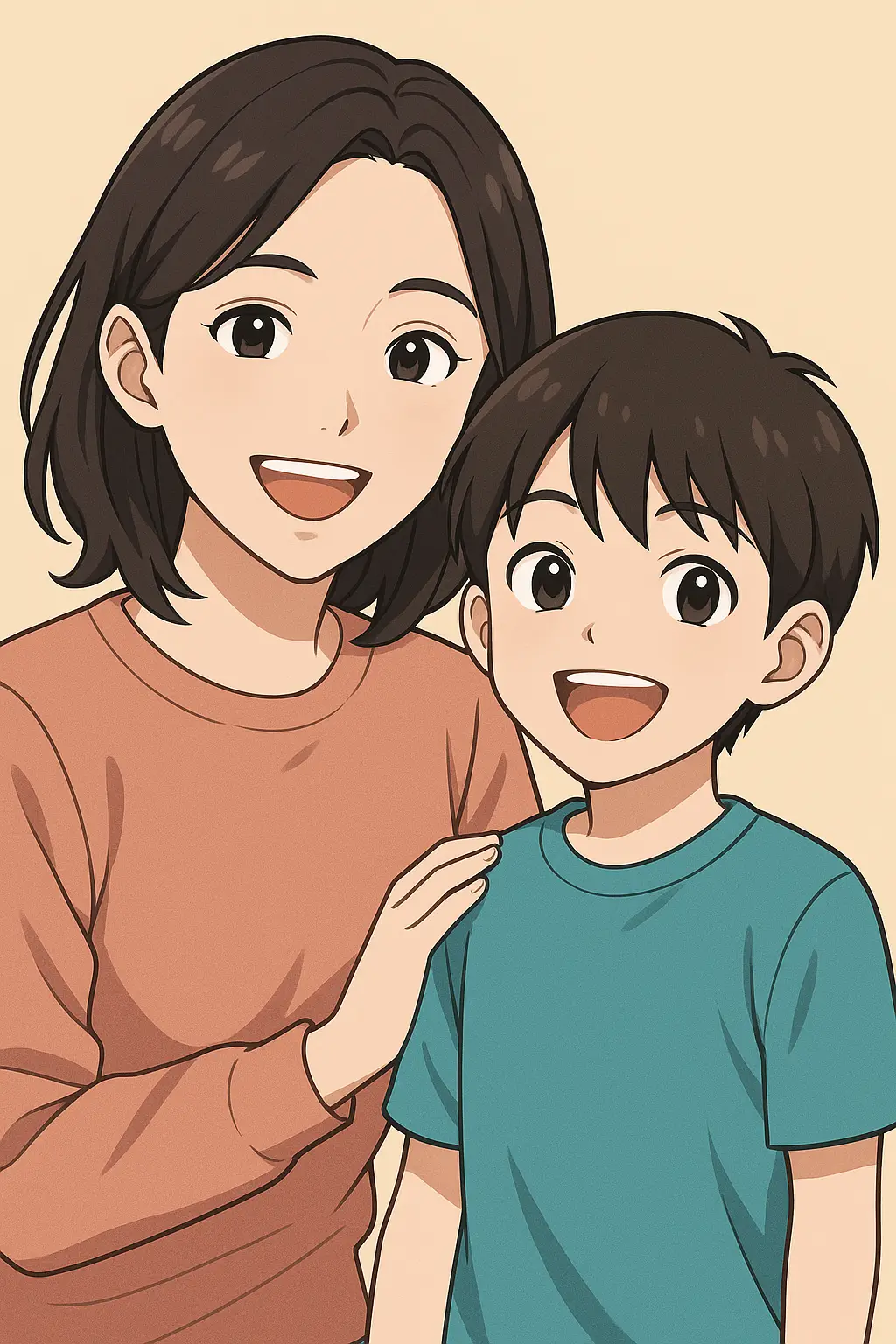









コメント