発達障害の子どもがベタベタしてくる理由とは?
「うちの子、気がつけばいつもベタベタしてくる…」「ちょっとでも離れるとすぐ抱きついてくる」――こんな経験、ありませんか?
子どもが親にくっつきたがるのは自然な甘えのひとつですが、発達障害の子どもの場合、年齢が大きくなっても強い“ベタベタ行動”が続くことがあります。これは決して「甘えすぎ」や「わがまま」ではなく、その子なりの理由や特性が背景にあるんです。
ここでは、「なぜベタベタするのか?」をいくつかの視点から整理してみましょう。
「ベタベタ行動」ってどんな状態?特徴と具体例
まず、「ベタベタ行動」とはどんなものを指すのかイメージしてみましょう。
- 常に抱っこやハグを求める
- 家の中でも親から離れず、後をついてくる
- 手をつなぎたがる、膝の上に座りたがる
- 夜寝るときも体をピッタリくっつけたがる
といった行動が代表的です。
発達障害の子どもの場合、この「くっつきたい気持ち」がとても強く、親が少し離れただけで強い不安を感じることがあります。
一般的な「甘え」との違いは、行動の頻度が高く、生活のいろいろな場面で見られること。ときには「ちょっと疲れるな…」と感じるほど続くこともあります。
発達障害特性による心理背景(不安・感覚過敏・愛着)
子どもがベタベタしてくる背景には、発達障害特有の心理的な要素があります。
- 不安の強さ
発達障害の子どもは、環境の変化や先の見通しが立ちにくいことから、強い不安を感じやすい特性があります。その不安を和らげるために、もっとも安心できる相手であるママに「ベタベタする」という形でくっつこうとするのです。 - 感覚過敏・感覚鈍麻
発達障害には「感覚の偏り」があることも多いです。- 触覚に敏感な子は、逆に「安心できる触れ方」を求めてベタベタすることがある
- 感覚が鈍い子は、強いスキンシップで「ちょうどよい刺激」を得ようとする
こうした感覚特性も、ベタベタ行動につながることがあります。
- 愛着やコミュニケーションのスタイル
言葉で気持ちを伝えるのが難しい子は、「くっつくこと」自体が愛情表現や安心の方法になっている場合もあります。つまり、「大好き」「安心したい」という気持ちを体で伝えているのです。
環境や生活リズムが影響するケース
子どものベタベタ行動は、心理的な特性だけでなく、環境や生活習慣の影響も大きいです。
- 環境の変化に弱い
保育園や学校で新しいことがあった、先生が変わった、友達とのトラブルがあった――そんな日には帰宅後にベタベタが強まることがあります。 - 生活リズムの乱れ
睡眠不足や疲れがたまると、安心を求める気持ちが増し、ママにベタベタしたくなります。 - 親子の関係性や家庭の雰囲気
家の中が落ち着いていれば子どもも安心しやすいですが、親が忙しくて不安を感じると「もっとかまって!」という気持ちからベタベタが増えることもあります。
つまり、ベタベタ行動は「発達特性」だけでなく、その日の出来事や家庭の状況にも左右されるのです。
ベタベタは甘え?それとも不安のSOS?
発達障害の子どもがベタベタしてくるとき、ママとしては「ただの甘えなのかな?それとも何か困ってるのかな?」と迷うことがありますよね。
実は、この“ベタベタ”には大きく分けて 「甘えのサイン」 と 「不安のSOS」 の2つの意味が隠れていることが多いんです。
どちらなのかを理解しておくと、接し方も変わってきて、ママの気持ちも少しラクになります。
甘えのサインとしてのベタベタ行動
まずは「甘え」のパターンから。
- 「ママ大好き!もっと近くにいたい!」
- 「いっぱい抱っこしてもらって安心したい!」
こんな気持ちの表れが、ベタベタ行動につながることはよくあります。
発達障害の子どもは、ことばで「大好き」と伝えるのが難しかったり、感情表現の仕方が独特だったりするので、スキンシップそのものが愛情表現になっているんです。
だから、抱きついてきたり、くっつきたがったりするのは、「ママが必要」「安心したい」というポジティブな甘えのサインでもあるんですね。
「この子なりの“愛情表現”なんだ」と思うと、少し受け止めやすくなるかもしれません。
SOS行動としてのベタベタ|ストレスや不安の表れ
一方で、ベタベタ行動が “SOSのサイン” になっていることもあります。
例えば…
- 学校や園で嫌なことがあった
- 環境の変化で不安が強くなった
- 疲れやストレスがたまっている
- 気持ちをうまく言葉で表現できない
こうしたときに、子どもは「ママにベタベタする」という行動で不安を解消しようとするんです。
特に発達障害の子どもは、言葉で「つらい」「助けて」と言うのが難しいことがあります。だから、安心できるママにくっつくことで「気づいてほしい」「安心させてほしい」と伝えているんですね。
もしベタベタが「いつもより強い」「やたら長く続く」と感じるときは、子どもなりのSOSかもしれません。
見極めチェックリスト|親が気づける3つの視点
じゃあ、「甘え」と「SOS」ってどうやって見分けたらいいの?と気になりますよね。
ここでは、ママが日常生活で意識できる3つの視点を紹介します。
- タイミングを見る
→ 学校から帰った直後、寝る前など“特定の時間”に強まるなら、不安や疲れが原因かも。 - 行動の頻度や強さを観察する
→ 普段よりも極端に長時間くっついて離れない場合は、SOSの可能性が高い。 - 他のサインと一緒に出ていないかチェックする
→ かんしゃくが増えた、食欲が落ちた、夜眠れない…など、他の困りごととセットで出ている時は要注意。
この3つを意識するだけでも、「今は甘えたいだけだな」「ちょっと不安が強そうだな」といった見極めがしやすくなります。
発達障害の子がベタベタしてくる時の基本的な接し方
「ベタベタされると、うれしい反面、ちょっとしんどい…」と思うこと、ありますよね。
でも実は、子どもにとってベタベタする行動は、ただのわがままではなく、安心したい・甘えたい・気持ちを伝えたいというサインなんです。
ここでは、発達障害の子がベタベタしてくるときに、ママができる基本的な接し方を紹介します。無理に全部やろうとせず、できる範囲で取り入れるのがポイントです。
否定せず受け止める|安心感を与える声かけ例
子どもが抱きついてきたとき、つい「もうやめて!」「今忙しいの!」と言いたくなることってありますよね。
でも、そこで強く否定してしまうと、子どもは「自分の気持ちを受け止めてもらえなかった」と感じてしまいます。
大切なのは、まずは子どもの気持ちを受け止めること。
例えばこんな声かけがおすすめです。
- 「○○くん、ママにくっつきたいんだね」
- 「不安だったんだね。ぎゅーってしようか」
- 「ちょっと待っててね。あとでいっぱい抱っこするよ」
完全に応じられないときでも、「気持ちは受け止めているよ」というメッセージを伝えるだけで、子どもは安心できます。
つまり、拒否するのではなく、“タイミングをずらす” という考え方です。
安心できる代替行動を用意する(グッズ・遊び)
いつでもずっとベタベタに付き合うのは、ママにとって負担が大きいですよね。
そんなときは、子どもが安心できる“代わりの行動”を用意しておくのがおすすめです。
具体例としては…
- お気に入りのぬいぐるみやクッションを抱っこさせる
- 安心グッズ(ママのにおいがするハンカチや小物)を持たせる
- ぎゅーっとできる遊び(タオルで包む、お布団でロール遊び)を取り入れる
こうした工夫をしておくと、子どもは「ママがいなくても安心できる方法」を少しずつ学んでいけます。
つまり、“安心を分散させる”イメージです。
子どもの気持ちを言葉にして伝える練習
発達障害の子どもは、気持ちを言葉にするのが苦手な場合があります。
そのため「不安」「さみしい」「抱っこしてほしい」と言えずに、ベタベタする行動で伝えていることが多いんです。
そこで効果的なのが、ママが子どもの気持ちを代弁すること。
- 「くっつきたいってことは、安心したいんだね」
- 「今、さみしい気持ちなんだね」
- 「ぎゅーってしたら落ち着くんだね」
このように言葉で整理してあげると、子どもも「自分の気持ちはこういうことなんだ」と理解しやすくなります。
少しずつ「抱っこしてって言える?」と促していくことで、言葉で気持ちを伝える練習につながります。
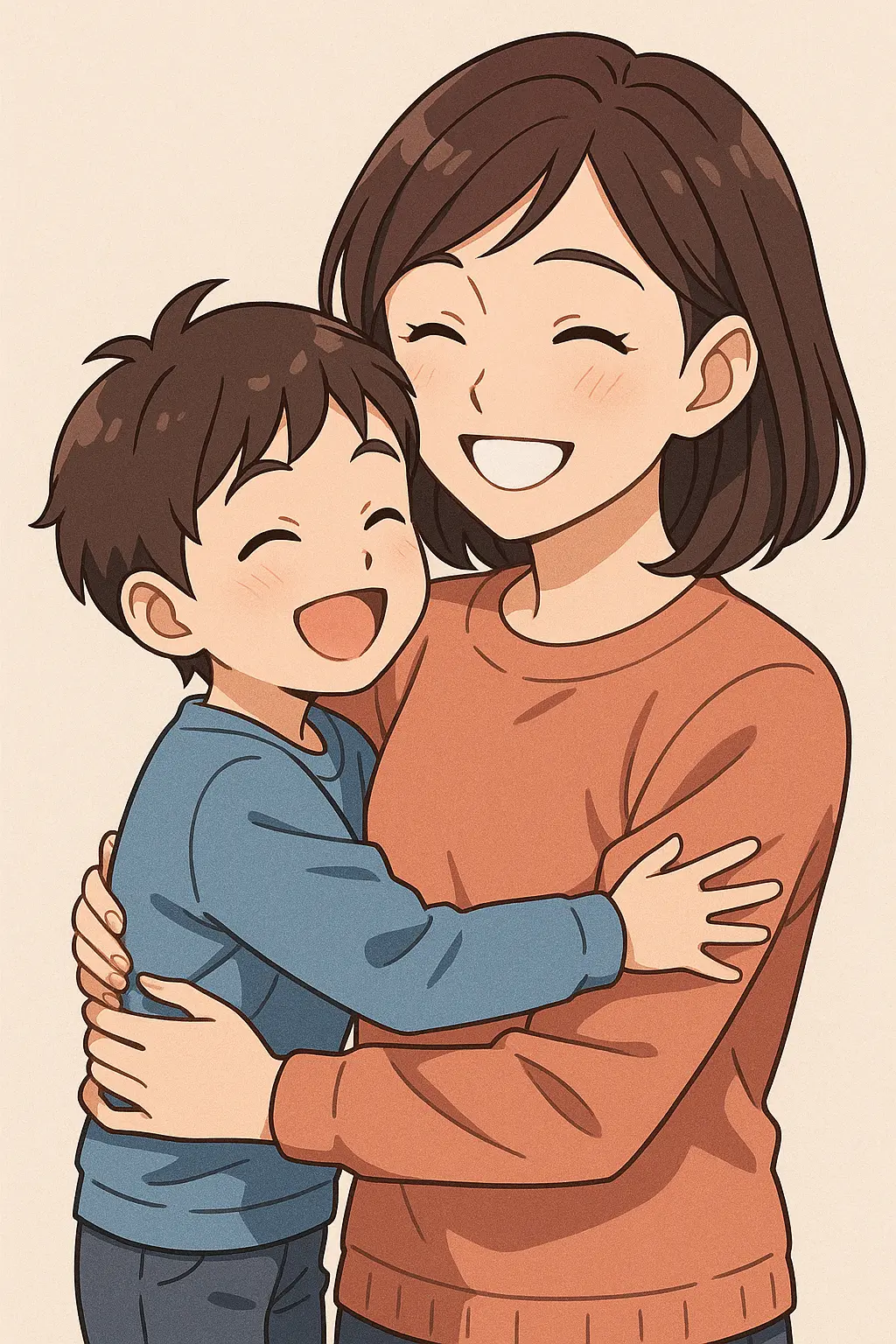
家庭でできる!ベタベタ行動への具体的な対応法
「ベタベタされるのはうれしいけれど、正直ずっと続くと疲れちゃう…」というのがママの本音だと思います。
でも大丈夫!工夫しながら関わることで、子どもの安心感を守りつつ、ママの負担を減らす方法があります。
ここでは家庭で今日から試せる具体的な対応法を紹介します。
スキンシップを計画的に取り入れる工夫
発達障害の子どもは、「いつどれくらいスキンシップができるのか」がわからないと、不安から何度も抱きついてきたりします。
そこでおすすめなのが、スキンシップを“計画的に”取り入れることです。
例えば…
- 朝の準備の前に「ぎゅータイム」を3分とる
- おやすみ前にハグやマッサージをする
- 1日の流れの中に「スキンシップの時間」を決めてあげる
そうすると、子どもは「あとで抱っこしてもらえる」と安心し、無理にベタベタを繰り返す必要が減っていきます。
“安心の先取り”ができるイメージですね。
視覚支援で「今」と「次」をわかりやすく伝える
発達障害の子は、「今はママが忙しい」「次に〇〇する」という時間の見通しが持ちにくいことがあります。
そのため「今すぐ抱っこして!」と強く求めてしまうのです。
そこで役立つのが 視覚支援。
- 「今はお料理、次は抱っこね」とカードやイラストで見せる
- タイマーを使って「3分後にぎゅーしようね」と伝える
- スケジュール表に「ぎゅータイム」を書き込む
こうした工夫で、子どもは「待てる時間」を体感できるようになります。
目で見て理解できると、不安が減って落ち着きやすいんです。
環境調整で安心スペースをつくる方法
子どもがベタベタしてくる背景には、「安心できる居場所が足りない」こともあります。
そこで、家の中に「安心スペース」をつくってあげるのも有効です。
具体的には…
- クッションや毛布を置いた「リラックスコーナー」
- 光や音を少し調整した落ち着ける空間
- 子どもが“ひとりでも安心できる”お気に入りの場所
このスペースを「安心のお部屋」「ほっとコーナー」と呼んでおくと、子どもも覚えやすいです。
「ここに行けば落ち着ける」と思える場所があると、ママにベタベタする回数も少しずつ減っていきます。
ママが無理せず楽になる工夫(協力・一人時間)
最後に忘れてはいけないのが、ママ自身の安心です。
子どもにずっとベタベタされていると、心も体も疲れてしまいますよね。
そんなときは、次のような工夫をしてみましょう。
- パパや祖父母に「ぎゅー係」をお願いする
- 一時預かりやショートステイを利用して、リフレッシュ時間をつくる
- ほんの5分でもお茶を飲んだり、深呼吸する時間をとる
大事なのは、ママが「がまんして全部やらなきゃ」と思わないこと。
ママが元気でいることが、子どもの安心にもつながります。
年齢別|ベタベタ行動への接し方の違い
子どもの「ベタベタ行動」は、年齢や発達段階によって意味合いや対応の仕方が変わってきます。
「まだ小さいから仕方ないのかな?」「この先もずっと続くのかな?」と不安になるママも多いですが、実際には成長に合わせてベタベタの理由や強さも変化していくんです。
ここでは、年齢ごとに押さえておきたい対応のヒントを紹介します。
幼児期(3〜6歳)の安心できる対応アイデア
幼児期は、まだまだ「ママ大好き!」の気持ちが強い時期。
発達障害の子どもは特に、安心のベースがママに大きく依存するため、ベタベタが頻繁に見られます。
この時期に大切なのは、「安心をたっぷり与える」こと。
- ぎゅーっとする時間を一日の中でルーティン化
- 抱っこのかわりに「おひざタイム」を作る
- 「ベタベタOKタイム」を先に設けてから遊びや活動に移る
こうした工夫で、子どもは「安心できる場所がある」と感じられます。
ただし、ママが疲れすぎないように、短時間でも濃いスキンシップを意識するのがおすすめです。
小学生期の自立心を育てる距離感づくり
小学生になると、学校生活が始まり、少しずつ「自分でできること」が増えていきます。
でも発達障害の子どもは、環境の変化や集団生活のストレスから、家では逆にベタベタが強まることもあります。
この時期に意識したいのは、「自立を意識しながらも安心感を残す」距離感づくりです。
- 学校から帰ったら「10分だけぎゅータイム」を決める
- 「今は一緒、次はひとり」と段階的に距離を取る練習
- 「待っていられたね!」と成功体験を言葉でしっかり褒める
こうすることで、子どもは「ママと離れても大丈夫」という感覚を少しずつ育てられます。
ポイントは、急に距離を取ろうとせず、段階的に練習することです。
思春期の子どもに合った「見守りと接し方」
思春期になると、体はぐんと大きくなり、友達関係も複雑になってきます。
でも心の中ではまだまだ不安が強く、「自立したいけど甘えたい」という気持ちの揺れが出てくる時期です。
この時期のベタベタは、幼児期のような抱きつきではなく、
- 「話を聞いてほしい」
- 「そばにいてほしい」
- 「安心できるリアクションが欲しい」
といった形に変わってくることも多いです。
思春期の子に大切なのは、「干渉しすぎず、でも安心を与える」バランス。
- 強いスキンシップよりも「言葉で安心を伝える」
- 「大丈夫だよ」「応援してるよ」と短い言葉で支える
- プライバシーを尊重しつつ、必要なときはそっと寄り添う
こうすることで、子どもは「自分はひとりじゃない」と感じながら、自立への一歩を踏み出せます。
学校や園でのベタベタ行動|先生との連携と対応法
家庭では「ママにベタベタ」ですが、学校や園では先生やお友だちにベタベタしてしまうこともあります。
これが悪いことではないのですが、集団生活の中ではトラブルや誤解につながることも。
だからこそ、家庭と学校が一緒になって子どもを支えることがとても大事なんです。
家庭と学校で一貫性を持たせる工夫
子どもにとって安心につながるのは、「どこでも同じルールがある」ということ。
家庭と学校で対応がバラバラだと、子どもは混乱して不安が強まり、ベタベタ行動が増えてしまうこともあります。
例えば、
- 家で「ぎゅーは3分」と決めているなら、先生にも伝えて同じようにしてもらう
- ベタベタしすぎたら「クッションを抱っこする」という代替行動を共通にする
- 子どもが落ち着く言葉(「あとでね」「順番だよ」など)を先生と共有する
こうして一貫した対応ができると、子どもは「同じルールがあるから安心」と感じ、ベタベタ行動も少しずつ落ち着いていきます。
お友だちにベタベタしてしまう時の対処法
発達障害の子どもは、「好き」「仲良くしたい」という気持ちをうまく言葉で伝えられず、お友だちにベタベタしてしまうことがあります。
でも相手の子がびっくりしたり嫌がったりすると、トラブルにつながることも…。
この場合は、
- 「手をつなぐのは先生やママと」とルールを決める
- 「ぎゅーしたいときはぬいぐるみへ」など代わりの方法を用意する
- 先生に間に入ってもらい、「ことばで仲良くしよう」と練習する
また、トラブルが起きてから叱るのではなく、事前に予防する工夫が効果的です。
例えば「今日は友だちにぎゅーしないで、タッチにしようね」と決めておくだけで、安心して行動できる子もいます。
支援学級・専門機関との連携方法
ベタベタ行動が強くて学校生活に影響が出ている場合は、支援学級や専門機関との連携も検討しましょう。
- 支援学級や通級指導教室では、「安心の方法を増やす練習」ができます
- 発達支援センターや放課後等デイサービスでは、専門スタッフが遊びを通して代替行動を教えてくれることもあります
- 学校のスクールカウンセラーに相談すれば、先生とママの間をつなぐサポートをしてくれる場合も
大事なのは、「家庭だけで頑張らない」こと。
学校や専門家と一緒に工夫していくことで、子どもにとってもママにとっても安心できる環境が整っていきます。
ママが疲れた時にできるセルフケア方法
発達障害のある子を育てていると、どうしても「ママ自身がクタクタになる」瞬間が出てきますよね。
四六時中ベタベタされたり、対応に気を張り続けたりすると、心も体も限界に近づいてしまいます。
でも安心してください。
「疲れた」と思うのはママの弱さではなく、ごく自然なことなんです。
ここでは、ママが自分を大事にできるセルフケアのヒントをご紹介します。
「疲れる」と感じるのは当然|罪悪感を持たない
まず一番大事なのは、「疲れて当たり前」と認めることです。
子どもがベタベタしてくるのは愛情や安心を求めているサインですが、受け止める側のママにはかなりのエネルギーが必要です。
「他のママはちゃんとやっているのに、私は疲れてしまう…」と比べなくても大丈夫。
ママ一人で全部を完璧にやろうとしたら、誰だって疲れます。
むしろ、「疲れた」と感じるのは頑張っている証拠。
その気持ちを否定するのではなく、「よし、ちょっと休もう」と受け止めることが、セルフケアの第一歩です。
一人時間・リフレッシュ時間の確保アイデア
次に考えたいのは、ママが自分だけの時間を持つことです。
「そんなの無理!」と思うかもしれませんが、ちょっとした工夫でリフレッシュのチャンスは作れます。
例えば…
- 子どもが寝たあとに好きな飲み物を飲みながらドラマを見る
- ほんの10分でもいいから深呼吸しながら散歩
- 家事を少し減らして、自分の趣味に時間を使う
- 子どもが通っている間に、カフェで一人時間を過ごす
大切なのは、「自分のために使う時間」を意識して確保することです。
たとえ短くても、ママの気持ちがリフレッシュできれば、子どもへの接し方もぐっと楽になります。
ママ自身が安心できる支援サービス・居場所活用
そして忘れてはいけないのが、外の力を借りること。
「自分だけで何とかしなきゃ」と思うと追い詰められてしまうので、安心できる支援や居場所を上手に使っていきましょう。
例えば、
- ファミリーサポートや一時預かりを利用して、数時間だけ子どもを預ける
- 児童発達支援や放課後デイサービスを利用して、子どもが楽しく過ごす時間をつくる
- ママの会やピアサポートで、同じ悩みを持つママとおしゃべりする
- どうしてもつらい時は、カウンセラーや支援センターに相談する
こうしたサービスを利用するのは、決して「甘え」ではなく、立派なセルフケアです。
ママが安心して過ごせる時間を持つことが、結果的に子どもの安心にもつながります。
よくある質問
発達障害の子どもが「ベタベタしてくる」行動について、ママからよく聞かれる質問をまとめてみました。
ちょっとしたヒントを知るだけでも気持ちが軽くなるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
Q1. 発達障害の子がベタベタしてくるのは成長とともに落ち着く?
A. 多くの場合、成長とともに落ち着いていく傾向はあります。
ただしスピードには個人差があり、すぐに改善する子もいれば、長く続く子もいます。
ベタベタ行動は「安心したい」「不安を解消したい」という気持ちの表れなので、適切なサポートを受けながら少しずつ自立のステップを踏んでいくと和らぎやすいです。
「いつか自然になくなるだろう」と放置するより、安心感を与えつつ自立を促す関わりがポイントです。
Q2. 他の子にベタベタしてしまう場合の対応は?
A. 他の子にベタベタしてしまうのは、「相手との距離感がわからない」ことが原因の場合が多いです。
そんなときは、
- 「手をつなぐのはママだけだよ」など、ルールをわかりやすく伝える
- 絵カードや写真を使って、OKとNGの行動を視覚的に示す
- 先生や友達にも理解をお願いし、トラブルにならない工夫をする
このように、子ども自身が「どうすればいいか」を理解しやすくしてあげることが大切です。
Q3. 兄弟姉妹への影響が心配なときはどうする?
A. 発達障害の子がベタベタ行動をしていると、兄弟姉妹が「私ばっかり我慢している」と感じてしまうこともあります。
そのため、
- 兄弟姉妹だけと過ごす時間を意識的につくる
- 「○○ちゃんのおかげで助かったよ」と役割や頑張りを認めて言葉にする
- 家族で一緒に安心できる遊びを取り入れる
といった工夫をすることで、バランスがとりやすくなります。
兄弟姉妹の気持ちもきちんとケアすることが、家族全体の安心感につながります。
Q4. ベタベタ行動は放置しても大丈夫?
A. ベタベタ行動を「困るけど放っておこう」と思うこともあるかもしれませんが、完全に放置するのはおすすめできません。
なぜなら、
- 不安が強くなって行動がエスカレートする
- 親子の関係がぎくしゃくする
- 自立のステップを踏みにくくなる
といったリスクがあるからです。
ただし、一度にやめさせようとする必要はありません。
「安心できる環境を用意しつつ、少しずつ距離を取れる練習をする」ことが理想的な対応です。
Q5. 限界を感じた時に相談できる機関は?
A. ママが「もう無理!」と思ったときに相談できる場所はいくつもあります。
代表的なのは…
- 児童発達支援センター:子どもの特性に合わせたアドバイスをもらえる
- 発達相談窓口(自治体):身近な支援制度やサービスを紹介してくれる
- 学校や園の先生・スクールカウンセラー:日常生活に合わせた対応を一緒に考えてくれる
- 発達障害者支援センター:専門的な視点から相談にのってもらえる
「自分が弱いから相談する」のではなく、「子どもと自分が安心して暮らすために相談する」という意識で、ぜひ気軽に活用してみてくださいね。
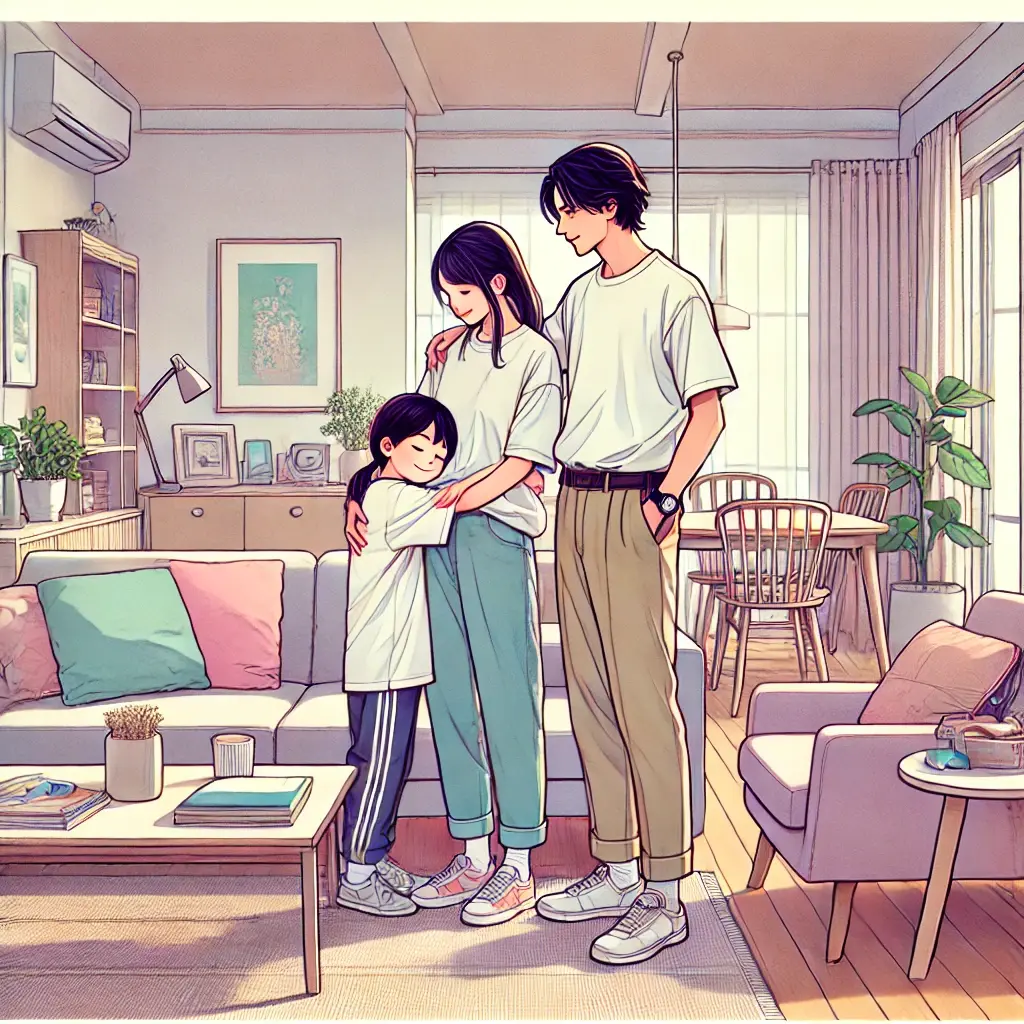
まとめ|発達障害の子どもの「ベタベタ行動」との向き合い方
ここまで見てきたように、発達障害の子どもの「ベタベタ行動」にはいろんな意味が隠れています。
単なる甘えに見えることもあれば、心の中で感じている不安やストレスのSOSである場合もあります。
ベタベタは「甘え」でもあり「SOS」でもある
まず知っておきたいのは、ベタベタするのは悪いことではないということ。
子どもなりに「ママに安心したい」「ここにいてほしい」という気持ちを表しているんです。
でも時には、「ちょっと苦しいよ」「一人じゃ不安だよ」という助けを求めるサインにもなります。
「ただ甘えているだけ」と切り捨てず、行動の背景にある子どもの気持ちを想像することがとても大切です。
否定せず安心できる代替手段を用意することが大切
とはいえ、ずっとベタベタされるとママも疲れてしまいますよね。
そこでポイントになるのが、「否定せず受け止めながら、安心できる代替手段をつくる」ことです。
たとえば…
- 「抱っこしてほしい!」に代わりに、好きなぬいぐるみを抱っこする
- 「そばにいて!」の気持ちには、声かけやスケジュールカードで安心感を与える
- 「一緒にいたい!」という思いを、スキンシップタイムを決めて叶えてあげる
こうした代替方法を取り入れると、子どもは安心感を持ちながら自立へのステップを踏めるようになります。
ママ自身の心を守りながら、専門家の力も借りよう
忘れてはいけないのは、ママの心のケアです。
「イライラしてしまった」「疲れてもう限界かも」と感じるのは、決してダメなことではありません。
むしろそれは、ママが一生懸命向き合っている証拠です。
そんなときは一人で抱え込まず、専門機関や支援サービスに相談することも立派な選択肢です。
児童発達支援や相談窓口、学校の先生などに話すだけでも気持ちが軽くなります。
ママが元気でいることが、結局は子どもにとっても一番の安心材料になります。
だからこそ、「自分を大事にすることは、子どもを大事にすることと同じ」と考えてみてください。
発達障害の子どものベタベタ行動は、時にママを悩ませますが、それは子どもからの大切なメッセージです。
甘えとSOS、どちらの面もあることを理解しつつ、代替手段を工夫して、そしてママ自身の心も守りながら…。
「一緒に安心できる関係をつくっていく」ことが、親子にとって一番大事なポイントです。
以上【発達障害の子どもがベタベタしてくる!原因と安心できる接し方・対応法まとめ】でした。











コメント