【基礎知識】発達障害の子に多い「抱きつく癖」とは?
「抱きつく癖」というと、多くのママが「甘えてるのかな?」「ちょっと困るな…」と感じるかもしれません。
でも、発達障害の子にとって抱きつく行動には ちゃんと理由や意味がある ことが多いんです。
ここでは、まず「どんな特徴があるのか」「どういう心理が隠れているのか」「どんな年齢や発達の時期に多いのか」を一緒に整理してみましょう。
抱きつく癖の行動特徴|家庭・園・学校でよくある場面例
発達障害の子に多い「抱きつく癖」は、家庭や園、学校などいろんな場所で見られます。
たとえば――
- 家庭内では、ママが料理しているときに急に後ろからギューッと抱きついてくる
- 保育園や幼稚園では、お友達に突然抱きついて驚かせてしまう
- 小学校以降になると、先生に強くしがみついて「離れたくない!」とアピールする
こんな風に、子どもの安心したい気持ちが「抱きつく」という形で表れやすいのです。
大人から見ると「急で困るな」と思うこともありますが、子ども本人にとっては 「気持ちを落ち着けるための方法」 になっていることが多いんですね。
甘えやわがままではない!抱きつく癖が示す心理サイン
「いつも抱きついてくる=甘えている、わがままを言っている」と思いがちですが、実はそうとは限りません。
多角的に見ると、抱きつきにはこんな心理が隠れていることがあります。
- 安心したい気持ち:ママや信頼できる人に触れることで「大丈夫」と感じたい
- 不安や緊張を和らげる:人混みや知らない場所で抱きついて心を落ち着ける
- コミュニケーションの代わり:言葉でうまく伝えられないから「抱きつく」で気持ちを表す
つまり抱きつく癖は、子どもにとって 「助けて」「安心したい」というサイン なんです。
だからこそ、「また抱きついて!」と否定するより、「あ、安心したいんだな」と気づいてあげることが大切なんですね。
抱きつく癖が出やすい年齢・発達段階とその傾向
抱きつく癖は、特に 就学前から小学校低学年ごろ によく見られます。
この時期は、まだ自分の気持ちを言葉で表現する力が十分に育っていないため、安心したいときに「体で表現する」ことが多いんです。
- 幼児期(3〜5歳):不安や刺激が強い場面で抱きつきやすい
- 小学校低学年(6〜8歳):お友達関係が広がる中で、抱きつきがトラブルの原因になることも
- 小学校中学年以降:徐々に「言葉で気持ちを伝える」方向に移っていく子が多いが、強い不安時には再び抱きつきが出ることも
発達障害の子は、特に 感覚の感じ方や不安の大きさが人一倍強いことがある ため、抱きつく癖が長く続く場合があります。
でも、それは決して悪いことではなく、「その子が安心するための方法」として自然なことなのです。
【原因を徹底解説】なぜ発達障害の子に抱きつく癖が多いのか?
「どうしてうちの子はこんなに抱きついてくるんだろう?」
そう思ったことはありませんか? 実は、抱きつく癖にはちゃんとした理由があります。
発達障害の子の場合、感覚の特性や心の安心の求め方 が普通の子より少し違うことがあって、それが抱きつき行動につながることが多いんです。
ここでは、その代表的な原因をひとつずつ見ていきましょう。
感覚過敏・感覚探求が影響する「触覚・固有感覚」の特性
発達障害の子には、感覚がとても敏感だったり、逆に強い刺激を求めたりする特徴 があることが多いです。
- 触覚の過敏さがある子は、ふわっとした触れ方が苦手でも「ギューッ」と強く抱きしめられると安心できることがあります。
- 固有感覚(体の動きや圧力を感じる感覚)を求める子は、強い抱きつきで「自分の体の位置」を確かめて落ち着くことがあります。
つまり、抱きつく癖は「ただの甘え」ではなく、感覚を調整するための工夫なんです。
これは大人でいうと「ストレスがたまったら肩をぎゅっと押してもらうと落ち着く」感覚に近いかもしれません。
不安や緊張を和らげる自己調整行動としての抱きつき
発達障害の子は、知らない場所や初めての人との関わりなど、不安や緊張を感じやすい場面で抱きつくことがあります。
これは「セルフコントロール(自己調整)」の一種で、自分で不安を和らげようとする行動なんです。
- 初めての集団に入るときにママにしがみつく
- 大きな音がしたときに友達や先生に抱きつく
このような抱きつきは、「怖いよ、安心させて」というサインでもあります。
大人から見ると突然でびっくりしますが、子どもにとってはとても大事な「安全確認」なんですね。
愛着形成や安心を求めるコミュニケーション手段
抱きつく癖は、子どもがママや周りの人に 「大好き」「安心したい」 と伝えるコミュニケーションのひとつでもあります。
特に言葉で自分の気持ちを伝えるのが難しい子にとっては、抱きつくことが「言葉の代わり」になるんです。
たとえば――
- 「不安だからそばにいてほしい」
- 「一緒にいると安心するよ」
- 「ママ、大好き!」
こうした気持ちを表す手段が「抱きつき」なんですね。
大人の私たちも、親しい人にハグされたら安心するのと同じ。子どもにとってもそれは自然な行動なんです。
他の行動特徴(揺れる・手をつなぐ等)との関連性
発達障害の子は、抱きつく癖だけでなく、「体を揺らす」「手をつなぎたがる」「物を握る」といった行動をすることもあります。
これらはまとめて「自己調整行動」と呼ばれることが多く、安心感を得るための方法なんです。
- 体を前後に揺らすことでリズムを作って落ち着く
- 手をつなぐことで「つながり」を感じて安心する
- 固いものを握ることで緊張をほぐす
つまり、抱きつきもこれらの行動と同じように、自分の心と体を落ち着けるための行動のひとつと考えると分かりやすいでしょう。
専門家が解説する抱きつく癖の肯定的な意味
発達支援の専門家は、「抱きつく癖は子どもが自分を落ち着けるために身につけた力」と捉えることが多いです。
一見すると「困った癖」に見えるかもしれませんが、自分なりに安心できる方法を見つけられたという点では、とても大切な成長の一歩でもあります。
もちろん、場面によってはトラブルの原因になることもあります。
でも、「抱きつきたい気持ち=安心を求めているサイン」と理解すれば、ママも子どもも少し気持ちが楽になるはずです。
【困りごと】抱きつく癖が引き起こす日常生活の課題
抱きつく癖は子どもにとって安心するための行動ですが、実際の生活の中ではちょっと困った場面を生むこともあります。
「かわいいけど大変」「理解してるけど正直しんどい」と感じるママも少なくありません。ここでは、よくある困りごとを整理してみましょう。
家庭での困りごと|常に抱きつかれママが疲れてしまう
家の中でママにベッタリ抱きついてくるのは、一見「甘えん坊でかわいいな」と思えるかもしれません。
でも、毎日ずっと抱きつかれるとママの体も心も疲れてしまうんですよね。
- 料理中に後ろから抱きつかれて手が止まる
- トイレに行くときも「待ってて!」と泣かれる
- 夜も離れず、ずっとくっついていないと眠れない
こうした場面が積み重なると、ママが「自由な時間がない」「息がつまる」と感じてしまうこともあります。
「かわいいけど正直つらい」――そんな気持ちになるのは自然なことなんです。
保育園・学校での困りごと|友達や先生とのトラブル例
園や学校でも抱きつく癖は出やすく、時にはお友達とのトラブルにつながります。
- 突然お友達に抱きついて驚かせてしまう
- 遊んでいる最中にギューッと抱きついて相手が嫌がる
- 先生にしがみついて離れず、活動に参加できない
子どもにとっては「大好き!」「一緒にいたい!」という気持ちでも、相手からすると「やめて!」と感じることもあります。
その結果、友達から距離を置かれてしまったり、先生から注意されてしまうこともあるんです。
これは、子どもにとってもママにとってもつらい経験になりがちですね。
公共の場での困りごと|見知らぬ人に抱きつくリスク
スーパーや公園など、公共の場でも抱きつく癖が出ることがあります。
特に発達障害の子は「相手が誰か」よりも「自分が安心できるかどうか」で行動することが多いので、知らない人に突然抱きついてしまうこともあります。
- スーパーで近くにいた人に抱きついてしまった
- 公園で初めて会った子にギューッとする
ママとしては「すみません!」と謝る場面が増え、冷や汗ものですよね。
さらに、相手によってはびっくりして嫌な反応をされることもあり、人間関係のトラブルにつながるリスクもあります。
周囲の誤解や否定的な反応が子どもに与える影響
抱きつく癖は子どもなりの安心のサインですが、周囲からは誤解されやすい行動でもあります。
- 「甘やかされているんじゃない?」
- 「わがままだからやめさせたほうがいい」
- 「もう大きいのに抱きつくなんて変だね」
こうした言葉や態度に、ママは心を痛めることがあるでしょう。
そして何より、子ども自身が「自分はダメなんだ」と感じてしまう危険性もあります。
本来は安心したいだけなのに、周囲から否定されると自己肯定感が下がりやすいんですね。
ママ自身のストレスや罪悪感への影響
一番身近で抱きつかれるママは、どうしても影響を受けやすいものです。
- 「また抱きつかれた…もう疲れた」
- 「他の子はできてるのに、なんでうちの子は…」
- 「ちゃんと支えてあげられてないのかな?」
こんなふうに、ストレスと罪悪感が同時に押し寄せてくることもあります。
でも、これは決してママのせいではなく、子どもの特性からくる自然な行動なんです。
大切なのは、「困った行動」としてだけ見るのではなく、どう支えれば子どももママもラクになるかを一緒に考えることです。
【対処法】抱きつく癖を叱らず支える支援アプローチ
「やめなさい!」と言いたくなる場面もあるけれど、抱きつく癖は子どもが安心を求める行動です。
だからこそ、頭ごなしに否定するのではなく、子どもの気持ちを理解しつつ、少しずつ別の方法を身につけていけるように支援することが大切です。
ここでは、家庭でもすぐ実践できるアプローチを紹介します。
「やめさせる」ではなく「気持ちを受け止める」対応が大切
まず大切なのは、抱きつき行動を「悪い癖」と決めつけないことです。
子どもは「抱きつきたい」というより、「安心したい」「つながりたい」という気持ちを抱いているのです。
- 「やめなさい!」と叱る → 子どもは不安が増して、ますます抱きつく
- 「安心したいんだね」と受け止める → 子どもは気持ちが落ち着き、次のステップに進みやすい
つまり、「ダメ!」より「気持ちはわかったよ」と受け止めることが支援の第一歩です。
抱きつきたい気持ちを代替する方法を用意する
子どもの気持ちを理解したうえで、抱きつきの代わりになる方法を用意してあげると安心につながります。
「抱きつき=落ち着く」を「別の方法でも落ち着ける」に少しずつシフトしていきましょう。
クッション・ぬいぐるみを抱かせる工夫
子どもが安心できるクッションやぬいぐるみを「安心アイテム」として渡すと、抱きつきたい欲求を安全に満たすことができます。
お気に入りのキャラクターや肌触りのよい布製品だと効果的です。
- 家ではソファに「抱きぐるみ」を置いておく
- 外出時は小さめのぬいぐるみを持ち歩く
こうした工夫は「ママじゃなきゃダメ!」という気持ちを少し和らげてくれます。
「ハグタイム」を決めて予測可能にする
「今すぐ抱きつきたい!」という衝動を落ち着けるには、「後でできる」ことを見通せるようにするのがポイントです。
たとえば――
- 「朝起きたら1回、寝る前に1回ハグしよう」
- 「ご飯のあとにギューっとする時間をつくろう」
このように「ハグタイム」をルール化すると、子どもは安心しやすくなります。
予測可能性を持たせると、不安がぐんと減るんです。
抱きつく代わりに「タッチ」や「ハイタッチ」へ切り替え
「抱きつきたい」気持ちを否定せずに、別の形に置き換える工夫も有効です。
- ママとなら → 「ぎゅー」から「手をギュッ」へ
- 友達となら → 「抱きつく」から「ハイタッチ」へ
特に集団生活では「ハイタッチ」がオススメ。スキンシップの満足感はありつつ、相手に負担をかけにくいからです。
少しずつ「これならOKなんだ」と学んでいけます。
相手の気持ちを学べるルールを少しずつ教える方法
抱きつきは「相手が嫌がることもある」という視点を育てることも大事です。
ただし一気に理解するのは難しいので、シンプルなルールから始めるとよいでしょう。
- 「抱きつきたいときは“いい?”と聞こうね」
- 「友達は手をつなぐときだけOKだよ」
このように相手の気持ちを尊重する体験を積み重ねると、社会性の育ちにもつながります。
スモールステップで行動を変えていく支援の流れ
発達障害の子は、急な変化が苦手です。だから、抱きつき行動も少しずつ段階を踏んで変えていくことが必要です。
- まずは「ママだけに抱きつこうね」と範囲を限定する
- 次に「ぬいぐるみでも安心できるよ」と代替手段を増やす
- さらに「友達にはハイタッチにしようね」と行動を切り替える
このようにスモールステップで支援していくと、子どもも混乱せずに取り組みやすいです。
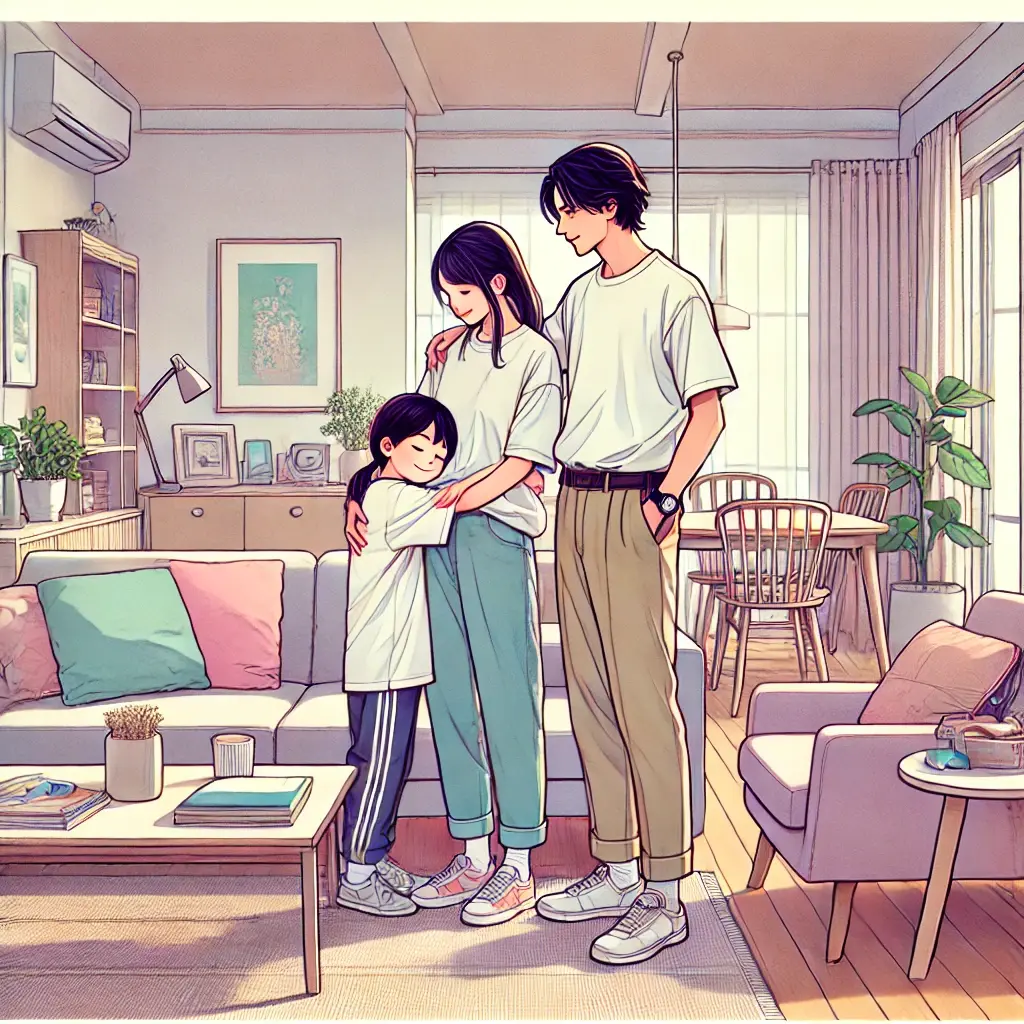
【声かけ実例】ママがすぐ使える安心できる言葉がけ
抱きつく癖は、子どもにとって「安心したい」という大切な気持ちの表れ。
でも、場面によっては「どう声をかければいいの?」と迷うこともありますよね。
ここでは、今日からすぐに使える声かけの工夫を紹介します。
難しい専門用語はなし!シンプルで分かりやすい言葉を選ぶのがポイントです。
「ダメ!」ではなく「こうしようね」で伝える工夫
子どもが抱きついてきたとき、つい「ダメ!」「やめなさい!」と言いたくなることもあると思います。
でも、この言葉は子どもに安心を与えるどころか、不安を強めてしまうこともあるんです。
そこでオススメなのが、否定ではなく「代わりの行動」を伝える声かけ。
- ✕「ダメ!友達に抱きつかない!」
- ○「友達には手をつなごうね」
こうすると、子どもは「何をすればいいのか」が分かりやすくなります。
「ダメ」ではなく「こうしよう」を意識するだけで、受け止められ方が大きく変わりますよ。
不安を和らげる安心ワードの活用
抱きつきたくなるのは、不安や緊張が強いサイン。
そんなときは、ママの言葉で「安心」を伝えてあげるのが効果的です。
「今ここにいるよ」「大丈夫だよ」
- 「ママ、ちゃんとそばにいるよ」
- 「大丈夫、大丈夫。見てるからね」
こんな短い言葉でも、子どもの安心感はぐっと高まります。
ポイントは、落ち着いた声で、ゆっくりと伝えること。
ママの声そのものが「安心のスイッチ」になることも多いんです。
行動を予告して切り替えをスムーズにする声かけ
発達障害の子は、急な変化に戸惑いやすい傾向があります。
そこで役立つのが、「これからどうするか」を前もって伝える声かけです。
「あとでギューしようね」「3回数えたらおしまい」
- 「ご飯を食べたあとにギューしようね」
- 「3回数えたらハグはおしまいね」
このように予告してあげると、子どもは気持ちの切り替えがしやすくなるんです。
予測できるだけで不安が減り、抱きつきが落ち着くこともあります。
友達関係を広げるためのモデルとなる言葉がけ
友達に抱きついてしまうのは、「一緒に遊びたい」という気持ちの表れ。
でも、相手にびっくりされてトラブルになりやすいのも事実です。
そんなときは、「こう言えばいいんだよ」という言葉のモデルを教えると役立ちます。
「手をつなごうって言ってみよう」
- 「抱きつくんじゃなくて、“手をつなごう”って言おうね」
- 「遊びたいときは“いれて”って言ってみようね」
子どもは真似して覚えるのが得意なので、具体的なセリフをそのまま伝えてあげるのが効果的です。
保育園・学校で先生に協力をお願いするときの伝え方
抱きつく癖への対応は、ママ一人では限界があります。
だからこそ、園や学校の先生と共有することがとても大切です。
お願いするときは、ただ「困ってます」と言うのではなく――
- 「安心したいときに抱きついちゃうことが多いんです」
- 「もし難しいときは“手をつなごうね”と声かけしていただけますか?」
と、子どもの気持ちと具体的な支援方法をセットで伝えると、先生も理解しやすくなります。
【家庭でできる工夫】抱きつく癖を安心に変えるアイデア
子どもの抱きつく癖は「困りごと」に見えることもありますが、家庭でちょっとした工夫をするだけで、安心感につながる習慣に変えていけます。
ママが「支援してあげよう」と身構えなくても、遊びや生活の中でできることがたくさんあるんです。ここでは、毎日の暮らしに取り入れやすいアイデアをご紹介します。
生活ルーティンに「安心できる時間」を組み込む
発達障害の子は、予測できるリズムやルーティンがあると安心しやすい特性があります。
たとえば「朝ごはんのあとにぎゅーっとする」「寝る前に必ずハグする」といったように、1日の中に“安心タイム”をあらかじめ決めておくのがオススメです。
「ママは必ずここで抱っこしてくれる」とわかると、子どもは不安なときにむやみに抱きつかなくても安心できるようになっていきます。
感覚統合あそびで体を満たし安心感を高める
抱きつく癖の背景には、感覚探求(体で強い刺激を感じたい気持ち)が隠れていることもよくあります。
そんなときは、遊びを通じて感覚を満たしてあげると、気持ちが落ち着きやすくなります。
布団でごろごろ・トランポリン・バランスボール
- 布団の上でごろごろ転がる
- トランポリンでジャンプする
- バランスボールに体をあずける
こうしたあそびは、固有感覚や前庭感覚をしっかり刺激できるので、「ぎゅっと抱きつきたい欲求」が和らぐことも多いんです。
しかも、家にあるものでできるので気軽に取り入れられますよ。
音楽・リトミックで全身を使った安心体験を増やす
音楽やリズム運動は、子どもにとって楽しいだけでなく、気持ちを落ち着ける効果もあります。
たとえば、リズムに合わせて体を動かしたり、親子で手をたたき合ったりするだけでも安心感が高まります。
「ハグ」だけが安心の方法にならないように、音楽やリズムを取り入れて“体で安心する体験”を広げていくのがおすすめです。
「スキンシップ日記」で子どもの行動を可視化する
「どんなときに抱きついてくるんだろう?」と分からなくて困ってしまうこと、ありませんか?
そんなときは、「スキンシップ日記」をつけると発見が増えます。
たとえば、
- 「朝、登園前に抱きついた」
- 「友達と遊んだあとに抱きついた」
- 「夜眠いときに抱きついた」
などを書き留めるだけでOK。
あとで見返すと、子どもの安心が必要なタイミングやきっかけが分かるので、声かけや対応がしやすくなります。
兄弟姉妹や家族全体で安心を共有する取り組み
ママひとりで抱きつきを全部受け止めるのは大変ですよね。
そんなときは、家族みんなで安心を分け合う工夫を取り入れてみてください。
- パパが「おかえりハグ担当」になる
- 兄弟が「一緒に手をつなぐ係」をする
- 家族で「ハイタッチの習慣」をつくる
こうして家族全員でスキンシップを共有できると、子どもも「ママだけじゃなく、みんなが安心をくれる」と感じられて、抱きつきが落ち着くこともあります。
【体験談】抱きつく癖と向き合った発達障害児ママの声
「うちの子だけ?」「私の関わり方が悪いのかな?」と悩むことも多い抱きつく癖。
でも、実際には同じような経験をしているママたちがたくさんいます。
ここでは、いくつかの体験談を紹介しながら、「抱きつく癖とどう向き合えばいいのか」を考えてみましょう。
「声かけを変えたら抱きつきが減った体験談」
あるママは、以前は「ダメ!やめなさい!」とつい言ってしまっていたそうです。
すると、子どもはますます不安になって、余計に抱きついてきていたのだとか。
そこで、「ダメ」ではなく「手をつなごうね」など代わりの方法を伝えるようにしたところ、徐々に抱きつきが減っていったそうです。
「言葉をちょっと変えるだけでこんなに違うんだ!」と驚いた、と話してくれました。
「ぬいぐるみに切り替えて安心できるようになった」
別のママは、子どもがとにかく抱きついてくるので、体が持たないと感じていたそうです。
そこで、お気に入りのぬいぐるみを“抱っこ相手”にする工夫を始めました。
「ギューしたくなったら、このくまちゃんを抱っこしようね」と伝えたところ、子どもはだんだんとぬいぐるみに気持ちを向けるようになったそうです。
もちろんママに抱きつくこともあるけれど、全部をママが引き受けなくてもよくなったことで、親子ともに楽になったとのことです。
「園との連携で友達とのトラブルが減った実例」
抱きつきが多いと、保育園や学校で友達にびっくりされることもありますよね。
あるママは、「友達を傷つけてしまったらどうしよう」と不安でいっぱいだったそうです。
でも、先生と一緒に“手をつなぐ”や“ハイタッチ”を練習してもらう取り組みを始めたところ、少しずつトラブルが減っていきました。
「先生に相談したら、子どもだけでなく私の気持ちもすごく軽くなった」と、ママ自身が支えられたエピソードです。
「叱らなくなって親子関係が楽になった私の実感」
「なんでこんなに抱きつくの?」とイライラして、毎日のように叱ってしまっていたママもいます。
でも、専門家の話をきっかけに「抱きつきは安心したいサインなんだ」と気づいたそうです。
それからは、叱る代わりに「どうしたの?」「ここにいるよ」と声をかけるようにしました。
すると、子どもも少しずつ安心して過ごせるようになり、ママ自身も「怒らなくていい」と思えるようになったとか。
「親子の関係が前よりずっと楽になった」と笑顔で話してくれました。
ママたちからのエール「焦らなくても大丈夫」
最後に、多くのママが口をそろえて言うのは、「焦らなくても大丈夫」ということです。
抱きつく癖はすぐにゼロになるわけではありません。
でも、子どもが安心できる方法を少しずつ見つけていくうちに、自然と落ち着いていくことも多いんです。
「完璧な対応じゃなくてもいい」
「少しずつでいい」
そんなママたちの声は、同じ悩みを抱える人にとって、大きな励ましになるはずです。

【まとめ】抱きつく癖は安心を求めるサイン|今日からできる支援法
発達障害のある子の「抱きつく癖」は、決して悪いことではありません。
むしろ、「安心したい」「気持ちを落ち着けたい」という子どもからのサインなんです。
ここでは、ママが心にとめておきたいポイントを整理していきましょう。
否定するのではなく理解して受け止めることが第一歩
まず大切なのは、抱きつく癖を頭ごなしに否定しないことです。
「困った行動だ」と思うと、つい「やめなさい!」と言いたくなる瞬間もありますよね。
でも、それは子どもにとって「安心したい気持ち」を拒否されることになってしまいます。
そこで、「どうしたの?」「ここにいるよ」と受け止める言葉をかけるだけでも、子どもはぐっと安心できます。
理解してもらえる経験は、子どもの自己肯定感を大きく育ててくれるんです。
抱きつく癖は「困りごと」ではなく「子どもの大切な個性」
抱きつく癖は、たしかに家庭や園、学校でちょっとしたトラブルにつながることもあります。
でも、抱きつくこと自体が「悪いクセ」ではありません。
それは子どもの特性であり、安心や信頼を伝える大切な表現方法なんです。
「困りごと」とだけ見るのではなく、「この子は安心を強く求める子なんだ」と理解する視点を持つことで、ママの気持ちも少し楽になります。
家庭・園・専門機関で連携して安心を支える大切さ
ママ一人で抱え込む必要はありません。
園や学校の先生、そして必要に応じて専門機関に相談することで、子どもに合った支援方法が見えてくることも多いです。
「家庭だけでは難しい」と感じたら、遠慮なく周りに頼ってみてください。
チームで子どもを支えることで、ママ自身の心も守られます。
今日から試せる声かけと工夫で少しずつ成長をサポート
大事なのは、完璧を目指すことではなく、「今日からできる小さな工夫」を積み重ねていくことです。
たとえば…
- 「あとでギューしようね」と予告をする
- ぬいぐるみやクッションを抱っこする代わりを用意する
- 「手をつなごう」と代替行動に切り替える
こんなシンプルな工夫でも、子どもは少しずつ「抱きつく以外の方法」も学んでいけます。
そして、子どもが安心して過ごせる時間が増えるほど、成長にもつながっていくのです。
以上【抱きつく癖がある発達障害の子にママができる支援と声かけ法|原因・対処法・体験談まとめ】でした。

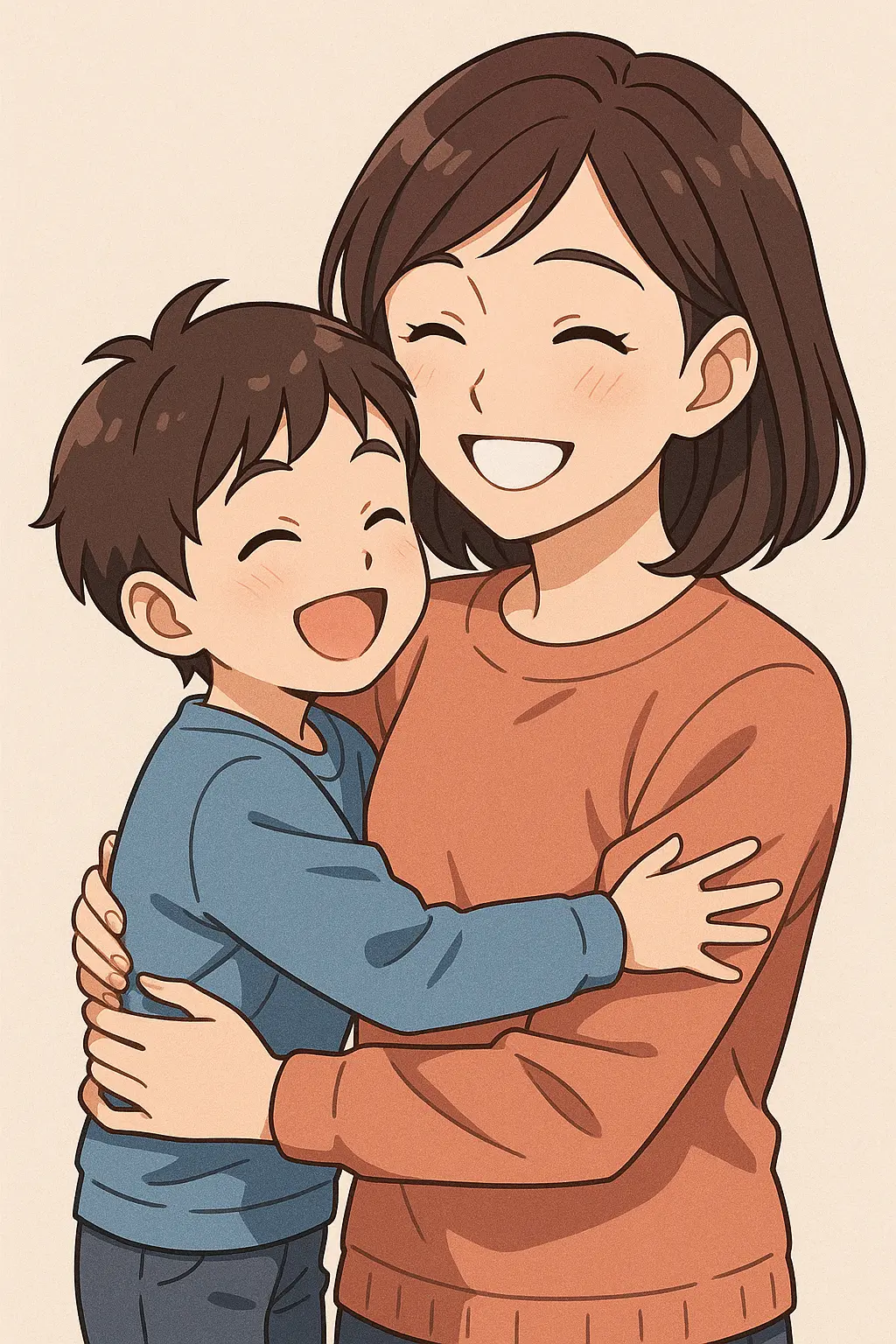









コメント