「まわりの子はもうおしゃべりしてるのに…うちの子だけ話さない。」そんなふうに感じて、不安になったことはありませんか?
自閉症のある子どもは、言葉の使い方や伝え方に、その子ならではの“ペース”や“スタイル”があるものです。でも、それは決して悪いことではありません。
この記事では、子どもが“話したくなる”関係を家庭で育てるためのヒントをわかりやすくご紹介しています。
言葉がなかなか出ないとき、親としてどう関わればいいのでしょうか?
「話してくれない…」と悩む前に知っておきたいこと
「うちの子、なんで話さないの?」
そう感じたこと、ありませんか?
自閉症の子どもと関わる中で、“話し方”や“会話のしかた”に違和感や不安を覚える保護者の方はとても多いです。周りの子が当たり前のようにおしゃべりしているのを見て、つい比べてしまったり、「このままで大丈夫かな…」と焦ってしまったり。
でも実は、それ、あなただけではありません。
自閉症の子どもたちには、それぞれ話し方の個性や表現の仕方のスタイルがあり、一見すると「話していないように見える」場合でも、実は自分なりの方法でしっかり伝えようとしていることもあります。
そして大切なのは、「話せるようにさせること」ではなく、
「話したくなる関係や環境をつくってあげること」。
このブログでは、そんな視点から、自閉症の子どもの“話す力”を育むためのアイデアや関わり方を、実践的かつ多角的にご紹介していきます。
- 自閉症の子どもによく見られる話し方の特徴って?
- 話してくれないとき、親としてどう接すればいい?
- 家庭でできる声かけや遊びの工夫ってある?
- ことばのプロに相談するベストなタイミングは?
そんな疑問に、客観的な視点と具体的なヒントを交えながら、わかりやすくお伝えしていきます。
「話さない=問題」ではありません。
それはただの「スタート地点」が違うだけ。
焦らず、ゆっくり。
お子さんの“今”を受け止めながら、一緒に“話す楽しさ”を育てていきましょう!
自閉症の子どもに多い「話し方のクセ」とは?
子どもが話すようになってくると、親としてはやっぱり「どんなふうに話すか」が気になりますよね。
とくに自閉症のある子どもたちは、話し方にちょっと独特なクセがあることも多く、最初は戸惑ってしまうかもしれません。
でも実はそれ、「話せない」のではなく、「その子なりの表現スタイル」だったりします。
ここでは、自閉症の子によく見られる話し方の特徴やパターンを、わかりやすく紹介していきます!
発語が遅い?一方的?話し方がユニークなワケ
「うちの子、まだ2語文も出てない…」
「ずーっとひとりごとみたいに話してるけど大丈夫?」
そんなふうに不安になること、ありますよね。
実は、自閉症のある子どもは、発語がゆっくりだったり、話し方が一方的になる傾向があります。
でもそれは、「発達が遅れている」というよりも、脳の情報処理のしかたや感覚の受け取り方が独特だからなんです。
たとえば…
- 順番に会話をするという“ターン交代”が難しい
- 自分の興味のあることを一方的に話すのが好き
- 相手の表情や空気を読むのがちょっと苦手
など、いくつかの要因が重なって、“ちょっとユニークな話し方”につながっていることがあります。
これって決して「悪いこと」ではなく、その子の個性。
まずは、「なぜそういう話し方になるのか?」という背景を知ることで、関わり方がぐっと楽になりますよ。
「あれ?なんか違う?」と感じる話し方のタイプ別特徴
オウム返し、単語だけ、表情がない…でも全部“意味がある”表現!
自閉症の子の話し方って、一見「普通と違う?」と思うこともありますが、それぞれにちゃんと理由があるんです。以下のような特徴がよく見られます。
■ オウム返し(エコラリア)
たとえば「ごはん食べる?」と聞くと、「ごはん食べる?」とそのまま返してくる。
これ、ただ真似してるわけじゃなく、言葉を覚えようとしていたり、安心感を得るための行動なんです。
■ 単語だけで話す
「りんご」「バス」など、名詞だけポツンと発するパターン。
文にはなっていなくても、ちゃんと“伝えたい気持ち”がある証拠。言葉の種を育てている段階です。
■ 声に抑揚がない、表情が乏しい
話していても感情がこもっていないように見えることも。
でもこれも、感情がないわけじゃなく、表現方法が苦手なだけ。心の中にはちゃんと気持ちがあるんです。
こうした特徴を「変だな…」と捉えるのではなく、
「そういう伝え方をしてるんだ」と理解することが大切です。
見方を変えるだけで、ぐっと子どもとの関係が良くなりますよ!
こんなにある!保護者が感じやすい“話し方の不安”
子どもの話し方について心配している保護者の方って、本当にたくさんいます。
特に自閉症のある子どもと向き合っていると、「うまく話せない=問題かも?」と不安になることもあると思います。
でも実はその悩み、とても自然なものなんです。
ここでは、保護者が感じやすい“話し方の不安”と、そこに隠れた視点のズレや気づきのヒントをわかりやすく紹介していきます!
「なんで話さないの?」が不安になるときに知ってほしいこと
「なんでこの子は話さないんだろう…」
「もう○歳なのに、単語も少ないのはやっぱりおかしい?」
そんなふうに感じたとき、つい「話さない=何か問題がある」と思ってしまいがちですよね。
でもここで一度立ち止まって考えてみてほしいのが、
“話す”という行動は、実はすごく高度なスキルだということ。
- 相手に関心を向けて
- 気持ちを言葉にして
- タイミングをはかって話す
…というプロセスが必要なので、どの子も一律にできるわけじゃないんです。
さらに、自閉症のある子は視覚優位(見て理解する力が強い)だったり、感覚過敏があったりするので、言葉を扱うのがちょっとハードル高く感じていることも。
つまり、「話さない」のではなく、「今は話しにくい状況にいるだけ」かもしれません。
発達のタイミングもペースも、一人ひとりちがっていいんです。
頑張らせすぎてない?話すことを「強制」しない関わり方
「ちゃんと話して」「それ何?言ってごらん」
親としてはつい、“言葉を引き出そう”と頑張ってしまうこと、ありますよね。
でもその気持ち、ときに子どもにとってプレッシャーになることもあるんです。
自閉症の子どもは、「今すぐ言葉にする」のが難しいことが多いので、急かされたり求められたりすると、かえって沈黙してしまうことも。
大事なのは、「話させる」ではなく「話したくなる環境をつくる」という視点。
たとえば…
- 子どもが好きな遊びに夢中になっているときに、さりげなく言葉を添えてみる
- 絵カードや写真を使って「これ、何だっけ?」と興味を引き出す
- 会話が出てきたら、中身より“話せたこと”を褒める
このように、安心して“話す”ことにトライできる空気をつくることが、最初の一歩になります。
会話=言葉だけじゃない!伝える力は話す以外にもある
そもそも、「話す」って本当に言葉だけなんでしょうか?
答えはNO。
子どもたちは、言葉が出なくてもさまざまな方法で“伝える”力を持っています。
たとえば…
- 指差しで「これちょうだい」と訴える
- 視線で好きなものを示す
- 絵カードや身振りで自分の気持ちを伝える
これらは全部、立派な“コミュニケーション”なんです。
そして実は、こうした非言語のやりとりを丁寧に受け止めていくことで、「伝える楽しさ」→「話したくなる」という流れにつながっていきます。
言葉が出ていない時期こそ、“伝えたい”気持ちを育てるチャンス。
話す=言語にとらわれすぎず、「今、どんな方法で伝えてくれているか?」に目を向けてみましょう。
【保存版】自閉症の話し方を伸ばす!家庭でできる5つの工夫
「どうやったらもっと話してくれるのかな?」
「うちでも何かできること、ないかな?」
そんなふうに思ったこと、ありますよね。
実は、家庭の中でできる小さな工夫が、子どもの“話す力”を育てるきっかけになることがたくさんあるんです!
ここでは、毎日の生活の中で取り入れやすい、5つの関わり方のポイントをご紹介します。
無理なく、楽しく。子どものペースで、“話す楽しさ”を一緒に育てていきましょう!
① まずは親が“まねっこ”!オウム返しの魔法
「バナナ」と言ったら「バナナだね」
「ブーブー」と言ったら「ブーブーきたね」
…これ、ただの“くり返し”に見えるかもしれませんが、実はとっても大事な関わりなんです。
自閉症の子は、言葉のキャッチボールがまだうまくできないことが多いですが、親が“オウム返し”してあげることで「通じた!」という感覚が育っていきます。
さらに、オウム返しを通じて言葉の音やリズム、意味を整理して覚えていくという学びにもつながるんです。
ここでのポイントは、「正しい言葉に直す」より「そのまま返す」ことを意識すること。
子どもの世界に寄り添う姿勢が、安心感につながります。
②「見せる×話す」で伝わる!動作と言葉をセットにしよう
言葉だけで説明しても、伝わりにくいことってありますよね。
自閉症の子は特に、「耳で聞くより、目で見る」方が得意なことが多いです。
たとえば…
- 「お風呂入ろうね」と言いながらお風呂を指さす
- 「りんご食べようね」と言って実物を見せる
- 「手、洗おう!」と言いながら実際に洗って見せる
こうやって、“ことば”と“実際の動作”をセットで伝えることで、言葉の意味を体感的に理解しやすくなるんです。
また、手遊び歌や絵本の読み聞かせなども、「見て・聞いて・動いて」覚えられるので効果的ですよ!
③ 会話のキャッチボールを育てる「ターン交代」練習法
自閉症の子どもにとって難しいのが、「順番にやりとりをする」という感覚。
会話って、言葉のやりとり=“ターン交代”の積み重ねなんですよね。
でも、いきなり「順番を守ろう!」と言っても、ピンとこない子が多いのが現実。
そこで役立つのが、遊びや生活の中でターン交代を体験する方法です。
たとえば…
- おもちゃを交代で動かす
- ボールを投げ合う
- 「どうぞ」「ありがとう」をやり取りする遊び
こんなふうに非言語のやりとりから始めて、徐々に言葉のターンへつなげていくことで、会話のリズム感覚が自然と育ちやすくなります。
④ 話せたことを全力でほめよう!自信を育てる声かけ術
話せた言葉がどんなに短くても、どんなにぎこちなくても、「話せたこと」そのものを大切にする声かけがとても大事です。
たとえば…
- 「バス!」→「バスって言えたね、すごい!」
- 「みず」→「お水ほしかったんだね、教えてくれてありがとう」
このように、言葉の内容よりも、“伝えようとした姿勢”を肯定してあげることで、子どもは自信をつけていきます。
逆に、「もっとちゃんと言って」「それじゃわからないよ」といった言葉は、せっかくのチャレンジを否定してしまうこともあるので要注意。
“うまく話す”より“話そうとしている”ことをしっかり受け止めることが、次の一歩につながるんです。
⑤「話したい!」を引き出すしかけと工夫アイデア集
「話しなさい」ではなく、「話したくなる」工夫をしてみませんか?
子どもが思わず声を出したくなるような“しかけ”を日常にちょこっと仕込むだけで、会話のきっかけが増えます。
おすすめの工夫としては…
- 選択肢を見せて「どっちにする?」と聞く
- 絵カードや写真を使って「これ、何かな?」とやりとり
- 音が出るボタンや録音マイクなど、遊びの中で言葉を楽しめるアイテムを使う
- 大人がわざと間違えて「これバナナでいい?」と笑わせてみる
こうした工夫で、「伝えたい!」「つたわった!」という体験が積み重なっていくと、
言葉を使うことそのものが“楽しい”と感じられるようになります。
迷ったらここ!言葉のプロや支援サービスの上手な頼り方
「このまま様子を見て大丈夫かな?」
「病院?療育?誰に相談すればいいの?」
そんなふうに迷ってしまったとき、ひとりで抱え込まなくて大丈夫です!
実は、子どもの言葉の発達やコミュニケーションに関する相談ができる場所や専門家はたくさんあります。
ここでは、「そろそろ相談してみようかな」と思ったときに役立つ情報や、支援機関との上手な付き合い方を紹介します。
①「様子見でいいの?」相談すべきタイミングとは
「もうちょっと様子を見ようかな」
「まだ小さいし、そのうち話すかも…」
そう思ってしまうのは、親としてごく自然な感情です。
でも、もしあなたが今、「なんとなく気になる」レベルの不安を感じているなら、すでに相談のタイミングかもしれません。
実は、支援の世界では「困ってから相談」よりも、
「困る前にゆるく相談する」ことのほうが大切と言われています。
相談することで…
- 子どもの現状を客観的に見てもらえる
- 自宅でできる具体的な関わり方がわかる
- 親自身の気持ちがラクになる
…と、メリットがたくさん。
しかも、相談したからといって「療育が必要」と決まるわけではありません。
「今は様子を見ながら、こんな関わりをしてみましょう」というアドバイスだけでも十分価値があるんです。
②ことばの訓練って何をするの?療育の現場レポート
「療育って具体的に何をしてくれるの?」
「“言葉の訓練”って厳しそう…」と思っている方も多いかもしれませんが、実はそんなに構えなくても大丈夫です。
たとえば、言語聴覚士(ST)や発達支援の専門スタッフは、子どもの「今の力」に合わせて、遊びの中で自然に言葉を引き出す関わりをしてくれます。
具体的には…
- おもちゃを使った模倣あそびで発語を促す
- 絵カードを使って「ことば」と「意味」をつなげる
- 会話のやりとり(ターン交代)の練習
- 表情・ジェスチャーも使った非言語コミュニケーションの強化
など、堅苦しい「訓練」というより、子どもが楽しく取り組める工夫がたくさんあります。
また、保護者へのフィードバックも丁寧にしてもらえることが多いので、家での接し方に自信が持てるようになる人も多いんです。
③地域にある“頼れる場所”を知っておこう
いざ相談したいと思っても、「どこに行けばいいの?」という疑問、ありますよね。
そんなときのために、地域で利用できる支援の窓口をいくつかご紹介します。
■ 市区町村の発達相談窓口(子育て支援課など)
→ 初期相談の入り口。発達の心配事について話せる場。
まずはここに電話してみるのが安心です!
■ 発達支援センター・療育センター
→ 専門スタッフによる評価や支援計画、療育の紹介などが受けられる。
相談だけでもOKなので、気軽に問い合わせを。
■ 児童発達支援事業所
→ 未就学の子どもが通う支援施設。遊びながら言葉や社会性を育む。
送迎あり・少人数制のところも多く、通いやすいのが魅力。
■ 保健センター・乳幼児健診での相談
→ 健診で気になることがあれば、そのまま支援につながることも。
「相談してもいいのかな?」くらいの感覚でOKです。
こうした場所を知っておくだけでも、いざというときに動きやすくなりますし、「一人じゃない」と感じられるはず。
「頼ること」は、子どもの未来への第一歩。
専門家の視点を借りながら、親子で一緒に“話す力”を育てていきましょう。
親だからこそできる!話す力を引き出す関わり方
自閉症の子どもの“話す力”を育てるうえで、家庭での関わり方って本当に大きなカギになります。
もちろん、専門家の支援もとても大切。でも、それと同じくらい大事なのが、毎日いちばん近くにいる家族のまなざしや声かけなんです。
ここでは、親だからこそできるサポートと、そのために知っておきたいポイントをお伝えします。
①「話せる日は必ず来る」焦らず見守る大切さ
つい、まわりの子と比べて焦ってしまうこと、ありますよね。
でも大丈夫。「言葉が出るタイミング」は、本当に人それぞれです。
自閉症の子どもは、言葉よりもまず「視覚」や「感覚」など、他の手段で情報を処理することが得意なタイプが多いんです。
つまり、言葉が出るまでにちょっと時間がかかるだけ。
だからこそ大切なのは、「いつかきっと話すようになる」と信じて、安心して見守る姿勢なんです。
実際、周囲が焦らずに接していると、子どももリラックスして、「話そう」とする意欲が高まりやすくなります。
“育つチカラ”は、安心感の中でこそ伸びる。その土台をつくれるのは、やっぱり親の存在です。
② 実は逆効果!やってしまいがちなNG対応3選
良かれと思ってやっていることが、実は子どもをプレッシャーでいっぱいにしていた…なんてこと、意外と多いんです。
ここでは、ありがちな“やってしまいがち”な対応を3つピックアップしてみました。
■ NG①「もっとちゃんと話して!」と求めすぎる
→ 子どもにとっては“ちゃんと話す”のハードルが高すぎる場合も。
言葉が出たときは、内容よりも「話せた!」を喜びましょう。
■ NG②「どうしてできないの?」と問い詰める
→ 本人にとっても理由がわからないことが多いです。
“できない理由”より、“できた瞬間”を見つけてあげて。
■ NG③「○○くんはもうしゃべってるよ」と比べる
→ 比較されると、自信がなくなってさらに話しにくくなることも。
その子のペースを尊重する言葉かけが大切です。
NG対応に気づけたときがチャンス!
今日から変えていけば、関わりはどんどん良い方向へ進みますよ。
③ 家族全員が“味方”になると子どもは話したくなる
「お母さんだけが頑張ってる…」なんて状態、よくありますよね。
でも実は、家族みんながちょっとずつ意識を変えるだけで、子どもはぐっと安心して話しやすくなるんです。
たとえば…
- お父さんも一緒に絵本を読んであげる
- きょうだいが「○○って言ってたよ」と通訳役になってくれる
- 祖父母が子どもの言葉をじっくり聞いてくれる
こうした小さな積み重ねが、「話していいんだ」「ちゃんと聞いてくれる人がいる」という安心感につながります。
言葉って、ひとりで育つものじゃないんです。
まわりに“聞いてくれる人”“寄り添ってくれる人”がいるからこそ、子どもは「話してみよう」と思えるようになります。
★まとめ:親の関わりは、言葉のチカラを育てる“最強のサポーター”
自閉症の子どもの話し方には、ひとりひとり違ったペースと形があります。
その“違い”を理解し、温かく、肯定的に関わることが、子どもの「話したい気持ち」を大きく育てるんです。
焦らず、比べず、寄り添って。
その姿勢が、子どもの言葉をそっと後押ししてくれますよ。
話さないのは“個性”のひとつ。少しずつ育てていこう
子どもの「話し方」や「言葉の発達」は、どうしてもまわりと比べたくなってしまうもの。
でも忘れてはいけないのは、“話さない”ということ自体が悪いわけじゃないということ。
自閉症のある子どもたちは、自分なりのペースやスタイルでコミュニケーションを育てているだけなんです。
もちろん、言葉が出ないことに不安を感じるのは当然ですし、「どうすればいいの?」と悩む日もあると思います。
でもそんなときこそ大切なのは、焦らず、比べず、楽しみながら関わっていくこと。
家庭の中でできるちょっとした工夫や、専門家のサポートをうまく使いながら、
「話せるようになる」ではなく「話したくなる」関係や環境を育てていくことが、子どもの言葉の力を引き出す大きなカギになります。
そしてなにより、子どもにとってのいちばんの安心材料は、
親の笑顔と「あなたのままで大丈夫だよ」というメッセージ。
親の笑顔は、子どもにとって最高の“ことばの種”になるんです。
小さな一歩でも大丈夫。今日から、できることから少しずつ始めてみませんか?
きっとその積み重ねが、子ども自身の「伝えたい」という気持ちを育てていきますよ。
さいごに
この記事では、自閉症のある子どもに見られやすい話し方の特徴や、親として感じやすい不安、家庭でできる5つの関わり方の工夫(オウム返し・見せる×話す・ターン交代など)、支援機関の活用方法についてお伝えしました。
なにより大切なのは、「話させること」より「話したくなる関係や環境づくり」。
焦らなくて大丈夫。言葉の芽は、安心の中でゆっくり育っていきます。
ご家族の笑顔とまなざしが、きっとお子さんの“ことばの種”を育ててくれます。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

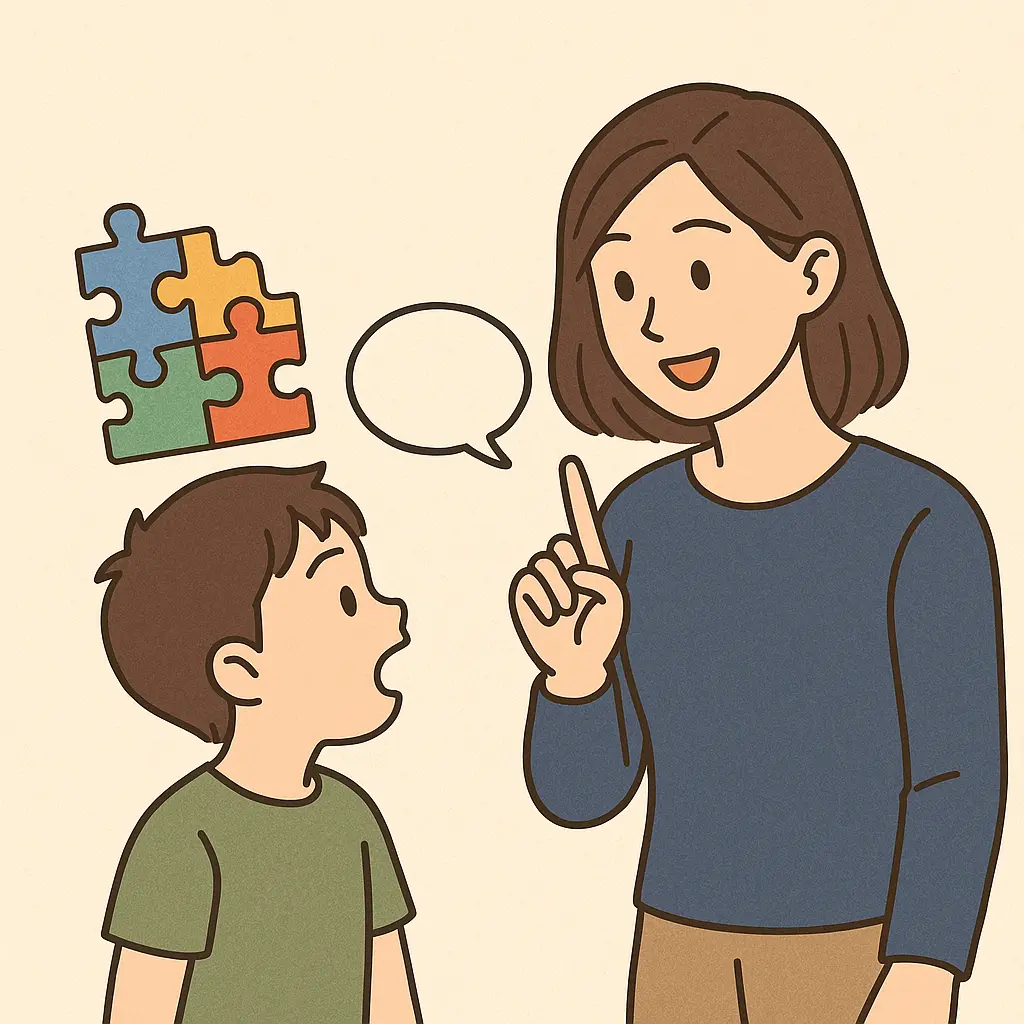









コメント