はじめに~もう悩まない!癇癪対応に効いた“手作りアイテム”の力とは?
「また癇癪(かんしゃく)…どうしたらいいの?」
そんな風に、わが子の突然の爆発に戸惑った経験、ありませんか?
自閉症の子どもを育てていると、理由がはっきりわからない怒りや泣き叫び、物を投げるといった“癇癪”に直面することがよくあります。最初は「わがままなのかな?」と思っていたけれど、よくよく観察してみると、「うまく言えない」「伝わらない」不安や、感覚の過敏さ、環境の変化」など、さまざまな要因が複雑に絡んでいることが見えてきます。
でも、だからといって、すぐに落ち着かせる魔法の言葉があるわけでもありません。
親としてできるのは、「この子が少しでも落ち着ける方法」をひとつずつ探していくこと。
そんな中で見つけたのが、“手作りお助けアイテム”という身近な工夫でした。
高価な療育グッズじゃなくても、100均で揃う素材や家にあるもので、子どもに合った癇癪対策ができるんです。
もちろん、どんなアイテムも「これさえあれば絶対大丈夫!」という万能グッズではありません。
でも、「これがあると少し気持ちが落ち着く」「癇癪の前兆に気づきやすくなった」「自分で気持ちをコントロールできるようになった」――そんな小さな変化を、私たち親子は実感してきました。
このブログでは、実際に試して「効果があった!」と感じた手作りアイテムを、作り方・使い方・活用のコツまで詳しく紹介します。
また、「なぜそれが効くのか?」という視点から、発達特性や感覚の違い、行動心理などにも軽く触れながら解説していきます。
癇癪への対応に悩むママ・パパたちが、「あ、これ試してみたい!」と気軽に思えるようなヒントを詰め込みました。
育児の正解はひとつじゃないからこそ、手作りという“柔軟さ”が武器になるかもしれません。
「できることから、気楽に試してみよう」
そんな気持ちで読み進めてもらえたらうれしいです。
癇癪の原因を知れば対応が変わる!自閉症の子がパニックになるワケ
自閉症のある子どもが癇癪を起こすと、つい親も一緒にパニックになってしまいがち。でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。「なぜ癇癪を起こすのか?」を知ることができたら、少し違った対応ができるかもしれません。
ここではまず、「癇癪ってそもそも何?」という基本から、よくあるトリガー(きっかけ)、そして事前にできる予防策までをわかりやすく紹介していきます。
【基礎知識】「癇癪」とは?自閉症の子に多い理由
癇癪(かんしゃく)という言葉、よく耳にするけど、改めて「どういう状態なの?」と聞かれると、意外と答えるのが難しいですよね。
簡単に言うと、「感情の爆発」。怒り・悲しみ・不安・フラストレーションがあふれ出して、泣いたり叫んだり、物を投げたりしてしまう状態です。自分で気持ちをうまく言葉にできなかったり、感情のブレーキがききにくくなっているときに起こりやすいんです。
特に自閉症の子どもたちは、以下のような特徴から癇癪が起こりやすいと言われています:
- 感覚の過敏さ(音・光・匂い・触覚などへの反応が強い)
- 予定の変化に弱い・見通しが立たないことが苦手
- ことばで気持ちをうまく伝えるのが難しい
- 「ねばならない」こだわりが強い傾向がある
つまり、環境や人とのやりとりにストレスを感じやすく、それが処理しきれなくなると癇癪につながるということなんです。これは「わがまま」ではなく、脳の特性によるものだと考えると、見方が変わってきますよね。
【あるある】子どもが癇癪を起こす“きっかけ”ランキング
「またか…」「どうしてここで怒るの?」
そんなふうに思ってしまう場面、実は多くの親が経験しています。癇癪にはパターンがあることも多く、よく観察してみると「きっかけ」が見えてくることがあります。
ここでは、自閉症の子どもによく見られる“癇癪のトリガー”をランキング形式で紹介します。
第1位:予定の変更・先が見えない不安
→ 例:「今日は公園行くって言ったのにスーパー!?」
→ 見通しがないと不安でいっぱいに。スケジュールカードや口頭予告が効果的!
第2位:大きな音・まぶしい光などの感覚過敏
→ 例:「掃除機の音で耳をふさいでパニック」「人混みで大暴れ」
→ 感覚刺激に対する“備え”が大事。イヤーマフなどの対策も◎
第3位:伝えたいことが伝わらないストレス
→ 例:「おやつが欲しいのに言えなくて怒る」
→ コミュニケーションカードなど、代替手段がカギ
第4位:思い通りにならない悔しさ・ルール違反へのこだわり
→ 例:「順番を抜かされてパニック」「赤じゃないとダメ!」
→ こだわりは“安心のサイン”と理解して対応を工夫する
第5位:疲れ・空腹・眠気など身体的な要因
→ 例:「お昼寝前にぐずる」「帰宅後に突然爆発」
→ 体調や生活リズムの見直しで改善するケースも多数
「うちの子にもこれ当てはまるかも…」というポイントがあったら、その場面に備えた工夫を用意することで癇癪の頻度がグッと下がることがありますよ。
【対策の基本】癇癪が起きる前にやっておくべき準備とは?
癇癪対応の最大のコツは、実は「起きてからどうするか」ではなく「起きる前にどう備えるか」にあります。いわゆる“予防”という考え方ですね。
たとえば:
- スケジュールカードや一日の流れの見える化 → 予定変更も安心感を持って受け入れやすくなる
- 感覚過敏に備えたグッズの持ち歩き → イヤーマフ・サングラス・触り心地のいいガーゼなど
- 癇癪の前兆を見逃さない“観察”の習慣 → 眉間にしわ・ソワソワ・急に無口…などのサイン
- 「気持ちの伝え方」を普段から練習 → 絵カードや“気持ちメーター”を取り入れるのも◎
また、親の側も「癇癪=悪いこと」ではないと捉えなおすことがとても大切です。
「癇癪は“助けて”のサイン」「まだ言葉でうまく伝えられないSOS」と考えることで、冷静な対応につながりやすくなります。
効果バツグン!癇癪を和らげた「手作りお助けアイテム」BEST6
「癇癪対策にいいって聞くけど、うちの子に合うのかな…?」
そんなふうに悩んでいた私が実際に試してみて、「これはよかった!」と実感できた“手作りお助けアイテム”を6つご紹介します。
どれも特別な道具や高価なグッズは必要なく、100均や自宅にあるもので手軽に作れるものばかり。しかも、ただのおもちゃではなく、子どもの感情・感覚・行動に寄り添う仕掛けが詰まったアイテムです。
それぞれの特徴や使い方、どんなタイプの子に合いやすいのかも客観的な視点でまとめています。あなたのお子さんに合いそうなアイテム、ぜひ見つけてみてくださいね。
感情を伝えやすくする「おちつくカード」
「なんで泣いてるの?」「どうして怒ってるの?」に答えられない子、多いですよね。
このカードは、子どもが今の気持ちを視覚的に選んで伝えられるようにするためのアイテムです。
たとえば「かなしい」「くやしい」「つかれた」など、子どもが言葉にしにくい感情をイラストや写真で表現し、カードとして並べておきます。
癇癪の前兆が見えたら「どれかな?」とカードを見せてあげるだけで、気持ちを“伝える手段”ができて落ち着く子が多いんです。
✔ おすすめポイント:
- 言葉が出にくい子や、感情表現が苦手な子に◎
- 大人も気持ちの変化に気づきやすくなる
✔ 材料:画用紙/写真/100均のラミネートシートなどでOK!
✔ 応用例:登園前やおやつ前など、トラブルが起こりやすいタイミングに事前提示するのも効果的です。
見ているだけでスーッと落ち着く「おちつきボトル」
キラキラとゆっくり沈んでいくビーズやラメ…。この視覚的な刺激に癒される子、多いんです。
「おちつきボトル」は、洗濯のり+水+ラメやビーズを入れたペットボトルで作る、簡易スノードームのようなアイテム。
子どもにとっては“じーっと眺めているだけで安心する”“気持ちが切り替わるスイッチ”のような存在になります。
✔ おすすめポイント:
- 感覚刺激に過敏な子や、視覚優位(見ることが得意)な子にピッタリ
- 癇癪後のクールダウンにも使える
✔ 材料:ペットボトル・洗濯のり・水・ビーズ・ラメなど(すべて100均で揃う)
✔ 注意点:フタをしっかり接着して安全に(接着剤やグルーガンがおすすめ)
かむことでスッキリ!「かみかみキューブ」
怒りや不安がたまったとき、無意識に指をかんだり服の袖をしゃぶったりする子、いませんか?
それって、実は口からの感覚刺激を求めているサインかもしれません。
そんな子におすすめなのが、安心してかめる素材で作った「かみかみキューブ」です。シリコンやガーゼ、フェルトなどで作り、口でグッと噛むことで気持ちが落ち着く子も多いです。
✔ おすすめポイント:
- 口に何か入れる癖がある子に
- ストレスが口に出やすい子に“安心のはけ口”を用意できる
✔ 材料:食品グレードのシリコン、フェルト、布など
✔ 応用例:お出かけ時のバッグに忍ばせておくと安心感◎
ここに入れば安心♪「手作り安心スペース」
「もう無理!」「ここから逃げたい!」と思ったとき、安心して避難できる場所があるだけで、癇癪が起こる回数がグッと減る子もいます。
段ボール・突っ張り棒・カーテンなどで作れる「安心スペース」は、子どもにとっての“自分だけの隠れ家”。
外部からの刺激をシャットアウトできる空間で、気持ちが整理できる時間を確保してあげましょう。
✔ おすすめポイント:
- 刺激に敏感な子、感情のコントロールが難しい子に効果的
- 自分で「そこに行けば落ち着ける」と理解できれば大成功
✔ 材料:段ボール・布・カーテン・クッションなど自由
✔ 注意点:ただの遊び場にならないよう、「落ち着きたい時に使う場所」としてルールを共有
手を動かすだけで気持ちが整う「ポットン落とし」
集中力が続かないときや、癇癪の余韻が残っているときにぴったりなのがこの「ポットン落とし」。
小さな穴にフタやコインを“ポットン”と落とすだけの単純な遊びですが、繰り返しの動作が心と身体を落ち着かせる効果があるとされています。
✔ おすすめポイント:
- 指先を使うことで自律神経が安定しやすくなる
- 「何かに集中したいとき」に気持ちを整えるスイッチに
✔ 材料:空き容器・ペットボトルキャップ・洗濯バサミなど
✔ 工夫ポイント:難易度を変えて、年齢や発達段階に合わせて調整可能
見通しがあると癇癪激減!「ミニスケジュールカード」
「あとでね」が通じない、予定が変わると大混乱…そんなときに力を発揮するのが「ミニスケジュールカード」です。
絵カードや写真で、これからの流れや行動を“視覚で見せる”ことで安心感を与えるという支援方法です。
✔ おすすめポイント:
- 時間や順番の概念がまだ曖昧な子にとって、視覚情報はとてもわかりやすい
- 予定変更の際も、カードを入れ替えるだけで混乱を最小限にできる
✔ 材料:ラミネートしたイラスト・マグネットシート・ポケットファイルなど
✔ 応用例:1日の流れを“朝だけ”でも提示するだけで、登園ぐずりが減ったという声も

【体験談】「癇癪が減った!」実際に使ったママたちのリアルな声
ここでは、実際に「手作りお助けアイテム」を取り入れてみた保護者のリアルな声をご紹介します。
「市販の療育グッズを買う勇気はなかったけど、手作りなら試しやすかった」
「ちょっとしたアイディアで、子どもの癇癪が減って本当にラクになった」
そんな声が集まりました。子どもたちの反応は本当にさまざまで、万人に万能な正解はありません。でも、工夫を重ねる中で見えてきた“うちの子に合った方法”は、他の家庭でもヒントになるはず。
一歩踏み出すきっかけとして、ぜひ読んでみてください。
話せない子の強い味方「おちつくカード」が奇跡を起こした!
発語がほとんどない3歳の男の子を育てているママの体験談です。
「いつも理由もわからず泣き出して、なだめるしかなかった。でも、『おちつくカード』で気持ちを指さしてくれるようになって、本当に世界が変わりました」
このご家庭では、「さみしい」「つかれた」「〇〇がしたかった」といったカードを10種類ほど作り、毎日見える場所に貼っていたそうです。すると数週間後、泣く前にカードを指差すようになり、親が気持ちを汲み取りやすくなったことで癇癪が減少。
言葉が出ないことは“伝えられない”ことではないと、改めて実感できたといいます。
視覚的に伝える手段を持つことで、子どもが「わかってもらえた」と感じることが、安心と落ち着きにつながったようです。
言葉に頼れない子ほど、こうした非言語的なツールが力を発揮するといえますね。
ぐずりが一瞬でおさまる!?「おちつきボトル」効果に驚き!
こちらは、4歳の女の子を育てるママからの声。
「帰り道で毎日のように癇癪を起こしてた娘が、“ボトルを見せただけで落ち着いた”瞬間があったんです。思わず2度見しました(笑)」
この子は、帰宅途中のスーパーや人混みなどで刺激を受けやすく、機嫌が突然悪化することが多かったそうです。
そこで取り入れたのが、キラキラの「おちつきボトル」。使い始めてからは「見せる→じーっと眺める→数分後には表情がゆるむ」という流れが何度もあったとか。
感覚統合の視点で言うと、“視覚刺激を使ったリラックス法”は、興奮状態にある神経を鎮めるのに効果的なことがあると言われています。
特に視覚優位の子には、自分で“見て落ち着ける”ツールとしておすすめです。
手作りということもあり、家用と持ち歩き用を作って使い分けているとのこと。「癇癪のピーク前にボトルを見せる」のがコツだそうです!
自分でクールダウンできる子に変わった「安心スペース」の威力
「逃げ場がない」――これがストレスの元になっている子、意外と多いんです。
6歳の男の子を育てるママから、こんなエピソードが届きました。
「癇癪が始まると毎回暴れて、止めるのも一苦労。でもある日、『ここでひとりになっていいよ』と段ボールのスペースを作ったら、びっくりするほど落ち着いたんです」
この“安心スペース”は、おもちゃの箱をひっくり返して、カーテンをつけただけの簡単なもの。でも、その子にとっては、外の刺激を遮断して“自分だけの時間”を持てる大切な場所になったそうです。
数週間後には、自分から「ちょっとここで休む」と中に入る姿も見られるようになり、パニックの頻度も減少。
親としても、「無理に止めずに“気持ちが戻るまで待てる”安心感ができた」と話してくれました。
「安心できる場所」があることは、子どもにとって“逃げ”ではなく“自分で感情を整える練習の場”にもなるんですね。
癇癪対応がラクになる!お助けアイテム活用5つのコツ
せっかく手作りで「お助けアイテム」を作っても、「使ってくれない」「全然効果がない気がする…」なんてこと、ありませんか?
それ、実はちょっとした“使い方のコツ”でグッと効果が変わるかもしれません。
癇癪は、ただの“問題行動”ではなく、子どもからのサインやSOSの表れ。だからこそ、アイテムをどう使っていくかがとても大切なんです。
ここでは、日々の育児の中で無理なく続けられて、しかも効果を実感しやすくなる5つの活用ポイントをご紹介します!
1:遊びの中で自然に取り入れるべし!
「癇癪のときに使おう!」と意気込むと、子どもが構えてしまって拒否することもあります。
でも、“日常の遊びの延長”としてアイテムを取り入れることで、自然と受け入れやすくなるんです。
たとえば、「おちつきボトル」をおもちゃとして見せたり、「ポットン落とし」を遊びに混ぜておいたり。
普段から触れているものなら、癇癪のときもスッと手に取ってくれる可能性が高まります。
感情が爆発する前に“慣れ親しんだアイテム”として使ってもらえることが、最大のポイント!
2:「使っていい時」をわかりやすくルール化
いくら効果的なアイテムでも、タイミングがバラバラだと混乱して逆効果になることも。
特に自閉症のある子どもは、「いつ」「どこで」「どう使うか」というルールがはっきりしている方が安心します。
たとえば:
- 「泣きたくなったら“おちつきスペース”に行っていいよ」
- 「怒ってきたら“かみかみキューブ”を使おうね」
- 「このカードは“言えないとき”に使っていいよ」
など、ルールを絵や言葉で視覚的に伝えておくことで、子どもが“自分で選んで落ち着く”力も育っていきます。
3:一緒に作ることで“愛着”がアップ
「これ、自分で作ったやつだよ〜!」と誇らしげに見せてくれた子、いませんか?
実は、子ども自身が作り手として関わると、そのアイテムへの愛着や使用頻度がグンと高まるんです。
シールを貼るだけ、色を塗るだけでもOK。
「どの色が好き?」「どんな模様にしようか?」と一緒に考えながら作る時間自体が、親子のコミュニケーションにもつながるというメリットもあります。
「自分の道具」という感覚があることで、癇癪時にもより効果的に働く可能性大です!
4:園や支援者と共有して使い方を統一
家庭でうまくいったアイテムでも、保育園や支援施設では使い方が違っていたら、子どもが混乱してしまうことも。
だからこそ、「このアイテムはこういうときに使ってます」と伝えて、周囲の大人と連携することがとても大切です。
✔ 連絡帳や支援計画に一言添える
✔ 写真を添えて「これが“おちつきカード”です」と共有
✔ 支援者からのフィードバック(意見)をもらい、使い方を見直す
こうしたやり取りを通して、子どもがどの場面でも同じように安心して行動できる“環境の一貫性”が生まれるんですね。
5:子どもに合った“ベストアイテム”を見つけよう
実は、これがいちばん大事なポイントかもしれません。
「Aちゃんに効いたから、うちの子にも!」と思っても、発達の特性や性格、感覚の敏感さは本当に人それぞれ。
大事なのは、「わが子に合うかどうか」を基準に少しずつ試してみることです。
効果が薄いと感じたら、やめてOK!代わりに別の方法を探してみればいい。
試行錯誤は決してムダじゃなく、“その子に必要なものを探す旅”なんです。
「遊びが好きな子には“ポットン落とし”がぴったりだった」
「音に敏感な子には“安心スペース”が救世主になった」
…そんな発見が、きっとあなたにも見つかるはずです。
手作りvs市販品!どっちが使える?メリット・デメリット徹底比較
「癇癪に効くアイテムって、結局“手作り”と“市販品”、どっちがいいの?」
これはよくある疑問です。SNSや育児本を見ても、手作り派と市販派で意見が分かれることも。
実際のところ、どちらにも良さがあって、どちらか一方が正解というわけではありません。
大切なのは、「その子に合うかどうか」と「家庭で使いやすいかどうか」という視点。
ここでは、手作り・市販それぞれのメリット&デメリットをしっかり整理しつつ、実際の育児現場で多くの家庭が実感している“ベストな活用法”についてもご紹介します!
【手作りの強み】コスパ◎&子どもにぴったりカスタマイズ
まずは手作り派の魅力から。
なんといっても最大のメリットは、「その子に合った形に自由にアレンジできる」こと!
市販品では対応しきれないこだわりや、苦手な素材なども、家庭で作るからこそ細かく調整できます。
✔ たとえば…
- 音に敏感な子には“静かな素材”だけで作ったおちつきボトル
- 好きなキャラのイラストを貼って「うちだけのスケジュールカード」
- 兄弟で色違いにして“自分専用”感を演出 など
さらに、材料はほとんど100均で揃うのでコスパも抜群。
「壊れたらまた作り直せばいいや」と気軽に考えられるのも、心の余裕につながります。
ただし、デメリットももちろんあります。
- 作る時間や手間がかかる
- 耐久性が弱いこともある
- 親が頑張りすぎると疲れる…
そんなときは、「手作り=完璧を目指すもの」と思わずに、“ゆるく・楽しく・子どもと一緒に”を心がけるとラクになりますよ。
【市販の魅力】すぐ使える&壊れにくい
一方、市販アイテムの強みは「すぐに使える安心感」と「耐久性の高さ」です。
癇癪対応グッズの中には、療育専門のメーカーが開発したものもあり、安全性や素材への配慮が行き届いているものが多いのが特徴。
「ちゃんと効果が検証されているグッズが欲しい」「忙しくて手作りする時間がない」というご家庭には、やっぱり心強い存在ですよね。
✔ たとえば…
- シリコン製のチューイング(かみかみグッズ)は、誤飲防止・衛生面も◎
- 療育施設でもよく使われている絵カードセットは、汎用性が高く長く使える
- 市販のスケジュールボードは、見た目もきれいで収納しやすい
とはいえ、市販品にも注意点はあります。
- 価格が高め(3,000〜5,000円以上が多い)
- 子どもが気に入らなかったときのリスクが大きい
- 細かいカスタマイズはしにくい
特に自閉症の子どもは「好き」「イヤ」がハッキリしていることが多いので、高価な市販品を買ったのに一切使ってくれなかった…というケースも珍しくありません。
【最強法】両方ミックスがいちばん使える説
実は今、多くの親御さんや支援者がたどり着いているのが、「手作り×市販のハイブリッド活用」という方法。
つまり、市販品の“安心・頑丈・時短”という強みと、手作りの“柔軟さ・親子の関わり・安さ”というメリットを組み合わせるやり方です。
✔ たとえば…
- 基本のスケジュールボードは市販品、予定カードは手作り
- 外出用のかみかみグッズは市販、家用は手作りのフェルト
- 「子どもが気に入った市販グッズ」に、ラベルや装飾を加えてカスタマイズ
この方法だと、最小限の手間で、最大限の効果を狙えるんです。
しかも、子どもに合わせて少しずつ調整しながら使えるので、長く・柔軟に活用できるのが魅力。
迷ったらまず、「どんな場面で、どんな困りごとをサポートしたいのか?」を明確にして、必要なアイテムだけを選ぶ&作るのがコツですよ。
【注意】こんな時は家庭だけで頑張らないで!専門機関を頼ろう
手作りアイテムや工夫を取り入れても、「どうしても収まらない癇癪がある」「毎日消耗してもう限界…」そんなふうに感じること、ありませんか?
まずお伝えしたいのは、あなたが悪いわけじゃないということ。
子どもの癇癪や行動には、家庭だけではどうにもできない“背景や特性”が関係している場合も多いんです。
「もっと頑張れば…」と自分を責める前に、“支えてくれる場所がある”ことを知ってほしい。
ここでは、「こんなときは迷わず専門機関に頼ってOK!」という判断の目安と、相談できる場所の例をご紹介します。
毎日癇癪が止まらない/暴れる・ケガをする
まず、次のような状況に心当たりがある場合は、家庭で対応し続けるのは非常に大変です。
- 癇癪が毎日のように起きる/長時間続く
- 怒りが激しく、物を投げたり叩いたりすることが多い
- 自分や他人にケガをさせる行動が見られる
- 睡眠・食事にも大きな影響が出ている
これらは、単なる“育てにくさ”ではなく、発達や感情の調整機能に関する支援が必要な可能性が高いサインです。
専門の視点からみると、「癇癪」という行動の背景には“ことばで気持ちを伝えられない”“脳の処理の仕方が違う”といった発達特性が関わっていることも多いのです。
放っておくと、自己肯定感の低下や二次障害(不安症・うつ症状など)につながるリスクも。
だからこそ、早めの相談が未来の安心につながります。
子育てに限界を感じたら、迷わず相談を
「もう無理かも…」「毎日怒ってばかりで自分が嫌になる…」
そんなふうに感じていたら、すでにあなたの心が悲鳴をあげているかもしれません。
子どもの癇癪を毎日受け止め続けるのは、本当にエネルギーがいります。
泣いて、怒って、なぐさめて、片付けて、また怒られて…そんな繰り返しに心がすり減ってしまうこと、誰にでもあります。
だからこそ、「疲れた」「助けてほしい」と思った時点で、相談していいんです。
専門機関は、“困った子どもを直す場所”ではなく、“困っている親子を一緒に支える場所”です。
完璧な親でなくていいし、「どうしたらいいかわからない」という気持ちのままでも大丈夫。
話をするだけでも、ふっと心が軽くなることがある。
「家庭だけでなんとかしなきゃ」と思わず、支援の手に委ねる勇気も、大切な一歩です。
相談先リスト:発達支援センター・小児精神科・療育施設など
いざ相談したいと思っても、「どこに行けばいいの?」「どうやって探せばいいの?」と迷う方も多いですよね。
ここでは、代表的な相談先をいくつかご紹介します。
■ 発達支援センター・子育て支援センター(市区町村が運営)
初めての相談先としておすすめ。発達の専門相談員が在籍しており、子どもの様子を聞いたうえで必要な支援につなげてくれる場合が多いです。
自治体のホームページや母子手帳の裏に記載があることも。
■ 小児精神科・発達外来(病院・クリニック)
癇癪や情緒面の心配が強いとき、医師による発達検査や診断が必要な場合はこちら。
予約が取りづらい地域もあるので、早めに探しておくのがポイントです。
■ 児童発達支援・療育施設(未就学児向け)
遊びや活動を通じて、感情・コミュニケーション・身体発達をサポートしてくれる施設。
親への関わり方アドバイスや、家庭との連携もしっかりしています。
自治体の“福祉サービス窓口”や支援センター経由で案内されることが多いです。
■ 保育園・幼稚園・通っている施設
園の先生は、日常の様子をよく見ているプロ。「家でこうなんです…」と相談してみることで、別の視点でアドバイスがもらえることも。
誰に相談してもOKです。「ちょっと困ってて…」という一言からでも、ちゃんと耳を傾けてくれる人がいます。
あなたはひとりじゃない、ということを忘れないでくださいね。

まとめ:癇癪は「成長のチャンス」!手作りアイテムで親子の絆を育てよう
癇癪って、できることならない方がいい。
できれば、起きてほしくない。
…そう思うのは当然です。実際、癇癪に付き合うのって、体力も気力も本当に消耗しますよね。
でも、ちょっと視点を変えてみると、癇癪は子どもが「困っている」「どうしていいかわからない」ときに発しているサインでもあります。
つまり、癇癪は「困った行動」ではなく、「成長途中のメッセージ」なのかもしれないんです。
そしてそのとき、“ちょっとした手作りアイテム”が親子のやりとりを助けてくれる存在になることがあります。
ラミネートしたカードでも、空き容器で作ったおもちゃでも、そこに「伝えたい」「伝わってほしい」という気持ちがあるなら、それはもう立派なコミュニケーションツール。
手作りアイテムは魔法の道具じゃない。でも、確実に親子の“味方”になる
ここまで紹介してきたように、手作りのお助けアイテムには、子どもを「落ち着かせる」だけじゃなく、親子の関係をちょっとだけ前向きにするチカラがあります。
もちろん、「これがあれば絶対に癇癪が止まる!」という魔法ではありません。
でも、
- 気持ちを伝えるきっかけになったり
- 落ち着ける時間を作ってあげられたり
- 「どうしたの?」と話しかける余裕が持てたり
そうやって、子どもとの関係に“小さな変化”が生まれていくんです。
それって、すごく価値のあることだと思いませんか?
「完璧じゃなくてOK!」焦らず、少しずつ前進しよう
「手作りアイテム」と聞くと、「時間かかりそう…」「自分には無理かも」と感じる方もいるかもしれません。
でも大丈夫。大事なのは“気持ちを形にしてみること”。
紙に○△□を描くだけでも、子どもにとっては意味があるかもしれません。
ビーズがひとつもなくても、水を入れただけのボトルが心を落ち着けてくれることだってあります。
子育ては毎日が試行錯誤。うまくいかない日があって当たり前です。
「今日はちょっとだけ頑張れた」「少し落ち着いて話せた」
その積み重ねが、いつか確かな前進になります。
癇癪は、子どもが自分らしく生きていくための“通過点”。
そしてあなたの手作りアイテムは、親子で乗り越えていくその過程に寄り添う、大切な相棒になります。
「できることから、少しずつでいい」
その一歩を、今日から踏み出してみませんか?
以上【癇癪に悩むママ必見!自閉症の子どもが笑顔を取り戻した「手作りお助けアイテム」大全集】でした

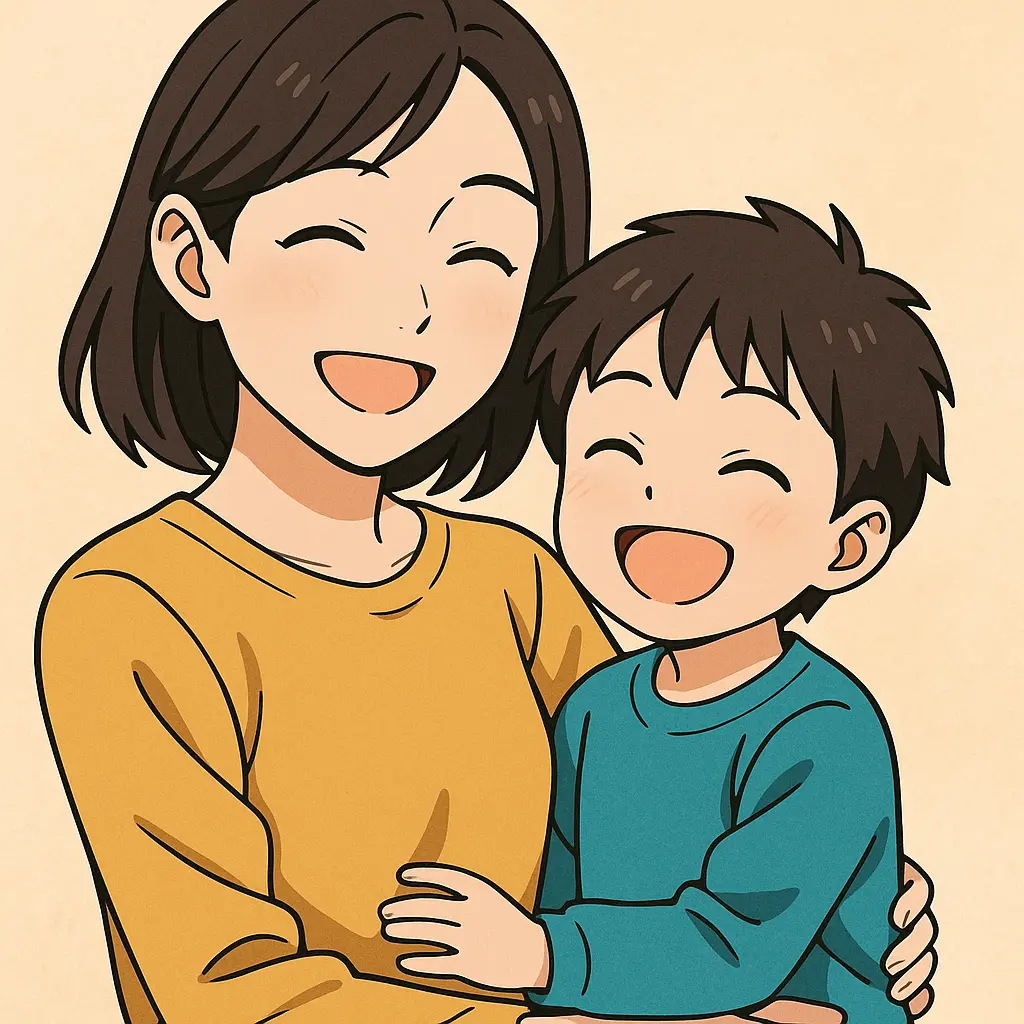









コメント