発達障害の子が一人の友達に執着するのはなぜ?心理と特徴を徹底解説
「うちの子、なんであの子にばっかりこだわるんだろう?」――そんな風に思ったことはありませんか?
発達障害の子どもにとって、特定の友達に強く執着するのは珍しいことではありません。そこには 脳の特性や安心感を求める気持ち が大きく関係しています。ここでは、その背景をわかりやすく解説します。
自閉スペクトラム症(ASD)やADHDに多い「こだわり行動」
発達障害の子どもは、「同じパターンを繰り返す」 ことや 「特定の対象に集中する」 ことが多く見られます。
ASD(自閉スペクトラム症)の子は特に「こだわり」が強く、一度「この子!」と決めた友達にべったりになることがあります。ADHDの子の場合は「思いついたらすぐ行動」という impulsive(衝動性)があり、結果的に一人の友達に強く固執してしまうことも。
こだわり行動=悪いことではなく、その子の安心のよりどころ であることが多いんです。
安心できる存在を求める心理|“安全基地”としての友達
子どもにとって、「この人と一緒なら安心できる」 という存在はとても大切です。
特に発達障害の子は環境の変化や人との関わりに不安を感じやすいため、信頼できる友達を“安全基地”として選ぶ傾向があります。
たとえば、「◯◯ちゃんと遊べれば大丈夫!」といった具合に、一人の友達に頼ることで心を落ち着けているのです。
これは大人でも「この人がいれば安心」という人がいるのと同じなんですよね。
友達関係が広がりにくい原因は「社会性の発達の遅れ」
発達障害の子どもは、相手の気持ちを読み取ったり、ルールを守ったりする“社会性”の部分が育ちにくい ことがあります。
そのため、「たくさんの友達とバランスよく遊ぶ」ということが難しくなり、結果的に一人の友達に執着してしまうのです。
「他の子にも声をかけよう」と思っても、やり方がわからなかったり、勇気が出なかったりすることも。
この“社会性の発達のスピードの違い”が、友達関係の広がりを妨げてしまうことがあるんですね。
不安やストレスを減らすための“偏った関わり”
子どもは、不安を感じたときに 「安心できる行動パターン」 を選ぶことがあります。
発達障害の子の場合、その方法のひとつが「一人の友達に集中すること」です。
たとえば、クラスの中でワイワイするのが苦手な子は、仲良しの子とだけ過ごすことで安心感を得ます。
つまり、執着は“心の安定を保つための工夫” でもあるのです。
発達特性によって異なる執着の現れ方
実は、子どもによって執着の出方はかなり違います。
- ASDの子 → 同じ友達と同じ遊びを繰り返しやすい
- ADHDの子 → 好きな子に急に強くアプローチしてしまう
- 知的発達の遅れを伴う子 → 遊び方が単調になり、一人の子に頼りやすい
どれも「困った行動」ととらえられがちですが、裏を返せば 「つながりたい」「安心したい」 という子どもの気持ちの現れです。
どんな時に起こりやすい?友達への執着行動が見られる場面
発達障害のある子どもが「この子とだけ遊ぶ!」と一人の友達に強くこだわる場面、実は色んなシーンで見られます。
ママからすると「どうしてうちの子は…?」と心配になることもありますよね。でも実は、その裏には安心したい気持ちや特性による行動が隠れているんです。ここでは、具体的な場面ごとに解説します。
幼稚園・保育園で「特定の子としか遊ばない」パターン
小さな子どもたちは集団生活の中で自然と遊び相手を見つけますが、発達障害の子は 「安心できる相手だけに絞る」 傾向があります。
たとえば「ブロック遊びは必ずAくんと」「おままごとはBちゃんとだけ」といった具合に、同じ子とだけ繰り返し遊ぶことがよくあります。
これは決して「友達が作れない」わけではなく、“信頼できる相手を選んでいる”とも言えます。ただ、先生や周囲から「もっといろんな子と遊んでみようね」と声をかけられると、子どもにとってはプレッシャーになってしまうことも。
小学校での「付きまとい」や「独占欲」のトラブル例
小学校に上がると、友達関係はさらに複雑になります。
この時期によく見られるのが、「特定の子にずっとついて回る」「遊びを独り占めしようとする」といった行動です。
たとえば休み時間に「◯◯くんと遊びたい!」と強く思い、相手が別の友達と遊んでいても割り込んでしまうことがあります。これが原因で「しつこい」「邪魔」と言われ、トラブルに発展することも…。
でも視点を変えると、これは 「相手とつながりたい」「一緒にいたい」気持ちの強さ の表れなんですよね。
習い事や放課後等デイでの特定の先生・友達への執着
放課後等デイサービスや習い事の場面でも、特定の先生や友達に強く執着するケースがあります。
「ピアノの先生が大好きで、他の先生にはなかなか慣れない」
「放課後等デイでいつも同じ子の隣に座りたがる」
これは、慣れた人や場所に安心感を抱く特性が関係しています。環境の変化が苦手な子にとって、「信頼できる人を頼ること」は心を落ち着ける方法のひとつなんです。
家庭でも「話題が一人の友達ばかりになる」ケース
家に帰ってからも「◯◯ちゃんがね!」「今日も一緒に遊んだんだ!」と、話題がいつも同じ友達のことばかり。
ママからすると「ほかの子の話はしないのかな?」と気になるかもしれません。
でもこれも、「楽しかったことを何度も振り返って安心したい」 という気持ちの表れです。
大人でも「今日は職場であの人とこんな話したんだよ」と何度も同じ人の話題をすること、ありますよね。子どもにとっても、それが“安心のルーティン”になっているんです。
年齢によって強くなりやすい執着の時期とは?
執着行動は、年齢によって強まったり弱まったりすることがあります。
- 幼児期:こだわり行動が目立ちやすく、特定の友達を選びやすい
- 小学校低学年:独占欲や付きまといがトラブルになりやすい
- 高学年以降:人間関係が複雑になり、執着の形が変化する(SNSや趣味を通じたこだわりなど)
つまり「今の執着は一生続くものではない」ことも多いんです。成長とともに関わり方が広がっていく可能性があるので、過度に心配しすぎなくても大丈夫ですよ。

ママ必見!友達に執着する発達障害の子への声かけ5選
「この子とだけ遊びたい!」と強く思ってしまうのは、発達障害のある子にとってよくあることです。
ただ、その気持ちが強すぎると友達トラブルにつながることもあるので、ママの声かけがとても大切になります。
ここでは、日常の中で取り入れやすい 5つの声かけのコツ を紹介します。
否定せずに共感する|「〇〇ちゃんが好きなんだね」
まず大切なのは、子どもの気持ちを否定しないことです。
「そんなにこだわらないで」「しつこいよ」などと突き放してしまうと、子どもは安心できず、さらに執着が強まってしまうことがあります。
そこでオススメなのが、「〇〇ちゃんが好きなんだね」「一緒に遊べて楽しいんだね」と気持ちを受け止める声かけです。
これだけで子どもは「ママにわかってもらえた!」と安心でき、落ち着きやすくなります。
気持ちを言葉にさせる|「どうして一緒に遊びたいの?」
発達障害の子どもは、自分の気持ちを言葉にするのが苦手なことがあります。
そのため、「どうしてその子と遊びたいの?」「どんなところが好きなの?」と、やさしく質問してみましょう。
気持ちをことばにすることで、自分の感情を整理する練習にもなります。
ママも「なるほど、だから執着してるんだ」と理解しやすくなりますよ。
関わりを広げるきっかけを作る|「今日は△△ちゃんも誘ってみよう」
執着が強い子は、どうしても遊ぶ相手が固定されがちです。
そんな時は「今日は△△ちゃんも一緒に遊んでみたら?」と、自然に関わりを広げる提案をしてみましょう。
大切なのは「無理に友達を増やさせる」のではなく、ちょっとしたきっかけを与えることです。
「〇〇ちゃんと遊ぶのも楽しいけど、△△ちゃんとも遊んでみたらもっと楽しいかもね」と前向きに伝えるのがポイントです。
行動を具体的に教える|「ずっとくっつくと疲れちゃうかも」
発達障害の子どもは、相手の気持ちに気づきにくいことがあります。
そのため「遊びたい気持ちはわかるけど、ずっとくっついていると相手も疲れちゃうかもね」と、具体的に行動の調整方法を教えるのが効果的です。
ただし「やめなさい!」と一方的に叱るのではなく、「どうしたら相手も楽しく遊べるかな?」と一緒に考える姿勢が大切です。
成功体験をほめる|「違う子とも遊べて素敵だったね」
新しい関わりに挑戦できたときは、大げさなくらいにほめるのが効果的です。
「違う子とも遊べてすごいね!」「新しい友達と遊んでる姿、かっこよかったよ」など、具体的に言葉にして伝えましょう。
こうした声かけは、「やってみてよかった」という成功体験の積み重ねにつながります。
それが自信となり、少しずつ友達関係を広げていくきっかけになるんです。
家庭でできる!執着をやわらげる遊びと関わり方
友達への執着は、子どもの心の安心とつながっているもの。だからこそ「やめさせる」よりも、家庭で少しずつ“広がり”をサポートしてあげる工夫が大切です。
ここでは、おうちで取り入れやすい遊びや関わり方を紹介します。どれも特別な道具はいらず、日常の中でできるものばかりですよ。
ごっこ遊び・ターンテイキングで“順番を待つ力”を育む
「順番を守る」「相手の反応を待つ」――これは友達関係に欠かせないスキルです。
ごっこ遊び(お店屋さん・お医者さんごっこなど)は、自然にターンテイキング(順番のやり取り)を練習できる遊びなんです。
例えば「ママがお客さんだから、次はあなたが店員さんね」と役を交代することで、「今は待つ」「次は自分の番」という流れを体験できます。
こうした体験が積み重なると、友達との遊びの中でも「順番を待てる」力につながります。
ソーシャルストーリーで“正しい関わり方”をイメージ練習
ソーシャルストーリーとは、簡単な絵や文章で「こんな時はこうする」と伝えるツールです。
たとえば「遊びたいときは『一緒に遊ぼう』って言おう」「相手が疲れてそうな時は少し離れてみよう」といった内容を絵本風にまとめてあげると効果的です。
実際の場面に出る前に、家庭で“予行練習”ができるのがソーシャルストーリーの強み。
イメージを持っていると、子どもは安心して行動できるようになります。
ロールプレイでトラブル場面をシミュレーション
おうちで「もし友達が他の子と遊んでいたら?」「順番を抜かされたら?」といった場面を再現して遊ぶのもおすすめです。
ママが友達役をして、「今は◯◯ちゃんと遊んでるから、あとでね」と伝える練習をしてみましょう。
実際のトラブルを“ゲーム感覚”で体験しておくことで、子どもは本番でも落ち着いて対応しやすくなるんです。
「怒らないで待てたね!」「ほかの遊びに切り替えられたね!」とほめることも忘れずに。
親子の会話がお手本!「モデル会話」で学ばせる
発達障害の子どもは、目で見て・耳で聞いたものをマネして学ぶ力が強いことがあります。
だからこそ、親子のやり取りそのものが“教材”になります。
たとえばパパとママの会話で「順番に話す」「相手の話を最後まで聞く」姿を見せるだけでも、子どもは自然と学んでいきます。
「ママはこうやってお話しするんだね」と気づけるよう、家庭の中で“お手本の会話”を見せることが大切です。
見える化(スケジュール・絵カード)で不安を減らす工夫
発達障害の子は、予定や流れがわからないと不安になりがちです。
そこで有効なのが “見える化”。絵カードやホワイトボードで「今日は誰と遊ぶ予定なのか」「終わったら何をするのか」を見える形にしておくと安心できます。
「今日は△△ちゃんと遊んで、そのあとはおうちでブロックね」と流れを視覚で伝えることで、執着がやわらぎやすくなるんです。
これにより「予定外のことが起きても大丈夫」という心の余裕が育ちます。
幼稚園・学校・支援機関と協力してできるサポート
友達への執着は、家庭だけで対応しようとするとどうしても限界を感じることがあります。
でも安心してください。園や学校、支援機関としっかり連携することで、子どもを守りながら成長をサポートできるんです。
ここでは、具体的にどんな協力ができるのかを紹介します。
先生と連携して“友達トラブル”を未然に防ぐ
一番身近で子どもを見てくれるのは、幼稚園や学校の先生です。
「いつも同じ子にくっついていませんか?」「休み時間に困ったことはありませんか?」と、先生と情報共有することがとても大切です。
先生が事前に気づいてフォローしてくれれば、トラブルを未然に防ぐことができるんです。
例えば「今日は席替えで自然に別の子と関わらせてみる」など、先生側でできる工夫もあります。
クラス全体で人間関係を広げる工夫をお願いする
執着をやわらげるためには、「他の子とも関われるきっかけ」を作ることが効果的です。
クラス全体の活動で「ペアを毎回変える」「グループ遊びを取り入れる」といった工夫を先生にお願いできると、子どもも自然にいろんな子と関わるチャンスを得られます。
「友達の幅を広げるのは本人の努力だけでは難しい」 ので、環境からサポートしてあげることがとても大切です。
放課後等デイサービスで学べるソーシャルスキルトレーニング
放課後等デイサービスでは、遊びや活動を通して 「順番を守る」「断られても気持ちを切り替える」 などのソーシャルスキルを練習できます。
これは専門スタッフがプログラムとして行ってくれるので、家庭や学校だけではなかなか身につけにくい部分を補うことができます。
実際に通っている子の中には、「以前より友達トラブルが減った」「相手の気持ちを考えられるようになった」という変化が見られるケースも少なくありません。
発達支援センターやスクールカウンセラーに相談する
「家庭でも学校でも対応が難しい」と感じるときは、専門の相談先を頼るのも安心です。
発達支援センターでは、子どもの特性に合った支援方法を一緒に考えてくれます。学校であれば、スクールカウンセラーに相談できることもあります。
「専門家の視点を入れる」ことで、ママの不安も軽くなり、子どもにとっても一貫した支援が受けやすくなるんです。
家庭だけで抱え込まず「支援の輪」を広げよう
一人で悩んでいると「私の育て方が悪いのかな」と感じてしまうこともありますよね。
でも実際には、子どもの特性に合わせて 周囲と協力しながら関わっていくことが大切です。
園や学校、デイサービス、支援センターなど、「支援の輪」を広げることで、子どもも安心できるし、ママ自身もラクになります。
家庭だけで抱え込む必要はありません。周りをうまく頼ることも、立派な子育ての一歩なんです。
ママが抱えやすい悩みと安心できる考え方
子どもが「一人の友達に執着する」姿を見ると、どうしてもママは不安や心配を抱えがちです。
でも実はその気持ち、どのママも通る自然な感情なんです。
ここでは、よくある悩みと、それに対して少しでも安心できる考え方を紹介します。
「友達に迷惑をかけていないか」の不安
「うちの子が相手の子を困らせていないかな…」と不安になること、ありますよね。
でも大事なのは、相手の子もその場で学んでいるという視点です。
子ども同士の関わりは、ちょっとした行き違いがあって当たり前。先生や大人が間に入りながら調整していくことで、お互いに「こういうときはどうするのか」を学んでいくんです。
ママが「迷惑をかけているかも…」と一人で背負い込む必要はありません。
「他のママからどう見られるか」気になる気持ち
周りのママの視線、やっぱり気になりますよね。
「また同じ子にくっついてる…って思われてるかも」と不安になるのも自然なことです。
でも覚えておいてほしいのは、子どもの行動=ママの評価ではないということ。
むしろ「ちゃんと子どもの特性を理解して工夫しているママ」だと気づいてもらえる機会にもなります。
もし気になるなら、サラッと「うちの子、今この子が安心みたいでね」と一言添えるだけでも印象は変わります。
「このまま友達が広がらなかったら…」将来への心配
「大きくなっても友達ができなかったらどうしよう」と先のことまで考えてしまうのもママの優しさですよね。
でも、子どもの人間関係は“今の形”がそのまま続くわけではないんです。
年齢や環境が変われば、自然と関わる相手も変わっていきます。
特に発達障害のある子どもは「安心できる関係を軸にしながら、少しずつ世界を広げていく」ことが多いです。
だから焦らず、今の安心できる友達関係を大事にしてあげることが、将来の広がりにもつながっていきます。
兄弟との関わりに差が出てしまうときの対応
兄弟姉妹がいると、「あの子は友達多いのに、この子は…」とつい比べてしまうこともありますよね。
でも兄弟といえど、性格も特性もまったく違うもの。
比べるよりも、「この子は安心できる関係を大事にするタイプなんだな」と受け止めてあげることが大切です。
もちろん兄弟間で不公平感が出ないように、それぞれの頑張りをちゃんと認めてあげる声かけも忘れないでくださいね。
子どもの気持ちを傷つけない声かけの工夫
「またその子にばっかり!」と否定的に言ってしまうと、子どもは安心できる居場所を否定されたように感じてしまいます。
だからこそ、声かけはできるだけ肯定的にするのがポイントです。
例えば…
- 「そのお友達が大好きなんだね」
- 「今日は他のお友達とも遊んでみる?」
- 「一緒に遊んでくれる子がいるって素敵だね」
こんなふうに、子どもの気持ちを認めつつ、新しい行動に少しずつ誘導するのがコツです。
年齢別で変化する!発達障害児の執着行動と友達関係
「一人の友達に執着する」行動は、年齢とともに少しずつ形を変えていきます。
発達障害のある子どもは特に、成長段階ごとに友達との関わり方に特徴が出やすいんです。
ここでは、年齢別の特徴と、その時期の関わり方のヒントを紹介します。
幼児期:強いこだわりが表れやすい時期
幼児期は、まだ社会性が育っている途中。
そのため「このおもちゃじゃなきゃ嫌」「この子としか遊ばない」など、強いこだわりが行動に出やすい時期です。
発達障害のある子どもは特に「安心できる相手」に強くひかれる傾向があるので、同じ友達にべったりしやすくなります。
でもこれは、安心を求める自然な姿。
無理に「他の子とも遊びなさい」と言うより、「この子と遊べてうれしいんだね」と受け止めてあげることが大切です。
小学校低学年:特定の友達を独占しやすい傾向
小学校に入ると、友達関係の幅が少しずつ広がります。
でも発達障害のある子は、まだ「この子とだけ遊びたい」という気持ちが強く出やすく、特定の友達を独占するような行動が見られることもあります。
たとえば、他の子が一緒に遊ぼうとすると怒ったり、不安になったり…。
これは「自分の安心の場を取られたくない」という気持ちの表れです。
この時期は、先生や親がやさしく関わりを広げるサポートをしてあげることがポイントです。
「今日は〇〇ちゃんも一緒に遊んでみようか」と少しずつ声をかけてあげましょう。
高学年:グループ活動や集団遊びに移行する時期
高学年になると、遊びや学びのスタイルが変わってきます。
グループ活動やクラブ活動など、複数人での関わりが増えるのが特徴です。
ただ、発達障害のある子どもにとっては「集団のルール」や「空気を読む」ことが難しく、戸惑うことも多いです。
この時期は、集団での関わり方を体験できる場を少しずつ増やしていくと安心です。
放課後等デイサービスや地域の習い事など、いろんな場面で「小さな成功体験」を積ませてあげると、本人も自信がつきます。
思春期:人間関係の幅が広がるが孤立リスクも
思春期に入ると、友達関係はさらに複雑になります。
グループでの付き合いや、SNSなどオンラインでの交流も増えてきます。
その一方で、発達障害のある子は「どう関わればいいか分からない」と感じて、孤立してしまうリスクもあります。
この時期は、友達の数よりも「安心できる少数の関係」を大事にすることがポイントです。
無理に広げようとするより、「一緒にいて安心できる友達がいる」ことを評価してあげると、子どもの自己肯定感が守られます。
長期的に見れば少しずつ関係が広がる
どの時期も、執着行動は「その子が安心したいサイン」です。
そして長い目で見ると、子どもは必ず少しずつ関係を広げていきます。
「今はこの形でいいんだ」と受け止めながら、ママがサポートを続けることで、友達関係も自然と変化していきます。
だからこそ焦らず、“今の安心”を大事にしながら、将来の広がりを信じて見守ることが何より大切です。
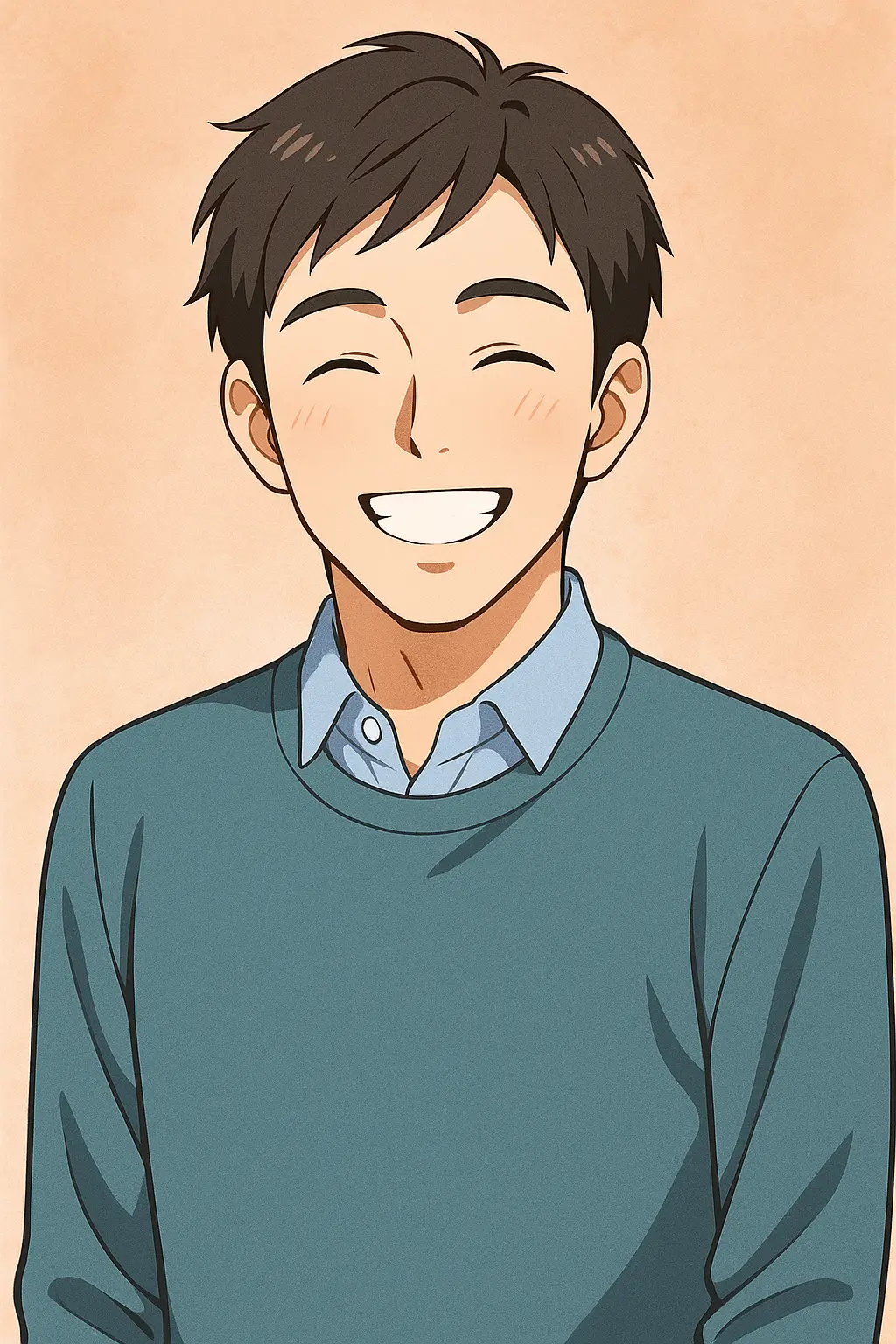
まとめ|執着は「困りごと」ではなく「成長のきっかけ」に変えられる
子どもが一人の友達に強く執着すると、ママはつい「このままで大丈夫かな…?」と心配になりますよね。
でも実は、この行動は 「安心したい」「つながりたい」という気持ちの表れ なんです。
「こだわりが強い=困りごと」と捉えがちですが、見方を変えれば 「安心できる存在を見つけられた」こと自体が大きな一歩 なんです。
発達障害のある子にとって、自分から関わりたい相手を選べることは大切な成長の証拠でもあります。
ママの声かけと支援次第で“成長のチャンス”になる
ここで大事なのが、ママの関わり方です。
「また〇〇ちゃんにばかり行って…」と否定するのではなく、
「〇〇ちゃんと一緒だと楽しいんだね」と気持ちを認めてあげると、子どもは安心できます。
さらに、「次はもう一人誘ってみようか?」と少しずつ声をかける ことで、子どもの世界はゆっくり広がっていきます。
つまり執着は、ママの声かけや環境次第で “人間関係を学ぶチャンス” に変えられるんです。
周囲と協力しながら、少しずつ友達関係を広げていこう
もちろん、ママ一人で抱え込む必要はありません。
幼稚園や学校の先生、支援の専門機関、放課後デイサービスなど、周囲と協力してサポートの輪を広げることが大切です。
「執着=悪いこと」ではなく、「今はこういう関わり方なんだ」と受け止めながら、少しずつ経験を積ませていくことで、子どもの友達関係は自然と広がっていきます。
だからこそ、ママには “焦らなくて大丈夫” ということをお伝えしたいです。
執着は困りごとではなく、子どもが安心を求めているサインであり、成長のきっかけなんです。
ママが子どもの気持ちを認め、周りと一緒に見守っていけば、きっと少しずつ子どもの世界は広がっていきます。
「執着がある=問題」ではなく、「執着がある=安心を見つけた」ことだと考えて、ゆったり構えていきましょう。
以上【発達障害の子が一人の友達に執着する理由とママの正しい声かけ・接し方ガイド】でした

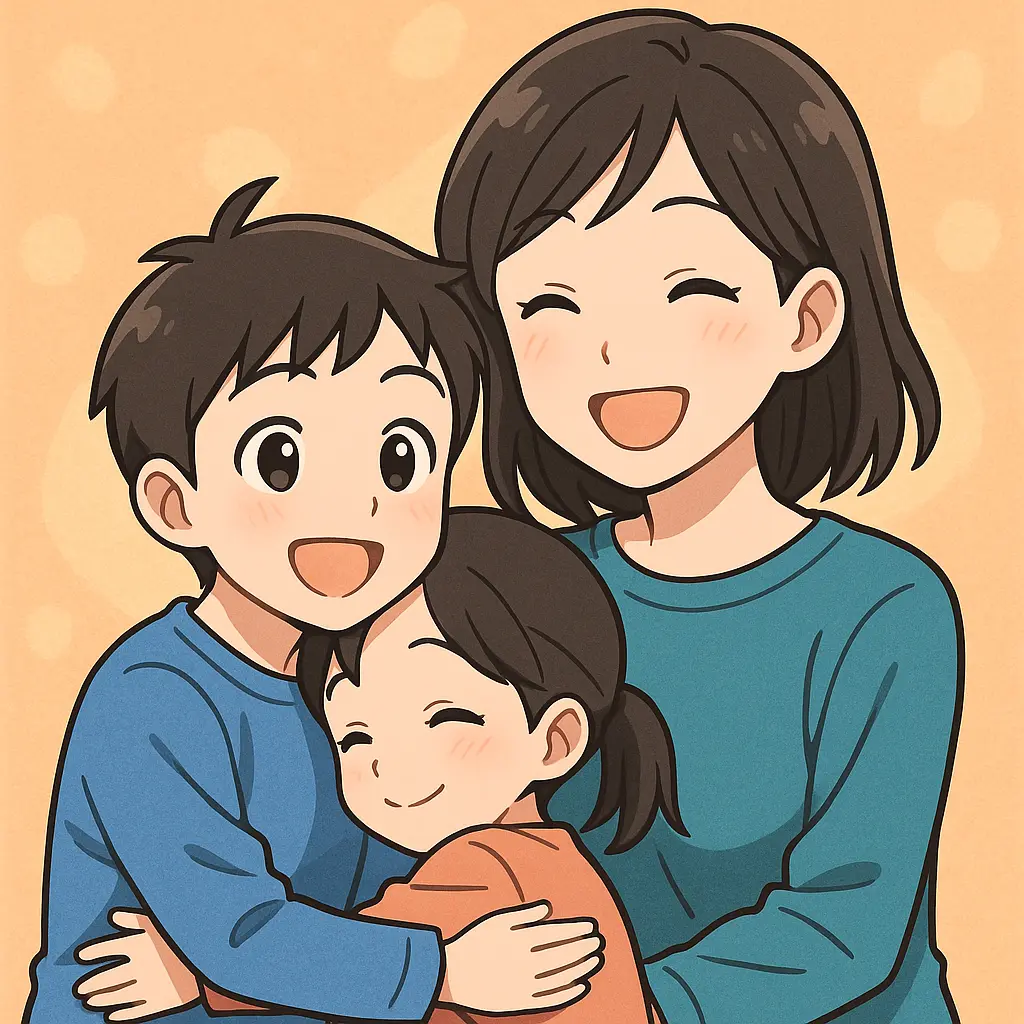









コメント