子どもが陰部を触る…それって問題行動?正しく理解して安心対応へ!
「うちの子、最近よく陰部を触るんだけど…これって大丈夫なのかな?」
「人前でも平気で触るから、周りの目が気になって…」
そんな悩みを抱えている保護者の方、実は少なくありません。
特に発達障害のあるお子さんの場合、このような行動が日常的に見られることがあり、親としては戸惑いや心配が募るものです。「これは性に関する問題?」「病気のサイン?」「しつけが足りない?」と、あれこれ考えてしまいますよね。
でも、ちょっと待ってください。
その行動には、子どもなりの“理由”や“背景”があるかもしれません。
たとえば、
- 感覚が過敏または鈍感で、心地よい刺激を求めている場合
- 不安やストレスを落ち着かせるために無意識にしている場合
- 年齢相応に出てくる性への興味や、自分の体への関心
- 単純にヒマで触ってしまうなど、習慣化された行動になっていることも
こうして見てみると、単に「悪いこと」「止めさせなきゃ」と決めつけるのは少し早いかもしれません。
大切なのは、「なぜその行動が起きているのか」を知ること。
そして、そのうえで子どもを傷つけずに、安心して過ごせるような対応をしていくことです。
この記事では、
- 発達障害の子が陰部を触る行動のよくある背景や原因
- 保護者がやってしまいがちなNG対応とその理由
- 子どもが安心して行動を見直せるための正しい声かけ術
- 今日からできる家庭での支援や具体的な工夫
- そして、困ったときに頼れる相談先まで、幅広く紹介していきます。
どんな子どもにも「行動には意味がある」と言われます。
この記事を読むことで、今抱えている不安が少しでも軽くなり、
お子さんとの関わり方に「なるほど!」と思えるヒントが見つかるはずです。
叱る前に、まずは理解することから。あなたとお子さんが笑顔で過ごすためのきっかけになりますように。

そもそも…発達障害の子が陰部を触るってどういうこと?
「なんで急にこんなことを?」「うちの子だけ…?」と驚いたり、不安になったりする親御さんは少なくありません。
特に、発達障害のあるお子さんが陰部を触る行動を見せたとき、「これは性の問題?それとも発達の影響?」と、どう捉えればいいのか悩んでしまいますよね。
まず最初にお伝えしたいのは、
陰部を触ること自体が必ずしも“問題行動”とは限らないということ。
子どもにとって、自分の体に触れることは「安心感」や「好奇心」の一部でもあり、とくに発達の過程においては珍しくない行動です。
ただし、発達障害の特性を持つ子どもたちは、この行動が強く出たり、頻度が高くなったり、人前で繰り返す傾向があるため、家庭や園・学校で戸惑われる場面が増えがちです。
そこでまずは、「どんな行動が見られるのか?」というところから、整理していきましょう。
こんな行動、見覚えありませんか?よくあるシーンを紹介
発達障害のあるお子さんが陰部を触る場面には、いくつかのパターンがあります。たとえば…
- ソファに座ってテレビを見ながら、無意識に手をズボンの中へ
- 夜、布団に入ると落ち着いた様子で触っている
- 保育園や学校で、人前にもかかわらず触ってしまう
- トイレで用を足した後、必要以上に触っている
- 怒られて不安になった時や、パニック直後に触る
こういった行動が見られた場合、「なにか性の問題?」と捉えてしまいがちですが、すべてが性的な意味を持っているわけではありません。
とくに自閉スペクトラム症(ASD)やADHDのお子さんには、感覚調整や安心のための行動として出ているケースが多いんです。
つまり、「不快だから」「安心したいから」「落ち着けるから」という目的で、手が自然とそこに向かっていることもあるのです。
発達障害の子に特有な「触る」行動の傾向とは?
ここで注目したいのが、「発達障害の子どもに特有な背景や傾向」です。
まず1つ目に多いのが、感覚の過敏や鈍麻(にぶさ)。
発達障害のあるお子さんの中には、肌の感覚に独特な特性を持っている子が少なくありません。たとえば、下着やズボンが擦れる感覚が不快だったり、逆に触れていないと感覚が落ち着かないなど、触ることで感覚を調整している可能性があります。
2つ目は、習慣化しやすいこと。
発達障害のある子は、同じ行動を繰り返すことに安心感を覚える子も多いため、陰部を触るという行動が“習慣”になってしまうことがあります。これが無意識のうちに日常化すると、やめるのが難しくなってしまうことも。
3つ目は、「場面の区別」が難しいこと。
たとえば、「人前では触ってはいけない」という社会的なルールを理解しにくかったり、空気を読むことが苦手な場合、“人が見ている”という感覚が薄く、人前でも平気で触ってしまうということがあります。
また、自己調整(セルフレギュレーション)としての意味も見逃せません。怒られたあと、パニック状態、環境の変化に不安を感じたときなど、“気持ちを落ち着けるための行動”として触っている子もいるのです。
\ここまでのまとめ/
- 陰部を触る行動は、すべてが性的な意味を持つわけではない
- テレビを見ながら、寝る前、ストレス時など、さまざまな場面で起こりやすい
- 発達障害の子どもには、
- 感覚の調整
- 習慣化の傾向
- 社会的ルールの理解の難しさ
- 自己安定(セルフレギュレーション)行動
が背景にあることが多い
- まずは「なんでその行動が出ているのか?」という視点で見てみることが大切
このように、行動を「問題」と決めつける前に、「背景にどんな気持ちや感覚があるのか?」に目を向けることで、よりやさしく、そして効果的に対応する道が見えてきます。

陰部を触る理由は1つじゃない!考えられる5つの背景
子どもが陰部を触る理由(5分類チャート)
┌── 感覚刺激を求めている(感覚調整)
├── ストレスや不安を落ち着かせる(セルフレギュレーション)
├── 性への関心(年齢相応の自然な興味)
├── 身体的な違和感(かゆみ・痛みなど)
└── なんとなく触る(習慣・退屈対策)
「なんでうちの子は何度言っても陰部を触るの?」
一見“よくない行動”に見えても、実はそこには子どもなりの理由や目的があることが少なくありません。
特に発達障害のある子どもたちは、行動の背景に“感覚”や“環境”が深く関わっていることが多く、表面的な部分だけでは判断できないのが特徴です。ここでは、よく見られる「5つの理由」について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
じつは“快感”ではなく“感覚刺激”が目的?
まず最も多いのが、感覚刺激を求めて陰部を触っているケースです。
私たちが日常的に手を組んだり、頬杖をついたりするように、発達障害のある子どもたちは、“自分にとって心地よい感覚”を探して行動することが多いんです。
陰部は敏感な部位なので、服の上からでも少し触れるだけで刺激が伝わります。
この「ちょうどいい刺激」が、感覚の調整や安心感を与えるという目的になっていることも。
とくに、感覚鈍麻(にぶさ)や感覚過敏がある子どもたちは、「普通の刺激」では落ち着かず、自分に合った刺激を無意識に求めてしまうのです。
ストレスで心を落ち着かせているサインかも
次に考えられるのが、ストレスや不安を和らげようとする“自己安定行動”です。
これはいわゆる「セルフレギュレーション」と呼ばれるもので、パニックになりかけたときや、不安が高まったときに気持ちを落ち着かせるための手段として現れます。
たとえば、怒られたあとや、慣れない場所・初めての環境などで、子どもが突然陰部を触り出す場面があったら、「あ、今ちょっと心が不安定なんだな」と気づいてあげることが大切です。
これも、「悪いことをしている」のではなく、“安心したい”という気持ちの表れ。
まずはそのサインに気づき、「どうしたら安心できるか?」を一緒に考えていけるといいですね。
性への関心?自然な成長とどう見極める?
「性に興味が出てきたのかな?」と思う保護者も多いはず。
実はその感覚も間違いではありません。子どもはある時期になると、自分の体に対する興味や、性に関する好奇心が自然と芽生えてきます。
これは、健全な成長の一環であり、ごく自然なこと。
ただ、発達障害のある子どもたちの場合、「性ってなに?」「人前でしていいこととダメなことの区別がつかない」など、発達のアンバランスさから行動が誤解されやすいという特徴があります。
大切なのは、
- 「触ること自体が悪い」と否定しないこと
- 「どこで、いつならOKなのか」を具体的に伝えること
このように、自然な性の発達と、社会的なルールの学びをセットで伝えることがカギになります。
かゆい・痛いなど、身体のSOSを見逃さないで
意外と見落としがちなのが、身体的な違和感やトラブルが原因になっているケースです。
たとえば、
- 皮膚のかゆみ(湿疹、かぶれ)
- トイレの後のふき残し
- 尿道炎や性器周辺の感染症
- 紙パンツや下着が合っていないことによる蒸れ・摩擦 など
こうした体の不快感から、かゆみや痛みをやわらげるために触っている可能性もあるんです。
とくに、発達障害のあるお子さんは「ここがかゆい」「痛い」などの言語化が苦手な場合があるため、行動で訴えることが多いという視点も忘れてはいけません。
まずは皮膚や陰部の状態をチェックし、必要に応じて小児科や皮膚科など専門医に相談することをおすすめします。
「ヒマだから触る」習慣化を防ぐには?
最後に意外と多いのが、「手が空いてるからなんとなく触ってる」パターンです。
とくに、自由時間が多かったり、ひとり遊びの時間が長かったりすると、“なんとなくやってみた”がそのまま習慣化することもあります。
発達障害のある子どもは、「一度身につけた行動を変えるのが苦手」な傾向もあるため、これが繰り返されることで、無意識のルーティン(習慣行動)として定着してしまうことも。
この場合は、「手遊びを増やす」「スケジュールを細かく区切る」など、手を使う代替行動や時間の使い方を工夫することが効果的です。
また、「やっていいこと/ダメなこと」の前に、「どうすれば触る必要がなくなるか?」という視点で支援を考えると前向きな対応ができます。
\ここまでのまとめ/
- 陰部を触る理由は“性的”とは限らない!行動には背景がある
- 感覚刺激を求めて触る子も多い。落ち着ける手段になっていることも
- 不安・緊張を和らげる“自己安定行動”としての可能性にも注目
- 性への興味は自然なこと。否定せず、適切な伝え方を心がけて
- 皮膚のかゆみや炎症など、身体的な問題がないかのチェックも重要
- “なんとなく”の習慣化を防ぐには、環境や日課の工夫がカギ
【注意】ついやりがちなNG対応3つ!逆効果になる理由とは?
子どもが陰部を触っているのを見たとき、親としては「ダメ!」「やめなさい!」と反射的に叱ってしまいたくなるのが正直なところですよね。
でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。
実はその“いつもの対応”、子どもの行動をエスカレートさせてしまったり、逆効果になっている可能性があるんです。
発達障害のある子どもたちは、言葉の意味をそのまま受け取りやすかったり、感情のコントロールが難しかったりするため、大人の対応がそのまま行動に影響しやすい傾向があります。
ここでは、ついやりがちな「3つのNG対応」と、それがなぜ逆効果になるのかを客観的に解説していきます。
「やめなさい!」は逆効果!?叱るより伝えたいこと
まず一番多いのが、「やめなさい!」「またやってるでしょ!」といった反射的な叱責。
これは誰でもやってしまいがちですが、発達障害のある子どもにとっては、ただ叱られるだけでは“なにがいけなかったのか”が理解できないことが多いんです。
しかも、「怒られる=悪いこと」とだけ認識されると、
- 陰部を触ること=恥ずかしいこと・悪いこと
- 体の話をするのはタブーなんだ
という、間違った価値観を植えつけてしまう可能性もあります。
さらに厄介なのが、「怒られる=注目してもらえる」と誤解してしまい、“わざとやる”ようになるケースもあるということ。
これでは逆に行動が強化されてしまいますよね。
大切なのは、行動そのものを否定するのではなく、「どうすればよかったか」を一緒に考えること。
「やめなさい!」よりも、「ここは人前だから、触るのはやめようね」とルールとして丁寧に伝える言葉がけが効果的です。
スルーしても解決しない!無視が招く落とし穴
逆に、「見て見ぬふり」をする保護者の方もいます。
「変に反応すると逆に気にするかな…」「あえて触れない方がいいのかな」と考えて、“無視”という選択をするケースですね。
たしかに、一時的にはその場の空気を乱さずに済むかもしれませんが、無視=何も伝わらないというリスクも大きいです。
発達障害のある子どもは、「どこまでOKでどこからNGなのか」の境界線を自分で判断するのが苦手な場合が多いため、何も言われなければ「やってもいい」と受け取ってしまうことも。
また、触ってしまう理由が「ストレス」や「不安」だった場合、無視されることでその気持ちが放置され、ますます不安が強まってしまう…なんて悪循環もあり得ます。
だからこそ、反応の仕方に迷ったら、“説明”や“誘導”という形で関わるのがおすすめ。
無視するよりも、「今は〇〇の時間だから、手は膝に置いておこうね」といったやさしい声かけで行動を切り替える工夫が大切です。
「悪いこと」と決めつけると心が傷つく理由
3つ目のNG対応は、陰部を触る行動に対して「そんなことしちゃダメでしょ!」「恥ずかしいよ!」「気持ち悪いからやめなさい」など、“人格否定”に近い言葉で強く言ってしまうこと。
これは一見、“常識を教えている”ように思えるかもしれませんが、子どもにとっては自分の体や気持ちを否定されたように感じてしまうことがあるんです。
とくに発達障害のある子どもたちは、言葉のニュアンスをうまく読み取れないことも多いため、「自分が悪い子なんだ」「触ったらだめな体なんだ」と自尊心や自己肯定感を大きく傷つけてしまうリスクがあります。
それが続くと、
- 「体について話すこと」=恥ずかしい、怖い
- 「困っても誰にも相談できない」
といった、思春期以降に深刻な悩みを抱えるきっかけになってしまうことも…。
だからこそ大事なのは、「行動は間違っていたけど、あなたの存在は大切だよ」と伝える関わり方です。
言い換えれば、叱るのではなく“教える”ことが親の役割なんですね。
\ここまでのまとめ/
- 「やめなさい!」だけでは、子どもは何がいけなかったのか理解できない
- 無視しても問題は解決しない!行動の背景を読み取り、やさしく声かけを
- 陰部を触ることを“恥ずかしいこと”“悪いこと”と決めつけるのは逆効果
- 人格を否定するような言い方は、自己肯定感を傷つけてしまうおそれがある
- 大切なのは“叱る”のではなく“伝える”。ルールや代替行動を教えていこう!
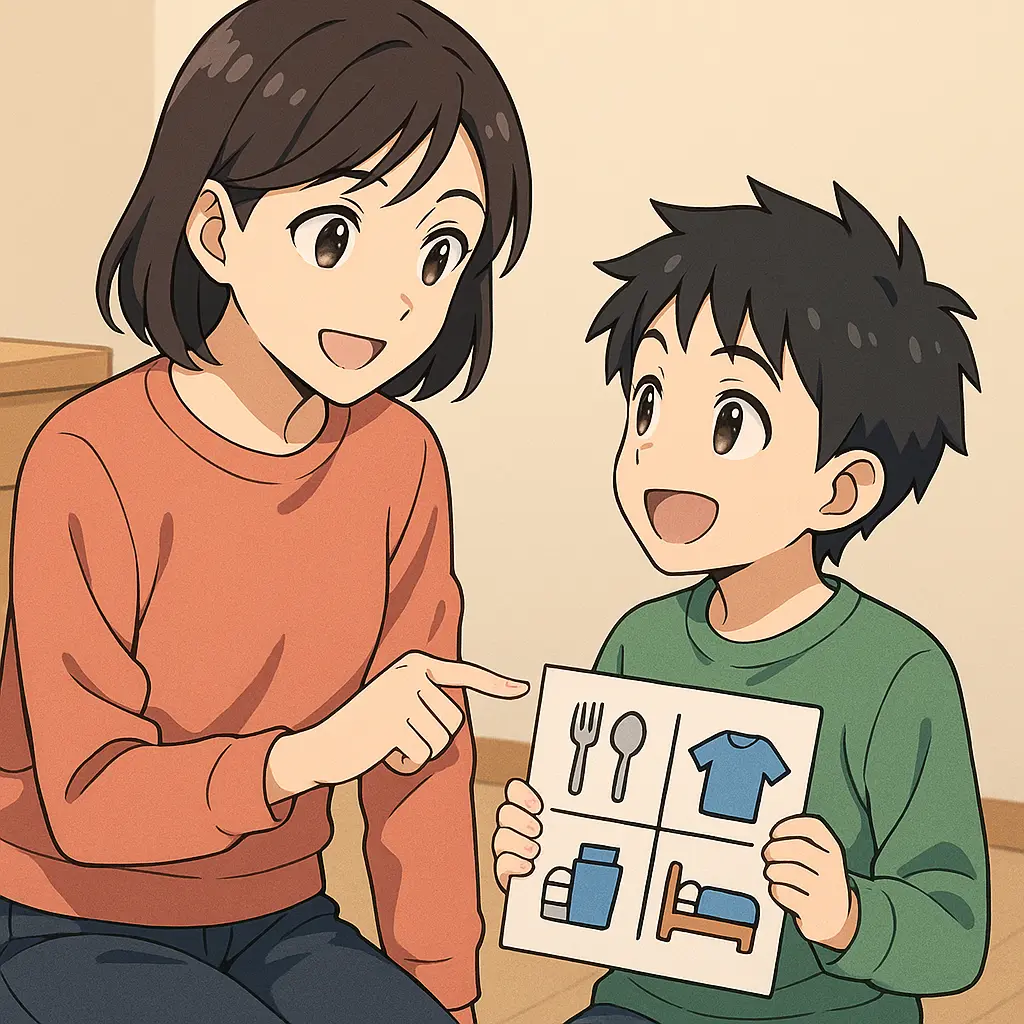
子どもが安心できる!やさしく伝える正しい声かけ術
「怒るのは逆効果ってわかったけど、じゃあどうやって伝えればいいの?」
そんなふうに思った方、安心してください。子どもの行動には理由があるように、対応の仕方にも“伝わりやすい言い方”があります。
ここで大切なのは、「止めさせる」ことだけを目的にしないこと。
子どもが安心できて、納得できるように伝えることで、行動が自然と変わっていくことも多いんです。
この章では、子どもとの関係を壊さず、でもちゃんと伝えるための4つの声かけのコツを紹介していきます。
「落ち着いて話す」がいちばんの第一歩
まず大前提として、伝えるときに親が“落ち着いていること”が何より大切です。
子どもが陰部を触っているのを見た瞬間、焦ったり驚いたりして「ちょっと!なにやってんの!」と大きな声で反応したくなる…それ、すごくわかります。でも、子どもにとってはその反応が恐怖や混乱のきっかけになってしまうことも。
特に発達障害のある子どもは、大人の感情に敏感だったり、言葉よりもトーンに反応することが多いので、「怒られてる!」「悪いことしちゃった!」と必要以上に感じてしまうことがあります。
だからこそ、まずは深呼吸して、いつも通りのトーンでやさしく声をかけることが基本中の基本。
「今は触らないようにしようね」と、短く・シンプルに伝えるだけでも十分効果的です。
「どこでなら触ってもいいか」を具体的に伝える
「触っちゃダメ!」と言うだけでは、子どもにとっては“いつ・どこでならOKなのか”がわからないままになってしまいます。
発達障害のあるお子さんの場合、曖昧な指示が伝わりにくいことが多いため、「ダメ」だけでは行動を変えるのが難しいんです。
だからこそ、「ここではダメ」だけじゃなく、「ここならいいよ」「このときなら大丈夫だよ」と、具体的に伝えるのがポイント。 たとえば…
- 「トイレの中や、お風呂のときならいいよ」
- 「寝るときにお布団の中なら触ってもいいよ」
というように、「プライベートな空間ではOK」という前提を伝えると、子どもも混乱しにくくなります。
禁止ではなく、“場所やタイミングのルール”として教えることが大切なんですね。
「触りたくなったらどうする?」代替行動を一緒に考える
陰部を触るという行動には、さまざまな理由があるとお話ししました。
たとえば、ストレスを落ち着けたいときや、暇なときの習慣として出ていることも多いです。
そんなときは、「触っちゃダメ!」と止めるだけじゃなくて、“代わりになる行動”を一緒に考えてあげるとすごく効果的なんです。
たとえば…
- 手で握れるおもちゃや、感触のいいボールを使う
- 深呼吸をする/手をぎゅっと握って離すなどのリラックス動作
- 「触りたくなったらママにぎゅってしていいよ」などの代替的な関わり方
このように、“自分の気持ちを落ち着けるための手段”を用意してあげることで、陰部を触る行動が減っていくこともあります。
「その行動を否定する」のではなく、「別の方法で満たしてあげる」という視点で接すると、お互いにストレスも少なくなりますよ。
子どもを傷つけない“肯定的な伝え方”のコツ
最後にいちばん大切なこと。
子どもの行動を否定せず、自己肯定感を守る伝え方を意識してみましょう。
たとえば、「なんでそんなことするの!」と怒ってしまうと、子どもは「自分が悪い」「おかしいのかな」と思ってしまいます。
でも、「触るのは悪いことじゃないよ。体は大事なものだから、大切にしようね」といった伝え方なら、子どもは受け止めやすく、安心して行動を見直すことができます。
発達障害のあるお子さんは特に、“否定されること”に敏感で、自信を失いやすい傾向があります。だからこそ、
- 「気持ちはわかるよ。でも今は別の方法を考えようね」
- 「ママはあなたのことが大好きだよ。困ったら一緒に考えようね」
といった、肯定と提案をセットにした声かけがとても効果的なんです。
| NGな声かけ | 子どもが感じること | OKな声かけ(言い換え例) |
|---|---|---|
| なんで触るの! | 怒られた、怖い | 触りたくなった?今は手を膝に置こうね |
| そんなことして恥ずかしいよ! | 自分の体が悪いの? | 体は大切だから、大事にしようね |
| もう!やめなさい! | わかんないけど怒られた… | 人が見てるところではやめようね |
\ここまでのまとめ/
- まずは親が落ち着いて対応することが、安心感を生む第一歩
- 「ダメ」だけでなく、「どこならOKか」を具体的に伝えると伝わりやすい
- 触りたくなる気持ちを代替行動で満たす工夫が効果的
- 肯定的な言葉がけで、子どもの自己肯定感を守りながら伝えるのがポイント
- 叱るのではなく、“一緒に考える”スタンスが大事

今日からできる!家庭でのちょっとした工夫と支援法
ここまで読んで、「なるほど、行動には理由があるんだな」と思っていただけたでしょうか。でも、「じゃあ実際に家庭ではどうすればいいの?」という声もきっと多いはず。
実は、毎日の生活の中で少しだけ工夫するだけでも、子どもの行動に変化が出てくることがあります。
特別な道具や知識がなくても大丈夫。ここでは、家庭で今日からすぐに取り入れられる支援のヒントをご紹介していきます。
環境を少し変えるだけで子どもの行動が変わる
まずは「環境づくり」が基本。子どもが陰部を触るタイミングや場所って、ある程度パターンがあることが多いんです。
たとえば、
- テレビを見ながらダラッとしている時間
- 一人で静かにしているとき
- 布団に入ってから寝るまでの間
このような「手が空いて、なんとなく落ち着いている時間」に無意識に触ってしまうケースがよく見られます。
そんなときには、“触りにくい状況”をつくってあげるのがひとつの方法。
- クッションを膝の上に置いておく
- 手遊びグッズを近くに置く
- 食後や入浴後にリラックスタイムの“ルール”を決めておく
など、行動を“予防する環境”に整えることで、自然と触る回数が減ることもあります。
無理にやめさせるのではなく、「触らなくても落ち着ける環境づくり」がポイントなんですね。
「暇だから触る」を防ぐ!生活リズムの整え方
「何もしてない時間=手が勝手に動く時間」になっていませんか?
発達障害のある子どもは、「予定がはっきりしている」「何をすればいいかが明確になっている」ことで行動が安定しやすくなると言われています。
そこで大切なのが、生活リズムを見直すこと。
- 毎日のタイムスケジュールを可視化する(絵カードやタイマーを活用)
- 朝・昼・夜の活動をルーティン化して、スキマ時間をなくす
- 「やることが決まっている」「次にやることがわかる」状態をつくる
こうすることで、「ヒマだから触る」というパターンを減らし、“落ち着いて行動できる時間”が自然と増えていきます。
さらに、夜の就寝前に手遊びやマッサージを取り入れることで、「眠る前はこの流れ」と習慣づけることも◎。
生活の中に安心できる“リズム”をつくってあげることが、行動の安定につながります。
感覚刺激が満たされる遊びで満足感アップ!
もしも「触ることで感覚刺激を得ている」ことが原因だった場合は、代わりに感覚が満たされる遊びや活動を取り入れると効果的です。
おすすめなのは、以下のような“感触遊び”や“体の感覚にアプローチできる遊び”。
- 粘土・スライム・感触ボールなどの手先遊び
- お風呂で水をすくう・沈める・バシャバシャする水遊び
- ふわふわのタオルや布を使ったスキンシップ
- マット遊びやストレッチなどで体全体を使った刺激を与える
こういった遊びは、「安心感」や「満足感」を自然と得られるので、触る必要性が減るケースが多いんです。
また、「今日は感覚刺激が足りなかったから触っていたのかも」と振り返るきっかけにもなります。
“代替となる心地よさ”を用意してあげることも、立派な支援なんですね。
発達段階に応じた性教育を始めてみよう
「性教育って、もっと大きくなってからでいいんじゃないの?」と思う方も多いかもしれませんが、実はそうでもありません。
特に発達障害のある子どもたちは、性に対する認識が曖昧なまま成長してしまうリスクがあるため、“今”からの性教育がとても重要です。
といっても難しく考えすぎなくてOK。
まずは以下のようなところからスタートしましょう。
- 「プライベートゾーン」について絵本やカードで伝える
- 「人前でしていいこと/だめなこと」を視覚的にわかりやすく
- 「自分の体は自分のもの」「人の体も大事」などの基本的なルールを教える
こうした学びを通じて、子ども自身が「なぜダメなのか」「どこでならいいのか」を理解できるようになっていきます。
また、親が“性の話題にオープンである”という姿勢を見せることも大事なポイントです。
「体のことは話してOKなんだ」という安心感が、将来の性被害防止や、自分を守る力にもつながっていきます。
\ここまでのまとめ/
- 家庭の環境を少し変えるだけでも、行動に良い変化が見られる
- 予定が見える生活リズムをつくることで、“ヒマだから触る”を防げる
- 感触遊びや感覚刺激が得られる活動を取り入れると満足感アップ!
- 発達段階に合わせた性教育を少しずつ始めることが、安心と自立につながる
- 親が「話しやすい雰囲気」をつくることが、子どもの行動理解を深めるカギになる
一人で抱え込まないで!園・学校・支援者との連携ポイント
「どうしてうちの子ばっかり…」「このままで大丈夫なのかな」
そんなふうに不安になったとき、つい「誰にも言えない」「親としてなんとかしなきゃ」と思い込んでしまいがちですよね。
でも、実はその“がんばりすぎ”が、親子ともに負担を大きくしてしまうことも。
発達障害のある子どもたちの支援は、家庭だけでがんばる必要はありません。
むしろ、園や学校、そして専門の支援者との連携こそが、より良い対応への近道なんです。
ここでは、無理なく支援の輪を広げるためにできる2つのポイントを紹介します。
「うちの子だけ?」と思ったら、まず共有しよう
子どもが陰部を触る行動を繰り返していると、「こんなことを相談しても大丈夫かな…」「恥ずかしい話かも…」と感じてしまう方もいると思います。
でも、実はこの悩み、あなただけではなく多くの保護者が感じていること。
そして、園や学校、支援機関の先生たちは、こうした行動への対応経験を持っている場合が多く、しっかり相談にのってくれます。
大切なのは、「子どもの行動に困っている」ではなく、「どう関わっていけばよいか一緒に考えたい」と伝えること。
- 園や学校の先生に「最近、こういう行動が家で続いていて…」と相談してみる
- 担任だけでなく、支援員・心理士・発達支援コーディネーターなどの専門職にも話してみる
- 保育記録や連絡帳を通じて、さりげなく様子を共有する
こうした小さな共有がきっかけとなって、家庭と園・学校で共通の対応ができるようになり、子どもにとっても一貫性のある支援が実現します。
何より、「私ひとりじゃない」と感じられることが、親自身の安心感にもつながります。
客観的な“行動の記録”が解決の第一歩に
もうひとつ大切なのが、「困っていることを伝えるときは、なるべく客観的な情報を添える」ことです。
そのために役立つのが、行動を記録する“ちょっとしたメモ”や“行動ログ”。
たとえば、
- いつ(時間帯・曜日)
- どこで(自宅・園・布団の中など)
- どんな状況で(退屈だった、怒られたあと、ひとりの時間など)
- そのとき子どもはどんな様子だったか
- どんな対応をしたらどうなったか
こういったことを記録しておくだけでも、「何がきっかけで行動が出やすいか」「どんな対応が効果的だったか」が見えてきます。
支援者や先生と共有する際にも、「主観的な印象」ではなく「事実ベース」でやりとりできるため、支援方針を立てるうえでもとても役立ちます。
また、記録を続けていくうちに、「最近この時間は触らなくなったな」など、ポジティブな変化にも気づけるようになるのも嬉しいポイントです。
アプリや手帳など、使いやすい方法で気軽に記録してみてくださいね。
\ここまでのまとめ/
- 陰部を触る行動に悩んだら、家庭だけで抱え込まず周囲と共有を
- 園や学校、支援者は“相談されること”に慣れており、力になってくれる存在
- 恥ずかしい・言いづらいと思っても、共有することで支援の選択肢が広がる
- 行動の記録は、支援者との連携をスムーズにするための有効な手段
- 記録をとることで、子どもの変化や成長にも気づきやすくなる
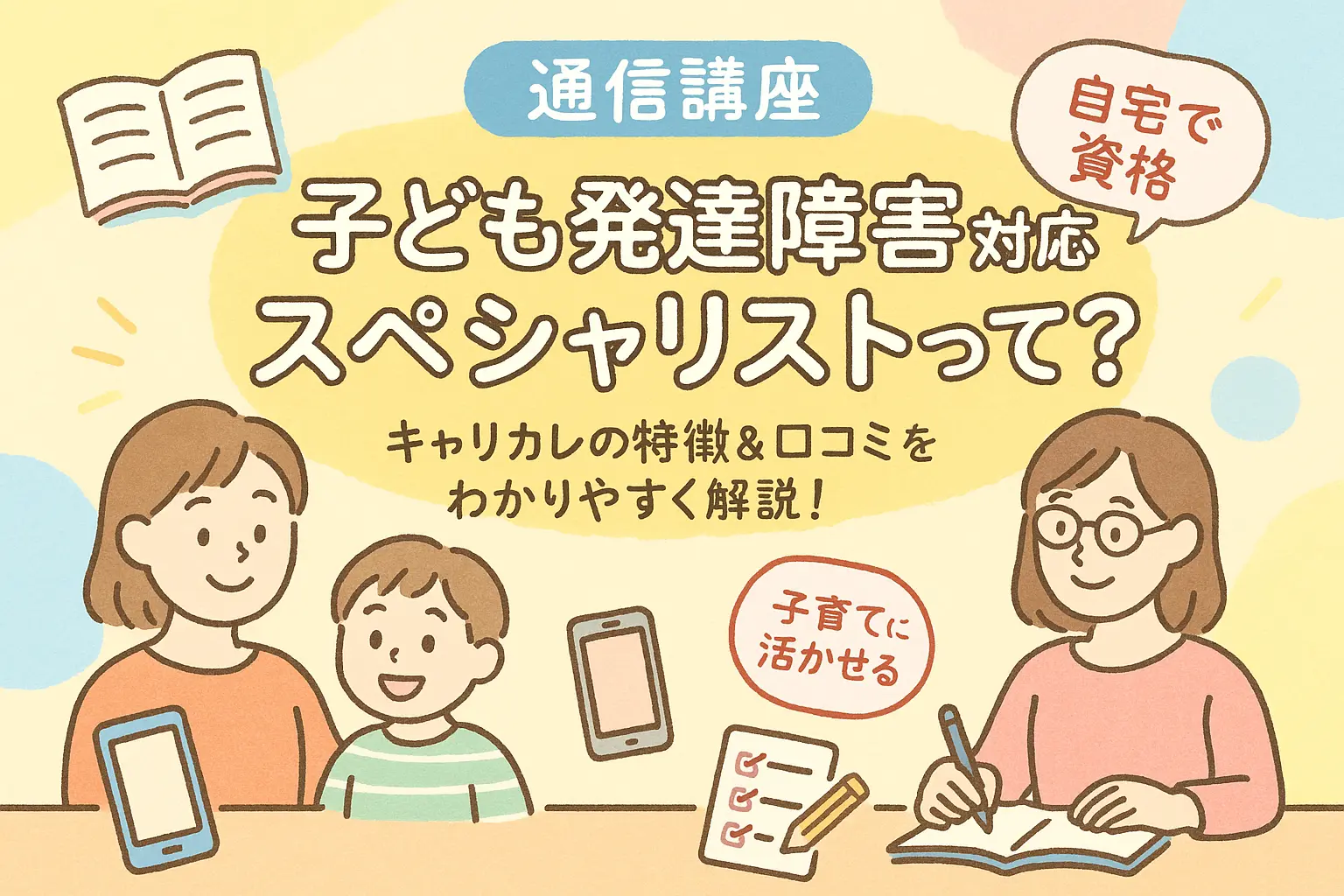
頼れる!相談できる専門機関と支援先まとめ
子どもが陰部を触る行動が続くと、「誰に相談したらいいのかわからない」「これって専門的な支援が必要なの?」と、不安になりますよね。
そんなときこそ、専門機関や支援先を活用することで、安心して前に進むことができます。
支援は「何かあってから」ではなく、“困り始めたとき”が相談のベストタイミング。
ここでは、保護者が気軽に頼れる3つの支援先をご紹介します。
「ひとりで悩まなくていいんだ」と思えるヒントが見つかるはずです。
地域の児童発達支援・相談機関を活用しよう
まず相談先としておすすめなのが、各自治体が運営・委託している「児童発達支援センター」「子ども家庭支援センター」などの地域支援機関です。
ここでは、保護者向けの相談窓口が設けられていて、
- 子どもの発達のこと
- 家庭での関わり方
- 通園や療育の選択肢
- 行動に対する対応方法
などについて、発達の専門家(保育士、臨床心理士、言語聴覚士など)が一緒に考えてくれます。
しかも、多くの機関は無料で相談可能。最初は電話相談や面談からスタートできるので、初めての方でも安心です。
「いきなり病院に行くのはちょっと…」と感じている方は、まずこうした地域支援機関に相談するのが気軽でおすすめです。
発達障害者支援センターで専門的な支援を受ける
もう一歩踏み込んだ支援を受けたい場合は、都道府県に1つ以上設置されている「発達障害者支援センター」が心強い存在です。
ここでは、
- 発達障害に関する専門的なアセスメント(評価)
- 家庭や学校との連携支援
- 必要に応じた医療・福祉機関の紹介
- 長期的な支援プランの立案
など、より専門的な視点からのサポートが受けられます。
対象は子どもだけでなく、思春期や成人期を見据えた支援も対応しているので、
「今だけじゃなくて将来のことも見据えて相談したい」
という方にもおすすめです。
注意点としては、事前予約が必要なことが多いため、連絡の際はホームページや電話で確認を。
一度相談をすると、継続的なサポートを受けられることも多く、安心して支援の場を広げていけます。
まずは病院でチェック!身体のトラブルの見極め方
子どもが陰部を頻繁に触っている場合、見落としたくないのが“身体的なトラブル”の有無。
たとえば、
- 湿疹やかぶれによるかゆみ
- トイレ後のふき残しや不衛生な状態
- 感染症や炎症(尿道炎・膣炎など)
- 下着や紙パンツが合わないことによる不快感
など、実際に「不快感」があって触っていることも少なくありません。
このような場合、まずは小児科や皮膚科、場合によっては泌尿器科・婦人科などの専門医に相談することで、
「行動の原因が体の問題かどうか」が明確になります。
発達障害のある子どもは、「かゆい」「痛い」と言葉でうまく伝えられないことも多いため、“行動でサインを出している”という視点がとても大切です。
身体的なトラブルが見つかれば、それを解決することで触る行動が自然と減る場合もあります。
まずは体の状態をチェックしておくことが、安心の第一歩になります。
\ここまでのまとめ/
- 困ったときは、ひとりで悩まず“地域の支援機関”に相談を
- 児童発達支援センターや子ども家庭支援センターは、無料で相談可能な心強い味方
- より専門的な支援が必要な場合は、発達障害者支援センターを活用しよう
- 陰部を触る行動の裏に“身体的トラブル”が隠れている可能性もあるので、まずは医療機関でのチェックも大切
- 早めの相談が、子どもにとっても親にとっても安心への第一歩になる
まとめ~「なんでこんなことを…」と思ったら、それは成長のサインかも。叱らず、寄り添い、安心できる関わりで子どもの心を守ろう!
子どもが陰部を触る行動を見たとき、「なんでそんなことするの?」「やめなさいって言ってるのに…」と感じたことがある方も多いと思います。
でも、この記事を通して見てきたように、この行動には必ず“理由”や“背景”があるんです。
とくに発達障害のある子どもたちは、
- 感覚が過敏・鈍感で刺激を求めていたり
- 不安やストレスで心を落ち着けようとしていたり
- 性に対する自然な関心が芽生えていたり
- なんとなく習慣として身についてしまっていたり
…と、大人にはわかりにくいけれど、本人にとっては“意味のある行動”としてやっている場合がほとんど。
だからこそ、「やめさせる」ことよりも、「なぜその行動をしているのか」に目を向けることが何より大切なんです。
また、叱ったり否定的な言葉をかけることで、
- 自分の身体を恥ずかしいものと思ってしまう
- 性に関する話を「してはいけない」と思い込む
- 親との信頼関係が崩れてしまう
といった深刻な心の傷につながるリスクもあります。
一方で、「気持ちはわかるよ」「ここなら大丈夫だよ」と伝えたり、
感覚を満たす遊びや代替行動を用意してあげることで、子どもは安心感を持ちながら少しずつ行動を変えていくことができます。
また、家庭だけで抱え込まず、園や学校、地域の専門機関とつながることで、より的確な支援が受けられ、親の心もぐっと軽くなります。
行動の裏には、その子なりの気持ちやサインが隠れている。
それに気づいて、寄り添っていくことこそが、親としてできる最大の支えなのかもしれません。

以上、「【保護者必見】発達障害の子どもが陰部を触るのはなぜ?子どもが安心できる正しい声かけ術」でした。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!











コメント