「なんか気になる…」と思ったとき、今日からできること
「うちの子、ちょっと他の子と違うかも?」
「目が合いにくい気がする…」「言葉が遅い気がする…」
そんな“なんとなく気になる”という感覚、実はすごく大切です。
でも同時に、「気にしすぎかも」「まだ小さいし様子見でいいよね」と、その気持ちを押し込めてしまう方も多いはず。
ここでは、そんな「気になる」の気持ちを大切にしながら、無理なくできる“今日からの行動”をご紹介します。
直感はスルーしないで!その“モヤモヤ”が大事なサイン
子育てをしていると、周りの子と比べてしまったり、「うちの子ちょっと違うかも…?」と感じることってありますよね。
特に1〜3歳ごろは発達のスピードに個人差があるため、なおさら気になりやすい時期です。
でも実はその「なんとなく違和感がある」という“親の直感”こそが、発達の気づきの入り口になることが多いんです。
これは心理士さんや保健師さんもよく言うことで、日々いちばん近くで子どもを見ている親の感覚は、決して軽視できないとされています。
もちろん、直感=発達障害というわけではありませんが、気づいた“今”だからこそ、できることもたくさんあります。
初期対応の第一歩は「じっくり観察」
いざ気になることが出てきたとしても、すぐに病院に行くほどでもない…そんなときは、まず「よく観察すること」から始めてみましょう。
たとえば、次のようなポイントを日常の中で少し意識してみてください:
- 名前を呼んだときの反応の有無
- アイコンタクトや指差しの頻度
- 遊び方や興味の対象
- 同じことを繰り返す行動がないか
- 言葉の使い方や身振り手振りでの意思表示
こういった観察を「記録として残しておく」ことで、後から相談する際にとても役立ちます。
しかも、「うん、今日はちゃんと反応してた」「あ、これは繰り返してるな」など、子どもの成長を“自分の目”で確認できることで、不安が少しやわらぐこともあるんです。
ひとりで抱え込まない環境づくりも大切
もしあなたが、「誰にも話せない」「不安だけど相談するのが怖い」と感じているなら、それはとても自然なことです。
でも、その不安をずっとひとりで抱え込んでしまうと、だんだん心も疲れてしまいます。
そんなときは、まずは身近な人に少しだけでも打ち明けてみることから始めてみませんか?
たとえば、
- 同じ年頃の子どもを持つママ友
- 保育士さんや担任の先生
- 保健センターの相談員さん など
「うちの子、ちょっと気になることがあって…」と話すだけで、「うちもそうだったよ」「それは個性かもしれないね」と返ってきて、気持ちがスッと軽くなることもあります。
また、相談する=すぐに診断される、ということではありません。
気軽に話せる場所や人をひとつ持っておくと、心の支えにもなります。
焦らなくて大丈夫。
でも、「なんか気になるな」と思えた“今”は、親としてすごく大事なアンテナが立った瞬間でもあるんです。
その気持ちを見過ごさず、少しずつでも行動に変えていけるよう、次のステップへとつなげていきましょう。
見逃さないで!自閉症の“かもしれないサイン”とは
「なんとなく他の子と違う気がする…」
「目が合いにくいような、そうでもないような…」
そんな“ちょっと気になる行動”って、実は見逃されやすいんです。
でも、早めに気づくことで子どもに合った支援や関わり方を見つけやすくなるのも事実。
ここでは、自閉症スペクトラム(ASD)のサインとしてよく言われる行動や、誤解しやすいポイントについて、わかりやすく解説していきます。
年齢ごとに違う「気になる行動」って?
自閉症のサインは、年齢や発達の段階によって見え方が変わることがあります。
たとえば、1歳で指差しがないのと、3歳で集団遊びを避けるのとでは、意味することが違ってくるんです。
▼年齢別の「気になるかも」チェック例
- 1歳〜1歳半ごろ
→ 名前を呼んでも振り向かない、アイコンタクトが少ない、指差しをしない - 2歳ごろ
→ 言葉の発達が遅い、オウム返しが多い、一人遊びばかりしている - 3歳以降
→ 友だちとのやりとりが苦手、ごっこ遊びに入れない、ルール変更でパニックになる
もちろん、これらの行動があったからといってすぐに「自閉症」と決まるわけではありません。
でも、いくつかの特徴が“セット”で見られる場合には注意が必要です。
「目が合わない」「言葉が遅い」だけで判断しないで
よくある誤解のひとつが、「目が合わない=自閉症」「言葉が遅い=発達障害」といった、単一の行動で判断してしまうこと。
たとえば…
- 人見知りが強くて目を合わせない子もいる
- 単語が少なくても、ボディランゲージで豊かにやりとりしている子もいる
こうしたケースもたくさんあります。
大事なのは、「目が合うかどうか」だけでなく、「どんなふうに人と関わろうとしているか」全体を見ること。
言葉の数よりも、気持ちを伝えようとする姿勢や表情、行動に注目すると、その子の“伝えたい気持ち”が見えてくることもあります。
他の子と違う=発達障害?誤解しやすいポイント
「同じ月齢の子はもっとしゃべってるのに…」
「〇〇ちゃんはちゃんとお友だちと遊べてるのに…」
周りの子と比べて不安になる気持ち、すごくよくわかります。
でも、「違う=発達障害」というわけではないということも、忘れないでください。
子どもにはそれぞれ、
- 得意なことと苦手なこと
- 成長の早い部分とゆっくりな部分
- 関わりのスタイル(マイペース/社交的など)
…があります。
ときには、「発達のスピードの個人差」や「性格の傾向」で説明がつくこともあるんです。
だからこそ、焦らず冷静に、“その子らしさ”と“発達の様子”の両方を見る視点を持つことが大切です。
そして、どうしても気になるときは、誰かに話してみることが次のステップへの一歩になります。
その不安、ちゃんと伝える準備できてる?家庭での記録のススメ
「気になることはあるけど、相談に行ったらちゃんと伝えられるかな…」
「うまく説明できる自信がない…」
そんなふうに思ってしまうのって、実はとっても自然なことです。
でも安心してください。家庭でのちょっとした“記録”があるだけで、相談がグッとスムーズになるんです。
ここでは、「どんな行動を見ておけばいいの?」「何を記録すればいいの?」という疑問にお答えします。
スマホひとつ、メモ帳ひとつでOK!今日からすぐに始められますよ。
見るべき行動は?チェックの視点は“関わり”にあり
「目が合うかどうか」「言葉が出ているか」などももちろん大事ですが、
実はそれ以上に大切なのが、子どもが人とどう“関わろう”としているかという視点です。
たとえばこんな行動を観察してみましょう:
- 名前を呼んだときに反応する?しない?
- 親の指差しを追うか、まったく見ないか
- 遊んでいるとき、大人に「見て!」とアピールしてくる?
- 遊びや食事のときの表情、喜怒哀楽の出し方
- 一人遊びのときに、こちらの存在に気づいていそうかどうか
大事なのは、発達の「できる/できない」よりも、“関わろうとしているかどうか”の姿勢に注目すること。
その子なりに頑張ってコミュニケーションを取ろうとしている姿が見えるかが、支援や診断の手がかりになるんです。
スマホでOK!相談前に撮っておきたい動画3選
相談先に行ったとき、子どもがいつもの様子を出してくれるとは限りません。
そんなときに役立つのが、家庭で撮っておいたスマホ動画!
診察室では見せない仕草や関わり方を見てもらえるので、専門家もよく「動画があると助かります」と言います。
おすすめはこの3つ:
- 呼びかけたときの反応(名前を呼ぶ、目が合うか)
- 遊びの様子(ひとり遊びか、見せようとするか、並べるだけか)
- 会話ややりとりの場面(声かけにどう返すか、表情の反応など)
長く撮らなくてOK!30秒〜1分程度で十分です。
「これ、ちょっと気になるな…」という場面があれば、パッと撮っておくとあとでとても役に立ちます。
書くだけで安心!簡単にできる「育児記録術」
動画に加えて、「ちょっとしたメモ」もものすごく効果的。
特に、「いつから」「どんなときに」「どれくらいの頻度で」という情報は、相談時に非常に重宝されます。
でも、かたく考えなくて大丈夫。たとえばこんなふうに簡単に書いてみましょう:
📝 育児メモの例:
- 5/10 お名前呼んでも3回に1回くらいしか振り向かない
- 5/12 積み木を色順に並べる遊びをずっとやっていた(30分)
- 5/13 「ごはんだよ」と声をかけると「うー」とだけ言って近づいてきた
- 5/14 犬の動画を見て「わんわん!」とはっきり言えた!
こんな感じで、「ちょっと気になること」「できたこと」「びっくりしたことなどを気軽にメモするだけでOKです。
特に記録をつけていくと、「できる日もあるんだな」「少しずつ反応が増えてるかも」といった成長の兆しも見えやすくなるので、親としての安心材料にもなります。
記録は、自分の安心のためにも、子どもの未来のためにもなる“見える化ツール”です。
「うまく説明できないかも…」と思っている方こそ、ぜひ今日からできる小さな記録を始めてみてくださいね。
診断はゴールじゃない!流れと心構えを知っておこう
「もしかして自閉症かも…」と思って相談に行った先で、「診断を受けた方がいいですね」と言われることがあります。
でもここで知っておいてほしいのが、診断が“終わり”じゃないということ。むしろ、そこからがスタートなんです。
診断までの流れや「グレーゾーン」の意味、そして親として大切にしておきたい心の持ち方を、一緒に確認していきましょう。
診断までのステップをざっくり解説
まず、発達の相談をしたあと、実際に「診断」を受けるまでにはいくつかの段階があります。
ここではよくある一般的な流れを、ざっくりと紹介します。
▼発達の診断までの主なステップ
- 保健センターや小児科などでの初期相談
→ 気になる行動について話し、必要に応じて紹介状をもらうことも。 - 発達外来・小児精神科・療育センターなどの専門機関を受診
→ 簡単な問診や行動観察から始まり、保護者への聞き取りなどが行われます。 - 発達検査の実施(WISC、K式など)
→ 年齢に応じた検査を行い、全体的な発達の様子を把握します。 - 医師・専門家による総合的な判断と診断
→ 結果をもとに、必要な支援や療育の提案がなされます。
このプロセスには数週間〜数ヶ月かかることもあるので、時間に余裕を持って動くことが大切です。
また、地域によって受診先の体制は異なるため、まずは自治体や主治医に相談するのがスムーズな一歩です。
「グレーゾーン」ってどういう意味?
発達に関する相談の中でよく出てくるのが、「グレーゾーン」という言葉。
これは、明確に診断名がつくわけではないけれど、発達に少し気になる特徴がある状態を指します。
例えば…
- コミュニケーションは取れるけど、集団が苦手
- こだわりが少し強くて、柔軟な対応が難しい
- 年齢相応の言葉の発達が見られないが、生活には大きな支障がない
など、“黒”でも“白”でもない=グレーな部分がある子どもたちが、このゾーンに含まれます。
グレーゾーンと言われた場合でも、必要に応じて療育を受けたり、保育園での配慮を受けられるケースが多くあります。
つまり、診断がないと支援が受けられない、ということはありません。
親が不安に振り回されないために大切なこと
診断を受けるとき、親としてはいろんな気持ちが湧いてくると思います。
「やっぱりそうだったんだ…」「この先どうなるの?」と、不安やショックを感じるのは当然のこと。
でも忘れないでください。診断は“ラベル”ではなく、“その子に合った支援を受けるためのヒント”です。
たとえば…
- 子どもが過ごしやすくなる環境を整えるため
- 困っていることを、少しでもラクにするため
- 学校や園での配慮を受けやすくするため
そのために、専門的な視点で「今の発達の状態」を知ることが、実はとても役に立つんです。
そして何より、子ども自身は診断名を背負って生きるのではなく、“その子らしく育っていくこと”が一番大切。
私たち大人がその成長をサポートしていく、という気持ちで関わっていけたら十分です。
不安なときは深呼吸。焦らなくて大丈夫。
「診断を受ける=重いこと」ととらえず、未来の選択肢を広げるためのツールとして受け止めてみてくださいね。
まとめ|悩んでいるあなたへ。いま、できることから始めよう
「目が合わないかも」「言葉が遅いかも」「他の子とちょっと違うかも」
そんなふうに感じて、検索して、この記事にたどり着いたあなた。
それって、すごく大きな“気づき”であり、子どもにとっても大きな“味方”がいるということです。
このページをここまで読んだということは、きっとあなたの中で、
「何かしたほうがいいのかな」「でも、まだ決めきれないな」
そんな揺れる気持ちがあるのかもしれません。
大丈夫です。今すぐ全部を解決しなくていいんです。
まずは、“気になる”という気持ちを認めて、そこからできることを、少しずつ始めてみましょう。
相談=すぐに診断、ではないから安心して
「相談に行ったら、すぐに“自閉症です”って言われちゃうのかな…」
そんなふうに不安になって、なかなか相談に踏み出せない人も多いと思います。
でも実際は、相談=診断される、というわけではありません。
相談の多くは、「様子を一緒に見ましょう」とか、「家庭でできることを一緒に考えてみましょう」といった“対話ベースのサポート”が中心です。
そして、話すだけでスッキリしたり、「こんな対応があるんだ」と新しい視点に気づくこともたくさんあります。
だからこそ、「相談すること=重い決断」ではなく、「自分と子どもをラクにする選択肢のひとつ」くらいの気持ちで大丈夫です。
早く気づけた分、サポートも早く届く
発達に限らず、早めに気づいて動くことで、子どもに合った支援や関わり方が見つけやすくなるのは間違いありません。
たとえば、
- 言葉の遅れに合わせた関わり方がわかる
- 保育園や幼稚園で配慮してもらえる
- 療育のような専門支援につながりやすくなる
など、子どもにとってラクになる環境を早めに整えてあげられるという意味でも、「気づいたとき」が最良のタイミングなんです。
そして何より、親のほうも、「どうしたらいいの?」という不安から「こうすればいいんだ」という安心に変わっていきます。
以上【体験談あり「自閉症かも…」と感じたとき最初に読むべきページ|親ができる初期対応マニュアル】でした。

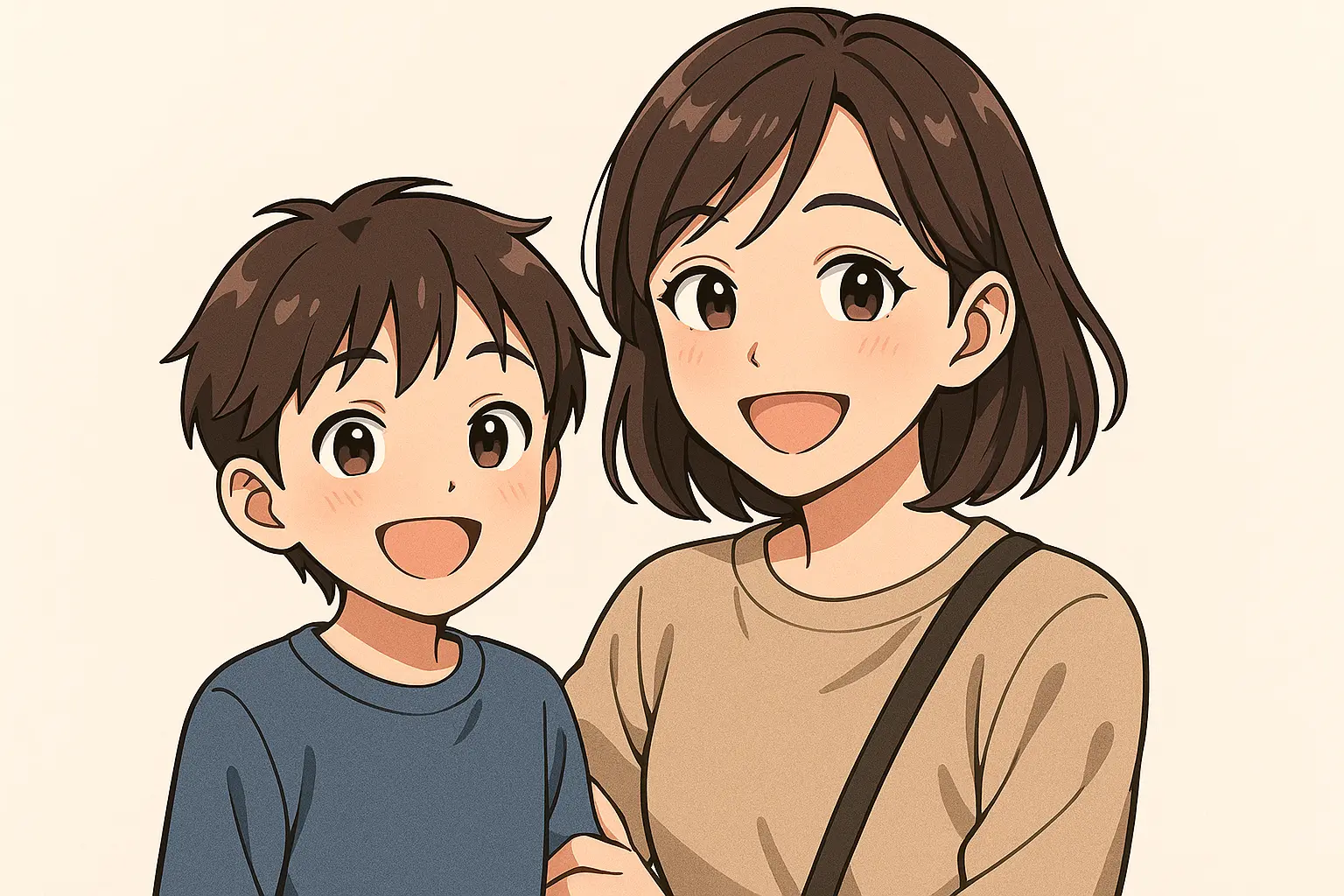









コメント