自閉症の子どもと感覚過敏・鈍麻をわかりやすく解説
自閉症の子どもを育てていると、「なんでこんなに音に敏感なんだろう?」「どうして服のタグを嫌がるの?」と不思議に思うことってありませんか?
実はそれ、「感覚の感じ方の違い」 が関係しているんです。ここを理解すると、子どもの行動の背景が見えてきて、日常が少しラクになります。
感覚過敏と感覚鈍麻の違いとは?行動にどう影響するのか
感覚には、耳で聞く「聴覚」、目で見る「視覚」、手で触る「触覚」などがあります。
自閉症の子どもは、これらの感覚が 「過敏」 か 「鈍麻」 のどちらかに偏りやすいんです。
- 感覚過敏:音や光、触れたものを「強すぎる!」と感じる状態
例)掃除機やドライヤーの音に耳をふさぐ、服のタグや靴下の縫い目がチクチクして我慢できない - 感覚鈍麻:逆に、刺激を「足りない」と感じてしまう状態
例)体を強く揺らす遊びを好む、同じ音を繰り返し聞きたがる、壁や物に体をぶつける
つまり、「過敏だから避ける」、「鈍麻だから求める」 という行動がよく見られるんです。
これが、日常生活で「なんでうちの子はこれを嫌がるんだろう?」「どうしてわざわざ同じことを繰り返すんだろう?」という疑問につながります。
自閉症の子が感覚刺激を求める理由とその心理
子どもが感覚刺激を求めるのには、ちゃんと理由があります。
大きく分けると3つです。
- 気持ちを落ち着けるため
不安や緊張が強いとき、自分に合った刺激で安心しようとします。
例)お気に入りのスクイーズを握ると落ち着く - 楽しい感覚を味わうため
触ったときの「ぷにぷに感」、光が動くキラキラ感など、心地よさを求めているんです。 - エネルギーを調整するため
じっとしていられないときに、体を動かす刺激でバランスを取ろうとします。
つまり、ただ「こだわっている」わけではなく、子どもなりの自己調整の方法 なんですね。
感覚刺激グッズが育児をラクにする効果と役割
ここで活躍するのが 感覚刺激グッズ です。
「手で触って安心するもの」「光や音で集中できるもの」など、子どもの感覚に合ったグッズを使うことで、育児のしんどさがぐっと減るんです。
たとえば…
- 癇癪対策:落ち着きやすいグッズを渡すことで爆発を防ぐ
- 集中力UP:手を動かすことで、学習や遊びに集中できる
- 安心できる居場所作り:グッズがあるだけで「ここなら大丈夫」と思える
つまり、感覚刺激グッズはただの「おもちゃ」ではなく、ママと子どもの毎日をスムーズにする “心のお守り” のような存在なんです。
【完全保存版】自閉症におすすめの感覚刺激グッズ一覧
感覚刺激グッズとひとことで言っても、種類は本当にたくさんあります。
子どもによって「落ち着くポイント」や「刺激が欲しいポイント」は違うので、まずはいろいろなタイプを知っておくのが大事です。
ここでは、感覚ごとにおすすめのグッズをまとめました。「これならうちの子に合いそう!」 という視点で読んでみてくださいね。
触覚を満たすグッズ|スクイーズ・加重ブランケット・感触ボール
触覚を刺激するグッズは、子どもにとって 安心感を与えるアイテム になりやすいです。
- スクイーズ
握るとむにゅっとした感触で、ストレス解消にぴったり。癇癪が起こりそうなときに「ギューッと握ってごらん」と渡すと、気持ちが落ち着くことがあります。 - 加重ブランケット
体全体にほどよい重みをかけることで、「抱きしめられているような安心感」 を感じやすくなります。寝つきが悪い子におすすめです。 - 感触ボール
ブツブツやぷにぷになど、さまざまな触感を楽しめるボール。遊びながら触覚刺激を取り入れられるので、「遊び×安心」 の両立に便利です。
聴覚を守るグッズ|ノイズキャンセリングイヤーマフ・ホワイトノイズ
聴覚が敏感な子にとって、日常の音はときに大きなストレスになります。
- ノイズキャンセリングイヤーマフ
電車やスーパーのざわざわが苦手な子に大活躍。「外出が怖くなくなる」 というメリットがあり、行動の幅を広げてくれます。 - ホワイトノイズマシン
「ザーッ」という一定の音で周囲の雑音をかき消すグッズ。寝かしつけや集中タイムに使うと、余計な音に邪魔されずに安心できる空間 を作れます。
視覚を整えるグッズ|オイルタイマー・光るおもちゃ・癒しのプロジェクター
視覚からの刺激は、子どもにとって「落ち着くスイッチ」になることがあります。
- オイルタイマー
カラフルな液体がゆっくり落ちていくのを見ていると、自然と心が穏やかになる んです。癇癪後のクールダウンにもおすすめ。 - 光るおもちゃ
光の動きに集中することで、余計な刺激を忘れて安心できることがあります。暗い部屋で使うと、「安心できる小さな世界」 を作れます。 - 癒しのプロジェクター
天井や壁に星や波模様を映し出すタイプ。寝る前のリラックスタイムに最適で、「寝るのが楽しみになる」 きっかけになります。
前庭覚&固有受容覚を育てるグッズ|バランスボード・トランポリン・加重ベスト
体の動きや姿勢の安定に関わる「前庭覚」と「固有受容覚」を満たすと、落ち着きや集中力 に直結します。
- バランスボード
ゆらゆら揺れる動きでバランス感覚を育てます。室内でも使えるので、雨の日でもエネルギーを発散できます。 - トランポリン
ピョンピョン跳ぶことで体の感覚が満たされ、「スッキリした!」 という感覚を得られます。多動傾向のある子にもおすすめ。 - 加重ベスト
適度な重みで体を安定させるグッズ。学習中や食事中に着ると、じっと座っていられる時間が増える こともあります。
嗅覚・味覚を刺激するグッズ|アロマ・チューインググッズの活用
意外と見落とされがちなのが嗅覚や味覚。でも、気分の切り替え にとても効果的なんです。
- アロマ
ラベンダーやオレンジなどの香りで、リラックス効果を期待できます。寝かしつけや不安が強いときにおすすめです。 - チューインググッズ
専用のシリコン製アクセサリーやペンダントをかむことで、口の感覚を安定させる 効果があります。爪かみや服をかむ癖がある子にぴったりです。
このように感覚刺激グッズは、触覚・聴覚・視覚・前庭覚・嗅覚 と幅広くカバーできます。
「うちの子はどの感覚に困りごとが多いのか?」を観察しながら選ぶと、より効果的に取り入れられますよ。

感覚刺激グッズの正しい使い方と注意点
感覚刺激グッズはとても便利ですが、使い方を間違えると「逆効果」になってしまうこともあります。
大事なのは “バランス” と “タイミング”。そして、安全に配慮しながら「ほどよく」取り入れることです。ここでは、日常で役立つ使い方のコツをまとめます。
癇癪対策と遊びのバランスをどう取る?
感覚刺激グッズは「癇癪を落ち着けるためのもの」と思われがちですが、遊びの中に取り入れることも大切 です。
- 癇癪が起きそうなとき → 気持ちを落ち着かせるツール として渡す
- 元気いっぱいのとき → 遊びながら感覚を満たすツール として使う
例えば、スクイーズや感触ボールは「怒っているときに握らせる」だけでなく、普段から遊びに取り入れておくと、「楽しいもの=安心できるもの」 というポジティブなイメージが定着します。
癇癪対策と遊びの両方でバランスよく活用すると、子ども自身が「今はこれを使えば安心できる」と自然に選べるようになっていきます。
効果的なタイミングは?学習前・外出前・癇癪前兆での活用
感覚刺激グッズは「困ったときに渡す」だけではもったいないです。“予防的に使う” ことで、トラブルを未然に防げます。
- 学習前
トランポリンやバランスボードで体を動かすと、エネルギーが落ち着いて机に向かいやすくなります。 - 外出前
ノイズキャンセリングイヤーマフを準備しておくと、騒がしい場所でも安心。「お出かけ=不安」から「お出かけ=安心」 に変わります。 - 癇癪の前兆
表情やしぐさで「そろそろ危ないな」と感じたら、早めにグッズを渡して気持ちを切り替える。これが一番効果的です。
「事前に使う」「前兆を見逃さない」 この2つを意識するだけで、癇癪の爆発を減らせる可能性が高まります。
使いすぎは逆効果!依存を防ぐ工夫と声かけ
どんなに良いグッズでも、使いすぎは要注意 です。いつでもどこでもグッズに頼るようになると、子どもが「自分で気持ちを切り替える力」を育てにくくなってしまいます。
工夫のポイントは次の2つ。
- 「ここでだけ使える」ルールを作る
例)寝る前だけ加重ブランケットを使う、外出のときだけイヤーマフを使う - 声かけで気持ちの切り替えを支援する
「スクイーズをギューッとしたら、今度は一緒に絵本を読もう」など、次の行動へつなげる声かけ を意識しましょう。
グッズに頼りすぎず、「自分で落ち着く方法を見つける」 力を少しずつ育てていくことが大切です。
安全に使うための注意点|誤飲・けがのリスクを避ける方法
感覚刺激グッズは安全に使うことが大前提です。特に小さい子や感覚探求の強い子は、思わぬトラブルにつながることもあります。
- 誤飲のリスク
ビーズや小さなパーツが入ったおもちゃは注意。必ず「誤飲の心配がないサイズ」を選びましょう。 - けがのリスク
トランポリンやバランスボードは転倒に注意。マットを敷く、周りを片づけるなど環境を整えてから使うことが大事です。 - 素材の安全性
口に入れても大丈夫な素材かどうか確認することも忘れずに。特にチューインググッズは 「食品グレードのシリコン」 など安全性が保証されているものを選びましょう。
【おうち療育】感覚刺激グッズを日常に取り入れる実践法
感覚刺激グッズは「特別な療育の場」でしか使えないものではありません。
むしろ、毎日の生活の中に自然に組み込むことで、本来の力を発揮 してくれます。
ここでは「朝の支度」「食事」「お風呂」「寝かしつけ」など、ママが一番困りやすい日常シーンを中心に、実践的な活用方法をご紹介します。
朝の支度・食事・お風呂・寝かしつけで使える活用法
一日の流れの中には「つまずきやすいポイント」がたくさんありますよね。そこにうまく感覚刺激グッズを差し込むと、子どもの切り替えがスムーズ になります。
- 朝の支度
バランスボードに数分立って遊んでから支度を始めると、体のエネルギーが整い「着替えやすいモード」に入りやすくなります。 - 食事
感触ボールをにぎりながら座ると、手を動かすことで気持ちが落ち着き、食事に集中しやすくなります。 - お風呂
光るおもちゃや泡立てネットを取り入れると「苦手なお風呂=楽しい時間」に変わります。嫌がる行動を和らげる効果が期待できます。 - 寝かしつけ
加重ブランケットやプロジェクターの柔らかい光は、「安心できる眠りのスイッチ」 になります。
ポイントは「困っている場面にピンポイントで導入する」こと。無理なく続けやすい工夫が、ママの負担も減らしてくれます。
癇癪を落ち着かせる3ステップ実践法
癇癪はどのママも一番大変な瞬間。そんなときこそ、感覚刺激グッズが役立ちます。
ステップ1:予兆を見つける
「声が大きくなる」「体をそわそわ動かす」などのサインを見逃さない。
ステップ2:グッズで気持ちを切り替える
スクイーズを渡して「ギューッと握ってみよう」、オイルタイマーを見せて「落ちるのを一緒に見てみよう」など、五感を使って意識をずらす。
ステップ3:落ち着いたら褒める
「落ち着けたね」「がんばったね」と伝えて、安心感と自己肯定感 を育てる。
癇癪を「ただ止める」のではなく、「落ち着ける経験を積ませる」 ことが大事です。
遊びの中に自然に取り入れる工夫|運動遊び・光や音を使った遊び
感覚刺激グッズは「困ったときだけ」ではなく、遊びの時間に取り入れるのもおすすめです。
- 運動遊び
トランポリンでジャンプ → ボール投げ → ゴロゴロ寝転がる、という流れを作ると、体の感覚を満たしながら遊べる。 - 光を使った遊び
光るおもちゃやプロジェクターを使って「どの色が出るかな?」とクイズ遊びをすると、視覚的に楽しみながら安心感 も得られます。 - 音を使った遊び
ホワイトノイズや楽器のおもちゃを取り入れて「音探しゲーム」にするのも効果的。「遊び=刺激の調整」 につながります。
こうすることで、子どもは「自然に感覚を整える経験」を積みやすくなります。
グッズ+声かけで効果倍増!ママができる具体例
感覚刺激グッズだけでも効果はありますが、ママの声かけをプラスすることで安心感が倍増 します。
- スクイーズを握らせながら
「ギューッとしたら、スーッと気持ちが落ち着くよ」 - プロジェクターを見ながら
「キラキラきれいだね、一緒に数えてみようか」 - 加重ブランケットをかけながら
「ぎゅっと抱っこしてるみたいで安心するね」
こうした言葉は、子どもにとって 「気持ちを整理するヒント」 になります。
グッズは“道具”、声かけは“心の支え”。両方合わせて使うことで、育児がぐっとラクになりますよ。
年齢別に見る!感覚刺激グッズの選び方と活用法
子どもの発達段階によって、感覚刺激グッズの選び方や活用の仕方は変わってきます。
「今の年齢に合ったグッズ」 を選ぶことは、安心感を与えるだけでなく、子どもの「できる!」を増やすきっかけにもなります。
ここでは、幼児期・学童期・思春期に分けて、それぞれのおすすめ活用法をご紹介します。
幼児期(3〜6歳)|遊び感覚で取り入れる安心グッズ
この時期は、まだ「遊び=学び」の段階です。だから、楽しい遊びの延長で感覚を整えるグッズ を取り入れるのが効果的です。
- おすすめグッズ例
- スクイーズや感触ボール → 握ったり投げたりする中で触覚が満たされる
- トランポリン → 体を使って感覚を調整しながらエネルギー発散
- ポイント
無理に「落ち着かせよう」とするよりも、遊びながら自然に感覚を満たすのがコツ。
例えば、癇癪が出そうなときでも「スクイーズでジュースを作るごっこしよう」と誘うと、楽しみながら気持ちを切り替えやすい です。
幼児期は「楽しさ」重視で。安心感を遊びの中で育てていきましょう。
学童期(7〜12歳)|学習前後の切り替えに役立つアイテム
小学校に入ると、机に座って学習したり集団生活をしたりする時間が増えます。ここで大切なのは、「気持ちを切り替える」ためのグッズ を取り入れることです。
- おすすめグッズ例
- バランスボードやストレッチゴム → 勉強前に体を動かして集中しやすくする
- ノイズキャンセリングイヤーマフ → 図書館や教室での雑音を軽減し、安心して過ごせる
- ポイント
この時期の子は「頑張りたいけど疲れる」ことが多いので、学習の前後で感覚を調整する習慣 を作ると効果的。
例えば、「宿題の前に3分トランポリン」「勉強後にスクイーズでリラックス」など。
学童期は「切り替えのサポート」がカギ。学校生活をスムーズにするための味方としてグッズを使いましょう。
思春期(中高生)|持ち歩きやすいグッズで人目を気にせず安心
中高生になると、友達や周囲の目が気になるようになります。
この時期は、「人前でも自然に使える」「自分で管理できる」 グッズを選ぶのがポイントです。
- おすすめグッズ例
- 小型のチューインググッズ → アクセサリー風のデザインなら違和感がない
- 小さなスクイーズやスティック型のおもちゃ → ポケットに入れてこっそり握れる
- 小型アロマやハンドクリーム → 香りで気分を切り替えやすい
- ポイント
思春期は「親から渡される」よりも、「自分で選んで持つ」 ことが安心につながります。
ママが「どれがいい?」と一緒に選ぶプロセスも大切。子どもが 「自分の安心を自分で守れる」 感覚を持てるようにサポートしましょう。
思春期は「自立」がテーマ。グッズをツールとして活かし、自己調整力を育てるチャンスです。
自閉症の子に合う感覚刺激グッズを選ぶポイント
感覚刺激グッズは種類がたくさんあるので、どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。
ポイントは、「子どもの感覚特性に合っているか」「コスパはどうか」「実際の口コミはどうか」 の3つです。
ここを意識するだけで、失敗がぐっと減ります。
感覚過敏タイプ・鈍麻タイプに合ったグッズの見極め方
まず一番大切なのは、子どもが 「刺激を避けたいタイプ(過敏)」 なのか、「刺激を求めたいタイプ(鈍麻)」 なのかを見極めることです。
- 感覚過敏タイプ
→ 音・光・触感などを「強すぎる」と感じやすい子。
例:ノイズキャンセリングイヤーマフで音を和らげる、タグのない服や柔らかい布素材のグッズを選ぶ。 - 感覚鈍麻タイプ
→ 刺激を「もっと欲しい」と感じやすい子。
例:トランポリンで体を大きく動かす、加重ブランケットで重みを感じる、スクイーズで強く握る。
ここを間違えてしまうと、せっかく買ったのに「全然使ってくれない…」となりがちです。
「うちの子は何に敏感?何を求めがち?」 を普段の様子から観察するのが第一歩です。
コスパ重視!100均や手作りで代用できるアイデア
感覚刺激グッズは専門店で買うと高額なものも多いですよね。
でも、100均や手作りアイテムでも十分代用できる ものがあります。
- スクイーズや感触ボール → ダイソーやセリアで購入可能。種類も豊富。
- オイルタイマー → 100均のおもちゃコーナーに置いてあることも。
- 加重グッズ代わり → ペットボトルにビーズや小豆を入れて手作り。
- 視覚刺激グッズ → ライトアップするインテリア雑貨や光るスティックを活用。
高価なものを買う前に、「まずは安いもので試す」 のがおすすめ。
「子どもが気に入るかどうか」を見極めてから、本格的なものに切り替えると無駄がありません。
専門家・先輩ママのおすすめ口コミから選ぶコツ
最後に頼りになるのが、実際に使った人の声 です。
- 専門家の意見
作業療法士や発達支援の先生が紹介しているグッズは、安心感があります。
「どういう子に合うか」まで具体的に教えてくれるので、選びやすいです。 - 先輩ママの口コミ
実際に使った感想はリアルで参考になります。
「加重ブランケットは夏は暑いから、薄手タイプがおすすめ」など、使ってみないと分からない工夫 を知ることができます。
口コミを見るときのコツは、「うちの子と似ているタイプの子の体験談」 を探すこと。
これでグッズ選びの失敗をぐっと減らせます。

感覚刺激グッズと療育・支援法の組み合わせ活用
感覚刺激グッズは単体でも十分役立ちますが、療育や支援法と組み合わせることで効果が倍増 します。
実際に現場でも「グッズ+療育」がうまく機能すると、子どもの安心感や集中力がぐっと高まるんです。ここでは、よく取り入れられている組み合わせを紹介します。
リトミックや音楽療法との相性|音とグッズで落ち着く環境づくり
リトミックや音楽療法は、自閉症の子にとってとても人気のある支援方法です。音楽のリズムに合わせて体を動かすことで、感覚の調整や表現の幅が広がるんですね。
ここに感覚刺激グッズをプラスすると、より安心できる環境になります。
- リズム遊びの前に スクイーズを握って気持ちを落ち着ける
- 音楽に合わせて バランスボードに乗る ことで、体幹やリズム感を育てる
- 曲の終わりに オイルタイマーを見てクールダウン
音+グッズの組み合わせ は、興奮しやすい子どもに「落ち着ける仕掛け」を与えるのにぴったりです。
ソーシャルストーリーや行動療法と合わせるメリット
「ソーシャルストーリー」や「行動療法(ABAなど)」は、子どもに分かりやすく行動の流れやルールを伝える方法です。
ここに感覚刺激グッズを加えると、子どもの理解や行動の定着を助ける効果 が期待できます。
- ソーシャルストーリー+グッズ
例:「スーパーに行くときはイヤーマフをつけて安心しよう」と絵本風に伝えると、実際の場面で使いやすくなる。 - 行動療法+グッズ
例:頑張った後にスクイーズで遊べるようにすると、「やってみよう!」という動機づけ につながる。
グッズは「ご褒美」や「安心のツール」として活用でき、療育で学んだスキルを実生活に持ち帰る架け橋 になります。
学校・放課後デイでの活用事例と家庭連携の重要性
感覚刺激グッズは家庭だけでなく、学校や放課後デイサービスでも広く使われています。
- 学校での事例
授業中にスクイーズを机の下で握ることで集中できた、音読の時間にイヤーマフをつけて安心して参加できた、などの声があります。 - 放課後デイでの事例
トランポリンや加重ブランケットを取り入れて「活動の前後で切り替えがスムーズになった」という報告もあります。
そして何より大切なのが、家庭と支援先の連携。
「家ではこのグッズをよく使っています」「学校ではこれが効果的でした」と情報を共有すると、子どもにとって 一貫性のある安心環境 を作ることができます。
グッズは場所をつなぐ“共通言語” のようなもの。家・学校・デイが同じ方向で取り組むと、子どもが安心して過ごせる場面が増えていきます。
【Q&A】感覚刺激グッズに関するよくある悩みと解決法
感覚刺激グッズは便利ですが、ママたちからは「気になる悩み」もよく聞かれます。
ここでは、実際に多い3つの質問に答える形で、解決のヒントをご紹介します。
「依存しすぎないか心配…」への対処法
グッズに頼りすぎて「ないと生活できないのでは?」と不安になるママも多いです。
確かに、感覚刺激グッズは安心を与える“補助輪”のような存在。ですが、上手に使えば依存は防げます。
- ルールを決めて使う
「外出のときだけ」「寝る前だけ」など、場面を限定すると自然にメリハリがつきます。 - 声かけで次の行動につなげる
「スクイーズを握ったら次は宿題ね」といったように、グッズ→行動の流れ を作るのが効果的です。
ポイントは、グッズを 「気持ちを落ち着けるきっかけ」 にすること。最初は頼っても大丈夫。徐々に自分で切り替える力を育てていけばいいんです。
「お金をかけずに工夫できる?」100均&手作りアイデア
感覚刺激グッズは専門品だと高価なものも多いですが、100均や手作りでも十分工夫できます。
- 100均アイテム
- スクイーズや感触ボールは定番
- 光るスティックやオイルタイマーはおもちゃコーナーにあり
- 手作りアイデア
- ペットボトルにビーズやスパンコールを入れて「スノードーム風ボトル」
- 布袋に小豆を入れて「手作り加重袋」
- 色とりどりの布切れで「感触遊び袋」
大事なのは「お金をかけること」ではなく、子どもに合った感覚を見つけること。まずは気軽に試せる方法から始めてみましょう。
「外出時に使うのは恥ずかしい?」持ち運びに便利な小型グッズ
「人目が気になる…」というのもよくある悩みです。特に成長してくると、本人も「目立つのは嫌」と思うことがありますよね。
そんなときは、小型で目立ちにくいグッズ を選ぶのがおすすめです。
- ポケットサイズのスクイーズやストレスボール → 握っても周りからは気づかれにくい
- アクセサリー型のチューインググッズ → ペンダントやブレスレット風で自然に使える
- 小型アロマや香り付きハンドクリーム → 「リラックスアイテム」に見えるので違和感なし
さらに、「外出時に使うのは特別な工夫」 として取り入れると、本人の自尊心も保ちやすいです。
「これがあれば安心して出かけられる」という経験が積み重なることで、外の世界へのチャレンジも広がっていきます。
まとめ|感覚刺激グッズは子育てをラクにする“お守り”
感覚刺激グッズは、正しく使えば子育ての強い味方 になります。
癇癪で手がつけられなくなる前に落ち着けたり、学習や遊びに集中しやすくなったり、外出先で安心感を持てたり…。
まさに、ママと子どもの毎日に寄り添う“お守り”のような存在です。
大事なのは、「タイミング」「バランス」「子どもに合った選び方」 の3つ。
- タイミング → 癇癪が起きる前や学習前後など、効果的な瞬間に取り入れる
- バランス → 癇癪対策だけでなく、遊びやリラックスにも使って偏らないようにする
- 子どもに合った選び方 → 感覚過敏か鈍麻かを見極めて、その子に合ったグッズを選ぶ
この3つを意識するだけで、グッズが 「ただのおもちゃ」から「毎日を支えるツール」 に変わります。
また、感覚刺激グッズは おうち療育に自然に取り入れやすい のも大きな魅力です。
「100均で買えるもの」や「手作りで代用できるもの」も多いので、無理なく始められます。
そして、リトミックやソーシャルストーリーなどの支援法と組み合わせると、効果はさらに広がります。
最後に一番伝えたいのは、ママ自身の安心もとても大切 だということ。
グッズを活用することで「これで大丈夫」と思える瞬間が増えれば、ママの心もラクになります。
その安心感が子どもにも伝わって、親子で心地よく過ごせる時間 が少しずつ増えていきますよ。
以上【自閉症 感覚刺激グッズの使い方完全ガイド|癇癪・集中力UPに効くおうち実践法】でした

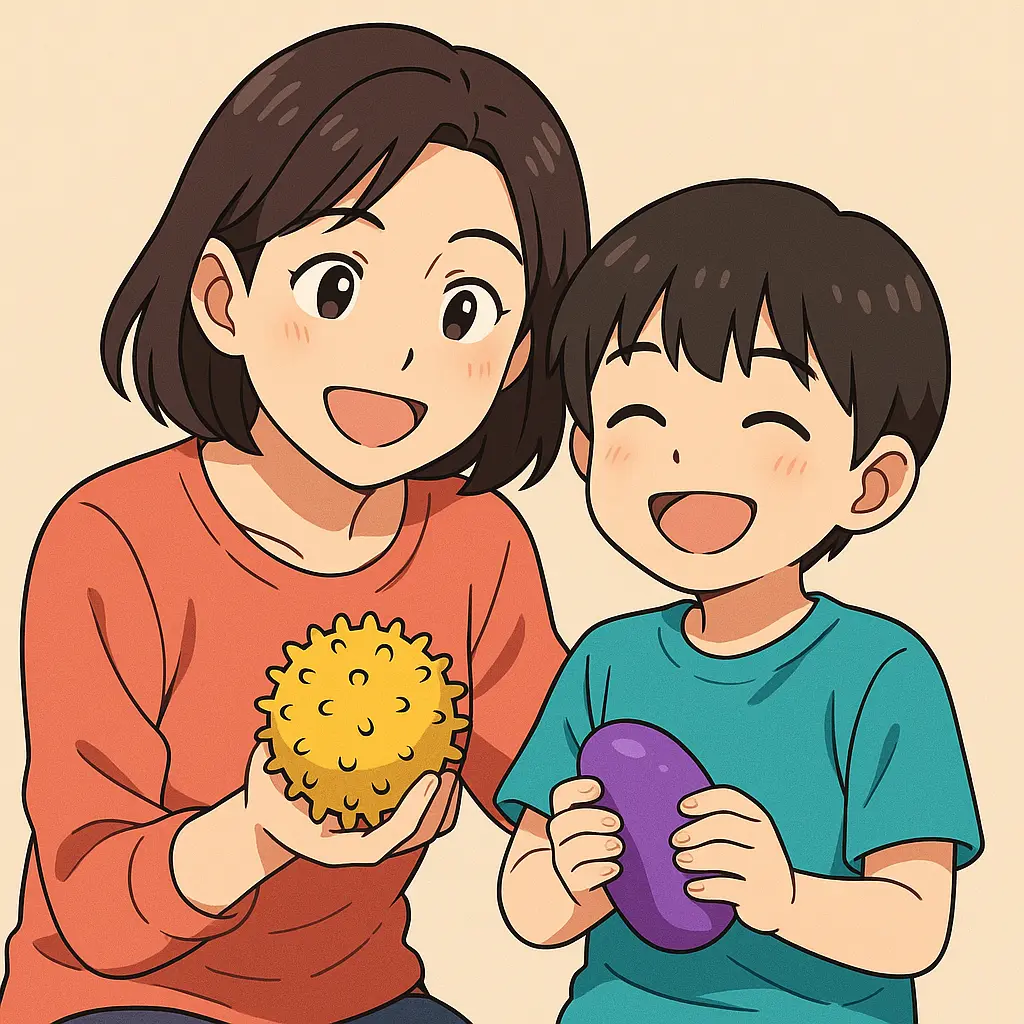









コメント