なぜ「発達障害」と「わがまま」の境界はわかりにくいの?
子育てをしていると、「これってただのわがまま?それとも発達障害の特性なの?」と迷う場面ってたくさんありますよね。特に周りから「甘やかしすぎじゃない?」なんて言われると、ママ自身も自信をなくしてしまうことがあります。
でも実は、この “境界線のあいまいさ” は、多くのママが同じように悩んでいるポイントなんです。
ここでは、どうしてその境界がわかりにくいのかを、いろんな角度から整理してみましょう。
わがまま行動の一般的な意味と子どもの成長段階
まず「わがまま」ってどういう意味でしょうか?
一般的には「自分の思い通りにしたい」「相手の気持ちより自分を優先する」という行動を指すことが多いですよね。たとえば「お菓子を買って!」と泣き叫んだり、順番を守らずに割り込んだりするような場面です。
でも考えてみると、子どもって成長の中で“わがまま”を通して学んでいく部分もあるんです。
2〜3歳のイヤイヤ期はまさにその代表で、「自分の気持ちを出せる」こと自体が発達のステップでもあります。だから一概に「わがまま=悪いこと」ではないんですよね。
発達障害特性と“わがまま”が混同されやすい理由
ではなぜ発達障害の子の行動が「わがまま」に見えやすいのでしょうか?
それは、発達障害の特性が“自分勝手に振る舞っているように見える”ことが多いからです。
- 感覚過敏で服のタグが気になって泣き叫ぶ
- 予定が変わるとパニックになる
- 興味があることに集中しすぎて呼びかけに応じない
こうした行動は、本人にとっては「困っているサイン」なのですが、周囲から見ると「わがままを通している」「わざと無視している」と誤解されやすいんです。
つまり、本人の中では“理由がある行動”なのに、外からは“わがまま”に見える。このギャップが境界をあいまいにしてしまうんですね。
境界が見えにくい日常場面(家庭・園・学校の例)
実際に「わがまま」と「特性」の境界がわかりにくい場面って、日常生活のあちこちにあります。
- 家庭:兄弟が遊んでいるおもちゃをどうしても譲れず、大泣きする
- 園(保育園・幼稚園):集団活動に入れず「やらない!」と拒否する
- 学校:授業中に立ち歩いてしまい「わざとふざけている」と言われる
親としては「できるときもあるのに、どうして今はできないの?」と混乱しますよね。これが「やらない(わがまま)」なのか「できない(特性)」なのか、判断が本当に難しいポイントなんです。
ママが境界に悩む心理|周囲の目や自己否定感
そして、境界がわかりにくいことがママを苦しめる理由のひとつが 「周囲の目」 です。
祖父母やママ友、さらには園や学校の先生から「甘やかしているんじゃない?」「しつけが足りない」と言われると、自分の子育てが間違っているのではと不安になります。
さらに、自分の中でも「これは特性だから仕方ない」と思う気持ちと「いや、甘えさせすぎかも」という気持ちが揺れ動いて、自己否定に陥りやすくなるんです。
でも忘れてはいけないのは、「悩む=それだけ子どもを真剣に考えている証拠」 だということ。境界に迷うのは決してママの弱さではなく、それだけ複雑なテーマだからなんです。

視点1|発達障害特性とわがままの違いを理解する
発達障害の子の行動は、一見「わがまま」に見えることがあります。でも実際には、特性による“困りごと” が背景にある場合が多いんです。ここでは、誤解されやすい行動の例や、違いを見分けるための視点を整理していきましょう。
衝動性・こだわり・感覚過敏が「わがまま」と誤解される例
発達障害の特性としてよく知られているのが 「衝動性」「こだわり」「感覚過敏」 です。
たとえば…
- 衝動性:スーパーで急に走り出してしまう
- こだわり:決まったお皿じゃないとご飯を食べない
- 感覚過敏:服のタグがチクチクして泣き叫ぶ
こうした行動は本人にとっては「どうしてもガマンできないこと」ですが、周りから見ると「わがままを言っている」「親が甘やかしている」と誤解されがちです。
実は“好き勝手をしている”のではなく、“本人にとって本当に困っていること”が原因なんですね。
発達障害特性と単なる甘え・わがままの区別ポイント
じゃあ、どうやって「特性による行動」と「単なる甘え・わがまま」を区別したらいいのでしょうか?
いくつかのポイントがあります:
- 繰り返し方:特定の場面で毎回起こるなら特性の可能性が高い
- 環境の影響:静かな場所なら落ち着けるけど騒がしいと爆発 → 感覚過敏の影響
- 本人の努力感:がんばっているけどできない様子がある → 「できない」であって「やらない」わけじゃない
つまり、「その行動の裏に“本人なりの理由”があるかどうか」を見極めるのが大切なんです。
年齢発達による自然な“わがまま”との違い
子どもは成長の中で「自分の気持ちを出す練習」をします。いわゆる イヤイヤ期 がそうですよね。
「おもちゃを貸したくない!」「ママじゃなきゃイヤ!」
こうした行動は、発達の過程で自然に出てくる“わがまま”です。
一方、発達障害の特性による行動は、年齢が上がっても続くことがあるのが大きな違いです。たとえば小学校高学年になっても強いこだわりや感覚過敏で生活に支障がある場合、それは「発達の段階で自然に消えていくわがまま」とは性質が違うんですね。
行動の背景を知ることで見えてくる境界線
最終的に大事なのは、行動そのものではなく“背景”を見ることです。
- 「宿題をやらない」→やる力がないのか?気持ちが切り替えられないのか?
- 「泣いて大騒ぎ」→甘えているのか?感覚がつらいのか?予定変更に対応できないのか?
こうして行動の背景を考えると、境界線が少しずつ見えてきます。
つまり、「わがままかどうか」ではなく「なぜそうするのか」に目を向けることが、ママにとっても子どもにとっても安心につながるんです。
視点2|環境調整で「わがまま」に見える行動は変わる
発達障害の子どもの行動って、環境が合うか合わないかでガラッと変わることがありますよね。
たとえば家では落ち着いていられるのに、園や学校ではトラブルが多い…なんて経験をしているママも多いと思います。
「同じ子なのに、どうして場所によってこんなに違うの?」
その答えは、子どもにとって環境が“過ごしやすいかどうか”にあるんです。
環境が合わないと発達障害特性が「わがまま化」する理由
発達障害の特性は、環境が合っていれば表に出にくいこともあります。
でも逆に、刺激が多すぎたり、予想外の出来事が続いたりすると、一気に行動に現れてしまうんです。
たとえば…
- 騒がしい教室で集中できず、立ち歩いてしまう
- 急な予定変更でパニックになり「行かない!」と拒否
- 匂いや音が強い場所で泣き叫んでしまう
こういう行動は、周囲から見ると「わがままを言っているように見える」のですが、実際は 環境が子どもの限界を超えてしまっているサインなんです。
親の声かけや対応次第で行動が変わるメカニズム
同じ場面でも、親の声かけや対応の仕方によって行動が変わることがあります。
たとえば…
- 「まだでしょ!」と強く叱ると、子どもはさらに反発
- 「あと5分で終わるよ」と予告すると、落ち着いて切り替えやすい
これは、「先が見える」かどうかで安心感が大きく変わるからです。
発達障害の子は、予測できない状況にとても不安を感じやすいんですね。
つまり、「わがまま」ではなく「どう対応されるか」で変わる行動も多いということ。親の一言で子どもの気持ちがラクになり、行動もスムーズになるんです。
周囲の理解不足で「わがまま」とラベルを貼られる問題
一番つらいのは、周囲の大人が特性を理解せずに“わがまま”と決めつけてしまうことです。
園や学校で「しつけができていない」「甘えさせすぎ」と言われた経験があるママも少なくないでしょう。
でもこれは、環境や特性を知らないことからくる誤解なんです。
本当は、支援や工夫次第で行動は大きく変わるのに、「わがまま」というラベルを貼られてしまうと、子ども自身も「自分はダメなんだ」と自己肯定感を下げてしまう危険があります。
だからこそ、周囲に正しく伝えること・理解してもらうことが大切なんです。
環境調整の工夫例(生活リズム・視覚支援・静かな空間)
じゃあ、具体的にどんな環境調整ができるのか?いくつか実践しやすい方法を紹介します。
- 生活リズムを整える:睡眠不足はトラブルの元。規則正しい生活で心を安定させる
- 視覚支援(スケジュール表・絵カード):予定を“目で見える化”すると安心感がアップ
- 静かな空間の確保:感覚が疲れたら落ち着ける場所(お部屋の一角や布団の中)をつくる
- 予告と見通し:「あと10分で終わるよ」と伝えるだけで切り替えがスムーズに
こうした工夫は「特別な支援」というより、ママや先生が少し意識するだけで変わる環境調整です。
視点3|癇癪や感情爆発は「わがまま」ではなくコントロールの未熟さ
子どもが突然大泣きしたり、物を投げたり、大声で叫んだり…。こうした「癇癪(かんしゃく)」や「感情の爆発」は、ママにとって一番つらい瞬間かもしれません。
つい「わがままを言ってるだけなのかな?」と思ってしまいますが、実際は違います。
発達障害の子どもの場合、気持ちのコントロールがまだ未熟で“うまく抑える力”が育ちにくいことが多いんです。つまり、わがままではなく“調整する力がまだ足りない”だけなんですね。
発達障害に多い「気持ちの切り替えが苦手」な特性
発達障害の子どもは、「切り替え」がとても苦手という特性を持つことがよくあります。
たとえば…
- 遊んでいたおもちゃを片付けるように言われると、大泣き
- テレビが突然終わると、パニックになる
- 思っていた予定と違うことが起こると、強く拒否
これは、気持ちの流れをスムーズに変える力(認知の柔軟性)が弱いためです。大人なら「しょうがない」と思えることでも、子どもには「世界が壊れた!」くらいに感じられるんですね。
切り替えができない=わがまま」ではなく「発達特性のひとつ」として理解することが大切です。
癇癪・パニックが「わがまま」と見られる仕組み
癇癪やパニックは、外から見ると「自分の思い通りにしたいから泣いている」ように見えます。
でも実際には、強い不安やストレスをどう処理していいかわからず爆発しているだけなんです。
- 「お菓子を買って!」と泣く → 単なるわがままに見える
- 実際は → 急な予定変更で不安、感覚過敏で疲れている、などの要因が隠れている
つまり、行動そのものだけを見ると“わがまま”に見えるが、背景を知ると“助けを求めるサイン”だとわかります。
親ができる感情コントロール支援の工夫
じゃあ、ママやパパにできることは何でしょうか?
大切なのは、「怒らないで落ち着きを取り戻す手助けをすること」です。
具体的には…
- 予告して心の準備をさせる:「あと5分でおしまいだよ」と伝える
- 感情に名前をつける:「悔しかったんだね」「嫌だったんだね」と共感する
- 安全な場所に誘導する:安心できる場所に移動してクールダウン
- 小さな成功体験を積ませる:「自分で気持ちを落ち着けられた!」という経験をつくる
こうした工夫は、「気持ちをコントロールする力」を少しずつ育てていくことにつながります。
癇癪を和らげる具体的対処法(落ち着くグッズ・深呼吸など)
癇癪やパニックのときにすぐにできる工夫もあります。
- 落ち着くグッズを渡す:お気に入りのぬいぐるみ、感触遊び、重たいブランケット
- 呼吸を一緒に整える:「スーハーしようね」と深呼吸を促す
- 視覚的に見せる:砂時計やタイマーで「あとどれくらい」を見える化
- 静かな空間に移動:光や音の刺激を減らして安心させる
大事なのは、「怒鳴って止めようとしない」ことです。癇癪は子ども自身もコントロールできなくて困っている状態なので、叱っても解決しません。むしろ「気持ちを落ち着けられる方法を見つけてあげる」ことが一番の支援になります。

視点4|「できない」と「やらない」の境界を見極める
子どもが言われたことをやらないとき、ママとしては「わざと?」「サボってる?」と思ってしまうことがありますよね。
でも実は、その行動には 「本当にできない」場合と「やらない(拒否している)」場合 があるんです。
ここを見極めるのはとても大事。なぜなら、できないのに“やらない”と叱ってしまうと、子どもの自信を失わせてしまうことがあるからです。逆に「やらないだけ」なのに全部助けてしまうと、甘え癖がついてしまうことも…。
発達障害による「できない」行動の典型例
発達障害の子どもがよく直面する「できない」には、いくつか典型パターンがあります。
- 注意が続かない:宿題に取り組んでもすぐ気が散ってしまう
- 作業の手順がわからない:服を着る、片付けをするなどのステップを覚えられない
- 感覚の問題:服のタグがチクチクして着られない、音が大きくて集中できない
- 言葉の理解が難しい:口頭での指示がわからず動けない
こうした場合、子ども自身も「やろうとしたのにできなかった」と感じていて、実は一番困っているのは本人だったりします。
単なる「やらない=わがまま」との違いを見分ける方法
「できない」と「やらない」を見分けるカギは、行動の背景に目を向けることです。
例えば…
- 宿題を「やらない」と言う → 本当は やりたいけど集中力が続かない
- 靴を「履かない」と駄々をこねる → 実は 靴下の感触が気持ち悪い
- ご飯を「食べない」と言い張る → 嫌いだから拒否なのか、食感が苦手で飲み込めないのか
“やらない=反抗”と決めつける前に「なぜそうしているのか?」を探る視点がとても大切です。
認知機能や発達段階を理解する重要性
子どもの行動を理解するときには、その子の発達段階や得意・不得意の認知機能を知ることが役立ちます。
- 5歳の子に「一人で片付けて」と言っても、まだ段取り力が未熟だから難しい
- 注意欠如特性がある子には、声かけだけでなく 視覚的なチェックリストが必要
- 作業記憶が弱い子は、複数の指示を一度に伝えると混乱してしまう
つまり「普通はできる年齢なのにできない」の裏には、発達の特性や認知の弱さが関係している場合が多いんです。
観察ポイント(繰り返し・一貫性・環境依存の有無)
「できない」と「やらない」を見極めるには、日常の観察がとても役立ちます。特に注目したいのはこの3つ。
- 繰り返し
毎回同じことで困っているか? それとも気分次第でできたりできなかったりするか? - 一貫性
ある場面では全然できないのに、他の場面ではできることはあるか? - 環境依存
家ではできないけど学校ではできる、逆に学校ではできないけど家ではできる、など環境で差があるか?
もし「どこでも一貫して難しい」なら、“できない”の可能性が高い。
一方で「できるのにやらないときがある」なら、“やらない=わがまま”に近い行動と考えられます。
視点5|専門家や支援機関とつながることで境界がはっきりする
「これは発達障害の特性?それともわがまま?」と迷うとき、ママひとりで答えを出すのはとても難しいものです。
そんなときに頼りになるのが、専門家や支援機関とのつながりです。第三者の目や専門的な知識を借りることで、ぼんやりしていた境界線が少しずつ見えてきます。
発達相談や医師が教えてくれる「特性と行動の違い」
自治体の発達相談や小児科、児童精神科などでは、子どもの行動を専門的に見てもらうことができます。
例えば…
- 衝動的に走り出してしまう行動 → 発達障害の「注意・衝動コントロールの特性」かもしれない
- おもちゃを片付けない行動 → 「片付け方を理解できていない」のか「やりたくない」だけなのかを見分けてくれる
専門家に相談すると、「これは特性だから工夫が必要」「これは年齢相応のわがまま」と整理してもらえるので、ママの中でモヤモヤしていた部分がスッキリすることも多いです。
保育園・学校との連携で得られる第三者の視点
家庭では手を焼いてしまう行動も、園や学校では違う姿を見せることがあります。
例えば「家では宿題を嫌がるけど、学校では集中できている」という場合、環境の違いが大きなヒントになります。
先生たちは毎日たくさんの子どもを見ているので、「発達段階でよくある姿」なのか「特性由来の行動」なのかを客観的に教えてくれる存在です。ママが一人で悩むよりも、先生と情報を共有し合うことで視野が広がります。
同じ悩みを持つママとのつながりで安心できる理由
同じように発達障害の子どもを育てているママとつながると、「うちだけじゃないんだ」とホッとできます。
支援センターの交流会やオンラインコミュニティでは、「わがままだと思ってたけど、実は特性だった」という体験談が聞けたり、逆に「その対応は“甘えさせすぎ”になるかも」というアドバイスがもらえたりします。
ママ同士だからこそ話せる気持ちがあるし、「悩みを共有できる場所」が心の支えになります。孤独に悩むよりも、気持ちがぐっと軽くなりますよ。
専門家との相談で境界がクリアになる実例
実際に、専門家に相談して境界が見えてきたケースを紹介します。
- 「片付けを何度言ってもできない」→ 検査で「作業手順を覚えるのが苦手」という特性が分かり、やり方を視覚化したらスムーズにできるようになった
- 「外出時に癇癪を起こす」→ 医師から「感覚過敏が原因」と説明され、静かな場所で休憩を入れる工夫で落ち着くようになった
- 「食事の好き嫌いが激しい」→ 栄養士に相談して「特定の食感が苦手」と分かり、調理法を変えるだけで食べられるようになった
このように、専門家は“できない理由”を具体的に教えてくれるので、「わがまま」なのか「特性」なのかが明確になり、対応も前向きに考えられるようになります。
境界を知ることでママが得られる3つのメリット
「発達障害の特性なのか、それともただのわがままなのか」――この境界を知ることは、ママの心を軽くするだけでなく、子どもとの関わり方を大きく変えてくれる力があります。
ここでは、境界を理解することで得られる3つの大きなメリットを紹介します。
子どもの行動を前向きにとらえられるようになる
境界を知ることで、ママは子どもの行動を「ただの問題行動」としてではなく、「特性があるからこうなっているんだ」と前向きに理解できるようになります。
たとえば…
- 「お友だちと遊べない=わがまま」ではなく、「コミュニケーションが苦手な特性があるから一人遊びを選んでいるんだ」
- 「同じ服しか着たがらない=頑固」ではなく、「感覚過敏で素材に敏感なんだ」
といった見方ができるようになります。
こう考えられると、「どうサポートすればいいか?」に視点が変わり、ママ自身が子どもの味方でいられる気持ちが強くなります。
イライラや自己否定感が軽減し心がラクになる
「また癇癪してる…」「なんでうちの子はできないの?」と感じると、ついイライラしたり、「私の育て方が悪いのかな」と自分を責めてしまうことってありますよね。
でも境界が分かれば、「これは子どもの性格の問題じゃなくて特性によるもの」と理解できます。
それだけで、ママの心はかなりラクになるはずです。
イライラの感情も、「仕方ないことなんだ」「工夫すれば乗り越えられることなんだ」と思えるようになると、自己否定感から解放されて、余裕を持って子どもに接することができるようになります。
家族や園・学校に正しく説明できるようになる
境界を知ることは、ママ自身の安心感だけでなく、周囲への説明にも大きな助けになります。
- パパや祖父母に「わがままなんじゃなくて、発達特性の影響なんだよ」と伝えられる
- 保育園や学校の先生に「こういう環境だと落ち着けるみたいです」と具体的にお願いできる
こうした説明ができると、家族や先生たちが理解して協力してくれる可能性がぐんと高まります。
その結果、ママが一人で背負う負担も減り、子どもにとっても安心できる環境が整っていきます。
ママがすぐに実践できる「境界を意識した子育ての工夫」
「これは発達障害の特性なのか、それとも単なるわがままなのか…」と迷うとき、ママができる工夫を知っていると安心ですよね。
ここでは、日常ですぐに取り入れられる子育てのヒントを紹介します。小さな工夫の積み重ねが、ママと子ども、どちらにとっても心地よい毎日につながります。
声かけの工夫(否定せず、行動の背景を伝える)
子どもが困った行動をしたとき、つい「ダメ!」「やめなさい!」と言ってしまうこと、ありますよね。
でも、否定ばかりだと子どもは「自分はダメな子なんだ」と思い込みやすくなります。
そこで大事なのが、行動の背景を言葉で伝える声かけです。
- 「大きな声を出したのは、びっくりしたからだよね」
- 「順番を待つのが苦手だから、イライラしちゃったんだね」
こんなふうに気持ちを代弁してあげると、子どもは「自分の気持ちを分かってもらえた」と安心できます。
先回り支援と環境調整でトラブルを予防する
発達障害の子どもは、環境によって行動が変わることが多いです。
例えば、人混みや大きな音のある場所に行くと、癇癪やパニックが起きやすい子もいます。
そんなときは「トラブルが起きる前に先回りする工夫」が役立ちます。
- 事前に予定を伝えておく(「今日はスーパーに行くよ。混んでるかもしれないから10分だけね」)
- 苦手な環境には、イヤーマフやお気に入りのおもちゃを持っていく
- 部屋の照明や音量を調整して、落ち着ける空間を作る
こうした工夫で、「わがままに見える行動」そのものを減らすことができるんです。
ごほうびや見通しを使って成功体験を積ませる方法
子どもは「できた!」という経験を重ねることで、自信を持てるようになります。
そこでおすすめなのが、ごほうびや見通しを活用する方法です。
- 「あと5分で終わったら、シールを貼ろう」
- 「今日はここまでできたら、おやつを食べよう」
こうした小さな見通しとごほうびは、子どもにとって「がんばれる理由」になります。
ただし、ごほうびはあくまできっかけ。目的は「やればできる」という感覚を育てることです。
癇癪やパニック時の安全確保と落ち着きルーティン
どんなに工夫しても、癇癪やパニックはゼロにはできません。
大切なのは、「起きたときにどう対応するか」です。
- まずは周りの安全を確保(家具をどける・危ない物を避ける)
- ママ自身も落ち着くために深呼吸
- 子どもには「落ち着けるルーティン」を用意する(毛布にくるまる・お気に入りのぬいぐるみ・静かな部屋へ移動)
この「落ち着きルーティン」を繰り返すことで、子どもは少しずつ「気持ちが収まる方法」を自分で学んでいけるようになります。
よくある悩みと境界理解での変化【体験談つき】
子育てをしていると、「これって発達障害の特性なの? それともただのわがまま?」と悩む場面が本当に多いですよね。
でも、境界を理解することで見方が変わり、ママの気持ちがぐっとラクになることがあります。ここでは、よくある悩みを例にしながら、境界を知ることでどう変わるのかを見ていきましょう。
「片づけしない=わがまま?」実は認知特性が背景に
「何度言っても片づけない。やっぱりわがままなのかな?」と思ったこと、ありませんか?
実はこれ、発達障害特有の認知の特性が関係していることがあります。
- 「どこから手をつけていいか分からない」
- 「“全部片づける”という曖昧な指示が理解しにくい」
- 「見通しが立たないと行動に移せない」
こうした特性があると、「片づけしない=反抗」ではなく、「できないから手をつけられない」というケースも多いんです。
「泣き続ける=甘え?」感情コントロールの未熟さが理由
買い物中やおうちで、泣き止まない子どもを見て「これは甘えてるだけ?」と感じることもありますよね。
でも実際には、発達障害の子どもは感情のコントロールがまだまだ未熟なことが多いです。
「やめたいけど気持ちが止められない」状態で泣き続けていることも。
これは甘えではなく、「気持ちのブレーキ」がまだ育っていないだけなんです。
「集団を乱す=迷惑?」感覚過敏や指示理解の困難さ
園や学校で「うちの子が集団を乱して迷惑をかけてしまう…」と悩むママも少なくありません。
でも、その行動の背景には 感覚過敏や指示理解の難しさがあることも。
- 周りの音や光が強すぎて耐えられない
- 指示が一度では理解できず動けない
- 急な予定変更に対応できず混乱する
こうした特性から、結果的に集団から外れてしまうことがあるんです。
「わがままだから乱している」のではなく、「環境が合っていないから困っている」と考えると、見方が変わりますよね。
境界を理解して変わったママたちのリアル体験談
実際に「境界を理解することで子どもとの関わりが変わった」というママたちの声を紹介します。
- Aさんの体験
「片づけしないのはわがままだと思っていました。でも、手順をカードにして見せたら少しずつ片づけられるように。できないだけだったんだと気づいて、イライラが減りました。」 - Bさんの体験
「泣き続けるのは甘えだと思っていたけど、気持ちを言葉で代弁してあげると落ち着くことが増えました。“この子なりに必死なんだ”と思えるようになりました。」 - Cさんの体験
「集団を乱してしまうのも“迷惑かけてる”と感じていました。でも先生から“感覚過敏の影響もある”と聞いて、耳栓や静かな休憩場所を用意したら落ち着けるように。周囲の理解の大切さを実感しました。」
まとめ|発達障害とわがままの違いを知れば子育てが安心に
子どもの行動を前に「これって発達障害の特性? それともわがまま?」と悩むのは、ママにとってとても自然なことです。むしろ、多くのママが同じように感じています。
でも、今回ご紹介してきたように、境界を理解することは「甘やかし」ではなく「正しい支援」につながるんです。
行動の背景を知ることで、「できない」を「やらない」と決めつけずにすみますし、感情の爆発や集団での困りごとも、ただの「迷惑」ではなく「特性のサイン」としてとらえられるようになります。
5つの視点を意識することで育児のストレスが減る
今回お伝えした 5つの視点(特性理解、環境調整、感情のコントロール、できないとやらないの違い、専門家とのつながり)を意識すると、子育ての見え方がガラッと変わります。
「わがまま」と思っていた行動の裏に、子どもなりの必死さや困り感があると気づけると、ママのイライラや自己否定感も軽くなります。
さらに、「どう対応すればいいか」が分かってくるので、育児の中で小さな成功体験を積み重ねやすくなるんです。
ママ自身が安心でき、子どもとの関係も前向きに変わる
大事なのは、ママ自身が安心して子育てできることです。
境界を知ることで「うちの子はダメなんだ」「私の育て方が悪いんだ」と思い込む必要がなくなります。
むしろ「この子にはこのやり方が合うんだ」と前向きに考えられるようになるはずです。
その安心感は、きっと子どもにも伝わります。ママが落ち着いて接することで、子どもも安心して少しずつ自分らしい成長をしていけるんです。
だからこそ、発達障害とわがままの境界を知ることは、ママと子どもの両方にとって大切なステップ。
「境界を理解する=支援の第一歩」 だと、どうか心に留めておいてくださいね。
以上【発達障害とわがままの違いは?境界を知って子育てがラクになる5つの視点】でした

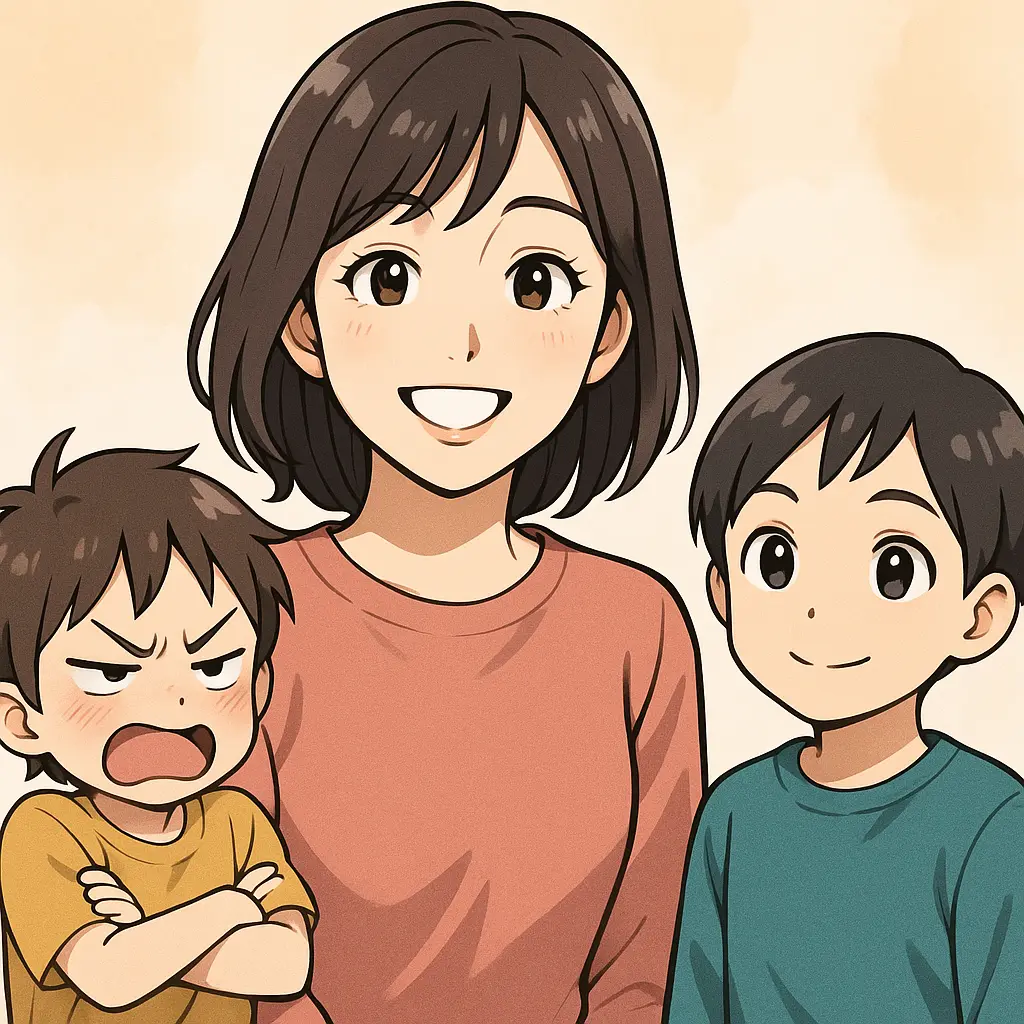









コメント