そもそも「落ち着くおもちゃ」ってどんなもの?感覚過敏な子に効く理由
「落ち着くおもちゃ」って聞くと、なんだか曖昧でふんわりしたイメージがありませんか?でも、発達特性のある子どもたち、特に感覚過敏や不安を感じやすい子にとっては、ただの“おもちゃ”以上の意味を持っています。
落ち着くって、どういう状態?
まず「落ち着く」というのは、外からの刺激でガチャガチャになっていた感覚や気持ちが、ゆっくり静かになっていく状態のこと。
これは、大人でも同じですよね。疲れてるときにお気に入りのアロマや音楽に包まれてホッとするような感覚です。
子どもの場合は、見たもの・聞こえた音・触った感触が「安心できる」「心地いい」と感じられると、自然と心と体の緊張がほどけていきます。
この“刺激を調整してくれる役割”をしてくれるのが、「落ち着くおもちゃ」なんです。
感覚過敏の子が「普通の環境」で疲れてしまう理由
発達特性がある子の中には、視覚・聴覚・触覚などの感覚がとっても敏感な子がいます。
例えばこんなことがよくあります:
- 教室の蛍光灯のチカチカがつらい
- 大きな音が急にするとパニックになる
- 洋服のタグや素材がチクチクして落ち着かない
私たち大人が何気なく過ごしている日常も、こういった子どもたちにとっては「常に戦いの連続」みたいなものなんです。
だからこそ、刺激を和らげてあげたり、自分で安心できる感覚を取り戻せるような“道具”が必要になります。それが「落ち着くおもちゃ」なんですね。
どんなおもちゃが“落ち着く”の?
落ち着くおもちゃにはいろんなタイプがありますが、共通しているのは以下のようなポイントです。
- 感覚が心地いい(ふわふわ・ぷにぷに・キラキラ・ゆらゆらなど)
- 自分のペースで触れられる(コントロールしやすい)
- くり返し遊べることで安心感がある
- 誰かと比べなくていい“ひとり時間”に使える
たとえば、ペットボトルにビーズや水を入れてキラキラと流れる様子を見たり、スクイーズのようなぷにぷにしたものを握ったり。視覚や触覚にやさしく働きかけて、心を落ち着かせてくれるおもちゃが人気です。
医療や療育の現場でも使われている
実はこの「感覚刺激で落ち着く仕組み」は、感覚統合療法(感覚統合アプローチ)の中でもよく使われている方法です。
作業療法士さんや発達支援の専門家たちも、「子どもが安心して過ごせるように、どんな感覚を取り入れるとよいか」をよく考えて活動に取り入れています。
つまり、「落ち着くおもちゃ」はただの遊び道具ではなく、“子どもをサポートするツール”として注目されているんです。
どんな子に向いてる?迷わないための「おもちゃ選び3つのポイント」
「落ち着くおもちゃって良さそうだけど、うちの子にも合うのかな?」
そんなふうに思った方、正直多いんじゃないでしょうか。
おもちゃって、一見どれも楽しそうに見えるけど、子どもの発達の段階や感覚の感じ方によって“合う・合わない”がけっこうハッキリ分かれます。
だからこそ、ただ「人気だから」「簡単に作れそうだから」ではなく、お子さんの特性に合わせて選ぶことが何より大切なんです。
ここでは、迷ったときに参考になる「おもちゃ選びの3つの視点」をご紹介します。
① 年齢と発達段階をチェック!
まず大事なのは、「何歳向けか」ではなく、その子が“どんな発達段階にいるか”を見ること。
たとえば…
- まだ感覚的な遊びがメインの子には、シンプルに握る・振る・見るなどの「五感で楽しめる」おもちゃがぴったり。例:キラキラボトル、ぷにぷにボールなど
- 手先が器用になってきた子には、「指先を使う」「並べる」「組み合わせる」遊びで集中力UP!例:ビーズ通し、フェルトの型はめパズルなど
- ごっこ遊びを楽しむようになった子には、想像力が広がるおもちゃが◎ 例:紙コップでつくるマイクやカメラ、段ボールハウスなど
年齢よりも、“その子が今どんな遊びをして楽しんでいるか”をヒントに選ぶと、すんなりハマることが多いですよ。
② 感覚のタイプに注目してみよう!
自閉症スペクトラムの子の多くは、感覚の感じ方に独自の傾向があります。
たとえば――
- 触る感覚に敏感な子は、ザラザラ・チクチクした素材が苦手なことも。やわらかくて“安心できる肌ざわり”の素材を選んであげるとGOOD!
- 視覚に強く反応する子は、キラキラ・ゆらゆら・色の変化が大好きなことが多いです。スノードーム風のおもちゃやラメ入りジェル系はヒット率高め。
- 音に敏感だけど“好きな音”には集中できる子もいます。カラカラ・ポコポコなど、心地よい音が出るおもちゃを選んでみてください。
感覚の“敏感さ”だけでなく、“どんな感覚なら安心できるか”という視点で見るのがポイント。
③ 使う“シーン”を想定して選ぶ!
最後に見落としがちなのが、「どんな場面で使いたいか」という視点。
落ち着くおもちゃは、“いつでも万能”というわけではなく、その子の気持ちが揺れやすいタイミングに合わせて活躍するんです。
たとえば…
- 癇癪が起きそうなときの気持ちの切り替えアイテムとして → 握って落ち着く「にぎにぎボール」や、目で追って集中できる「スノードーム系」
- 登園前や外出前の不安軽減に → コンパクトで持ち運びしやすい「感覚ボトル」や「小さめスクイーズ」など
- 寝る前の“安心スイッチ”に → ゆっくり眺める「光のゆらぎ系」や「音が心地いいおもちゃ」
使うシーンを意識しておもちゃを選ぶと、「ただのおもちゃ」から「困ったときのお助けアイテム」になることもありますよ◎
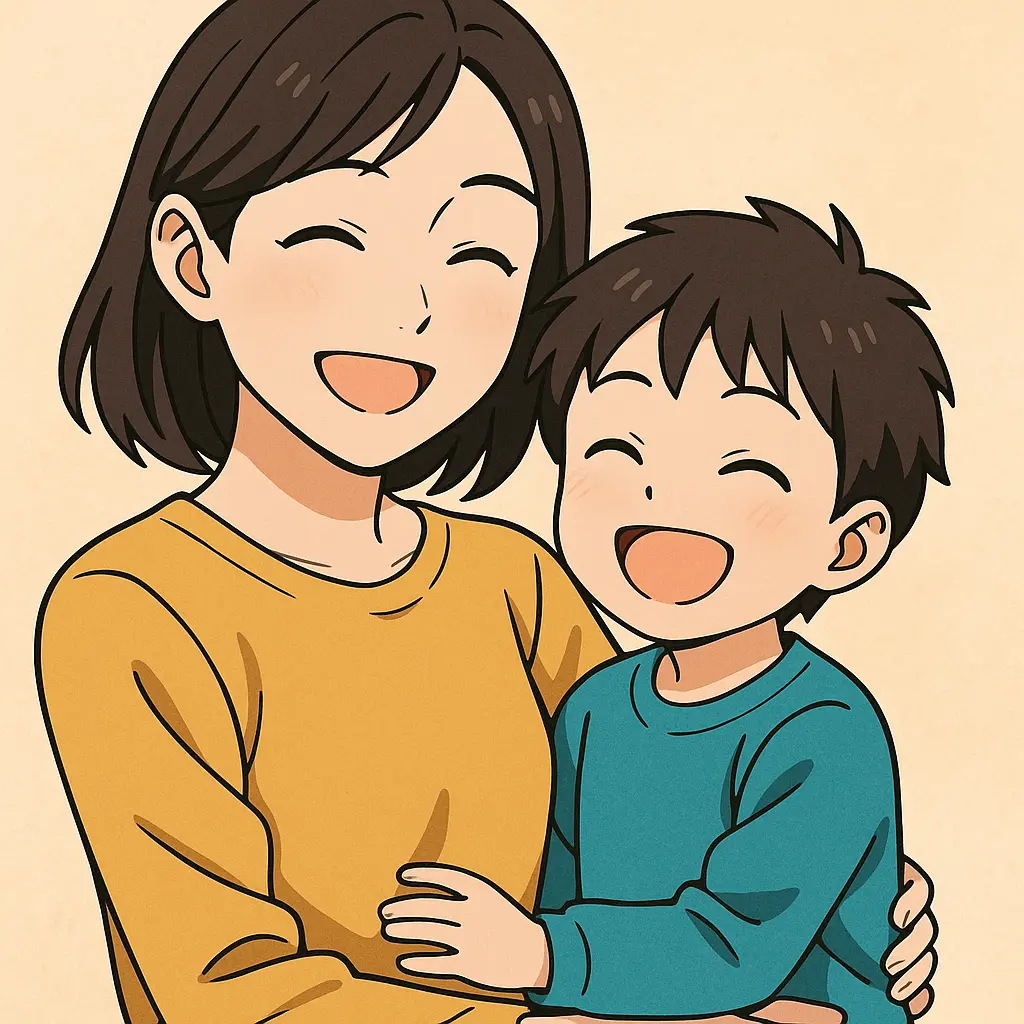
【家にあるものでOK】自閉症の子が落ち着く♪手作りおもちゃ10選(素材別)
「手作りおもちゃって興味あるけど、材料そろえるの大変そう…」
そんなふうに思った方もご安心を!実は、おうちにあるものや100均で買える素材だけでも、子どもが落ち着けるおもちゃは簡単に作れるんです。
ここでは、「ペットボトル」「ジップ袋」「段ボール」などの身近な素材別に、感覚遊びにつながるおすすめおもちゃを10個ご紹介します。
どれも簡単でコスパも◎なので、まずは気になるものから試してみてくださいね♪
1. 【ペットボトル】キラキラ・ゆらゆら感で視覚が落ち着く「スノードーム風ボトル」
ペットボトルに水とラメ、ビーズを入れるだけでOK。
振ると中のキラキラがゆっくり落ちていく様子が、見ていてとても心地いいんです。
視覚優位の子や、見て落ち着きたい子にぴったり。
液体の粘度を変えると流れ方も変わるので、何本かバリエーションを作るのもおすすめ!
2. 【ジップ袋】ぷにぷに感覚が楽しい「センサリーバッグ」
ジップ袋にヘアジェル+ビーズやスパンコールを入れて密封すれば完成。
ぷにぷに・もにゅもにゅした感触に夢中になる子、多いです!
触覚の刺激が苦手な子でも、手を汚さずに感触遊びができるのがポイント。
押したり、動かしたり、視覚と触覚の両方に働きかけてくれます。
3. 【段ボール】指先を使って集中力UP!「ボール転がし迷路」
段ボールのフタ部分にレーンを貼って、ビー玉や小さなボールを転がすだけ。
手首や指の操作が必要になるので、集中力と微細運動の練習にも◎。
音が大きくなりすぎないようにスポンジ素材を使うと、聴覚が敏感な子にも安心です。
4. 【ストロー】ひっぱって気持ちスッキリ!「ストローネックレス」
切ったストローを毛糸に通すだけ。通すときの指先トレーニングにもなりますし、
できあがったらガシャガシャ・カシャカシャ音も心地よく、触っても軽い感触が◎。
くり返しの動きが好きな子や、口でくわえることで安心する子にもおすすめ。
5. 【スポンジ】握って感覚を整える「にぎにぎスクイーズ」
使い古しのスポンジに輪ゴムを巻くだけで、なんちゃってスクイーズ完成!
ぎゅっと握る → 離す、をくり返すことで、感覚の自己調整にもつながります。
イライラ・モヤモヤした気持ちを解放する“お助けアイテム”として使う家庭も多数。
6. 【紙コップ】おしゃべりごっこに使える「マイク風おもちゃ」
紙コップにアルミホイルを丸めてのせると、簡単に“マイクごっこ”スタート♪
コミュニケーションが苦手な子も、道具があるとおしゃべりしやすくなることも。
自己表現やごっこ遊びの導入にちょうどよく、感情のアウトプットにも役立ちます。
7. 【フェルト】やさしい手ざわりで遊べる「型はめパズル」
フェルトをいろんな形に切って、箱の穴に合わせて入れていく遊び。
やわらかい手ざわり&くり返しの安心感で、意外と長時間集中して遊ぶ子も多いです。
音も出ないし、誤飲の心配も少ないので、静かに遊びたいときにもぴったり。
8. 【お米】さらさら&コロコロ感触に癒される「米びつセンサー遊び」
タッパーにお米を入れて、フィギュアや小さなおもちゃを中に隠して探す遊び。
“さらさら”という感覚と、“探す”という目的が楽しくて没頭しやすいんです。
ただし口に入れちゃうお子さんには注意。誤飲対策として布やジェルに置き換えるのもアリ。
9. 【輪ゴム+洗濯ばさみ】パチンと感覚がクセになる「引っぱり遊びセット」
輪ゴムを引っぱって洗濯ばさみでつまむ。
このシンプルな動作が、手の力加減や集中のコントロール練習に◎。
“手を使って気持ちを落ち着かせたい子”にぴったりのアクション系おもちゃです。
10. 【トイレットペーパーの芯】回して集中「くるくるビーズマシン」
芯の中にビーズやストローを入れて、くるくる回る仕掛けをつけると、
見た目にもおもしろくて、視覚・聴覚への適度な刺激がうれしいおもちゃに。
「見ること」で気持ちを安定させやすい子におすすめです。
【年齢別ガイド】1歳〜小学生まで!発達段階に合わせた手作りおもちゃアイデア
「手作りおもちゃってどれも良さそうだけど、うちの子の年齢には何が合ってるの?」
そう思ったことありませんか?
実は、おもちゃ選びでいちばん大事なのは“その子の発達段階に合っているかどうか”なんです。
年齢が同じでも、できること・興味のあることは子どもによってバラバラ。だからこそ、“月齢○歳”ではなく、「今どんな力が育っているか」を基準に考えてみましょう。
ここでは、1歳~小学生くらいまでの子を目安に、発達段階別にぴったりなおもちゃのアイデアをご紹介します!
1〜2歳:感覚を楽しむ“はじめての安心遊び”
この時期はまだ言葉も少なく、「目で見て楽しい」「手で触って気持ちいい」といった感覚刺激が中心の遊びがメイン。
しかも、急に大きな音や新しい感覚にびっくりすることも多いので、“刺激がやさしい”おもちゃが安心材料になります。
おすすめはコレ:
- キラキラボトル(視覚に優しく、見ているだけで落ち着く)
- にぎにぎスポンジ(握ることで手の感覚を安心させる)
- センサリーバッグ(触覚が敏感な子にも好評)
この頃のおもちゃは、“できる・できない”よりも“気持ちよさや安心感”を感じることが大切。大人が「こうやって使うんだよ」と遊び方を見せてあげるのも◎です。
3〜4歳:くり返し遊び&予想できる動きが大好き!
3歳ごろからは、少しずつ「こうしたらこうなる」が分かってきて、くり返しの遊びが楽しくなる時期。
また、「触る」「入れる」「出す」といった単純な動作のくり返しに集中する子も多いです。
この頃におすすめのおもちゃは…
- ポットン落とし(穴に入れる動きがクセになる!)
- ボール転がし迷路(動きの見通しが立ちやすく、集中力UP)
- ストローネックレス(手先を使ってひも通し、感覚統合にも◎)
この年代の子は、「何度もくり返す」「じっくり一人で遊ぶ」ことが増える反面、急な変化や失敗に不安を感じやすいことも。
おもちゃも“予測できる動き”や“成功体験が得られやすい構造”にしてあげると、安心して遊べます。
5〜6歳:指先の操作と“できた!”体験で自信を育てる
5歳前後になると、「もっと難しいことがやりたい!」という気持ちも芽生えてきます。
指先が器用になり、ちょっとした工程や順序を理解できるようになると、“作業っぽい遊び”や“チャレンジ要素のあるおもちゃ”が喜ばれます。
おすすめは…
- フェルトの型はめパズル(集中力と空間認識に効果的)
- ビー玉迷路(段ボール製)(自分で組み立てる工程が楽しい!)
- 洗濯ばさみ遊び(力加減を学ぶ感覚遊びにも)
この年齢の子には、「がんばったらできた!」という達成感が心の安定にもつながります。
反対に、「うまくできない」「難しすぎる」と感じるとイライラや不安が強くなることもあるので、レベル設定は“ちょっと頑張ればできる”くらいがベストです。
小学生〜:自分で工夫したり、気持ちを整理できるおもちゃへ
小学生になると、ある程度の自己理解が進み、「今ちょっと落ち着きたいな」「一人でいたいな」と感じることが増えます。
そんなときに、自分の気持ちを整える“セルフコントロール系のおもちゃ”があると、とても心強いサポーターになります。
この頃におすすめなのは:
- 手の中で転がせるスクイーズ(強く握ることでイライラ発散)
- 視覚で癒されるラメ入りボトル(気持ちの切り替えに)
- 自分で作る簡単DIYキット系おもちゃ(工夫・達成感・自信につながる)
また、この年代の子には、「他の子と違っていい」「自分の安心の方法があっていい」という気づきを育てることも大切。
おもちゃを“自己理解や感情調整のツール”として活用できると、学校生活や家庭でも過ごしやすさがアップします。
【感覚別】見て安心・触って落ち着く!タイプ別おすすめおもちゃリスト
「このおもちゃ、人気って聞いたけど、うちの子にはあんまり…」
そんな経験ありませんか?
それ、実は子どもの“感覚のタイプ”に合っていないのかもしれません。
自閉症スペクトラムの子どもたちは、五感の感じ方がとってもユニーク。
たとえば、「音に敏感」「光のチカチカが好き」「手触りで安心する」など、反応の出方がひとりひとり全然ちがうんです。
だからこそ、「その子がどんな感覚で落ち着けるのか」を見つけることが、おもちゃ選びのヒントになります。
ここでは、視覚・触覚・聴覚の3タイプ別におすすめの手作りおもちゃをご紹介!
「うちの子、こんなときに落ち着いてるかも…」と、思い当たることがあれば、ぜひ試してみてくださいね♪
見て安心するタイプ(視覚優位の子)
「キラキラ」「ゆらゆら」「ぐるぐる」など、視覚的な動きに夢中になる子っていますよね。
そんな子には、見ているだけで気持ちが落ち着くおもちゃがぴったり。
とくに“ゆっくり変化するもの”や“光や色の変化が美しいもの”は、高確率でハマる傾向があります。
\ おすすめアイテム /
- キラキラスノードーム風ボトル(水・オイル・ラメで癒しのゆらぎ)
- ラメ入りスライムバッグ(見た目も触感も◎)
- 万華鏡風のぞきアイテム(繰り返し模様で集中力アップ)
- 100均の光るLEDライトに装飾をつけたもの(夜の安心スイッチに)
📝 ワンポイント解説
視覚優位の子は、目からの情報で気持ちを整理する傾向があります。
そのため、「見るだけでOKなおもちゃ」も立派なリラックスツールになるんです。
触って落ち着くタイプ(触覚敏感・触覚鈍麻の子)
手や指に“触れる感覚”に敏感だったり、逆にたくさん触っていないと落ち着かない子には、触覚系のおもちゃが活躍します。
このタイプの子は、素材や感触へのこだわりが強いことが多いので、いろんな手ざわりを試して「これなら安心できる!」という感覚を見つけてあげるのがコツ。
\ おすすめアイテム /
- スクイーズ風にぎにぎスポンジ(ぎゅっと握る感覚でリセット)
- フェルトの型はめ遊び(やわらかい+指先も使える)
- 感触ボール(スポンジ・米袋・ジェルなど)
- 手作り“お米袋”センサリー(中に小物を隠して宝探し遊びにも)
📝 ワンポイント解説
触覚過敏な子には“ふわふわ”“ぷにぷに”などのやわらか素材が◎。
一方、触覚鈍麻タイプの子には“ザラザラ”“モコモコ”といったはっきりした感触が落ち着くこともあります。
音で落ち着くタイプ(聴覚過敏 or 聴覚に敏感な集中型の子)
音に敏感な子は、「急な大きな音」にはパニックになりやすいけど、好きな音やリズムにはピタッと集中できることがあります。
特に、一定のテンポ・繰り返す音・やさしいトーンの音は、安心につながりやすい傾向があります。
\ おすすめアイテム /
- カラカラマラカス(ペットボトル+ビーズ)
- ポコポコ系おもちゃ(たとえば緩衝材“プチプチ”)
- 水の流れる音がする仕掛けボトル
- 手で回すプロペラ風アイテム(風きり音+視覚刺激)
📝 ワンポイント解説
「音=刺激が強い」と思われがちですが、“自分で出せる音”や“予想できる音”は、安心材料になることも多いです。
「この音好き!」が見つかれば、その音を頼りに気持ちの切り替えができるようになることも。
【100均神アイテム】ダイソーで揃う!手作りおもちゃの材料とレシピ集
「手作りおもちゃって楽しそうだけど、材料ってどこで買えばいいの?」「意外と高くついたらどうしよう…」
そんなふうに感じたことがある方、大丈夫です。強い味方、それが“100均”です!
実際に、自閉症スペクトラムの子の保護者さんたちの間でも、「これは助かった!」「何度もリピ買いしてる!」という声が多いのが、ダイソーなどの100円ショップ。
今回は、そんな“100均の神アイテム”を活用した、感覚刺激にぴったりな手作りおもちゃの材料と簡単レシピをたっぷりご紹介します♪
なぜ100均グッズがおすすめなの?
まず前提として、子どもが安心して遊べるおもちゃを手軽に準備したいと思ったとき、100均は最強です。
その理由は…
- 素材が豊富(見て・触って・音も出るものが揃う)
- コストが安くて、失敗してもダメージ少なめ
- 「ちょっとだけ試したい」にもぴったり
- 代替えがきくので、同じ物を複数作れる
つまり、感覚過敏・感覚鈍麻など感覚の好みがはっきり分かれる子にも、「試行錯誤」がしやすいんです。
\ 100均で揃う!感覚別おすすめアイテム一覧 /
| 感覚タイプ | おすすめ素材(ダイソー・セリア) | おもちゃ例 |
|---|---|---|
| 視覚 | ラメ、カラーセロファン、スノードームキット | キラキラボトル、光のトンネル |
| 触覚 | スポンジ、ジェルビーズ、毛糸、フェルト | にぎにぎボール、センサリーバッグ |
| 聴覚 | ビーズ、小石、鈴、空容器(ふた付き) | マラカス風ボトル、ポコポコ缶 |
| 手先の動き | 洗濯ばさみ、ストロー、モール、輪ゴム | つまみ遊び、ひも通し |
| 創造遊び | カラーペーパー、段ボール、シール | ごっこ遊び小道具、型はめボックス |
かんたん♪100均アイテムを使った手作りレシピ3選
①【視覚】キラキラに夢中!「スノードーム風ボトル」
材料:
- ペットボトル(透明なもの)
- ラメ/ビーズ/グリッター
- 水と少量の洗濯のり or ベビーオイル
作り方:
- ペットボトルに水+洗濯のり(またはオイル)を7割ほど入れる
- ラメやビーズを入れる(色の組み合わせで表情が変わる!)
- ふたをしっかり接着剤で固定して完成!
ポイント:
水+のりの比率で流れ方が変わるので、「うちの子はゆっくり落ちるのが好き」など観察しながら微調整OK!
②【触覚】やわらかくて気持ちいい!「センサリーバッグ」
材料:
- ジップ袋(チャック付き)
- ヘアジェル(透明タイプ)
- スパンコール・ビーズ・小さなフィギュアなど
作り方:
- ジップ袋にヘアジェルを半分くらい入れる
- お好みの小物を入れて空気を抜きながら密封
- 必ずフチをテープで補強しておくと安全◎
ポイント:
触るだけでなく、視覚的にも楽しめるので、指先の不安定さや気持ちの切り替えが苦手な子にぴったり!
③【聴覚】カラカラ音で落ち着く「手作りマラカス」
材料:
- 空の小ボトル(ペットボトルや調味料容器)
- ビーズ、乾燥豆、小石など音の出るもの
- テープ(飾りと補強用)
作り方:
- ボトルに好きな素材を3分の1ほど入れる
- ふたをしっかり閉じてテープで固定
- デコレーションして完成!
ポイント:
音の種類で落ち着き方が変わることもあるので、素材を変えて数種類作っておくと◎。
プチアドバイス|100均活用の注意点&アレンジ術
注意点:
- 小さな部品は誤飲に注意!(乳児・口に入れやすい年齢の子には特に)
- ジップ袋やボトルはしっかりと密封・補強しておくことが大切
- 強い刺激(光・音)が苦手な子には素材選びを慎重に
アレンジ術:
- 同じ材料で「兄弟用・予備」も作っておくと◎
- シールやマスキングテープでデコると、子ども自身の“好き”が反映されて、愛着が湧きやすい
- 子どもと一緒に作ることで、遊ぶ前から楽しい体験に変わる!

「作って終わり」じゃない!癇癪・不安・切り替えに効く“使い方の工夫”5選
せっかく頑張って手作りしたおもちゃ、子どもが最初だけちょっと遊んで、あとは放置…。
そんな経験、ありませんか?
実はそれ、おもちゃの「使い方」にひと工夫が足りなかっただけかもしれません。
おもちゃって、ただ渡せば自動的に落ち着く“魔法の道具”じゃありません。
とくに自閉症スペクトラムの子の場合、「どう使うか」「いつ使うか」「どんなふうに関わるか」がめちゃくちゃ重要なんです。
ここでは、癇癪(かんしゃく)や不安、気持ちの切り替えが苦手な子に対して、手作りおもちゃを“効果的に使うための5つの工夫”をご紹介します!
① 癇癪が起こる“前兆サイン”に先回り!「予防アイテム」として使う
癇癪がドーンと爆発してからでは、どんなおもちゃも正直なかなか効きません。
だからこそ、子どもが不安定になりそうなタイミングを予測して、先におもちゃを使うのがカギ!
例えば――
- 登園前に気分がざわざわしているとき
- 人混みや苦手な音がある場所に行く前
- 昼寝明けで不機嫌になりがちなとき
そんな場面で、あらかじめ「安心できるお気に入りおもちゃ」を手渡しておくと、爆発を防ぎやすくなります。
いわば“気持ちの保険”のような役割。意外と効きます。
② “安心スペース”とセットで使うと落ち着きやすい
子どもが不安になったりパニックになりそうなとき、逃げ込める“安心できる場所”があると、それだけで違います。
たとえば、
- ふとんの端っこやカーテンの中
- クッションで囲った「安心基地」
- テントや段ボールハウス など
そんな空間に、お気に入りの感覚おもちゃ(例:スクイーズ・キラキラボトル)を置いておくと、子どもが“自分で落ち着ける場所と手段”を見つけやすくなります。
「おもちゃ+安心空間」の組み合わせで、効果は2倍以上に!
③ 「気持ちを切り替える合図」として使う
気持ちの切り替えが苦手な子にとって、次の行動に移るのって結構ハードル高いんですよね。
そんなとき、手作りおもちゃを“切り替えスイッチ”として使うのもおすすめ。
たとえば、
- 朝のルーティンの合間に「キラキラボトルタイム」を入れる
- お風呂前に「ぷにぷにスクイーズを3回握ったらおしまい!」
- お片付けの前に「おもちゃを1回転がしたら次のステップへ」
「これをしたら、次はこれね」という“見通し”と“切り替えの儀式”があることで、子どもは安心して移行しやすくなります。
④ 「自分で落ち着けた体験」を積み重ねる
「ママがなだめてくれる」ではなく、「自分で落ち着けた!」という経験は、自己調整力を育てるうえですごく大切。
たとえば、
- 癇癪を起こしかけたとき、自分でスクイーズを握ってクールダウンできた
- お気に入りのセンサリーボトルを眺めて深呼吸できた
- プチプチをつぶしているうちに怒りが落ち着いた
こうした小さな成功体験が、「次も自分でできるかも」という自己効力感(セルフエフィカシー)につながります。
「子どもが自分で使えるおもちゃ」に育てていく感覚、大事です◎
⑤ あえて“親子の時間”に取り入れて関係づくりにも活用
おもちゃ=ひとり遊び、と思われがちですが、実は親子のコミュニケーションに使うのも効果的なんです。
- おもちゃを一緒に作ってみる(「この色どう?」「名前つける?」など会話も生まれる)
- 子どもが使っているときにそっと横に座って見守るだけでも、「安心できる存在が近くにいる」という感覚に
- 「これで癇癪おさまったね!」と一緒に気づきを共有すると、言葉にならない感情の理解にもつながる
親子で使うことで、おもちゃはただの道具ではなく、“心の橋渡し”にもなってくれるんです。
この5つの視点を取り入れるだけで、「なんとなく遊ぶおもちゃ」から「子どもを支えるお守りアイテム」に進化しますよ。
【リアル体験談】うちの子にはこれが効いた!ママたちの手作り成功ストーリー
「ほんとに手作りおもちゃで落ち着くの?」
そう思っている方、きっと少なくないですよね。実際、ネットで「いいよ!」って紹介されているおもちゃでも、「うちの子には合わなかった…」ってこと、よくあります。
でも逆に、「まさかこれが!?」というようなシンプルなおもちゃがドンピシャでハマることも。
そこで今回は、実際に発達が気になる子を育てているママたちから集めた“手作りおもちゃ成功ストーリー”を紹介します!
年齢や特性が違っても「わかる~!」と感じられるリアルな声ばかりなので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
① 見るだけでスーッと落ち着く!「キラキラボトル」が癇癪予防に【3歳男の子】
最初はペットボトルにラメと水を入れただけの簡単なやつ。でも、これが予想外に大ヒット!
朝の登園前、癇癪が起きそうなときに「ボトル見てごらん」と渡すと、ジーッと見つめて呼吸が落ち着いてくるんです。
「癇癪が起こる前に落ち着ける」って初めての経験で、感動しました。
📌 ママのひとこと:
“おもちゃを渡すタイミングがポイント”。前兆が見えたらすぐ使うのがコツ!
② 気持ちの切り替えがスムーズに!「お米センサリー袋」で自己調整ができた【4歳女の子】
触るのが大好きな娘。イライラするときに、お米を入れたジップ袋で“宝探し遊び”をしてもらうようにしたら、怒ってたのが嘘みたいに落ち着くようになりました。
「見つけた〜!」って笑ってるうちに切り替えができていて、親の声かけがなくても落ち着けることが増えました。
📌 ママのひとこと:
“手を動かすことで気持ちが整理できる子”にはすごくおすすめです!
③ 外出先でも大活躍!「ストロー通しネックレス」でぐずり回避【2歳男の子】
ちょっと待つだけの時間が苦手で、すぐぐずぐず…。そんなとき、100均のストローを切って毛糸に通すだけのネックレスを作って持ち歩いていたら、外出中に集中して遊んでくれるようになりました。
手先も使うし、音も出ないし、何より「作業に夢中になれる」のがいいみたい!
📌 ママのひとこと:
コンパクトで持ち歩きやすい=“いつでも安心材料を持ち歩ける”という安心感にもつながってる気がします◎
④ 急なパニックにも対応できた!「スクイーズもどきスポンジ」で気持ちをリセット【5歳男の子】
癇癪というより、突然バァーン!ってスイッチが切れるタイプのパニックがあって…。でも、普段から「イライラしたらこれをにぎるよ」って習慣づけたことで、少しずつ自分で気持ちを落ち着かせられるようになってきました。
とくにスポンジを輪ゴムで縛った“にぎにぎおもちゃ”が手になじむみたいで、使い勝手バツグンです。
📌 ママのひとこと:
自分で“気持ちを切り替えるツール”として持たせることで、子どもにとっても安心のよりどころになってます。
⑤ 毎晩の寝かしつけに♪「光のボトル」で入眠がスムーズに【6歳女の子】
夜なかなか寝つけない子で、興奮してずっと動き回ってました。でも、100均の光るLEDライトにスパンコールを入れたボトルを作ってからは、「これを見ると眠たくなる~」と自分から布団に入ってくれるように。
ルーティンとして定着してくれて、今では親子にとって“おやすみスイッチ”です!
📌 ママのひとこと:
「おもちゃ=寝る前の合図」みたいな使い方で、習慣化するのが良かったみたい◎

まとめ|手作りおもちゃは“安心のカタチ”。楽しく作って笑顔を増やそう!
ここまで読んでくださったあなたはもうお気づきかもしれません。
そう、手作りおもちゃって、単なる“遊び道具”じゃないんです。
とくに発達が気になる子どもたちにとっては、「自分が落ち着ける感覚」「気持ちを切り替える方法」を知ることが、日常生活を心地よく過ごすための大切なステップになります。
そしてそれは、高価な市販品じゃなくても、おうちにある材料で、十分叶えられる。
むしろ、その子にぴったりの感覚や特性に合わせてカスタマイズできるのが、手作りのいちばんの魅力なんですよね。
子どもにとって“安心できる存在”は、物だけじゃない
もうひとつ忘れてはいけないのは、
手作りおもちゃには「ママやパパが作ってくれた」という安心感も詰まっているということ。
「これ、あなたのために作ったよ」
そのメッセージが伝わるだけで、子どもにとっては“心の避難所”のような存在になることもあるんです。
使いながら、子どもと一緒に“自分に合う安心”を見つけていこう
感覚の感じ方は、一人ひとり本当に違います。
「この子はどんな手ざわりが好き?」「どんな音なら安心できる?」と、一緒に試しながら探していく時間そのものが、親子の信頼関係を育てる時間にもなります。
うまくいかない日があっても大丈夫。
ときには、「作ったけど全然使ってくれなかった!」なんてこともあると思います(笑)。でも、その“試してみた経験”がきっと次につながるヒントになるはずです。
「落ち着く」は、“楽しい”と“安心”の間にある
手作りおもちゃのいいところは、子どもが安心しながら、同時にちょっと楽しくなれること。
「不安→落ち着く」だけじゃなく、「安心→やってみたい!」というプラスの気持ちにもつながりやすいんです。
感覚が整うと、心が整います。
心が整うと、日常のあちこちで少しずつ“できること”が増えていきます。
そのきっかけが、おうちで作った1つのおもちゃだったりするから面白い。
以上【簡単&安い 自閉症の子が笑顔に♪手作りで落ち着くおもちゃ20選|年齢・感覚・素材別】でした。











コメント