子育てが劇的にラクになる!発達支援で役立つ“魔法の声かけ”とは?
「子育てが大変だな…」と感じる瞬間、ありませんか?特に発達障がいのあるお子さんを育てていると、コミュニケーションがうまくいかないことでイライラしたり、疲れ果ててしまうことも少なくないですよね。
でも、ちょっと待ってください!実は、声かけひとつで子どもの行動がガラッと変わることがあるんです。これが、発達支援の現場でもよく言われる“魔法の声かけ”。たった一言で、子どもの気持ちが軽くなったり、行動がスムーズになったりすることがあるんです。
でも、「魔法の声かけ」ってどんな言葉?どんな場面で使えばいいの?そんな疑問を解消するために、今回は発達支援に役立つ声かけフレーズ集をまとめました。
発達障がい児とのコミュニケーションが難しい理由
発達障がいのある子どもたちは、コミュニケーションが苦手なことが多いです。これにはいくつかの理由があります:
- 感覚過敏や鈍麻がある
- 例えば、音に敏感な子どもは、大きな声で話されるとそれだけでパニックになってしまうことも。逆に、聴覚が鈍感な子どもには小さな声だと届かないこともあります。
- 言葉の理解に時間がかかる
- 言葉の意味を一度で理解できなかったり、指示が長すぎると混乱してしまうことがあります。
- 自己表現が苦手
- 「嫌だ」「助けて」などの気持ちを上手に言葉で表現できない場合、泣いたり癇癪を起こしてしまうことも。
こうした特徴を理解した上で、子どもの特性に合った声かけをすることが大切です。
ただ「早くして!」と言うだけでは伝わらない場合もあるので、その子が理解しやすい言葉やトーン、タイミングを見極めることがポイントです。
「声かけひとつ」で子どもの行動が変わる!
例えば、朝の支度がなかなか進まないとき。
親:「早くして!」
子:「(無視して遊んでいる)」
この状況、よくありますよね。でも、ここで「早くして!」の代わりに、こんな声かけをしてみてください。
親:「次は靴下を履こうね!」
子:「うん!」
どうでしょう?一つの指示を具体的に伝えるだけで、子どもが動きやすくなるんです。これが“声かけひとつで行動が変わる”ということです。
また、泣いている子どもに対しても、「泣かないで!」ではなく、
「どうしたの?教えてくれる?」と声をかけることで、気持ちを言葉にするきっかけを作れます。
これって実は、子どもの自己肯定感を高める声かけにもつながるんです。
「泣かないで」は否定形ですが、「教えてくれる?」は子どもの存在を肯定する表現ですよね。
迷ったらコレ!発達支援に効く声かけフレーズ集
どんなシチュエーションでも対応できる万能フレーズを覚えておくと、いざというときに役立ちます。
例えば:
- 朝の支度:「まず〇〇からやってみよう!」
- 癇癪モード:「落ち着いてから話そうね」
- 片付け:「全部じゃなくて、まずおもちゃだけ片付けようか!」
これらのフレーズは、具体的でシンプルだからこそ子どもに伝わりやすいんです。
さらに、「できたら教えてね」「次は何をする?」など、子どもの自主性を引き出す声かけも効果的です。
でも、これらのフレーズを覚えるだけではなく、「いつ」「どんなトーンで」「どのタイミングで」声をかけるかがポイントです。
例えば、焦っているときにはゆっくりとしたトーンで、落ち着いているときには元気なトーンで声をかけることで、より効果的なコミュニケーションが取れるようになります。
\ここまでのまとめ/
- 発達障がい児とのコミュニケーションが難しいのは、感覚特性や言葉の理解の違いがあるから。
- 声かけひとつで子どもの行動が変わる!具体的でシンプルなフレーズが効果的。
- 「早くして!」ではなく、「まず〇〇してね」「できたら教えてね」のように段階的な指示出しがポイント。
- 子どもの自己肯定感を高める声かけフレーズは、「できたね!」「教えてくれてありがとう」などの肯定的な言葉。
- トーンやタイミングも大事!焦っているときほど、ゆっくり穏やかに声をかけることで安心感が伝わる。
発達支援で劇的効果!“声かけ”の基本3ポイント
「子どもへの声かけって、どんな言葉が効果的なんだろう?」って悩むこと、ありませんか?
特に発達障がいのある子どもとのコミュニケーションでは、ちょっとした声かけの工夫が劇的な効果を生むことがあるんです。
ここでは、そんな“魔法の声かけ”を 3つの基本ポイント に分けて紹介していきます!
これを覚えれば、日常のイライラもグッと減らせるかも!?
迷わない!声かけの目的別フレーズ集
声かけを考えるとき、まず大事なのが 「何のために声をかけるのか?」 を意識すること。
ただ「早くして!」と言うだけでは、子どもには伝わりにくいことが多いんです。
だからこそ、声かけの目的をしっかり見極めて、それに合ったフレーズを選ぶのがコツ。
例えば、こんな目的別フレーズを試してみましょう!
1. 指示を出したいとき
- 「まず〇〇をしてみよう!」
- 例:「まず靴下を履こう!」
- 「これが終わったら次は〇〇だよ!」
- 例:「歯磨きが終わったら次は顔を洗おう!」
ポイント:
- 行動を分けて具体的に伝えることがカギ!
- 「〇〇して!」よりも「まず〇〇しよう!」の方が優しい印象に。
2. 共感して安心させたいとき
- 「そうなんだね、困ったね」
- 例:「ブロックが壊れちゃったんだね、悔しかったね」
- 「教えてくれてありがとう!」
- 例:「泣いてる理由を教えてくれてありがとうね」
ポイント:
- 子どもの気持ちをまず受け止めることで、安心感が生まれる。
- 親の共感が伝わると、子どもは「自分の気持ちが理解された!」と感じられる。
3. 自己肯定感を育てたいとき
- 「できたね!すごいじゃん!」
- 例:「お片付けできたね!上手にできたね!」
- 「成長してるね!」
- 例:「昨日よりもスムーズに準備できたね!がんばったね!」
ポイント:
- 結果だけでなく、過程を褒めることで自己肯定感がアップ。
- 何気ない行動でも「できたね!」と声をかけるだけで、子どもは達成感を感じられる。
NGワードはコレ!肯定的な声かけのコツ
声かけで意識したいのが、「否定形を肯定形に変えること」。
例えば、「早くしなさい!」や「なんでできないの?」と言ってしまうと、子どもはプレッシャーを感じてしまいがち。
でも、これを少し言い換えるだけで、子どもの反応がガラッと変わることがあるんです。
否定形 → 肯定形の言い換え例
- 「走らないで!」 → 「ゆっくり歩こうね!」
- 「泣かないで!」 → 「落ち着いてから話そうね!」
- 「片付けないとダメだよ!」 → 「おもちゃから片付けてみよう!」
なぜ肯定形がいいの?
- 否定形は 「○○しないで」 と指示しても、子どもには「○○する」という行動だけが残ってしまいがち。
- 例えば、「走らないで!」と言われても、頭の中には「走る」という行動が浮かぶだけで、「歩く」という代替行動が提示されていない。
- そこで、「ゆっくり歩こうね!」と 具体的な行動を指示することで、子どもは「歩く」という行動に意識を向けやすくなる。
シンプルが最強!子どもが理解しやすい言葉選び
発達障がいのある子どもたちにとって、長い説明や抽象的な言葉は理解が難しいことがよくあります。
だからこそ、シンプルでわかりやすい言葉を使うことが大切。
シンプルフレーズ例
- 「手を洗おうね!」(洗面所に向かいながら)
- 「これが終わったら次はお片付けね!」
- 「おもちゃはここに置こう!」
さらに効果を高めるには?
- 視覚支援を取り入れる:
- 文字や絵で示すと、理解しやすさがアップ。
- 例:「お片付けの手順カード」や「時間割カード」など。
- ジェスチャーを加える:
- 例えば、「座ってね」と言いながら座る動作を見せると、視覚的なヒントが増えて伝わりやすくなる。
\ここまでのまとめ/
- 声かけの目的を明確にして、指示・共感・自己肯定感を引き出すフレーズを意識しよう。
- 否定形の言葉は、肯定形に変換することで伝わりやすさがアップ!
- 例:「走らないで!」→「ゆっくり歩こうね!」
- シンプルでわかりやすい言葉選びがカギ。視覚支援やジェスチャーを組み合わせるとさらに効果的!
- 子どもの成長を感じたときは、しっかり褒めることも忘れずに!「できたね!」「教えてくれてありがとう!」などの肯定的な声かけが自己肯定感を育てる。

子育てがラクになる!シチュエーション別声かけフレーズ
「なんでうちの子、言うこと聞いてくれないの?」
「朝の支度が遅くてイライラ!」
「片付けなんて全然やらない!」
こんな風に思ったこと、ありませんか?
でも、実は 声かけの工夫ひとつで子どもの行動が変わる ことがあるんです。
ここでは、日常の具体的な場面別に 効果的な声かけフレーズ をたっぷり紹介していきます。
シチュエーションごとに 簡単に使える言葉 を覚えて、子育てをちょっとラクにしてみましょう!
朝の支度が進まない!そんなときの声かけ5選
朝は 子どもにとっても親にとっても一日の始まりの時間。
でも、「早くして!」がつい口癖になってしまうこと、ありませんか?
これを言われると、子どもは焦って逆に動けなくなってしまうことも。
そんなときは、こんな声かけを試してみてください!
- 「まず〇〇からやってみよう!」
- 朝の支度はたくさんの工程があるので、ひとつずつ具体的に指示を出すことがポイント。
- 例:「まず靴下を履いてみよう!」「靴下が履けたら次はシャツね!」
- なぜこれが効果的?
- 子どもは「全部やって!」と言われるとどれから手をつけていいか分からなくなることが多いです。
- スモールステップで一つずつクリアしていくことで、達成感も味わえます。
- 「できたら教えてね!」
- これも 達成感を感じさせる魔法の言葉。
- 例:「ズボン履けたら教えてね!」
- なぜこれが効果的?
- 子どもは「できた!」と親に伝えることで 承認される喜びを感じられます。
- 「次は〇〇だね!」
- 朝の支度を 順番に示してあげることで、次にやることが明確に。
- 例:「歯磨きが終わったら次は顔を洗おう!」
- なぜこれが効果的?
- 予測可能性があると子どもは安心して行動しやすくなります。
イヤイヤ期・癇癪モード突入!イライラしない声かけ法
「イヤイヤ!」「やりたくない!」と 拒否の連発…。
特にイヤイヤ期や癇癪が始まると、親もどうしていいか分からなくなりますよね。
でも、ここで無理に「やりなさい!」と押し付けるのは逆効果。
そこで、こんな声かけをしてみましょう。
- 「気持ちを教えてくれてありがとう」
- まずは子どもの感情を受け止めることが大切。
- 例:「怒ってるんだね。教えてくれてありがとう」
- なぜこれが効果的?
- 子どもは 自分の感情を受け止めてもらえると安心感を感じるものです。
- その結果、冷静になりやすくなります。
- 「落ち着いたら話そうね」
- 怒りの感情が収まらないときは クールダウンの時間を作る。
- 例:「少し落ち着いたらお話ししようね」
- なぜこれが効果的?
- 子ども自身が 感情のクールダウン方法を覚えるきっかけにもなります。
遊びたくない?やる気スイッチをONにする声かけ
やるべきことがあるのに、遊びたがる子ども。
そんなとき、親としては「早くやりなさい!」と言いたくなりますが、それではやる気は湧きません。
ここでおすすめなのが 選択肢を与える声かけです。
- 「どれからやってみたい?」
- 子どもに 選択肢を与えることで、自主性を引き出す。
- 例:「宿題とお片付け、どっちからやる?」
- なぜこれが効果的?
- 子どもが「自分で選んだ」という感覚を持つことで やる気が出やすくなります。
- 「一緒にやってみようか!」
- 親が一緒に取り組むことで、 安心感を持たせる。
- 例:「宿題一緒にやろうか?」
- なぜこれが効果的?
- 子どもは 一人だと不安でも、親と一緒なら安心して取り組めることが多いです。
友達トラブル発生!ケンカを収める声かけフレーズ
子ども同士のケンカは避けられないもの。
でも、ここで感情的になって「なんでそんなことしたの!」と言っても、子どもは反発するばかり。
こんなときこそ、冷静に問いかける声かけが効果的です。
- 「どうしてそう思ったの?」
- 子どもの気持ちを引き出す質問で 状況を整理。
- なぜこれが効果的?
- 子ども自身が 自分の感情を言葉にする練習になります。
- 「次はどうしようか?」
- 解決策を一緒に考えることで、 自分で行動を選択する力を育てる。
片付けできない!そんなときの“段階的声かけ”術
片付けが苦手な子どもには いきなり全部片付けろ!は逆効果。
まずは小さなステップを設定して成功体験を作ることが大事です。
- 「まずおもちゃから片付けよう!」
- 「まず」「次に」「最後に」と 順番を示すことで成功しやすく。
- 「片付けたら次は何しよう?」
- ごほうび感を持たせることで、 片付けが楽しいこととしてインプットされる。
\ここまでのまとめ/
- 朝の支度はスモールステップで指示出し!「まず〇〇からやってみよう!」でスタートダッシュ。
- イヤイヤ期・癇癪時はまず共感。「気持ちを教えてくれてありがとう」で心を開かせる。
- やる気スイッチをONにするには選択肢を与える!「どっちからやる?」で自主性を促す。
- 友達トラブルには冷静な問いかけが効果的。「どうしてそう思ったの?」で自己表現をサポート。
- 片付けは段階的に。「まずおもちゃから」で小さな成功体験を積み重ねる!

特性別!発達支援に効く声かけフレーズ集
発達障がいと一口に言っても、その特性は子どもによって様々です。
例えば、同じ「片付けてね」という声かけでも、ASDの子どもとADHDの子どもでは 受け取り方が全く異なる ことも珍しくありません。
だからこそ、特性に合わせた声かけの工夫が必要です。
ここでは、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障がい) の3つの特性別に、具体的な声かけフレーズを紹介していきます!
それぞれの特徴に寄り添った言葉選びで、子どもの安心感や自己肯定感を引き出しましょう。
ASD(自閉スペクトラム症)の子ども向け
ASDの子どもたちは、予定外の出来事や急な変化が苦手 という特徴があります。
また、感情表現が苦手なため、「何をしていいのか」「何を感じているのか」が うまく伝えられないことも多い です。
そんなASDの子どもには、以下のような声かけが効果的です。
- 「これを終わったら次は○○だよ!」
- 例:「ブロック遊びが終わったら、次はお片付けだよ!」
- なぜこれが効果的?
- 予測可能性を持たせることで安心感を与える。
- ASDの子どもは「次に何をすればいいのか」が分からないと不安になりやすいです。
- そこで「次の行動」を具体的に伝えることで、頭の中で準備ができ、行動に移りやすくなります。
- 「困ったことある?」
- 例:「ブロックが壊れちゃって困ってる?」
- なぜこれが効果的?
- ASDの子どもは、自分の感情を 言葉にするのが苦手 な場合が多いです。
- 「困ってる?」と聞かれることで、「あ、自分は困ってるんだ」と 感情のラベル付けができる ようになります。
- さらに、この声かけを続けることで、「困ったら言ってもいいんだ」という 安心感 も育まれます。
ADHD(注意欠如・多動症)の子ども向け
ADHDの子どもたちは、注意力が散漫になりやすく、衝動的な行動をとりがち。
「ちょっと待って」と言われても、すぐに行動を抑えるのが難しいことがよくあります。
そんなADHDの子どもには、焦らせない、具体的な行動指示がポイントです。
- 「ゆっくりで大丈夫だよ」
- 例:「焦らなくていいから、ゆっくりやろうね!」
- なぜこれが効果的?
- ADHDの子どもは 周囲の刺激に敏感 なため、「早く!」と言われるとパニックになりやすいです。
- そこで、「ゆっくりでいいよ」と言うことで、 落ち着いて行動に集中できる 環境を作り出します。
- 「これを3回やって休憩ね!」
- 例:「この計算問題を3回やったら休憩しよう!」
- なぜこれが効果的?
- ADHDの子どもは、時間感覚が曖昧 な場合が多いです。
- 「いつまでやればいいの?」と分からなくなり、集中力が切れやすいのが特徴。
- そこで「3回」という 具体的な回数 を提示することで、目標が明確になり、集中力をキープしやすくなります。
LD(学習障がい)の子ども向け
LDの子どもたちは、読み書きや計算が苦手 な場合が多いです。
しかし、学習面の課題が強調されると、「自分はできない子なんだ…」と 自己肯定感が下がってしまう ことも。
そこで、小さな成功体験を積み重ねて自信をつける 声かけが有効です。
- 「一緒にやってみよう!」
- 例:「このパズル、一緒にやってみようか?」
- なぜこれが効果的?
- 「一人でやりなさい!」と言われると、 やる前から諦めてしまう 子どもも多いです。
- しかし、「一緒にやろう!」と言われることで、「失敗してもいいんだ」「困ったら助けてもらえるんだ」という 安心感が得られます。
- 「できることが増えてるね!」
- 例:「昨日よりもたくさん読めたね!すごい!」
- なぜこれが効果的?
- LDの子どもは、「できないこと」に注目されがちです。
- しかし、「できること」に目を向けることで、 自己肯定感を育むことができる。
- さらに、「昨日よりも」という 成長の視点を加える ことで、前向きな気持ちが生まれやすくなります。
\ここまでのまとめ/
- ASD(自閉スペクトラム症):予測可能性を持たせる声かけで安心感を与える。
- 例:「これが終わったら次は〇〇だよ!」
- 感情表現が苦手な場合は「困ったことある?」と尋ねて感情の言語化をサポート。
- ADHD(注意欠如・多動症):焦りやすいので、具体的な指示と休憩の区切りがポイント。
- 例:「ゆっくりで大丈夫だよ」
- 「これを3回やって休憩ね!」で集中力をキープ。
- LD(学習障がい):小さな成功体験を積み重ねて自己肯定感を育てる。
- 例:「一緒にやってみよう!」
- 「できることが増えてるね!」で成長を実感させる。
親子関係が変わる!声かけ一つで子育てがラクになる理由
子育てをしていると、「なんでうちの子は言うことを聞いてくれないの?」と悩むことってありますよね。
ついイライラして、「早くして!」や「いい加減にしなさい!」と言ってしまうこともあると思います。
でも実は、そんなときこそ声かけの内容や言い方をちょっと変えるだけで、子どもとの関係がぐっと良くなることがあるんです。
ここでは、声かけがもたらす心理的な効果や、つい言ってしまいがちなNGフレーズの言い換えテクニックを紹介します。
「子どもが言うことを聞かない=親の失敗」ではなく、コミュニケーションのすれ違いがあるだけ。
そのズレを調整する方法が「声かけ」なのです。
ポジティブな声かけが子どもを変える!そのメカニズム
まず大前提として、子どもは親の声かけにとても敏感です。
なぜなら、子どもにとって親は「安心の拠り所」であり、「自分を受け止めてくれる存在」だから。
たとえば、朝バタバタしているときに「なんでまだパジャマなの!?早く着替えて!」と怒ってしまうと、
子どもは「怒られた」「自分はダメなんだ」と受け取ってしまいます。
でも、同じ状況でこんな風に言われたらどうでしょう?
「もうすぐ出かける時間だね。着替えられるかな?手伝おうか?」
どうですか?子ども目線で見ると、怒られたというよりも“気にかけてもらえた”感覚になりますよね。
これが、ポジティブな声かけの効果です。
声かけが子どもを安心させる心理的効果とは?
心理学的にも、「共感的な声かけ」は子どもの安心感を育て、行動を安定させると言われています。
「怒られたから動く」のではなく、「分かってもらえたからがんばろう」という気持ちに変わるんです。
しかも、ポジティブな声かけは自己肯定感の土台作りにもつながります。
「できたね」「がんばってるね」と言われた経験が増えると、子どもは「自分は大丈夫」と思えるようになっていくのです。
親がリラックスすれば、子どもも落ち着く
これは本当に大事なポイントなのですが…
親のイライラは、ほぼ確実に子どもに伝わります。
「イライラした口調」「急かすような声かけ」は、子どもの不安をあおってしまいます。
逆に、親が落ち着いた声でゆっくり話すと、子どももスッと落ち着いたりするんです。
これはいわゆる“感情のミラーリング”。
親が感情をコントロールできていると、子どもも自然とその空気に引き寄せられるんですね。
だから、まずは深呼吸。
声かけをする前に、一瞬でもいいので「落ち着いた自分」を取り戻してみましょう。
それだけで、声のトーンや言葉選びが変わって、子どもとの関係も少しずつ変わってきますよ。
つい言ってしまうNGフレーズをチェック!
「つい言っちゃうんだよな…」という言葉、ありませんか?
でもそれ、実は子どもの行動を止めるどころか逆効果になっているかも。
ここでは、よくあるNGフレーズと、その言い換え例を紹介します。
| NGフレーズ | 言い換えフレーズ | 効果・理由 |
|---|---|---|
| 「早くして!」 | 「あと〇分で出かけるよ」 | 時間の見通しが立ち、安心できる |
| 「ダメ!」 | 「どうすればよかったかな?」 | 考えるきっかけを与える |
| 「何回言ったら分かるの?」 | 「次はどうしようか一緒に考えよう」 | 解決に向かう会話に変わる |
こうした言い換えは、子どもを責める言葉ではなく、未来に目を向ける言葉になっています。
子ども自身が「じゃあどうしようかな」と考える力も育ちますし、親子の関係性もギクシャクしにくくなります。
とはいえ、完璧を目指さなくて大丈夫。
大切なのは、「伝え方を意識してみよう」と思えることそのものです。
まずはできるところから、声かけをポジティブにしていきましょう!
\ここまでのまとめ/
- ポジティブな声かけは、子どもの安心感や自己肯定感を育てる。
- 「どうして○○なの!?」より、「どうすればよかったかな?」が効果的。
- 親の落ち着いた声かけが、子どもの落ち着きにもつながる(感情のミラーリング効果)。
- NGフレーズは肯定形や見通しを与える表現に変えることで、親子の対話がスムーズになる。
- 大事なのは、完璧を目指すことよりも“意識して声をかけること”!

発達支援に効く声かけフレーズ集で子育てのストレスを減らそう!
ここまで読んで、「声かけってやっぱり大事なんだな」と感じていただけたのではないでしょうか?
そうなんです、子どもへの声かけは、子育ての“道しるべ”のようなもの。
どんなタイミングで、どんな言葉を使うかによって、子どもの反応や行動は大きく変わってきます。
特に、発達障がいのあるお子さんとのコミュニケーションでは、一言の声かけが子どもの安心感ややる気に直結することが本当に多いです。
だからこそ、「ただ言う」ではなく、「どう言うか」を意識するだけで、親子関係がぐっとラクになるんです。
声かけ次第で親子関係が激変する!
「うちの子、全然言うことを聞かない!」と思っていたのに、
声かけを「〇〇しないで!」から「〇〇してみようね!」に変えただけで、急にスムーズに動き出す。
こんな変化、実はよくあります。
なぜなら、声かけは子どもとの“架け橋”だから。
その橋が壊れていると、いくら大声を出しても気持ちは伝わりません。
でも、言葉のかけ方を少し変えるだけで、その橋は修復され、やり取りがスムーズになるんです。
シチュエーション別フレーズを試してみよう
どんなにやさしい気持ちでいても、「今、何て言えばいいの?」と迷うこと、ありますよね。
そんなときに役立つのが、今回紹介したシチュエーション別の声かけフレーズ集です。
朝の支度、癇癪、お片付け、遊びの促し、友達とのトラブル対応……
どれも子育て中によくある場面ばかり。
声かけの具体例を覚えておけば、「もうどうしていいか分からない!」という場面でも、落ち着いて対応できる自信がつきます。
そして何より、子どもが少しずつ「わかってもらえてる」と感じるようになっていくことが一番の成果です。
肯定的な声かけで子どもの自己肯定感を育てよう!
声かけの一番の目的って、「行動をコントロールすること」ではなく、
子どもが自信を持って前に進めるようにすることなんですよね。
だからこそ、「できたね!」「ありがとう」「昨日よりスムーズだったね」など、
子どもの成長や努力に目を向ける言葉を、どんどんかけていくことがとっても大切です。
否定よりも肯定。命令よりも提案。
そのちょっとした積み重ねが、子どもの“自己肯定感”という土台を育てていきます。
\ここまでのまとめ/
- 声かけひとつで、子どもの行動や気持ちは大きく変わる!
- 親子関係をラクにするカギは「どう伝えるか」にある。
- シチュエーション別フレーズを使うと、対応がスムーズになる。
- 否定的な言葉より、肯定的・共感的な言葉が子どもの自己肯定感を育てる。
- 完璧じゃなくてOK!できるところから、声かけを意識してみよう!
【Q&A】子育てがラクになる!声かけフレーズに関するよくある質問
声かけが大事だと分かっていても、「思うように伝わらない…」「言い方が分からない…」なんてこと、ありますよね。
ここでは、よくある声かけに関する悩みに答えていきます!
実際の育児現場で役立つ対処法を具体的に解説していくので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
Q1:「声かけしても子どもが聞いてくれない!」そんなときの対処法
「〇〇しようね!」「今すぐやって!」と声をかけても、子どもが全然反応してくれない…。
こんな場面、日常茶飯事ですよね。
でも、ここでちょっと立ち止まって考えてみましょう。
子どもが聞いてくれない理由は、一つではありません。
考えられる原因:
- タイミングが悪い(夢中になって遊んでいる最中)
- 声かけが抽象的で分かりにくい(「早くしなさい」など)
- 親の声が“ノイズ化”している(普段から命令口調が多い)
解決策:
- 視線を合わせてから声をかける
- 子どもが何かに夢中になっているときは、まずその行動に目を向けることが大事。
- 例えば、積み木で遊んでいるなら、「お、すごい!高く積んでるね!」と声をかけてから、「次はお片付けしてみようか?」と伝える。
- 共感→指示の順番で伝えると、受け入れやすくなります。
- 具体的に伝える
- 「早くして!」ではなく、「〇〇をしてから、次は〇〇だよ!」と スモールステップで伝える。
- 例:「靴下を履いたら教えてね!」「靴を履いたら次はお出かけだよ!」
- 選択肢を与える
- 子どもが「やりたくない!」と言うときは、選択肢を提示して自分で選ばせる。
- 例:「お片付けする?それとも歯磨きから始める?」
- 自分で選ぶことで 自主性が育ち、やる気が出やすくなるんです。
Q2:「兄弟間で声かけが不公平に感じる…」調整のコツとは?
兄弟がいると、どうしても「お兄ちゃんばっかり褒めてる」とか「妹だけ優しくしてる」と感じること、ありますよね。
でもこれ、実は 兄弟間の年齢差や発達特性に合わせた対応をしているだけだったりします。
✅ 問題の本質:
- 年齢差や発達特性の違いがあると、同じ言葉でも伝わり方が異なる。
- 子どもの視点では、不公平感が強調されやすい。
解決策:
- 「〇〇だからこうしたんだよ」と説明する
- 例:「お兄ちゃんには『一緒にやってみよう!』って言ったのは、お片付けがまだ苦手だからだよ。〇〇ちゃんは一人でできるから『ありがとう!』って言ったんだよ。」
- なぜこれが効果的?
- 子どもは「なんで?」が大好き。説明してもらうことで 納得感が増し、不公平感が減る。
- 個別対応の意図を伝える
- 「お兄ちゃんには今、〇〇を頑張ってもらってるんだよ。〇〇ちゃんには〇〇をお願いしようかな!」
- 「一人一人の得意・不得意を見てるよ」というメッセージを伝えることで、自己肯定感も育まれる。
- みんな一緒の時間を設ける
- 「みんなでお片付けタイム!」など、公平感を持たせる時間を作ることで、「自分だけ違う…」という感覚が和らぐ。
Q3:「感情的になってしまう…」親自身のセルフケア方法
子どもがなかなか言うことを聞いてくれないとき、ついイライラしてしまうのは 誰でも同じ。
「声かけが大事」と頭では分かっていても、親だって感情のコントロールが難しいときがありますよね。
イライラの原因を振り返ろう
- 自分の疲れやストレスが溜まっている
- 子どもへの期待値が高すぎる
- 完璧な親であろうと頑張りすぎている
✅ セルフケアの具体策:
- 深呼吸 or カウント法
- 怒りがこみ上げてきたときは、「5秒間深呼吸」 or 「5つ数える」。
- その間に「何を伝えたいのか」「どんな声かけが良いのか」を 冷静に考える時間を作る。
- 感情を言葉にしてみる
- 子どもに対しても、「ママ、ちょっとイライラしてるかも」と伝えてしまうのもアリ。
- 「今、ママは焦ってるから深呼吸して落ち着くね」と言うと、子どもにも 感情のコントロールの仕方を見せることができます。
- 完璧じゃなくてOK!
- 今日はダメでも、明日またやり直せばいい。
- 「さっきはつい怒っちゃったね。ごめんね。次は〇〇って言ってみるね!」と リセットすることで、親も気持ちが楽になります。
\ここまでのまとめ/
- 声かけしても通じないときは、「視線を合わせる」「具体的に伝える」「選択肢を与える」の3つがポイント!
- 兄弟間の声かけの不公平感を減らすには、「理由を説明する」「個別対応の意図を伝える」ことが有効。
- 親がイライラしてしまったときは、「5秒間深呼吸」「感情を言葉にする」「完璧を求めない」ことでリセットしやすくなる!
声かけを工夫することで、親子の関係性がぐっとラクになります。
でも、一度やってすぐに成果が出るものではありません。
まずはできるところから、「ちょっと言い方を変えてみよう」と意識してみることが大事。

さいごに~「焦らなくて大丈夫。あなたの声かけが子どもの心を育てる」
発達に特性のあるお子さんとのコミュニケーションで、どう声をかけたらいいのか迷うことってありますよね。
この記事では、そんな日々の「困った!」を少しでもラクにできるように、朝の支度や癇癪対応、遊びの促し方まで、すぐに使える声かけフレーズをシチュエーション別にまとめました。
声かけで一番大切なのは、「完璧な言葉」を見つけることではなく、「あなたの気持ちが伝わる言葉を見つけること」です。
うまく言えなくても、「伝えたい」「サポートしたい」という気持ちがあれば、それだけで十分。
今日紹介したフレーズを一つでも取り入れてみてくださいね。
たとえ昨日うまくいかなかったとしても、今日の一言で子どもの心がぐっと動くこともあります。
だからこそ、焦らず、少しずつ。あなたのペースで取り組んでいけば大丈夫です!
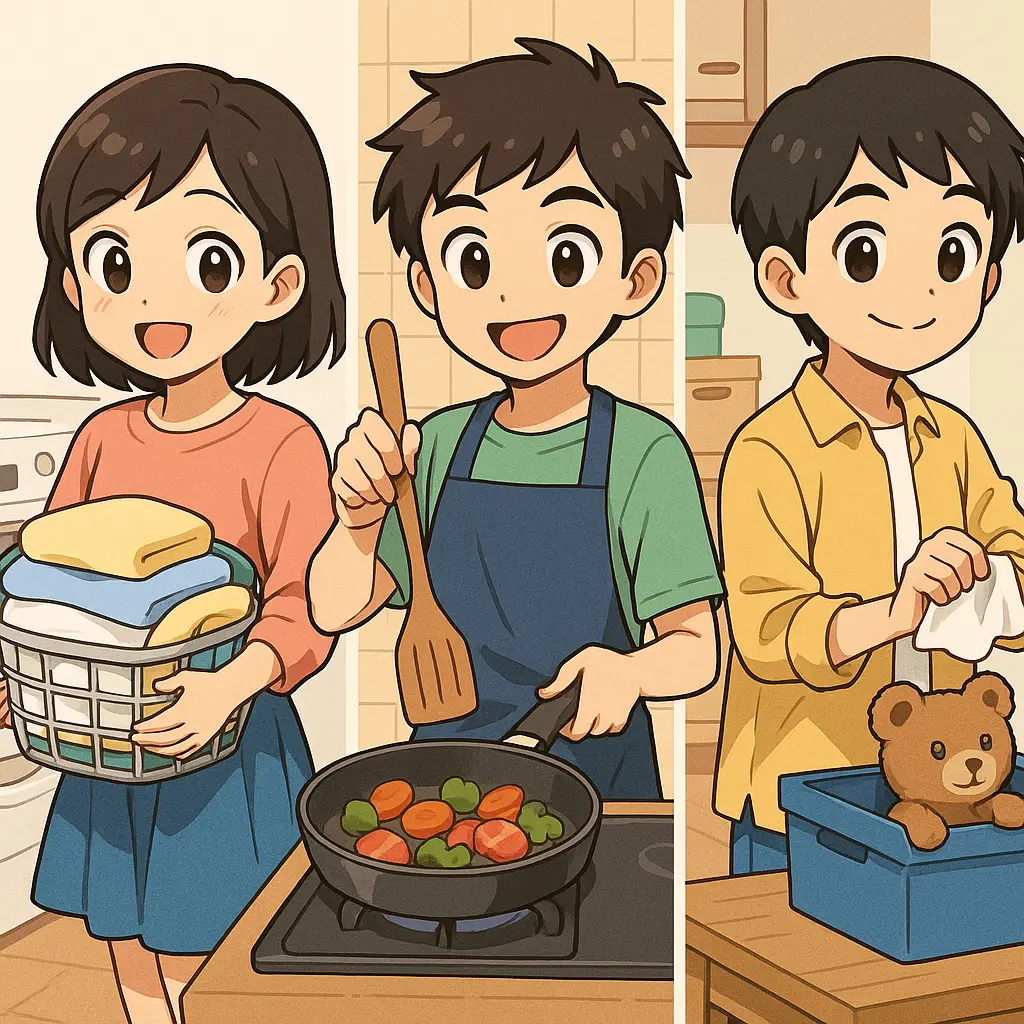
以上、「子育てがラクになる!発達支援に役立つ声かけフレーズ集」でした。最後までお読みいただき本当にありがとうございました!











コメント