お子さんが急に叩いたり、物を投げたりしてしまう行動に困ったことはありませんか?他害行動に悩むと、「どうしてこんなことをするんだろう…」と戸惑ったり、不安になったりしますよね。
でも、実はこれらの行動には「助けて」「わかってほしい」という子どものサインが隠れていることが多いんです!この記事では、親子で穏やかな日常を取り戻すために役立つ10の具体的な方法をご紹介します。環境を整える工夫から、感覚遊び、視覚支援の使い方まで、家庭で今すぐ試せるヒントが満載です。
「どうしたら親子で少しずつ穏やかな毎日を取り戻せるんだろう?」と思っている方は、ぜひ読み進めてみてくださいね!
はじめに
「他害行動に悩む親御さんへ!この記事でヒントを見つけてみませんか?」
こんにちは!この記事を読んでいるということは、お子さんの「他害行動」について悩んでいるのではないでしょうか?他害行動という言葉を聞くと、どこか重くて心配になるかもしれません。でも、それはお子さんが何かを伝えたくて表現している方法のひとつであり、親としてその背景や理由を理解することが大切なんです。
「どうして叩いちゃうの?」「なんでこんなに怒るの?」と疑問や不安を抱えている方も多いと思いますが、それらの行動にはちゃんと理由があります。そして、その理由を少しずつでも知ることができれば、親御さんの不安が和らぎ、お子さんとの関係がもっとスムーズになることもありますよ。
この記事では、「他害行動」の原因や背景を分かりやすく説明しながら、家庭でできる対応策をたっぷりご紹介します。たとえば、どんな環境が子どもにとって安心なのか、どう声をかければ気持ちが落ち着くのか、具体的な方法をお伝えします。これらのヒントが、親御さんにとって「やってみよう!」と思えるきっかけになると嬉しいです。
また、この記事ではただ感情論に寄りかかるのではなく、客観的な視点を交えた説明も意識しています。たとえば、自閉症の特性や、感覚過敏などの科学的な背景も踏まえています。これにより、「あ、うちの子にもこれ当てはまるかも」と腑に落ちる瞬間がきっとあるはずです。
もちろん、すべての家庭やお子さんに同じ方法が当てはまるわけではありません。でも、「試してみる価値がありそう!」と思えるものを見つけていただける内容になっていると思います。この記事が、少しでも心の負担を軽くし、「大丈夫、やれることがあるんだ」と前向きになれるお手伝いができれば幸いです。
どうぞ最後まで読んでいただき、実際に使えるヒントを見つけてみてくださいね!親子で一歩ずつ進んでいきましょう。
自閉症の他害行動ってどんなもの?
他害行動というと、なんだか聞き慣れない言葉かもしれません。でも、実際に親御さんの育児の中で、「叩く」「噛む」「物を投げる」などの行動に困った経験がある方は多いのではないでしょうか?これらが「他害行動」と呼ばれるものです。最初にお伝えしたいのは、これらの行動は決して「子どもがわざとやっている」わけではなく、その裏にはいろんな理由や背景があるということです。それを一緒に理解していきましょう。
他害行動の具体例と原因を知ろう
他害行動は、他人に危害を加える行動のことを指します。たとえば、兄弟を叩いたり、学校で友達を噛んでしまったり、カッとなって物を投げたりするような行動が当てはまります。一見すると「突然始まった」「何でそんなことを?」と思うような行動でも、実はその背景にはさまざまな原因が隠れています。
たとえば、以下のようなケースがあります:
- 感覚過敏: 小さな音や強い光、肌に触れる感触など、特定の刺激に敏感すぎて、それを避けるために他害行動が起こることがあります。
- ストレスや不安: 環境が変わったり、予定が急に崩れたりすると、不安やストレスから行動に出てしまうことがあります。
- フラストレーション(欲求不満): 自分の気持ちや要求が相手に伝わらないもどかしさが行動として現れることもあります。
- 模倣: 他の子どもや大人の行動を見て学習し、それを無意識に真似してしまう場合もあります。
他害行動は「突然の問題行動」として見られがちですが、実際には子どもが「何かを伝えたい」「困っている」というサインであることが多いのです。そのサインを見逃さないことが、親としての第一歩になります。
他害行動の背景に隠れる「子どものサイン」
子どもは、自分の中にある不安や不快感をうまく言葉で表現できないことがよくあります。その代わりに、行動で示すのが自閉症の特性を持つ子どもたちの特徴のひとつです。これを「サイン」として受け取る視点を持つことが大切です。
たとえば、感覚過敏の子どもにとって、普通の音や光が「耐えがたい刺激」になることがあります。そんなとき、その刺激を避けようとして、叩いたり、物を投げたりする行動が現れる場合があります。また、新しい環境やいつもと違う状況に直面すると、自分のペースを守れなくなり、不安から他害行動を取ることもあります。
また、他害行動が「不快感」だけでなく「関心を引きたい」という気持ちから出る場合もあります。「僕のことをもっと見てほしい」「助けてほしい」といった子どものニーズが表現として現れるのです。このように、他害行動にはさまざまな背景やサインが隠れていることを覚えておいてください。
他害行動を理解することが解決のカギ!
ここで知ってほしいのは、「他害行動は悪いことをしたいからやっているわけではない」ということです。他害行動は、子どもが「助けが必要だよ」と教えてくれているサインです。その行動だけを叱るのではなく、なぜそうなったのか、その原因や背景を見つけることが解決の第一歩になります。
たとえば、叩く行動が多い場合、「子どもは何にストレスを感じているのか?」「どうすればそのストレスを軽減できるのか?」を考える必要があります。また、感覚過敏による行動であれば、「その刺激を減らす方法は?」「子どもが安心できる環境をどう作る?」といった工夫が求められます。
子どもの他害行動を冷静に受け止め、その背後にあるニーズを理解することで、親子関係がより良い方向に進んでいきます。何よりも、子どもが「安心して自分を表現できる場」を作ることが大切です。他害行動は「困った行動」として見られがちですが、それを「理解のきっかけ」と捉えれば、親としての視点もぐっと広がるはずです。
他害行動は「子どもの声なき声」とも言える大切なサインです。その背景を理解し、親子で一緒に乗り越えるための手がかりを見つけていきましょう。
他害行動を減らす!親が試したい10の秘訣
自閉症の子どもの他害行動を減らすためには、いろいろな工夫が必要です。でも、一つ一つのアプローチを少しずつ試していくことで、親も子どもも安心できる毎日に近づけるはず。ここでは、実践しやすい10の秘訣をご紹介します。
環境を整えるだけで行動が変わる!
他害行動が引き起こされるきっかけの一つに、周りの環境が関係していることがあります。例えば、音や光、温度など、子どもにとって刺激が強すぎる環境ではストレスが溜まりやすくなります。そこで、まずは環境を見直してみましょう。
具体的には、
- 音の調整: テレビの音量を下げたり、イヤーマフを使って音を遮断したりする。
- 光の調整: 窓に遮光カーテンをつける、強い光を和らげるスタンドライトを使用する。
- 安心スペースの確保: 子どもが「ここなら落ち着ける」と思える場所を作る(お気に入りのぬいぐるみやクッションを置くのも◎)。
子どもがリラックスできる環境を整えるだけで、行動が落ち着くこともあります。「子どものストレスを減らすには?」という視点で工夫してみましょう。
行動の「原因」を特定して効果的に対策
他害行動が起こる原因を探ることは、行動を減らすための第一歩です。「何がきっかけで叩いたり、噛んだりしているんだろう?」と考え、行動が起こる前後を観察してみましょう。
ポイントは次のような点です:
- 行動前の様子を記録: どんな状況や出来事が行動を引き起こしたのか(場所、時間、周囲の人など)。
- 行動後の反応をチェック: 行動が起こったあと、子どもがどう感じていたのか(スッキリしているのか、逆にイライラが続いているのか)。
例えば、「特定の音がすると物を投げる」「兄弟と遊ぶときだけ叩く」といったパターンが見えてくるかもしれません。原因を知ることで、適切な対策がとれるようになります。
見通しがあると安心!視覚支援の活用法
自閉症の子どもたちは、次に何が起こるのかが分からないと不安を感じることがあります。そこで、視覚的な支援ツールを使うと、子どもの安心感がぐっと高まります。
- スケジュール表: 一日の流れを絵や写真で示す。「次はおやつ、そのあと公園」といった順番を視覚的に伝える。
- 選択肢カード: 「赤いシャツと青いシャツ、どっちにする?」のように、自分で選べる形にする。
- ごほうびボード: 良い行動ができたらシールを貼るなど、達成感を感じられる工夫を。
視覚支援を取り入れると、「今から何をすればいいのか」が明確になり、無駄な不安やイライラを減らせます。
子どもが安心する「肯定的な言葉」の魔法
子どもに対して「ダメ!」と否定ばかりしていませんか?もちろん危険な行動を止めるのは大事ですが、肯定的な言葉を意識して使うと、子どもは安心感を得て、自己肯定感が育ちます。
たとえば、叩いてしまったときには、
- 「叩かないで、手でなでなでしてくれると嬉しいな」
- 「叩かずに言葉で教えてくれてありがとう!」
というように、「してほしい行動」を伝えることで、行動の改善につながります。声のトーンや表情も柔らかくすることで、子どもの心により響きやすくなります。
身体で感情を発散!簡単にできる運動遊び
感情が溜まりすぎると、それが他害行動として表れることがあります。そこで、感情を体で発散する運動遊びを取り入れてみましょう。
おすすめの活動:
- ジャンプ運動: トランポリンやクッションの上でジャンプしてエネルギーを発散。
- リトミック: 音楽に合わせて体を動かすことでリズム感とリラックス効果を得る。
- 風船遊び: 風船をポンポンと落とさないように遊ぶだけで、集中力アップと笑顔も引き出せます!
運動を取り入れると、身体的にも気持ち的にもリフレッシュでき、落ち着きが出る場合があります。
他害行動を肯定しない!一貫した対応で改善
他害行動が起きたとき、「つい甘やかしてしまう」または「怒りすぎてしまう」という親御さんも少なくありません。一貫性を持った対応をすることで、子どもが「してはいけないこと」と「していいこと」を理解しやすくなります。
具体的には、
- 叩いたら反応しすぎない: 大げさに反応せず、冷静に「それは痛いよ」と伝える。
- 良い行動を褒める: 手をつなげた、言葉で伝えられたなどの良い行動をすぐに褒める。
適切な行動を強化し、他害行動を減らす一貫性が大切です。
順番を守る練習がカギ!ターンテイキングの工夫
順番を守る(ターンテイキング)は、他害行動を減らす社会的スキルのひとつです。日常の中で楽しく練習してみましょう。
おすすめの方法:
- カードゲームやすごろく: 順番を意識しやすい遊びを活用。
- おしゃべりターン制: お話しする時間を親子で交互に決める練習。
遊びの中で学ぶことで、子どもにストレスを与えずスキルを育むことができます。
感覚遊びで心をリラックス!
感覚過敏が原因で他害行動が起きている場合、感覚統合遊びを取り入れると効果的です。
たとえば:
- 砂遊び: 触感を楽しむ。
- 水遊び: 涼しさと触感でリラックス。
- スライム遊び: 触って楽しい柔らかい素材で気分転換。
これらの遊びは、子どもの感覚を落ち着かせる手助けになります。
他害行動のサインを見逃さない観察力
他害行動の前には、必ず何らかの「サイン」があることが多いです。小さな表情や仕草の変化に注目し、早めに対応する習慣をつけましょう。
例えば、「手を強く握る」「眉間にシワが寄る」といったサインを見逃さず、落ち着ける環境に導くことで、行動を未然に防げることがあります。
専門家の力を借りて親子で一歩前進!
最後に、専門家のサポートを受けることも大切です。地域の療育センターや発達支援の専門機関に相談することで、親子の状況に合った具体的なアドバイスが得られます。
専門家の力を借りることは「助けを求める」ではなく、「より良い方向へ進む選択肢を増やす」ことです。安心して利用してみましょう!
これら10の秘訣を少しずつ試しながら、お子さんに合った方法を見つけてみてくださいね!
他害行動が起こったときの具体的な対応方法
他害行動が突然起こると、親も驚いてしまったり、どうしていいかわからなくなることがありますよね。でも、そんなときこそ冷静さが大切です。ここでは、突発的な他害行動への「その場での対応」と、その後の「フォローアップ」の具体的な方法を解説します。事前に心の準備をしておくことで、いざというときに落ち着いて対応できるようになりますよ。
突発的な他害行動への「瞬間対応」マニュアル
他害行動が起きたら、まずは 安全確保 が最優先です。子どもが何かを投げたり、誰かを叩こうとしている場合、周囲の人や子ども自身がケガをしないようにすることが重要です。大切なのは、冷静さを保ちながら、子どもが落ち着くのをサポートすることです。
安全確保のポイント
- 周囲の危険を取り除く: 投げられそうな物や壊れやすいものをそっと遠ざけましょう。
- 他の子どもを安全な場所に移動させる: 特に兄弟姉妹がいる場合、巻き込まれないよう距離をとることが大事です。
子どもを落ち着かせる方法
- 静かに声をかける: 「大丈夫だよ」「少しゆっくりしようね」と落ち着いた声で話しかけます。怒ったり、大きな声を出すと、子どもの不安や興奮がさらに高まる可能性があります。
- 抱きしめるか、そばにいるだけでもOK: 子どもが落ち着けるなら、優しく抱きしめてあげたり、そばで見守るだけでも安心感を与えられます。ただし、嫌がる場合は距離を取りつつ見守りましょう。
避けたいNG行動
- 大声で叱る: 恐怖心を与えるだけで、行動の改善にはつながりません。
- 感情的に反応する: 怒ったり焦ったりすると、子どもはさらに混乱してしまいます。
ポイントは、子どもが安心感を取り戻せるような対応を心がけることです。行動をすぐに止めることだけがゴールではなく、子どもの気持ちや状況に寄り添う姿勢が大切です。
他害行動後のフォローが次につながる!
突発的な他害行動が収まった後も、親としては「これで終わり」とは思わず、次に同じようなことが起きないように振り返りをするのがポイントです。この振り返りを「フォローアップ」と考え、子どもとの関わり方を少し工夫してみましょう。
フォローの具体的なステップ
- 子どもが落ち着いてから声をかける
行動直後はまだ気持ちが高ぶっていることが多いので、少し時間をおいてから、「何があったのかな?」と優しく話しかけます。このとき、叱るのではなく、「どうしてそうしたのか」を子どもの言葉や態度から引き出してみてください。
例:
- 「びっくりしたけど、何か嫌なことがあったかな?」
- 「さっき叩いちゃったけど、何か伝えたかったのかな?」
子ども自身も自分の気持ちを整理するきっかけになります。
- 行動の背景を一緒に振り返る
親としても、「どんなきっかけがあったのかな?」と冷静に考えてみます。たとえば、
- 直前に環境が変わった?(急な予定変更や新しい場所)
- 特定の音や光が刺激になった?
- 誰かとのコミュニケーションでフラストレーションを感じた?
原因を把握することで、次回同じ状況を避ける工夫ができます。
- 解決策を一緒に考える
子どもと一緒に「次に同じようなことがあったらどうするか」を考えてみましょう。視覚支援ツールや簡単な合図(手を挙げる、バツのジェスチャーなど)を使えば、子どもが行動以外の方法で気持ちを伝える練習ができます。
例:
- 「次は嫌なときは『ちょっと待って』って言ってみようか。」
- 「おもちゃが取り合いになったら、先生に相談してみる?」
- 良い行動を見逃さず褒める
子どもが少しでも他害行動以外の方法で気持ちを表現できたときは、すかさず褒めてあげましょう。
- 「ちゃんと声で伝えられたね!えらいよ!」
- 「今日は手を出さずにお話しできたね、すごい!」
こうしたポジティブなフィードバックが、次の行動改善につながります。
フォローのポイントは親子の信頼関係を育むこと
フォローアップは、子どもに「叱られる時間」ではなく、「一緒に解決策を考える時間」だということを意識してください。子どもは失敗を通じて学び成長します。親が温かくサポートすることで、子どもも安心して次に挑戦できるようになります。
他害行動は一度で解決するものではありませんが、こうした対応を続けることで少しずつ改善していきます。焦らず、子どものペースに合わせて一緒に進んでいきましょう!
他害行動が減った!成功した親子の体験談
他害行動に悩んでいると、「うちの子も改善できるのかな…?」と不安に思うこともありますよね。でも、少しずつ工夫を続けていけば、親子で新しい方法を見つけていけるんです!ここでは、実際に他害行動が改善した成功事例をご紹介します。同じような悩みを抱えていた親御さんの経験が、みなさんのヒントになれば嬉しいです。
ケース1: 環境調整でおだやかな日々を取り戻したAさん親子
【背景】
3歳の男の子、たくや君(仮名)は、外出先で他の子どもを叩いてしまうことが頻繁にありました。スーパーや公園で知らない子に手を出してしまい、お母さんのAさんも「外出が怖い…」と感じるようになっていたそうです。
【取り組み】
たくや君が叩く前後の状況をAさんが詳しく観察したところ、どうやら「音や人の多さ」が原因でストレスを感じていることに気づきました。そこで、以下の環境調整を取り入れました:
- 音に対する工夫: イヤーマフを外出時に持ち歩き、たくや君が嫌がる大きな音を遮断。
- 人混みを避けるスケジュール作り: スーパーは混雑する時間帯を避けて買い物に。公園も静かな時間帯を選ぶように。
- 安心できるアイテムを携帯: お気に入りのぬいぐるみを持ち歩くことで、不安を和らげる工夫を。
【結果】
環境を整えるだけで、たくや君の行動は大きく改善!外出先で叩く行動が徐々に減り、お母さんも「もっと外に出ても大丈夫なんだ」と自信が持てるようになったそうです。
ケース2: 視覚支援で気持ちを伝える方法を学んだBさん親子
【背景】
5歳の女の子、みきちゃん(仮名)は、自分の思い通りにならないと、すぐにお友達を噛んでしまうことがありました。幼稚園でも「噛む行動」が原因でトラブルになることが多く、お母さんのBさんも「どうしていいかわからない…」と困り果てていました。
【取り組み】
幼稚園の先生のアドバイスで、みきちゃんが感情をうまく伝えられないことが原因だとわかり、「視覚支援ツール」を導入することにしました:
- 感情カードを使う: 「怒った」「悲しい」「嫌だ」といった感情を表すカードを用意し、気持ちを伝える練習を開始。
- スケジュール表の活用: 幼稚園での1日の流れを絵カードで見せることで、次に何が起こるのかを予測しやすくした。
- 成功体験を褒める: カードで気持ちを伝えられたときはすぐに褒め、「伝えられるんだ」という自信を育てる。
【結果】
視覚支援を始めて数ヶ月後には、噛む行動が大幅に減少。みきちゃんはカードを使うことで自分の気持ちを伝えられるようになり、トラブルが減ったそうです。Bさんも「もっと早く試してみればよかった」と感じたそうです。
ケース3: 感覚遊びで落ち着きを取り戻したCさん親子
【背景】
4歳の男の子、けんた君(仮名)は、家でも外でも突然物を投げる行動が目立っていました。特に、何かを頼まれたときや指示をされたときにパニックになり、家の中で物が散乱することも。
【取り組み】
感覚過敏の可能性を考えたCさんは、「感覚統合遊び」を取り入れることにしました:
- 砂遊びやスライム遊び: 指先を使う遊びで集中力を高めつつ、ストレスを軽減。
- 重い物を運ぶ活動: 箱やタオルを運ぶ遊びで、けんた君が身体を動かして気持ちを落ち着けられるように。
- 落ち着きスペースの確保: 部屋の一角にクッションや毛布を置き、「ここでリラックスできるよ」という場所を用意。
【結果】
感覚遊びを続けるうちに、けんた君は徐々に物を投げる行動が減り、自分で落ち着きを取り戻せるようになりました。Cさんは「遊びを通じて、息子がリラックスできる方法を見つけられた」と笑顔で話してくれました。
成功事例から学ぶポイント
どの事例にも共通しているのは、子どもの特性や行動の背景を理解し、それに合った支援を工夫していることです。成功のカギは、次の3つに集約されます:
- 子どもの行動を観察して原因を特定する: どんな状況で行動が起きるのか、しっかり見極めることが第一歩です。
- その子に合った支援方法を試す: 環境調整、視覚支援、感覚遊びなど、具体的な方法を取り入れる。
- 小さな成功体験を積み重ねる: 子どもが少しでも改善できたときにしっかり褒め、モチベーションを高める。
親子で工夫を続ければ、必ず改善への道が見えてきます。今回の事例が、「うちもできるかも!」と思うきっかけになれば幸いです!
まとめ
他害行動に悩んでいると、「どうしてうちの子はこんなことをするんだろう?」とモヤモヤしたり、つい感情的になってしまうこともありますよね。それに、「もうどうしたらいいのかわからない…」と不安になってしまうことも、きっと少なくないはずです。でも、ここまでお伝えしてきたように、この記事の10のポイントを少しずつ試していくことで、親子の関係に変化が生まれ、少しずつ穏やかな日常を築くことができます。
行動の背景を知ることが改善の第一歩!
これまでにも何度か触れましたが、他害行動はただの「困った行動」ではありません。子どもが「何かを伝えたい」「不安やストレスを抱えている」というサインであることが多いんです。たとえば、感覚過敏や環境の影響、コミュニケーションの困難さなど、他害行動にはいろいろな理由が隠れています。その背景を知ることが、行動を改善するための第一歩です。
行動そのものを「止めること」だけに集中してしまうと、子どもの気持ちを理解する機会を逃してしまうことがあります。なぜその行動が起きたのか、その背後にある原因に目を向けることで、親としての視野も広がりますし、次の一歩が見えてくるはずです。
子どもと一緒に「成長する道」を歩もう
子どもの行動を変えるには、親も「どうすればこの子に合った支援ができるんだろう?」と考えながら試行錯誤していく必要があります。でも、安心してください!完璧である必要はありません。一つずつ工夫を取り入れて、小さな成功体験を積み重ねることで、親も子どもも一緒に成長していけるんです。
たとえば、環境調整をしてみたり、視覚支援を導入してみたり、感覚遊びを取り入れてみたり…。最初は「これで本当にいいのかな?」と不安になるかもしれませんが、小さな成功体験が積み重なるうちに、「これがうちの子には合ってるんだ!」と自信が持てるようになるはずです。
10のポイントを自分たちに合った形でアレンジしてみて
この記事で紹介した10のポイントは、あくまで「ヒントの集まり」です。全部を一気に取り入れる必要はないし、必ずしもすべてが自分の子どもに合うわけでもありません。大切なのは、「無理なく、続けられる方法」を見つけることです。
たとえば:
- 視覚支援が効果的なら: スケジュール表や感情カードを工夫してみる。
- 感覚遊びでリラックスできるなら: 毎日少しずつ取り入れてみる。
- 環境調整で安心感が生まれるなら: 子どもが過ごしやすいスペースをさらに整えてみる。
こうしたアレンジを加えながら進めていくことで、子どもにとっても親にとっても無理のない支援が可能になります。
親も「頼れる場所」を見つけて、一緒に進もう
他害行動に向き合うのは、親一人で抱える必要はありません。専門家や支援団体、本やオンラインリソースなど、頼れる場所を見つけることで、より効果的なサポートが受けられます。
支援を受けることは「自分ができない」ということではなく、「より良い方法を見つける選択肢を増やす」という前向きなステップです。むしろ、専門家や他の親たちとつながることで、新しい視点や解決策が見つかることも多いんです。
少しずつ前に進めば大丈夫!
他害行動の改善には時間がかかることもありますが、焦る必要はありません。一歩一歩進んでいけば、親子ともに少しずつ変化が訪れます。この記事を参考にしながら、子どもの特性を理解し、支援の工夫を重ねることで、親子で乗り越える力を育むことができます。
「大丈夫、少しずつやってみよう!」という前向きな気持ちで、ぜひこの記事の内容を日々の育児に取り入れてみてください。親子で笑顔が増える日常を目指して、一緒に成長していきましょう!
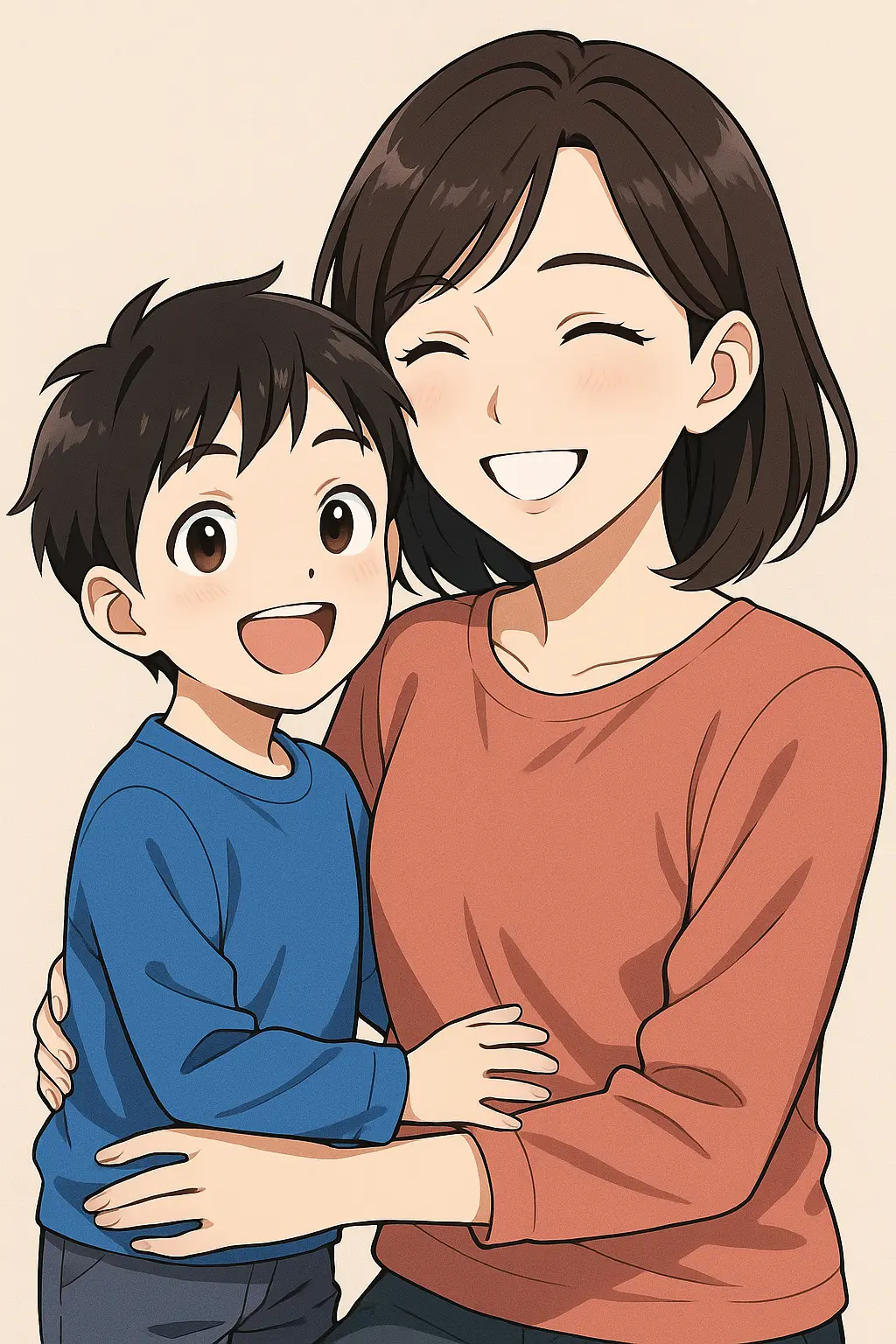
さいごに
最後まで読んでいただき、本当にありがとうございます。この記事を読んで「これならできそう!」と思えるポイントが一つでも見つかったなら、とても嬉しいです。
今回ご紹介した10のポイントには、家庭で今すぐ取り入れられるアイデアがたくさんあります。
- 環境を整える: 子どもが安心できるスペースを作る。
- 視覚支援を活用する: 感情カードやスケジュール表で不安を減らす。
- 感覚遊びを取り入れる: スライムや砂遊びでリラックス。
これらを一つずつ試してみるだけで、親子で穏やかな日常に近づけるはずです。
他害行動は「困った行動」ではなく、子どもが発する「サイン」であることを忘れずに。焦らず、小さな一歩を積み重ねていけば、親子で一緒に成長していけます。環境調整や視覚支援を試したり、支援団体に相談したりしながら、自分たちに合った方法を見つけてくださいね。
この記事が、少しでも前向きな気持ちになれるきっかけになれば幸いです。改めて、最後まで読んでいただきありがとうございました!これからも親子で笑顔いっぱいの日々を築いていきましょう!
以上【自閉症の他害行動を減らす!親が知っておきたい10のポイントとは?】でした。











コメント