自閉症の子に多い「叩く・つねる」などの他害とは?
自閉症のお子さんを育てていると、「どうして叩いちゃうの?」「友達をつねってしまって…」といった悩みに直面するママも多いと思います。実は、これらは専門的には「他害行動」と呼ばれています。
他害行動というとちょっと怖い響きですが、子ども自身が「相手を傷つけたい」と思ってやっているわけではなく、気持ちをうまく伝えられないストレスや、感覚の違いから出てしまう行動であることが多いんです。
ここでは、具体的にどんな行動を指すのか、どんな場面で出やすいのか、そして「ただのかんしゃく」との違いについて見ていきましょう。
他害行動とは?叩く・かみつく・暴れる具体例
「他害行動」とは、相手に対して手や体を使ってしまう行動のことを指します。たとえば、こんなケースがよくあります。
- 兄弟や友達を叩いてしまう
- 腕をつねる
- 怒ったときにかみつく
- パニックになって物を投げる・暴れる
大人からすると「危ないからやめて!」とすぐに止めたくなる行動ですが、子ども自身にとっては「やめよう」と思ってやっているのではなく、気持ちを表現する手段が手を出すことになってしまっているケースが多いんですね。
特に、自閉症の子どもは「ことばで説明するのが苦手」「感覚に強い反応を示す」などの特性があるため、こうした行動が出やすくなることがあります。
他害が出やすい年齢や日常シーン
「うちの子だけなのかな?」と不安になる方も多いのですが、実際には幼児期〜小学校低学年ごろにかけて、手が出やすい子は少なくありません。特に以下のようなシーンで多く見られます。
- おもちゃの取り合いで欲しいものをうまく言えず叩いてしまう
- 園や学校での集団生活の疲れやストレスからつねってしまう
- 大きな音や人混みなど、感覚的にしんどい場面で暴れてしまう
- 予定変更や「やりたいことができない」状況でパニックになりかみつく
つまり、「特別なことをしていなくても日常の中で自然に起こりやすい」ということです。
大切なのは、他害行動が出る背景には必ず理由があるという視点で見てあげること。
自閉症の他害と「ただのかんしゃく」の違い
よくママから聞かれるのが「これは自閉症の特性?それとも普通のかんしゃく?」という疑問です。
一般的なかんしゃくは、「イヤ!」という気持ちを強く出すときに誰にでも見られるものです。成長とともに言葉や我慢が増えれば少しずつ減っていきます。
一方で、自閉症の子の他害は、感覚過敏・言葉の遅れ・見通しのなさといった特性が強く関係していることが多いです。
- かんしゃく → 「欲しい」「イヤ」が中心。気持ちの切り替えができれば落ち着く
- 他害 → 本人のストレスや不安を処理できないために手が出る。繰り返し起こりやすい
つまり、ただのわがままや親のしつけ不足ではなく、発達特性から来る行動である可能性が高いのです。
この違いを知ると、「私の育て方が悪いんじゃない」と安心できるママも多いはずです。
自閉症の子が手を出す原因|他害の背景を知ろう
子どもが叩いたり、つねったりしてしまうと、どうしても「うちの子は乱暴なのかな…」と心配になってしまいますよね。でも実は、自閉症の子が手を出してしまう背景には、必ず理由やきっかけがあります。
ここを理解してあげることが、ママ自身の安心にもつながるし、子どもに合った支援や工夫を考える大きなヒントになります。
言葉で伝えられない不満や欲求
自閉症のお子さんの多くは、「気持ちや要求をことばで表現するのが苦手」という特性を持っています。
たとえば…
- 「おもちゃが欲しい」と言えなくて、相手の手を叩いてしまう
- 「やめてほしい」と言えずに、つねってしまう
つまり、ことばの代わりに体が先に動いてしまうんです。
これは「攻撃したい」からではなく、自分の思いを伝える方法が限られているから。
ここで大切なのは、ママが「どうせまた叩いた」と思うのではなく、「何を伝えたかったのかな?」と気持ちの背景を探ってあげることです。
感覚過敏・感覚鈍麻による刺激への反応
自閉症の子は、音・光・におい・触覚といった感覚にとても敏感だったり、逆に鈍感だったりすることがあります。
たとえば…
- 大きな声や騒がしい場所でパニックになり、思わず叩いてしまう
- 肌に触れる感覚が不快で、相手を振り払うようにつねる
- 痛みに鈍感で力加減がわからず、強く押してしまう
これらは本人にとっては「つらい刺激から身を守ろう」とする自然な反応。
周囲から見ると“他害”に見えてしまうけど、実は防御反応なんですね。
ルーティンが崩れることで生じる強い不安
自閉症の子は、決まった順番や流れ=ルーティンをとても大切にする傾向があります。
- いつもの道を通らなかった
- 予定していた遊びができなかった
- ご飯の時間やお風呂の時間がずれた
こうした「予想外の変化」に出会うと、不安や混乱からかみついたり、暴れたりすることがあります。
これは、「どうして変わったの?」という理解が難しいために起きるストレス反応。
ママとしては「ちょっと変わっただけなのに」と思うかもしれませんが、子どもにとっては大事件なんです。
注目を引きたい・気持ちを伝えたい場合
「ママ、こっちを見て!」という気持ちが強いときに、手が出てしまうこともあります。
- 遊んでほしいのに声をかけても気づいてもらえなかった
- 自分の気持ちをうまく表せなくてイライラした
- 「もっと注目して!」というサイン
本当は「遊ぼう」や「かまって」と言いたいのに、ことばで伝えられないから叩く・つねるという方法を使ってしまうんですね。
これは裏を返せば、「ママに気づいてほしい」という愛情のサインとも言えます。
疲れや空腹・体調不良が影響するケース
意外と見落とされがちなのが、体調やコンディションです。
- お腹がすいているときにイライラして叩く
- 眠いときや疲れているときにパニックになって暴れる
- 風邪気味や体調不良のときに、イライラが増してつねる
大人でも「お腹がすくと機嫌が悪くなる」ことはありますよね。
それと同じで、子どもも体の不調が行動に直結します。
ママが「最近疲れてそうだな」「ちょっとお腹すいてるかも」と気づいてあげるだけで、予防につながることも多いんです。
「どうして?」が「なるほど!」に変わる子育てのヒント
自閉症の子が叩いたり、つねったりするのは、悪気があってやっているのではなく、伝えられない思いや不安の表れです。
- 言葉で伝えられない
- 感覚に敏感すぎる
- ルーティンが崩れる
- 注目してほしい
- 疲れや空腹
こうした背景を理解してあげることで、ママの「どうして?」が少しずつ「なるほど!」に変わっていきます。
その場でできる!自閉症の子の他害行動への対応法
子どもが急に叩いたり、つねったりすると、ママとしては「どう止めたらいいの!?」とドキッとしますよね。
でも大丈夫、その場でできる対応の工夫を知っておくと、気持ちがずっとラクになります。
ここでは「すぐに実践できる5つのポイント」を紹介します。
まずは安全を守る|周囲の子や自分を落ち着かせる工夫
一番大切なのは、子ども自身と周囲の安全を守ることです。
たとえば園や公園など人が多い場所では、相手の子がびっくりして泣いてしまうこともあります。そんなときは、
- そっと子どもの体を押さえてそれ以上手が出ないようにする
- 周囲の子を少し離して安全な距離を確保する
- ママ自身が落ち着いた態度で「大丈夫だよ」と安心させる
ここで焦ってしまうと子どもも余計に不安定になります。
まずは「危なくない環境をつくる」ことに意識を向けるのがポイントです。
怒鳴らない!冷静に対応する声かけのコツ
つい「やめなさい!」と強い口調で言ってしまいがちですが、怒鳴ると逆効果になることが多いです。
なぜなら、自閉症の子は大きな声や表情の変化に敏感で、余計にパニックを強めてしまうことがあるからです。
代わりにおすすめなのは、
- 落ち着いた声のトーンで短く伝える
- 表情もできるだけ冷静に保つ
- 「深呼吸」をしてから声をかける
ママが落ち着いていると、子どもにもその雰囲気が伝わって安心感につながるんですね。
「叩かない」など短く具体的な言葉で伝える方法
自閉症の子には、長い説明や抽象的な言葉は伝わりにくいことが多いです。
「なんでそんなことするの!」よりも、「叩かない」「手はおひざ」など、短くて分かりやすいフレーズが効果的です。
また、ジェスチャーを合わせて見せると理解しやすくなります。
たとえば「手はおひざ」と言いながら、自分の手をひざに置いて見せてあげる。
視覚的に伝えることで、子どもが「どうすればいいか」をすぐにイメージできます。
静かな場所へ移動してクールダウンさせる
人が多い場所や大きな音がある環境では、子どもがさらに混乱してしまうこともあります。
そんなときは、静かな場所に移動してクールダウンするのがおすすめです。
- 教室の隅や、家の中の落ち着けるコーナー
- 車の中や、静かな廊下
- 家なら「お気に入りの毛布やクッションがある場所」
こうした“安心できるスペース”をあらかじめ用意しておくと、ママも子どもも対応しやすくなります。
「ここに来れば落ち着ける」という習慣をつくってあげると、子どもも安心して切り替えられるようになります。
他害の後に正しい行動を見せて学びにつなげる
他害が起きた後に大切なのは、「どうすればよかったのか」を教えてあげることです。
叩いてしまったときに「ダメ!」で終わってしまうと、子どもは「じゃあどうすればいいの?」と分からないままになってしまいます。
たとえば…
- 「欲しいときは“ちょうだい”って言うんだよ」
- 「イヤなときは“やめて”って言ってみよう」
- 「手で叩くんじゃなくて、ママに言ってね」
そしてできたときには、しっかり褒める!
「叩かなかったね、言えたね!」と肯定的に伝えることで、少しずつ正しい行動が増えていきます。
少しずつで大丈夫!毎日の積み重ねが力になる
子どもが手を出してしまったとき、ママはどうしても焦ってしまいますよね。
でも大切なのは、
- 安全を守る
- 冷静に声をかける
- 短く具体的に伝える
- 落ち着ける環境をつくる
- 正しい行動を教える
というシンプルな流れです。
他害行動は「今すぐ完全になくす」のは難しいけれど、毎回同じ対応を積み重ねることで、子どもは少しずつ学んでいきます。
ママも「完璧じゃなくていい」と思って、できることから取り入れてみてくださいね。

毎日の生活でできる|自閉症の他害を減らす予防策
叩く・つねるなどの他害行動は、その場での対処も大事ですが、実は「普段の生活の工夫」で減らしていくことができます。
予防の工夫を積み重ねることで、子どもが安心して過ごせる時間が増え、結果的に他害が出にくくなるんです。
ここでは、おうちでできる 5つの予防のポイント をご紹介します。
スケジュールや絵カードで安心できる見通しをつくる
自閉症の子は、「次に何が起きるのか」が分からないと不安になりやすいんです。
その不安がたまると、叩いたり暴れたりといった行動につながることもあります。
そこで役立つのが スケジュール表や絵カード。
たとえば…
- 朝の支度 → 保育園 → お迎え → ごはん → おふろ → 就寝
という流れを、写真やイラストで並べて見えるようにする。
そうすることで、子どもは「次はこれをするんだ」と安心でき、気持ちの見通しが持てるんですね。
特に予定が変わるときは、事前に絵カードを差し替えて伝えるとスムーズです。
気持ちを伝えるツールを増やす(ジェスチャー・絵カード・AAC)
手が出てしまう一番大きな理由は、「うまく気持ちを伝えられないから」。
そこで、ことば以外の伝え方を用意してあげることがとても大切です。
たとえば…
- 「欲しい」ときは手で指差し(ジェスチャー)
- 「やめて」と言えないときは「×マークのカード」を渡す
- 専用アプリやタブレット(AAC)で気持ちを選んで伝える
こうしたツールを用意することで、「叩く」以外の選択肢を子どもに与えられます。
伝え方が増えると、自然と他害は減っていきやすいんです。
感覚過敏に配慮した環境づくりの工夫
自閉症の子には、音・光・におい・触覚に敏感な子が多いです。
そのため、日常環境を少し工夫するだけで、かなり過ごしやすくなります。
たとえば…
- 大きな音が苦手なら ノイズキャンセリングイヤホンや耳栓
- まぶしい光がしんどい子には サングラスや帽子
- 服のタグや素材に敏感な子には タグを切る・肌触りのよい服
環境が整うと、子どものストレスが減り、手が出るきっかけを減らすことができます。
「なんで暴れるの?」と思っていたら、実は音や光がつらかった…なんてこともよくあるんです。
運動や遊びでエネルギー発散できる仕組み
子どもはエネルギーの塊。
特に自閉症の子は、体を動かすことで気持ちを落ち着けられることが多いです。
おすすめは…
- トランポリンでジャンプ遊び
- おふとんにゴロゴロ転がる
- 公園でブランコやすべり台
- 家の中ならバランスボールやクッション遊び
こうした「体を使ったあそび」を取り入れると、ストレスがたまりにくくなり、叩く・つねる行動の予防につながります。
褒めて育てる!自己肯定感を高める声かけ
最後にとても大事なのが、褒めることです。
子どもは「叩いちゃダメ」と注意ばかりされると、自己肯定感が下がってしまいます。
でも逆に、
- 「叩かなかったね、すごいね!」
- 「ちゃんと“ちょうだい”って言えたね!」
- 「手を出さずに待てたね!」
といった小さな成功を褒めると、「自分はできる」という気持ちが育ちます。
これが積み重なると、他害行動そのものが減っていくことも多いんです。
叩く・つねるを減らすには予防がいちばん大切
毎日の生活にちょっとした工夫を取り入れるだけで、他害行動を減らすヒントはたくさんあります。
- スケジュールや絵カードで安心感をつくる
- 気持ちを伝えるツールを用意する
- 感覚過敏に配慮した環境を整える
- 体を動かしてストレスを発散させる
- 褒めて自己肯定感を育てる
こうした工夫を積み重ねていけば、「叩く」「つねる」といった行動も少しずつ落ち着いていきます。
ママができる予防策は、子どもの安心にもママの心の余裕にもつながるんですね。
園や学校での「叩く・つねる」行動への対応
家庭での工夫に加えて、園や学校でどう対応するかもとても大切です。
集団生活の中では、どうしても子ども同士の関わりが増えるので、叩く・つねるといった行動が起きやすいんですよね。
でも、ママ一人で抱え込まなくても大丈夫。
先生や支援機関と連携することで、子どもに合ったサポート体制をつくることができます。
先生との連携|事前共有で安心できるサポート体制
まず大切なのは、担任の先生との情報共有です。
ママが「うちの子はこういう場面で手が出やすい」と伝えておくことで、先生も予測しやすくなります。
たとえば、
- 「大きな音にびっくりすると叩くことがある」
- 「おもちゃの順番待ちが苦手」
- 「予定変更があると混乱してしまう」
こうした情報を事前に共有しておくだけで、先生は先回りして支援できるんです。
また、園や学校での様子を家庭と共有することも大切です。
「今日はこんな場面で落ち着けましたよ」とか「今日は疲れていて手が出やすかったです」といった報告があると、家庭と園で一貫した対応ができるようになります。
友達への理解を広げる工夫(ソーシャルストーリー活用)
集団生活では、周りの子どもたちにどう理解してもらうかも重要です。
自閉症の子が叩いてしまうと、友達は「なんで?」と不安になりますよね。
そんなときに役立つのが ソーシャルストーリー。
これは、絵や短いお話で「どうして叩いてしまうのか」「どう接したらいいのか」を分かりやすく伝える方法です。
たとえば、
- 「Aくんは大きな音が苦手なんだ」
- 「びっくりしたときに手が出ることがあるけど、悪気はないんだよ」
- 「優しく声をかけてくれると安心できるよ」
こうした内容を絵本のように伝えることで、子ども同士の理解が深まりトラブルが減りやすくなるんです。
もちろん、これは先生が主導して行うことが多いですが、ママからも「ソーシャルストーリーを使ってもらえませんか?」と提案してみてもいいですね。
発達支援センターや療育施設と連携するメリット
他害行動が続いているときは、発達支援センターや療育施設との連携も心強い味方になります。
メリットとしては…
- 専門家の視点からアドバイスをもらえる
- 家庭・園・支援機関で一貫した対応ができる
- 個別支援計画を立ててもらえることもある
たとえば、療育の先生が「園ではこういう工夫をすると落ち着きやすいですよ」と具体的に提案してくれることがあります。
それを先生とママが共有することで、子どもに合ったサポートがぐっと効果的になるんです。
また、専門機関が関わることで先生自身の安心感にもつながり、「どう支援すればいいか分からない」という不安を減らすことができます。
園や学校と連携すれば他害対処もスムーズに
園や学校での対応は、ママ一人で頑張る必要はありません。
- 先生と事前に情報共有しておく
- 友達への理解を広げる工夫をする
- 支援機関と連携して専門的なアドバイスを受ける
この3つを意識するだけで、子どもが安心して過ごせる環境が整いやすくなります。
そして何より、ママ自身の「孤独感」も減っていくんですね。
ママの心を守るセルフケアと支援の受け方
子どもが叩いたり、つねったりする行動が続くと、どうしてもママの心はすり減ってしまいますよね。
「私の育て方が悪いのかな」「どうしたらいいのか分からない」と、自分を責めてしまうこともあるかもしれません。
でも、忘れないでほしいのは、ママの心の元気は子どもの安心にも直結しているということ。
ここでは、ママが自分を守りながら子育てを続けられるためのヒントを紹介します。
「自分のせいじゃない」と理解する大切さ
まず一番大切なのは、「子どもの他害はママのせいじゃない」と理解することです。
他害行動は、子どもの発達特性や環境からくる反応であって、ママのしつけ不足や愛情不足ではありません。
それを知らない周囲の人から「甘やかしてるからじゃない?」なんて言葉をかけられると、本当に胸が痛みますよね。
でも専門家の立場から見ると、これは「特性による行動」であり、誰のせいでもなく起こりうるものなんです。
ママが自分を責め続けると、気持ちがどんどん疲れてしまうので、まずは 「私のせいじゃない」と自分に言い聞かせてあげてください。
同じ悩みを持つママとつながる安心感
一人で悩んでいると「私だけが大変なのかも」と感じてしまいがちですが、実際には同じように悩んでいるママはたくさんいます。
- 発達障害児の保護者会やサークルに参加する
- SNSやオンラインコミュニティで気持ちを共有する
- ブログや体験談を読むことで「うちだけじゃない」と安心できる
こうしたつながりを持つことで、「分かってもらえる場所がある」と心が軽くなります。
ときには「うちも同じで大変だよ」と笑い合えることが、何よりの支えになるんです。
客観的に見ても、ピアサポート(同じ立場の人との支え合い)はストレスを軽減し、育児の継続力を高める効果があると言われています。
専門家に相談して一人で抱え込まない方法
それでも「どう対応していいか分からない」「自分だけでは限界」と感じるときは、専門家に相談するのが一番の近道です。
- 発達支援センターや療育施設
- 保健センターの発達相談
- 児童発達支援や放課後等デイサービスのスタッフ
- 医師や臨床心理士など専門職
こうした専門家は、ママの悩みを聞いたうえで具体的な対応方法や支援制度を提案してくれます。
一人で抱え込んで苦しくなる前に、「助けを借りてもいい」と自分に許可を出してあげましょう。
ママの心が元気だと子どもも安心できる
ママが心を守るためには、
- 「自分のせいじゃない」と理解すること
- 同じ悩みを持つママとつながること
- 専門家に相談して支援を受けること
この3つがとても大切です。
子どもの行動を落ち着ける工夫ももちろん大切ですが、ママの心が元気であることが一番の支えになります。
「私も大事にしていいんだ」と思えることが、子どもにとっても安心につながるんです。
他害が続くときに考えるべき医療的アプローチ
家庭や園・学校で工夫しても、どうしても 叩く・かむ・暴れるといった他害が長引くことがあります。
そんなとき、「もうどうしたらいいの?」とママの心も限界に近づいてしまいますよね。
ここで知っておきたいのが、医療的なサポートを受ける選択肢です。
医療の力を借りることは「親としての負け」ではなく、むしろ 子どもとママを守るための大切な一歩なんです。
発達検査や医師の診察を受けるメリット
まず考えられるのは、発達検査や専門医の診察です。
発達検査では、
- 子どもの強みや苦手な部分
- ことば・コミュニケーションの発達段階
- 感覚や行動の特徴
などを詳しく調べてもらえます。
これにより、「なぜ手が出てしまうのか?」という背景が客観的に見えてくるんです。
例えば「言葉の理解がまだ追いついていないから」「感覚の刺激に敏感だから」など、行動の理由を理解できること自体がママの安心につながるんですよね。
また、医師に相談することで、園や学校に対しても 診断書や意見書という形でサポートをお願いしやすくなるメリットもあります。
薬物療法が検討される場合の選択肢
「薬」という言葉を聞くと、少し不安になってしまうママも多いと思います。
でも、薬物療法はあくまで必要な場合の一つの選択肢です。
例えば、
- 強い興奮で日常生活に支障がある
- 自分や他人を傷つけるリスクが高い
- 睡眠障害や強い不安が重なっている
こういった場合に、医師の判断で少量の薬を使うことがあります。
もちろん 副作用や効果の見極めが大事なので、定期的に医師と相談しながら進めます。
薬は「全部を解決する魔法」ではありませんが、子どもの行動を少し落ち着ける助けになることもあるんです。
大切なのは「薬に頼る・頼らない」という二択ではなく、その子と家族にとってベストなバランスを探すことです。
成長とともに変わる他害への長期的な見通し
そして忘れてはいけないのが、子どもの成長とともに他害の表れ方は変わるということです。
小さいころは言葉で気持ちを伝えられず、手が出やすい子も多いですが、
少しずつコミュニケーション力や自己調整力が育っていくと、手が出る頻度は減っていくケースが多いです。
専門家の視点からも、「今の姿がずっと続くわけではない」と考えることが大切です。
ただし成長に伴って「暴言」や「無視」など、行動の形が変わることもあるので、長期的にサポートを受けながら対応していくことが安心につながります。
ママにとっても、「先の見通しが持てる」ことが心の支えになるんですよね。
医療や専門機関を頼ることは前向きな選択肢
- 発達検査や診察を受けると、行動の背景が客観的にわかる
- 薬は必要な場合に検討される選択肢であり、万能ではないけれど助けになることもある
- 成長とともに行動は変わるので、長期的なサポート体制を整えておくことが大切
他害が続くときこそ、ママが一人で抱え込むのではなく、医療や専門機関に助けてもらうことが前向きな選択肢になります。
「うちの子もサポートを受けていいんだ」と思えることが、安心への第一歩です。
体験談|自閉症の子の他害行動と向き合ったママの声
ここでは、実際に自閉症のお子さんを育てるママがどのように 「叩く・つねる」といった他害と向き合ったか を紹介します。
どのケースも簡単に「こうすれば解決!」という話ではありませんが、工夫や支援を重ねることで少しずつ変化が見えてきたエピソードです。
兄弟を叩いてしまったときの対応事例
あるママは、年下のきょうだいをお兄ちゃんがいきなり叩いてしまうことに悩んでいました。
きょうだい喧嘩とは違って、本人は「遊びたい」「構ってほしい」という気持ちが強かったのに、言葉で表現できずに手が出てしまったそうです。
最初は「叩いたらダメ!」と叱ってしまったものの、それでは逆に泣きわめきが強くなってしまいました。
そこで取り入れたのが、「叩かないよ。遊びたいときは“あそぼ”って言おうね」と、短くて分かりやすい声かけ。
さらに「一緒に遊べたね!」「待てたね!」と 良い行動をしたときにしっかり褒めるようにしたところ、少しずつ叩く回数が減っていったそうです。
客観的に見ても、これは「代替行動を教える+褒める」という有効な方法で、専門家も推奨している対応です。
園で友達をつねってしまったときの工夫
別のママは、幼稚園でお子さんが友達をつねってしまう行動に頭を抱えていました。
どうやら「近くに来てほしくない」という気持ちを、ことばで伝えられずにつねって表現していたようです。
そこで園の先生と話し合い、
- 「いや」と言う練習を家庭でも取り入れる
- 嫌なときは手を胸の前でクロスするジェスチャーを一緒に覚える
- 事前に「今日はたくさんのお友達がいるよ」と 見通しを伝える
といった工夫を続けました。
すると徐々に、つねる代わりに「いや」と言える場面が増えてきて、先生からも「トラブルが減りましたよ」と言ってもらえたそうです。
ここでのポイントは、園と家庭で連携して同じ対応を続けること。子どもが混乱せずに学べたことが成功につながりました。
他害が減って親子関係が楽になった体験談
あるママは、日常的に子どもから叩かれることで、正直「もう限界…」と感じていたそうです。
でも、発達支援センターに相談したことで、「叩くのは不安や混乱のサイン」だと気づけたことが大きな転機になりました。
支援者と一緒に「スケジュールを見せる」「静かな場所で休む」などの対応を続けたところ、叩く行動がだんだん減少。
ママ自身も「叩かれても、前みたいに怒鳴らずに対応できるようになった」と感じているそうです。
何より変わったのは、「この子はわざとじゃない」と思えるようになったこと。
その気持ちの変化によって、親子の関係がぐっと楽になったそうです。
「他害」は子どものSOSに気づくきっかけ
- きょうだいへの他害は「遊びたい」のサインかもしれない
- 園での行動は家庭と連携して対応すると効果的
- 専門家に相談することでママ自身の気持ちが楽になり、親子関係も改善することがある
体験談からわかるのは、他害は「ダメなこと」ではなく、子どもの困りごとの表れだということ。
ママが工夫を重ねたり、周囲と協力したりすることで、少しずつ解決に近づいていけるんです。
まとめ|ママが安心して子育てを続けるために
自閉症のお子さんが「叩く」「つねる」といった行動を見せると、ママとしてはとてもショックを受けたり、どうしていいか分からなくなってしまうこともありますよね。
でも、ここで忘れないでほしいのは、子どもの行動には必ず理由があるということです。
例えば、
- 言葉で気持ちを伝えられない frustration(もどかしさ)
- 感覚の敏感さや不安からくるパニック
- 注目してほしい気持ちの表れ
こうした背景を理解できると、「ただの問題行動」として捉えるのではなく、子どもなりのSOSのサインだと考えられるようになります。
その場での対処+予防策で少しずつ落ち着く
大切なのは、「今すぐどうするか」と「これからどう防ぐか」を両方意識することです。
たとえばその場では、
- 周囲の安全を守る
- 短く分かりやすい言葉で伝える
- 静かな場所でクールダウンさせる
といった対応が役立ちます。
一方で予防策としては、
- スケジュールや絵カードで「見通し」を持たせる
- 気持ちを表現できるツールを増やす
- 感覚に合った環境を整える
- 運動や遊びでエネルギーを発散させる
などを続けることで、少しずつ行動が落ち着いてくることがあります。
もちろん、すぐに変化が出ないことも多いですが、小さな工夫の積み重ねが大きな安心につながるんです。
支援を受けながら、安心して子育てを続けられる
そして何より大事なのは、ママが一人で抱え込まないことです。
発達支援センターや園・学校の先生、専門家、同じ悩みを持つママ仲間…。
そうしたサポートを得ることで、「私だけじゃない」と思えたり、具体的な対応方法が見つかったりします。
客観的に見ても、親が安心して子育てできる環境が整うと、子ども自身の成長にも良い影響を与えることが分かっています。
だからこそ、「助けを借りてもいい」「私も大切にしていい」と思えることが、子どもの笑顔にもつながっていきます。
自閉症のお子さんの他害行動に向き合うのは、確かに簡単なことではありません。
でも、子どものサインを理解し、少しずつ工夫を重ね、必要な支援を取り入れることで、親子の毎日はきっと今より楽になります。
以上【自閉症の子が叩く・つねるとき…他害の原因と正しい対処法をママ目線で解説!】でした

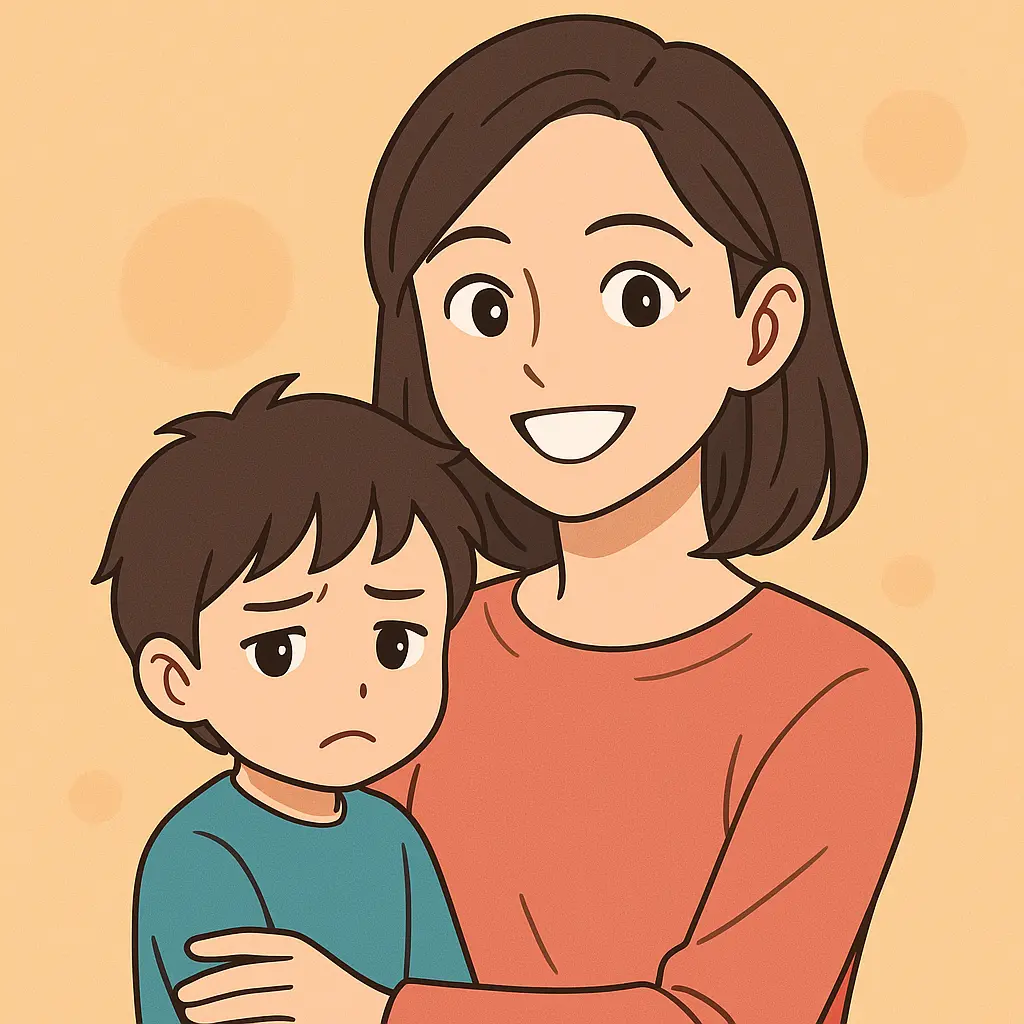









コメント