重度知的障害の子に多い「唾吐き行動」とは?
「うちの子、どうしてこんなに唾を吐いてしまうんだろう…」と戸惑ったことはありませんか?
実は、重度知的障害のある子どもには「唾吐き行動」がよく見られるんです。
どんな様子が見られるの?
- 家の中でも外出先でも、場所を選ばずに繰り返すことがある
- 遊んでいるときやテレビを見ているときなど、一見落ち着いているタイミングでも突然始まる
- 大人が注意しても、すぐにやめられない
こうした行動は「こだわり」や「感覚の特性」から起きていることが多く、本人も無意識に繰り返してしまうことがあるんです。
誤解されやすい「わざとやっている」の真実
周りの人から「しつけがなってないんじゃない?」とか「わざと人を困らせようとしているのでは?」と言われた経験があるママも少なくないと思います。
でも、唾吐きは“いたずら”や“反抗”ではありません。
- 感覚を楽しんでいる(口の中の感触や音を感じたい)
- ストレスや不安を表現している
- 言葉で気持ちを伝えられない代わりに行動で示している
このように、子どもなりの理由や背景が必ずある行動なんです。
だからこそ、ママが「悪いことをしている」と受け止めてしまうと、お子さんへの関わりがつらくなってしまいます。むしろ「この子にとって必要なサインなんだ」と理解すると、気持ちが少し軽くなるはずです。
唾吐き行動が起こる主な原因3つ
唾吐き行動には「ちゃんとした理由」が隠れていることが多いです。
ここでは特に多い原因を3つに分けて説明しますね。
1. 感覚刺激を求める(口・舌の感覚過敏/鈍麻)
まず多いのが、感覚の問題です。
重度知的障害のある子どもは、口や舌の感覚が 「強く感じすぎる(過敏)」 か、逆に 「あまり感じにくい(鈍麻)」 ことがあります。
- 感覚に敏感な子 → 口の中に唾がたまると気になって仕方なく、外に出してしまう
- 感覚に鈍い子 → 唾を吐くことでようやく「口の感覚」をはっきり感じられる
つまり、唾吐きは子どもなりの“感覚あそび”や“自己調整”になっていることがあるんです。
2. コミュニケーション手段としての唾吐き
次に考えられるのが、気持ちを伝える方法のひとつとして唾を吐いているケース。
言葉で「嫌だ」「やめて」「こっちを見て」と伝えられないとき、
- 大人がすぐに反応してくれる
- 強い刺激で注目を集められる
このように、唾吐きが 「すぐに気づいてもらえる手段」 になってしまうことがあります。
もちろんママからすると困る行動ですが、子どもにとっては“わかってほしいサイン”なんですね。
3. 不安やストレスの表出・環境の影響
最後に、ストレスや不安を吐き出している場合もあります。
- 環境の変化(知らない場所・人混み)
- 音や光などの刺激が強すぎる場所
- 気持ちが落ち着かないとき
こういう場面で唾を吐くことで、「安心したい」「落ち着きたい」というサインを出していることがあるんです。
また、家庭や学校などで大人が強く注意しすぎると、それ自体がストレスになって唾吐きが増えることも…。
つまり 環境の影響が大きい行動 でもあるんですね。

家庭でできる唾吐き対策の基本
唾吐き行動を見ていると、「なんとかやめさせたい!」と思うのがママの本音ですよね。
でも実は、無理に止めようとするよりも“環境を整えること”がとても大事なんです。ここでは、家庭で実践しやすい基本的な工夫をご紹介します。
無理にやめさせようとしない/安全を確保する
子どもが唾を吐くと、どうしても「やめなさい!」と強く言いたくなるものです。
でも、無理に止めさせようとすると逆にエスカレートしてしまうことも少なくありません。
大事なのは、まず安全を確保すること。
- 外出先ならタオルやティッシュをすぐ出せるようにしておく
- 家の中では吐いても拭きやすい場所を決めておく
- 周囲の人に事情を説明しておく
「完全にやめさせる」ではなく、“とりあえず安心できる環境を整える”ことから始めると、ママの心の負担も軽くなります。
注目しすぎない対応が大切
唾を吐いたとき、ついじっと見たり大きな声で注意したりしてしまいませんか?
でも実は、注目されることが子どもにとって「うれしいご褒美」になっている場合があるんです。
- 強く注意すると → 子どもは「ママがすぐ反応してくれる」と学んでしまう
- 見すぎると → 「注目してもらえた!」と行動が続きやすい
もちろん完全に無視するのは難しいですが、なるべく冷静に淡々と対応するのが効果的です。
「吐いてもあまり反応してくれないな」と感じると、自然に回数が減ることもあります。
日常生活で取り入れやすい工夫
唾吐きを減らすためには、日常の工夫も役立ちます。
- 代わりの行動を用意する:ストローで水を飲む、ガムや噛むおもちゃを使う
- 落ち着けるルーティンをつくる:決まった時間に好きな音楽を聴く、安心する遊びを取り入れる
- 「吐きやすい状況」を避ける:人混みや騒がしい場所を短時間にする
こうした工夫は、ママにとっても「次はこうしてみよう」と考えやすい方法になります。
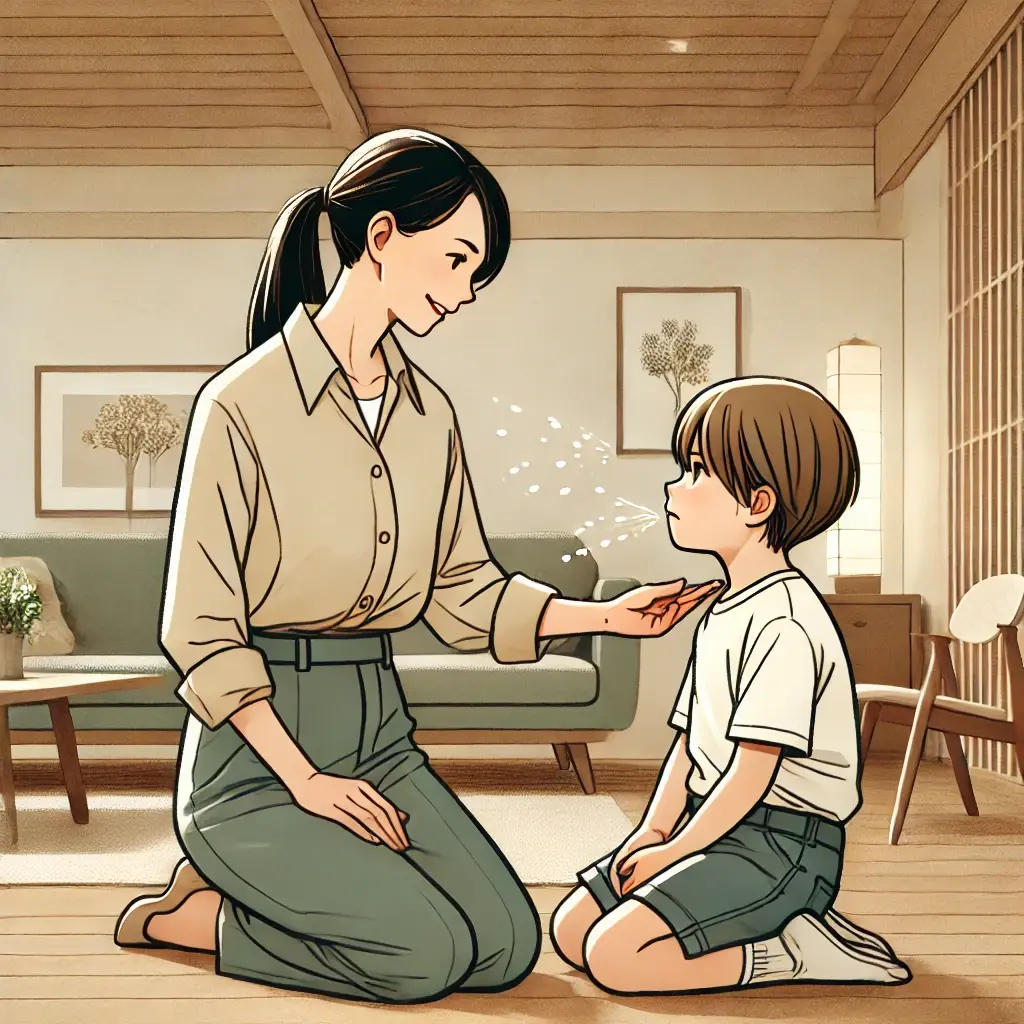
【実践編】ママがすぐ試せる唾吐き対策アイデア5選
「すぐにでもできる方法を知りたい!」というママに向けて、家庭で実践しやすい対策アイデアを5つ紹介します。
どれも特別な準備はほとんど不要で、日常の中に取り入れやすいものばかりです。
1. 声かけの工夫:短く肯定的に伝える
子どもが唾を吐いたとき、つい「ダメでしょ!」「やめなさい!」と強く言いたくなりますよね。
でも実は、長い言葉や否定的な言葉は子どもには届きにくいことが多いです。
- 「口はふこうね」
- 「お水のもうね」
このように、短く・シンプルで・肯定的な声かけを心がけると、子どもも理解しやすくなります。
叱るより「次にどうしたらいいか」を伝える方が、落ち着いて行動を切り替えやすいんです。
2. 代替行動グッズ:ストロー・ガム・噛むおもちゃ
唾を吐きたい気持ちの裏には「口や舌で何かを感じたい」という欲求が隠れていることがあります。
そこで役立つのが、代わりの行動を満たすグッズです。
- ストローでジュースや水を飲む
- キシリトールガムを噛む(嚥下が安全な子の場合)
- 噛むおもちゃやセンサリートイを使う
こうしたグッズは100均やネットでも手に入るので、気軽に取り入れられます。
「吐く」から「噛む・吸う」へと置き換える工夫がポイントです。
3. ルーティンを安定させる:安心できる流れづくり
子どもは予測できることに安心します。逆に予定が崩れると不安が高まり、唾吐きが増えることも。
だからこそ、毎日の流れをできるだけ一定に保つことが大切です。
- 起きる時間、食事の時間、寝る時間をそろえる
- 外出や予定の変更がある日は、絵カードや口頭で事前に伝える
こうすることで、「次に何があるか分からない不安」からくる唾吐きを防ぎやすくなります。
4. ストレスサインを先取り:事前に回避する工夫
「吐く直前にこんな表情してるな」「落ち着きがなくなると吐きやすいな」など、
ママなら気づける小さなサインがありますよね。
この“予兆”を先取りして行動すると、唾吐きを未然に防ぎやすくなります。
- 落ち着かない様子 → 好きな音楽を流す
- 外出前に不安そう → お気に入りのおもちゃを持たせる
- 人混みが苦手 → 出かける時間をずらす
子どもの「しんどい」を見抜く力は、毎日一緒に過ごすママだからこそ持っているものなんです。
5. 行動記録をつける:パターンを見つけて対策
「いつも夕方に多いな」「特定の場所で起きやすいな」など、行動にはパターンがあります。
そこで役立つのが、行動記録をつけること。
- いつ唾を吐いたか
- どんな状況だったか
- 直前にどんな出来事があったか
これを簡単にメモしていくだけで、原因やトリガーが見えてくるんです。
見つかったパターンをもとに、医師や支援者と共有すれば、より効果的な支援につながります。
学校・支援機関と連携するときのポイント
唾吐き行動は、家庭だけでなく学校や施設でも起こることがありますよね。
だからこそ、先生や支援員と同じ情報を共有し、みんなで一緒に取り組むことが大切です。ここでは、学校や支援機関とスムーズに連携するためのポイントを紹介します。
先生や支援員への伝え方
先生や支援員に伝えるときは、「困っていること」だけでなく「うまくいった工夫」もセットで伝えるのがおすすめです。
- ✕「最近、唾を吐いて困ってます」
- ○「最近唾を吐くことが多いですが、ストローを使うと落ち着くことがあります」
このように話すと、先生も対応しやすくなり、家庭と学校で一貫した支援ができます。
また、感情的になりやすい場面だからこそ、冷静で具体的な情報を意識して伝えると効果的です。
支援会議で伝えるべき観点
学校や療育センターでは、定期的に「支援会議」が開かれることがあります。
そのときに、以下のような観点を整理して伝えると話し合いが深まります。
- 頻度やパターン(どんなときに多い?時間帯は?)
- 家庭での工夫(代替グッズや声かけなど)
- 子どもが落ち着く場面(安心できる環境や人)
こうした情報を共有することで、「学校でも同じ工夫を取り入れてみよう」という流れが生まれやすくなります。
支援会議は「ママだけが頑張る場」ではなく、子どもを囲むチームで支えるための大切な時間なんですね。
医師・療育センターに相談する際のチェックリスト
専門機関に相談するときは、なるべく客観的なデータを持っていくことが大事です。
その場で「最近よく吐きます」と伝えるだけだと、医師も具体的なアドバイスがしづらいんです。
相談前にチェックしておくと役立つポイントは:
- いつ(時間帯・曜日)唾吐きが多いか
- どんな場面(外出・食事・遊び)で起きやすいか
- 直前にどんな出来事があったか
- 家庭で試した対策とその結果
この情報があると、医師や専門スタッフも「なるほど、こういう背景があるのか」と理解しやすくなるんです。
その結果、薬や訓練の調整など、より的確な支援につながります。
ママ自身の心を守る工夫
唾吐き行動が続くと、子どもだけでなくママの心もどんどん疲れてしまいますよね。
「私の育て方が悪いのかな」「ちゃんとできていないのかな」と自分を責めてしまうこともあると思います。
でも、まず大切なのはママ自身の心を守ることなんです。
「しつけ不足ではない」と理解することが第一歩
周囲の人から心ない言葉をかけられると、「やっぱり私のしつけが足りないのかも」と落ち込んでしまうことがありますよね。
でも、唾吐き行動は“しつけ不足”ではなく、発達特性からくるものです。
- 感覚の特性
- コミュニケーションの難しさ
- 不安やストレスの表出
こうした背景があるからこそ、行動として表れているんです。
だから「私が悪いのではない」と理解することが、ママの心を守る第一歩になります。
同じ悩みを持つママの声を紹介し安心感を与える
「うちだけじゃないんだ」と思えるだけで、気持ちはぐっと軽くなります。
実際、同じように唾吐きに悩むママはたくさんいます。
- 「外出先で何度も吐かれて、泣きたくなったことがある」
- 「でも先生に相談したら、少しずつ減ってきたよ」
- 「記録をつけるようにしたら、自分も落ち着いて関われるようになった」
こうした声を知ると、「私だけじゃない」という安心感が生まれます。
ママが孤独にならずにすむように、同じ悩みを共有できる仲間やコミュニティに出会えると心強いですね。
自分を責めないセルフケア習慣
ママが元気でいられることは、子どもにとっても大切なことです。
だからこそ、自分を責める代わりに「自分を大事にする時間」を意識的につくることが必要です。
- 10分だけでも好きな音楽を聴く
- 甘いお菓子やコーヒーでリラックスする
- 日記やSNSで気持ちを書き出す
- 信頼できる人に愚痴を話す
小さなことでもOK。「自分を大切にする練習」を重ねることで、ママの気持ちが安定していきます。
まとめ|唾吐き行動は理解と工夫で変わる
ここまで、重度知的障害の子どもに多い唾吐き行動について、原因や家庭でできる工夫、支援機関との連携方法などをお伝えしてきました。
改めて大切なのは、「原因を知る → 対策する → 支援につなげる」という流れです。
- 原因を知る:感覚の特性なのか、不安やストレスなのか、まず背景を理解する
- 対策する:家庭でできる工夫や代替手段を取り入れてみる
- 支援につなげる:学校や専門機関と情報を共有し、チームで取り組む
このサイクルを繰り返すことで、子どもの行動は少しずつ落ち着いていきます。
ママに伝えたいこと
唾吐き行動が続くと、つい「私の育て方が悪いのかも」と感じてしまうこともありますよね。
でも、ママが一人で抱え込む必要はありません。
- 同じように悩んでいるママがたくさんいること
- 学校や支援者に相談できること
- そして、子ども自身にも必ず“できるようになる力”があること
子どもの唾吐き行動に向き合うママのがんばりは、必ず子どもに伝わっています。
小さな一歩を積み重ねることが、子どもの安心や成長につながっていきますよ。
以上【重度知的障害の子の唾吐き行動|原因と家庭でできる対策・支援方法】でした。











コメント