「毎日“早くして”って声をかけても、なかなか動いてくれない…。子育て中、そんな場面に何度も出くわしていませんか?特性のある子どもとの関わりでは、こちらの思いがうまく伝わらず、“なんで言うことを聞いてくれないの?”と悩むことも多いですよね。
でも実は、それは反抗ではなく、“わかりにくさ”や“安心のなさ”が原因かもしれません。
この記事では、子どもとの関係をより良くするためのNG対応とOK対応のポイントをわかりやすく解説します。
子どもに気持ちが伝わる関わり方、知りたくありませんか?
読んだその日から使えるヒントがきっと見つかりますよ。」
「どうして言うこと聞かないの?」と悩む前に知っておきたいこと
「何回言ったらわかるの?」「どうしてこの子は言うことを聞いてくれないの?」
こんなふうに思ったこと、ありませんか?
自閉症スペクトラム(ASD)の子どもを育てていると、日常のちょっとした指示やお願いがスムーズに通らないことって、正直よくありますよね。
例えば、「ごはんだからおもちゃ片付けて」と言っても動かない。時間になっても着替えない。お風呂に行こうとしても逃げていく。親としては困る場面でも、本人には本人なりの理由や感じ方があるんです。
でも、ついイライラしてしまったり、「うちの育て方が悪いのかな…」なんて自分を責めてしまったりする方も多いはず。
だけど、安心してください。それって親御さんのせいじゃないんです。
自閉症スペクトラムの子どもは、コミュニケーションのスタイルや感じ方が“少し違うだけ”。その違いを理解していないと、「言うことを聞かない=わがまま」「反抗してる」と受け取ってしまいがち。でも実はそこには、本人が困っている“サイン”や“理由”が隠れていることがよくあるんです。
本記事では、「言うことを聞かない」と感じたときにやってしまいがちなNG対応と、子どもの特性に寄り添ったOK対応を、わかりやすく紹介していきます。
また、家庭でできる工夫や、親が心をラクにするための考え方、使える支援ツールや相談先などもあわせてご紹介。
子どもの行動の“背景”を知ることで、「聞いてくれない…」という悩みが、きっと「なるほど、そういうことだったのか」に変わるはずです。
「できないこと」に注目するのではなく、「できる形を一緒に探す」――そんな視点を持って、一緒に考えていきましょう!
言うことを聞かないのは“反抗”じゃない!自閉症スペクトラムの子どもの特性とは
自閉症スペクトラムの子どもが「言うことを聞かない」と感じるとき、決して「反抗」や「わがまま」だけが原因ではありません。その行動の背景には、発達や認知の違いからくる、数々の要因が複雑に絡み合っています。ここでは、多角的かつ客観的な視点から、なぜそのような行動が見られるのかを解説します。子どもたちが特別なスタイルで世界を感じ、反応しているという事実を理解すれば、より適切な対応法が見えてくるはずです。
曖昧な指示は伝わらない?“わかりづらさ”の壁
自閉症スペクトラムの子どもたちは、具体的で明確な情報を必要としていることが多いです。たとえば、「すぐに片付けなさい」という指示は、大人には十分伝わっているように感じても、子どもにとっては抽象的すぎる場合があります。
- 抽象的な言葉やニュアンスが理解の障壁となり、「何をすれば良いのか」が曖昧になってしまうのです。
- 具体例として、「おもちゃを箱に入れてね」といった、イメージしやすい説明に変えることで、子どもも行動に移しやすくなります。
このように、「わかりづらさの壁」を乗り越えるためには、視覚的なサポートや、段階的な指示の提示が鍵となります。子どもが自分のペースで情報を処理できるよう配慮することが大切です。
環境の変化や音に敏感!行動の裏にある“不安”や“こだわり”
自閉症スペクトラムの子どもは、周囲の環境から非常に敏感な影響を受けることがよくあります。ちょっとした音や光の変化、普段と違うルーチンの中で、「不安」や「こだわり」が強く表れることがあります。
- 環境の急な変化:例えば、普段とは違う場所や、家庭内で突然の予定変更があると、子どもは戸惑いや不安を感じることが多いです。
- 感覚過敏:大きな音や明るすぎる光、触感の違いなどが、子どものストレスの原因となる場合があります。
このような状況では、子どもが「言うことを聞かない」と見えるのは、自分の安心感を確保するための“自衛行動”かもしれないのです。環境を整え、安心できる空間を作り出すことや、あらかじめ変化に慣れるための準備をすることで、不安を軽減する工夫が求められます。
怒ってる?無視してる?実は本人も“困ってる”だけかも
周囲からは「怒っている」や「わざと無視している」と受け取られる行動も、実は子ども自身がどう対処していいかわからず、深い困惑や不安を感じているサインである場合がほとんどです。
- 感情のコントロールが難しい:自閉症スペクトラムの子どもは、自分の感情をうまく表現したり、コントロールしたりするのが難しい場合があります。
- コミュニケーションの苦手意識:そのため、指示に対する反応が遅れたり、上手く返答できずに「無視している」ように見えてしまうことがあります。
- 内面のストレス:実は、何度も試みたけれども自分なりにどう行動して良いかわからず、戸惑っている状態かもしれません。
こうした行動を単なる「反抗」と決めつけずに、子どもが何を感じ、どう困っているのかを読み解く努力が必要です。支援者としては、「困っている」というサインに気づき、安心感を与えるためのサポートに目を向けることが大切です。
やってしまいがち!逆効果なNG対応5選とは?
「もう限界!」「どうして言うことを聞いてくれないの…?」
そんなふうに感じたとき、つい強めに対応してしまうことってありますよね。子育てって、毎日が本気勝負ですし、感情が揺さぶられるのも当然です。
でも、自閉症スペクトラムの子どもには、その場しのぎの“強い対応”が逆効果になることがよくあります。
むしろ、子どもが混乱したり、親子の信頼関係が崩れたりして、状況が悪化することも…。
ここでは、ついやってしまいがちな「NG対応」を5つピックアップし、なぜそれが逆効果になるのかを、わかりやすく解説します。
怒鳴る・大声はNG!「伝えたいこと」が届かなくなる
イライラがピークに達すると、つい声を荒げてしまう…。これは、誰にでもあることですが、自閉症スペクトラムの子にとって「大きな声」は脅威やストレスの原因になってしまうことが多いです。
特に、聴覚過敏をもっている子どもにとっては、怒鳴られるだけでパニックになることも。
また、「怒られていること」には気づいても、「どうして怒られているか」が理解できないケースもあるんです。
つまり、怒鳴ることで親の意図は届かず、恐怖や混乱だけが残るということも…。
大切なのは、冷静に、シンプルな言葉で、必要なことだけを伝えることなんです。
「なんでできないの?」は自信を失わせる一言
これも、つい言ってしまうセリフのひとつですよね。でも実はこれ、子どもの心に深く突き刺さる一言なんです。
自閉症スペクトラムの子どもは、「できない」ことにもちゃんと理由があります。たとえば、
- 指示が難しくて理解できていない
- 環境の変化に対応できない
- 気持ちをうまく切り替えられない など
そういった背景を知らずに「なんでできないの?」と言われてしまうと、自分はダメなんだ…という思いを強めてしまいます。
できない理由を責めるのではなく、「どうすればできるか」を一緒に探していく姿勢が大切です。
力づくで従わせても、反発しか生まれない
「もう、いいからやって!」と手を引っ張ったり、無理に動かしたり…。
一見、すぐ解決したように見えるかもしれませんが、これは“強制”であって、理解や納得にはつながっていません。
強制的に行動させられると、子どもは「嫌なことをされた」と記憶し、その場面を避けたり、親との距離を取るようになってしまうことも。
特に自閉症スペクトラムの子どもは、「自分のペースを大切にしたい」という強い感覚を持っていることが多いので、無理に動かされることでストレスが爆発してしまうこともあります。
対応のコツは、子どもが納得できる形で選ばせる・誘導すること。力ではなく、信頼で行動を引き出していくのがベストです。
他の子と比べるほど、やる気は失われる
「○○くんはもうできてるのに…」「お姉ちゃんはちゃんとしてたよ」
このような“比較の言葉”は、子どもにとってプレッシャーでしかありません。
自閉症スペクトラムの子は、他の子と同じようなペースや方法で成長しないことがごく自然です。
それなのに「他の子はできてる」と言われると、「じゃあ自分はダメなんだ」と感じてしまいます。
しかも、子どもによってはその言葉を“否定”や“拒絶”として捉えてしまうこともあるので、注意が必要です。
親として意識したいのは、「昨日のその子」と比べて成長を見つけること。少しでも前進していれば、それは立派な進歩なんです。
わざと無視すると、信頼関係が一気に崩れる
「もう知らない」「話しかけても無視しておこう」――
言うことを聞かない態度にイライラして、わざと距離を取ってしまう…。そんなときもあるかもしれません。
でも、自閉症スペクトラムの子どもにとって、“親からの反応がない”=“自分は見捨てられた”と感じやすい傾向があります。
その結果、安心感を失い、不安からくる行動がさらに増してしまうことも。
もちろん、冷静になるために少し距離を取るのは大切。でもそれは、「無視する」のではなく「落ち着いたら話そうね」と一言添えるだけで、印象はまったく違います。
無視するのは良くない言動のみで、子どもの存在そのものを無視するということではありません。
信頼関係は、日々のやりとりの積み重ね。一時の感情で壊さないためにも、“関係を切らない対応”を意識することが大切です。
「伝わる」ってこういうこと!自閉症スペクトラムの子へのOK対応5選
「言ったのに動いてくれない…」という場面、日常的によくありますよね。
でもそれって、“言ったつもり”で終わってしまっていて、実は伝わっていないだけかもしれません。
自閉症スペクトラムの子どもたちは、言葉だけの指示や曖昧な表現では理解が難しいことが多いです。
でも、ちょっとした伝え方の工夫で、スッと行動してくれたり、「わかってくれた」と笑顔になったりする瞬間がぐっと増えます。
ここでは、毎日の生活にすぐ取り入れられる、子どもに“伝わる”OK対応のコツを5つご紹介します!
「具体的に」「視覚で」伝えるとスッと行動できる!
自閉症スペクトラムの子どもにとって、「言葉だけの指示」はとても抽象的。
例えば、「ちゃんとして」「片付けて」などの曖昧な言い方では、“何をどうすればいいか”がイメージできないことも多いんです。
そこで効果的なのが、具体的な言葉+視覚情報!
たとえば、「おもちゃを箱に入れてね」と、具体的な行動を示したり、写真や絵カードを使って「これをこうしてね」と視覚的に示すことで、子どもは理解しやすくなります。
また、タイマーやスケジュールボードを使って「見える形」で予定を伝えるのも◎。
“視覚で理解する”というルートを使うことで、情報処理がしやすくなり、行動につながりやすくなるんです。
選ばせることで納得感UP!“選択肢のある声かけ”が効く
「これやって!」「今すぐ片付けて!」と一方的に指示されると、大人だってちょっと反発したくなりますよね。
それは子どもも同じ。特に自閉症スペクトラムの子どもは、自分でコントロールできる感覚=“見通し”や“安心感”をとても大事にします。
そこでおすすめなのが、“選ばせる”声かけ。
例えば、「お風呂は今入る?それとも10分後にする?」や、「赤い服と青い服、どっち着る?」といった選択肢を与えることで、「自分で選んだ」という納得感が得られ、行動に移りやすくなります。
重要なのは、どちらを選んでも親がOKな選択肢を用意すること。
子どもの“主体性”を引き出す関わり方、ぜひ試してみてください。
「ダメ」じゃなくて「こうしてみよう」で肯定的に伝える
「走らないで!」「触らないで!」「違うでしょ!」
つい注意するときって、「ダメ」「~しないで」と否定形で言ってしまいがち。でも、否定の言葉ばかりだと、子どもは“どうすればいいのか”がわからなくなってしまいます。
そこでポイントになるのが、“肯定的な伝え方”。
例えば、「走らないで」ではなく「歩こうね」、「触らないで」ではなく「手はここに置こうね」など、“してほしい行動”を具体的に伝えると、子どもは理解しやすくなります。
否定され続けると、自己肯定感も下がってしまいます。
だからこそ、できる行動に目を向けて言葉を選ぶことが大切なんです。
毎日の“お決まりパターン”が子どもに安心感を与える
「次、何するの?」「どうなるの?」
見通しが立たないことに強い不安を感じるのが、自閉症スペクトラムの子どもの特性のひとつ。
逆に言えば、“毎日決まった流れ”があると、それだけで安心できるんです。
たとえば、「起きる→顔を洗う→ごはん→着替える」など、決まった順番や流れ(ルーティン)を定着させることで、行動へのハードルがグッと下がります。
さらに、スケジュール表や絵カードを使って“見える化”すると、見通しがより明確になり、不安が減ります。
子どもにとって“いつもと同じ”は、心の安全基地。
ルーティンの力、あなどれません!
できたらすぐ褒める!タイミングがカギになる理由とは?
褒めるって大事、とはよく言われますが、自閉症スペクトラムの子にとっては「褒め方」と「タイミング」が特に重要なんです。
ポイントは、「できた瞬間」に短く、具体的に褒めること。
たとえば、「自分で靴はけたね!」「“お願いします”って言えたね!」など、何がよかったのかをはっきり伝えると、子どもも自分の行動を理解しやすくなります。
逆に、時間が経ってから「さっきのあれ、よかったよ」と言っても、子どもは何のことかわからず、ピンと来ないことも…。
褒めることで、「こうすればいいんだ」という成功体験が積み重なり、自信や自発性が育っていきます。
行動が変わるって、実はこの積み重ねなんです。
家庭でできる!子どもの行動を引き出すちょっとしたコツ
自閉症スペクトラムの子どもとの毎日は、「どうしたら動いてくれるのかな?」「やらせたいことが全然進まない…」という悩みの連続ですよね。
でも実は、ちょっとした工夫で子どもの行動がスムーズに引き出せることも多いんです。
しかも、その工夫は特別なものじゃなくて、家庭で無理なくできるものばかり。
ここでは、毎日の生活で“ちょっとやってみたら変わった!”と実感しやすいコツを3つご紹介します。
「まずはこれだけ!」の小さな目標設定が成功のカギ
「片付けて!」「着替えて!」「全部できてないでしょ!」
ついつい、あれもこれもやってほしくて欲張っちゃう気持ち、よ〜くわかります。でも、一度に複数のことを求められると、子どもは混乱してしまうんです。
特に自閉症スペクトラムの子どもは、物事を順序立てて処理するのが苦手なことも多く、ハードルが高すぎると“できない”から始められないということがよくあります。
そんな時に使えるのが、“スモールステップ”という考え方。
たとえば、「ランドセル全部片付けて!」ではなく、
「まずはプリントを机の上に出そうね」→「次に連絡帳を出そうか」…と、一つひとつの行動を小さく分けて提示してあげるだけで、ぐんとやりやすくなります。
“できた”を積み重ねることで、やる気や自信も育ちやすくなるんです。
苦手を“好き”でサンドする!メリハリある流れでスムーズに
「着替えは嫌だけど、ゲームは大好き」
そんな子どもの“好き”をうまく活用するのが、このコツ!
自閉症スペクトラムの子どもにとって、苦手なことや嫌なことへの切り替えは大きなストレス。
そこで使えるのが、“サンドイッチ法”と呼ばれる関わり方です。
具体的には、
「好きなこと → 苦手なこと → また好きなこと」という流れで活動を組むイメージ。
たとえば、
「ブロック遊び → 着替え → 絵本読み聞かせ」など。
この流れを作ることで、「好きなこと」の安心感が「苦手なこと」のハードルを下げてくれるんです。
さらに、「着替えができたら絵本にしようね!」と伝えることで、見通しも持ちやすくなり、スムーズに行動へつながることが増えてきますよ。
見える化で達成感UP!カレンダーや行動記録を活用しよう
目に見えない「できた」「がんばった」は、子どもにとって実感しにくいもの。
だからこそ、“見える化”の工夫がとっても効果的なんです。
たとえば、
- カレンダーに「できたシール」を貼る
- 一日の流れをマグネットで表示する
- 行動記録を一緒につけて振り返る など
こうした視覚的なフィードバックがあると、子どもは「自分はできた!」と目で見て確認できるので、やる気や自己肯定感につながりやすくなります。
特に自閉症スペクトラムの子どもは、「できた」「がんばった」を頭の中だけで整理するのが難しいことも多いため、“結果を見せる”ことがとても有効です。
「できたね!」と一緒に喜びながら見返すだけで、“次もがんばろう”という前向きな気持ちが自然と育っていきますよ。
もう自分を責めないで!親が知っておきたい心の持ち方
「私の育て方が悪いのかな…」「もっと上手に声かけできていれば…」
子育ての中で、そんなふうに自分を責めてしまう瞬間、ありますよね。特に、自閉症スペクトラムの子どもとの毎日は予測できないことの連続で、「なんでこうなるの…」と落ち込んでしまうことも。
でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。
あなたは、毎日すごく頑張ってるんです。
ここでは、子どもに関わるうえで親としての心の持ち方を整えるヒントをお伝えします。自分を大切にしながら、子どもと向き合っていくための視点、きっと見つかるはずです。
「育て方のせいじゃない」…まずはここを理解しよう
まず最初に伝えたいこと、それは――
自閉症スペクトラムは「親の育て方が原因でなるものではありません」。
これは、医療・発達・心理のあらゆる分野で明確に言われていること。
それでも、日常の中でうまくいかないことが続くと、「やっぱり私の声かけが悪かったのかも…」「ちゃんとしつけなかったから…」なんて、つい思ってしまいますよね。
でも、子どもの行動には“脳の特性”が関係しているということを、まずは冷静に受け止めることがとても大切です。
もちろん、親の関わり方で“やりやすく”なる部分はたくさんあります。でもそれは「責任」ではなく「支援の方法」。
「親のせいじゃない」――そう思えるだけで、心がふっと軽くなる瞬間がきっとあります。
“困った行動”は“助けて”のサインかも
「癇癪を起こす」「言うことを聞かない」「落ち着きがない」――
そんな行動を見ると、大人側はつい“困った子”と感じてしまいがちです。
でも、視点を少し変えてみると、それは子どもからの“困っているよ”というサインかもしれません。
たとえば…
- 感覚がつらくてパニックになっている
- 言葉で表現できなくて、行動で伝えようとしている
- 予定変更に対応できなくて、どうしたらいいかわからない
そう考えると、「困った子」ではなく「困っている子」という理解に変わりますよね。
子どもが「助けて」と言えない代わりに起こしている行動かもしれない――そう思えたとき、対応の仕方も、気持ちの余裕もぐっと変わってくるはずです。
ひとりで頑張らなくていい!頼れる支援先に相談しよう
子育てって、時に「孤独との戦い」でもありますよね。
特に発達に特性がある子どもを育てていると、「相談してもわかってもらえないんじゃないか」「親としてしっかりしないと」って、つい一人で抱え込んでしまいがち。
でも、覚えておいてほしいのは、
ひとりで頑張る必要はまったくない、ということ。
最近では、各自治体にある「発達支援センター」や「子育て相談窓口」、療育施設、児童発達支援事業所、保育士・臨床心理士など、頼れる専門機関や人がたくさんあります。
また、同じような立場のママやパパとつながれる親の会やオンラインコミュニティも心強い存在。
「わかってくれる人がいる」「ひとりじゃない」って感じられるだけでも、心の負担はぐっと軽くなります。
そして何より、“親が安心できること”が、子どもにとってもいちばんの安心につながります。
知って得する!支援機関とおすすめサポートツール
「毎日が手探り…」「もっと楽になる方法があれば知りたい」
そんなふうに感じたとき、ちょっと立ち止まって思い出してほしいのが、“支援はすぐそばにある”ということ。
自閉症スペクトラムの子どもとの暮らしでは、「どうすればもっとスムーズに過ごせるんだろう?」という小さな悩みの連続。でも、その悩みをひとりで抱え込まなくてもいいんです。
ここでは、自治体などの相談窓口や療育機関、そして家庭で役立つ便利グッズやアプリをご紹介します。知っているだけで、子育ての視界がぐんとひらけるはずです!
市区町村でも相談できる!療育・発達支援の活用術
「療育って病院に行かないとダメなんでしょ?」
そう思っている方も多いかもしれませんが、実はお住まいの市区町村にも無料で相談できる窓口があるのをご存じですか?
たとえば…
- 子育て支援センター
- 発達支援センター(児童発達支援センター)
- 福祉課や保健センター
これらの機関では、子どもの発達に関する悩みや不安を気軽に相談できる場を設けており、必要に応じて療育サービスや専門機関につないでくれることもあります。
しかも、療育は「困っている子」だけが通う場所ではなく、「より良い関わり方を学べる場所」。
「うちの子、ちょっと気になるかも…?」という段階でも、早めに相談しておくと、支援の選択肢が広がりやすくなるんです。
また、地域によっては親向けの講座や交流会、発達支援グループなども実施されていることがあるので、情報収集だけでも価値あり!です。
家庭で使える!タイマー・アプリ・視覚支援グッズ紹介
「支援グッズって特別なものが必要?」
いえいえ、そんなことありません!
家庭にあるものや、100円ショップ・アプリストアで手に入るものでも、自閉症スペクトラムの子どもにとってすごく役立つアイテムはたくさんあります。
たとえば…
■ タイマー
→ 「あと5分で終わりだよ」が“見える化”されるだけで、子どもは切り替えやすくなります。砂時計やキッチンタイマーでもOK!
■ スケジュールボード
→ 朝の支度や帰宅後の流れをイラストや写真で見せると、「次に何をすればいいか」が明確になり、不安が減ります。
■ ピクトグラム・絵カード
→ 言葉だけで伝えづらい場面では、視覚情報で補うと理解度がグンと上がります。無料でダウンロードできる素材も豊富。
■ アプリ
→ スケジュール管理、気持ちの見える化、お片付けタイマーなど、発達支援向けのアプリがたくさん登場しています。
※例:「ルクミータイマー」「できたよ!」「こどもカレンダー」など
こうしたツールを使うことで、“わからない”を減らし、“見える安心”を増やすことができるんです。
「もっと早く知っていれば…」と思うような便利な支援やグッズ、意外とたくさんあるんです。
知っておくことは、子育ての引き出しを増やすこと。そしてそれは、親の心の余裕にも直結します。
無理なく取り入れられるものから、ぜひ試してみてくださいね!
「言うこと聞かない」を変えるのは“正しい関わり方”だった!
子どもが言うことを聞いてくれないと、つい「どうして?」「もう限界…」って思っちゃいますよね。
でもここまで読んでくださったあなたなら、きっと気づいたはずです。
「言うことを聞かない」ように見える行動の裏には、“伝わっていない”とか“困っている”という理由があるということ。
そして、それを理解したうえで関わり方を変えてみるだけで、子どもの反応が少しずつ変わってくるということも。
大事なのは、「どうやって言うことを聞かせるか」ではなく、
「どうすれば伝わるか」「どうすれば子どもが安心して動けるか」を考える視点なんです。
もちろん、うまくいかない日もあるし、感情的になってしまう瞬間もあると思います。
でも、そんなときも「よし、また明日やってみよう」と思えるだけで十分です。
親が100点満点じゃなくても、関係は築いていけるんですから。
そして忘れないでほしいのは――
あなたはもう、すでにたくさん頑張っているということ。
その頑張りをちょっとだけ“方向修正”してあげることで、子どもも親も、もっとラクに、もっと笑顔で過ごせる毎日が待っているかもしれません。
さいごに
「言うことを聞かない…」と感じる子どもの行動には、実は“反抗”ではなく、伝わりにくさや不安、見通しのなさといった特性のサインが隠れていることがあります。
この記事ではそんな背景をふまえて、
- やってしまいがちなNG対応と、その理由
- 子どもが安心して行動できるOK対応のコツ
- 家庭でできる小さな工夫や支援ツールの紹介
- 支援機関とのつながり方や親の心の整え方
など、今日から取り入れられるヒントをたっぷりお届けしました。
子育ては毎日の積み重ね。うまくいかない日があって当たり前です。
でも、関わり方を少し変えるだけで、子どもとの関係はぐっとラクになる可能性があります。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!




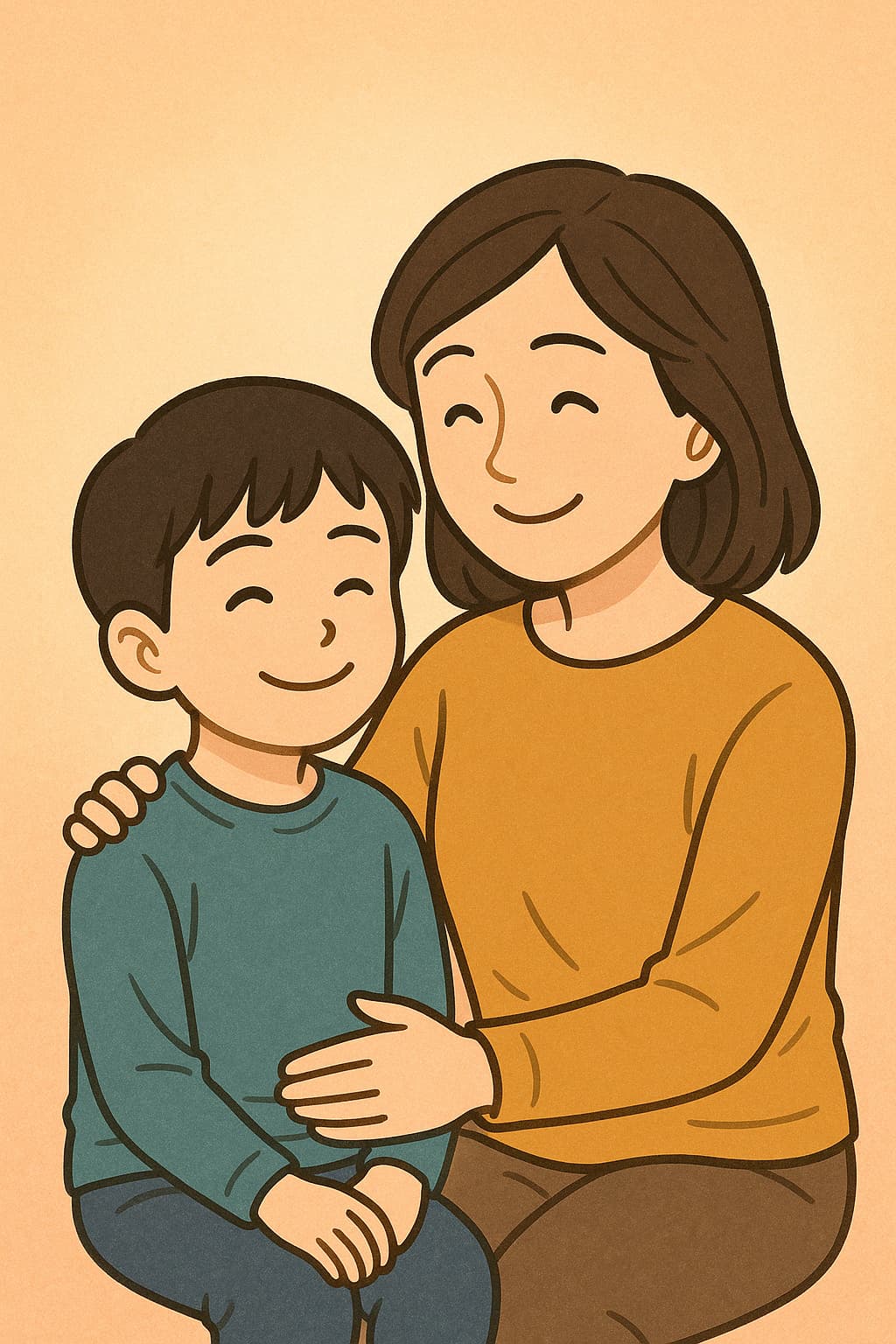
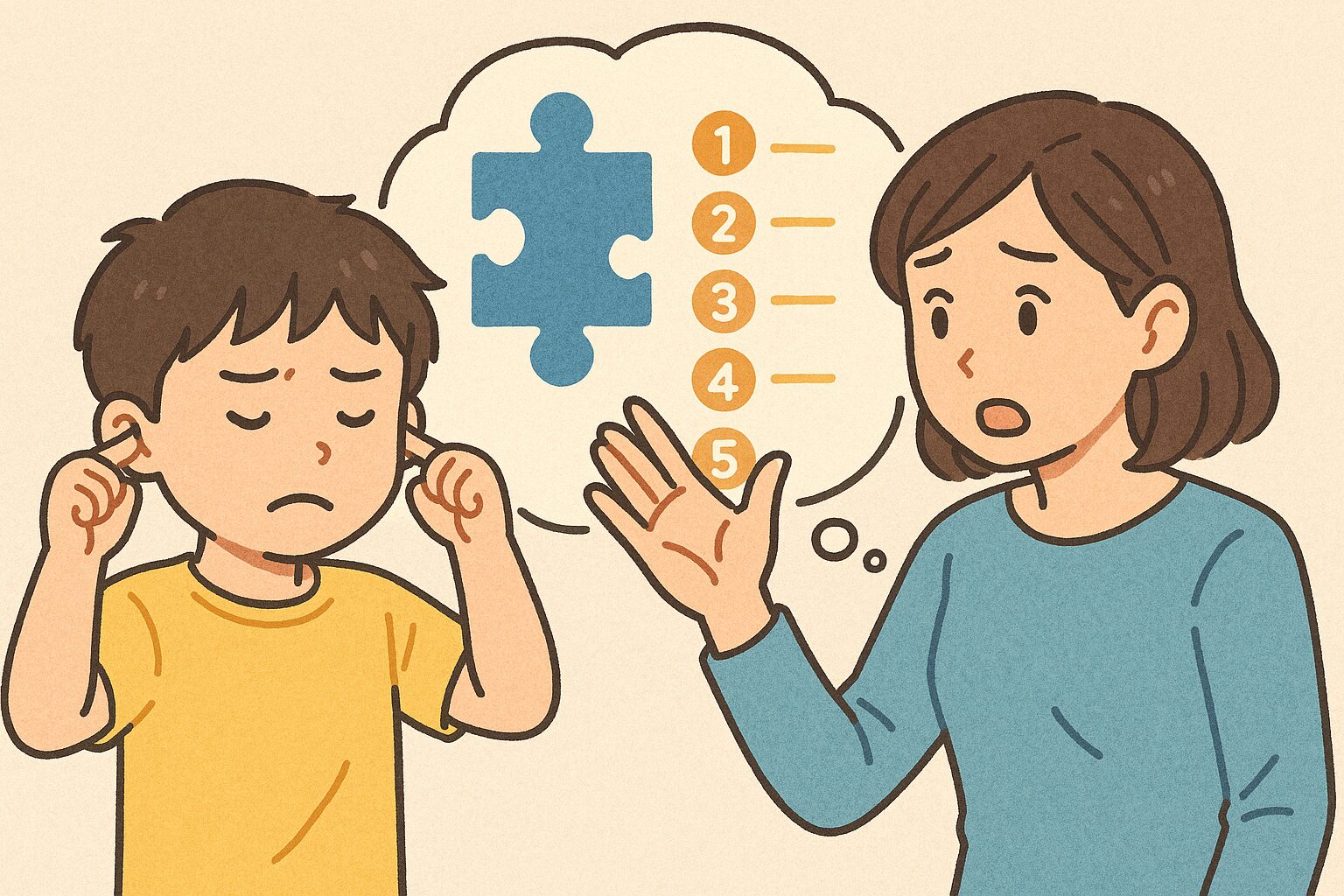
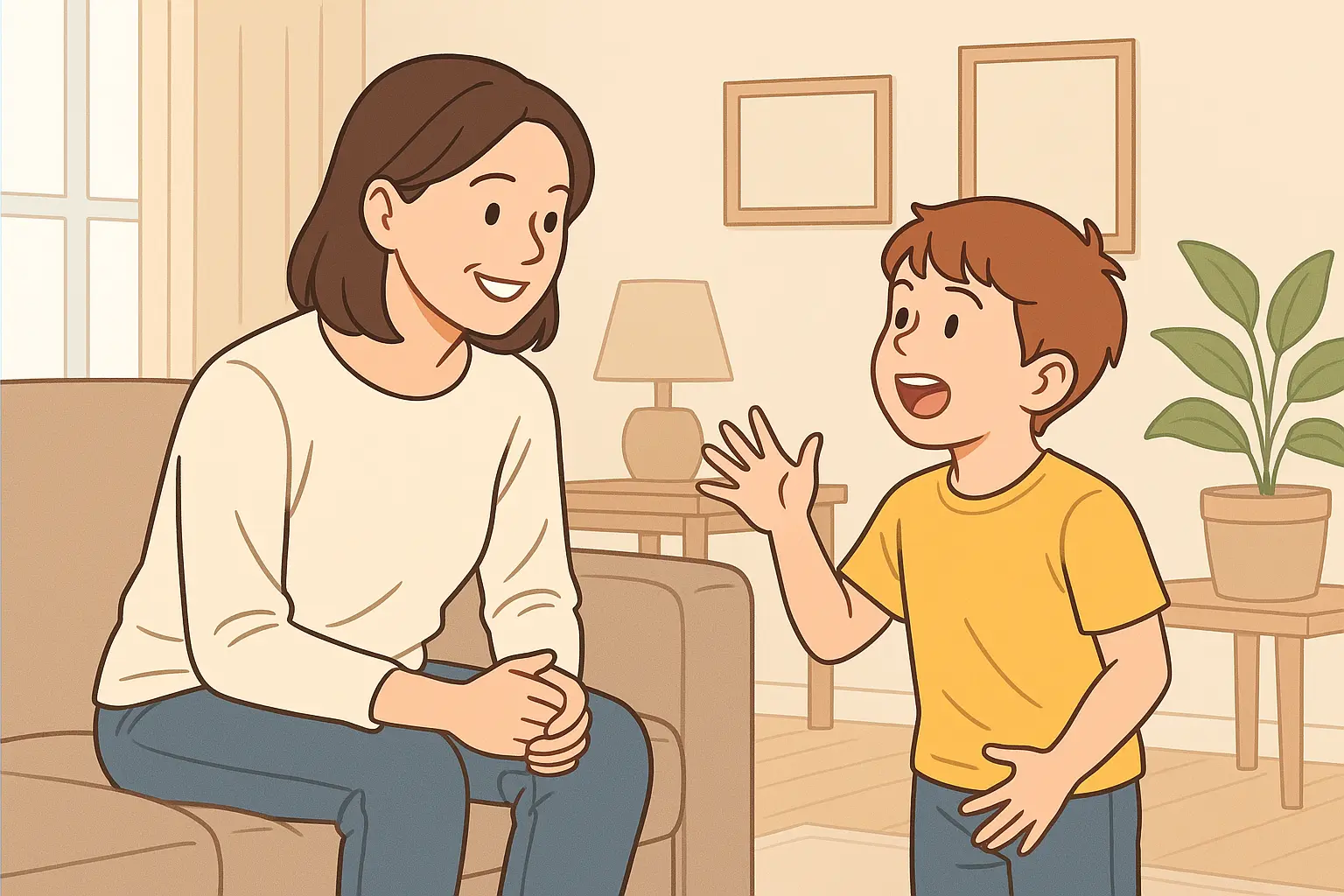



コメント