もう限界?なぜアスペルガーの人から執着されてしまうのか
「なんでこんなに距離が近いんだろう…」
そう感じたこと、ありませんか? アスペルガー症候群(ASD)の人は、人との距離感の取り方に独特の傾向があります。もちろん、それは本人の性格のせいではなく、発達特性からくる認知の違いによるものです。
彼らは「人と仲良くなりたい」「信頼できる人を大切にしたい」という気持ちがとても強く、それが行動として表れると、周囲から見ると“執着”のように感じられることがあります。ここでいう執着とは、単なる好意や興味を超えて、生活や時間の多くを相手とのやり取りに費やす状態を指します。
特性からくる“距離感のズレ”と周囲のしんどさの正体
ASDの人は、社会的な距離感の「グラデーション」を理解するのが少し苦手な場合があります。例えば、職場や学校で「知り合い」「友達」「親友」という段階的な関係の違いを、感覚的にはっきりと認識できないことがあります。
そのため、一度「この人は安心できる」と思うと、その人に対して急に親密な距離感で接するようになることがあります。本人にとっては自然な行動でも、相手からすると「いきなり距離が近すぎる」と感じてしまうことがあるんですね。
しかもこの距離感のズレは、相手に悪意があるわけではないので、指摘してもなかなか自覚しにくいという特徴があります。これが、周囲がじわじわと疲れてしまう大きな原因のひとつです。
実際によくある「しんどい行動」パターンとは?
では、どんな行動が“しんどい”と感じられやすいのでしょうか。たとえば…
- 毎日、何度もLINEやSNSのメッセージが届く(しかも即レスを求められる)
- 急に会いたいと連絡が来る、予定が合わなくても何度も誘われる
- 会話が一方的で、話題が相手の興味に偏っている
- 断っても、「じゃあいつならいい?」と食い下がる
- SNSの投稿に毎回コメントや“いいね”を欠かさない
これらは、一見するとただの「熱心な友人」にも見えますが、頻度や強さが過剰になると、受け取る側は息苦しさや疲労感を覚えるようになります。
無意識のうちに関係がこじれるメカニズム
厄介なのは、この執着的な行動がほぼ無意識に行われているという点です。本人は「迷惑をかけよう」と思っているわけではなく、むしろ「仲良くなれて嬉しい」「もっとつながっていたい」というポジティブな動機から行動しているケースがほとんど。
ところが、受け取る側は「プレッシャーを感じる」「自分の時間が奪われる」と感じてしまい、だんだんと心の中に距離を置きたくなる感情が芽生えます。そして、その気持ちが態度に出ると、今度は相手が「嫌われたのでは」と不安になり、さらに接触を強める——この悪循環が関係のこじれを生むのです。
こうしたメカニズムを理解しておくと、「なぜこうなってしまったのか」が冷静に整理でき、今後の距離の取り方や対応方法を考えやすくなります。
※まずは「なぜ執着が起きるのか?」という背景を理解すると、距離感づくりがスムーズになりますよ。
→ 自閉症の大人が特定の人に執着する理由と支援の考え方はこちら
アスペルガー特性と「執着」の深い関係
アスペルガー症候群(ASD)の人が見せる“執着”には、特有の認知や感情の働きが関係しています。ここを理解しないまま「困った行動」とだけ捉えてしまうと、対応が一方的になったり、相手を無駄に傷つけたりすることもあります。逆に、この背景を知っておくことで、「ああ、こういう理由があったんだ」と冷静に受け止められるようになるんです。
こだわりや限定的な興味が人に向かう理由
ASDの大きな特徴のひとつが、興味や関心の範囲が狭く深くなりやすいこと。趣味や物事に強くのめり込み、時間や労力を惜しまず集中する傾向があります。この「限定的な興味」が、人間関係にも向くことがあります。
例えば、職場や学校で「この人といると安心できる」と感じた瞬間、その相手が“特別な存在”として頭の中で位置づけられるんです。そして、その安心感を求めて、同じ人と繰り返し接触しようとします。
物事へのこだわりが「人へのこだわり」にシフトすることで、日常的に相手を意識する時間が増え、結果として周囲から“執着”に見える行動が増えるわけです。
「仲良くなったら離れられない」心理構造
もうひとつの背景には、信頼関係の構築に時間がかかる特性があります。ASDの人は、初対面の人や関係が浅い相手には警戒心を持つことが多いですが、あるラインを越えて「安心できる」と感じた瞬間、その人との関係を強く維持しようとするんですね。
これは、長い時間をかけてやっと築いた信頼を失いたくないという気持ちの表れでもあります。だからこそ、一度仲良くなると「もっと関係を深めたい」「離れたくない」という行動が強くなるんです。
客観的に見ると、これは“依存”というよりも「安心できる人を大事にする」本能的な行動。ただし、その強さが過剰になると、相手にとっては負担になってしまう、というすれ違いが生まれます。
曖昧な関係の理解が難しいことで起きる誤解
ASDの特性として、人間関係の曖昧な境界線を理解するのが苦手という点も挙げられます。例えば、「知り合い」と「友達」の違い、「友達」と「親友」の境界、仕事上の付き合いとプライベートの距離感など、社会的な“暗黙のルール”が感覚的にわかりにくいことがあります。
そのため、相手が「ちょっと距離を置きたいな」と感じていても、その微妙なサインを読み取れず、同じペースで接触を続けてしまうことがあります。そして、その行動が「空気が読めない」「しつこい」と受け取られ、誤解や関係悪化につながってしまうのです。
これらの背景を理解しておくと、「相手がわざとやっているわけではない」という視点を持ちながら、より建設的な距離のとり方を考えることができます。
※距離感の難しさには、アスペルガー特有のこだわり特性が関連していることもあります。
詳しいこだわりの例はこちらで解説しています。
→ アスペルガーに多いこだわり行動と育児ストレス対処法
ターゲットにされやすい人の特徴…あなたも当てはまる?
アスペルガーの人からの“執着”は、誰にでも起こりうることですが、実は特定のタイプの人がターゲットになりやすい傾向があります。これは「あなたの性格が悪い」という話ではなく、あなたの魅力や人柄が、相手にとって安心感を与えやすいということなんです。
ただ、その“安心感”が時に過剰な依存を引き寄せてしまうこともあるため、自分の傾向を知っておくことは大切です。
優しくて断れない性格が引き寄せる依存
まず最も多いのが、優しくて相手の気持ちを優先しがちなタイプ。
「せっかく誘ってくれたし…」「傷つけたくないから…」と考えて、会う約束やお願いを簡単に受け入れてしまう人です。
ASDの人にとって、この“受け入れてくれる態度”は「この人は自分を理解してくれる存在」という強い安心感につながります。その結果、「この人ならもっと仲良くしてくれるはず」という思い込みが生まれ、距離が一気に縮まりやすくなるのです。
しかし、断れない性格のまま無理を重ねると、自分が消耗してしまう危険性もあります。相手のためにも、自分のためにも、“やさしい拒否”を覚えることが大切です。
早すぎる返信や丁寧すぎる対応が誤解を招く
もうひとつの特徴は、連絡のレスポンスが早すぎるタイプ。メッセージが来たらすぐに返信し、しかも長文や丁寧な文章で答えてしまう人です。
もちろん、これは社会的には好印象な対応ですし、仕事や一般的な人間関係ではむしろ評価されるスキルです。
しかしASDの人の場合、この対応が「自分とのやり取りを優先してくれている」という強いサインとして受け取られることがあります。
その結果、「もっとやり取りを増やしてもいいんだ」「この人は自分とずっとつながっていたいんだ」と誤解され、連絡の頻度や要求がエスカレートすることもあるんです。
適度に間をあけたり、返信を簡潔にすることは、決して失礼ではなく健全な距離感を保つための工夫と言えます。
過去にも似た経験がある人が持つ共通点
実は、過去にも「人から強く依存された経験がある」という人は、再び同じような状況に巻き込まれやすい傾向があります。
これは、あなたが“頼られやすい雰囲気”や“受け入れる器の大きさ”を持っているからです。
相手に安心感を与える能力は、間違いなく長所です。ただし、ASDの人にとってはその安心感が「この人こそ自分の理解者だ」という思い込みにつながり、結果的に依存のスイッチを押してしまうことがあります。
客観的に見ると、これはあなたが悪いのではなく、相性や距離感の調整の問題です。
過去の経験を振り返り、「どのタイミングで距離が縮まりすぎたのか」を意識しておくことで、同じパターンを繰り返さずに済みます。
心を守る!アスペルガーの人との距離の取り方の鉄則
アスペルガーの人との関係で「しんどいな…」と感じたとき、つい極端に距離を置いてしまいたくなることがありますよね。
でも、いきなり関係を断ってしまうと、相手を大きく傷つけたり、逆に執着を強めてしまうこともあります。
大切なのは、自分の心を守りながらも相手を否定しない距離感を作ること。そのためには、いくつかの鉄則があります。
相手を傷つけずに自分を守る“境界線”の作り方
まず意識したいのが、「ここから先は踏み込まれたくない」という自分の境界線を明確にすることです。
これは相手に対して壁を作るというよりも、お互いが快適に過ごせる範囲をはっきりさせるというイメージに近いです。
たとえば、
- 平日は夜◯時以降は返信しない
- 休日は自分の予定を優先する
- プライベートな話は共有しない
こういったルールを「自分の都合」としてやんわり伝えることで、相手は拒否された感覚を持ちにくくなります。
特にASDの人は、あいまいな表現よりも具体的なルールのほうが理解しやすい傾向があります。
「物理的距離」と「心理的距離」を組み合わせる方法
距離をとるときは、物理的距離と心理的距離の両方を組み合わせるのが効果的です。
- 物理的距離:会う回数や時間を減らす、座席を離す、会う場所を限定する
- 心理的距離:返信までの時間をあける、会話の内容を仕事や共通の趣味に絞る
どちらか一方だけではうまくいかない場合があります。
たとえば、会う回数を減らしても、毎日長文メッセージを送っていたら心理的距離は縮まったまま。逆に、心理的に距離を置こうとしても、毎日顔を合わせる環境なら物理的距離はゼロです。
両方を少しずつ調整していくことで、相手にも自分にも負担の少ない距離感が作れます。
関係を切らずに整えるための基本マインド
忘れてはいけないのが、距離をとる=関係を切ることではないという考え方です。
ASDの人は「突然いなくなる」「無視される」など急な変化に強い不安を感じやすく、それが逆に執着を悪化させることもあります。
だからこそ、「関係を終わらせる」のではなく「関係を整える」という意識が大事です。
これは、相手にとっても安心でき、自分にとっても消耗しにくい状態をつくるための考え方です。
また、距離をとることに罪悪感を持つ人もいますが、自分を守ることは相手を守ることにもつながると考えてOKです。
無理に合わせ続けるより、適切な距離感を保ったほうが、長期的に良い関係を続けやすくなります。
今日からできる!アスペルガーとの距離を上手にとる5つの方法
「距離をとる」と聞くと、なんだか冷たいことをしているように感じるかもしれません。
でも実際は、お互いが安心して関係を続けるための大事な工夫なんです。ここでは、今日から試せる5つの具体的な方法をご紹介します。
1. 返信の間隔をあける“ゆるやかレス”戦法
アスペルガーの人は、やり取りのパターンやリズムを大事にする傾向があります。もし毎回すぐに返信していると、それが“通常モード”として定着し、相手も同じペースを期待するようになります。
そこで試してほしいのが、あえて返信までの時間を少しあける「ゆるやかレス」。
たとえば、これまで5分以内に返信していたなら、まずは30分〜1時間に延ばしてみましょう。急に数日空けるのではなく、段階的にペースを落とすのがコツです。
この方法は、相手に「この人はいつも即レスしてくれる」という思い込みをやわらげ、自然にやり取りの頻度を減らす効果があります。
2. 会う回数を無理なく減らすスケジュール管理術
物理的に会う時間を減らすことは、心理的距離を保つ上でも有効です。
ただし、「もう会えません」とバッサリ切るのではなく、自分の予定を優先して“自然に”会う機会を減らすのがポイント。
たとえば、
- 「この週は家族の予定があって…」
- 「今月は仕事が立て込んでるんだ」
こういった具体的かつ自分都合の理由を添えると、相手も受け入れやすくなります。無理なく回数を減らせば、関係を壊さずに距離を保てます。
3. 1対1を避ける“グループクッション”活用法
1対1で長時間過ごすと、どうしても距離が急速に縮まりやすくなります。
そこで効果的なのが、複数人で会う「グループクッション」。
友人や同僚など第三者を交えて会うことで、会話や関心が分散し、過剰な集中があなた1人に向かいにくくなります。
また、グループでの交流は相手にとっても新しい人間関係を広げるきっかけになる場合があります。
4. 生活環境を見直して物理的距離を確保
距離感の調整は、環境づくりから始めるのも効果的です。
- 職場なら座席を変える
- 学校なら席順や班を調整する
- 通勤・通学時間をずらす
こうした物理的距離の確保は、相手に直接「距離を置きたい」と伝えなくても、自然に接触頻度を減らせる方法です。特に毎日顔を合わせる環境では、物理的な変化が心理的な負担を軽減します。
5. 相手の興味を別の方向にそらす会話の仕掛け
アスペルガーの人は、一度興味を持った対象に強く集中する特性があります。もしその対象が「あなた」になっている場合は、意識を他の話題や人に向けてもらう工夫が必要です。
たとえば、
- 「そういえば、この前言ってた◯◯のイベント行った?」
- 「◯◯さんもその話好きそうだよ」
こうして相手の興味を別の活動や人物に向けることで、“あなた一点集中”をやわらげることができます。これは相手にとっても新しい楽しみを広げるチャンスになります。
5つすべてに共通して言えるのは、「急な変化は避ける」ということです。少しずつペースや環境を変えることで、相手も違和感なく新しい距離感に慣れていきます。
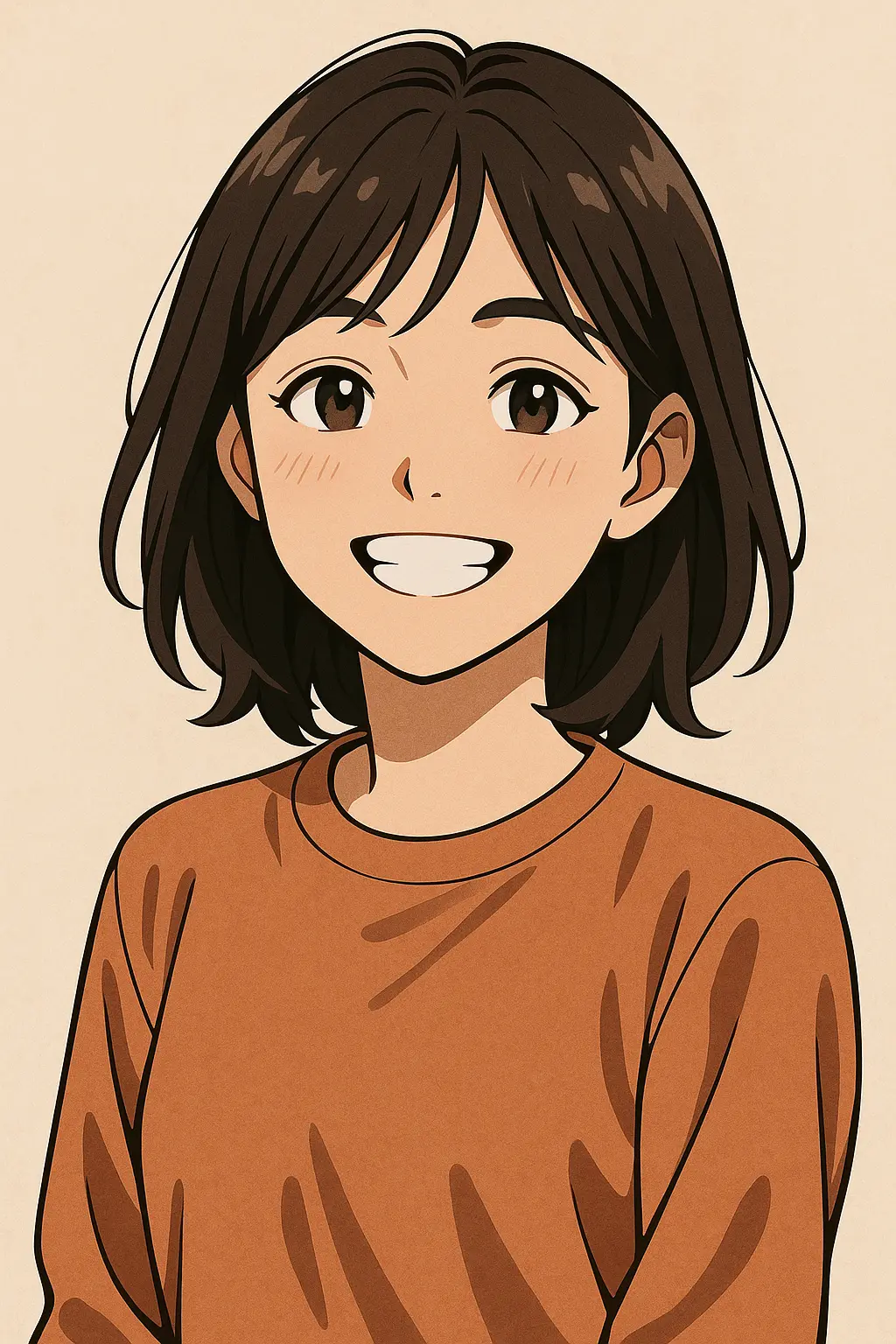
角が立たない!気持ちをうまく伝える会話術
距離をとるときに一番気を使うのは、「どうやって伝えるか」ですよね。
ストレートすぎると相手を傷つけるし、あいまいすぎると伝わらない…。特にアスペルガーの人は、あいまいなニュアンスや遠回しな表現を読み取るのが苦手な場合が多いので、伝え方には工夫が必要です。
ここでは、相手との関係を壊さずに、自分の気持ちや希望をはっきりと伝えるための3つのコツをご紹介します。
“Iメッセージ”で自分の都合として伝える
まず大事なのは、「あなたが悪い」という言い方を避けることです。
「あなたの連絡は多すぎる」「あなたと会うのは疲れる」といった“YOUメッセージ”は、相手を責められているように感じさせ、防御的な反応を引き出してしまいます。
代わりに使いたいのが、“Iメッセージ”。
これは、「私はこう感じる」「私はこうしたい」という、自分を主語にした伝え方です。
例えば、
- 「夜はゆっくり休みたいから、返信は朝にするね」
- 「週末は家族と過ごしたいんだ」
このように自分の事情として伝えると、相手は“拒否された”と感じにくくなるんです。
具体的なルール設定で相手を混乱させない
ASDの人は、あいまいなルールよりも、明確で具体的なルールのほうが理解しやすい傾向があります。
たとえば「夜はあまり連絡しないでね」という曖昧な表現よりも、「平日の夜8時以降は返信しないことにしている」とはっきり言ったほうが誤解が少なくなります。
また、ルールは守れる範囲で設定することが重要です。守れないルールを作ると、一貫性がなくなって信頼を損ねる原因になります。
ルールを作るときは、
- 時間(◯時以降は連絡しない)
- 頻度(会うのは月1回まで)
- 内容(仕事の話は勤務時間内だけ)
のように、数字や条件を明確にすると効果的です。
何度も同じ表現を使い、一貫性を保つコツ
一度伝えたことでも、相手がすぐに完全に理解できるとは限りません。
ASDの人は「一度聞いたから覚えているだろう」という前提で動くと、すれ違いが起こりやすくなります。
そこで大切なのが、何度でも同じ表現で繰り返すこと。言い方を変えず、ルールや希望を一貫して伝えることで、相手も「これは本当に守るべきことなんだ」と理解しやすくなります。
例えば、毎回「夜8時以降は返信できないんだ」と同じ言葉で伝えると、相手の中でルールが固定化され、習慣として受け入れられやすくなります。
この“一貫性”は、距離感を保つための最強の武器と言っても過言ではありません。
そのまま使える!シーン別やんわり断り文例
「距離を置きたいけど、どう言えば角が立たないの?」という悩み、ありますよね。
特にアスペルガーの人との関係では、感情的に拒否されることへの敏感さや、あいまいな表現が理解しづらい特性があるため、断り方にはちょっとしたコツが必要です。
ここでは、よくある4つのシーン別に、やんわり伝えられる実用フレーズをご紹介します。
すべて、自分の事情として伝える形にしているので、相手を否定せずに距離を保ちやすくなります。
【連絡が多いとき】
「返信が遅くなっても気にしないでね」
これは、相手に「即レスはできない」という前提をやんわり示すフレーズです。
「返事が遅い=嫌われた」と感じやすい人にとって、この一言は安心材料になります。
ポイントは、「遅くなるけど気にしないで」と“お願い”ではなく“お知らせ”として伝えること。
こうすることで、相手は「じゃあ少し間をあけても大丈夫なんだ」と受け取りやすくなります。
【会いたい誘いが続くとき】
「しばらく忙しくて会えないんだ」
直接「もう会いたくない」と言うのは衝撃が大きいですが、「忙しい」という理由は相手にとって理解しやすく、感情的な衝突を避けやすいです。
ただし、「また落ち着いたら連絡するね」など、未来に会える可能性を残す一言を添えると、相手の不安を減らすことができます。
この「希望の残し方」が、執着を悪化させないための重要なポイントです。
【話が長いとき】
「あと5分で出かける時間なの」
ASDの人は、相手の時間感覚や予定を読み取るのが難しいことがあります。
そのため、「そろそろ終わりにしよう」ではなく、「◯分後に〜しないといけない」という具体的な時間制限を伝えるほうが効果的です。
この言い方だと、相手も「じゃあ今は切り上げるべきなんだな」と理解しやすく、感情的な拒否ではなく“状況の都合”として受け止めてもらえます。
【境界を超えるお願いのとき】
「それは私にはできないんだ」
このフレーズは、一見ストレートですが、「できない」という事実ベースの言い方なので、「やりたくない」とは別のニュアンスになります。
例えば「お金を貸して」「秘密を話して」など、自分の境界を超えるお願いが来たときには、この一言でしっかり線を引くことが大事です。
さらに、「別の方法を探そう」「◯◯さんに相談してみたら?」と代案を添えると、拒否の印象をやわらげられます。
これらのフレーズはすべて、相手を否定せず、自分の事情として距離を調整できる形になっています。
急に全部を実践しなくても、まずは1つの場面から取り入れてみると、相手との関係が少し楽になるはずです。
やってはいけない距離の置き方と安全な方法
距離をとるとき、「もう無理!」と限界を感じて一気に関係を断ちたくなること、ありますよね。
でも、アスペルガーの人との関係では、やり方を間違えると逆効果になってしまうことが多いんです。
ここでは、避けたほうがいい距離の置き方と、関係を壊さずに距離を保つための安全な方法をご紹介します。
突然の連絡遮断やブロックは逆効果になる理由
「もう耐えられない!」と、LINEをブロックしたり、SNSで急に関係を切ってしまうと、相手は強い不安や混乱を感じます。
特にASDの人は、予想外の変化や理由のわからない出来事にとても敏感で、「なぜ?」という疑問が執着や追跡行動を強めるきっかけになってしまうことがあります。
また、突然の遮断は「嫌われた」「裏切られた」という感情を呼び起こし、トラブルや対立の火種になることも。
どうしてもブロックが必要な場合は、最終手段として、他の方法を試しても改善が見られないときに限定しましょう。
安心感を残したまま距離をとる段階的ステップ
距離を置くときの理想は、「少しずつフェードアウトする」ことです。
いきなり関係を断つのではなく、連絡頻度や会う回数を段階的に減らし、相手が新しいペースに慣れる時間を作ります。
例えば、
- 返信時間を徐々に遅くする
- 会う予定を月2回→月1回に減らす
- 会話の内容を趣味や共通の話題に絞る
こうしたステップを踏むことで、相手の不安を最小限に抑えつつ、自分の負担を軽くできるんです。
これは「相手のため」というよりも、長期的に関係を安定させるための戦略でもあります。
信頼できる第三者や支援機関に頼る判断基準
もし自分だけでは対応が難しいと感じたら、第三者や支援機関に頼ることも選択肢のひとつです。
特に職場や学校では、上司や担任、スクールカウンセラーが間に入ることで、直接伝えにくいこともスムーズに共有できます。
頼るべきタイミングの目安は、
- 自分の生活や仕事に支障が出てきた
- 相手の行動がエスカレートしている
- 話し合っても改善が見られない
また、地域の発達障害者支援センターや精神保健福祉センターは、当事者との関係づくりや対応方法について具体的なアドバイスをくれることがあります。
「自分が弱いから頼る」ではなく、「状況を健全に保つために活用する」と考えると、相談しやすくなりますよ。
ストレスをためないためのセルフケア習慣
アスペルガーの人との距離感を調整していると、知らないうちに自分が疲れてしまうことがあります。
「そんなに無理してないつもり」でも、心や体は正直です。だからこそ、日常的にストレスをためないための“セルフケア習慣”を持つことが大事なんです。
ここでは、すぐに始められる3つのセルフケアのポイントをご紹介します。
自分のストレスサインを早めにキャッチする方法
まずは、自分のストレス状態に早く気づくことが第一歩。
ストレスがたまると、睡眠の質が落ちたり、食欲が変わったり、気分が落ち込みやすくなったりします。
例えば、
- 朝起きるのがつらい日が続く
- 人と会うのが億劫になる
- ちょっとしたことでイライラする
こうしたサインは、「心が疲れてきているよ」というアラートです。
自覚できたら、無理に関係を続けようとせず、少し距離を置く行動を取ることが大切です。
相談できる相手をあらかじめ確保しておく重要性
ストレスを抱え込んでしまう人の多くは、「誰にも言えない」状態に陥っています。
特に人間関係の悩みは、相手に直接言えないことが多く、心の中にたまりやすいですよね。
だからこそ、あらかじめ相談できる相手を確保しておくことが重要です。
友人や家族でもいいですし、同じような経験をした人や専門家でも構いません。
相談相手は、
- 否定せずに話を聞いてくれる
- 秘密を守ってくれる
- 解決策を一緒に考えてくれる
こういう人を選ぶと、話したあとの安心感が全く違います。
「困ってから探す」のではなく、「元気なうちに探しておく」のがポイントです。
気持ちをリセットできる趣味・休息時間の作り方
人間関係で疲れた心は、意識的にリセットする時間が必要です。
これは「何もしない時間」でもいいですし、好きなことに没頭できる趣味でも構いません。
例えば、
- 30分だけ好きな音楽を聴く
- ウォーキングやヨガで体を動かす
- コーヒーをゆっくり淹れて飲む時間を作る
- 創作や料理など“手を動かす”活動をする
大事なのは、その時間だけは相手のことを考えないと決めること。
これを習慣にすることで、心の回復スピードがぐっと上がります。
セルフケアは「自分を甘やかすこと」ではなく、長く健全な人間関係を続けるための土台作りです。
まずは1つ、小さな習慣から始めてみましょう。
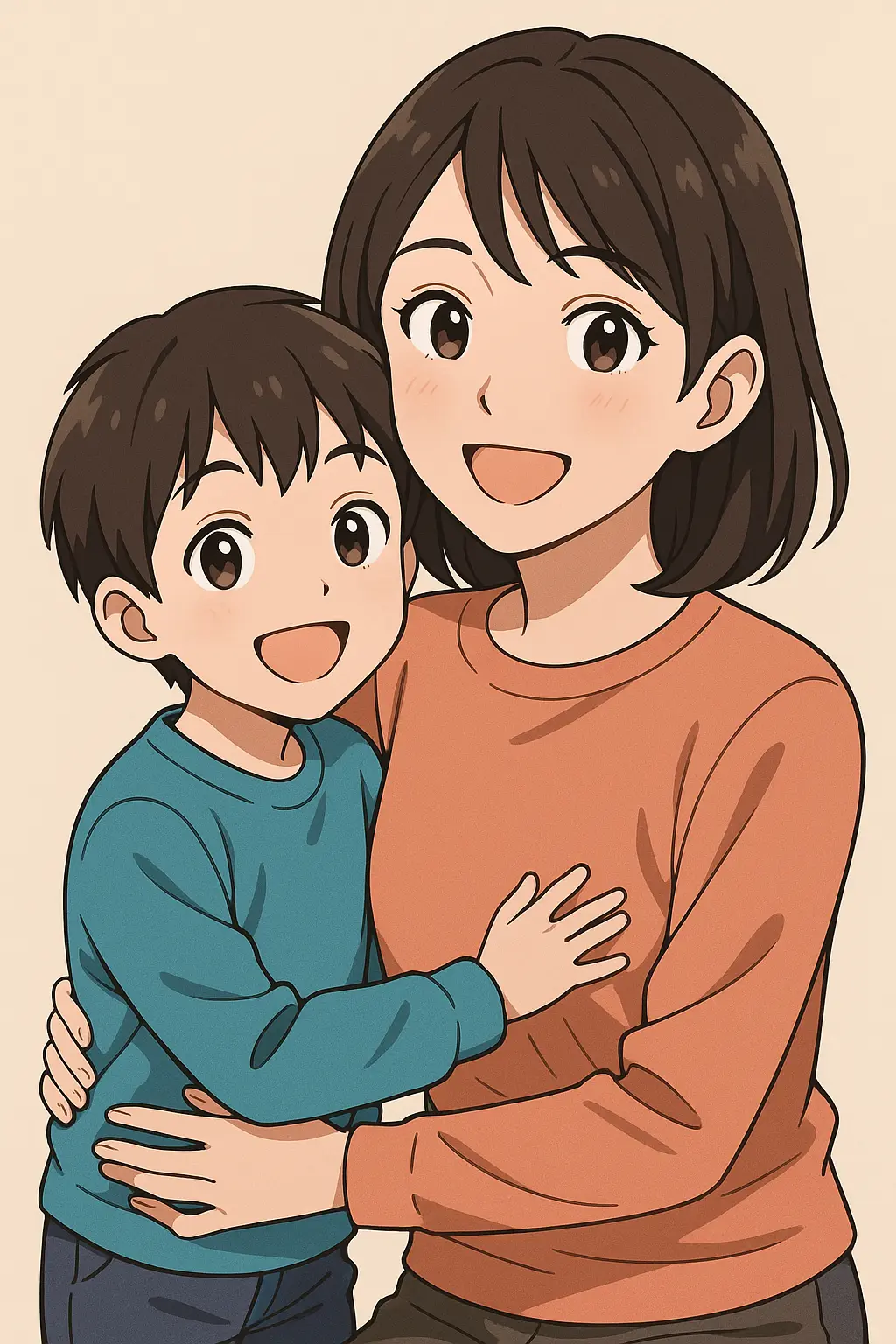
まとめ:自分も相手も守れる“ちょうどいい距離感”を見つけよう
アスペルガーの人との距離感に悩むとき、つい「どうしてこうなるの?」と相手の行動ばかりに目が向きがちです。
でも忘れてはいけないのは、執着は本人の悪意ではなく、特性からくる自然な行動だということです。
執着は特性ゆえのもので、悪意ではない
アスペルガー症候群(ASD)の人が見せる“距離の近さ”や“頻繁な接触”は、安心感や好意の表れであることが多いです。
つまり、嫌がらせをしようとしているわけではなく、「信頼しているからこそ関わりたい」という気持ちが行動になっているんです。
この視点を持つと、「拒否」ではなく「調整」として距離を考えられるようになります。
相手を敵と見なさずに対応することは、自分の心の余裕にもつながります。
距離の取り方は「関係を断つ」ではなく「関係を整える」
距離をとるというと、極端に「関係を切る」というイメージを持つ人もいますが、それは必ずしも正解ではありません。
特にASDの人にとって、突然の関係断絶は強い不安や混乱を引き起こし、執着を逆に強めてしまうことがあります。
だからこそ、目指すべきは「関係を整える」こと。
物理的な距離と心理的な距離をバランスよく調整し、お互いに無理のない関係を作ることが大切です。
自分と相手、双方が安心できる関係づくりがゴール
最終的なゴールは、自分も相手も安心して関係を続けられる状態です。
そのためには、
- 自分の心を守る境界線を持つ
- 相手にわかりやすくルールや希望を伝える
- 少しずつ距離を整えていく
といった工夫が必要になります。
距離感の調整は一度きりではなく、状況や関係性の変化に合わせて見直していくものです。
「自分の安心」と「相手の安心」の両方を大切にする姿勢が、長く良い関係を保つカギになります。
以上【執着されて限界…アスペルガーの人との“心地よい距離感”の作り方と上手な伝え方】でした。

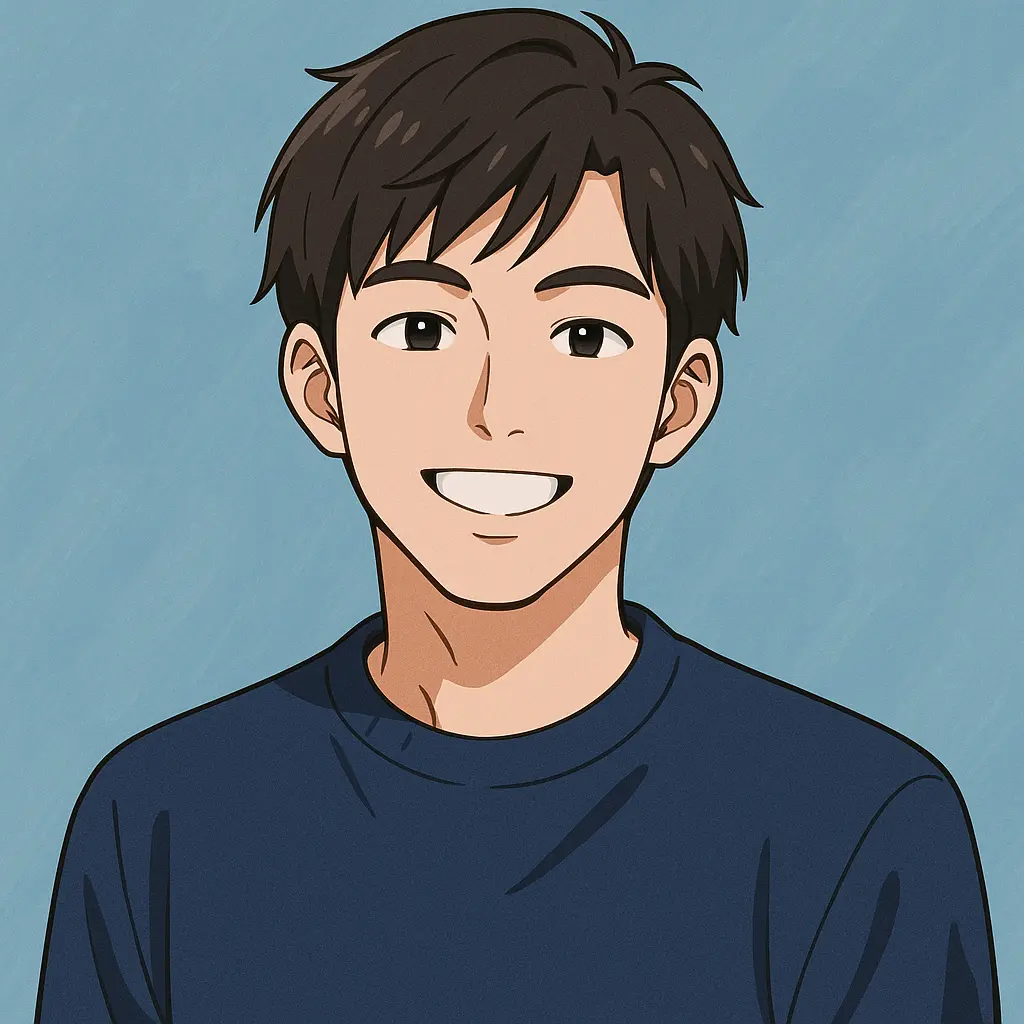









コメント