「何度言っても聞いてくれない…」そんな毎日に、ちょっと疲れていませんか?
自閉症のあるお子さんとのやりとりで、「話を聞いてくれない」と感じる場面は少なくありません。繰り返し声をかけても反応がなかったり、まるで無視されているように感じてしまったり…。でも、実は“聞こえていない”のではなく、“伝わっていない”だけかもしれないんです。
この記事では、そんな悩みに寄り添いながら、実際に効果があった5つの声かけの工夫をご紹介します。
あなたの声かけ、子どもに届いていますか?
明日からの関わり方が少しラクになるヒント、ぜひ探してみてください。
はじめに
「なんで話を聞いてくれないの?」——その疑問、今日で解決します!
自閉症のあるお子さんと日々向き合っていると、こんな風に感じたことはありませんか?
「声をかけても反応がない…」
「お願いしても無視される…」
「聞いてないふりをしてるのかな?」
こういった悩み、実は多くの保護者が共通して感じていることなんです。でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。
本当に「話を聞いてない」のでしょうか?
それとも、「聞こえてない・伝わってない」だけかもしれません。
実は、自閉症のある子どもたちの「話を聞かない」という行動の裏には、感覚過敏、認知の特性、言語理解の難しさなど、さまざまな要因が関係しています。決して“わがまま”だったり“わざと無視している”わけではないんです。
この記事では、そんな「話を聞かない」と感じるときに実際に効果があった5つの工夫をご紹介していきます。すべて、私自身や支援現場で試してきた“リアルな経験”に基づいた実践法ばかり。
「声かけが伝わらない…」と悩んでいる方にとって、少しでもヒントになれば嬉しいです。
自閉症の特性を理解しながら、“伝わる工夫”をすることで、コミュニケーションはちゃんと変わっていきます。
「話を聞いてくれない」と感じたその瞬間こそ、関わり方を見直すチャンスです!
それでは早速、「どうして話を聞いてくれないのか?」という根本的な疑問から、一緒に紐解いていきましょう。
自閉症の子が「話を聞かない」のはナゼ?意外な理由とは
子どもに声をかけたのに返事がない。
何度呼んでもこちらを見てくれない。
そんなとき、つい「話を聞いてくれてない」と感じてしまうこと、ありませんか?
でも実は、自閉症のあるお子さんの場合、“話を聞かない”のではなく、“聞こえにくい”または“伝わりにくい”状況にあることが少なくありません。
このセクションでは、「なぜそうなるのか?」という行動の背景にある理由や視点を、わかりやすくひもといていきます。
「話を聞く」って、実はこんなに奥が深い!
私たちが何気なく使っている「話を聞く」という行動。実はこれ、かなり複雑な認知活動なんです。
たとえば、
- 相手の声を聴覚でキャッチする
- それを言葉として理解する
- 必要があれば頭の中で処理して
- そして反応する
…この一連の流れを、数秒のうちに自然にやってのけているのが、いわゆる“聞けている状態”なんですね。
でも自閉症のある子どもたちは、このどこかのステップでつまずきが起きやすい特性を持っています。だから、「聞いてないように見える」けど、実はその裏に“努力してるけど難しい”現実があるんです。
自閉症の特性が“聞けない”を引き起こす?
ここで知っておきたいのが、自閉症の子どもには発達特性に由来する“聞くことの難しさ”があるということ。
たとえば、
- 聴覚過敏:周囲の音がすべて同じ音量で聞こえてしまう。結果、声かけがノイズにまぎれてしまうことも。
- 注意のコントロールが苦手:興味のあることに集中していると、他の音や声がまったく入ってこないことがある。
- 言語理解の苦手さ:抽象的な言葉やあいまいな表現を、うまく理解できない。
こういった要因が重なって、「話を聞けない」「聞いてないように見える」という状況が起きているんです。
つまり、“聞かない”のではなく、“聞けない”ということも多い。ここを理解できると、親としての見方も少し変わってくるかもしれません。
「無視してるの?」と思ったときに知ってほしいこと
声をかけても返事がないとき、「わざと無視してるのかな?」と思ってしまうこと、正直ありますよね。
でも、少し視点を変えてみると——
子どもは今、別のことに強く集中していて、声が“届いていない”のかもしれません。
あるいは、自分の中で一生懸命“処理中”で、すぐには反応できないだけかもしれません。
このとき、すぐに怒ったり、「なんで無視するの!」と責めてしまうと、子どもは“聞こう”とすること自体をやめてしまうこともあります。
だからこそ、「無視じゃないかも?」という別の見方を持つことがとても大切なんです。
ほんの少しだけ、子ども側の世界をのぞいてみる気持ちで接してみると、コミュニケーションの可能性がぐんと広がりますよ。
工夫① 絵カード・スケジュールで一目で伝わる!視覚で“聞かせる”技
自閉症の子どもに言葉だけで伝えようとしても、うまく伝わらないことって多いですよね。
「いま何の話をしてるの?」って顔をされたり、「急にそんなこと言われても…」とばかりに固まってしまったり。
でも、そんなときにすごく効果的なのが、“視覚的な情報”を使って伝えること。
つまり、「見ることでわかる」工夫です。
「見える化」でコミュニケーションが激変した理由
自閉症のある子どもたちは、よく“視覚優位”と言われます。これはつまり、「耳で聞くより、目で見て理解する方が得意」という傾向があるということ。
だから、「あと5分で出かけるよ!」って言葉だけで伝えるよりも、
時計の絵や“出かける”のイラストを見せた方が、ずっと伝わりやすいんです。
しかも、言葉は時間とともに消えてしまうけれど、視覚情報は“その場に残る”という強みも。
これが、自閉症の子にとって安心感につながるんですよね。
「何をすればいいか」「次に何が起こるのか」がわかると、子どもも余計な不安を抱かずに済みます。
結果として、“指示が通る”確率もぐんと上がるんです。
家庭でできる!超シンプルな視覚支援アイデア集
視覚支援って聞くと、ちょっと難しそう…と感じるかもしれませんが、実はめちゃくちゃ簡単にできる方法もたくさんあります。
たとえば…
- 絵カードをラミネートして、冷蔵庫に貼っておく
- 「やることリスト」をイラストで作って壁に貼る
- 100均のマグネットやホワイトボードで予定表を作る
こんな感じで、身近なものを使ってすぐに始められるんです。
大切なのは「子どもがパッと見て理解できるかどうか」。
文字よりも、シンプルなイラスト+短い言葉の組み合わせが効果的です。
また、まだ絵が難しい年齢の子には、実物の写真を使うのもおすすめですよ!
朝の準備がスムーズに!我が家の視覚支援ルーティン
わが家でも、朝の支度にずっと苦戦していました。
「顔洗って!」「着替えて!」って何度言っても聞こえてない(ように見える)…なんて日常茶飯事。
そこで取り入れたのが、「朝の準備スケジュールカード」です。
- ①起きる → ②顔を洗う → ③服を着る → ④朝ごはん → ⑤出発!
この流れを、イラスト入りで順番に貼り出して見えるようにしただけなんですが、効果は抜群。
「次、何する?」と自分から確認するようになったんです。
指示を出さなくても、子ども自身がカードを見ながら動けるので、親のイライラも激減。
お互いにとってストレスの少ない朝のルーティンになりました。
この視覚支援、ちょっとした工夫で日常のストレスがグッと減るので、本当におすすめです!
工夫② 好きなことに乗っかるだけ!“聞く耳”を開く魔法の声かけ
自閉症の子どもとやりとりしていると、どうしても“聞いてもらえない”場面って多くありますよね。
でも、そんなときに頼りになるのが、「その子の“好き”」です。
えっ、そんなことで?と思うかもしれませんが、これが意外なほど効果的なんです。
実際に、「好きなもので声かけに乗っかる」だけで、びっくりするくらい反応が変わることもありますよ。
好きなものが“話を聞くスイッチ”になるワケ
子どもって、自分の興味があることにはすごい集中力を発揮しますよね。
特に自閉症の子どもたちは、好きなものに対して“一点集中”する特性が強く出ることがあります。
逆にいえば、興味のないことには全く反応がない、なんてこともあるわけですが…
だからこそ、声かけに“その子の好き”を上手に盛り込むと、一気に聞く姿勢が変わるんです。
たとえば、
- 電車が好きなら「〇〇線が出発するよ!」
- 恐竜が好きなら「ティラノサウルスさんがご飯食べてるよ〜」
- キャラクター好きなら「アンパンマンが待ってるよ!」
といった感じで、日常の声かけを“その子の世界”に置き換えてみると、不思議と伝わりやすくなるんですよ。
これは、ただ気を引くためだけじゃなく、脳が興味のある情報に自然と反応しやすいという科学的な側面もあります。
つまり、“好きなもの”は脳を刺激する入り口になるというわけですね。
「電車が出発するよ!」我が家の神フレーズ集
わが家の息子は、大の電車好き。駅名や発車メロディにまで詳しくて、「これは使うしかない!」と声かけを全部“電車仕様”に変えてみたところ、大成功でした。
たとえば…
- 「今から着替え列車が出発します!」→ 着替えスタート
- 「5分後にごはん急行が発車します!」→ ごはんタイムの合図
- 「出発進行〜!」→ お出かけ前のかけ声
- 「次は〜、おふろ〜、おふろ〜です」→ お風呂誘導
こんな風に、子どもが好きな世界観に合わせてアレンジするだけで、スーッと耳に入っていくんです。
もちろん、これは電車に限らず何でも応用できます。
「ぬいぐるみが呼んでるよ」でもいいし、「恐竜が行こうって言ってる」でもいい。
大事なのは、子どもが“ワクワクするフレーズ”に置き換えること。
この工夫、見た目には些細に見えますが、親子のコミュニケーションのハードルがぐっと下がる魔法みたいな方法なので、ぜひ試してみてくださいね。
工夫③ 一言ずつ、ゆっくり、具体的に!伝わる声かけの鉄則
「伝えたはずなのに、まったく伝わってない…」
自閉症の子どもとのやり取りで、こんな場面に心当たりがある方、多いと思います。
でも、もしかしたらそれ、言葉の“量”や“スピード”が多すぎて、届いていないだけかもしれません。
実は、「話し方」を少し工夫するだけで、子どもの反応がガラッと変わることがあるんです!
情報が多すぎると届かない!“脳の渋滞”を防ぐ話し方
私たち大人は、何気なくこんなふうに話してしまいがちです。
「そろそろお出かけだから、靴下はいて、帽子も持ってきて、ついでにお茶も準備してね!」
でも、これって情報量が多すぎて、自閉症の子にとってはまるで“脳が渋滞してしまう”ような状態になってしまうんです。
聞いている途中で「え、何て言ったっけ…?」と、フリーズしてしまうのも無理はありません。
だからこそ有効なのが、「一言ずつ」「ゆっくり」「具体的に」伝えること。
たとえば…
- 「靴下はこうね」
- (終わったら)「次は帽子だよ」
- (さらに)「お茶をカバンに入れてね」
このように情報を“小分け”にして伝えることで、子どもが整理しながら行動に移しやすくなるんです。
効果絶大!伝わる言葉とNGワードの違いとは?
声かけの内容をほんの少し変えるだけで、子どもの反応は驚くほど変わることがあります。
【OKな言い方】
- 「おもちゃをお片づけしよう」
- 「イスに座ってね」
- 「今からごはんだよ」
【NGになりやすい言い方】
- 「ちゃんとして」
- 「早くして」
- 「そろそろやろうか」
違い、わかりますか?
OKな言い方は“何をどうするか”が具体的に伝わるんですが、
NGな言い方はあいまいすぎて、子どもには理解しにくいんです。
特に「ちゃんと」「そろそろ」などの抽象的な表現は、自閉症の子どもにとっては非常に難しい言葉。
見てわかる・行動に移せるレベルまで“翻訳”する意識がとても大事なんです。
一歩ずつがカギ!スモールステップで成功体験を積む
そしてもうひとつ大切なのが、「一度にやらせようとしない」こと。
たとえば、「お出かけの準備をしてね」と言っても、
それには「着替える」「トイレに行く」「バッグを持つ」「玄関に行く」など、実は複数のステップが含まれています。
これを一気に言われると、子どもは混乱してしまうのも無理はありません。
だから、「1ステップずつ区切って伝える=スモールステップ」がとても効果的。
一つずつできたら、ちゃんと「できたね!」と伝えてあげることで、“成功体験”が積み上がっていきます。
成功体験が増えると、「話を聞くこと=できること」「声かけに反応する=安心できること」につながっていくんですね。
この「声かけの鉄則」は、日々の積み重ねがカギになります。
でも逆にいえば、少しずつ変えるだけでもしっかり成果が出るということ。
次に声をかけるときは、「短く・ゆっくり・具体的に」の3つをぜひ意識してみてくださいね!
工夫④ 反応がなくても焦らない!「待つ」ことで生まれる信頼
声をかけても、反応なし。
「聞こえてる?」「無視してるの?」と、つい不安やイライラが出てきてしまうことってありますよね。
でも、そんなときこそ試してほしいのが、「待つ」という関わり方です。
実は、自閉症の子どもたちは、声をかけられてから反応するまでに“時間がかかることがある”んです。
だから、大人が焦って次々に話しかけてしまうと、逆に伝わらなくなってしまうことも…。
少しの“待ち時間”が、信頼や安心感につながる大切な時間になることもあるんですよ。
3秒待つだけで変わる!?子どものペースを大切に
たとえば「イスに座ってね」と声をかけたとき、すぐに動かないからといって「ほら、早く!」と急かしていませんか?
でも実は、子どもは頭の中で一生懸命その言葉を処理して、次の行動を考えている最中かもしれません。
そこでおすすめなのが、“3秒ルール”。
声をかけたら、意識的に3秒以上、何も言わずに待つんです。
これだけで、
「あ、聞こえてたんだ!」
「今、ちゃんと理解しようとしてたんだ!」
という場面に出会えることも少なくありません。
この“ちょっとした間”が、子どもにとってはとても重要な“考えるための時間”なんですよね。
私たち大人のスピード感ではなく、子ども自身のペースに合わせることが大事。
それができると、親子のコミュニケーションが驚くほどスムーズになることがあります。
待つって難しい…でも“親の心構え”が一番大事!
とはいえ、実際に「待つ」って、意外と難しいんですよね。
特に忙しい朝や、時間に追われているときなんてなおさらです。
「早く動いてほしい」「なんでまだやってないの?」って、つい言いたくなる気持ちも本当によくわかります。
でも、そんなときこそ大切なのが、“親の側の心構え”なんです。
- 「今、がんばって処理してるところかも」
- 「まだ行動に移せないだけで、伝わってるかもしれない」
- 「この子には、この子のタイミングがある」
こうした視点を持てるだけで、心の余裕が生まれ、子どもにも安心感が伝わります。
そしてもうひとつ。
「待ってくれる大人がいる」という体験は、子どもにとって“信頼の土台”にもなっていくんです。
急がされずに、自分のペースを尊重される経験って、それだけでとても大きな意味がありますよね。
完璧に“待てる親”になろうとしなくても大丈夫。
少しだけ意識して「黙って見守る時間」を増やしていくだけで、子どもの反応や表情が変わってくるはずです。
この「待つ」という関わり方は、簡単そうで奥が深いですが、親子の信頼関係を育てるうえでとても効果的な工夫のひとつです。
次回、声をかけたら、ぜひ3秒だけ“見守る時間”を試してみてくださいね。
工夫⑤ 「聞ける環境」づくりで子どもの集中力が変わる!
「ちゃんと声かけてるのに、全然聞いてない…」
そんなとき、子ども本人の問題だけじゃなく、“周りの環境”が影響していることも実は多いんです。
自閉症の子どもたちは、感覚がとても敏感だったり、特定の刺激に強く反応してしまったりすることがあります。
そのため、聞こえていないのではなく、聞こえすぎて困っている、なんてケースもあるんですよ。
だからこそ大切なのが、「聞こえやすくなる環境づくり」。
つまり、“聞く力”をサポートするのは、声のかけ方だけじゃなく、「空間の整え方」も大きく関係しているというわけです。
音・光・視界…刺激を減らすだけでグッと楽になる
まず知っておきたいのが、自閉症の子どもたちの多くは“感覚過敏”を抱えている可能性があるということ。
たとえば…
- テレビの音が少しでも鳴っていると集中できない
- LED照明のちらつきや明るさでソワソワしてしまう
- 視界の中におもちゃや人の動きがあると気が散ってしまう
こんな状態で声をかけても、実際には情報が多すぎて“聞くどころじゃない”状況なんですよね。
逆に言えば、余計な刺激をちょっと取り除くだけで、驚くほど集中できるようになることも。
たとえば…
- テレビや音楽を一旦オフにして声かけ
- 照明をやさしい光に変える
- 目の前に余計なものを置かないようにする
ほんのちょっとの工夫ですが、子どもが安心して“聞く体勢”に入れる環境づくりとしてとても効果的です。
我が家の“聞く空間”ルール!リビングでもできる簡単環境づくり
「そんなの専用の部屋がないと無理…」と思うかもしれませんが、
実はリビングでも、工夫次第で“聞ける空間”はつくれます!
わが家では、次のような“聞く環境ルール”を決めています:
- 声かけするときは、テレビと音楽は一時停止
- 子どもの正面に立って、目を合わせてから話しかける
- 周囲のおもちゃや気が散りそうなものは一時的に見えない場所に置く
これだけでも、子どもの反応がまるで違うんです。
特別な防音室や支援グッズがなくても、「今この子が落ち着いて聞ける状況か?」を考えるだけで、環境づくりはスタートできます。
そして何より、「この子が集中しやすい空間ってどんなだろう?」と考えること自体が、子どもに寄り添う姿勢そのものでもありますよね。
「声かけ」+「環境」=伝わりやすさが倍になる!
この方程式、ぜひ日常の中で取り入れてみてくださいね。
声かけに悩んだら思い出して!“伝わる5つの工夫”まとめ
「どう声をかけたらいいのかわからない…」
「何度言っても通じない…」
そんなふうに感じたとき、ちょっと立ち止まって、これまで紹介してきた“5つの工夫”を思い出してみてください。
毎日子どもと向き合っていると、うまくいかない日もあります。
でも、少しの工夫でコミュニケーションはちゃんと変わっていきます。
視覚・興味・短く・待つ・環境!5つの鉄板ルールをおさらい
ここで、もう一度“伝わるための5つの工夫”をおさらいしておきましょう。
- 視覚で伝える:絵カードや予定表など、「見える化」で理解しやすく!
- 興味にのせる:好きなものを声かけに取り入れて“聞くスイッチ”をオン!
- 短く・具体的に:あいまいな言葉より、「何をどうするか」を一言ずつ。
- 待つ:反応がなくても焦らず3秒。子どものペースを大切に。
- 環境を整える:音や光、視界の刺激を減らして“集中しやすい空間”をつくる。
この5つは、どれも特別な支援道具がなくてもすぐに実践できることばかりです。
完璧にやろうとしなくてOK!ひとつでも意識するだけで、子どもの反応が少しずつ変わっていくのを感じられるはずです。
「伝わらない」は親のせいじゃない。伝え方を変えてみよう!
子どもに話しかけてもうまく伝わらないと、
「私の言い方が悪いのかな…」
「育て方を間違えたのかも…」
そんなふうに、自分を責めたくなる気持ちになること、ありますよね。
でも、それって本当に親のせいなんでしょうか?
子どもに合った“伝え方”を知らなかっただけかもしれない。
今のやり方が、その子にはちょっと難しかっただけかもしれない。
実際、自閉症のある子どもは、“聞く力”にも個性や特性があるものです。
だからこそ、「伝わらない…」と感じたときは、“伝え方を変えてみる”という柔軟な視点を持ってみることがとっても大切。
それだけで、親も子もお互いにラクになるケースは本当にたくさんあるんです。
コミュニケーションは一方通行じゃありません。
「伝えたい」+「伝わる工夫」で、親子の関係はもっとあたたかくなります。
「うまくいかない日があっても、次は違う方法を試してみよう!」
そんなふうに前を向けるヒントになれば嬉しいです。
「伝わらない…」と悩むあなたへ。自分を責めないでください
どれだけ丁寧に声をかけても、反応がない。
何度言っても、動いてくれない。
そんな日が続くと、「私の育て方が悪いのかな…」って思ってしまうこと、ありますよね。
でもまず、知っていてほしいのは――
「伝わらない=あなたのせい」ではありません。
子育てって、正解が見えにくいもの。
ましてや、自閉症のあるお子さんとの日々は、“普通の方法”が通じないことも多いからこそ、不安や孤独を感じやすいんです。
だからこそ、この章では「うまくいかない日」との向き合い方、そして“ひとりでがんばらなくていい”ということをお伝えしていきます。
「うまくいかない」そんな日があっても大丈夫
SNSを見れば「子どもがスムーズに動いてくれた」「こんなに成長しました!」なんて報告が並んで、つい比べて落ち込んでしまうこと、ありますよね。
でも、そもそも家庭の状況も、子どもの特性も、毎日のコンディションも全部違うんです。
ある日はうまくいっても、次の日は全然ダメ、なんて当たり前。
“子育ては波があって当然”なんですよ。
大切なのは、「昨日よりもうまくやろう」とか「完璧にこなさなきゃ」ではなくて、
「できなかった日も、自分を責めずに切り替えること」
「何か一つでもうまくいったら、それをちゃんと認めてあげること」
そんなふうに、“自分にもやさしくする視点”を持つことなんです。
うまくいかなかった日は、がんばった自分に「おつかれさま」って声をかけてあげてくださいね。
一人で抱え込まないで!相談先・頼れる支援の窓口まとめ
もし、「どうしたらいいか本当にわからない…」「限界かも…」と感じたときは、ひとりで抱え込まないことが何より大切です。
いまは、頼れる場所・話せる人がちゃんとあります。
ここでは、具体的な相談先をいくつかご紹介します:
● 発達支援センター・児童発達支援事業所
地域にある支援機関で、発達に関する相談や家庭での関わり方のアドバイスが受けられます。
● 保育園・幼稚園・学校の先生
日常の様子を一番よく見ている先生方も、子どもの特性を理解している“身近な専門家”です。気になることは遠慮なく相談してOK。
● 発達外来・小児科
医師の視点から、発達の評価や支援機関との連携をサポートしてくれます。医療的な相談も安心してできます。
● 地域の子育て支援センター・保健師
親同士が交流できる場や、専門職による育児相談が受けられる場所として活用できます。
● 同じ立場の保護者のつながり(SNS・当事者会など)
同じような悩みを共有できる人の存在は、「自分だけじゃない」と思える心の支えになります。
大切なのは、「がんばりすぎる前に、声をあげること」。
そして、「支援を受けること=甘え」ではなく、“子どもによりよく向き合うための大切な一歩”だということです。
“話を聞かない”のではなく、“伝わってない”だけかもしれません
——今日からできる5つの工夫で、親子の関係がグッと近づきます!
「どうして話を聞いてくれないの?」と悩んでいた日々も、少し視点を変えてみると、
“聞こえていない”のではなく、“届いていないだけ”だったんだと気づくことがあります。
今回ご紹介した5つの工夫は、どれも特別な道具やスキルがなくても、日常の中ですぐに始められるものばかりです。
- 見て伝える(視覚支援)
- 好きなものにのせる(興味で引き出す)
- 一言ずつ、ゆっくり、具体的に(わかりやすい声かけ)
- 待つ(子どものペースに寄り添う)
- 環境を整える(集中できる空間づくり)
この5つをちょっとずつ取り入れていくことで、
「伝わる喜び」や「通じた実感」が増えていき、子どもとの関係性がぐっとやわらかくなるはずです。
もちろん、毎日がうまくいくわけじゃありません。
それでも、「伝え方を工夫すれば、もっと伝わるかもしれない」という気持ちが持てると、
子育てのしんどさが少し軽くなる瞬間が必ず訪れます。
「聞いてくれない」と悩んでいたその声かけが、
いつか「ちゃんと届いた!」という嬉しい瞬間に変わりますように。
焦らず、あきらめず、小さな“伝わった”を積み重ねていきましょう。
あなたの関わり方ひとつで、子どもとの距離はもっと縮まりますよ。
さいごに
最後まで記事を読んでいただき、本当にありがとうございました。
日々の子育ての中で、「伝わらない…」と悩みながらも、お子さんと向き合おうとしているあなたの姿勢に、心から敬意を表します。
今回ご紹介したのは、
「視覚で伝える」「興味に寄せる」「短く・具体的に話す」「待つ」「環境を整える」という、
伝える力を育む5つの工夫でした。どれも特別な道具や技術がなくても、すぐに実践できる身近な方法です。
毎日がうまくいくわけじゃなくても大丈夫。
大切なのは、伝わらなかった時に「どう伝えよう?」と前を向くその気持ちです。
どうか、自分を責めすぎず、ひとつひとつのチャレンジを認めてあげてください。
明日からの声かけが、少しでもラクに、そして前よりも楽しくなりますように。
どんな日も、あなたのがんばりはきっとお子さんの心に届いています。

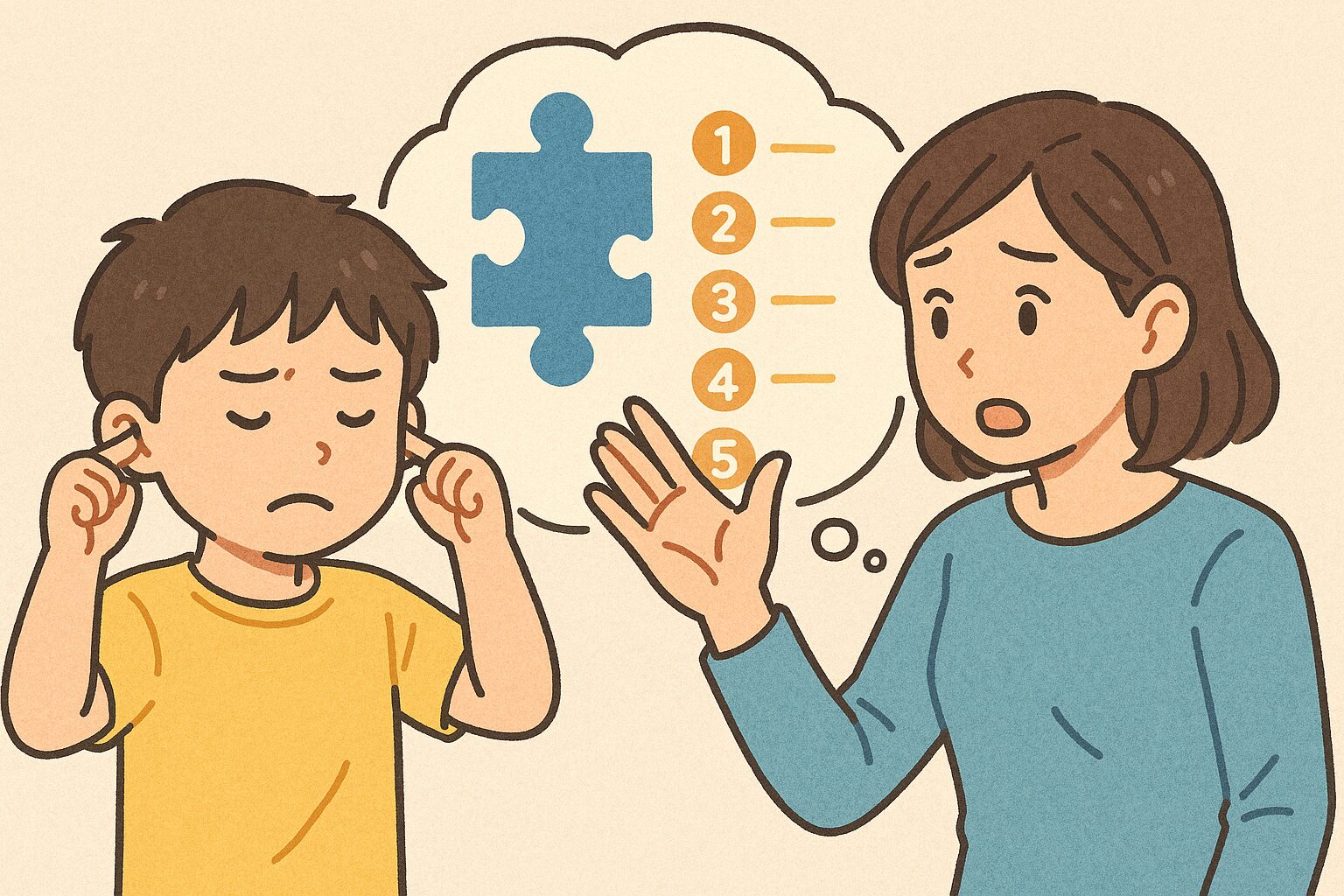



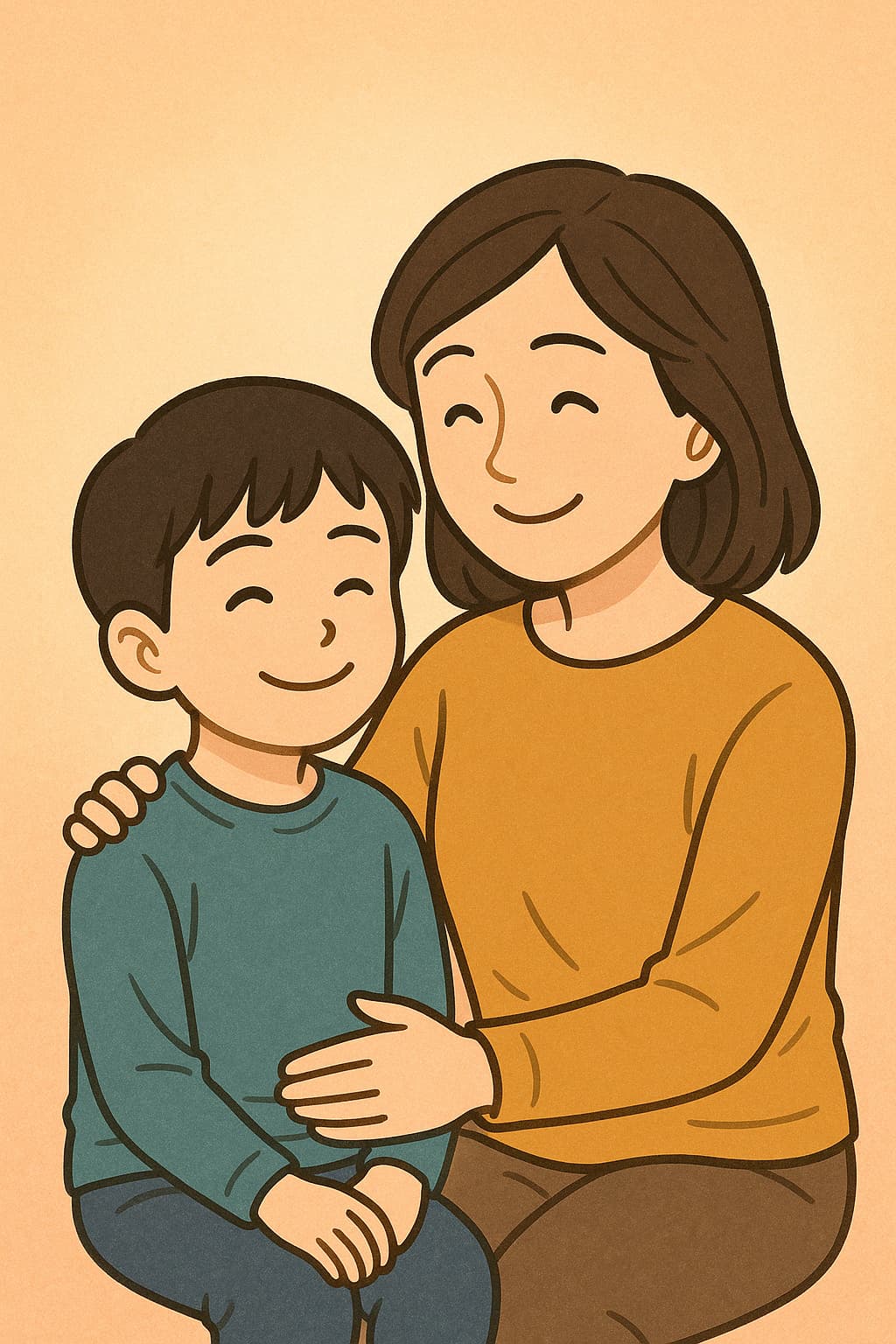
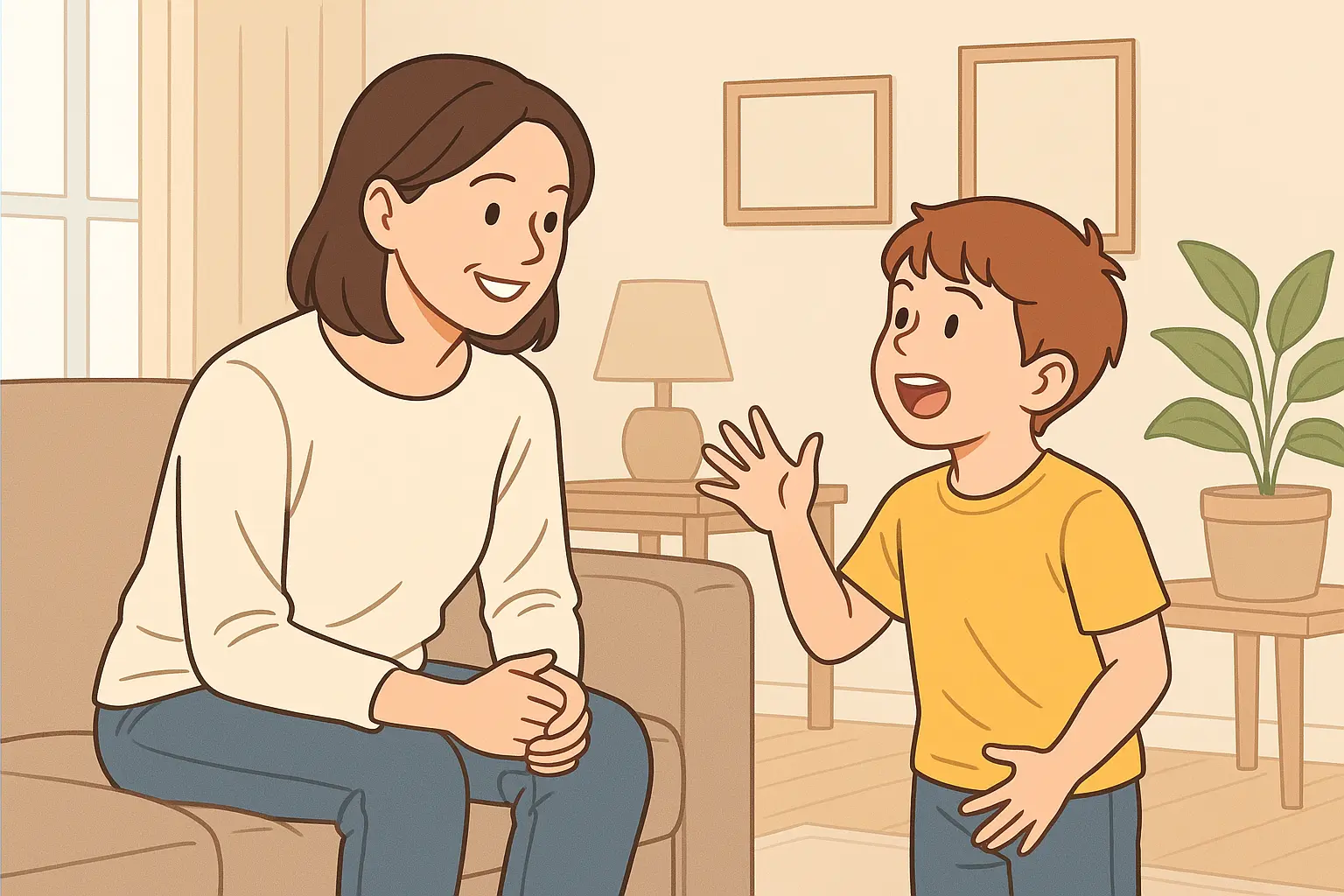



コメント